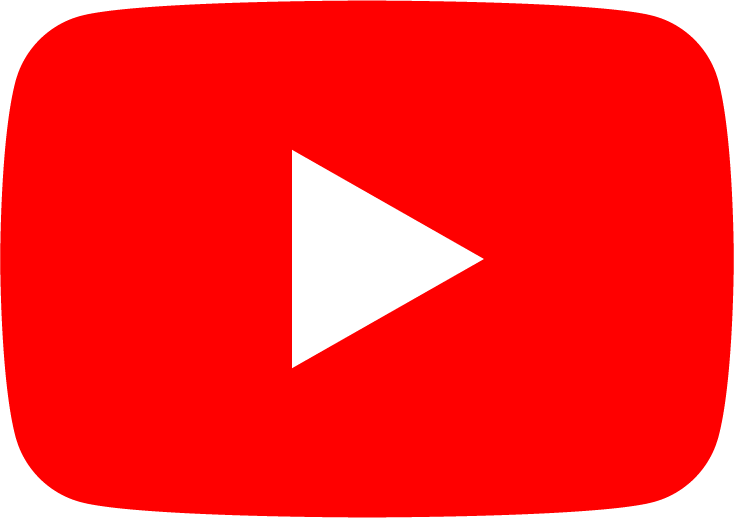- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「第一部会」
- 企業会計審議会第9回第一部…
平成13年6月15日
金融庁
企業会計審議会第9回第一部会議事録について
企業会計審議会第9回第一部会(平成13年5月18日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第9回第一部会議事録
日時:平成13年5月18日(金)午後4時02分~午後6時02分
場所:中央合同庁舎第4号館9階10階共用第一特別会議室
- ○斎藤部会長
-
それでは、定刻になりましたので、これから第9回の第一部会を開催いたします。
委員の皆様方には、お忙しいところお集まりいただきましてまことにありがとうございます。
前回ご説明いたしましたように、本日の部会は、前回に引き続いて論点整理に向けてご審議いただく予定にしておりますが、その前に、監査法人トーマツから先日公表されましたM&Aに関する世界規模での調査報告につきまして、監査法人トーマツの内山参考人をお招きいたしましてご報告をいただくことにしております。
それでは、まず内山参考人からよろしくお願いいたします。
- ○内山参考人
-
ただいまご紹介いただきました、監査法人トーマツの内山でございます。本日はよろしくお願いいたします。
私は現在、監査法人トーマツのコーポレートファイナンス部というところに所属しておりまして、M&A業務に携わらせていただいております。本日お集まりの先生方は、M&Aのことをよくご存じと思いますが、私どもが日ごろやっておりますことも踏まえまして、実態の方をご参考にしていただければと思っております。
今ご紹介いただきましたとおり、本年の3月15日に東京証券取引所で、私ども、買収合併に関する世界調査を発表させていただきました。どうも日本の会社がM&Aに弱そうだなと、何となく皆さん、雰囲気を感じていらっしゃると思うのですが、この調査により、ある程度のところがはっきりしたものでございますので、ご報告させていただきたいと思います。
お手元に「SOLVING THE MERGER MYSTERY 企業合併の謎を解く」という調査書を配付させていただいていると思います。ぜひご参考にしていただければと思います。
この調査は、私ども監査法人トーマツが所属しておりますDeloitte Touche Tohmatsuという世界組織がございまして、ここと、そのコンサルティング会社でありますDeloitte Consulting、この2社が共同で米国において2000年に実施した調査でございます。質問した内容は、6分野の質問内容で、50件の質問を投げさせていただきました。6分野と申し上げますのは、企業プロフィール、M&A履歴、M&A戦略、買収対象の選定、合併・買収交渉の進展及び交渉プランニング・統合に関する事項でございます。母集団といたしましては、世界 540社から回答をいただきました。半数が年商5億USドル以上、日本円ですと600億円以上の会社が半数を占めております。そのうち日本企業が56社を占めております。約10%でございます。
この調査から、どうもM&Aに日本の企業はなれていないなということがわかりました。全世界ベースでのM&Aの調査によりましても、実はほんの3分の1の企業しかM&Aに成功していると思っていないという結論が出ております。これに対して日本の会社はわずか8%、これだけしか成功していると思っていないと回答してまいりました。では、成功した、成功しないをどうやって分けるかということになりますけれども、私どもは、非常に簡単に、「あなたの企業が予定された期間のうちにM&Aの明文化された目標を達成した例、それはどのぐらいあるんですか。」と聞かせていただきました。「1から10までで答えてください。1がめったに達成していない、10は常に達成している。」と、こういう尺度ではからせていただきました。このうち8以上の回答を得た会社を成功していると私どもは見なしまして、この数字をはじき出させていただきました。
特に全世界企業と比べますと、日本の会社がどうしてM&Aに不慣れなのだろうかということになるわけなんですけれども、ここに書いてありますように、4点が私どもの調査から浮き彫りになりました。
お手元の全世界調査と日本企業調査の比較の最初のページの上のM&A部門の規模(人)と書いてあるグラフを見ていただきたいんですが、実はほとんどの世界の大きな会社は、M&Aの専門部門を持っております。例えばGEさん、GEキャピタルさんもそうですし、日産と提携したルノーさんもそうですけれども、M&Aの専門家がいらっしゃいまして、この方々を中心にM&Aをやっております。ところが日本の企業の場合には、ご承知のとおり経営企画部はあるのですが、本当に細かいところまですべてやるM&Aの専門部隊はないということでございます。この表を見ていただくとわかるとおり、実際にM&Aの専門部隊というように聞いてみますと、日本の会社は46%の会社がない。専門部隊としてはないと。経営企画部はあるけれども、M&Aの専門部隊はない。ところが、そのようにないと答えたのは、全世界では20%です。この全世界の方は日本の会社を含んでおりますので、日本の会社を含めた上の全世界が20%、日本の会社だけが46%、というように読んでいただければと思います。
それから、その横の円グラフを見ていただきたいのですが、調査によりますと、日本の会社は、例えば買収をしようと決めたときに、どういう基準で買収会社を選定しようかが余りはっきりしていない。何となく投資銀行からいい買い物ですよと言われて買う例が多かったという回答をいただきました。これをごらんになっていただいてわかるとおり、日本の場合には、そういう選定基準がありますのはわずか13%、全世界ベースでは半分以上、56%の会社が選定基準を持っております。
それから、1枚めくっていただきまして、「デューディリジェンスのプロセスにおける最大の問題点」と書いたグラフがあるかと思います。こちらを見るとわかるとおり、実は日本の会社は、組織的なデューディリジェンスの手続を踏んでいないことがわかります。組織的でないデューディリジェンスのプロセスが日本の場合には55%回答がございまして、全世界としては21%。これは、例えば会計、税務、法務、いろいろなデューディリジェンスをやるわけですが、それが余りきちんとリンクしていない。組織的に企業の価値を上げるような方向に、あるいは統合に向けて、リンクされたデューディリジェンスのプロセスがないということを象徴しております。
最後に、その下で、「移行計画と統合を開始するタイミングに関し、統合計画がない、またはその他と回答した割合」と、「統合計画をいつごろから開始しますか」という質問をさせていただきました。8つのタイミングを我々は区切ってみました。最初は戦略をつくるとき、2番目はターゲット企業を選定したとき、3番目はデューディリジェンスのとき、4番目はバリュエーション/シナジー効果分析のとき、5番目は合併発表のとき、6番目は合併発表の後合併前まで、7番目は合併期日後1カ月以内。8番目はそれ以外。こういう期日を切りまして、いつから統合計画を始めますかと聞いてみたところ、実はそんな統合計画はもともとないという会社、あるいは統合してから考えましょうという会社が、両方合わせて日本の会社は26%ありました。世界では、そのような会社は、わずか6%しかありませんでした。
以上のように、(1)M&A専門部隊の欠如、(2)不明瞭な買収会社選定基準、(3)組織的でないデューディリジェンスのプロセス、および(4)不明確な統合計画が日本の会社の弱点であることがわかりました。
それでは、M&Aを成功させるためにはどうしたらいいのかをアンケートの結果から考えてみたいのですが、そのためには、なぜM&Aによる成長を会社は選択するんだろうかという観点から入ってみるのが一番いいのではないかと思います。なぜ会社がM&Aを選ぶかというと、非常に答えは簡単でございまして、市場における力学の根本的な変革のための手段を提供してくれるからであります。その根本的な変革、すなわちそれは経済価値を創出するからだと思います。経済価値の源泉としましては、3つありまして、そこに書いてありますとおり、(1)効率、すなわち、規模の経済、選択と集中を実現し、コストも最大限に抑制をすること、(2)マーケットパワー、すなわち、自社のブラントの評判を高めて、競合他社が持つ専門的知識を自社のために獲得すること。それから(3)再創造。すなわちリ・インベンションの略ですけれども、自社だけではなくて、産業全体を自社に有利になるように変革させることです。こういう3つの源泉をM&Aという手法がもたらしてくれるので会社はM&Aによる成長を望むという基本的な考え方があるわけでございます。
したがいまして、それを踏まえて考えますと、成功するか、成功しないかというのは非常に簡単でございまして、このM&Aが我が社にとってどのような価値をもたらしたのだろうかと考えてみれば、おのずと成功の秘訣がわかってくるのです。私の方で挙げさせていただきましたのは、M&Aの戦略にまず忠実になってほしいということ。もともと立てたM&Aの戦略、それに忠実にM&Aのプロセスを進行していってほしい。日本の場合は、必ずしも経済価値を高める、という意識だけではなくて、いわゆるステークホルダーを大事にしたいと考えている会社が多いため、どうもM&Aの戦略がぼやっとしてしまう。もう少しきちんと経済価値の定量化を図った方がいいのではないのかというのが最初のポイントでございます。
それから2番目は、これもご承知のとおり、シナジーを買収の場合には求めるわけでございますけれども、このシナジーにしっかり注目してM&Aを行っていく必要がある。実際に、シナジーを得ることが一番重要であると考えている会社が全体の3分の2、63%ほどございます。ただ単純に、統合によってシナジーがこうありますねと分析するだけでは、決してうまくいっていないようでございます。シナジーを確実ならしめるために、シナジーの効果の見きわめとその明確化、その実現の優先順位づけ、そういった優先順位づけをして追跡調査をしているという総合的なアプローチをすると、31%ほど成功率が向上するという結果が出ておりまして、ここが非常に大事だと思っております。
それから、これは先ほど図を見ていただきましたとおり、デューディリジェンスを他のM&Aの活動と結びつける必要があるということでございます。どうも拝見しておりますと、公認会計士に財務のディリジェンスをお願いします、弁護士さんにリーガルのディリジェンスをお願いします、労務の問題は労務の専門家にお願いします、あるいは環境の問題は環境の専門家にお願いしますといった多角的なデューデリジェンスをおこなっているようですが、その間のコミュニケーション、あるいは発見された事項がどのように最終的にM&Aのプロセスに結びついていくかが余りはっきりしない会社が多いんですね。やりっぱなしが多いので、どうもここが1つのウィークポイントになっているようです。
それから、統合に向けて計画・構造を早目に準備するということですが、基本的にM&Aによる成功というのは、もちろん一緒になってシナジーを高めていくということですので、いち早く統合するということが重要になるわけでございます。その統合の速度、統合の仕方、これは非常に重要になるかと思います。
それから、これもよく言われることですけれども、人材等の流出の問題に早くから小まめに取り組む。企業の合併とか買収が発表されますと、従業員は途方もなく不安になります。この不安を払拭するために、リーダーシップを発揮して、そして各人の役割を明確に伝える。どのような形で組織が動いていくのかを絶えず連絡していく。こういうことが非常に人材の流出防止に大きく貢献することになると思います。人材等の「等」の中には、顧客及びサプライヤー、これも含まれております。合併した後、どうも重要なお客さんが逃げたとか、あるいは合併した後、仕入れ先から逃げられたとか、そういう例も多々ございますが、ここは非常に難しいのですが、事前にしっかりお話をしていくということしかないと思います。
最後に、6番目でございますけれども、適切なコミュニケーションをM&Aプロセス全体を通じて図っていくことです。冒頭申し上げましたとおり、外国の企業はM&Aの専門部隊がございます。ある特定の方が全部のプロセスに関与いたしまして、適切なコミュニケーションをとっていっております。一方日本の会社では、どなたかがプロセスに関与されていますが、一つ一つが何かサブルーチンのようになってしまって、その間をうまくコミュニケートしていないように見受けられます。この点も1つの大きなM&Aの失敗につながるものになるのではないかと懸念されております。
結論といたしましては、恐らくここに掲げている10ポイントが重要になると思います。この中には今までお話ししました6ポイントが散りばめられているだけでございます。あえて真新しいことを申し上げますと、2番目の、あらかじめ買収価格の上限を決めて買収交渉をしてくださいということ、また7番目の、バリュードライバーを明らかにして、統合をそこに集中させてくださいということです。この辺が多少話から漏れた点で、その他は今お話しした次第でございます。
余り細かい点はご説明できなかったと思いますけれども、もし質疑応答の中で対応できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。ただいまのご報告につきましてご質問やご意見等がございましたら、どうぞご自由にご発言ください。
- ○八木委員
-
アメリカのプーリング法の、特に適用・実態について、もしお気づきの点があったらお聞きしたいんです。1つは経営者の継続とか、当事者の規模が非常に拮抗しているケースとかで、いずれが買い手か売り手か、買収・被買収が判然としないようなケースがございませんかという質問と、プーリング法とパーチェス法が現在両方併存した形になっておりますが、現在、格別の不都合が起きていないかという、2点について、もしお気づきの点があったら教えていただきたいと思います。
- ○内山参考人
-
まず1点目で、どちらが買収会社で、どちらが被買収会社かわからないようなケースがあるか、ないかというお話でございます。私が実務で見ている限りにおいては、合併なり買収をしたときは、確かに似たような規模、あるいは本当に持分の結合のような状況が生じているケースは多々あるかと思うのですが、長い目で見ますと、実はどちらかが買収会社で、どちらかが被買収であります。その期間もそんなに長くなくて、2年とか3年で、わかってしまうケースがほとんどだと思っております。特にアメリカの案件ではこれ点が非常にはっきりしておりまして、どちらかが要するにマジョリティーをとる、すなわち、経営の実権を握るというケースがほとんどであるかと見受けております。
2番目のご質問の、パーチェス法とプーリング法が併存しているために起こる弊害と申しますか、そういうのがあるかどうかということです。皆さん、やはりできればプーリングしたいというのがあるようでございますけれども、実務の観点から見ますと、経営者の責任をある程度明確化するという観点で、パーチェス法に限った方がいいとおっしゃっている方も逆にいらっしゃいます。特に米国等はそうなっていると伺っておりますけれども、そういう観点でパーチェス法だけに絞った方がいいのではないか。ある意味で、いろいろなケースがあると思いますけれども、いろいろな弊害が出てきているのではないかとおっしゃっている声の方が多いように思われます。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。
- ○八木委員
-
経理処理をやらなければならないのはその年だと思うんでございますが、その段階では、もうこれは買収だとするケースが多いということにつながるんでございましょうか。
- ○内山参考人
-
ケース・バイ・ケースだと思います。
- ○八木委員
-
わかりました。ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
引頭委員どうぞ。
- ○引頭委員
-
素朴な質問ですけれども、M&Aをする場合に、買収価格なんですが、現金による買収の場合と株式交換による場合と、実務の上では金額の決め方は違うんでしょうか。
- ○内山参考人
-
これもケース・バイ・ケースというのが正確なお答えかと思いますけれども、基本的に違いはないかと思います。買収金額は幾らである。ただ、その買収金額をお支払いする方法はキャッシュであるか、あるいはストックであるかという問題でございますので、基本的には買収価額の決め方自体は、その買収のための対価に基本的には左右されないというのが実務かと理解しております。
- ○斎藤部会長
-
伊藤委員、どうぞ。
- ○伊藤委員
-
具体的なことで恐縮なんでございますけれども、小さい金額の買収の場合は余り問題にならないんですけれども、相当大きな金額で、最近はオークション方式がはやっております。そうしますと、日本の今の商法のいろいろなレギュレーションとか、そう簡単に臨時株主総会を開くわけにいかないということで、もちろんデューディリジェンスの問題もございますけれども、現実問題、大変日本のM&Aというのは制度的にもやりにくいということが実例としてございませんか。
- ○内山参考人
-
そうですね。おっしゃるように、大きな買収の場合に、特に株主総会の問題ですとか、法的な問題によって足かせがあって、大きな買収がやりづらいというケースは確かにあるかと思います。
また、もう一つの切り口としまして、やはり税務にも大きな問題がございまして、4月1日から企業組織再編税制が導入されましたけれども、税務も、今まで買収が起こりにくくなっていた1つの要因だったのではないかと思いますので、単なる商法だけの話ではないかと思います。
- ○伊藤委員
-
先ほどの八木さんのご意見ではないけれども、会計的な面で、何か日本の今の制度がネックになっているということはお感じになりますか。
- ○内山参考人
-
実務の立場から申し上げさせていただきますと、やはり経済実態が同じであるにもかかわらず、会計処理方法が変わってしまう点が非常にネックになります。例えば吸収分割で会社を買収した場合と合併した場合とで、会計制度委員会の研究報告の会計処理を使いますと、違ってくるのが非常に困るというのが事実でございます。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
合併に先立って、まだ公表されていない段階かもしれませんけれども、見積財務諸表を何期間かつくる、それは3期なのか5期なのかわかりませんし、粗っぽい数字かもしれませんけれども、そういうことはされるんでしょうか。
- ○内山参考人
-
はい、やります。
- ○大日方委員
-
そのときに、この合併に企業結合会計のどの方法が適用されるかということに対して、もうわかっている場合はその方法なんでしょうけれども、例えば両方を試算してみることもされるんでしょうか。
- ○内山参考人
-
それは状況によってやります。と申しますのは、特に、ある一部門を買収するときに、それが今回の、例えば会社分割法を使ってやるときに、売買処理法なのか、簿価引継法なのか、それによって財務上のインパクトは非常に変わりますので、プロフォーマーをつくるときに考慮いたします。
- ○大日方委員
-
そのときに、合併後のキャッシュフローは会計処理によって変わらないんですけれども、損益を気にする企業の方から、何か合併の条件みたいなものをいじって、見かけ上だけなんですが、例えばパーチェス法ではなくてプーリングを適用できるようにならないかというような相談というのはないものですか。
- ○内山参考人
-
実際ございますね。
- ○大日方委員
-
その大きな理由はどういうことでしょうか。
- ○内山参考人
-
先ほどお話ししましたのは、もうプーリングをやめようとおっしゃっている方も逆にいらっしゃるぐらいで、実務の中ではやはり経営者責任を発揮させようと。すなわち、例えば100億で株式を買収したにもかかわらず、例えば、もし結合であれば、それは30億しか出ていない。つまり、70億ののれんに相当するものが出ていないということになると、非常に経営者にとって経営がイージーになってしまう。その部分についての責任がどうなるかとか、価格に合った買収に関する責任を将来どこまでやっていくんだというのをはっきりさせる意味では、パーチェス法に基づいた方がいいというのも最近は多くなってきていると思っております。しかし、先生のおっしゃるとおり、そうは言ってもまだやはりプーリングで、何とか条件をいじってでもいいからこっちの方に持ってきてほしいと言う人もございます。
- ○大日方委員
-
そのときの企業側のニーズ、プーリングを選びたいときのニーズというのは、のれんの償却問題でしょうか。それとも、結果的に総額が変わらないので、内訳の振りかえだけかもしれませんが、フェアバリューで評価した資産の償却、どちらを気にされているんでしょうか。
- ○内山参考人
-
もちろん償却による利益減というのはあるのですけれども、最近やはり会社さんはROEなりROAの指標というものを非常に気にされておりまして、特に記者発表のときに、うちはROEがこれだけになりました、ROAがこれだけになりましたというお話をします。特にROAにかなり影響しているかと思いますが、その意味でも、やはりパーチェスよりもプーリングの方がいいということだろうと思います。
- ○大日方委員
-
わかりました。ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、伊藤委員。
- ○伊藤委員
-
日本の中の具体的なM&Aの状態をお伺いしたいんです。私どもの身近な例では、基本的には、全く人格をお互いに尊重し合って、人についてお互いに必要な人はできるだけ残していく。もちろんこれはポータブルな年金システムもできていませんし、いろいろな問題はもちろんございますし、終身雇用の問題もいろいろあって、まだ国際化されていない部分もかなりあるわけですね。そういうのが実際の買収例として多いのですが、どうなっていますか。
- ○内山参考人
-
ご承知のとおり、いわゆる世界的なグローバル化の流れの中で、日本の会社も合従連衡を図っていかないと生き残っていけないということと、やはりバブル時代にいろいろ手を出したノンコアのビジネスになかなか目が届かなくなってきている点があります。コアの方が調子がよくなくなってきているということで、本当に教科書どおりですが、ノンコアのビジネスをその価値が高まるような会社に売却をして、売却した資金をコアに集中していくという動きは非常にございます。それは、話の流れとしましては、もちろんグローバリゼーションの一環だと思いますけれども、国内でもかなりそれはシビアに今考えられていまして、そういう会社は多々ございます。最近はかなり考え方の面では欧米と差がなくなりつつあるとご理解いただければと思います。
また、実務の一例ですが日本の会社同士の買収の場合は、買収価額の調整の問題がありました。例えば2001年3月31日の財務諸表をベースに買収価額を決めて、実際に買収、あるいは合併でも結構ですが、それを10月1日に行うケースを考えてみてください。買収が行われるのが今年の10月1日、半年後です。そのときに、今までは買収価額がほとんど調整されないんですね。私がもし売り手だったら、その半年の間にキャッシュを抜いて、価値を減らしたままにした上で、買収価格は100億なら100億そのままということを考えるのですけれども、このようなことが起こっても今までは買収価額の調整が行われなかった。そういう形で、実はバブルの時代のころ、日本の会社は多々やられてしまったわけです。買収価額を一旦決めた後で、私どもは、クロージング・オーディットと呼んでいるんですが、10月1日現在の財政状態をもう一度見て、3月との差額についてきちんと決済する。こういう実務が日本の会社の中では大分行われるようになってまいりました。ここ二、三年の話であると思います。
ここで1つ、問題になるのが、買収価額の変更をどう会計処理するのか。あるいは税務上どう扱うのかということです。特に税務の取り扱いが、まだかなり会計に影響を及ぼしている点もございまして、簡単に買収価額の調整ということで金銭をやりとりすることはできないというのが、もう一つ日本の買収がスムーズにいかない要因になっているかと思われます。具体的に申し上げますと、例えば100億円で買収をして、運転資本の増減を起因に2億円調整するとします。そうすると、本当は運転資本がへこんだために98億円でよかったんですが、一たん100億円で決済してしまった後、その2億円を現金でやりとりしますと、本来その対価は株式の調整ということですが、なかなか税務上そう見てくれない。寄附金とかに見られて、なかなかきちんと買収価額の調整に回らないというのが現状でございます。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
今アメリカで、のれんの償却の問題ですけれども、定期的な償却をせずに減損だけを認識した方がいいという提案が行われていまして、それがM&Aの実態を反映する方法だということが言われたりしているんですけれども、実際に現場で仕事をされている感覚として、のれんをある期間にわたって償却する方法と、それから償却せず減損という方法と、どちらが実態に合っているかコメントをいただけたらと思うんですが。
- ○内山参考人
-
非常に難しいご質問なので、きちんとお答えできるかどうかわからないのですが、業態とか、もちろんビジネス自体に依存するところもあるかと思います。例えばハイテク産業で、そのノウハウ自体が非常に重要である。そのために高く買いました、それだけの価値があると思って買いました。ところが、日進月歩の技術があるものでございますので、すぐそれが凌駕されてしまって何の価値もなくなってしまったというように考えますと、償却ではなくて減損という考え方でその部分を処理していくのが実態にあうような気がいたします。また、伝統的な産業で、ある程度のれんというものも時の経過に応じて規則的に減価していくような業種もあろうかと思いますので、その業種、業態、会社によって、実態と会計が合うか合わないかが違うのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
安藤委員、どうぞ。
- ○安藤委員
-
先ほど、今まで当初は対等のように見えても、数年たつと合併か、被合併かがわかると言われました。どういうメルクマールでそう見るのかに関心があるんですけれども、例えばその1つとして、どちらの監査法人を引き継いでいるかというようなこともメルクマールになりますでしょうか。
- ○内山参考人
-
おもしろいですね。メルクマールになるか、ならないかというふうに聞かれれば、なり得るのではないかなとは思いますが、それによってどちらかが買収だ、どちらかが被買収だというのは余りご判断にならない方がよろしいかと思います。むしろやはり一番のポイントは人ではないかと私は理解しております。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
今、パーチェスと持分プーリングが想定されているのですが、フレッシュスタートもあると思います。フレッシュスタートの場合には、取引の実態として文字どおりフレッシュスタートである。ですから、大規模なリストラとか、今までの当事会社の業態がほとんど変わる。そういうようなものが想定されると思うんですけれども、そのような企業結合というものがあるだろうか、あるいはあっただろうということをご経験されましたでしょうか。
- ○内山参考人
-
すみません。そのフレッシュスタートというのは、もう少し厳密に言いますとどういう形でしょうか。
- ○黒川委員
-
両当事会社が、もう過去の業態、あるいはその会社の実態とは全く離れて、新たなスタートであると。合併後、あるいは企業結合後に新しい会社がスタートしたんだと、フレッシュスタートというのはそういうような意味です。
- ○内山参考人
-
残念ながら、それに関しましては私の経験ではございません。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。それでは、特にご質問がないようでしたら、次の議事に移りたいと思います。内山参考人におかれましては、本日は貴重なご報告をいただきまして大変ありがとうございました。お礼を申し上げます。
- ○内山参考人
-
どうもありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
それでは、前回に引き続きましてご審議をいただきたいと思いますが、まず事務局から、本日の審議についての説明をお願いいたします。
- ○辻前企業会計専門官
-
それでは、基本的には前回に引き続き本日もご審議いただきたいわけですけれども、前回ご審議いただいた中で、この部会用の資料の最後のところに、その他の論点をまとめているのですが、前回も割と議論が集中したんですけれども、ここについては企業結合の会計の本体部分とは直接関係がないということと、こういったような形で論点整理として公表したときに、ここにコメントが集中するのが予想されるわけですけれども、それも企業結合会計の検討という意図からしてみると、やや異なるのではないかと考えられますので、本日は、一たんその他のところについては論点整理では文章化しないということにして、ご審議をお願いしたいと考えております。
- ○斎藤部会長
-
要するに、全体の構成のうち、最後のその他の論点についてカットをして、それ以前の部分について前回に引き続いてご審議をいただきたいと、そういう趣旨ですね。お気づきのところからご自由に論点をお出しいただければと思います。
- ○八木委員
-
前回、欠席をしてしまいまして、そのときいろいろその他のところに大分集中したと聞きましたけれども、やはりパーチェス、プーリングと、この辺が本来の検討テーマだと思いましたので、少し考えを申し述べたいと思うんです。
まず、3月9日に、私、ここで、発行体側からの意見ということで幾つかのことを申し上げましたけれども、その後、3月27日に、この関係の方には多分お送りしていると思いますが、企業会計制度に関する提言を経団連の方から出しております。その中で、企業結合会計がほんの6行ばかり書いてあります。まずここに1つ、我々実務者のニーズといいますか、お願いが1つあるわけで、簡単に読ませていただきますと、企業組織再編が進展する中で、我が国の再編の実態に応じた基準の検討を進めていく必要がある。検討に当たっては、対等合併などプーリング法の適用が妥当であるケースが多いと言われる我が国の企業再編例を詳細に分析し、パーチェス法を適用すべき事例の明確化を行う。また、連結と個別の所有のあり方や共通支配にある企業組織再編の扱いについても検討が必要である。こういうように、世の中の流れのように短絡して1つの方向に行くのではなくて、いろいろ実態を分析していただきたいというところから、いろんなお話を申し上げたわけでございます。
それにつけても、先ほど内山参考人との議論の中で、プーリングに対して、ある種の誘導尋問的といいますか、企業側でいろいろなことをやって、プーリングに合格する条件をつくるための動きがあるというような、その弊害的な要素が議論の中にあったので、その辺は異議ありということもあるんですけれども、それは冗談としても、要するに我々の今身の回りに起きているいろいろな日本の実例においては、やはり客観的に見てもプーリング的であるというものが非常に多いということを我々も認識しておりますので、その関係で議論したいんでございます。
まず1つ、プーリング、パーチェスの議論をする際に、アメリカのFASBの動きというのは非常によく認識しているわけですが、そこへ至ったいろいろな経緯が、例えば国際会計基準では両方があるのに、G4+1とか、アメリカの流れの中で何かプーリングを排除してパーチェスだけに行くという1つの流れができ上がっていく。アメリカでもいろいろ議論があるということで、なぜそうなんだということになると、いろいろな条件を企業側がつくり上げて、それでプーリングを適用するというような、その弊害論のようなものがその中に1つある。そうすると、何かパーチェスがメーンでプーリングは下位概念というか、下位の方式である。そういう意識がだんだん醸成されているような雰囲気を感じるんでございます。ここの場では、ぜひプーリングとパーチェスは対等のものとして、真っ正面からメリット、デメリットを議論していただきたいと一番先に思うのでございます。そのために、例えば連結決算から見てどうだ、個別決算から見てどうだ。例えば合併というのは、とりあえず連結の問題ではなくて、個別企業と個別企業の問題ですから、個別決算の問題としてまずとらえるわけだけれども、それは連結にどういう影響を与えていくかとか、この前申し上げたんですが、いろいろマトリックスというんですか、そういうものでケースをつくって、いろいろなそれに適した方法を議論していくというアプローチが要るのではないかと思ってこの前申し上げたところでございます。
前置きが長くなりましたけれども、結局どうしてそうなんだということですけれども、まず、我が国の企業組織の再編が、先ほどのお話しのように、近年非常に増えてきておりますし、これからも増えると思います。現に私どももそういう渦中にございまして、売ったり買ったり買われたり、いろいろなことがあるわけなので、これからますますそういうものが出てくると思うんですね。その中で対等合併というような、プーリングがまさに妥当であると思われているケースはやはり結構多いわけですね。無理してそういうところへ持っていくというのではなくて、現にそういうケースがあるわけでございまして、そこのところを無理してパーチェスへ持っていくというようなことはやはり合わないということで、両方を準備しておく必要があるのではないかと、これが何よりも実態から見て感じるわけでございます。
逆にパーチェスの弊害と言うのは言い過ぎですけれども、すべてをパーチェスに特化していくことに対して、やはり懸念を感じるところがございます。我々のところでも現金買収はパーチェスだと、これはもう納得なのですが、合併が結構ケースとして多いわけなので、そういう場合には、やはりパーチェスを適用するというのは、まだ今のルールとしてはなっていないわけでございますので、これをまたそっちの方へもし持っていくようなことがあると、やはり別の意味の弊害が出てくるのではないかと思います。
それで、先ほども買収する方とされる方というのは非常に判然としないとか、その後の企業の運営においても、先ほど二、三年かかるとおっしゃいましたけれども、二、三年たっても実際どうなんだろうと。人の動きの中でそういうものがはっきりしないケースというのが現に動いておりますし、これからもそういうものが結構主流になっていくケースが多いんではないかと思うんですね。そういうことからして、合併した会社のB/Sを考えると、片方が全部時価で、片方が全部簿価だというようなケースが起きる。それが規模が限りなく似たようなケースだと、非常にわかりにくいB/Sができてくると、この前も申し上げたかと思うんでありますが、そういう現実の問題があるので、一種の連結の宿命かとは思うんでございますけれども、でき上がってくるB/Sは合併前と合併後では非常に変わったものになっていくというような、そういうことが逆に本当に実態を反映したものになるのかどうかということを感じるところでございます。
それからあと、特にそのケースで、不動産などで含み益があるケースは、まさにそういう弊害というか違和感といいますか、前の形と全然違った形が長く続くわけなので、そういうところで問題が起きないかどうか。この辺、資本への影響も出てきますから、その辺の議論をぜひ尽くしていただきたいと思っております。
それから、商法上の取り扱いは、これは当然検討する必要があると思うんですけれども、連結同様の処理をしていくのかどうか。さっき言いましたように、企業合併というのは個別の企業の問題でございますので、そういうことで準拠性、あるいは連結と個別の適合性といいますか、そういった観点から、やはり十分議論していかなければならない。特に商法で、連結計算書類の導入が2003年ごろというご予定を聞いておりますけれども、それに本腰が入っていくと、そこでもそういう情勢をはっきり、要するに準拠性、整合性といったようなポイントを、これもやはりよく議論しておかなければならないのではないかと感じております。
それから、税法も、適格再編であれば両者簿価ベースで結合するということになると思うのですが、確定決算との関係も議論の中に入れていかなければならないということで、経営的にパーチェス法にそぐわないケースというものが、やはり非常に多く発生するであろうから、我々としてはプーリングも同じウエートで方法論としては残しておいていただきたいと感じておるわけでございます。
長々と申し上げましたけれども、ポイントは、つまるところ、両方のケースが適当であるという実態が出てくるということでございます。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。伊藤委員、どうぞ。
- ○伊藤委員
-
八木さんからいろいろご意見を言っていただいたので、私も基本的に同じ考え方なのですが、先ほど来内山さんにもお伺いしたのですけれども、確かに国際的なM&Aというのはこれから大変行われますし、それから、国内的にも企業の選択と集中でもって、事業採算に乗らないものを分離して、そしてそれを再生させるということが、これから当然のことですけれども、企業としては成長のためにやっていかなければならない。ただ、現実の事態というものと将来の方向とは、まだやはり時間的ギャップがありまして、今の日本の社会の中における実態は、やはり人格的に対等という形で、基本的に分離したとしても、そこに行く人たちの将来のことを考え、あくまでも仕事をする者を単に分離して捨ててしまってもいいという考え方ではなくて、そこにおける従業員のことだとか、あるいは事業の実態とかいうものを何とかして残していきたいと言いつつ売却していっているわけですね。日本的なそういう商慣習がいつまでも私は続くとは思わないのですが、今の実態も無視はできないので、八木さんがおっしゃるように、パーチェスという大きな世界の流れというのはよくわかるんでございますが、やはりプーリングというものもあわせて検討していただきたい。ただ、その場合に、プーリングを適用する条件というものはやはりきちんと決めておかなければならないだろうとは思います。財界あるいは経済界の今の実態はそういうことになっているということをご認識いただいて、先生方の方でご議論いただければ大変ありがたい。
以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
- ○大日方委員
-
私も、企業結合と言われているケースの中にプーリング法がふさわしいケースがあるということには賛成なんです。その中で、教科書的な言い方ですが、典型例というと対等合併が真っ先に挙がるということも、それで異論はないんです。けれども、その対等合併というときに、アカデミックな世界だけなのかもしれませんが、株式の時価総額で見た規模だけで、それが同じかどうかで対等かどうかと見る意見もあるんですが、ここまでの皆さんのご意見を聞いておりますと、対等合併と言っているときの、その中には、必ずしも株価総額の規模だけでなくて、それ以外の現場での対等だという実感のようなものがある。その場合、どういうことがあれば対等合併と意識されているのかということを、もう少し具体的な、例えば人なのか、あるいはビジネスの継続なのか、どういうことがあると対等だと見なしているのかということを、どなたでも結構なんですけれども、お答えいただければ。
- ○伊藤委員
-
それに参考になるかどうかわかりませんが、やはり何といっても基本的には出資比率の問題がございますね。したがいまして、51対49ということと、これは明らかに買収と被買収という、資本政策は分かれるんでございますが、その場合でも、基本的には役員の、つまりCEOとCOOですね、それを交代で出すとか。つまり資本政策上は、最終的に、例えば保証の比率とか何かを含めて51対49でやったとしても、経営的にはお互いに、要するに相手の意見を十分尊重してやりましょうと。それから、従業員についてはお互いに引き継いで、49%の方の従業員を切るということはしないわけですね。できるだけの配慮をしましょうというのが、要するに日本的な円満な、そして時間をかけて、合併してから、例えば少なくとも四、五年をかけて徐々にやっていきましょうというのが一般的なやり方です。
やはり50対50の合併というのはよくあります。ただ、これはなかなか後でいろいろな問題を起こしますけれども、最初のスタート時点ではそういうのが非常に多い。少なくとも我々の会社の場合とか財閥系の企業の場合は、非常に多いと思います。ネットビジネスとか、新しいそういった外資系の会社は少し違うと思いますけれども、そういう点においては、例えば合併の比率の問題とか、役員の構成の問題とか、あるいは従業員の引き継ぎだとか、そういうところに幾つかの条件をきちんと整理する必要があろうかと思いますけれども。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
今、国際的な動向について多少言及がありましたので、来週、IASBの理事会がありまして、そこで議論されるペーパーが出てきていまして、その中では、これは多分公表される資料にはならないと思いますが、ビジネスコンビネーションのステアリングコミティーが幾つかの可能性を検討しているんです。その検討の中で、やはりプーリングのケースは、今のところIASCのステアリングコミティーではいろいろな議論があるのですが、残すという議論は捨てられておりません。したがいまして、プーリングとパーチェスが併存するということの可能性は全く捨ててはおりません。
ただ、その場合におけるプーリングの適用については幾つかの考え方があるんですが、その1つのステアリングコミティーが大方賛成しているという考え方には、何段階かのステップは経るんですが、最初に例えば50:50という出資比率でスクリーニングをかけまして、そこを通った上で、さらに取締役の数ですとか、それから財務政策への影響とか、幾つかの要件で、どちらかが行使できるようなパワーがあるのかどうかという判定をし、その次に、さらに相対的な公正価値とか、それから、それぞれが持っている持分権の実質的な中身のようなものをある程度吟味した上で、どちらかが買収したものと見れるかどうかというプロセスを経まして、それでも特定できないような場合に限って、プーリングという提案が行われていまして、これはかなり幾つかの細かい要件を設定はしておりますけれども、そういうものをクリアした、ある意味ではレアなケースというのが国際的には予定されているようです。
ただ、先ほどの内山参考人からのお話にもありましたように、米国などの文化を前提にしますと、どっちが買った方か、買われた方かというのはかなり明確だということなんですけれども、今の、先ほど八木委員、それから伊藤委員からご指摘のあった、日本的な合併ないしは企業結合のあり方が、そういうような幾つかのステップを経た段階でなおかつ対等であり、ベネフィットとリスクをシェアしているということであれば、そこにはある種、そういうプーリングが国際的な視点から見ても妥当性があるというケースが考えられる可能性はあるんではないか。そういう感想を持ちましたので、述べさせていただきました。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
今の山田委員の説明された考え方というのは、出資比率が50:50というのが必要条件なわけですね。つまり50:50を少しでも違えたときには、そこから先は進まないという、そういうお考えなわけですね。
- ○山田委員
-
そういうフローチャートがあるんですが、ただ、後で問題点として、49と51であっても、それ以下の条件を入れたときに逆転しているケースがあるかもしれない、ないしは対等なケースがあるかもしれないということで含みは残しております。今私が申し上げたのは、あくまでもたたき台の議論でございますので、ファイナルでも何でもないんですが、一応スタートとしては50:50。ただし、必ずしもそれ以外のケースを全くそこでは排除しているかというと、そうでもないという、明確ではない部分を残した考え方です。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
今の出資比率についてもう少し確認というか、教えていただきたいんです。これは山田委員と、それから伊藤委員に対してですが、例えば出資比率といったときに、こういうケースもある。合併比率が1対2で発行済株式数が逆に2対1で、その結果として合併後の会社における出資比率がたまたま1対1、50:50になったと、こういうようなこともあろうかと思うんです。そういうことを含めて、要するに企業結合後の会社における発行済株式数の中で、事前の当事会社の株主が持っていた比率が50:50であったというような意味なんでしょうか。その出資比率50:50の意味をもう一度確認したいと思います。
- ○山田委員
-
IASCのペーパーでは、投票権で50:50ということを前提にしているようです。
- ○黒川委員
-
投票権であったとしてもいいんですけれども、要するに、そのときに合併比率が1対2で、その発行済株式数が2対1だったら、掛け算すれば1対1になるので、そういう意味ですかということです。
- ○山田委員
-
そこまで触れていないと思いますが、最終的にでき上がった状態で50:50、私はそう読んでいますが、そこの中身になると、今の段階ではよくわかりません。
- ○斎藤部会長
-
伊藤委員、ご発言はございますでしょうか。
- ○伊藤委員
-
最終的な姿として、でき上がったもので50:50ということに普通は考えておりますね。したがいまして、その会社が倒産したときとか、あるいはその会社が本当に資金的に困ったときの保証も50:50で行うということですね。そういうのは我々は対等と考えていますけれどもね。
- ○斎藤部会長
-
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
今、ご質問を聞いていて、想定されている事例がどれだったか見えなくなったので確認したいんですけれども、A社という会社とB社という会社が合併して、たまたま旧株主同士で1対1の投票権だったという話を想定されているのか、それともA社とB社が同じ事業で合弁会社をつくって、50:50の出資をしましたと。企業結合会計の上でこの場合の扱いがどうなるのかという話をされているのか、見えないところがあったので、最初の方は本当にプーリングとパーチェスの話だろうと思いますし、後の事例というのは、恐らくJVに対する投資をどう認識するかという話だし、固定資産だけを出資したような合弁をつくったら、これは固定資産の交換だから損益は生じないというような議論も出てくる。そういうテーマだろうと思うんですが、2つのうちどっちを想定されるのか、確認したいんですけれども。
- ○斎藤部会長
-
私は、今の小宮山委員の2つの問題のうち前者と理解して話を承っておりましたけれども、それは間違いでしょうか。
- ○山田委員
-
私は前者の話だと理解しております。
- ○斎藤部会長
-
小宮山委員、よろしいですか。大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
会計の前提というか、そもそも論になってしまって恐縮なんですが、海外の会計基準・草案の説明を見るときに、必ず取得した側と被取得側が決まるというときの発想の根本には、企業を丸ごと買うことによって、買収側、取得側がそれを一種の道具として使って、経営の効率化になるとか、今まで自分で持っていない弱点を補完するとかという、そういう暗黙の前提があると思うんです。日本でよく産業界の方々が言われている対等合併といったときに、恐らく海外に向かって説得する上では、対等の合併というものを理解してもらう必要があると思うのですが、どういう合理的な企業ビヘービアが対等合併になるのか。私は、当然合理性があると思っているんですけれども、そのときに、例えばよくあるメガ競争になって、今の1社規模では研究開発投資を賄い切れないから、規模の経済を求めているような場合には、双方にメリットがあると思うのです。そういうものを対等合併の存在意義というか、経済合理性と考えていいのではないかなという感じがするんですが、海外の動きではそういうような発想というのは基本的に余りなくて、必ず買収した側のツールとして使われるという発想になっているわけです。恐縮なんですが、対等合併の経済合理性というか、メリット。それが合理的な企業ビヘービアとして十分に存在し得て、それは取得という概念と全く違うということを説明していただきたいと思っています。
- ○斎藤部会長
-
難しい問題を投げかけられたわけですが、即答されますか。基本的には風土とかそういう話ではなくて、対等合併ということの経済合理的なインセンティブをきちんと説明していただけると、プーリングというものの意味を対外的に説得する上でも非常に役に立つのではないでしょうかというご指摘でありますけれども。
- ○伊藤委員
-
大変難しいですね。銀行の例を申し上げますと、1つの理由としては、1行ではインフラ投資がものすごくかかる。したがって、それに対する節減効果が非常に期待できるということを1つの大きな理由にしておりますね。もちろん企業でも、先ほどのジョイントベンチャーとは違う異質のものを、要するにどうやって買収していくかということがよくあるわけなんですね。例えばマーケットが同じ。マーケットツールを見ておりますから、例えば化粧品会社ですと、いろいろな販売店があって、そこがマーケットツールを持っている。そうすると化粧品以外の、例えば女性が利用できるような製品を開発して、そのマーケットツールに流す。そのために新しい事業を買収することもあり得るわけですね。したがって、その場合に、買収という形で完全に、70対30でもいいし、51対49でもいいんですが、企業を吸収してしまって、そのときに、買収のときには必ず経営者は全部自分たちのものにしてしまう。つまり、経営者はほとんど自分たちの会社のメンバーで固めてしまうと。もちろん、要するに銀行の保証もすべて100%こちら側で見るとか、こういうようなやり方をやっていることがないわけではないが、非常に少ないと思いますね。そのときには、当然のことながら今までいた会社は効率が悪いわけですから、従業員を何割かカットしていかなければならないという想定をしなければならないわけですけれども、なかなか今の日本の事業では、それは非常に難しいので、そういうことはよほどのことがない限り数が少ないと私は思います。
したがいまして、理論を構成する上において、限られたものをすべてだということに持っていっていいのかどうかには大変疑問を感じるということを申し上げているわけですね。
このあたりはよく財界としても検討して、お答えしなければならないとは思っております。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどの対等合併における出資比率の関係と、今の大日方委員の合理性という点を合わせて、質問をしたいんでございます。非常に奇異な例かもしれませんけれども、例えば1つの会社がハイテク企業で、ハイテク企業だからというわけではないんですけれども高収益企業で、1株当たりの持分金額が非常に大きい。しかし、会社の全体の規模はそれほど大きくないので発行株式数は小さい。それともう一つ、片や伝統的な企業というと予断がありますが、余り収益率は高くないけれども、非常に規模が大きくて発行済株式数が大きいというような企業が合併をしたとします。そうすると、それが1対5の割合ぐらいの一般的な従業員数とか、それから伝統的な会計で測定したところの資産の規模は1対5ぐらいであった。しかし収益力が違っていて、株価も非常に違っているから、株価総額としては要するにフィフティー・フィフティーということになる。これが先ほどの出資比率がフィフティー・フィフティーになる原因でございますよね。要するに、出資比率ができ上がった会社のフィフティー・フィフティーというのは、株価総額がフィフティー・フィフティーだったというのと同じようなものだろうと思うわけですけれども、そういうような会社が合併したときの対等合併の合理性というんでしょうか。要するにハイテクのような収益率が非常に高い会社と、低い会社であっても規模が大きい。こういうときの合理性というのはどこにあるのか。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、八木委員。
- ○八木委員
-
説明が非常に難しいのですが、今の日本で当面起こり得るのは、むしろ同業の中でのいろいろな企業の整理整頓のようなものにつながる部分とか、そういうことが、金融を例にとられましたけれども、ほかにもいっぱいこれから出てくるだろうと思うんです。そういうのが我々の頭の中にある現実の話で、今の黒川先生のお話の場合だったら、対等というケースはまず起きないのではないかなと。方法論の問題の前に、そういう経営戦略が現実に起こり得るかどうかという方において、非常に極端な例をお出しになったと思うんですが、なかなかあり得ないケースなのかなという感じがしております。
- ○黒川委員
-
例がハイテクと言ってしまったために、そちらの方に流れてしまったんですけれども、私の言いたかったのは、むしろ収益力が非常に違っていて、かつ規模が違っているという例ですね。そのときに一緒になったと。それでも、先ほどの出資比率はフィフティー・フィフティーだったら対等の定義をひとまず満たしているわけでございます。そういう、非常に小さいけれども高収益を上げている経営者がいて、会社があって、組織があって、それと、余りうまくいっていないような、でも規模が大きい会社があって、これが合併をしたと、こういうようなときに対等という意味合いが保てるのかどうか。そういうことを戦略と絡めてお聞きしたかった。
- ○伊藤委員
-
それは経営戦略の問題ですからお答えしますと、それは十分あり得るんですよ。例えばどういうことかといいますと、収益率とか、あるいは企業の将来性というのは、ゴーイングコンサーンかどうか、より疑問視するわけですね。ハイテクというのはライフタイムが短いですから。そうすると、そういう企業はアメリカによくありますけれども、例えばもっと規模が大きく、成長率が低いけれども安定的にキャッシュ・フローをふやしていけるところと一緒になって、より強固に基盤を形成していくということは、これは現にアメリカのネットビジネスが既存企業と一緒になるケースであって、それは日本でも十分考えられるわけですね。非常に時価総額が大きいけれども、それがいつまでも続かないということになれば、より地道な企業と一緒になって政策基盤を強くしていくということは十分あり得ますよ。だから、そのときに、対等でもいいから、要するにお互いに尊重し合って会社を将来存続させたいという、そういう創業者がおれば、当然、経営政策上あり得るということですね。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。西川委員、どうぞ。
- ○西川委員
-
コストカッティング目的の企業結合でプーリングが出てくるというのは大体わかるような気もするんですけれども、それ以外の話について、まず初めにフィフティー・フィフティーだというのを前提にして話をしていくと、連結した企業体全体を見ての規模ということから始めると、なかなか規模の調整というのはできないですから、思い通りプーリング法の幅を広げるというのはなかなか難しいのではないかという感じはしたので、対外的にプーリングの幅を広げたいということであれば、もう少し何かロジックが必要ではないかと、そういう感じがしました。
- ○斎藤部会長
-
現時点で特にご発言はございますでしょうか。
八木委員と伊藤委員におかれましては、現時点では西川委員のお話は伺ったと。
- ○八木委員
-
検討いたします。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
今のことに関連するかどうか定かではないんですが、プーリングとパーチェスの使い分けの基準として、規模、中でも株価総額が言われているわけですが、それは基本的には大きい方が小さい方を取得するという話しです。ところが、逆さ合併というような、小さい方が大きい方を吸収するということを認めますと、それを許すということを認めた瞬間に、逆に大きいからといって吸収するということではないということを認めざるを得なくなるはずですから、フィフティー・フィフティーという基準は、多分絶対的なものでは論理的にはあり得ないだろうと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
ほかにご発言はございませんか。時間はまだございますので、どうぞご発言をいただければと思います。
長坂委員、どうぞ。
- ○長坂委員
-
先ほどからの話で対等合併のお話があります。今、2社という前提で50:50というお話が出ていますけれども、最近ですと銀行とかで3社統合とか、そういうのがあります。そういった場合も一応3社対等ということもあり得るという前提でお話をしているんでしょうかという、これは質問です。
- ○斎藤部会長
-
いかがでしょうか。つまり、可能性としては、3社が合併したときに、合併した後の持分構成のうち、合併前のどれか1つの会社の旧株主が過半をとるかどうかという判断の基準と、もう一つは、3社がほぼ対等であって、それぞれ3分の1をとるという、それが少しでもずれていればということを言っているのか、それが問題だと思うんですけれども。多分先ほどの、2社の場合にフィフティー・フィフティーが対等合併の条件だという議論からすると、もしかすると、今の3社の合併のケースでは、合併後にどの会社も持分の過半をとれないということを言っているような気もするんですが、それはどうなんでしょうか。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
IASCの議論の中で、3社間の合併というのは可能性としては捨てていないんですね。ただ、検討としてはほとんど2社間の企業結合の話をしていまして、これが3社間にも拡大できるというような、今されている議論はそうなっています。それから、IAS22号はもともと3社は否定していないという考え方もありまして、ただ実態的に海外等で起こっているケースで、3社間の合併というのはほとんどないと聞いていまして、実はまだ余りそこは十分な検討の対象にはなっておりませんが、ロジカルには含まれるという形で今整理されているようです。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、八木委員。
- ○八木委員
-
銀行その他で行われているような、3社の買収・被買収の関係をどう整理するかということになると、これもまたAがB、CがDをというような、そういうことになるのかですね。これもまたややこしい、整理を要する点だなということで、今の長坂さんのご質問は、同じように両面から検討していかなければならない問題を含んでいると思っております。
- ○斎藤部会長
-
神田委員、どうぞ。
- ○神田部会長代理
-
フィフティー・フィフティーが対等かどうかが、どうして問題を難しくさせるかというと、恐らく会計にあらわれるものに着目するとフィフティー・フィフティーかなということになって、それをロジカルに詰めていくと、大日方委員がおっしゃったように、それは必ずしもそうは言い切れないということになるのではないかと思うんですね。つまり会計にあらわれないところで決まっている。これは実は法律の間違いというか、わながありまして、ご承知のように法律上は新設合併という制度と吸収合併という制度がありまして、法律だけを言いますと、新設合併というのはA社もB社も消えて、新たにC社をつくるわけですけれども、吸収合併の場合はA社かB社か消えるのはどちらかであって、A社ならB社が残るわけですね。しかし、経済実態の場合、吸収合併というのはBはAを吸収しているんですかというと、決してそうではなくて、実務でいうところの対等合併も、すべて法的には吸収合併の形式で行われている。これはいろいろ理由があるからであって、新設合併の形式はとられていないわけですね。
したがいまして、法律だけを見て新設合併だから、何か両方消えたとか、吸収合併は一方だけ消えたと言えないわけですけれども、恐らく同じような問題が、会計も制度ですからあって、もう少し言いますと、人とかそこで決まっているのではないかと思うんですね。例えば社長を交代で出すかどうか。従業員を引き継いで、その後の処遇ですね。これを同じ処遇――同じ処遇というか取り扱いですけれども、恐らくアメリカでは社長を交代で出しましょうというのはないと思うんですよね。それから従業員の処遇も、引き継いだ従業員と、それまでいた従業員を同じ基準で処理しましょうというのは恐らくなくて、それはある種の次の経営政策から人を切るなら切る、切らないなら切らないということでなるし、その次の経営政策というのは、その経営者がやることであって、順番に社長を出しましょうというのは恐らくない。この辺は直接会計にはあらわれない実態ですよね。ですから、なぜ順番に社長を出しましょうという動きが成り立つのか、私にはよくわかりませんけれども、やはりそういう特殊性というのはあるのではないでしょうかね。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
- ○伊藤委員
-
よくわかりますよ。
- ○斎藤部会長
-
先ほどの長坂委員の出されたケースも、例えばA、B、C、3つが合併したというときに、3つが合併したというふうに考えるか、場合によってはAとBが合併して、できた会社がCを合併したかというふうに見ることによって話が当然違ってまいりますし、もし後者をとった場合には、A、B、Cを組み合わせる順番をどう決めるかで結果が全部違ってくる可能性があるわけですね。ですから大変厄介な問題ではあると思っておりますけれども。
どうぞ、黒川委員。
- ○黒川委員
-
先ほどから、パーチェスと持分プーリングとの識別規準を想定されたような議論が今日は続いておりますので、もう一つそれに関連する質問をしたいと思うんですけれども、企業結合後の重要な部門というんでしょうか、事業部門の売却というようなことがアメリカのAPBの12の識別規準の中には1つございます。あらかじめそういう重要な部門を売却する予定があるようなものは持分プーリングではないんだと、こういうような言い方をされております。
そこで、それについて一つ、経済界の代表の方から、それはそうだと、あるいは違うんだというようなことと、それからもう一つ、みずほファイナンシャルグループの場合の例が皆さんよくご存じなので、挙げたいんですけれども、これは重要な事業部門の売却は想定されていないけれども、ファイナンシャルグループになった後、その後の段階において、それぞれの今までの業態をばらばらにして、縦のものを横にするというんでしょうか。3つの大きな事業部門に分ける、再構成する、そういうようなこともあらかじめ計画されておりました。それと、それに伴って支店の統廃合なども想定されているわけでございますけれども、そういう状況でも、ずっと同じ業態が続いている、あるいは対等であったというような、あるいは持分プーリングの定義に合致しているんだというように考えられるのかどうか。あいまいな質問で恐縮ですけれども、何か回答していただければ助かります。
- ○斎藤部会長
-
どちらにお願いしたらよろしゅうございましょうか。
- ○伊藤委員
-
これは大変難しいんですよね。基本的に経営者の我々としてみれば、要するに何らかの形で新しい会社をつくった場合、あるいは先ほどの吸収合併という法的な形をとった場合にせよ、それが従来よりもよくならなければならない。これは経営者としては当然のことですね。それができなければ、その経営は失敗したことになるわけであって、その日本的な評価が何かというのは非常に難しいんですよね。つまり利益だけでいいのか。要するに合併をして、損を落として身軽くしたから利益が出たということで評価され得るんだろうか。やはり社会的なレピュテーションが極めて重要である。つまり会社の品質と申しますか、レピュテーションがそれによって上がるかどうか。そのレピュテーションが上がるというのは何なのかということですよね。従業員の満足度とか、利益も出ているけれども、その利益というのはある種のみんなの満足感の中に生まれた利益であると、そういうようなものが経営者としては極めて重要です。必ずしも利益が出ればいいというものではない。つまり、ゴーイングコンサーンで利益を出し続けるような素質をつくっていくことが経営者の使命だと思っているわけです。
もちろん経営というのは、その経営者の変動によって変化しますから、利益が変化したりしますけれども、しかしながら、その素質が絶えず残っていって、利益が出る体質にしたかどうかですよ。その利益を出したかどうかというときに、従業員を犠牲したということで日本的なレピュテーションが維持できるかどうかを我々は絶えず判断しつつ考えております。これは古い財閥系の会社とか、八木さんのところのような大企業とか、そういうところはそう考えて政策を判断している。銀行もそういうことはあるだろうと思います。
小さい企業がそれぞれ合併するとか、ネットビジネスがぱっと一緒にひっつくとかいうものがすべての企業の形態かというように考えるのか、あるいは古い体質の会社の、大企業のあり方を考えるか、これは議論を要するところだと思いますけれども、一般的な日本のコンセンサスというのはどこにあるかということを我々は考えていかなければならないのではないか。
以上です。お答えになったかどうかわかりませんけれども。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか、黒川委員。
- ○黒川委員
-
一応承りました。考えてみます。
- ○伊藤委員
-
パーソナルな意見が入っておりますから、誤解のないように。
- ○斎藤部会長
-
審議会ですから、常に財界を代表してご発言いただく必要もないわけでございます。
いかがでしょうか。山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
きょうのペーパーの6ページのところに、リステートという項目が1つ挙がっているのですけれども、ここでの問題点の挙げ方です。我が国の現行の実務では財務諸表のリステートは行われていないので、持分プーリング法を採用した場合においてリステートを要求するかどうかという問題点があるということと、我が国においても財務諸表の比較可能性の観点からリステートが必要であるとする意見がある。それから、リステートを要求するとした場合には、その具体的な手続や問題点を検討していく必要が出てくると予想されるということですが、きょう神田先生もいらっしゃいますが、今、財務諸表のリステートあるいは遡及して修正するということは、我が国の現行の枠組みの中、法的な枠組みの中では、やはりこれは不可能と考えるのが妥当でしょうか。
- ○斎藤部会長
-
神田先生からお答えいただけますか。
- ○神田部会長代理
-
基本的に商法の議論だけを申しますと、年度決算で確定したものを事後的に、もちろん間違いを修正するということはできますけれども、そうでなかったこととするということは想定していないと考えざるを得ないと思います。と申しますのは、法的にはそこで確定した利益に基づいて利益処分案なり、その処理案が株主総会で決議されて、ずっと続いているわけですから、もちろん間違っていた場合のリステートは、非常に典型的な場合は単なるミスもあるかもしれませんが、粉飾決算のような場合には、これは全部計算をし直して、実は利益があって利益処分したけれども、利益はなかったわけだから利益処分も無効である。もちろんそれはそうですけれども、いわゆる正しい会計基準の中でのリステートということは、恐らく遡及するというのは想定していないということかと思います。ただ、ほとんどそういうことを議論したことはないと思うんですね。ですから、企業会計の方で可能だということになれば、あるいは法律上も一定の範囲で可能だという議論は可能かと思います。一定の範囲でというのは、一遍生じた法律効果を覆滅させることはできないと思いますので、払った配当は有効。そういう条件のもとで、財務諸表自体は企業会計上適正なリステートであれば、それは今の商法上もリステートしてよろしいという考え方は成り立ち得ないではないと思いますけれども、あいまいなお答えですみません。
- ○斎藤部会長
-
今たまたま問題になったから気になったんですけれども、今の部分は、持分プーリング法を採用したときに、例えば比較可能性の観点からリステートするという、そういう話でしょうか。
- ○山田委員
-
私は実は2つ含んでおりまして、参考情報として過去の財務諸表を現在の情報で直すという話と、それから、国際的なところで行われる会計方針を変更した場合に、過去にさかのぼって期首の剰余金を修正するというような問題と、両方何かあるような感じがしていまして、特に後者の場合は、現在国際的には2つ、会計基準を変更したときに当期の損失とする方法と、それから期首の情報を修正するという方向があるんですが、これを統一して、もう期首の剰余金の修正だけにしようという議論が始まっていまして、厄介だなと思っていたものですから、そういうことを含めて、必ずしも今日の問題だけではないことで失礼しましたが、そういう意味でした。
- ○斎藤部会長
-
私が申し上げたかったのは、ここで言っている比較可能性というのは、時系列の比較可能性ですよね。そうするとむしろパーチェスが比較可能性を損なうわけですね、評価替えしますから。プーリングの場合には、ストックに関する限りでは続いているわけでありまして、それがプーリングのケースで時系列の比較可能性を確保するためにリステートとするという議論にどうしてなるのかということがわからなかったものですからお伺いしたんですけれども。
- ○辻前企業会計専門官
-
この意見を言われた方は、必ずしもリステートした方がいいというようなお立場ではないんであろうとは思うんですが、持分プーリング法を採用した場合は、リステートをするということが、海外ではそうするということは割と知識としては一般的というか、実務でよく言われているということから、例えば持分プーリング法という考え方を日本に入れてきた場合には、一緒に取り入れていく必要があるのかどうか検討する必要が出てくるのではないでしょうかという趣旨でしたと思いますので、ここでは要するに持分プーリング法をそもそも採用するかどうかというあたりから議論になってくるというような理解でおります。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
持分プーリングというか、合併にシナジーがない場合は、1足す1が2になるような合併の場合に、キャッシュ・フローは変わりませんから、その場合プーリング法は合併のタイミングからニュートラルであります。仮に期末に合併していても、極端な話、前年度から合併していたという仮想ができるんですけれども、パーチェスの場合には合併タイミングがフェアバリューを変えてしまうために、前から合併していたらどうなるかということが計算しにくいわけですね。そのために多分ないと思うんですが、逆に、シナジー効果があると、必ずしもプーリングは合併のタイミングからニュートラルでないので、リセットする意味がほとんどないわけです。パーチェスで意味がないのと同じように、合併タイミングが違うこと、合併期日を仮想的に動かしたときに、プーリングも必ずしも単純計算でリステートできる状況ではない。つまりシナジーがあるとできないので、本来はやる意味がないと思われます。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、神田先生。
- ○神田部会長代理
-
さっき私は一般論として申し上げたんですけれども、今合併の話が出ましたので、合併会計については商法上は議論がありまして、前回の平成10年の改正のときに、商法上もきちんと定めようかどうかとということで議論したんですけれども、最終的には実務にゆだねるということで規定を行ったんですね。そのときに主として議論がされましたのは、どういう例でもいいですけれども、A会社とB会社が8カ月たったところで合併をした。Bが吸収したとしますと、その後4カ月たちまして、Bについては商法の監査は12カ月分、Bの会計監査人なり監査役がやりますけれども、Aという会社は8カ月で消滅していますので、その8カ月分をだれが監査するんだと。それは12カ月たったところでBという、一緒になっているわけですけれども、会計監査人と監査役が合併前B会社のみならずA会社の8カ月分もやるのかどうか。あるいはAがそこで必ず決算して監査してからやってきなさい。ロジカルに言えばその2通りですけれども、それならもういっそのこと期首にさかのぼって、最初から監査との関係ではA社はなかった。すなわち合併は期首に起きていたものとして取り扱うという規定を例えば置くことによって、商法上、特に監査との関係ですけれども、明確になるのではないかという議論は盛んにしたんですね。ただ、盛んにしたというのは法制審議会の当時商法部会ですけれども、私の記憶では、ヒアリングをしたときに実務の取り扱いはたしか分かれていて、それで、これは何か法律で一律にドイツなんかは決めていますけれども、決めるのがいいかどうかということについては必ずしも自信が持てなかったために、それまでも合併はずっと行われてきているわけですから、そこは実務にゆだねましょうということで特に規定を設けなかったという経緯がございます。ただ、これは合併に限ってのお話で、先ほどは遡及一般についての合理的な考え方ですけれども。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
- ○神田部会長代理
-
パーチェスかプーリングかを決める基準として、会計のロジックとして次のようなことが可能なのかというご質問をさせていただきたいのですけれども、1つは、私が先ほど言いかけたことで、例えば今回、企業再編税制の基準になっていますような、80%以上の従業員が引き継がれた場合とか、常務クラス以上の役員が引き継がれた場合、そういう人にものすごく着目して、そういう場合はプーリング法ですという、そういうのは会計のロジックとして成り立つのかどうかというのが1点です。
もう1点は、これも今回の企業再編税制でとられている考え方ですけれども、税制の方を先に申しますと、連結納税というのはまだ導入されていませんけれども、いずれ導入される。連結納税の対象になり得るような企業の間では、営業の移転ではなくて個別資産の移転であっても課税の繰り延べを認めましょうと。簡単に申しますと、企業グループ一体となっているのだから、別に左のものを右にして、右のものを左の中で動いているだけで、パーチェスは行われていないという考え方ですね。同じような考え方は会計でもとれるのか。すなわち連結会計の対象になっている中で物が動いた場合には、別にフィフティー・フィフティーだとか何とかだということは言わなくて持分プーリングだという、そういう考え方というのは、ある種連結だから同じですけれども、仮に個別で考えた場合ですけれども、ロジックとしてあるのかどうかというのを教えていただきたいんですが。
- ○斎藤部会長
-
後者については、今のお話は、連結集団内部での資産の移転ないし合併ですね。これは通常、連結を開始する時点で既にパーチェスに準じた処理が行われていて、あとはその中で合併をしてみても、そのままで、それ以上の変化はないわけですから、それをプーリングと呼ぶか何と呼ぶかは私はわかりませんけれども、個別資産についても評価替えというのは起きないんだろうと思うんですね。もちろんその場合の前提は、連結を開始する時点で、いわゆる全面時価評価をしている。部分時価評価ではないということが前提になりますけれども、その場合には、いずれにしても個別資産についての評価替えは生じないだろうと思います。
それから、前者の問題については、特に人に着目するというのは、その事業サイドに着目するわけですが、通常会計のロジックでは、これまでは事業よりは持分に着目してきた。そのときに、事業に着目するというのが持分に着目する見解に対する代替案なのか、あるいは補完的な役割を持つのか。その辺がよくわからないんですけれども、いろいろな議論はあると思います。ありますけれども、持分サイドに全く着目しないで、事業だけで考えるという議論は、多分少ないのではないかと思いますね。ただ、それが不可能ということはもちろんないと思うんですけれども、その辺、どうでしょうか。むしろ小宮山先生とか、あるいは大日方さんから発言をしていただいた方がいいかもしれませんが。
- ○大日方委員
-
例えばプーリングの論拠として言われている、持分の継続といったときのメルクマールというのは幾つかあると言われているわけですが、そういうとき、やはり基本的には持分比率がメーンで、ただ、そのときに絶対基準があって少しでも欠けたらというのではなくて、それが多少いびつであっても、違うことで補完的に継続性を認められるならばもちろん継続企業と認める。例えば連結の範囲のような考え方で、基本は数値基準でいくわけですが、実数を考えるときに、数値基準オンリーですと、形式を悪用して、例えば50%にとどめると連結から外れるということがあるので、そこを補完するという意味でほかの基準を入れているわけです。基本的にはそういう考え方で、持分の継続、あるいはビジネスの継続といった場合にも、その持分とか出資比率、あるいは議決権というのをメーンに考えつつ、ビジネスで使われる資産の継続性や人の継続性を補完的に使っているのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
多分会計のロジックとしては、持分とか時価総額とかいうロジックから来るんだろうと思うんですね。ただ、実務をやっている実感としては、8割以上の従業員が変わらないとか、常務以上が1対1でずっといくとかいうのがプーリングだというのは非常に実感としてわかるんですね。ただ、これを会計的に説明するというのは難しいんだろうという気はしているんですね。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございます。神田先生、当面こんなことでよろしゅうございますか。
- ○神田部会長代理
-
わかりました。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
神田先生がおっしゃられたように、会計上あらわれることのないデータを会計基準でコアに使うのは多分難しいんではないかというお含みがあったかもしれないんですけれども、ただ、その役員――従業員にするのは難しいのかもしれませんが、役員については、その役員に対する貸し付けを別立てで勘定を分けておくようなこともあります。役員に対しては、そうやって不正の危険を開示するという発想を持っているわけで、必ずしも人に帰着させて会計処理を変えるというのが全くないわけではないので、それが会計上耐えられない、非常にソフトとかファジーな基準というわけではないと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
このきょうの資料の3ページなんですけれども、実態に即して持分プーリングが妥当な場合があるということで、その場合に持分の継続が今問題になっているんですけれども、それをどう識別するかというところで、例えばこの3ページの(4)の4のところです。余り先走りしてもいけないんですけれども、持分の結合というとき、一番わかりやすいケースとして、50%ずつ、あるいはそれに限りなく近いということが出てくるわけです。しかし、その問題を(5)の共通支配下の問題とあわせて考えてみますと、例えば共通支配下の取引、先ほど神田委員の方からもご質問があったわけですけれども、そこに一たん入っている企業については、すでに連結が始まっている。企業結合会計が広い意味では適用されていて、その後に合併されても、会計処理は異ならないということがあり得るわけですね。そうしますと、その場合に、これはもちろん持分の継続というのが前提になっているわけですけれども、そこの持分の継続というのは、出資比率の50%ずつということからは外れていますよね。ですから、持分の継続と、出資比率の50%ということがどれほど同質のものなのかということが非常に疑問なわけです。
そうしますと、先ほどの内山参考人の説明にもありましたように、むしろ持分の継続というのは人の動きで端的にあらわれるということであれば、定性的な基準というのを特定して何か設けるということは難しいかもしれませんけれども、それを幾つかの識別規準に設けるということは十分可能なのかなという感じなんですね。ポイントは、今後実態として持分プーリングの方が適しているようなケースがあり得る。その場合に、それは何かというと持分の継続だと。それは必ずしも出資比率と同質のものではない。出資比率だけにあらわれる、それが50%ずつということではないのではないか。その1つの例として、共通支配下にある子会社の合併というのは50%ずつの出資にもちろんならないわけですから、こういうケースを考えてみても、そのようなことが言えるのではないかという感想ですけれども。
- ○斎藤部会長
-
ただ、共通支配下の企業間の合併については、先ほど私が申し上げましたように、プーリングと呼ぶのが適当かどうかわからないんですね。ですから、それを支える論拠として持分の継続という概念を持ち出す意味があるかどうかもわからない。そういうケースに該当すると思います。
- ○辻前企業会計専門官
-
今の☆の4のところですが、どう特定するか問題となってくるというようなこのご指摘は、どちらかというと日本だけで決めるというよりも、それを海外に対して説得できるような形に整理するのは難しいという面も入っていたのではないかと記憶にありますので、つけ加えさせていただきます。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
50:50が何か突出して言われて、定着すると困るのですが、もちろん個人的な意見ですけれども、例えば40:60でもプーリングを使う論理的余地はあるだろうという気がするわけです。50:50という限界は、どちらかというとプーリングを制限するという、ある意味でそういうスタートラインに立っているわけですけれども、逆にパーチェスの論理が必ずしも当てはまらないのではないかという状況がそろっていれば、プーリングを使ってもいいとも言えるのではないかと。例えば40:60というと、大きい方から見て3分の2の規模のものを取得するとことになるわけですが、例えばその株価総額で考えた場合に、自分の株価総額の3分の2の投資案件を、仮にパーチェスが要るような時価発行増資をして現金支出をするというのは、途方もない設備投資ですから、現実離れしたフィクションだとも言えるわけです。ただ、その場合に、やはり説得的であるためには、それを補完するような、そのときには人的要素も考え得るみたいな形の使い分けの基準というのもあり得るのではないかという気がしております。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
特にほかにご発言はないでしょうか。辻山委員。
- ○辻山委員
-
誤解があるといけないので。共通支配下にある会社が、支配確立時点でもちろん一たんパーチェスが適用されるわけですね。それがその後現実に合併になった場合に、パーチェスが一たん適用されたものがそのまま適用されるという、そういう意味で、それが持分プーリングだということではなくて、それがなぜそのまま、一たんパーチェスでなったものがそのまま連結の中で同様の処理が継続されるのかという、その考え方の中に持分の継続というものがあるでしょうという、そういう意味で先ほど申し上げたので。
- ○斎藤部会長
-
それだったら通常のゴーイングコンサーンの場合と同じことですよ。それはやはり持分が継続しているのではないですか。
- ○辻山委員
-
そうです。
- ○斎藤部会長
-
わかりました。ありがとうございました。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどから識別規準になじむかどうかということで、人的な従業員とか経営者、こういう議論がなされていて、大方の議論はなじむだろうと。会計上はなじまないかもしれないけれどもなじむだろうと、そういうようなことだったと思うんですけれども、これは全く私も同感――同感というのは、一応識別規準というのは会計の前提となる取引とか、そういう実態の識別という1つの仕組みにアメリカなどではなっていて、要するに会計の対象である取引自体がパーチェスという取引なのか、持分プーリングという取引なのかという識別の規準と、それに対して、そう識別されたならば会計処理はこうなるという考え方でいくと、会計処理の前提である取引自体をどのような側面から識別していくのかという点でいけば、いろいろなものが考え得ることなのではないか。要件として考え得るのではないか。ですから、先ほどからの議論はそこに尽きているだろうと思います。
そこで、アメリカでは、例えば企業結合における当事者の意思というようなあいまいなものも識別規準の中で議論されているという点もあるんですね。意思というか目的というか、そういうようなものですら検討したらどうかという議論もあったぐらいでございますので、実態を識別するに当たっては、非常にいろいろなものを議論することができるのではないか、また、した方がいいのではないか。そこに日本的な経営の特質というものが入ってくる。そういう仕組みになっているんだろうと、考え得る余地があるんだろうと思いました。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
識別規準に人の継続性ということを入れられるかどうかというときに、恐らくワークするかどうかは、合併の基準を裏切るというか、約束を破ってしまうような行為があるときに、どの程度拘束がかかるかということだと思うんです。要はビジネスの継続性というと、主要な部分の資産を売ってはいけないということをやろうとしても、多分余りサンクションなしで売ることができると思うんですが、ただ従業員の場合であれば、日本の労働法制のおかげで、そう簡単に一方だけの側、吸収側でもどっちでもいいですが、一方側だけの理屈で削減するということは多分できないでしょう。そこでサンクションがかかるので、ある引き継ぎを要件にプーリングを認めたとしても、後で逸脱するような行為というのはそう簡単に起こらないと想定できれば、識別の要件に入れることは可能ではないかという感じがしております。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
それでは、おおむね時間になりましたので、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。
次回、6月1日の部会につきましては、論点整理の原案を文章化して、それをご審議いただくことを考えております。次回の審議に先立って原案をご送付できるように作業を進めていきたいと考えております。
次回につきましては、6月1日金曜日の14時から16時を予定しておりますけれども、詳細につきましては改めて事務局からご連絡申し上げます。
本日はお忙しいところをまことにありがとうございました。これで散会いたします。

 検索
検索