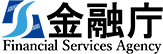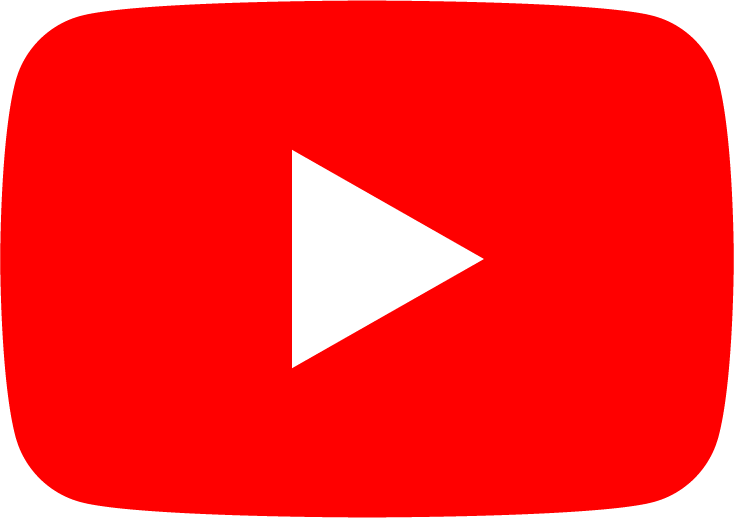平成14年2月8日
金融庁
企業会計審議会第16回第一部会議事録について
企業会計審議会第16回第一部会(平成14年1月11日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第16回第一部会議事録
日時:平成14年1月11日(金)午後2時01分~午後4時03分
場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室
- ○斎藤部会長
-
それでは、定刻になりましたので、これから第16回の第一部会を開催いたします。
委員の皆様には、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、前回に引き続きまして、パーチェス法に係る論点について意見交換を行う予定にしております。
最初に松岡委員から、前回の報告に補足する事項についてご説明をお願いいたします。
- ○松岡委員
-
それでは本日は、まず前回の部会のときに承りましたふたつの課題に関しまして、具体的には、ひとつ目として企業結合完了後、取得対価の配分手続が終了するまでに開示される財務諸表の位置づけに関しまして、ふたつ目といたしましては、条件付取得対価が規定されている米国における合併契約事例の紹介をあわせてさせていただいた後に、簡単な設例を用いまして、段階取得の会計処理についての比較検討についてお話をさせていただきたいと思います。
それでは、お手元の4枚のレジュメに従いましてお話をさせていただきたいと思います。
ひとつ目の開示例といたしましては、AOL Time Warnerの開示例の紹介でございます。
まず(1)といたしまして、これは2001年2月9日付の8-Kに対する修正においてどのような開示がなされているかを簡単にまとめさせていただいたものでございます。その中の「重要な取引」と題しますところで、以下のような記載がされておりました。
必要と思われるところだけ理解の補足のために読ませていただきますと、まず、2001年1月11日にAmerica OnlineとTime Warnerは、以前公表したAOL Time Warnerを設立して合併するための契約を完了した。合併の完了日が1月11日であるということでございます。その合併は株式交換として構成された。合併に先立ち、America OnlineとTime Warnerは、AOL Time Warnerという社名の持株会社を新たに設立し、AOL Time Warnerは100%子会社を2社創設した。取引完了時に一方の100%子会社がAmerica Onlineと合併し、America Online社となるとともに、他方の100%子会社はTime Warnerと合併しTime Warner社となった。その結果、America OnlineとTime WarnerのいずれもAOL Time Warnerの100%子会社となった。
この合併の結果として、America Onlineの旧株主はAOL Time Warnerの約55%持分を有し、Time Warner の旧株主はAOL Time Warnerの約45%持分を有するようになった。この合併は2001年第1四半期に企業結合の会計処理方法であるパーチェスに従い、AOL Time WarnerによってTime Warner の取得として会計処理される予定である。この場合、Time Warnerが被取得企業であるということでございます。
この8-Kは、恐らくわが国でいうところの臨時報告書に類するようなものであろうと考えられますので、このような記載がなされております。
続けて読ませていただきますと、パーチェス法の下では、Time Warnerを取得するために要する見積コスト約1,470億ドルは、それらの基礎をなす純資産に対して各々の見積公正価値の比率に基づき配分されることとなる。購入価格が取得した純資産の見積公正価値を上回る額はのれんとして記帳されることとなる。
この部分につきましては、いわゆるパーチェス法の会計処理の概要について記述しているものと考えられます。
引き続きまして、(2)といたしまして、その後の2001年11月14日日付の10-Qにおきまして、どのような開示がなされているかをお話しさせていただきたいと思います。
まず、連結財務諸表に対する注記の1、重要な会計方針の要約の箇所におきまして、第1、第2段、中略のところまでは先ほどお話させていただいた内容とほぼ同じでございますので省略させていただきまして、2ページ目の取得した純資産の箇所から読ませていただきます。
取得した純資産、識別された無形資産及びのれんの公正価値や加重平均有効期間の見積は、暫定的な見積に基づいている。取得した純資産、識別された無形資産及びのれんに対する購入価格の配分を終了させるためには追加的作業が必要である。AOL Time Warnerは、購入価格の最終的な配分結果が以下の連結財務諸表に含まれる金額と大きく異なることはないと考えているというような記載がなされております。
また、注記の2におきましては、合併関連コストに関して次のような記述がなされておりました。
合併との関連でAOLは事業の見直しを行い、America OnlineとTime Warnerの事業を再構築すべく、いくつかの計画を実行した。その計画の一部としてAOLは、2001年第1四半期に約9億6,500万ドルのリストラ負債を当初未払計上した。AOLは追加的な決議により認識が要求されることとなる会計上の基準が満たされたことから、第2四半期に6,500万ドルの負債を、第3四半期には1億ドルの負債を追加的に未払計上した。これらのリストラ未払費用は、AOLが特定事業から撤退し集約するコストのほか、多数の事業ユニットに跨がる従業員を解雇するコストにも関連している。これらの金額はパーチェス法のもとで企業結合において引き受けた負債として認識され、Time Warnerの取得コストの配分に含められた。故に、そのような金額は合併との関連で記帳されることとなる追加のれんを生じさせたというような記載がされております。
中略の後、この合併関連コスト及び記帳されたリストラクチャリングに係る負債は、経営者がコミットしているAOLのリストラクチャリング・プランに基づいている。これらのプランは経営者が結合後会社の統合を引き続き評価し購入価格の配分を完了させるにつれて、第4四半期において精緻化される予定である。いかなる追加リストラ関連コストも、リストラクチャリングに係る負債の一部分となるか、あるいは合併関連コストに含められることとなるというような記載がなされてございました。
今申し上げました開示例は、いわゆる取得対価に条件が付されていない事例に該当するのではないかというように考えられます。
なお、2000年2月11日の開示のフォームでいきますと、S-4におきましては、被取得企業でありますTime Warner社の役員が、Time Warner株主が受け取ることとなる、このAmerica Onlineの株価が合併発効日前に下落するということを制限するような条項が、この合併契約においてなされていないということは、この合併がいわゆる対等合併、真実の合併とも言われておりますけれども、そういったものであるためであると考えているというような記述がなされておりましたので、参考までにお話をさせていただきました。
もうひとつ参考といたしまして、取得対価の未決条項、あるいは取得対価の配分手続と関連する主なSFAS141号の開示規定を簡単に紹介をさせていただきたいと思います。なお、現行の国際会計基準の22号もほぼ同様の内容でございます。
まず、企業結合の完了年度の財務諸表に対する注記として開示が求められております事項といたしましては、ひとつ、取得契約に明記されている偶発的な支払い、オプション、もしくはコミットメント、並びにそれらが生じた場合に採用予定である会計処理方法、これはパラグラフの51-Fに該当いたします。もうひとつといたしましては、終了していない取得対価の配分については、その事実及び理由、次年度以降では取得対価の当初の配分になされた重要な修正の性質とその金額を開示してください。これはパラグラフ51-Hでございます。
なお、重要な企業結合が決算日後、財務諸表の公表時までに完了した場合も、実行可能である限り、今申し上げましたような注記が必要とされております。それはパラグラフの56でございます。
それでは、続きまして、もうひとつの開示事例といたしまして、MCI WorldComの開示例を紹介させていただきたいと思います。レジュメの3ページ目でございます。
説明の便宜上、3ページの一番下の方ですね。合併の背景の箇所からお話をさせていただきたいと思います。
読ませていただきますと、1996年11月、MCIはBTとの合併に合意した。1997年8月、BTとMCIは、MCIとBTとの合併において、MCI株主が受け取ることとなる対価を引き下げるとする、合併条件に対する修正に調印した。1997年10月、WorldComは、調整条項付きで、一株当たり価値41.5ドルの自社株式と各MCI株式との交換を申し出た。この金額は、MCIとBTとの合併においてMCI株主がその当時の米国におけるBT預託株式価格に基づいて受け取ることとなる金額を上回るものであった。いい条件を提示したということでございます。GTEはその時一株当たり40ドルで各MCI株式を現金で取得する合併をMCIへ申し出た。これは一株当たり40ドルと、41.5ドルよりも低い金額となってございますが、すべて現金でという条件で新たに申し込んだということでございます。MCI役員はそれらの申し出を検討し、両社とさらに交渉を重ね、現行条項の下で考えられている合併対価をBTが引き上げる可能性についてBTと議論した。WorldComは、調整条項付きで、一株当たり価値を以前の41.5ドルから51ドルへ引き上げることを申し出、当事会社とBTとの間で交渉した結果、二社は合併に合意した。その結果、MCIとBTとは現行の合併契約を解除することに双方合意したと記載されてございます。
それでは、レジュメの3ページに戻っていただきまして、この場合の被取得企業であるMCI側の株主に関して記載している箇所を紹介させていただきたいと思います。それはリスク要因の中の合併によって、対象の株主がどういったものを受け取るかということについての記載箇所でございます。「MCI株主」のところを読ませていただきます。
この合併後、各MCI普通株式は取り消され、その交換として、合併前の特定の20日間におけるWorldCom普通株式の平均価格に基づいて算定された、WorldCom普通株式数が付与されることとなる。仮にWorldCom普通株式の平均価格が29ドルから41ドルまでの間におさまるならば、MCI普通株式一株に付き、51ドルを特定の20日間におけるWorldCom株式の平均価格で除して算定されるWorldCom普通株式数が付与されることとなる。パターンの2といたしまして、仮にWorldCom普通株式の平均価格が29ドル未満ならば、MCI普通株式一株につきWorldCom普通株式数1.7586が付与されることとなる。このWorldCom普通株式数1.7586の当初価値は51ドル未満となるであろう。もうひとつのパターンといたしましては、仮にWorldCom普通株式の平均価格が41ドルを上回るならば、MCI普通株式一株につきWorldCom普通株式数1.2439が付与されることとなる(この場合のWorldCom普通株式数1.2439の当初価値は51ドルを上回る)。このWorldCom普通株式の平均価格は、この合併発効前の3営業日前までの連続する20営業日のナスダック市場におけるWorldCom普通株式の売高値と売安値の平均値として算定される。WorldComは一株に満たない株式を発行しない。代わって、そうでなければ受け取ったはずの一株に満たないWorldCom普通株式の合併日における市場価値相当額の現金が付与されるというように記載がされてございました。
今申し上げました例示は、取得企業の株価が特定の価格帯、具体的には29ドルから41ドルまでの間にある場合には、取得対価の価値を保証している事例に該当するのではないかというように考えられます。
なお、1998年9月14日付の8-Kのほかの箇所では、この合併の結果、MCI普通株式一株につき、MCI WorldCom普通株式数1.2439が付与されたというような記述がございましたので、WorldComの平均株価は、恐らく41ドルを上回っていたであろうというように推測されます。
以上が開示例の説明でございます。
それでは、配付させていただいております別紙の設例を用いまして、IASBのスタッフ案、具体的には段階法と全面時価評価法との組み合わせだと思いますが、そちらと一括法と全面時価評価法との組み合わせ、3つ目として段階法と部分時価評価法との組み合わせによった場合の会計処理について、設例を用いてご説明申し上げます。
まず前提でございますが、企業Aは、企業Bの発行済株式総数のうち、20%をX1年度末に600で、60%をX2年度末に2,400で、それぞれ取得した。X1年度末及びX2年度末における企業Bの識別可能純資産の簿価及び公正価値は、以下のようであったというように仮定を置きます。各年度の数値は記載のとおりでございます。
なお単純化のため、ここでは各年度末での識別可能純資産簿価は同額、変動がない。税効果及びのれん償却は考慮しないとしております。また企業Aは、X1年度において企業B株式に対しまして20%を取得しているような仮定になっておりますが、持分法を適用していなかったというように仮定しております。
それでは、具体的に連結仕訳を見ていくことといたします。
まず、段階法と全面時価評価法との組み合わせと考えられるIASBのスタッフ案のもとでは、まず
 番のところで、支配獲得時の公正価値への評価替えの仕訳が記載されております。これは全面時価評価法を前提にしておりますので、記載のとおり、支配を獲得した時点の時価ですべて評価されるということで、評価差額は公正価値の3,000から簿価2,000を引いた1,000を認識しております。
番のところで、支配獲得時の公正価値への評価替えの仕訳が記載されております。これは全面時価評価法を前提にしておりますので、記載のとおり、支配を獲得した時点の時価ですべて評価されるということで、評価差額は公正価値の3,000から簿価2,000を引いた1,000を認識しております。 次に
 番といたしまして、取得している80%部分について資本との相殺消去仕訳が記載されてございます。ここでのポイントとなりますのは、段階法を前提としておりますので、評価差額の700ではなかろうかと思います。注4に記載のとおり、段階法でございますので、まずX1年度末時点の含み益500に対しまして20%を掛けた100と、X2年度末の含み益1,000に60%を掛けた600との合計700が評価差額として算定されることになります。
番といたしまして、取得している80%部分について資本との相殺消去仕訳が記載されてございます。ここでのポイントとなりますのは、段階法を前提としておりますので、評価差額の700ではなかろうかと思います。注4に記載のとおり、段階法でございますので、まずX1年度末時点の含み益500に対しまして20%を掛けた100と、X2年度末の含み益1,000に60%を掛けた600との合計700が評価差額として算定されることになります。 続きまして、
 番では、残りの20%部分につきまして、資本の部分を少数株主持分へ振り替えるという仕訳でございまして、ここでのポイントとしては、注8に記載させていただいていますとおり、少数株主持分は600と、全面時価評価法を採用しておりますので、支配獲得時の時価、公正価値の3,000に少数株主持分の20%を掛けて600となっているということでございます。
番では、残りの20%部分につきまして、資本の部分を少数株主持分へ振り替えるという仕訳でございまして、ここでのポイントとしては、注8に記載させていただいていますとおり、少数株主持分は600と、全面時価評価法を採用しておりますので、支配獲得時の時価、公正価値の3,000に少数株主持分の20%を掛けて600となっているということでございます。 続きまして、一括法と全面時価評価法との組み合わせのもとでは連結仕訳がどうなるであろうかといったことについて記載をさせていただいております。
 番につきましては、先ほどと同様、全面時価評価法を前提としておりますので、評価差額は1,000ということになります。
番につきましては、先ほどと同様、全面時価評価法を前提としておりますので、評価差額は1,000ということになります。 続きまして、資本との相殺消去(80%部分)の仕訳でございますが、この時点での特徴といたしましては、のれんの金額600であろうと考えられます。注の10に記載のとおり、一括法でございますので、支配獲得をした公正価値の3,000の80%、累計の80%を掛けた金額2,400を公正価値の3,000から控除した600、これがのれんの金額として認識されるということでございます。資本の少数株主持分への振替につきましては、先ほどのIASBスタッフ案と同様でございます。
3つ目のパターンといたしまして、段階法と部分時価評価法との組み合わせのもとにおきます連結仕訳がどうなるかということが記載されております。
まず、ここでは、段階法でございますので、まず20%取得時の公正価値への評価替えが
 で記載されております。記載のとおり20%取得時点におけます含み益の20%相当額の100が評価差額として認識されてございます。
で記載されております。記載のとおり20%取得時点におけます含み益の20%相当額の100が評価差額として認識されてございます。 同様に
 のところでございますが、追加で60%取得時の公正価値への評価替えは、その時点での含み益1,000に対しまして、追加の取得相当額60%を乗じた600の金額が評価差額として認識されるということになります。
のところでございますが、追加で60%取得時の公正価値への評価替えは、その時点での含み益1,000に対しまして、追加の取得相当額60%を乗じた600の金額が評価差額として認識されるということになります。 また、
 のところでは、部分時価評価法でございますので、少数株主持分は400と、これは注12で記載のとおり簿価ベースでございますので、2,000の20%の400が少数株主持分として認識されるということでございます。
のところでは、部分時価評価法でございますので、少数株主持分は400と、これは注12で記載のとおり簿価ベースでございますので、2,000の20%の400が少数株主持分として認識されるということでございます。 今まで申し上げました結果を表にいたしましたものが、その下に記載してございます。コメント欄を読ませていただきますと、その結果からどのようなことが伺い取れるかといったことを一応書かせていただいております。まず、全面時価評価法の下では、識別可能純資産は取得日現在の公正価値――3,000でございます――で認識され、少数株主持分は取得日現在の識別可能純資産の公正価値に少数株主持分割合を乗じた額、600で認識される。段階法と全面時価評価法との組み合わせの下でのみ、取得が達成される前の各取引に関連して、各取引日時点での公正価値と取得日現在の公正価値との差額に、各取引により取得企業が新たに保有するに至った割合を乗じた額の合計額が評価差額として、この例で言いますと評価差額100として認識されるということでございます。
簡単ではございますが、私の方からの説明は以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
ふたつの性質の違った問題を続けてお話しいただきましたために、理解しにくいかもしれません。前段は株式交換比率ないし取得対価の問題でありますし、後段は段階取得ないし一括取得の処理の問題でありますけれども、ただいまの松岡委員からのご報告につきまして、まずご質問等がございましたらご発言ください。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
仕訳の方で説明されたIASBスタッフの資料ということですが、出典はどこでしょうか。
- ○辻前企業会計専門官
-
以前の部会で、山田先生からIASBの動向についてご報告をいただきましたので、お願いして、このような仕訳になるのではないかというような推測をしていただいたということでございます。
- ○山田委員
-
ということは、スタッフ案と書いてあるのは、実は公表されておりませんけれども、IASBのスタッフがつくった資料がございまして、必ずしもそれを入手されたというわけではないんですね。
- ○辻前企業会計専門官
-
そのときの部会でのご報告がスタッフの案というようなご紹介だったので、ここでは仮にそのような名前を使わせていただいたということです。
- ○山田委員
-
くどいようですけれども、あくまでも松岡委員の推測ということであるということでよろしいでしょうか。
- ○辻前企業会計専門官
-
そういうことになります。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はございますか。
中島委員、どうぞ。
- ○中島委員
-
2番目にご説明になったMCI WorldComのケースですが、後の方に出てくるBTとかGTEとの関係がよくわからなかったのですが。
- ○斎藤部会長
-
松岡委員、お願いいたします。
- ○松岡委員
-
合併の背景のところで補足させていただきますと、当初MCIとBTとの間で、一たん合併をするという合意があったということでございます。それに対しましてWorldComが、より好条件を提示して合併をしたいという申し出を行った。GTEも同様に、好条件を別途提示をして合併に割り込みたいということでございます。GTEの方は、記載のとおり40ドルと、当初WorldComが提示しました41.5ドルよりも1.5ドルぐらい低いという価値になっていようかと思いますが、WorldComの方は、一株当たりの価値41.5ドルの自社株式という提案でございまして、GTEの方では満額現金で40ドル。ですから、推測の域は脱しませんが、株ではなくて現金であれば、この1.5ドルぐらい値が低くても、もしかしたら応じていただけるのではないかというような読みも恐らくあって、GTEの方は提示をしたのではないかというように思われます。
その後に、4ページに記載をさせていただいていますが、結果としてWorldComの方は、当初の41.5ドルという条件から51ドルへ引き上げましたので、MCIとしては、もともと合併条件としてBTと一たん合意していたわけですが、そちらの方が条件が有利だろうということで、一たん合併契約を解除して、最終的にWorldComとの合併に至ったというような経緯でございます。
- ○中島委員
-
ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
要するに、現金買収でなくて株式交換による買収となると、このケースだと2割ぐらいは対価が違うということですね。
最初のケースのAmerica OnlineとTime Warnerについては、二、三日前の日経新聞で報道されておりまして、非常に大きな話題になっておりますので、皆様方、よくご承知かと思います。ここでは1,470億ですけれども、新聞報道ですと全部含めると1,830億ですか、そのくらいのプレミアムのついた対価といいますか、株式交換で買収して膨大なのれんを計上したけれども、どうも株価が上がらないというか、どんどん下がってしまうので、今度まとめて一括してのれんを償却する。そのような話が1月8日の日経の夕刊で報じられておりました。
どうぞ、長坂委員。
- ○長坂委員
-
仕訳の方の質問ですが、IASBスタッフ案ですと、この評価差額が最終的には残ってくると思います。これは資本勘定に入るものと考えてよろしいのでしょうか。
- ○松岡委員
-
過去の部会におきまして山田委員に説明していただきました内容を、私単独で恐らく考えると、たしか再評価積立金のようなたぐいの表現をお使いになっていたかと思いますので、国際会計基準でいくと資本の部に入る内容のものであろうと、これは私が個人的に考えた回答でございます。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
一応ボードの中での議論では、再評価積立金という形で、20%取得時以降に支配を獲得するまでの間に生じた含み益を取り込むというのが、今の22号の理解としていいのではないかという了解になっていると思います。
- ○斎藤部会長
-
取り込むとはどのような意味ですか。
- ○山田委員
-
ですから、評価差額という科目ではなくて、再評価か何かという科目に多分なると思いますが、このように資本の部の中でオンバランスになるという意味です。
- ○斎藤部会長
-
その分が投資勘定と相殺されるのかということですか。
- ○山田委員
-
投資勘定と相殺されずに残ってしまう。今の松岡委員の2枚目の一番下の方にまとめの表がございますね。それの1)というところの700から始まる一番下に100がひとつ残っていると思いますが、これが資本勘定に、多分名前は再評価積立金とか、そのような名前でオンバランスになってくるという処理になるということです。
- ○斎藤部会長
-
いずれにしても、その分が段階法だと残りますが、一括法だと相殺されてなくなるわけですよね。そうではないですか。
- ○山田委員
-
それで結構です。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ないでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
今の点ですが、私もIASBの処理を熟知していないので、よくわからないところがあるんです。通常ですと、一括法であれ段階法であれ、のれんがすべて償却し終われば、結果が必ず同じくならなければいけないはずでありますが、この場合、仮に評価差額を放置するというか、何もしないでのれんだけ償却をする。あるいは減損処理でもいいんですけれども、そうすると結果が違うんです。仮に同じにしようと思うと、この評価差額はのれんの償却に見合って取り崩していく。これがカウンターパートで双方同額だけ膨らんでいるだけですから。とすると、基本的にこの2)の一括法と全面時価評価法との組み合わせと、IASBスタッフ案の決定的な違いはどこにあるかというと、こののれんを100だけ大きくして、それに見合って評価差額を100立てている。そののれんの償却パターンと評価差額の取り崩しパターンが異なる場合に結果に違いが出てくる。もしもこれがのれんの償却に見合って評価差額を戻してしまうと、単純に水膨れしているだけで、ネットでは変わらないわけであります。とすると、IASBスタッフ案という呼称でいいかどうかわかりませんが、この1)の方はオリジナルな意味を持つとすれば、のれんの償却パターンとその評価差額のその後の取り崩し。その期間帰属の配分パターン、あるいはその後リサイクルするかわかりませんが、そこにかかっているのではないかと思います。したがって、この会計処理方法が閉じた体系として説明されるためには、この評価差額のその後の帰趨がどうなるのか。例えば極端な話、のれんを生み出した資産を処分してしまっても、なおかつここの部分はずっと残り続けるのかというような点にかかっていると思います。
- ○斎藤部会長
-
残るのではないでしょうか。要するに、この設例は、X1年度末とX2年度末の簿価が変わっていないケース、つまり、その間に利益の留保がないケースと考えていますが、含み益の話にするとややこしいので、今は含み益の話をしないで、この1年間に利益が留保されたケースで考えた方が簡単なんですよね。そうすると、段階消去をとった場合、第1回目の取得日から第2回目の取得のときまでに生じた留保利益に対する持分相当額が、段階消去の場合には相殺されないで連結剰余金に残る。一括取得だとそれが相殺されてしまい、のれんが違ってくるわけですね。のれんが違う分だけは連結剰余金の違いになるわけで、したがって、それはずっと残るんですよね。この場合の含み益相当額は全く同じ話で、恐らく今、大日方委員がおっしゃったとおり残ってしまうと思います。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
残ると思います。それで、のれんとひもをつけて何らかの形でこの評価差額を償却するということはないので、したがって、そのもととなった、例えばこの場合だと土地か何か、書いていませんが、土地なら土地の処分に合わせて通常の評価差額の処理という形になると思います。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ないでしょうか。
特にきょうの松岡委員から補足的にご説明いただいたことについては、ご質疑よろしゅうございますか。
小宮山委員どうぞ。
- ○小宮山委員
-
この評価差額は確かに仕訳的に残りますが、全く取り崩されることはないんですか。そこが疑問として残りますが、その資産の評価が変わったとしても、これは全く関係ないという認識ですか。
- ○山田委員
-
少なくともリンクはしないと思います。
- ○小宮山委員
-
例えば、恐らくこのやり方ですと、インタンジブルの評価というのが入ってきますよね。同じものの評価が違うようなケースは、多分評価差額にこれは入るんだろうと思いますね。その場合で、そちらの評価が変わったときでも、やはり取り崩さないということになるんですかね。
- ○斎藤部会長
-
それはまた別の議論ではないでしょうか。その場合に、例えばインタンジブルを評価替えしたときに評価損が生じたら、それと今の繰り越されている評価益を相殺するというルールは考えることは可能ですけれども、何も決まっていないですよね。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
確かにそこははっきりしていないんだと思います。ただ、私はIASBで議論したとき漠然と思っていたのは、通常のIAS16号の資産の評価、時価評価の方を使って出てくる再評価積立金のような扱いをするのかなと思っていたのですが、考えてみるとそのような必要もないので、したがって、この部分というのは、IASB的に言うと第2フェーズのところで議論するという処理に多分なるのかなと感じた次第です。
- ○斎藤部会長
-
よろしくどうぞお願いします。
ほかにないでしょうか。
ほかになければ、また後で戻ってくださっても結構ですが、もう少し一般的な話に入って、前回に引き続いてパーチェス法の検討1という、この間のテーマに関して意見交換を行いたいと思います。特にどの論点かという順番は設けませんので、思いついたところからご自由にご発言ください。
- ○辻前企業会計専門官
-
それでは、前回の資料ですけれども、皆さんのお手元にお配りしております黒表紙の大体真ん中ぐらいにレジュメの順番につづり込んでいます。済みません、お手数をおかけしまして。
- ○斎藤部会長
-
資料がおわかりいただけたところで、ご自由にご発言ください。
梅山委員、どうぞ。
- ○梅山委員
-
前回の審議会の私の発言の訂正も含めて、ひとつお話しさせていただきたいのですけれども、前回、公正価値の測定方法のところで、市場性のある有価証券につきまして、金融業については特殊性があるのではないかと、そのようなことで、すべて市場価値で測定することについて、もう少し検討していただけたらどうかというように発言いたしたのですが、改めてその後考えましたところ、特に金融業に限って会計上特別に留意するところはないのかなという感じがいたしました。したがいまして、前回業界の特殊性について申し上げたことにつきましては訂正させていただきたいと思います。
その発言のついでに、もうひとつ思いついたところですが、公正価値の測定方法ではないのですけれども、資料で後ろの方に資本の増加額の取り扱いのところがございます。この資本の増加額の取り扱いについては、すべて資本金とするかどうかという検討をこれからしていただくのだろうと思いますが、一部の企業で土地の再評価法に基づきまして再評価差額金を上げているケースですけれども、この土地の再評価法を見てみますと、合併の場合には、その再評価差額については法律上は引き継がなければいけないというような文言がたしかあったかと思います。一方で、会社の分割による企業結合の場合には売買という解釈がとれますので、これは分割会社から承継会社に移る場合に再評価差額金は取り崩せる。そのような格好で、企業の結合の形でも、適用される法律によっては再評価差額金が承継されなければならないケースと承継をする必要がないケースというように分かれるかと思いますので、この辺の日本における土地の再評価法についても勘案しながら、資本の増加のところはご検討をしていただく必要があるのかなと思っています。
話がふたつに分かれましたが、以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
それは了解できますね。正確に今すぐ思い出せませんが、その他有価証券のお話でしたでしょうか。
- ○梅山委員
-
有価証券、特にその他の有価証券のところです。これについては公正価値で評価をするわけですけれども、それにつきまして、評価差額金ということでリサイクルしなくなってしまうと保有している有価証券が大きいものですから影響があるのではないかというように考えたわけですが、会計上の取り扱いとしては、それは考える必要はないのではないかなということでございます。
- ○斎藤部会長
-
それは金融業に限定しない一般論として、その他証券の評価差額金があったとして、それが継続企業であれば、実現すればリサイクルされますけれども、合併で引き継がれた場合にはリサイクルしないという形になることについて異論はないと、このような意味ですね。
- ○梅山委員
-
金融業だからといって、それについて異論を持ち出すことはないのではないかなということでございます。
- ○斎藤部会長
-
わかりました。
おっしゃる意味は、恐らく金融業だから特に問題とはしないということであって、一般論としてどうかということは依然としてオープン・イシューなわけですね。
- ○梅山委員
-
そうでございます。
- ○辻前企業会計専門官
-
とっかかりというわけでもないのですけれども、9ページの方になりますが、8の
 で逆取得の取り扱いというのを前回ご説明頂いたわけです。このように「連結財務諸表上は」というように考えた場合におきまして、個別財務諸表の方をどうするかというような問題もあろうかと思いますけれども、逆取得に該当した場合に、そもそも個別財務諸表の会計処理を修正するのは非常に大変ではないかというような見方もあるようでございますし、結果的には、要するに会計上の取り扱い、会計上の取得企業の方を形式上の存続会社にするような処理が一般的になるのではないかというような見方もあるようですが、そのあたりについて、ご意見があれば伺っておきたいと思います。逆取得の取り扱いのあたりですね。
で逆取得の取り扱いというのを前回ご説明頂いたわけです。このように「連結財務諸表上は」というように考えた場合におきまして、個別財務諸表の方をどうするかというような問題もあろうかと思いますけれども、逆取得に該当した場合に、そもそも個別財務諸表の会計処理を修正するのは非常に大変ではないかというような見方もあるようでございますし、結果的には、要するに会計上の取り扱い、会計上の取得企業の方を形式上の存続会社にするような処理が一般的になるのではないかというような見方もあるようですが、そのあたりについて、ご意見があれば伺っておきたいと思います。逆取得の取り扱いのあたりですね。 - ○斎藤部会長
-
いかがでしょうか。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
今のお話は、結局、商法の規定上は、逆取得の場合であっても形式上の形で割り切らなければいけないということで、だから、連結だけは逆取得という実態に合わせて入れかえてしまうということをおっしゃっているわけですよね。
- ○辻前企業会計専門官
-
ここで書いてある8の
 の考え方でいくとそのようなことになると思いますが、ただ、それは非常に負担が大きいというような見方もあるようですので、その場合は結局取引の方を、要するに最初の時点に――最初というか、合併で存続会社を決めるときに、もう会計上の見通しを立てて、取得企業になる側を存続会社にするというようなパターンが一般的になるのではないかという見方も耳にしたので、そのあたり、逆取得の個別財務諸表の会計処理をいろいろ考える上で、ご意見を伺っておきたいところですが。
の考え方でいくとそのようなことになると思いますが、ただ、それは非常に負担が大きいというような見方もあるようですので、その場合は結局取引の方を、要するに最初の時点に――最初というか、合併で存続会社を決めるときに、もう会計上の見通しを立てて、取得企業になる側を存続会社にするというようなパターンが一般的になるのではないかという見方も耳にしたので、そのあたり、逆取得の個別財務諸表の会計処理をいろいろ考える上で、ご意見を伺っておきたいところですが。 - ○山田委員
-
商法上、逆取得を、連結上買った方と買われた方が逆になるから、それに合わせて商法上、それを見込んでどちらが存続会社か決めるとなると、実は普通の取得になってしまうということではありませんか。
- ○辻前企業会計専門官
-
そのような事態を考えると、逆取得ではなくなってしまうということですが、逆取得とここには書いてありますが、実際実務上はそういうものが出てくるのかどうなのかというあたりですね。
- ○斎藤部会長
-
それはわからないのではないですか。そのくらいのコストを払ってもやりたいという人はいるかもしれない。
- ○山田委員
-
ちょうど今、その議論を財団でもやったわけですが、普通挙げられている例は、上場されているけれども余り活発に活動していない会社があって、非上場会社が上場基準をクリアしないで上場企業になるためにそのような形で使うというケースがあるという例がひとつあります。例えばそういうのを当てはめるとなると、今のように実質非上場会社が買ったので、そちらを商法上のところで継続会社にしてしまうと、ねらっている効果が実現できなくなるのではないかなと思いますが。
- ○辻前企業会計専門官
-
ご意見は承っておきます。
- ○山田委員
-
ですから、そのようなことは多分起こらない。つまりねらいがなければ通常このような逆取得ということはないので、何らかの規制があって、それをクリアしてある効果をねらおうとしているんだろうと思いますが、それを商法上のところで実質を優先した形に決めさせてしまうと、何か本来ねらっていた効果がなくなってしまうのではないかなと思います。
- ○斎藤部会長
-
西川委員、どうぞ。
- ○西川委員
-
どのようにして存続会社を――会計上の存続会社という概念があるのかどうかわかりませんが、それをつくるのかよくわかりませんけれども、商法上の存続会社は被取得企業のままにして、会計上は取得企業をあたかも存続会社であるようにやれるという話になるのであれば、それはそれでいいんだろうと思うんです。ただ、どう考えても、商法上の存続会社が被取得企業であったら、個別の財務諸表では自分の資産を一たん時価に変えるという、できないことをしないといけなくなりますから、それを何らかの会計上の存続会社のような概念を商法の中でつくってくれるのであれば、それはそれでいいのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
実際問題としては、A、B両社があって、A社が非常に大きいけれども債務超過だと。3期連続だと場合によっては上場停止になる、そのときにB社と合併するとき、B社の方を取得会社にしてパーチェス法を適用すれば、A社は評価替えできますよ。それで債務超過をクリアしてやるけれども、実質的にはA社の方が取得会社で、名前はA社が残る。そのようなケースは商法上は幾らでも考えられるのではないですか。
- ○山田委員
-
しかし、支配している方がB社の株主だったらB社になる。
- ○斎藤部会長
-
A社が大きいので、実際には支配している方はA社ではないですか。法の形式上も、それからパーチェスを適用する上でもB社の方を取得会社にする。それですと、連結上は取得会社をかえなければいけませんから、膨大なコストがかかりますけれども、そのコストに引き合うだけのベネフィットがなければやらないし、引き合うと思えばやるのではないですか。
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
この各様のケースで、どのようなケースがまともなケースなのか、分けないと言いにくいのでしょうけれども、今の部会長が言われたのは何十年か前に実例がございましたよね。要するに、欠損の解消のために逆取得のパターンで合併をするというケースだと。よく実務的にあったのは、欠損金を持っている会社の税務上の繰越欠損金を利用するために逆取得になるケースで、大体悪いケースしか浮かびませんが、いいケースというのはどのような場合があるのかなと思ったのですが。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
法律上の存続会社と、いわゆるアメリカの基準でいう取得企業がずれているケースの問題だと思いますが、単純に経済合理性というか、ノーマルな行動を考えた場合に、存続会社となるA、B、ふたつあって、必ずしもパーチェス法でいう議決権の大きさ、あるいは時価総額の大きさの相対比の大きい方が、合併においてイニシアチブをとるという保証は現実面ではないわけですよね。極端な話、4対1ぐらい、つまり80%、20%ぐらいで企業結合すると。そうすると、どうしてもアメリカのパーチェス法による考え方だと、20%側が取得されてしまって評価替えの対象になるということになるかもしれないわけですが、現実問題では、要は企業活動を行っていく上で、支配するという場合には、基本的には希少資源を持っている方がバーゲニングパワーは大きいわけでありますよね。ボトルネックを握っている方がどこでも買える普遍的なものを持っているよりも強いわけでして、そこで20%の側がこのような技術を持っているとか、あるいは極端な話ですと、20%の側が単独1人で持っているというか、少数の大株主に支配されている。一方80%の方はものすごく分散してしまっているという場合には、基本的に意思決定のパワーも全然違っているわけですよね。
ですから、パーチェス法でいう取得企業と被取得企業の決定原理が、現実の社会におけるどちらがイニシアチブをとるかというのと必ずしも一致していない以上、いつでも、特に法の蝉脱をねらわなくても、普通に存続企業として決まる会社と取得企業とはずれる可能性は存在しているのであって、この問題は、パーチェスの考え方が単なる形式基準で決めていることに由来しているために生じてしまう。それを防ぐには、どのような場合にどちらがイニシアチブをとるかというのを会計基準で取り込まなければいけないわけですが、それができないとなれば、基本的には解決不能な問題だと思います。やりようがないと思います。
- ○斎藤部会長
-
確かにおっしゃるとおりであって、今、希少資源の話は別にしまして、20%の方、つまり小さい方の会社に重要な少数株主がいるという場合には、アメリカの基準でも、これは持株だけで取得側を決めるという原則の例外になっているわけですね。ですから、実質論として話をすると、そのような問題は確かに次々出てくるわけであって、今おっしゃったようなことをきちんと考えますと、もしかすると逆取得のケースは必ずしも悪用でないケースでも出てくる可能性は残るわけですね。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
そのとおりなので、結局何をねらって、どのようなケースだけに絞るかというところで、何らかの定義というか縛りを入れないと、先ほど大日方委員が言ったように意図しないケースまで入ってくるのではないかと思います。
ちょうどIASBでも議論しているのは、IASBの定義は株の発行で、発行の結果、実質的な買収企業の株主が過半の、ないしは十分な支配を得る株を受け取るという定義になっているわけですけれども、それは株を持った方がイコール支配を持つという前提が置かれていて、必ずしもそうでないケースについては、多分それが当たらないわけですね。今、そこを株ではなくて支配という概念で切りかえたらどうかという提案が行われておりまして、それもよく考えていくと、だれの支配かというのが、株主なのか会社なのかというあたりのところで、もう少し詰めていかないと、非常にねらっているケースと、何かねらわないケースが入ってくるような感じが少しあるので、いずれにしても、これをどう定義していくかという、その方法が非常にクリティカルだなという感じですね。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はありますか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
2点ほどありますが、恐らくお開きのところで、近いところから言いますと9ページのところですけれども、資本の部の扱いなんです。パーチェス法の場合に、基本的に被取得企業の合併前の資本の内訳を基本的に問わない。その意味でリセットされるということですが、先ほど幾つか例がありましたけれども、資本の部の中には、異なる時点でまたがっているものの、複数の取引をもって初めて完結するような項目がないとは言えないものもあるわけです。比較的最近のトピックスでも、例えば自己株で生じたような資本剰余金のようなものがあるわけですが、そのようなものを完全にリセットしてしまっていいのかどうか。そうすると、異時点間にまたがって、途中で合併が入ったときに、そこを全く引き継がなくていいのかどうかという点について、もう少し検討が必要かなという気がいたします。それが1点目です。
もう1点目は、これは単純に原理原則論ですが、前回も説明させていただきましたけれども、パーチェスの考え方からすると、本来であれば受け入れ資産の評価額はフェアバリューというか、基本的にはマーケットで売っているのを買ったのと同じだということですから、原理原則論はそこに立てて、あとは実行可能性の問題で、できるだけ時価に近いようなものを推定値で得るという点で構わないんです。ただ問題は、どうやってもフェアバリューと異なるものがあるかもしれない。前回言われていたひとつは負債ですけれども、負債のフェアバリューが一体何なのかよくわかりませんが、そこと、もうひとつは、先ほど多少話題に出ていましたけれども、少しフェアバリューに似ていて違うので非常に厄介な話ですけれども、減損した貸出金の評価のようなものですね。通常継続している場合には、当初実効利率で割り引いているわけです。それはフェアバリューではないわけですが、合併に当たってフェアバリューに直すと。つまり、あたかも流動化を仮定して、極端な話、かなり額面を割り引かないと売れなくなってしまうわけですけれども、そこはフェアバリューにするのかしないのか。つまり、パーチェスとはいえ、かなり重要なところは、市場で売っているものを買ったらという仮定が適用できないような項目があるのではないか。その点を網羅する必然性はないのですが、主要なものについてピックアップして、あとは原理原則とその運用ルールの問題とを識別するのが議論としてはわかりやすいのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
第1点の異時点間で、合併時点では未決状態にあるものは、今挙げられた自己株もそうかもしれませんし、さっき梅山委員の方から出された、その他有価証券のものもそうかもしれませんね。持っていて、もし将来売れば、ゴーイング・コンサーン・ベースであればリサイクルしますけれども、パーチェスで吸収されたときには、リサイクルする余地がなくなって資本に拘束されますから、そのような違いもあるかもしれません。そのようなものについて、それでよしと、構わないというのもひとつの考え方ですし、やはり検討を要するという考え方もあると思います。
第2点の承継する資産・負債のフェアバリューでありますけれども、パーチェスというのは基本的に資産・負債をフェアバリューで引き継ぐというのが定義になっていて、フェアバリューでないのは多分のれんぐらいだと思いますが、実際には、この間も議論になりましたように、例えば税効果を適用したときの繰延税金資産とか、今例に出されました負債とか、場合によっては貸出債権もそうかもしれませんが、フェアバリューとは言えないもので引き継ぐ可能性が幾らも実はあり得て、概念的にはパーチェスが持っている本質的な欠陥だと思いますけれども、それを少なくとも理屈の上でどうやって解決して、実際の実務指針といいますか、実際に使えるようなルールとしてどのようなものを決めるのかということは当然考えなければいけないことは、もうおっしゃるとおりだと思いますね。
今のに関連しても結構ですし、それ以外でも結構ですが、ご発言はありませんか。
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
もし山田委員が回答をご存じでしたら教えていただきたいのですが、日本の今とっている会計基準の中で、若干、例えばIASとかFASの規定とは違うところがあるものがありますよね。例えば年金について、15年というかなり長い期間を認めている。これを合併のときにどう考えるか。前にも論点として出ていたと思いますし、それから、例えば金融業について特に問題ないというように先ほど発言があったので、余り発言していいかどうかよくわかりませんが、繰延ヘッジ会計というのをとっていますね。ところがIASとかFASの世界は時価ヘッジ会計ですね。繰延ヘッジ損失とか繰延ヘッジ利益というのがパーチェスをやるときにどのように引き継がれるのか。若干会計基準の違いがあるところからか、違う問題が出てくるような気も少ししています。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、ご発言はありますか。特にないですか。
恐らくIASの立場からすれば、繰延ヘッジをやめろということでしょうね。IASにそろえろと。
- ○山田委員
-
これは日本の固有の問題なので、ここで解決していただくのがいいと思います。
- ○辻前企業会計専門官
-
くどいようですけれども、逆取得のところですね。あるとして、その場合、個別財務諸表はどうあるべきかというか、どのような会計処理をしたらいいのかという点について、ご意見がある方があれば伺っておきたいのですが。
それとあわせて、株式移転で共同持株会社を設立する場合の共同持株会社の個別財務諸表上の取り扱いですね。パーチェス法を適用する場合は、ぶら下がっている子会社のうちの買収された方を時価評価することでパーチェス法を適用したというように考えるのかどうかといったあたりですね。ご意見があれば伺っておきたいのですが。
- ○斎藤部会長
-
どうでしょうか。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
前ご紹介したかもしれませんが、IASではそれがやはり議論されまして、オーストラリアの方からは、完全持株会社が取得者で、下にぶら下がったふたつが被取得者で、下のふたつを全部パーチェスでやってくっつけるという方法が採用されているようですけれども、最終的にその方法は採用されなかったということなので、今、辻前さんがおっしゃったような、実質的な当事者のどちらかが買収者、どちらが被買収者というのが、今IASBでは暫定的に決まっている方向です。
- ○斎藤部会長
-
従来のふたつの会社が解散して、その持株会社をつくったというなら、それはフレッシュスタートでしょうけれどもね。しかし、そのままくっつくわけですから、多分今、山田委員がご紹介なさったような方向に落ち着くのではないのかという感じはしますが、IASBはフレッシュスタートが好きですからわかりませんけれども。
- ○山田委員
-
今回はフレッシュスタートにいかないという方に一応なっています。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、西川委員。
- ○西川委員
-
要するに、辻前さんの問題意識を確認しますと、純粋持株会社をつくって、その下に旧会社がふたつあって、片方が被取得会社になった。その被取得会社の個別財務諸表で今までどおりの会計をやっているのに、その持株会社を続けた連結財務諸表で、その被取得会社の方は取得の時点で時価に変わった会計をその後続けなければいけないというと、個別から連結に直すというのが非常に手間である。そうであったら、個別財務諸表のところを取得された時点で1回時価にかえて、そこからスタートするような会計を個別財務諸表でとるということが、連結としてパーチェス法の会計処理をするために必要なのではないかということでしょうか。そうだとしたら、確かにそのようなことが許されるのであれば、それをしないとなかなか難しいだろうという感じはしますけれども。
- ○辻前企業会計専門官
-
そこまでは意図していなくて、共同持株会社の、例えばA株式とB株式とあったときに、例えばBの方が買収された場合は、A株式は簿価ベースで評価して、B株式の方は時価ベースで評価するというのが、パーチェス法を適用した共同持株会社の個別財務諸表でそのようなものを開示すべきなのかなといったあたりですが。
- ○斎藤部会長
-
辻前さんのお話は、共同持株会社の個別財務諸表の話で、西川先生がおっしゃっているのは、買収された、下にぶら下がっている側にプッシュダウンを使うかどうかという話ですね。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
逆取得のケースですが、仮に企業に子会社、関連会社が全くないとした場合に、ないのに連結をつくるのは少し変ですが、パーチェス法を適用して反映させるとしたら、全く子会社、関連会社がないにもかかわらず、個別と連結で全然結果が違ってしまうわけですよね。それを防ぐためには、個別上も連結と同じ発想でやってもらうことがいいんですが、そのためには、恐らく商法上それが認められるかどうかということが論点になろうかと思うわけです。そうすると、やはり商法学者に問い合わせるのが一番なのですが、商法上、存続会社が合併を受け入れる資産を簿価で引き継ぐことは、これまでも決して否定されてこなかったわけですから、事実上の取得会社側の資産を簿価で受け入れることは問題ないだろう。問題は、みずからの資産が評価替えされることだと思いますが、現有オンバランスされている資産が評価替えされることについては、これも商法上否定されていないわけですね。土地再評価とかやっているわけですし、有価証券も時価評価をやっているわけですから、法律上障害があることはないわけです。ただ、残っている論点は恐らくふたつぐらいあって、ひとつは、持っている資産の評価替え以上に、みずからのれんを計上するというところがボトルネックになる可能性――これは商法上どのように扱い得るかということで、単純に資産の原価か時価かという問題を超えている点が1点です。
それともうひとつは、会計ルールでこれから考察されるであろうパーチェス法の適用範囲、あるいは取得会社の決定基準というのが、法律上義務づけるに当たってロバストなものなのかどうか。つまり、形式的・客観的に明らかで、予測可能性というのは法的安定性を害さない程度に明確なものでない限り、基本としては条文として取り込むのはかなり厳しくなるだろうと思わざるを得ないわけで、その辺の兼ね合いがどのようなことか。つまり、ディスクロージャーも、税効果のように自動的に全部商法上で認めるというようにできるかどうかは、その辺にかかっているのではないか。前者の方が論理的な問題なので、みずからの評価替えでのれんを計上することができるかというのは非常に難しいと思いますが、後者の方は多少立法技術というか、法の運用技術の問題なので、その点、2点ほど、恐らく意見を求めた方がいいのかなと考えております。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
今の大日方委員のご意見ですけれども、簿価は認められているから、基本的に会計ルールで決めてしまえば商法上問題ないというような趣旨ですか。両方とも簿価であれば商法上適法だから、会計の上で、例えば片方時価評価してはならないというように決めてしまえば、それが商法違反になることはないという、そのような趣旨ですか。違いますか。
- ○大日方委員
-
今までプーリングが法律で認められてきたわけですよね。ですから、商法上受け入れる資産について時価をとらなければいけないということはないので、逆さ合併ですから、受け入れる資産については相手方は簿価を引き継ぐわけですけれども、そのことが否定されることはまずないだろう。
問題は、自分のところが今度フェアバリューで評価替えされるわけですね。その点について、個別資産については経験があるので、特に法律上できないということもないと思いますが、問題は、そののれん、もう少し細かく言えば識別可能無形資産の振り替えのようなものも含みますが、商法上見たときに、みずからの評価替えでのれんを計上して資本を増やすように映るわけですね。それが通常はできないけれども、合併のときなぜできるかというのを法律論としてどうクリアできるかという問題点と、あとは、あるときはみずから評価替えしないわけですね。つまり取得企業と存続会社が一致している場合は、みずからを評価替えをしない。ところが、逆さだと言われたときにみずからを評価替えする。何が逆さであって、何が逆さでないかという基準が、法律論として、その使い分けが非常にハードなものでないと、法律論からすると、恐らくそれは蝉脱とか脱法行為に使われる危険があるので入れられないということになりかねないので、そこを明確な基準でつくれるかどうか。あるいは、仮に会計の側で、その前提としている例えば規模規準のようなものは、法律上、一体そのようなものを取り入れることができるアイデアなのかといった点が問題になるのではないかということです。
- ○斎藤部会長
-
よろしいですか。
西川委員、どうぞ。
- ○西川委員
-
今のはおっしゃるとおりだと思います。
あとのれんに関連して、多分資本金は存続会社が引き継ぐと思いますが、自分の分が今度、自分の今までの未処分利益がクリアされて資本剰余金になって、受け入れた側の方の未処分利益を引き継ぐというような、そのような問題も大きいのではないかという感じがします。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
辻前さんが念頭に置いている逆さの会計処理を、多分一度何か仕訳で示していただいた方が議論しやすいのではないか。つまり資本の部が完全に――私の知っている例だと、資本の部の発行する株式は株を発行した会社の株の顔をしているわけですけれども、資本の部の中身は実質的な買ったところにすっぽり入れかえてしまうのですね。ですから、実質的に買った会社がもしもみずから株を発行した場合に得られたであろう資本金というのに資本金を変えるとか、そのような資本の部の中身がすっぽりと入れかわるような処理をIASBでは考えているのですが、その辺、資本の部のところはどう考えられるのですか。
- ○辻前企業会計専門官
-
そのような問題はありますが、それよりも前に、例えば先ほど小宮山先生がおっしゃったような、連結財務諸表は別として、個別財務諸表のレベルでは簿価と簿価をくっつけるとか、極端に言えば税法基準だったら税法基準のままでやってしまうとか、例えば大日向先生がおっしゃったような、商法で障害があるのでしたら、何かそこだけ妥協したパーチェス法というか、一部変形したようなパーチェス法を適用するとか、いろいろ考え方はあろうかと思いますが、それを考えていく上で、参考になるようなご意見があったらお伺いしておきたいというあたりですけれども。
- ○斎藤部会長
-
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
今の問題で、もうほとんど尽きているのかもしれませんけれども、これは大日方委員がおっしゃったように商法学者に確認をするのが一番いいと思います。結局合併の場合に、名目上存続会社とされたわけだけれども、パーチェス法の適用で実質的に被取得と認定されるということは、名目上は名前が残っているけれども、中身は取得された会社だと、このように認定するから、名目上それは残っているけれども、すべて評価替えも行われるし、資本も入れかわると、このようなことが想定されるわけですよね。ですから、名前は名目上存続会社とされたけれども、それを消滅会社と認定できるかどうかという、そこにかかっているのではないかと思うんですよね。商法上それができるかどうか。
ですから、個々の処理の仕方について、それぞれ限定的にどこまで商法と調整をしていくかというのも、その次の段階で、もし仮に、今私が言ったように名目上のものと実質を商法が許さないということになれば、今度調整の問題が出てくるわけですけれども、その前に我々が考えている、そもそものパーチェスの考え方が商法上受け入れられるかどうかというところだけ確認したいと、このようにまず思います。まず確認していただきたい。
- ○三國谷審議官
-
済みません。少しだけ確認したいのですが、先ほど、土地再評価法があるから商法上も土地はいいのではないかというお話のようにお受けしたのですが、そこがそのようなぐあいに商法に結びつくのかどうか、ご見解をお聞かせいただければと思いますが。
- ○大日方委員
-
資産再評価したときには2種類あるわけですね。ひとつは損益になるパターンですね。もうひとつは、資本の部に算入されてリサイクルしない、恒常的に残る場合。改正土地再評価法の場合には後者の場合で、恒常的に残るというか、リサイクルできないわけですね。つまり、それを商法が一応認めているということは、立法論としては、再評価したものが資本の部に算入されて永続的に残るということを法として完全に否定されているわけではないだろうということです。
- ○三國谷審議官
-
そこが一般法と特別法の関係なのかもしれませんが、商法で道がないので土地再評価法で、これは議員立法できていて、今の再評価法というのは今度の3月でなくなるのであって、その処置をまた法律で別途決めているものですから、その特別法の話が直ちに一般法の方に敷衍されるのかどうかは、これはややいろいろな考え方があり得るのかなと思いましてお話しした次第です。
- ○斎藤部会長
-
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
逆取得の話ですけれども、今までの議論というのは、基本的に被取得会社のケースは時価以下で商法上はオーケーだと。ところが、取得会社の側――これ、法律的な取得会社、被取得会社という意味で使っていますけれども――場合は取得原価主義になるというのがひとつのネックになって、この問題が起きているというのが共通の理解ですね。
ただ、このようなケースではないかなと思いますが、例えば債務超過会社を吸収合併することは、商法上、今までできないというように解されていますよね。ところが、営業権の評価が大きいような場合には、それを評価して引き継ぐということが出てきますよね。要するに簿価で引き継ごうとするけれども、商法上債務超過会社は吸収合併できないという制約があって、結果的に営業権が計上されてしまうケース。逆取得の例では、逆の制約が働く場合があるのかなと、今ふと思ったのですが、そのような点はないですか。
- ○斎藤部会長
-
逆の制約とはどのようなものでしょうか。
- ○小宮山委員
-
簿価で引き継げば済むけれども、商法上簿価では引き継げないから、営業権を評価した上で引き継がざるを得ない。要するに、会計上の取得会社であって、商法上の被取得会社について、今のと逆のような事例があるかなと少し思ったのですが。
- ○斎藤部会長
-
ただ、その場合に計上する営業権は、商法上の逆取得の処理では法律上の存続会社に承継されますが。
- ○小宮山委員
-
やらざるを得ない。
- ○斎藤部会長
-
得ないですよね。でも会計上はしないわけですよね。
- ○小宮山委員
-
会計的にはしないという話ですね。
- ○斎藤部会長
-
会計上はやるわけにいかないですか。
- ○小宮山委員
-
商法上、適法ではないという話になりますね。
- ○斎藤部会長
-
でも、逆取得で商法上の処理であれば、その範囲内であればそれはよいのでしょう。
- ○小宮山委員
-
そうなるのではないですか。
- ○斎藤部会長
-
一応合法ですよね。いいか悪いかは別にして合法ですね。
- ○小宮山委員
-
合法ですね。ただ、取得会社を識別して、それをベースに果実を考えるというところで進めると、それが制約になってきますよね。
- ○斎藤部会長
-
だから、それをそのままやったら自己創設のれんになりますけれども、ただ、会計上はそれを計上しないことにするわけですね。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
逆取得のときの存続会社というのも、多少日常用語化して通じているので問題はないのですが、きちんと定義というほどのことではないのですが、仮に社名が残っていると。登記簿上の本社、本店というか、所在地とか、そのような法律の形式的定義だとすると、例えば評価替えを嫌がるために逆取得を使っておいて、しばらくしてから社名を戻すということがあるので、そうすると法律上やりようがないから、形式上存続会社なので評価替えしようがないんだということになってしまうと、簿価を引き継がざるを得ないということになってしまうと、後で社名変更するのは実質的には存続していないということになるので、そこに枠をはめられるかどうか。セットにならざるを得ないのではないかと。そこは枠をはめられないとなると、やはり利用される危険は非常に高いわけで、そこはかなり形式的であるということであるとすると、そこに依存して会計処理を決めるというのはやはり問題であろうと思われますので、その点も考慮すべきだと思います。
- ○斎藤部会長
-
基本的には、それは取得会社をどのような基準で決めるかという問題に全部帰着してしまいますよね。
名前だけであれば、今、大日向委員がおっしゃったように、合併した後で事実上の取得会社、つまり形式上の被取得会社の名前にすぐくるっと変えてしまいますから、それはもうどうしようもないですよね。
ほかにご発言はないでしょうか。
基本的には、ここは企業結合の会計基準を決める審議会であって、適用指針ないし実務指針を決める場では必ずしもありませんので。もちろんこの先にそのような問題が控えているということを念頭に置きながら議論しなければいけないことは確かですが、議論としては、基準のレベルの議論をなるべくして、余り手間どらずに公開草案に持っていきたいというように私は考えておりますけれども。
何かないでしょうか。
北村委員、どうぞ。
- ○北村委員
-
今のご議論を伺っておりまして、私の単純な頭ですと、パーチェス法というものが、ここで取得企業とか被取得企業という言葉を使っています。では、取得企業というのは何をもって取得企業と言っているのかという議論は、もう多分終わっているかと思いますが、パーチェス法というのは、例えば株式を発行するのが取得企業ということで使っていらっしゃるんですよね。違いますか。
- ○斎藤部会長
-
逆取得でしたら、株式を発行する側が被取得企業になりますが。
- ○北村委員
-
ですから、逆取得というのはないのではないかということを私は言いたいわけです。そのようなところを非常に明確にしておきますと、それは逆取得などではなくて、ただ取得した後で、だれが支配しているかというのは、それは人ですよね。ですから、そのようなところが違うだけなのであって、逆取得というように持っていくのがどうなのかなと思ったのです。
- ○斎藤部会長
-
ただ、それは国際的な通念とはかなり乖離する見解ではありますね。
- ○北村委員
-
違ってきてしまうんですけれどもね。
- ○多賀谷課長補佐
-
これは、小宮山先生だけではないのですが、今、小宮山先生が提起された問題に対する確認ということですが、個別財務諸表という議論と、商法と会計という議論と、議論が両方あったかと思います。その後者の議論では、いわゆる連結、個別という関係の議論が最初にあって、それから、小宮山先生がご提起された点というのは、むしろ商法決算と会計といいますか、証取法決算で、その個別決算自体が違う決算になるという可能性も考慮するかどうかという論点ではないかなと思われるのですが、その点はどのような皆さんのご感覚なのでしょうか。
- ○小宮山委員
-
商法上はオーケーで会計上はノーだというと、そのようなお話になってしまいますよね、先ほどの話。
- ○辻前企業会計専門官
-
別件になりますけれども、前回のこのレジュメですと、例えば1ページ目にパーチェス法の定義について、例えばこのようなものではないかという形で、書き出しているわけですけれども、この後の方ですね。8ページのあたりになると、例えば少数株主持分の算定方法として、全面時価評価法とか部分時価評価法について少し書いてあるのですが、例えば連結財務諸表原則の中では、パーチェス法とはどのような方法だというような書き方はしておりませんけれども、企業結合ということでは、パーチェス法の定義というようにすると現金買収も入ってくると思います。そうした場合に、現行の連結財務諸表原則でいっている全面時価評価と、それと部分時価評価法の位置づけですとか、あと段階法と一括法との組み合わせ方法とか、そのあたり、影響してくるのかどうかというあたりについて、ご意見があればお伺いしておきたいんですけれども。
- ○斎藤部会長
-
差し当たり、この時点ではご発言はないですか。今の辻前さんの出された問題に必ずしも限定されなくて結構ですが、ご発言があれば承りますが。
どうぞ、長坂委員。
- ○長坂委員
-
関係ない話ですけれども、先ほど少しお話がありましたけれども、取得企業の定義のお話です。これはパーチェス法の検討の2の方で、何かその定義の議論をするということがありまして、特にここでは取得企業の定義というのは出ていないように思いますが。
- ○辻前企業会計専門官
-
パーチェス法の2の方では、のれんの会計を中心にご議論いただこうかというように考えておりまして、取得企業の議論はその後というような形で考えております。
- ○長坂委員
-
でも、今後それは一応定義を決めていくわけですね。わかりました。
あと、もうひとつですが、先ほどの部会長のお話と関係するのですけれども、私も、ここでの議論が個別財務諸表という話と商法の話で、どうなのかなというように思っていたんです。一応ここでの議論は連結、個別関係なく議論をしていくということで、それと商法で少し離れてくるものがあっても、個別と商法が離れた場合にはどうするかというのはまた別の議論なので、それはまた別途考えるという考えでよろしいわけですか。
- ○斎藤部会長
-
基本的にそのようなことだと思いますね。ここでの議論は、いわば会計基準を決める場でありますので、当然ディスクロージャーの観点から、努めて合理的な基準を考えるということですが、実際問題として、商法というのは非常にきつい制約条件が働いてきますので、その商法によってできないようなことをするわけにはいかないですよね。ですから、その調整は当然しなければいけないわけですが、それをどのように考えるか。つまり、同時にいつも考えているわけですが、議論の仕方としては2段構えにならざるを得ないということだと思いますね。
- ○長坂委員
-
今のと関係していますが、9ページの資本の増加額の取扱いのところで、個別財務諸表上も資本の増加額のすべてを拠出資本とすることを強制するかどうかというお話であります。もうこれは利益剰余金とか、そのようなものの取り込みをするのか、それとも拠出資本にするのかと、そのような議論だというお話があったのですが、もうひとつ、対価の額というか、資本の増加額自体が、今の商法と時価でやろうとしているパーチェスと、多分金額がずれてくるので差額が出ると思うんです。これも個別財務諸表で評価が離れて、個別財務諸表では連結でやる時価まで資本の額を増加していいのかという、そのような議論も含まれているという考えなのでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
この文章に限って言えば、個別財務諸表上の増加する資本の額ということだと思いますね。ですから、そこで作成される個別財務諸表上の資本の増分を分類上すべて拠出資本とするか、そうでないかという問題であって、これ以外のものが別につけ加わってくるという話は、多分この文章では想定されていないと思いますけれども。
- ○長坂委員
-
そうすると、ここの中の議論では個別財務諸表上の資本金はそこまで増加させるとか、そのようなことは考えられないということですかね。
- ○斎藤部会長
-
「そこまでは」の「そこ」とは何でしょうか。
- ○長坂委員
-
そこの個別財務諸表上の資本金を、連結でパーチェス法で処理した――時価で評価した資本金まで増加させるということは前提とはしないということでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
つまり、会計上パーチェスを使ったときに増加する資本の額に対して、現在の商法の基準でやったときは時価以下ですから、必ずしもその両者がと一致しない。その場合に、今のご質問の趣旨は、個別財務諸表上の資本の額を、商法によるものではなくて会計上のパーチェスの額に合わせるということを前提とした議論かという話ですね。
- ○長坂委員
-
そうですね。前提として議論していいのかどうかというか、本当はそこまで決めてもいいのかなと私は個人的に思っているのですが。
- ○斎藤部会長
-
でも、それは商法との相談もありますから、あらかじめここで決めてしまうというわけにはいかないと思いますね。
ほかにないでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
ひょっとしたら決まっていないという回答なのかもしれませんが、今後の見通しについてお尋ねしたいのです。パーチェス法の取得企業の定義と、パーチェス法の適用範囲、プーリングとの使い分けの規準は、リンクして決めることも技術的に可能だと思いますが、取得者が判定できないときにプーリング。もう一方で、取得者はわかるけれどもプーリングという形で切り離すことも、もちろん概念的には可能だと思います。どちらを決めろということではありませんが、議論の将来のスケジュールとして、プーリングとの使い分けが問題になるくらいの時点まで、パーチェス法による取得者の決定基準というのは議論の俎上に上らないということなのでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
これはだれが答えるかで結果が違ってくると思います。私個人の見解として申し上げますけれども、今の問題、つまり取得者の決定基準の話は、プーリングの検討をした上でないと多分できないだろうと思っています。事務局等からご異論があればどうぞ。
- ○辻前企業会計専門官
-
手前どもの方では、ごく単純にパーチェス法の各論をやって、プーリング法の各論をやって、その後、論点整理の真ん中のところをやっていけばいいのではないかなと考えただけですが。
- ○斎藤部会長
-
ほかにないでしょうか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
少々違う話なので恐縮ですけれども、本日松岡委員が冒頭にご説明になられた資料についてでもよろしいですよね。
1番目の方の事例については、まだお聞きしていなかったと思うので――これは先ほど部会長がおっしゃいましたけれども、これの含意は何だったのかということなのです。前回の審議会で、いろいろな識別可能な資産に対する原価の配分の問題とか、のれんの金額も当初それの差額で残りですから、金額もまだ確定していないとか、そのような途中段階の未確定な段階は、どのように会計上理解したらいいのだろうかというような質問があったので、それに対して松岡委員の方で、ご足労ですけれども、このような資料をつくってくださったのかなというようにも思っているんです。この資料から何を我々は学べばいいのだろうか少し教えていただきたい。
- ○斎藤部会長
-
これは松岡委員にお答えいただいた方がいいと思います。
- ○松岡委員
-
私の回答の趣旨といたしましては、配分手続が終わっていないからといって、特別の規定がされている――特別の規定と申し上げますのは、例えば仮勘定だけですとか、そういったようなB/S上の処理だけでいいというような規定は国際的には見当たらないということをまずひとつ言いたかったわけです。したがいまして、年度決算の場合は年度に近い時点で企業結合が完了した場合が問題になるでしょうし、例えば日本でいうと半期報告書が開示になっておりますし、四半期で開示する場合も、第何クォーターの同じ確定期間前の、例えば第3クォーターの開示をする場合に、第2クォーター時点で企業結合が完了したという場合も、要するに同じような問題が生じるわけでございますが、基本的には当然交渉もしておりますので、開示する時点での最善の見積りの金額に基づいて原則的な処理を行っていますというような、そのような処理になっていますということを一番の趣旨として申し上げたかったわけです。
したがいまして、1番目のAOLの例で言いますと、これはたまたま2001年1月11日が完了日でございますので、ですから、そういった意味で言うと、今年度の12月決算が本当の配分期間、米国でいうと1年がクリアするところでございますが、当然四半期ベースで開示する必要があるわけでございます。(2)で書いている10-Qは第3クォーターの分でございまして、その時点では、2ページ目の記載にあるように、まだ配分期間の1年も経過しておりませんし、そういった意味ではまだ暫定的で、正確な識別可能資産の特定ですとか、より合理的な価格の算定手続が残っていますと、そのような条件だけれども、その時点でわかる範囲内では配分手続を行っていますというような開示をしているということをあらわしているわけでございます。したがいまして、前回の部会で確定なのかどうなのかというような、財務諸表を確定として位置づけるべきなのかどうなのかというようなニュアンスのご質問も承ったかと思いますけれども、そういった意味では、ある意味開示になるものをその時点で最善の見積りで確定しているというように考えた方がいいのではないか。配分手続の認められている期間がありますので、その期間が終了すると、当然に取り扱いが違うという意味で、その時点で識別可能純資産・負債の特定ですとか測定手続はそういった意味で確定すると、そのような流れになっているというように理解すべきではなかろうかというように考えております。
- ○斎藤部会長
-
黒川委員、よろしゅうございましょうか。
- ○黒川委員
-
今の確定というのが、この例は、要するにまだクォーターの段階でのデータなので、今年というか、2001年12月31日のデータでどのように表示されるかということを見てから、今の問題についてはもう一回確認した方がいいというように思いますが、そのようなことはないのでしょうか。クォーターの段階なので、確定という概念がいまひとつわからなかった。私どもが言っている確定というようなものとどのようにつながるのか、よくわからなかったのですが。
- ○松岡委員
-
逆に、黒川委員が今おっしゃられている、確定という意味の財務諸表というのはどのような意味でございますか。商法決算の確定という意味ですか。
- ○黒川委員
-
そうですね。あるいは株主総会に示されるというような。
- ○松岡委員
-
という意味でございますか。それと、わが国でいうと半期報告書で開示になるようなものは確定ではないというような理解でよろしいのですか。
- ○黒川委員
-
そのような理解で今は使いましたけれども、その確定という言葉をどのように使ったらいいかということも問題かもしれません。
例えばわが国の半期報告書の段階で表示されたものは、その状況までのデータとしては確定している。それは修正しない。それはそうですよね。その修正報告書は出さないということですから、そういう意味だとみんな確定はしていくのですが、その後で、例えば引当金についてももしかしたら出てくるかもしれない。
- ○松岡委員
-
引当金の例示も、2ページ目の、例えば合併関連コストのところで書かせていただいておりますけれども、AOL Time Warnerの例で、例えば8-Kが開示されてから第1四半期の開示、第2、第3と追っていって見ていただけると恐らく一番よろしいのかもしれません。その時点での最善の見積りに従って、例えば無形資産ですとか、のれんの金額というのは基本的に配分されておりますので、その時の経過とともに新たに識別されて確定されたり、あるいは金額がより合理的になっていく結果として、無形資産の対象が例えば増えるですとか、のれんの金額も変更していきます。しかし、この間お話し申し上げましたように、配分手続の期間は基本的に米国においては1年だと思いますので、要するに黒川委員がおっしゃるような意味での確定した財務諸表という意味では、恐らく1回限りだと思いますけれども、出た時点で、その金額とほぼ同じ金額が、配分期間が終わった後の実質ベースの識別可能資産・負債が決まった金額とはそんなに大差がないというようなことになるではなかろうかというように推測されます。
- ○斎藤部会長
-
伊藤委員、どうぞ。
- ○伊藤委員
-
最後でございますので、少し違う観点で要望等を申し上げてよろしゅうございますか。
きょう、八木委員もおられますけれども、もう皆さんご存じのように、経営は極めて厳しい状況に追い込まれておりまして、恐らく今年度の各社は相当な思い切ったリストラクチャリングをやらないと、日本経済というか、日本の企業経営の再生をできないと思うんです。そうしますと、やはり当然のことながら分社、分割、合併ということもやはりいろいろ駆使して生き延びていこうということを当然のことながらやるわけですね。これはアメリカだってそうだと思いますし、今度のAOLとTime Warnerの問題にしても、その前のJDSユニフェーズの問題も、株式交換を重ねて、その後大変株価が暴落して、要するに評価損をこうむっておる。それを一挙に償却できない。要するに毎期毎期償却するのに大変だから一挙に落とすとか、いろいろな産業界の要望もかなり入って会計基準が変わったんではないかと、これはあくまでも推測ですが。
もちろんその会計基準というのは、世界のコンバージェンスもありますから、私の立場でこんなことを言うのは大変申しわけないんですけれども、しかしながら、前にも何回もいろいろ縷縷、産業界の意向も申し上げましたけれども、やはりパーチェスという大きな流れの中に日本が逆らえないという形の中で進んでいるとしますと、つまり、今の産業界の置かれているタイミングと、それから今の会計論との間というのが大変厳しい中でミスマッチする可能性があるわけですね。したがいまして、時価会計そのものについては、産業界は大変にみんなその方向に考えていますけれども、しかし、それが日本の企業経営を根底から崩して、もう芽を摘んでしまうということになってはぐあいが悪いと私は思うわけです。確かに日経の編集長の水野さんなんかは、何回か「経営の視点」というところでいろいろ論説を張られて、プーリングそのものがむしろ競争力の喪失だという意見もいろいろ出ています。しかしながら、やはり今の日本のいろいろな制度そのものを是認しつつ、我々は企業経営を展開していることも事実なんですよ。
なぜこのようなことを申し上げるのかと申しますと、したがいまして、国際会計基準において暫定合意という形でどんどん進んでいく中で、我々が、それではその方向に従うとすれば、どのようなタイミングで今後この議論を進めていくのか。つまり、1年ぐらいかけて我々はゆっくりやれるのか、あるいはもう半年で決着しなければいけないのかというところのことは、今でなくて結構ですが、ご検討いただきたい。
もうひとつの問題点は、合併税制において、一応適格企業に関しては税の繰り延べをしてきているわけですね。もちろん企業経営というのは会計そのものを税と一緒に考えているわけではありませんけれども、最終的には、私どもはやはり税を念頭に置いて会社経営を考えております。つまり、プーリングを廃止されてパーチェスになって、要するに簿価だったものが時価になって、それについて税がかからないという約束は何もないわけであって、このような問題も我々は視野に置いて会社の経営を考えなければいけないということが実態の問題でございますので、会計理論を数値に展開していただくのは大変結構なのでございますが、会社経営の立場からいきますと、そのスケジューリングをごく大ざっぱにご検討いただいておいてほしいというように一応思います。我々としましても、経団連等を中心に、まだ八木委員といろいろご検討いただきたいと思っていますが、経営という立場において、一言だけ少しお願いと申しますか、コメントさせていただきました。ご参考にしていただければありがたいと思います。
以上です。
- ○斎藤部会長
-
承りました。ありがとうございました。
特にこの際どうしても一言というのはありますか。
辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
念のための確認ですが、きょういただいた資料の数値例の方で、少し教えていただきたいんです。段階法ですと、当初20%取得したときののれんがたまたま100になっていて、それが後に時価評価したときの差額がまた、たまたま同じ100になっていますが、仮に最初ののれんが600で取得ではなくて550で取得されて、のれんが50になっているような場合に、60%取得時に時価が3,000になったような場合はどのようなことになるのか、それを教えていただきたいと思います。たまたま最初ののれん計上額と、後に支配獲得時の時価評価差額が一致している事例ですけれども、それが違っている場合にはどのようになるのでしょうか。
- ○松岡委員
-
お答えになるかどうかわかりませんけれども、のれんの算定方法は通常の算定方法どおりでございまして、要はこの評価差額のところの金額でよろしいですか。それは、当初取得した時点の純資産の公正価値と、次に取得した時点の公正価値との差額掛ける当初取得割合です。そのロジックは多分どのようなケースになっても変わらないと思いますので、この例でいくと、X2年度末の識別可能純資産額と、第1年度末の識別可能純資産額の公正価値の差額掛ける第1年度末に取得した20%割合。第1年度末に取得していた取得割合を掛けたものが評価差額になるというようなロジックだと思いますけれども、回答になっていますでしょうか。
- ○辻山委員
-
単なる確認ですが、最初の20%取得時に500の時価額があったものですね。2,500のうち20%取得していますので500、これに600出しています。そのうち100がのれんになっていますが、その後60%追加取得したときに、これがちょうど評価差額相当分になっているんですね。たまたま一致しているのですが、のれん計上額が仮に50だった場合の、その残りの差の50の扱いについて教えていただきたいと思ってご質問しております。
- ○斎藤部会長
-
済みません。時間が来ておりますので、部会終了後ということでお願いいたします。本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。
次回の部会は2月22日(金)午後を予定しておりますが、詳細につきましては改めて事務局からご連絡いたします。
議論としてはかなり細かいところに入ってきて、成熟した段階で、最終段階が近いような印象も受けますが、実はそうではなくて、まだまだ、何かよくわかりませんけれども前途遼遠な感じもいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。
本日は、お忙しいところ、どうもありがとうございました。
これで散会させていただきます。