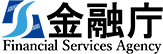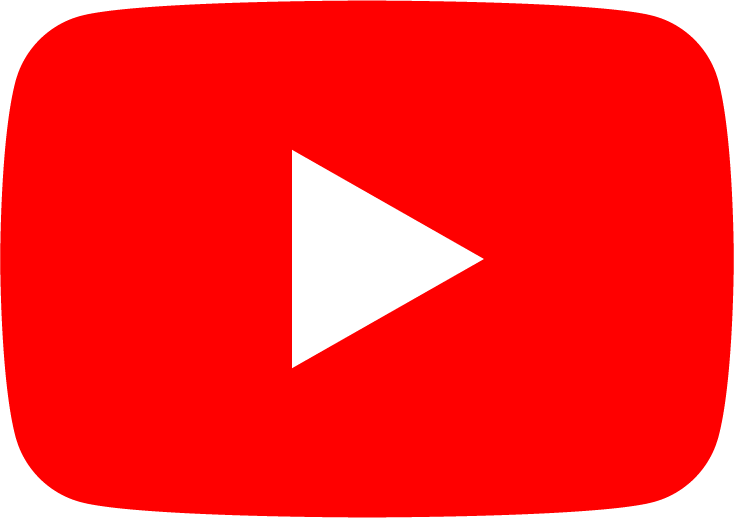平成13年1月16日
金融庁
企業会計審議会第4回固定資産部会議事録について
企業会計審議会第4回固定資産部会(平成12年12月8日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第4回固定資産部会議事録
日時:平成12年12月8日(金)午後3時30分~午後5時35分
場所:中央合同庁舎第4号館4階共用第一特別会議室
- ○辻山部会長
-
それでは定刻になりましたので、ただいまから第4回固定資産部会を開催させていただきます。
本日は、皆様方お忙しいところを御参集いただき、ありがとうございます。
前回は、固定資産の減損会計のうち、3点にわたり意見交換を行いました。まず我が国の固定資産の会計処理、会見監査等の実務から見て、米国基準や国際会計基準などの国際的な減損会計基準を適用するとした場合に、どのような問題が生じるのかなどにつきまして、主に会計監査人の立場からということで太田委員に御報告いただきました。また川村委員からは、主に将来キャッシュフローの見積もり、割引率について理論的な観点から御報告をいただきました。最後に山田参考人から、主に英国における投資不動産の会計基準や会計処理について御報告をいただき、意見交換を行いました。なお、この投資不動産の問題につきましては、2月の部会におきまして改めて審議を行う予定にしております。
本日は、第2回、第3回の当部会の審議におきましても話題になりましたけれども、固定資産の減損会計のうち、資産のグルーピングの問題、いわゆる共用資産や全社資産の取り扱いをどうするかという問題、のれんの減損をどう考えるかという問題について意見交換を行いたいと思います。
そこでまず、のれんの問題を考えるに当たって参考になると思われます企業買収等の際に用いられます割引キャッシュフロー(DCF)による企業評価の方法につきまして、中央青山監査法人の五十嵐則夫参考人、三橋優隆参考人、大塚勝弘参考人から御報告をいただいて、意見交換を行いたいと思います。また、お手元の議事次第にございますように、2番目に小宮山委員からのれんの減損について御報告をいただき、意見交換を行いたいと思います。最後に、秋葉委員から資産のグルーピング、全社資産の減損及び減損損失の配分について御報告をいただき、意見交換を行いたいと思います。
それではまず第1の議題でございますけれども、五十嵐参考人、三橋参考人、大塚参考人から御報告をちょうだいしたいと思います。では、よろしくお願いいたします。
- ○五十嵐参考人
-
中央青山監査法人の五十嵐でございます。それでは御依頼によりまして企業評価方法についてということで、特にDCF法による特定部門の事業資産の評価を中心にということで御報告させていただきます。御報告につきましては、お手元の資料に基づきまして進めさせていただきます。
御説明は、大塚参考人の方からいたしますので、よろしくお願いいたします。
- ○大塚参考人
-
中央青山監査法人トランザクション・サービス部の大塚と申します。私ども中央青山監査法人のサービスの一つであります、いわゆるバリュエーション・サービスということで、企業価値の分析評価を行っております。今回、お手元にあるこの資料ですが、これは私どものサービスの中で一般的な実務事例に基づきまして、その非常にベーシックな考え方だけをとりまとめております。
時間も25分と限られていますので、早速、御説明をさせていただきたいと思います。まず、資料の3ページ目をあけていただきたいのですが、私どもの部署では企業価値の分析評価につきましては、主にM&Aの支援サービスに関連して行われる付随的なサービスとして位置づけております。したがって、買収、いわゆるバイサイド、買い取る側の立場、あるいは売却する側の立場、それぞれの立場でバリュエーション・サービスを行っております。評価の対象となるものですが、これは、ここに書かれていますように、株式そして特定事業資産の2通りに大別されます。株式の方は、基本的には一般の企業の株式を買収する場合、事業資産の方は、他の企業の特定部門の事業資産を買収する場合と、大まかに分けてこの2通りに大別されております。
4ページ目をあけていただきたいのですが、その評価の方法といたしましては、以上のような評価方法を列挙しております。これは公認会計士協会で公表されております株式等鑑定評価マニュアルに記載されている評価方法を列挙しておりますが、この中で私どもがよく使う方法といたしましては、1番の純資産方式及び2番の収益方式、それから4番の比準方式といったところを頻繁に使っております。今回、固定資産の減損ということに関しまして、特定の事業資産の評価に関しましてどういうふうに実務的にやっているかということについて、焦点を当てて説明したいと思います。
それでは、5ページ目から具体的に評価方法について説明させていただきたいと思います。5ページ目のところで、一応、特定事業資産の評価について基本的な考え方をまとめております。特定事業の買収ということに関しまして、いわゆるアセットディールの場合は、考え方といたしましては、既存の事業の事業価値を評価する場合に関しては、当該事業に投下された資本、いわゆるその事業に直接使用されるような資本に関して、その構成する事業資産の集合体としての価値を測定することがポイントとなります。例えば、この既存の特定事業を買収する場合の、特に買収ということを考えますと、その買収価格というものが中心になってくるわけなのですけれども、これはその事業に使用される個々の資産の時価の総額ではなく、いわゆるその事業から得られる将来のキャッシュフローや利益といった経済的効果に基づいて決定されるケースが多いということです。ただ、例外といたしましては、例えば事業グループ内の事業の再編、子会社同士のインテグレーションとか、そういった事業の再編や、あるいは民事再生法の適用等で救済的な買収が行われるような場合、こういった場合は、どちらかというと経済的効果というよりも、個々の資産の時価に基づいて評価するケースもございます。
事業に投下された資本ということなのですけれども、これは私どもの方では、一応、当該事業に特別に、直接使用する資本というふうに考えておりまして、ここの左下の絵のところの四角く囲まれた内容が、事業に投下された資本というふうに考えられております。大きく分けて、運転資本、固定資本、それからあと、その事業運営の過程で生じた債務ということで、固定負債、こういったところが投下事業資本ととらえております。これは、それぞれの事業によって、この投下資本の内容というのは一概に固定しているものではなく、それぞれの事業の内容を見ながら投下資本の内容というのをアイデンティファイしていくという作業を行っております。
続きまして6ページ目を見ていただきたいのですが、先ほど申し上げましたように、既存の特定の事業を買収する場合、その買収の評価額というのは収益還元的に評価された、いわゆるすなわち経済的効果に基づいて評価するわけなのですが、その評価額は基本的にはというか、一般的には事業に投下された個々の資産の時価の総額を通常の場合は上回る、上回らないと、こういった買収というのは通常行われないわけなんですけれども、基本的には上回ります。この上回った部分というのを、プラスアルファーとして、プレミアムとしてとらえております。レアなケースといたしましては、事業を取得することによって得られる経済的効果が、ここの資産の時価の総額を下回るという場合もございます。これはどういうことを意味するかというと、その事業単独で見れば、将来リターンによって投下資本は回収できないということを一般的には意味している。ただ、基本的に買収とかの場合は、その事業の単独で見る場合だけではなく、買収した後のシナジー効果というのも考慮してプラスアルファーが出れば買収するので、事業単独で見たときに、いわゆる経済的効果が、収益還元的な評価が、個々の資産の時価を下回るケースというのもございます。
実際の取引の中では、この事業価値の評価についてなのですが、これはそれぞれ営業譲渡の契約によりまして、その投下資本を構成するすべての資産・負債が引き継がれるとは限りません。例えば売掛金や買掛金などをそのターゲットとなる会社が全体としてコントロールして、他の事業の債権債務との切り分けが困難な場合は、売掛金、買掛金などを譲渡対象としないケースもございます。したがって、譲渡価格、この買収価格というのは、譲渡対象資産・負債によって変動いたします。したがって、私どものサービスの中心となるのは、このプレミアム部分というのをどういうふうに評価するか、営業権をどういうふうに評価するのかが、その評価の中心となります。
また、実際、営業譲渡の予定日よりも実際の評価というのはずっと以前に行われるために、基本的にこの譲渡対象資産はかなり譲渡日に変動するということが多いので、やはりそういう意味からも、この営業権を中心に評価するということになります。
それでは営業権の評価方法について、7ページ目から具体的に御説明申し上げたいと思います。営業権は、理論的には2つの概念、コンセプトに基づいた価値評価方法が考えられます。一つはいわゆる差額概念というか、名称でいけば純資産価値評価という名前をつけておりますが、これはいわゆる差額の概念でして、先ほど申し上げましたように将来の予想利益やキャッシュフローの収益還元的に評価した現在価値額が、それぞれの事業資産、投下資本の個々の時価の総額を上回る部分を営業権として評価する方法でございます。この方法の式がその四角の中に書いてあるのですけれども、基本的にはこれは各年度の予想の将来利益、あるいは税引き後のキャッシュフローを期待収益率で割り引いた各年度のキャッシュフロー、それの総額と個々の投下資本の時価の総額との差額部分を営業権とみなす方法でございます。
もう一つが超過収益力の還元価値評価というふうになっていますが、これはいわゆる将来の予想利益、キャッシュフローから通常、この投下資本であれば得られるであろうという正常的な利益、あるいはキャッシュフローを差し引いて超過収益力を算定するという方法でございます。これは税法上の営業権、財産評価基本通達上の営業権も、基本的にはこの超過収益力還元価値評価の考え方に基づいて規定されております。これの計算方式は、各年度の予想超過収益額の合計額が、いわゆる営業権の評価額とする方法でございます。各年度の予想超過収益額というのをどういうふうに求めるかと申し上げますと、基本的には各投下資本、いわゆる事業を構成する資産から一般的に生まれるであろうという最低のリターンを、同業種の平均をROI、あるいは一般的な利子収入を掛けることによって算定いたします。そして、各年度の実際この事業から得られる予想キャッシュフローとの差額を超過収益力として算定する方法でございます。
今申し上げましたように、超過収益力のもととなる、通常得るべき最低のリターンというのをここにcと表していますけれども、これは、そのときどきによって同業種の平均ROIを使ったり、市場金利、いわゆる一般的な利子収入を使ったりと、そのときどきで使い分けております。例えば、同業種の平均ROIを使うような場合というのは、成熟産業で参入障壁が低く、同業種のROIが非常に低い場合、このような場合は同業種の平均ROIを使うケースもございますし、例えば業界全体が非常に成長産業で、高収益になっている、参入障壁も非常に高いような場合は、その事業を行っていること自体でかなりグッドウィルというか、営業権、のれんを持っていると判定できますので、そういった場合は、一般的な利子収入を使うケースが多いです。
具体的には、今申し上げた2通りの方法で営業権を評価するわけなのですけれども、その中で、両方とも収益還元的な考え方に基づいて評価するということは共通しているのですけれども、そのときにキャッシュフローを使うのか、会計上の利益を使うのかということで、方法としては両方あるわけなのですけれども、8ページに書いておりますように、いわゆる将来獲得するキャッシュフローを還元する、いわゆるディスカウント・キャッシュフロー法、DCF法を使うことによるメリット、私ども基本的には会計上の利益を使わないでキャッシュフローを使う場合が多いのですけれども、それの理由は、やはり一番大きなメリットといたしまして、会計上の利益はやはり対象事業の会計方針によってかなり変動するということが挙げられます。いわゆる対象となる事業の収益の認識基準、あるいは減価償却の方法、これによって会計上の利益はかなり大幅にぶれてきますので、そういう意味ではキャッシュフローを使った方が、絶対的な数字が取れるというふうに判断しております。
それでは、各年間のキャッシュフローをどのように算定するかということについて、9ページ目にまとめております。通常、私ども、これは株式評価でも特定事業の評価でも大体同じなのですけれども、特に特定事業の評価に際して使用するキャッシュフローは、その事業の営業によって得られる利息の考慮前のネットキャッシュフローを利用しております。利息を考慮しないということは、当該事業に投下された資本の調達の源泉、いわゆるこれは銀行からの借り入れによって資金調達したのか、あるいは増資によって資金調達したのかといった、いわゆる資本の調達の源泉を考慮しない、加味しない、その事業そのものから得られるキャッシュフローを把握するという意味で、利息を考慮しておりません。特に特定事業の評価に関しては、一般的には事業別のPLにたまに支払利息、受取利息みたいな金融収支が計上されているケースもありますけれども、基本的にはこういった金融費用というのは各事業部にアイデンティファイできないケースが多いので、何らかの配付を行っているケースが多いので、そういう意味では特定の事業のキャッシュフローを表していないという意味からも、これは利息は考慮しておりません。
特に特定事業の評価で将来キャッシュフローを把握する場合は、ターゲットとなる事業、あるいは会社から将来の利益計画を入手するわけなのですけれども、ほとんどの会社の場合、利益計画は事業計画の中に織り込まれつくっていただいているのですけれども、キャッシュフローの計画というのはつくっていないケースがほとんどでございます。いわゆる資金計画というのを入手していないケースが多いです。
したがって、私どもは会計上の利益に基づいて出てくる利益計画から、ある一定の加減算を行うことによってキャッシュフローを把握しております。それがこの下の真ん中の四角の式になっております。いわゆる各年度のキャッシュフローは、営業利益に1-実効税率を掛けることによって、税引き後の営業利益を出して、そこに減価償却費を足します。それから、費用の中に含まれる非現金支出費用を加えて、あとそれから売掛金、買掛金、そして在庫等の運転資本増減を加味する、そういった形で各年間のキャッシュフローを出しております。この中で、特にこれも実務的には、各会社のターゲット事業の利益計画の中から非現金支出費用というのを把握するのは、非常に困難になっておりますので、*1に書いていますように、退職給与引当金等の負債性引当金の繰り入れについては、これは本来であればキャッシュフローということであれば、取り崩されて各従業員とかに支払われたときにキャッシュアウトが出てくるわけなのですけれども、便宜的に繰入時に繰入金額相当額のキャッシュアウトがあったと仮定するケースが多いです。
運転資本増減につきましては、先ほど申し上げましたように売上債権の増減と仕入債務の増減、そして在庫の増減、基本的にはこの3つの要素から運転資本増減を計算しております。
先ほど申し上げましたように、各ターゲットの会社、あるいはターゲット事業の方から将来の利益計画を出していただいているのですけれども、基本的には将来のキャッシュフローは私どもの方では2つの観点から分析しております。1つが、会社の方から入手いたしました対象事業の事業計画上の利益計画、そしてもう一つが、対象事業の直近の実勢、この2つを考慮しながら、将来のキャッシュフローを把握しております。対象事業の直近の実勢を織り込んでいる理由は、やはり会社、あるいは対象事業が作成した利益計画上の将来利益というのは、基本的にはやはり目標利益が含まれているケースが多いので、その事業の現在の実力を上回る利益水準であるケースが多いので、やはり過去の実勢を見ながら将来のキャッシュフローを見込んでおります。
10ページ目に入ります。では、キャッシュフローをどの年度まで、何年間織り込むかという観点で、一応、予測期間というテーマになっているのですけれども、これに関しましては、各ターゲット事業、あるいは各会社さんによって変えております。その変える要素、予測期間を設定する要素といたしましては、ここに書かれていますように物理的な要因、あるいは経済的要因、そして戦略的要因といったものが考えられます。物理的な要因といたしましては、例えば製造業の場合、対象の事業を構成する主要設備の物理的耐用年数がございますので、それに基づいて予測期間を設定する方法。それから経済的要因といたしましては、対象事業の主要製品・サービスのライフサイクルを考慮して予測期間を設定する。あるいは対象事業のバリューチェーンと書かれておりますけれども、基本的にその事業が行う、例えば開発・仕入れ・製造・販売・アフターサービスといった、そういったバリューチェーンの中の、この事業に関しまして、どこにバリューがあるのかということを焦点におきまして予測期間を設定する。それから戦略的要因といたしましては、これはあくまでも買う側、投資する側の要因なのですけれども、この買収プロジェクトの投資回収期間の目標というのが設定されていれば、それに見合った形で予測期間を設定する。あるいはその買収目的が、いわゆる対象事業の何が欲しいのか、先ほど申し上げましたバリューチェーンの中の販売チャンネルが欲しいのか、あるいは生産力が欲しいのか、ブランドが欲しいのかといったウォンツによって、やはりこの予測期間を変えるケースがあります。
この10ページの後半のところで事例を載せておりますが、これは一概には言えないのですけれども、例えば半導体製造業、LSIのメーカーの場合ですと、当然、製品のライフサイクルというのは、シリコンサイクルに対応して今、2~4年と非常に短くなっております。現在のマーケットシェアというのは、次の世代のLSI市場で確保できるかどうかというのが、非常に今のマーケットとしては不明である。それから製造装置自体は非常に高いものであって、例えば1台1億とかするような製造装置もございます。しかし、その一方で、経済的陳腐化というのはライフサイクルに依存しております。これはどういうことかといいますと、例えば次世代のLSI市場になると、この製造装置が使えないケースというのが非常に多い。こういった場合は、こういった事業環境を前提にいたしますと、やはり予測期間というのは製品のライフサイクル期間に合わせて4年と設定するという一つの考え方がございます。
また、IT産業におきまして、例えばIT産業の中のソフトウェアパッケージの製造業の場合は、やはり製品のライフサイクルというのが非常に短い。概ね2~3年であろうと。参入障壁が非常に低いものである。それからあと、高額の固定資産は不要ということで、これに関しましては、やはり製品のライフサイクルに合わせて予測期間は3年と設定するというケースがございます。
こういったように、予測期間は各事業環境、あるいはその対象事業の強み・弱みを考慮しながら設定しております。
11ページ目をあけていただきたいのですが、それでは予測期間が終了した後の事業価値をどう見るかということで、これに関しましては、大きく2つの考え方がございます。一つは、処分価値でその事業の予測期間終了後の価値を見る方法、もう一つは、予測期間終了後もそのまま事業がずっと継続していくという仮定のもとに、継続価値として見る方法と2つございます。処分価値の方は、例えばその事業の事業環境や収益構造というのが非常に不安定であり、事業の永続性に関して疑義があるような場合、これはもうその財産の処分価値で予測期間終了後のバリューを見る。例えば継続価値に関しましては、その事業の提供する商品やサービス、あるいはそのマーケットシェアというのが過去の業績から見ても非常に安定的である。これに関しましては、その予測期間終了後も長期にわたって採算性が確保できる可能性が高いような場合、こういった場合は継続価値で見る。これは一つの例示ですけれども、そういうような、やはりこれに関しましても、その事業環境、あるいはその事業の強み・弱みを考慮しながらターミナルバリューを処分価値を取るか、継続価値を取るかというのを判断しております。
続きまして、これで予測期間及びその予測期間終了後のキャッシュフローというのが算定されたわけなんですけれども、今度、これを現在価値に割り引かなければなりません。そのときに使用する割引率なのですけれども、私どもの経験から申し上げまして、この割引率をどう取るかによって、バリューした結果というのは非常に大きく変動いたします。その意味で、この割引率というのは非常に抽象的な概念なのですけれども、非常に重要なファクターとなっております。一言でいえばこの割引率というのは、投資の採算基準の問題ではないかと思っております。特にこれは株式の評価と違いまして、特定事業の資産の評価の場合は、株式評価と同様の資本コストの概念だけでは算定するのが非常に困難、あるいは相手方であったりお客さんを説得するのが、非常に困難なケースがございます。というのは、やはり特定事業の場合は株式のように類推する、あるいは比準するべき客観的なマーケットというのがございませんので、やはりそういった意味では評価の主体となる人、それはお客さんであったりターゲットであったりするわけなのですけれども、そういった人たちの期待収益率を前提に割引率を設定していくわけなのですけれども、非常に主観的な数値となりやすいということが言えるかと思います。
私どもではこの割引率を設定する場合、事業資産の評価に関しましては、2つの要素を考慮しております。一つが、投資によって得られる期待リターン、いわゆる期待利益です。そしてもう一つは、投資に必要な資金をどのように調達するか、この2つの要素を考慮して割引率を設定しております。考え方としては、先ほど申し上げましたようにROIを使う方法、そして資本コストを使う方法と、大きく考え方として2つに分かれるかと思います。投資に得られる期待リターン、その事業を買うことによって得られる期待リターンというのがある程度明確な場合は、このROIを使う方法というのが一つ考えられるかと思います。これは、例えば投資サイドの社内のハードルレートである期待CFROIであったり――このCFROIというのはキャッシュフローROIです――あるいはその同業他者のキャッシュフローROIであったり、こういったROIを使うということが一つ考えられます。これは特定の事業資産の場合は、やはり先ほど申し上げましたように投資サイドにとって株主価値との直接的な結びつきがないところからROIを採用するというのは合理的だとは思うのですけれども、一つデメリットといたしましては、その投資を行うことによるリスクを考慮できないというデメリットがございます。
一般的には、やはり資本コストを使うケースが多いです。資本コストを使う場合は、これは株主価値、株式の価値と違いまして、あくまでもその評価する主体のいわゆる投資資金の提供サイドから見た、期待する株主価値の増加を考慮した資本コストということが前提になります。したがって、例えばバイサイド、いわゆる買収する側がその事業を評価する場合、あくまでもその買収する側が、その買収資金をどうやって調達するかによって資本コストが決定されるということです。資本コストの中にもいろいろ考え方がございまして、ここに書かれていますように、株価期待収益率、あるいは資本資産評価モデル、市場調達金利、加重平均資本コストというふうにございますが、特定事業資産の場合はこのCAPMと言われる資本資産評価モデルを使うケースが多いです。CAPMによる自己資本コストということで、右側に計算式を載せていますけれども、CAPMというのは、皆さん御存じだと思うのですけれども、キャピタル・アセット・プライシング・モデルといいまして、いわゆる安全な証券利子率、リスクフリーな利益率に加えまして、個別の投資リスクに応じた一定のリスク料を考慮して割引率を設定する考え方でございます。
この式を見ていただくとわかりますけれども、右側の( )内のrm -rf ' というのがこれが市場のリスクプレミアムになっております。この考え方は、市場の一般的なリスクプレミアムにその特定事業のβ値を掛けたものをその事業のリスクプレミアムととらえて、それに安全証券利子率を加えたものを期待収益率とする方法です。ここでβと書いてあるのは、これは特定企業の株式の利回りと市場平均利回りとの相関関係を回帰分析的に表した一定の数値です。もうちょっと具体的に説明いたしますと、このリスク、rm というのはトピックス等の市場平均利回りですので、あくまでもその事業、あるいはその業種に対応した利回りでないケースが多いので、一応、この特定業種、あるいは特定企業の利回りと市場平均利回りとの相関関係である指数を掛けたものを使うことによって、その当該事業、あるいはその当該業種のリスクプレミアムを算定するという考え方をとっております。
こういった予測期間のキャッシュフロー、それからターミナルバリュー、予測期間終了後の事業価値、そして割引率と、この3つの要素を使うことによって、DCFによる事業資産の評価ができるわけなのですけれども、ここで13ページを見ていただきたいのですけれども、私ども、特定の事業の資産の評価、あるいは株式の評価に関しまして、このDCFを使うケースというのが非常に多いわけですし、DCFで計算してくれというふうにリクエストしてくるお客さんもだんだんふえてきております。しかし、一方DCFにも限界がございまして、今ここに書かれている2つの項目が、DCFにとっては結構デメリットではないかと感じております。
まず一つといたしましては、DCFで使う利益計画というのが、あくまでも唯一無二のものであると。いわゆる私どもが評価計算に使うときに入手する事業計画というのは、あくまでも最初に立案された静態的なものであって、将来の事業環境の変化に応じた経営者、マネージメントの進路の変更とか、デシジョンメーキングとかが介在するという前提はございません。いわゆる事業計画の中の利益計画というのは、非常に数多くのアサンプション、仮定を前提に数値化されているものでございます。さらにこれらの仮定というのは、本来であれば時間の経過とともに顕在化して、事実というのが判明されるわけなのですけれども、そういったものは考慮されていない。したがって、この利益計画自体の真実性といいますか、予測の精度というのが非常にばらつきがあるということです。
そしてもう一つといたしましては、現在価値へ割り引く割引率がバリュエーションに大きく影響してくるわけなのですけれども、これがある程度マーケットのリスクを反映して一定率が採用されておりますけれども、あくまでもこれは株式市場の中で同等のリスクを有する株式から推計されたものでしかない。あくまでも株式市場が完全性であるという前提のもとに、それと大体同等のリスクを有しているだろうと判断されて使われた株式の期待収益率でしかないといったところで、その絶対的根拠というのはちょっと乏しいのかなという感じもしております。
したがって、私どもはバリュエーション・サービスをやる上において、このDCFだけでは評価しておりません。当然、DCFの結果出てきた数字がリーズナブルなのか、合理的なものかどうかというのは、いわゆる類似会社、あるいは類似業種の比準法を用いて確認しております。これは税法上の類似業種比準法だけではなくて、同業他社、あるいは同業種のPER、株価収益率、あるいはPBR、PSRといったようなものを用いて、このDCFで出てきた数字というのを、合理性を裏付ける数字を同時並行的に算出しております。今、DCFの限界と申し上げましたけれども、例えばこれの一歩進んだ方法としてモンテカルロDCFというのがございまして、これはいわゆる将来の利益の企業価値を決定づけるバリュードライバーの将来の確率分布をあらかじめ設定して、そのドライバーを、例えば営業利益率を変動させることによって、複数のシナリオを設定することによって、できるだけ真実に近いというか、将来の発生の可能性、確率が高いシナリオを、事業計画、利益計画に基づいて計算するといった方法も、やはり今後考えていかなければならないかと思っております。
すみません。ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
ただいまの参考人の御報告に対しまして、何か御質問・御意見等がございましたらお出しいただきたいと思います。
- ○品川委員
-
先ほど御紹介のあった鑑定マニュアルは、商事法務研究会から出されたものでありまして、私が当時、その研究メンバーの一人だったのですが、そのときも、いろんな問題点がありましたので、その後、どういうふうに解決されているかということも含めて、ちょっとお尋ねしたいのですが、最初に、3ページに、株式価値と特定事業資産と2つに分けて御説明があったわけでありますが、特定事業資産のDCFを算定する場合に、株式価値の算定と全く同じなのかどうか、違うとすれば、どういう違う点があるのかということ、まず確認しておきたいと思います。先ほどの御説明の中で、若干ニュアンスの違う御説明もありましたけれども、ほぼ同じような説明もありましたので。
次の4ページの評価方法は、これはほとんど株式の評価にかかわる従来の、いわゆる評価方法を、一応、一覧表示したものだと思われますが、その中で特に、先ほどのDCFの場合のターミナルバリューを計算する場合もそうですが、処分価格を計算する場合に、清算所得、あるいはキャピタルゲインに対する税金部分をどういうふうに控除するかということが、マニュアルをつくるときの非常に大きな問題になったわけで、最近の税法の取り扱い自体もいろんな変遷を経ているものですから、そういうことについて実務的に特にどういうふうにしているのかということと、もう1点だけ、ターミナルバリューを計算する場合に、特に土地等については、地価が下落しているか上昇しているかという現状で将来その価値がどうなるかということは極めて困難な作業を伴うわけでありますが、現在のように10年間も地価が下落している場合に、そういうことを織り込むのか織り込まないのか、あるいは独自の予測を立てるのかどうか、一応、この3点についてとりあえず説明していただければと思います。
- ○大塚参考人
-
それではお答えいたします。
まず1点目の質問なのですけれども、基本的な考え方といたしましては、株式のバリュエーションも事業資産のバリュエーションも基本的なコンセプトというのはそれほど変わりはないです。ただ、先ほど申し上げましたように特定事業資産の評価、いわゆる営業譲渡に係る評価といいますのは、一番大きな違いといたしましては、まず営業譲渡価格というのは、その引き継ぐ譲渡資産によって変わってくるので、あくまでも営業譲渡の買い取り価格、あるいは売却価格というのは、やはり個々の資産構成によって変わってくるので、焦点といたしましては、営業権の評価に焦点を当てているというのが株式評価と一番違うところでございます。
そしてもう一つ違うのは、先ほど申し上げましたけれども、割引率の考え方がかなり株式評価の場合と事業資産の評価の場合が違ってくる。株式評価の場合は、当然、その評価の対象となる会社の資本の調達の源泉から見た資本コストを使います。ターゲットとなる会社の、いわゆる貸方サイドの資金調達源泉から見た自己資本コスト、あるいは加重平均資本コストを使います。しかし、特定事業資産の場合は基本的には、例えば買い取る側の立場に立った場合、買収する側の立場に立った場合は、買収資金をどのように調達するかということを考慮した上において、バイサイドの方の資金調達、いわゆる株主価値に基づく資本コストを使用します。すみません。今思いついたところで、ここのところが一番大きいかなという感じがするのですけれども。
そして、2点目、3点目の質問のターミナルバリューなのですけれども、基本的に税金は、先ほどおっしゃられたように、これは処分したとしても、そのターゲットとなる会社が清算するわけではないので、基本的には税金というのは織り込みません。土地の評価なのですけれども、これは非常に難しいのですけれども、要は、例えば予測期間10年たったときに、10年後の土地の価格なんていうのはやはりわからないので、そのときの傾向として顕著に値下がり、値崩れが起きているような場合は、当然、その値下がり率というのは考慮いたしますけれども、基本的にはその現時点の土地の評価額と、もうそのまま据え置いているケースが実務的には多いです。それがいいか悪いかという問題は別にいたしまして、実務的には今の時価をもう10年後の時価として据え置いているケースというのが多いです。
以上でございます。
- ○辻山部会長
-
よろしいでしょうか。
- ○品川委員
-
最初のところで、もうちょっと確認したいのですが、その株式価値と特定事業用資産は、特定事業資産の場合は、これは買い取る場合ですから、その部門を全部買い取るわけですね。株式価値の場合は、会社の株式を全部買い取る場合の値段と、あるいは5%から10%買い取ると過半数になるから、企業支配ができるということで買い取る場合と、あるいは最初から過半数を買い取る場合と、さらに株式の場合ですと、譲渡する側、先ほどは買収する側の説明でしたけれども、譲渡する側の値段としてはどういう値段が正当なのかということで、これは特に株式の評価に関しては、実務的にいろんな疑問なり問題なりに遭遇しているものですから、その辺もあわせて御説明いただければと思います。
- ○大塚参考人
-
これは、株式に対してですか。
- ○品川委員
-
先ほどは、ほぼ同じだという御説明だったものですから、株式にはかなり違ってくるのじゃないかと思いまして。
- ○大塚参考人
-
考え方として、いわゆる計算のロジックとしては、同じようなコンセプトに基づいて計算しますけれども、先ほどおっしゃいましたように、株式にしても、事業資産にしても、当然、買い手側の理論と売り手側の理論というのが違ってきます。当然、我々は買い手側の理論に立って評価する場合もございますし、売り手側の理論に立って評価する場合もございます。特に売り手側の立場に立って、例えば過半数以上を売却するような場合は、コントロールプレミアムといったところも考慮しなければならないですし、そういう細かいと言っていいのかどうかわからないのですけれども、そういったところをいろいろ吟味していくと、その事業資産の評価と株式の評価とが違ってくるかと思うのですけれども。
- ○辻山部会長
-
ほかにございますでしょうか。
- ○太田委員
-
7ページのところで、営業権の評価方法に純資産価値評価と超過収益力還元価値評価があるという御説明だったと思うのですが、純資産価値評価の方をとる場合で、これは総体としてのキャッシュフローから割り引いた価値から個々の資産・負債の時価の合計額を差し引いたものが営業権だという御説明だったと思うのですけれども、実務的に個々の資産、特に固定資産に限ってみた場合に、その場合の個々の資産の時価というのは、どのような形で算定される場合が多いのか、お聞かせ願えないでしょうか。
- ○大塚参考人
-
それも、その時々、どこまで資料を入手するかによって変わってくるのですけれども、固定資産の中の土地はやはりインディペンデント・アプレイザルというか、不動産鑑定士がとらえる時価、あるいは相続税の評価の評価額を使うケースが多いです。建物とか土地に関しましては、特に機械装置、工具、器具、備品に関しましては、あくまでも会計上の簿価をベースにしております。というのは、私どもデュー・デリジェンス・レビューとかやって深く入り込んでいれば、その個々の資産に関して、例えば使っている、使っていない、いわゆる遊休資産であればもう残存価値しか見ないよとかいうことはできるんですけれども、例えば情報がある程度限られている場合は、会計的にはいわゆる会計上の減価償却が、その事業の主体である会社側が価値の減少を評価しているものだというふうな前提に立っていますので、機械装置とか工具、器具、備品に関しましては、実務的には会計上の簿価を使っているケースが多いです。
- ○辻山部会長
-
よろしいでしょうか。
そのほか、ございますでしょうか。
- ○大塚委員
-
少し私の感想を言わせていただいて、よろしいでしょうか。
7ページの特定事業資産の評価の2つの式があるのですけれども、今の話を聞いていますと、大体特定資産の対象の期間が3年から4年くらいの期間になっているということから考えると、いわゆる上の純資産価値評価の方が、将来のキャッシュフローだけを予測して、資産と負債については現在の時価でもって計算するというわけなのですけれども、下の方の超過収益力の還元価値になりますと、t年度のそれぞれの予想時価を見積もらなきゃいけない。そういった意味から言うと、差額概念の方がむしろよりきちっとした数字が出てくるんじゃないか。私はそういう印象を受けたのですけれども、それについては、どうでしょうか。
- ○大塚参考人
-
実務的に申し上げますと、下の方のt年度の個々の資産、負債の予想時価といいましても、いわゆるターゲットである会社側が事業計画の中で利益計画以外に予想貸借対照表の推移みたいなのをつくっていただいているところは、それを使うケースもあるのですけれども、各年度の時価というのは非常に見積もりにくい。具体的に私ども何をやっているかとといますと、例えば減価償却に関しましては、例えば毎年の減価償却をそのまま減らしていくと。それから運転資本、いわゆる売掛金、買掛金、あるいは在庫に関しましては、そのときの滞留日数で、当然、売り上げがどんどん右肩上がりにふえていけば、当然、それに見合った形で売掛金、買掛金、棚卸し資産というのもふえていきますから、そういったのを売り上げの伸びに照らし合わせて、売掛金とか棚卸資産とか、買掛金を増加させていくというような程度にとどめております、実務的には。
- ○大塚委員
-
ちょっとだけ気になったものですから申し上げたいのですが、12ページのこのCAPMによる自己資本コストの式なのですが、これは実務的に応用されてこういう形でやられているというのは、私なりに差し支えないと思うのですが、CAPMという理論そのものの考え方で言うと、β(rm -rf ')になっているのですけれども、rm というのはマーケット・ポートフォリオのリターンというのが本来のCAPMの理論でありまして、そしてその後もrf 'じゃなくてrf という、いわゆるリスクフリーレートだけというのが本来のCAPMのもとの理論の形でありまして、それをこういう形でもって少し異なったバージョンでもって実務的に応用しているというのはそれなりにわかるのですけれども、もとの理論はちょっと違うということだけを申し上げたいと思います。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
もしあれでしたら、先に進ませていただきまして、後ほどまた質疑の時間があると思います。この特に用語等の説明に関しましてでしょうか。
- ○品川委員
-
最後のところで、DCFを類似会社比準方式とか類似業種比準方式で検証するというお話があったのですが、DCF自体については、限界ということで、いろいろ問題点があるということで、私も実務的に非常に大きな問題があると思うのですが、実際、検証する場合に、現実にどういう誤差が生じていて、問題があるのかどうか、その辺、実際に検証したことの結果をちょっとお知らせいただければ、大変ありがたい。
- ○辻山部会長
-
では、この点についてどうぞ。
- ○大塚参考人
-
検証というような高尚な作業・分析はやっていないのですけれども、基本的に私どもDCFを出す場合も、一つのシナリオで出すということは、ちょっとリスクが高いのでやっておりません。一番うまくいったときの利益計画、あるいは一番確実で、実際ベースでいったときの利益計画というような形でDCFで2通りの数値を出して、2通りの数値を出せば当然、レンジが出てきますので、そのレンジと先ほど言いましたPERとかPBRとか、そういったものとの数字を比較して、大体の幅を決めて、その後、やはりこれは交渉事ですので、その中で、いろんな交渉の中で詰めていくという形になるかと思います。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それでは、また後ほど追加的な意見交換ができると思いますので、先に進ませていただきます。
次に小宮山委員から御報告をお願いいたします。
- ○小宮山委員
-
公認会計士の小宮山でございます。のれんの減損について、少し報告をせよということで報告をさせていただきます。
お手元に資料が2つあると思いますが、(資料2)と書いた資料と、その次に(参考)として「のれんの減損に関する参考資料」というのがございます。本文の中で引用しているパラグラフがこの参考に入っておりますけれども、主として資料2に基づきまして説明をさせていただきたいと考えております。
6月28日に「論点整理」が公表されたわけですけれども、のれんの減損に関して論点というのは2つございました。一つは、企業結合によって取得した資産又は資産グループについて減損を認識する場合、関連するのれん、連結調整勘定を含むわけですが、これの帳簿価格を当該資産又は資産グループにどのように配分すべきかどうか、もう1点は、のれんの配分後の資産グループに減損損失が生じた場合に、その減損損失をどのようにグループの構成資産とのれんを配分するか、この2点でございます。もう大分昔になりましたので、確認のため、米国基準とIASでどういうふうになっているかという点を確認させていただきたいと思います。
まず最初は米国基準でございます。FAS121で規定されているわけですけれども、まず第一に、回収可能性のテストの対象となる資産がパーチェス法により会計処理された企業結合により取得されたものである場合には、回収可能性の決定の際にのれんは資産グループに含まれなければならない。
第2点として、取得資産の一部がテストされる場合には、他の方法がより適切な場合を除き、のれんは取得時の長期資産及び識別可能無形資産の公正価値の比率により配分される。
3番目が、のれんが減損損失が計上される資産と関連する場合には、長期性資産と識別可能無形資産の帳簿価額を減額する前に、のれんを消去しなければならない。
第4点は、減損が認識される場合には、減損後の帳簿価額が新たな取得価額となり、減損の戻入れは認められないという点でございます。
一応、



 というのは対応するように書いてございますけれども、2番目が国際会計基準の規定でございます。まず1点として、キャッシュ生成単位について減損テストを実施する場合、財務諸表上認識されているのれんについては、第1段階としてボトムアップテスト、第2段階としてトップダウンテスト、より大きなキャッシュ生成単位というふうな意味ですけれども、これを実施しなければならない。2点目として、のれんの帳簿価額は合理的及び首尾一貫した基礎でキャッシュ生成単位に配分される。3点目として、減損損失はまずのれんに配分され、各資産の帳簿価額に基づいて比例按分される。4点目としては、回収可能額の見積もりに変更があった場合には、減損の戻し入れを行うが、のれんについては非常に稀な場合を除いて、原則として戻し入れは行わない。この4番目の趣旨は自己創設のれんの計上は禁止するという趣旨に対応して、のれんを後で戻し入れるということを保守的に規定しているというふうな趣旨のようでございます。ここで米国基準と国際会計基準というのを比較させていただいたわけですけれども、中身としては実はよく似ております。それで、次にのれんの減損についてわが国はどういうふうに考えたらいいのかという私見でございます。
というのは対応するように書いてございますけれども、2番目が国際会計基準の規定でございます。まず1点として、キャッシュ生成単位について減損テストを実施する場合、財務諸表上認識されているのれんについては、第1段階としてボトムアップテスト、第2段階としてトップダウンテスト、より大きなキャッシュ生成単位というふうな意味ですけれども、これを実施しなければならない。2点目として、のれんの帳簿価額は合理的及び首尾一貫した基礎でキャッシュ生成単位に配分される。3点目として、減損損失はまずのれんに配分され、各資産の帳簿価額に基づいて比例按分される。4点目としては、回収可能額の見積もりに変更があった場合には、減損の戻し入れを行うが、のれんについては非常に稀な場合を除いて、原則として戻し入れは行わない。この4番目の趣旨は自己創設のれんの計上は禁止するという趣旨に対応して、のれんを後で戻し入れるということを保守的に規定しているというふうな趣旨のようでございます。ここで米国基準と国際会計基準というのを比較させていただいたわけですけれども、中身としては実はよく似ております。それで、次にのれんの減損についてわが国はどういうふうに考えたらいいのかという私見でございます。 わが国の場合、個別財務諸表でのれんが計上されるということは非常に少うございまして、基本的には連則財務諸表において連結調整勘定というかたちで出るものが多いということが言えるかと思います。会計士協会の方で「決算開示トレンド」というのをここ数年、毎年出しておりますけれども、'97年から'99年まで3年間で調査対象の会社は500社あるわけですけれども、個別財務諸表でのれんが計上されている会社というのは、18~24社の間におさまっている。一方、連結調整勘定が載っかっている会社というのは、462~463社というふうになっております。
のれんの問題というのは、ちょうど連結の制度が新しくなったばかりでして、過去は大体5年でやっていたところが多くて、それと新しい基準ですと20年までということで、ちょうどのれんの償却年数が端境期にあるような、そういう状態にございます。先ほど国際会計基準と米国基準を比較させていただいたわけですけれども、国際会計基準の方ではその以前にもIAS第22号の「企業結合」というのが出ておりまして、その中で回収可能価額が帳簿価額より低い場合には、減損損失を認識されなければならないと、同じような趣旨が既に存在しておりました。一方、FAS121の場合ですが、もう大分古い時期になりますけれども、APB17ですからもう30年以上前になるのですか、この中に無形資産の価値や将来の便益の見積もりが未償却残高を大幅に減額することを示す場合がある、この場合には短くするということが要求されております。日本の場合、あまりこのような取り扱いというのは、過去は明らかにはなかったわけですけれども、この連結の新しい制度ができてから、会計士協会から会計制度委員会の報告第7号というのが平成10年5月12日に出ております。そこでどういうふうに書かれているかといいますと、連結調整勘定の効果が取得時の見積もりに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる状況が発生した場合には、連結調整勘定に相当の減額を行わなければならないということが書かれております。
比較してみますと、IASの場合はもともと企業結合の方で規定した内容というのが、減損という考え方にかなり近いように思いますし、アメリカの場合や会計士協会の指針というのは、臨時償却的な意味合いが強いような書き方がされているという感じがいたします。いずれにしても、前から議論がある点ですけれども、のれんの評価減についてもやはり臨時償却と減損の問題というのは混在しているのかなというふうに考えられます。
こののれんの問題というのも、あとで申し上げますけれども、企業結合の会計の問題として扱うのか、減損会計の問題で扱うのか、両方あると思いますけれども、基本的にIASの場合ですと、個別資産としてのれんの回収可能性というのは、基本的に算定できないという観点に立っているようでございますし、FASの場合ののれんを考慮せずに長期資産や識別可能無形固定資産の減損の判定ができない、この辺で減損会計の中でのれんの問題を一緒に含めようという考え方になっているようです。今年の3月から連結のルールが変わっているわけですけれども、現行の連結財務諸表原則の中では、投資と資本の消去で出てきた差額がすべて連結調整勘定になっている。これは昭和50年に出た旧原則では、営業権と連結調整勘定が別個に出てくるというふうな規定になっていまして、いずれにしても、差額でよくわからないというふうな内容は変わらないわけでございまして、IASの背景やFASの背景と我が国の場合はあまり変わらないのかなというふうに考えられるわけでございます。
そういう意味で、基本的には減損の判定単位ごとにのれんの未償却残高を配分するのがよいのではないかというふうに考えられます。それでは、どうやって配分するのかというのが次に問題になるわけですけれども、米国基準では取得時の長期資産と識別可能無形資産の公正価値の比率によるというふうにしております。IAS36は、この辺、考え方がはっきりしていませんで、合理的及び首尾一貫した基礎で配分すると書かれています。ただ、後ろの方の付録A64というところを見ますと、一応、正味の公正価値による比例配分を合理的な基礎に当たると書かれておりまして、米国基準と同じ処理をしたとしても、IASで問題になることはないのかなという感じがいたします。米国基準でなぜ公正価値をとっているかというのは、これは見ても内容がどうも、背景がはっきりいたしません。最終的な基準上はバックグラウンドでもわからないですし、公開草案の説明でも、なぜこの考え方をとったかというのは、どうもはっきりいたしません。ただ、私が実務家として感じるのは、実務的に採用できる恐らく一番簡便な方法じゃないかなという感じがいたします。
ただ、このIASの規定とFASの規定というのはよく似ているというふうに申し上げましたけれども、実は範囲が違います。FAS121というのは長期資産と識別可能無形資産の減損というのだけが対象とされていますし、IAS36というのはすべての資産の減損が対象とされているという意味で違ってきます。例えばアメリカの場合ですと、こういう規定になっている関係でのれんのうち、長期資産と識別可能無形資産の減損というのは121の対象になるし、それ以外ののれんというのはAPB17が対象になるということになるのだろうと思います。ただ、我が国の実際に実務というのを考えますと、ある会社の支配を獲得するといった場合に、これは先ほど、つい前に終わった第一部会でも議論がありましたけれども、資産負債の時価評価の段階で識別可能な無形資産が計上されるというのは、今のところの日本の連結の慣行には恐らくないものだろうと思います。そうしますと、設備等の重要性が乏しい産業に属するような企業買収というふうな場合には、必ずしも公正価値の比率によってのれんを配分するということが合理的でない場合も出てくるのかなと考えられます。
下に
 ~
~ まで私案といたしまして、こういうふうに考えたらどうだろうかという点を述べてございます。一つは、原則として取得時の資産の公正価値の比率によりのれんを配分する。2番目として、先ほどの方法による配分が適当と認められない場合には、その他、合理的な方法の採用を認める。この辺でさっき、中央青山監査法人の方から説明された評価の方法と関連してくる部分もあるのかなと思います。3番目として、キャッシュ生成単位が識別できない場合には、のれんの配分は行わない。この場合には、その取得された企業全体で減損の判定を行うということになろうかと思います。4番目は当たり前のことですけれども、のれん自体が重要性が乏しい場合には、のれんの配分は行わないことができる。5番目として、減損損失はのれんに優先的に割り当てる。6番目として、のれんの減損の戻し入れは行わないということでございます。
まで私案といたしまして、こういうふうに考えたらどうだろうかという点を述べてございます。一つは、原則として取得時の資産の公正価値の比率によりのれんを配分する。2番目として、先ほどの方法による配分が適当と認められない場合には、その他、合理的な方法の採用を認める。この辺でさっき、中央青山監査法人の方から説明された評価の方法と関連してくる部分もあるのかなと思います。3番目として、キャッシュ生成単位が識別できない場合には、のれんの配分は行わない。この場合には、その取得された企業全体で減損の判定を行うということになろうかと思います。4番目は当たり前のことですけれども、のれん自体が重要性が乏しい場合には、のれんの配分は行わないことができる。5番目として、減損損失はのれんに優先的に割り当てる。6番目として、のれんの減損の戻し入れは行わないということでございます。 これは、この報告をするにあたり、いろいろ考えてみまして、やはりのれんの減損の問題というのは、企業結合会計というものと非常に密接な関係がある問題もございます。問題点によりましては、結合会計の中でどう考えるかという視点が決まらないと、次のステップが出てこないという問題もあるのかなという感じもいたします。幾つかその点を列挙してございます。一つは、支配獲得時ののれんの算定ということです。もちろん持分法を適用している場合には、潜在的にあるわけですが、現行の連結原則では、支配の獲得時に連結調整勘定というのが初めて出てまいります。これは持分法の適用会社であっても同じわけでございまして、全面時価評価法というのを採用する場合には、子会社となった時点で連結調整勘定の再計算が行われます。部分時価法が採用される場合には、過去の取得分に対する連結調整勘定相当額、償却後という意味ですが、それはそのまま引き継がれるということになります。そうしますと、例えば関連会社であった時点の取得価額が子会社した時点の取得分よりかなり高い場合ですとか、業績が悪化した関連会社が子会社化した場合、こういう場合には、連結調整勘定自体の資産性に疑義が出てくるような場合もあるのかなと。今のところですと、機械的に連結調整勘定が出てきていますので、そういう問題点もある。このような場合の取り扱いを検討する必要があるのかどうかというのが第1点でございます。
第2点は、取得後の事業統合等。先ほどシナジー効果という話はよく出てくるわけですけれども、子会社の取得後に事業統合が行われた場合に、その後の事業に使用する資産というのはある程度統合されてしまうわけです。そうしますと、その後の事業のキャッシュフローで減損を判定するといった場合、どれとどれを対応させるのかという問題が出てくるわけです。つまり、キャッシュフロー自体の中に自己創設のれんと考えている部分が入ってくる。そうしますと、それを考えると減損分は少なくなってしまうだろうという見方も一つあるわけです。この辺の考え方については、IAS36の付録のB102~104というところに、この辺が議論されたという話が書いてございます。さらに取得された企業を統合していく関係で、要らない事業はまた整理していくという話があるのだろうと思いますけれども、これにより発生する損益ですとか、これに対応する連結調整勘定というのはどういうふうに処理されるかというのは、必ずしも明確ではないのだろうと思います。
3番目としまして、取得後の減損の検討ということでございまして、実務上、支配権の対価相当額として一定額に、先ほど品川委員の質問にもちょっと関係してくるかもしれませんけれども、支配権の対価として時価に一定のプレミアムを加えて企業買収が行われるということもございますし、競争入札を行いますと、比較的高い金額で企業買収が行われるという場合も出てまいります。この場合も、その取得原価である、第三者間で最終的に合意した金額であるということは間違いないわけですけれども、結果としてそののれんの金額は多額になることがあります。こういう場合について取り扱いを検討する必要はないかというのが3つ目のポイントでございます。
'99年の9月に公表されたFASBの企業結合と無形資産に対する公開草案では、このような場合に2年以内に回収可能性のテストを行いなさいというふうな提案になっております。なぜ、そういう要求をしたかというのは、背景に若干書いてございますけれども、一応、のれんというのは、要するに残余、レジデュアルだ、したがって、そういう形でしか測定ができない、だから、常に過大表示の可能性というのがあるんじゃないかということが書かれております。
4番目として、のれんの償却年数ということでございまして、連結原則では20年、商法上は5年というふうになっております。この償却期間と、これも先ほど第一部会で同じ議論が出たような気もするのですけれども、この償却期間と主要な資産の残存耐用年数、減損の判定時のキャッシュフローの見積期間、この辺について何か関連させるということを検討する必要はないだろうかというのが4点目でございます。
最後は難しい問題をみんな企業結合だと言って逃げたような感じもしないではないのですけれども、以上でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
ただいまの小宮山委員からの御報告につきまして御意見をちょうだいしたいと思いますけれども、特に当部会に関係するところでございますが、3ページ目に、一応私案という形ですけれども、
 ~
~ のような考え方が出されております。さらに3のところで、企業結合との関係について論点の指摘がございますので、第一部会長も御出席でございますので、どうぞ御発言をお願いいたします。
のような考え方が出されております。さらに3のところで、企業結合との関係について論点の指摘がございますので、第一部会長も御出席でございますので、どうぞ御発言をお願いいたします。 - ○品川委員
-
4ページの最後に支配権の対価相当額としてプレミアムつきで企業買収を行った場合でありますが、これは株式の取得として株式を相当高く買った場合に、株式の取得価額としてバランスシートに計上されることになろうかと思いますし、それが連結にならないで、そのまま取得価額となった場合の、その株式の減損をどう考えるのかということをちょっとお伺いしたいのですが。今、税法の取り扱いでは、そういう支配対価は償却を一切認めないという通達を出しているのですけれども、それとの関係と、その通達の矛盾みたいなものもいろいろ考えさせられるのですが、その辺はいかがでしょうか。
- ○小宮山委員
-
基本的には対象となった事業を連結したときに出てくる連結調整勘定、のれん、これの減損の問題としてここでは書いております。ただ、実はここに書こうと思って書けなかったのが、今、品川委員から出たポイントでございます。買収対象になった企業自体の減損を問題にするとなりますと、個別財務諸表で載っかっている株式の評価額がどうなのかというのは、当然出てくるわけです。その問題がどうかということは、前にどこかでも申し上げましたし、問題点としては残っているだろうというふうに思います。その減損の基準に何をとるかということと関係しますけれども、確率基準をとりますと、基本的にそういう可能性が高いという前提に立ちますので、よけい問題が大きくなるというふうになるのかなというふうに考えていますけれども。
- ○辻山部会長
-
ほかに御発言ございますでしょうか。
もしございませんようでしたら、いったん秋葉委員の御報告の方に進ませていただいて、あとでまとめて質疑を行いたいと思います。よろしいでしょうか。では、あとでということで、秋葉委員の報告の方に入らせていただきます。
では、秋葉委員、よろしくお願いいたします。
- ○秋葉委員
-
会計士の秋葉でございます。
私の方はお手元にあります資料3、全部で7~8枚ほどですけれども、それに従ってお話しさせていただきたいと思います。
私の方で御報告させていただくのは「全社資産の減損について」というテーマでありますけれども、この全社資産の考え方は、今、小宮山委員の方から御報告がありましたように、のれんの減損に関連する部分が多うございまして、特にIASの場合にはかなりそこの部分と重複しているといいますか、準用している部分が多いように見受けられます。
まず、そのお手元のペーパーに従ってお話し申し上げますと、まず問題の所在としては、これは先ほどお話がありましたが、6月の論点整理で既に出ているところでございますが、共用資産や全社資産は独立して直接的にキャッシュフローを生み出すわけではないという特徴がありますので、減損の認識や測定に際してキャッシュフローを識別する場合には、識別が可能なように合理的な範囲内でグルーピングを行う必要があるということで、これが共用資産も含むと思われますが、具体的な問題が出てくる。その問題の一つがグルーピングということかと思います。これは後でもちょっと申し上げたいのですが、一応、論点整理の場合には、「減損の認識や測定に際してキャッシュフローを識別する場合には」という条件というか、前提を置いていまして、理屈としては、このキャッシュフローを識別しないで減損の認識や測定を考えるということもあり得るのかなというふうには思いますが、それは若干後で述べさせていただくとしまして、オーソドックスにこういうふうに考える場合にグルーピングの考え方はどうするのだということで、次の2番に入らせていただきたいと思います。
そのときにグルーピングの利用方法とそれぞれの手順における問題点というのを簡単に列挙したわけですが、この際、IAS、国際会計基準の方を参考にしております。US基準の方は、特に現行ルールの方がこの全社資産のグルーピングという点があまり明確ではないのかなと思いまして、国際会計基準の方がわかりやすいということで、そちらを中心に挙げているわけですけれども、これは先ほどのれんのところでも問題といいますか、手順としてありましたように、大きく4つに分かれると思います。一つが、まずキャッシュ生成単位の把握、それからロにありますように、その全社資産の帳簿価額を配分するという話、そしてハになりますが、配分した後の回収可能額とその帳簿価額を比較する。ニにありますように、そのキャッシュ生成単位ごとの減損損失を今度はいかに各構成資産に配分するかというのがポイントになろうかと思います。
先ほどのれんのところでもこのロの全体の配分、それからニにありますような各キャッシュ生成単位で出てきた減損損失をさらにまた配分するところ、これが問題として挙げられましたが、そういう意味では問題の所在というのは非常に似ておりまして、その辺のところをもう少し、右側に述べた問題点にかかわらしめてお話しさせていただければと思います。
まず、そもそもキャッシュ生成単位というキャッシュフローを生み出す単位の把握が重要になってくるわけですが、この際にUS基準のFASBの方でも、他の資産からもたらすキャッシュフローから概ね独立したキャッシュフローをもたらす単位というか、グループを考えておりますけれども、こういう独立した最小の単位というのは、考え方としてはわかるわけですけれども、実際上、どういうふうに括り出すかというのは、非常に実務的な面では特に難しいのではないかというふうに思います。これに関しましては、以前の報告で、例えば一つの工場で複数の製品をつくっているというような場合に、その工場という単位で見るのか、複数の製品の方に着目して見るのかというふうな点も考えられるかと思いますし、この辺はもう少し資産別に考えていくと、究極的にはといいますか、特徴的には賃貸資産のようなものは独自にキャッシュフローを生み出すということで、別途投資不動産として括るのかどうかというところにも関係していくのかなと思います。
取り急ぎここでは問題点ということだけで挙げまして、一応、そのキャッシュ生成単位が把握されれば、この全社資産を配分するという手続になるわけですが、IASの場合にはここでまずボトムアップテストと言われますように、その各キャッシュ生成単位に配分するという手続をとることを示しております。この場合、各キャッシュ生成単位に合理的な配分基準をもって行うということにしているわけですが、先ほどのれんの場合に公正価値というお話がありましたが、IASの場合の説例では、帳簿価額の耐用年数をウェーティングしたような加重平均で按分するといったような説例が出ております。ただ、合理的な配分基準ということは、いろいろな指標が考え方としてはあるのかなという気もいたしまして、例えば注1ということで、この1ページ目の下から2ページ目にかけて述べておりますが、我が国でもセグメントの会計手法の中の例示として、2ページ目の最初の方にございますが、共用資産の配賦基準としまして、利用面積とか人員数とか、取扱量(金額)、生産量(金額)というものも明示しておりまして、このような配賦基準、配分基準ということも考えられないのかということが一つあろうかと思います。
次にまた1ページに戻っていただきまして、このボトム・アップテストをIASなんかの場合ですと原則的にまず行うことになっておりますが、ロの(ロ)にありますように、合理的に配分できない場合には、トップ・ダウン・テストと呼ばれるような、より大きなキャッシュ生成単位にこの全社資産等を配分するという手続が求められます。この場合に、右側の問題点にありますように、合理的な配分ができないという場合には、というのは具体的にどういうことだということ、これをもう少し明示しなければいけないということになろうかと思いますし、より大きなキャッシュ生成単位に配分するということになりますと、一番大きいのは企業単位になるということが考えられますけれども、こういう場合に、先ほどのDCFのお話にもありましたが、キャッシュフローの具体的な見積期間をどうするかいったようなことも問題としては挙げられるかと思います。
さらに、いろいろ問題がある中で一つ考えられるのは、他の個々の資産には減損の兆候が見られないという場合でも、全社資産のみにある場合、このような場合にはどうするかということも、問題点としては考えられるのではないかというふうに思います。
手順としては、ハにありますようにキャッシュ生成単位において回収可能額を把握し、それから今配分されたような帳簿価額を比較してキャッシュ生成単位ごとに減損を把握するわけですが、次のニとしまして、その把握された減損損失を今度はさらに各構成資産に配分するというような手続が必要になってきます。この際の問題点として考えられることの一つとしましては、右側の●にありますように、この減損損失の配分を各構成資産に一律に戻してあげていいかどうかという点があろうかと思います。この際、先ほどの小宮山委員の報告にありましたが、IAS、それから一般的にも、まずはのれんに優先して配分すべきだというような議論がされておりまして、ただ、次の議論としましては、のれん以外の無形資産に優先的に配分されるべきなのか、無形資産、有形資産、区別なく配分されるかというような議論が、どうもあるようです。この問題としましては、のれんの場合とも絡むと思うのですけれども、いわゆる無形資産の回収可能性といいますか、資産性、これをどう考えるかという点が言われているようでありまして、この辺を考慮すれば、まずは無形資産に優先的に配分されるべきではないかということが言われているようです。
さらに、もう一つの議論としましては、個々の資産を見たときに、帳簿価額が正味の売却価格を上回っているという場合には、そういうような資産にまず優先的に配分すべきではないかという議論もありますので、この場合にはそういう各資産ごとにばらつきといいますか、優先的に簿価が正味価格を上回っていると、そういうものが多く減損を生み出しているのだということを仮定して配分するわけですが、一方でグルーピングの意味を考えますと、そういうような個々の資産に優先的なことを考えて配分するというは、妥当なのかどうかということが言われているようです。
さらには、2つ目に挙げました問題は、この減損損失を各構成資産に配分する基準はどうするかということですが、一般的には先ほどロで述べましたような全社資産の帳簿価額を配分する基準と同じ基準で配分するということは言えるのではないかと思います。さらに、全社資産を念頭に置いていますが、共用資産という形の複数のキャッシュ生成単位にまたがるような資産も考えられるわけですけれども、こういうようなものについても、部分的に減損損失を認識すると考えてよいのかどうか。すなわち、全社資産の場合には、一部分減損するというのが、この配分を通じて理解がしやすいわけですけれども、先ほどの例が、例えば一つの工場なり製造ラインで複数の製品を使っている、そういった場合に、その設備として複数のものをつくっていますけれども、一つのラインなり製品のところの減損によって、3分の1とか2分の1とかという減損とすることが考えられるのかどうかといったようなことも問題点として挙がるのではないかというふうに考えます。
以上は、簡単ですがグルーピングのIASを中心にした方法と、それであっても具体的にかかわる問題点を列挙させていただきましたが、2ページ目のところに移りまして、(2)としたところでは、冒頭申し上げましたように減損の認識とか損失に関してキャッシュフローを識別する場合には、当然、今のような議論になるわけですけれども、もしキャッシュフロー以外の定性的な基準によってその減損の認識とかを考える場合には、グルーピング以外の判断要素もあるのではないかということで、(2)に、これは一つ私見にはなると思いますけれども、挙げさせていただきました。すなわち、例えば例としましては、(2)のイにありますように、もうその全社資産なりが廃棄、処分予定が決定されたという場合には、その具体的キャッシュフローの分析を伴わずに減損というふうなことが考えられないかどうか。それからもう少し発展させまして、その全社資産自体が潜在用役をもう提供できないというような場合に、どう考えるか。さらにもう少し進みますと、その全社資産自体の時価が極めて著しく下落しているという場合に、直接的に減損の存在を考えることができないか、ないしは必要がないかという点であります。特に、その全社資産が本社ビルといったように、直接キャッシュフローを生み出す性格を有する不動産の場合には、その企業がその事業用といいますか、本社ビルとして独自に使っているというような、事業資産としての性格はもちろんあるわけですが、別途、特に商業ビル等であれば、直接キャッシュフローを生み出すという性格もありまして、その本社ビル自体がどのぐらい自己利用に伴うのれんが含まれているのか、使用価値と公正価値の差は妥当なものと考えられるのかというようなことが、特に懸念されるのではないかというふうに思います。
この減損の認識とか測定の話というのは、入り口の議論でもありながら、最後まで議論となるようなところかと思うのですけれども、一応、私なりにこの問題について、若干整理したところは次のところのセクションになっておりまして、若干立ち入った部分もあろうかと思うのですけれども、ここの部分の考え方いかんによっては、今のような部分に影響を与えると思いますし、今後の議論にも関係するというふうに思われますので、若干述べさせていただきたいと思います。
最初は、確認としましては、まずそもそもこの減損会計の意義というのは、6月の論点整理で示されておりますように収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった帳簿価額を一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように減額する会計処理であって、将来に損失を繰り越さないための臨時的な減額と考えることが妥当であるというふうに示されております。
これを踏まえて、理念的な考え方としては、利益計算における費用配分を重視する観点からは、過年度の回収額も含めて、まずその投資期間全体を通じた回収額を見積もって、その価値が当初投資額を下回っていれば、減損の認識を行う、このときに、見積もった回収額をもとにして、再度算定された未償却額、すわなちその減損後の帳簿価額と、それから減損前の帳簿価額、この差をもって減損損失を測定するというような考え方が示されておりまして、これは論点整理の確認になるわけですが、これを踏まえて減損の認識測定をどう考えるかということになりますと、これはちょっと私見が入るわけですが、IASなりFASBで言われているような経済基準とか確率基準ということも、ここで示されたような理念的な考え方とはちょっと異なるわけで、いずれをとるかということを結論として考えた場合でも、理念的な考え方の代替的な手段にはなるのでしょうと。そうすると、8月までに各界からいただいたようなコメントも踏まえれば、実務上も適用が可能な、ないしは容易な確率基準が妥当ではないかというようなことが一つ考えられるかと思います。
ただ、ここの場合、確率基準を仮にとるとしましても、アメリカ基準がとっているような割引前キャッシュフロー総額が唯一の指標かどうかということは若干検討する必要があると思いますが、一つ減損の認識に関しては、こういったような整理が考えられます。
次に、減損損失の測定については、これも先ほど申し上げたような理念的な考え方とは異なりますけれども、これまで考えられているようなことを整理すれば、その回収可能性を反映させるという観点からすれば、考え方としては使用価値の方が妥当なことになるのではないかというふうに思われます。ただし、これも実務的な各界からのコメントとか、それからこれからの具体的な適用性を考えますと、この使用価値については客観性に問題があるというふうなことが考えられますので、例えば合理性が認められないという場合には、公正価値にするといったような方法が考えられるのかなと個人的には思っております。
そうしますと、今のように(3)、(4)というような方法で今後議論を進めていった場合に、すなわち例えば確率基準を採用して、さらに割引前のキャッシュフロー総額で減損を認識するというようなことをとり、さらにIASでふまえているようなトップ・ダウン・テストということも含めて採用するということになりますと、全社レベルで全社資産が検討されるというようなことが予想されます。そうすると、結論的にどうなるかといいますと、本社ビルなどの全社資産の時価が極めて著しく下落していても、結果としてその減損を認識する必要がないという可能性がありまして、特にそういう不動産のものにつきましては、非償却性資産の土地を含みますので、売却されるまでは損失が認識されないというような結果になってきます。
したがって、ちょっと先取りするようで非常に恐縮なのですが、こうなってきますと、結局、減損する資産が考えられているものよりも狭まってくるということも考えられまして、政策的な面があるかと思いますけれども、この辺も考慮すべきではないかと思っております。この辺のお話は、次の3ページ目のところで、前々回にお話しさせていただいたところでも触れましたが、減損会計の定義は先ほどの論点整理のところでも示されておりましたけれども、いろんなケースを考えたときに、それ自体が減損とは考えられないかという点の問題にもつながってくるというふうに思っております。
ここの部分は繰り返しになりますので割愛させていただきまして、3ページ目の最後のところで、3番としまして、全社資産の減損についての個別財務諸表における問題点ということを、簡単に触れさせていただきたいと思います。先ほどのれんのケースでも個別と連結の問題が示されましたが、全社資産についてもいろんなケースが考えられますが、単純な場合分けとしまして、当然、4つのケースが考える。すなわち、個別では減損は認識されて、連結でも認識される、それからケース4のように、個別では減損が認識されないが、連結でも認識されない。これは非常にわかりやすい話ですので、問題は少ないと思いますが、ケース2、ケース3のように、例えば個別財務諸表上は減損が認識されますが、連結上は認識されないというケースも場合によってはあるのではないか、それから逆に、個別上は減損が認識されませんが、連結上認識されるというケースも考えられるかと思います。これはちょっと個々のケースをどういう想定をするかによってありますが、このようなケース2とかケース3のケース、これも実際にはあり得るということで、このようなことを一応念頭に置きながら考えていかなければいけないというふうに思います。
さらに個別と連結という話も、いわゆる親会社の個別財務諸表と、それから親会社のレベルでの連結財務諸表というレベルでケース2、ケース3が考えられますが、個別財務諸表の中には子会社独自の単独での個別財務諸表というのも、特に商法決算を考えますと存在しますので、そうすると、子会社レベルでは減損している、ないしは減損していないが、親会社レベルの減損では逆の方向に出るということも考えられまして、これは致し方ないと言えば致し方ないという割り切りもできますが、実務的に考えると少し整理した方がいいのじゃないかというような指摘もできるところかと思います。
以上、簡単ですが、私がお話しさせていただきまして、最後に後ろの方、今回ちょっと特にお話をしていませんが、先ほど申し上げたIASのところで具体的な全社資産の説例がありますので、これを御参考までに添付させていただいております。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
特に全社資産、共用資産の問題、扱い、それからグルーピングの問題を中心に御報告をいただきました。
ただいまの秋葉委員の報告並びに先ほどの小宮山委員の報告で、重なっている部分も大分ありますので、あわせて御質問・御意見等ございましたらお出しいただきたいと思います。お願いします。
- ○斎藤委員
-
まず手始めに秋葉委員の今御報告いただきましたレジュメの2ページの一番下、その上に書いてきたような方法で減損の認識測定をしたときに、本社ビルなどの全社資産の時価が著しく下落していても、減損を認識しないようなケースが出でくるという、その中に土地のような場合も含まれて、非常に懸念されるというお話に至りましたけれども、それは、一つの考え方は、その上で言っている使用価値、あるいは現在価値、それと公正価値の関係をどう考えるのかという問題でもあるような気がするのです。例えば早い話が、在庫品について低価評価をいたしますけれども、それは簿価と時価を比べてとっているわけです。その時価も、基本的には在庫を将来、売却したときの収益というものの期待価値で本当はとるべき話なのだけれども、在庫というのは短期に回転しますし、結局、それ自体はそのまま売るわけですから、将来の売却価格が将来に期待されるキャッシュフローであって、現在の時価をその推定値と考えているわけです。ですから、在庫はそういう意味で、基本的には減損と同じ考え方だと思うのですけれども、現在の時価に切り下げるという方法をとっている。
土地についても、私は基本的に同じ考え方を適用することは可能だと思うのです。土地の場合に、結局、土地を使って年々の収益を得るわけですけれども、通常の償却性の資産と違いまして、ターミナルバリューは残るわけです。これは非常に大きいわけで、そのターミナルバリューを現在の段階で推定して現在価値に加えなければ評価にならないわけで、そのときに、将来土地を処分するといいますか、あるいは自分の予想期間の一番最後に残るはずの土地の価値の相当分、それを現在に割り引いたときの推定値を現在の時価にしているんだというふうに考えれば、土地も現在の公正価値を使うという方法で減損を測定することは可能ではないかと思う。ただ、その場合に制約になりますのが、その上にあります確率基準を採用し、割引前キャッシュフロー総額で減損を認識するといいますか、そういうのが制約になっていまして、土地の場合には割引前のキャッシュフローを基準にして現在の簿価が過大かどうかということを判定してしまいますと、土地は無限に使えますから、キャッシュフローの割引前の価値というのは幾らでも大きくなるわけであって、そこで減損に引っかからなくなる可能性がある。ですから、そこを何とかすることの工夫をすれば、ここで言っている本来の、より原則に近いバリュー・イン・ユースといいますか、現在価値と、一定の特定の状況下での一種の近似的な測定値としての公正価値との関係を整理することによって、対応は可能ではないのかなという印象を持っています。以上です。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。この点について、秋葉委員、よろしいでしょうか。
ちょっと私の方から。今の秋葉委員の2ページでございますけれども、このビルが全社資産であった場合に、単独でこのビルの減損を考えるという場合でしたら、今の御指摘がそうなのですけれども、全社資産であって、そのグルーピングいかんによっては全社で十分なキャッシュフローが生み出されているようなケースを、恐らく秋葉委員も想定したのかもしれない。この点については、いかがでしょうか。
- ○斎藤委員
-
それだったら、減損に該当するのでしょうか。
- ○辻山部会長
-
それでも減損させなければいけないという御趣旨なのでしょうか。ここではこの「?」というのは、必要がない可能性があるというのは、ないと困るという、ちょっとその辺の……。
- ○秋葉委員
-
多分、そこが一番、現状の世の中での状況と理屈も踏まえたお話と結論のところの関係をどう調整するかというところになるのかなというふうに思っておりまして、すなわち、今、この2ページ目の最後で触れましたように、そもそも減損というのをどう考えるかというところにもあると思いますけれども、全社資産は一方ではこの会社の全体の事業に使われて、それが使われることによって、確かにその会社独自のキャッシュフローを生んで、その会社が全体にかかわるということで、各キャッシュ生成単位に分けられないと。したがって、十分に使っているということが言えたときに、その本社ビルなりを減損と考えるのか否かという問題なわけですけれども、一つは、まさにそういうふうに使っているわけですから、独自に利用するということで、そこに価値があって、したがって、減損させる必要はないというのは、一つといいますか、もしかするとちゃんとした理屈に伴う考え方かと思いますが、一方で、ちょっと直感的なところもあるのかもしれませんが、本社ビルのような商業ビルですと、別途独自にキャッシュフローを生み出すという性格を持っていまして、その場合にみずから使うということによって、それだけ本当に使用価値というものが、その固有の公正価値と比べて非常に幅があって、のれんが生じるというものなのかどうかというような懸念といいますか、印象が私なんかはございまして、特に簿価に比べて時価が2割、3割といったような状況というのは、昨今よく見られる話でして、そういうものがこの2ページ目の5に触れますように、減損の認識でも確率基準を使いながら、また割引前キャッシュフローで判断するということとか、それからボトムアップのみならずトップダウンということで、全社レベルで判断するということになると、結果としてその減損ということは出てこないので、本当にそれでいいのかなという、そういう疑問なのですけれども。
ここのところは、私の方がちょっと考え違いをしているかもしれませんけれども、印象としてもはそういうふうに思っております。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
斎藤委員。
- ○斎藤委員
-
ちょっと御質問ですが、今のお話の中で、もしかして僕の聞き違いかもしれないのですけれども、土地の、あるいは本社ビルのようなものを持っていて、そのバリュー・イン・ユースといいますか、現在価値、それが十分公正価値を上回る、つまりのれんが十分にあるということに疑いを持たれるケースが存在するとおっしゃいましたか。
- ○秋葉委員
-
そうですね。
- ○斎藤委員
-
そういたしますと、その投資の主体がもし合理的であれば、当然、現在価値が時価を下回れば時価で売却するわけですけれども、そういう合理的でない投資の主体までを考えなければいけないという御意見なのでしょうか。
- ○秋葉委員
-
整理すると、多分、そういうことになるのかもしれないのですけれども、そういうことがあるということを仮定すること自体が理屈としてはおかしいということもあるかもしれませんが、本当にそういうことはないのかなというのも一方で気にあるというところです。
- ○斎藤委員
-
それは、ここであまりそういう議論をしてもしようがないと思いますが、少なくともガバナンスの構造がしっかりしていれば、そういう経営者は株主によって首を切られるはずだと思いますけれども。
- ○辻山部会長
-
では、その件はまたこれからの議論の中でも出てくると思いますけれども。秋葉委員の御報告の3ページ目ですけれども、ただいまの質疑との関連で、ロのようなケースで、この秋葉委員の御報告の中では、割引前ベースでは回収できるということに問題提起が一応限定されておりますけれども、土地の時価が著しく下落していて、そして全社資産がある。グルーピングによって、全体で一つのグルーピングとされていた。そのキャッシュフロー全体が割引後であっても回収できるというふうにみなされていて、この本社ビルがその事業活動の中で十分に利用されている場合、この場合であっても、減損が認識されないということについて懸念を表明されたというのが、この2ページ目の御報告の趣旨というふうに解釈したのですけれども、そうであれば、減損に当たらないのではないかという解釈もできるのですけれども、この点はいかがなのでしょうか。
- ○秋葉委員
-
まさにそういうことで、割引前のベースで回収できない、できるということですけれども、多分、手順を追って考えると、こういうケースについて自分で十分に利用しているので、減損には当たらないということにはなろうかと思いますのですけれども。そのときに、多分ポイントとして、この認識の問題と関わるのですけれども、割引前のキャッシュフロー総額をバーにして、そこで減損するかどうかということを判定していくというのも、確率基準ということが一つの応用としては当然あるわけですが、そこのやり方をもう少し変えると、もしかすると減損を認識するということも、確率基準という考え方のもとで考え得るのではないかと。これは確率基準を採用したときの問題点といいますか、ポイントとしてアメリカでも挙げられているところかと思いますけれども。
それともう一つ、全社資産が機能していれば、各キャッシュ生成単位に貢献していますので、何らかの形で各キャッシュ生成単位に常に割り振る、すなわち、ボトムアップテストだけを行うということになれば、どこかのキャッシュ生成単位で調子が悪くなれば、半自動的に減損というものが考えられていくわけですけれども、常に全社レベルで考えますと、結局会社がだめにならない限りは減損は生じないということになりますので、そこら辺がそうでよいのかなというのが客観的にあるということでございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
ほかにどなたか。品川委員。
- ○品川委員
-
若干、言葉尻みたいなところで恐縮ですが、2ページと3ページにそれぞれ、2ページは「時価が極めて著しく下落」、3ページは「極めて」という用語を使わなくて、「時価が著しく下落」というふうに使い分けているのですけれども、これは何か数値的な差額を意識して使い分けているのでしょうか。
- ○秋葉委員
-
すみません。3ページ目の方は以前に用いた資料から直接持ってきたところなので、あわせるために直すのがちょっと心苦しいので、そのまま持ってきているだけで、他意はございません。どちらかというと、「極めて著しく」というイメージでございます。
- ○品川委員
-
数字的には何か具体的な、50とか70とか、そういうイメージがあるのですか。
- ○秋葉委員
-
あえて申し上げれば、多分、著しく下落といいますのは、従来からの強制評価減等で用いているような、ニュアンスとして50%となるのかなという気もしますが、そういう意味で極めて著しくというのはもっと、2割とか3割とかになるかもしれませんが、1割でも結構なのですが、とにかくそのぐらいに下がっているときに、いかがでしょうかというのがここでの私の前提にはたしかなっているかと思います。
- ○辻山部会長
-
よろしいでしょうか。
- ○品川委員
-
はい。ありがとうございました。
- ○辻山部会長
-
そのほか、ございますでしょうか。どうぞ、太田委員。
- ○太田委員
-
すみません。全社資産ですとか、共用資産についての取り扱いで基本的なところなのですか、前回、私は主にはアメリカの基準によった場合の、各社どうしているかというようなお話をいろいろな方から聞いたのですが、その場合に、少なくてもアメリカ基準を実際に適用するときには、明らかに物理的に一つの資産を判定するときに配分するというような発想は、あまりお持ちでなかったような印象を持っております。逆にこちらの国際会計基準の中では、かなり具体的な配分の方法とかの例があって、配分するというようなことが前提になっているように思うのですけれども、その辺は考え方として、配分を原則としてやっていく方向がいいのか、あるいはやはり何となく、何か例えば一つの機械がたまたまその後の工程によって2種類、3種類の製品になっているから、機械のうちの3分の1が減損していて、残りの3分の2は減損していないという結論は、何となくちょっと、いろんな要素を除いた後で変かなという気もいたしますので、その辺を詰めた方がいいのかなという気がしております。
- ○辻山部会長
-
ただいまの太田委員の御発言は、このボトムアップテスト、トップダウンテスト、どちらかといえばトップダウンテストに近いようなイメージでお考えになっているという御意見として承ってよろしいのでしょうか。
- ○太田委員
-
というよりも、どちらの方の考え方をとっていくべきなのかということを議論した方がいいのじゃないかと思いますけれども。
- ○辻山部会長
-
この場が議論の場なので、もし御意見があれば、どうぞお出しいただきたいと思います。
- ○太田委員
-
どらかというと、一つの資産を、ある意味で明確に分けられるケースというのもあるとは思うのですけれども、分けられないケースにまで配分してしまうというのは、ちょっとどうなのかなというふうに私は個人的には思います。
- ○辻山部会長
-
わかりました。では、御意見として。
- ○秋葉委員
-
確かにそういう考え方があると思いますが、同じことで恐縮なのですけれども、2ページ目の5で触れましたように、どうも私が念頭に置いているのは全社資産の中でも本社ビルといったような不動産、特に土地の割合が高いというものを暗黙のうちに想定しているふうがあるのですけれども、そういう形でもしここにありますようにトップダウンテストで、本社ビルを会社全体のグルーピングに含めるということになると、特に日本の場合には不動産は土地の割合が高いですから、償却もしません、それから、会社全体で判定をします、そうすると、会社がいい状態のときには減損はしないわけで、会社がもうだめになりそうなときに初めて減損するという形で、初めてどんと土地に関する減損損失が生じるということに結果的になるのじゃないか。そのような形の処理になることで、いいのかどうか。
それから、もうちょっと具体的に言えば、この減損の基準が、まず1期目に導入されたときに、まずそこで減損がでなければ、恐らく翌年に出るとか、その翌々年に出るということは余り考えられなくて、ほぼ1発勝負になると思うのです、まず初年度の適用の仕方がですね。その初年度の適用の仕方はもちろんいろんな経過措置等の考え方も最終的にはあろうかと思いますけれども、その1発目の適用のときに、このタイプの本社ビルのものは、割引前キャッシュフローの総額での減損認識、それからトップダウンテストの採用ということになると、減損損失が出てこないということが考えられまして、恐らくそうなってくると、会社がだめになるまで出てこないということになりますから、果たしてその減損の基準としてどうなのかというのが、ちょっと心配といいますか、懸念しているところでございます。
- ○辻山部会長
-
ほかに御発言は。では。
- ○斎藤委員
-
先ほど私が、その場合は減損に相当するのだろうかというふうに申し上げましたのは、全社資産を配分するということを前提として議論したときに、その文脈の中で減損に該当するかどうかということを申し上げたわけなのですが、今の秋葉委員と太田委員のやりとりを承っていますと、感覚としてはむしろそれは全社資産としての配分を行う範囲をどう考えたいいのかという問題の方が重要であって、秋葉委員の御心配をもし解消しようとすれば、本社ビルのような資産について配分といいますか、全社資産として扱わないという、そういうルールを考える方が手っとり早いという感じはいたしますし、その方が多分、太田委員の今の御発言の実感にも合うのじゃないかという感じがいたします。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございます。
では、小宮山委員。
- ○小宮山委員
-
多分、同じ趣旨になるのかもしれないのですけれども、共用資産と言っているのと全社資産をどう定義しているかが、人によって大分違っている感じなのです。例えば本社ビルにABCDというふうに4つ事業部が入って、Aという事業部をやめましょうと。それかわり、Eという事業部をつくって入れましょうと。それはキャッシュフローを生み出すのです。だから、そういうのをここで考えているキャッシュ生成単位と言うのかどうかという話なのかなという気がするのです。IASが全社資産とのれんの減損というのを同じふうな基準でやっていますけれども、それに従う必要があるのだろうか。私はのれんというのは、ある資産グループに直接のキャッシュフローを生み出しているだろうと思う。本社資産というのは、貢献していないとは言わないけど、生み出していないだろうと。別の基準でもいいのじゃないかと考えているわけですが、ちょっとその辺の定義を少し明確にしたところで話さないと、何か違うものを話ししているのかなという気がするのです。そうすると、全社資産だけ抜き出して、貢献していることは確かだけれども、それ自体、時価が下落している以上、減損の対象も個別にするという考え方もターミナルバリューで評価するというと出てくるわけで、そういうふうに考える方が考えやすいのかなと思っているのですけれども。
- ○辻山部会長
-
そのほか。どうぞ。
- ○秋葉委員
-
今の二人の先生方のコメントを踏まえれば、私もそういう方法が一つあるのかなということで、先ほど斎藤先生がおっしゃいましたように、全社資産といえどもボトムアップテスト、これを原則的なことにして、ないしはこれのみにして、そういうふうに各キャッシュ生成単位に割り振ると。そうすると、土地の非償却性資産が各キャッシュ生成単位等に割り振られることによって、減損のところが出てくれは、半自動的に損が出るということは保たれるかなとは思っております。
それからもう一つの考え方としましては、この2ページ目の上の方の(2)に示させていただきましたように、今、小宮山委員の方からお話がありましたように、ちょっと違う基準で考えていくということもあり得るかなというふうに思っております。ただ、この辺を考える際には全体的な減損の認識とか測定の話、特に認識の問題、そこのところともかかわってくるので、若干この2ページ目のところで立ち入ったような御説明をさせていただいたというふうな経緯でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
そのほか、この機会に御発言、ございますでしょうか。
- ○太田委員
-
今の全社資産の、多分主には土地ではないかと思うのですけれども、それの評価について、減損会計の枠組みの中で考えますと、どうしても投資とその回収ということの枠組みで考えざるを得ないのではないかと思いますので、ここ10年ぐらいの土地の時価の下落というのは非常に異常な事態であると思いますので、全く減損の枠組みとはまた別に、そういうことを手当するという考え方もあり得るのではないかなというふうに思いますが。
- ○辻山部会長
-
それは、ちょっとこの減損会計の枠組みとはずれてまいりますし、異常事態だからといって、会計上、過去に事業資産について大幅な下落を契機として時価との差額を切り下げたということは、ちょっとございませんので、それはまた当部会、当審議会の議論からもかなり外れていくような、注記ということは考慮の範囲かもしれませんけれども、ちょっとまた別の議論ではないか。ただ、御意見は参考にさせていただきたいと思いますけれども。
そのほか、ございますでしょうか。
- ○逆瀬委員
-
小宮山先生にちょっとお伺いしたいのですけれども、御説明の中でキャッシュ生成単位というのが一つのきょうの議論の大きなテーマですけれども、一般的にキャッシュ生成単位というのは、例えば連結がメインだということで、連結で考えるといったときに、大体、先生の感覚ではどれぐらいにブレークするればいいのか。幾らでも細かくできるし、幾らでも粗くできるというわけですけれども、実務のことを考えるときに、議論されているわけですが、大体どれぐらいなのかなという、これは感覚的なあれで結構なのですけれども。
- ○小宮山委員
-
少なくともセグメントの分け方より細かいということは確かでしょうね。セグメントの考え方と非常によく似た議論になっちゃうのですけれども、セグメントで考えているのは、事業リスクの類似ですよね。これは資産の利用の仕方の類似ですよね。だから、それより細かいだろうということは明らかにわかるのですが、具体的にちょっと申し上げられないですね。
- ○逆瀬委員
-
もう1点、よろしいですか。
秋葉先生に教えていただきたいのですが、この資料の3枚目で、最後の論点、3でケースが4つに分けられておりまして、個別と連結とで泣き別れになるようなケースがあると。これはもう重大な議論なのですけれども、減損を考えるときに、連結で考えるのか、個別で考えるのか、これも議論の大前提だと思いますが、この辺についての、ここははっきりした御意見はなかったのですが、どうすべきだと。我々としては同じであるべきだと思うわけですが、この辺についてのお考えを、よろしければ御開陳いただきたいと思います。
- ○秋葉委員
-
まさにここも難しい問題なのですけれども、だからゆえに、さらっと終わってしまったというのもあるのですが、単純に言えば、3ページのようにケースは多分4つあって、逆瀬さんもお話のようにケース1、ケース4は問題がないと思います。ですから、ケース2、ケース3が実務的には問題になると思うのですが、連結財務諸表で考えれば、連結ベースで考えるということも一つの割り切りかと思うのですが、そうすると、商法上どうするかという場合とか、それからこれは単純に、先ほど申し上げましたが、親会社の個別財務諸表、それから親会社の連結財務諸表のほかに、子会社のそれぞれの個別の財務諸表もございますので、そこでどうするかというのもございまして、現状のやり方を延長すれば、個別も連結もそれぞれ考えなきゃいけないという話になってしまうので、それはちょっと確かに大変かなというのは私も印象としております。ですから、一つの割り切りとしては、連結だけでやるということもあるのかなと思いますが、そうすると、この個別財務諸表の位置づけとも絡むわけですが、特に商法上も含めてどういう扱いにするかということが問題としては挙がるのじゃないかと思います。
- ○辻山部会長
-
よろしいでしょうか。
今、秋葉委員、個別がむしろ子会社の方のというふうな御発言でしたけれども、逆瀬委員のお話は、個別といっても親会社の個別と連結の問題、そこが……
- ○逆瀬委員
-
一番問題になるのは、そこが一つだと思います。
- ○辻山部会長
-
で、その点については、ちょっと宿題にさせていただきたい。
- ○斎藤委員
-
小宮山委員のお話で、どさくさ紛れに全部一部会に押しつけられるのは、ちょっと困るので(笑)、確認だけさせていただきたいのですが、先ほどの3ページから4ページにかけての論点のうち、(1)は確かにこれは企業結合の議論との関係をよく考えて、恐らく並行して話を詰めていかないと、きちんとした議論にならないなという感じがいたします。
(2)は、これはどうなのでしょうか。ちょっと私が誤解しているのかもしれませんけれども、これは何も合併、結合のケースだけでなくて、例えば自分が買った資産を別の用途に使って、それによってキャッシュフローを改善しているというときもこれは出てくる問題であって、減損の局面だけですから、それを切り下げる簿価の範囲をどこまでにするかという問題で、基本的には取得価額の範囲内で、そのケースで自己創設のれんが出ることは、多分ないのではないかというのが私の印象です。
それから(3)は、これは取得後の問題でありますので、基本的にやはりこの部会の守備範囲ではないかなという感じがいたします。
(4)はちょっとデリケートなので、よくわかりませんが、どの問題もこれは両方の部会の話がきちんと辻褄があっていなければいけないことは自明でありますけれども、主な担当部会は、(3)についてはこの部会でよろしいのではないかと思います。(1)だけがちょっと心配かなという感じがしております。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それでは、時間になりましたので、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。
本日は、五十嵐参考人、三橋参考人、大塚参考人にはお忙しいところを御報告いただきまして、どうもありがとうございました。
なお、次回の当部会の日程でございますけれども、1月26日(金)午後3時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。次回は固定資産の減損会計のうち、対象資産の問題、減損の兆候の問題などについて、ヒアリング及び意見交換を予定しております。正式には、改めて事務局より皆様に御案内をさせていただきたいと思います。
本日は、皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。これにて散会とさせていただきます。