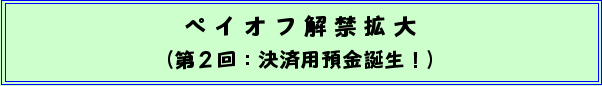 |
|
1 |
はじめに 2004年11月24日、フィリピンのマニラにて、本稿を書き始めています。本日午後、日・フィリピン経済連携協定(Japan Philippine Economic Partnership Agreement)の「大筋合意」に向けての事務レベルでの交渉が終了しました。2日半にわたり、会場の投資委員会のオフィス6階で、半ば缶詰め状態になって大詰めの交渉が行われたのです。今回の会議を含め、本会合・非公式会合を合わせて計8回に及ぶ会議の積み重ねを経て、ここまでたどりつきました。 今回の交渉は、あくまでも主要点に関する「大筋合意」に向けてのもので、29日の首脳レベルでの合意の後、協定の条文交渉等の作業が本格化します。最終的に署名されるまで、まだしばらく時間がかかるでしょう。したがって、交渉結果については、後の機会に譲りたいと思います。 ところで、金融庁が経済連携協定のための交渉に参加していることは、あまり知られていないのではないでしょうか。そもそも、経済連携協定は、二国間において、関税の引下げなどモノの貿易の自由化のほかに、サービス、資本、人の自由な移動の促進、さらには人材育成をはじめとする様々な協力の推進を目指すもので、経済関係全体について、包括的な連携を強化しようという取組みです。我が国は、これまで、シンガポール(2002年1月署名)、メキシコ(2004年9月署名)との間で経済連携協定を締結し、現在、フィリピンのほか、タイ、マレーシア、韓国との間で交渉を行っています。 金融庁は、これらの交渉において、「サービス分野」の中の金融サービスの自由化を目指すとともに、金融監督当局との間での協力関係の促進を図るべく、積極的に参画してきています。以下、金融サービスの自由化と金融面での協力のそれぞれについて、もう少し詳しく御説明しましょう。なお、文中意見にわたる部分は、筆者の個人的な見解です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
金融サービスの自由化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
金融分野での協力 ここまで、金融サービスの自由化交渉について詳しく述べてきました。確かに、金融市場の自由化は重要です。しかし、もっと重要なことは、交渉を通じて相手国の監督当局との関係を築くことができるという点です。アジア諸国では、財務省や中央銀行が金融機関の監督権限を有しているケースが多いようです。金融庁は発足後6年あまりしかたっていない若い組織です。経済連携協定交渉を機会として、これまであまりお付き合いのなかった相手国の財務省や中央銀行との間で、対話のチャネルが着々と築かれています。 他国の監督当局との関係を強化することは、相互に進出している金融機関の監督を適切かつ効率的に行う上で不可欠の前提といえましょう。また、相手国の当局の方で、監督体制や監督能力の向上のために、我が国の経験やノウハウを知りたいというニーズがあるかもしれません。このように監督当局間で様々な協力を行っていく際に強固な基盤となるのが、経済連携協定の「金融サービスに関する協力」の章です。 例えば、日・シンガポール経済連携協定の「金融サービスに関する協力」の章においては、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を目的として、金融サービスの分野において協力することがうたわれています。 規制監督に関する協力の具体的な成果として、証券市場に関する情報交換のための枠組みが整備されました。両国の証券市場における規制・監視を効果的に行う上で、有効に活用されています。さらに、協定成立後も、両国間の協力上の諸問題について協議を継続することができるよう、フォローアップのための委員会が設置されています。 もちろん、このような「協力章」が協定の中に設けられていなかったとしても、監督当局として海外の当局と連携を強化するよう努力すべきことは当然であり、「協力章」がなければ協力できないというものではありません。しかし、協力関係を円滑に進めるためには、二国間の条約において「協力章」が設けられることが望ましいのは言うまでもありません。その意味で、どのような「金融サービスに関する協力」の章を設けるのかについて、相手国の当局と交渉すること自体、関係強化のための一つの重要なステップとなるでしよう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
おわりに 我が国の金融機関のアジア諸国への進出は、今後一層活発化することが予想されます。その中で、経済連携協定は、進出のための環境の整備に資するとともに、両国の当局の間で監督上の協力を強化するための基盤を提供するものであり、非常に意義のあるものと考えられます。今後とも、交渉に積極的に参画していく必要があると考えています。 |
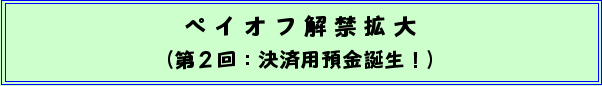 |
今回は、預金保険制度で保護される預金の種類について、決済用預金を中心に説明しましょう。 |
|||||||||||
1 |
.決済用預金誕生物語!? 前月号で、『利息が付かないこと(無利息)、いつでも払い戻し請求できるもの(要求払い)、振込みなどの決済サービスに使うことができる』という要件(これからは、「3要件」といいます。皆さん覚えてくださいね!)を満たす決済用預金は17年度以降に金融機関が破綻した場合でも、引き続き、預金全額が保護されると説明しました。 なぜ、決済用預金を全額保護するのかと疑問をもたれる方が、いるかもしれませんね。これは、我が国で行われる資金決済の手段が、米国に代表されるような小切手の授受による方法よりも、口座振替えや口座振込みなど直接預金口座を利用することが多いという事情にあります。小切手による支払いと比べると、口座振込みは、破綻の翌日に履行される振込みの指示(「指図」といいます。)を破綻時に取り消すことができず、例えば、公共料金が預金から引き落とされてから支払い先の企業の口座に振り込まれるまでの間(これを「仕掛り中」といいます。)に、その金融機関が破綻すると決済そのものができなくなる可能性があるのです。 また、日常生活から考えれば、決済資金は振込み日の何日か前に入金されていますよね。その間に金融機関が破綻した場合も、せっかく支払い用に預金しておいたものが名寄せ(注1参照)されるまで、しかも1千万円以内の金額でしか払い出すことはできないのです。 こうした我が国の特有の決済慣習をふまえ、金融機関が破綻した場合であっても一般の事業者や個人等が行う預金口座を通じた決済を確実に完結させるためには、全額保護される決済用預金の創設が必要だったのです。 |
||||||||||
|
|||||||||||
2 |
.決済用預金と決済性預金があると聞いたけど・・・ よく「決済性預金と決済用預金はどう違うの?」という質問を頂きます。今までの預金保険制度では、当座預金・普通預金・別段預金を総称して「決済性預金」と呼んでいました(図参照)。法律上は「特定預金」とされていたのですが、この3種類とも資金決済に利用することができることから、「決済性預金」としたほうがご理解いただきやすいということでこう呼んでいたのです。17年3月までは、この決済性預金(特定預金)を決済用預金とみなして全額保護しています。 |
||||||||||
(図) |
|||||||||||
|
|||||||||||
| ※ 3要件とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」のこと。 | |||||||||||
3 |
.決済用預金は、どこで開設できるの? 決済用預金を提供することは、金融機関の義務ではありません。各金融機関が決済用預金に対する預金者のニーズを判断して提供するものです。 また、3要件を満たす預金であれば、どんな名称であっても決済用預金として全額保護されるので、預金者の皆さんはどの預金が決済用預金に該当するかを各金融機関の窓口で確認していただく必要があります。 金融庁が、各金融機関に当座預金以外で決済用預金を提供又は提供に向けた準備・検討の状況をヒアリングしたところ、11月で約25%の金融機関が決済用預金を既に提供し、約70%の金融機関が提供に向けた準備・検討をしていると回答がありました。このヒアリングは当分の間実施し、結果を金融庁のホームページで「報道発表など」欄に掲載します。 |
||||||||||
|
|||||||||||
4 |
.「名寄せ」って協力義務があるの? 先程、「名寄せ」について説明しましたね(1.の(注1))。テレビや新聞でも、「ペイオフ本格実施に向けて、金融機関が名寄せ作業を行っている。」という報道がされているのを見聞きした方もおられるのではないでしょうか? 実は、「名寄せ」を行うのは預金保険機構(注2)という組織なのです。各金融機関は、預金保険機構が行う「名寄せ」に必要な預金者ごとのデータを整備しているのです。 各金融機関は、預金保険機構からの指示に従い、預金者の皆さんの氏名、生年月日、住所や電話番号等についてダイレクトメールを送付するなどして確認しているのですが、中には、数十万円から数百万円の残高があるのに、預金者と連絡がつかないものもあるそうです。預金口座を開設したときは正しい氏名、住所、電話番号であっても、その後、改姓したり転居したりした方は特に気をつけてください。 もし、破綻した金融機関において、預金者データが整備されていないとどうなるのでしょう? 預金保険機構は預金の払戻しをするときに、必ず、本人確認の手続を行います。その際、破綻金融機関に届けていた住所、氏名、生年月日、電話番号などが、預金の払戻請求の書類に記載されたものと異なる場合は払戻しはされません。転居の事実がすぐに証明できればいいのですが、何も証拠がな い場合は最終的に裁判にもつれこむ可能性さえあるのです。 「名寄せ」のためのデータ整備は、金融機関の破綻処理を迅速、円滑に行うために必要な作業なので、金融庁や預金保険機構の検査官がその精度をチェックしていますが、預金者の方の皆さんの協力がなければ完全な整備は不可能です。もし、結婚や転居などで氏名、住所、電話番号等が変わった場合は、速やかにその金融機関に届け出るようお願いします。住所や名義変更の手続を忘れただけで、預金払戻しのために裁判をするなんて面倒ですよね・・・。 こうした「名寄せ」についてご質問のある方は、預金保険機構までお問い合わせください。 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| (今月はここまで。来月号は決済用預金PARTIIとして、決済用預金の3要件を徹底解剖します。こうご期待!) | |||||||||||
|
このコーナーでは、先に閉会した第161回国会で成立した金融庁関連の法律について、その経緯や内容を詳細に説明します。本号は、「違法年金担保融資対策法(貸金業規正法の一部改正法)」についてです。 |
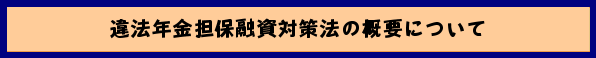 |
1 |
.違法年金担保融資対策法成立の背景 年金や生活保護給付、障害者給付など、受給者の生活上不可欠な公的給付については、生活に困窮した受給者が、その受給権を譲渡、担保等に供してしまうと、その生計の維持に支障をきたすおそれが大きく、公的給付の趣旨に反することから、国民年金法、厚生年金保険法等の各公的給付に関する根拠法令において、その譲渡や担保提供等の行為が禁止されています。 しかしながら、近年、貸金業を営む者が公的給付を受けている者の困窮に乗じて、当該債務者から、年金等の振込口座の預貯金通帳やキャッシュカード等を提出させて預かり、預貯金口座に振り込まれた公的給付を貸付債権の弁済に充てる等の不正行為が行われ、社会問題化しています。 こうした状況を受け、公的給付の受給者である債務者の保護、及び貸金業の適正な遂行の確保を図るために必要な措置を講じるべく、今般、議員提案により「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。いわゆる違法年金担保融資対策法。)」が提出され、平成16年12月1日に国会で成立し、同年12月8日に公布されました(平成16年法律第158号)。 |
||||||
2 |
.違法年金担保融資対策法の内容 |
||||||
|
|||||||
3 |
.おわりに この改正法は、違法年金担保融資への対策強化に大きく資するものと考えており、今後は改正法に基づき、関係当局の体制及び連携の強化・充実を図るなど、違法年金担保融資業者の排除に向けた取組みを一層強化します。また、改正法の広報・啓発活動の充実等にも取り組んでまいりたいと考えています。 |
||||||
※ |
「改正法」や苦情相談窓口等の連絡先について、詳しくは金融庁ホームページの「違法年金担保融資対策法が成立しました」、「違法な金融業者にご注意」にアクセスしてください。 |