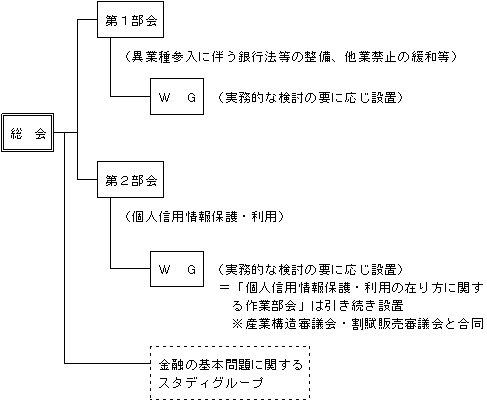
1 |
.金融庁における金融審議会の開催 |
||||||||
|
|||||||||
2 |
.審議事項及び今後の審議の進め方 今般の金融審議会については、8月4日の総会において、今後の運営方針として、審議事項及び今後の審議の進め方について以下のように了承された。 |
||||||||
|
| 金 融 審 議 会 委 員 名 簿 | ||
平成12年9月現在 |
||
| 会 長 | 貝 塚 啓 明 | 中央大学法学部教授 |
| 会長代理 | 蝋 山 昌 一 | 高岡短期大学長 |
| 委 員 | 井 上 定 彦 | 連合総合生活開発研究所理事・ 島根県立大学総合政策学部教授 |
| 江 頭 憲治郎 | 東京大学法学部教授 | |
| 大 塚 宗 春 | 早稲田大学商学部教授 | |
| 翁 百 合 | 日本総合研究所主席研究員 | |
| 神 田 秀 樹 | 東京大学法学部教授 | |
| 倉 澤 康一郎 | 武蔵工業大学環境情報学部教授 | |
| 杉 田 亮 毅 | 日本経済新聞社副社長 | |
| 高 橋 伸 子 | 生活経済ジャーナリスト | |
| 田 島 優 子 | さわやか法律事務所弁護士 | |
| 田 中 直 毅 | 21世紀政策研究所理事長 | |
| 原 早 苗 | (財)消費科学センター事務局長・ 消費科学連合会企画委員 |
|
| 福 間 年 勝 | 三井物産(株)取締役副社長 | |
| 堀 内 昭 義 | 東京大学経済学部教授 | |
| 八 木 良 樹 | (株)日立製作所代表取締役副社長 | |
| 吉 野 直 行 | 慶應義塾大学経済学部教授 | |
| 〔計17名〕 | ||
| オブザーバー | 増 渕 稔 | 日本銀行理事 |
| 森 昭 治 | 金融再生委員会事務局長 | |
| (敬称略・五十音順) | ||
金融審議会の部会等の構成イメージ
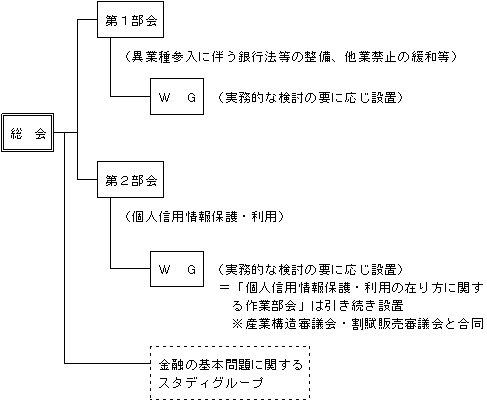
1 |
.はじめに 金融庁は、本年7月1日に金融監督庁を改組して設置された。金融庁は制度の企画立案から検査・監督・監視までを一貫して担当するとともに、銀行、保険、証券等の業態を横断的に所管することから、これらの特色を最大限に活かし、金融を取り巻く環境の変化に的確に対応して、機動的かつ整合的な政策の遂行に努めている。 金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、金融業務の高度化、国際化等の急速な進展を踏まえ、高い専門能力を保持するとともに、国際的な整合性の確保を図りつつ、預金者、保険契約者、投資者等の利便性の向上と保護に努めることが重要であると考えている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.機構定員要求の内容 金融庁では、上記のような考え方に基づき、平成13年度機構定員要求において、情報通信技術(IT)の急速な進展、金融システム改革、ペイオフ解禁等を踏まえつつ、検査・監督・監視体制の整備を行うとともに、金融行政の専門性、先見性向上のための体制整備等のため、205人の増員を図ることとしている。具体的な要求内容は以下のとおりである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
.予算要求の内容 上記の機構定員要求に伴う経費のほか、機動的な検査の実施、検査監督手法の改善、海外当局との連携強化等を図るための経費を折り込んで、平成13年度予算要求において、総額125億円の要求を行うこととしている。 また、「日本新生特別枠(非公共)」において、総額21億円を要望している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金融庁の組織(13年度要求後の姿) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
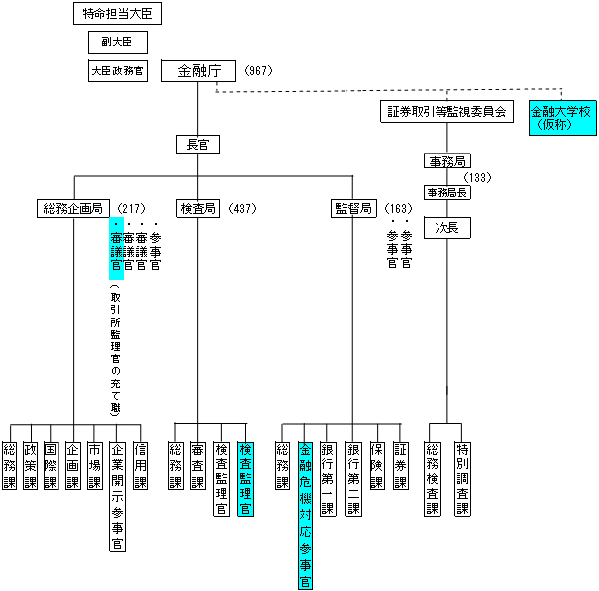 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年度金融庁概算要求の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 |
.上記のほか、「日本新生特別枠」(非公共)で2,128百万円を要望。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.各々の計数を百万円未満で四捨五入したため、計数が符合しない場合がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「日本新生特別枠」(非公共)の要望 |
||
1 |
.有価証券報告書等の開示書類の電子化「IT革命の推進」 |
1,153百万円 |
| 有価証券報告書等の開示書類を電子化し、書類の提出、縦覧等をインターネットを通じて行うシステムの構築。 | ||
2 |
.国際会計基準事務委託「経済の新生に特に資する施策」 |
243百万円 |
| 国際会計基準委員会における設定、改訂等に対し、我が国の意見・立場を積極的に発信するための調査分析、広報事務等を要件を満たす民間法人に委託する事業。 | ||
3 |
.財務局ネットワークシステム等の構築「IT革命の推進」 |
312百万円 |
| 金融庁と地方財務局とを専用線でネットワークし、検査監督等各種システムを相互に利用するシステムの構築。併せて、テレビ会議システムの導入を図る。 | ||
4 |
.申請・届出等手続の電子化及び総合文書管理システムの構築「IT革命の推進」 |
197百万円 |
| 金融庁に対する各種の申請・届出等の手続をインターネットを通じて行い、提出された文書等の決裁・通知・保存・廃棄までの文書のライフサイクルを電子的に管理するシステムの構築。 | ||
5 |
.インターネット証券情報分析システムの構築「IT革命の推進」 |
86百万円 |
| インターネット上において、証券市場の変動を意識した悪質な情報を流しているサイトを常時検索・抽出するシステムの構築。 | ||
6 |
.証券取引等に関する情報管理システムの構築「IT革命の推進」 |
85百万円 |
| 一般から寄せられる各種の証券取引情報を迅速に処理するため、受付から担当係への回付を自動的に行い、事案の顛末結果をデータベースとして保存、活用するシステムの構築。 | ||
7 |
.ネットワークを利用した研修システムの構築「IT革命の推進」 |
51百万円 |
| 検査監督に係る必要な知識を職員の机上のパソコンを利用し、研修を行えるシステムの構築。 | ||
| 合 計 2,128百万円 |
||
1 |
.株式等譲渡益課税に係る税制措置 (所得税・個人住民税) |
||||||||
|
|||||||||
株式等の譲渡所得等の課税については、平成11年度税制改正において、平成11年3月末をもって有価証券取引税等を廃止するとともに、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度については、平成13年3月末までの経過措置とされたところであるが、我が国経済における株式市場の重要性の高まり、各種金融商品に係る課税の中立性の確保、申告分離課税への一本化が株式市場に与える影響等に鑑み、源泉分離選択課税制度を維持する。 更に、源泉分離選択課税制度を維持した上で、株式市場の活性化や課税の中立性確保のため、どのような制度の改善がありうるかについては、欧米諸国における関連税制も参考としつつ、株式取引の実態を踏まえ、検討する。 |
|||||||||
2 |
.企業組織再編に係る税制措置 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
3 |
.市場基盤の整備等に資する税制措置 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
4 |
.法人事業税の見直し (法人事業税) |
||||||||
|
|||||||||
東京都等で導入された外形標準課税については、閣議において、種々の問題を孕むものと認識されており、本年7月に公表された税制調査会中期答申においても、税率設定については自由度を有する仕組みとしつつ、課税標準については全国共通のものとすることが適当であるとされていることから、特定の銀行だけを狙い撃ちで課税する根拠となっている地方税法第72条の19(法人事業税の課税標準の特例)の廃止を求める。 なお、上記の是正が直ちに困難な場合には、公平・中立等の租税原則や他の政策目的との整合性等が確保されるよう、同条の規定の実施については、現行地方税法に規定されている法定外普通税及び法定外目的税と平仄を合わせて事前協議制を導入する等の是正を求める。 |
|||||||||
5 |
.金融商品に係る税制措置 |
||||||||
|
|||||||||
|
現行の株式等譲渡益課税制度の仕組み |
|
| 資料1 |
|
|
|
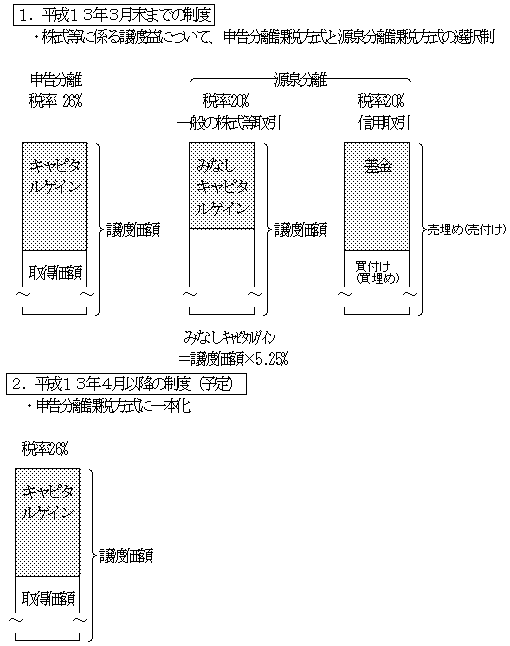 |
資料2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融商品への課税制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 |
.指針策定の背景 最近、事業会社等の異業種による銀行業への参入の動きや、店舗網を持たずインターネット上でのみサービスの提供を行う業務形態等、従来の伝統的な銀行業にはない新たな形態の銀行を設立する動きが見受けられる。 このような動きは、金融技術の革新、競争の促進等を通じて、我が国金融の活性化や利用者利便の向上等に寄与する可能性があり評価し得るものであるが、反面、資本形態、業務形態、店舗形態の面において従来にない新たな動きであることから、銀行法上要請されている銀行業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から、免許審査・監督上適切な対応が必要となる。 よって、金融再生委員会・金融庁は、去る8月3日、現行銀行法の運用上の指針として「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応(運用上の指針)」を、パブリックコメントも踏まえ策定・公表したところである。 本指針は、最近の新たな形態の銀行に対する対応について、5つの問題点に整理し、それぞれにつき免許審査及び免許後の監督における留意点を整理したものである(なお、監督上の対応は同様の形態を持つ既存銀行にも適用されることとなる。)。以下、この5つの問題点毎に、本指針のポイントを説明する。 |
||||||||||||||||||||||||||
I |
.子銀行の事業親会社等からの独立性の確保の観点 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
II |
.事業親会社等の事業リスクの遮断の観点 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
III |
.事業親会社等と総合的な事業展開を図る場合の顧客の個人情報の保護の観点 事業親会社等と子銀行の間では、両者のシナジー効果を図る観点から、特に、顧客情報を相互に活用することが予想されることから、これについての免許審査・監督上の留意点を定めたものである。 具体的には、顧客情報の相互利用を行う場合には、最低限、利用する業者の範囲、利用目的、利用方法等を明確にした上で、顧客本人の明示的な同意を得る等、子銀行において、顧客の個人情報の保護のための方策が十分講じられているかどうかについて、免許審査や免許後の報告徴求等により確認することとしている。 |
||||||||||||||||||||||||||
IV |
.資産構成等が国債等の有価証券に偏っている場合のリスク管理や収益性の観点 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
V |
.有人店舗を持たずインターネット・ATM等非対面取引を専門に行う場合の顧客保護等の観点 インターネット・ATM等非対面取引を専門に行う銀行は、基本的に有人店舗を持たないが、そのような店舗形態であっても、利用者保護等の観点から問題が生じないような体制を整備する必要がある。そのような観点から、 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 等の点について、無店舗営業であっても適切に対応し得るための態勢が整備されているかどうか、免許審査及び免許後の監督においてチェックすることとしている。 |
1 |
.はじめに 先般(7月28日)、「平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画」を公表した。この検査基本方針及び基本計画は、平成12検査事務年度(12年7月〜13年6月)における検査の実施方針や実施予定数を定めているものであり、昨事務年度から金融検査の透明性をより一層高めることを目的として、策定後直ちに公表しているところである。 以下、金融検査のこれまでの実施状況や体制整備の状況について簡単に紹介したうえで、本事務年度の検査基本方針及び基本計画のポイントについて、順次説明を加えていくこととしたい〔平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画(原文)は、ホームページの「報道発表等」及び「金融庁ニューズレター」のコーナーに掲載している〕。 |
||||||
2 |
.金融検査〜これまでの実績 |
||||||
<検査実施状況> |
|||||||
|
|||||||
<検査体制の整備について> 金融監督庁検査部は164名体制からの立ち上げであったが、金融検査の重要性が高まるなかで、ここ2年の間に155名の検査部職員が増員された。これにより、金融庁検査部は319名体制となり、検査を業種・業態毎に担当する部門制も16部門体制となり、専門的・効果的な検査の実現に向けての基盤が徐々に整備されつつあるものと考えている。 |
|||||||
3 |
.検査基本方針のポイント 検査基本方針のポイントは、第一に、早期是正措置や金融検査マニュアルの導入などを背景に、金融検査に対して、これまで以上にその質的水準の向上や手続きの透明性が求められていることを踏まえ、公正で信頼性の高い検査を実施することである。 第二に、平成14年4月に予定されているペイオフの解禁や、情報通信技術の発達等の金融環境の変化を踏まえ、効率的で実効性の高い検査を実施することである。 以下、検査基本方針よりポイントととなる箇所を抜粋し、解説を加えることとしたい。 |
「平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画」(抜粋) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(解説) |
||||||||||||||||
| ・ | 検査マニュアルを整備・公表することは、監督当局の検査監督機能の向上及び透明な行政の確立に資するだけでなく、金融機関の自己責任に基づく経営を促し、もって金融行政全体に対する信頼の確立につながるものと考えられる。こうした観点から、これまで平成11年7月には預金等受入金融機関に対する「金融検査マニュアル」、平成12年6月には「保険検査マニュアル」を発出したところであるが、本事務年度は、証券取引等監視委員会と協調し、「証券検査マニュアル」の整備に取り組むこととした。 こうした方針に基づき、先般(8月29日)、「証券検査マニュアル・ワーキンググループ」を設置し、検討を開始したところである。このワーキンググループは、証券業協会及び証券会社4社をはじめ、東京証券取引所、日本公認会計士協会等から実務家にオブザーバーとして参画を得て、当庁職員となっている商法学者や公認会計士を含む検査部、証券取引等監視委員会事務局、監督部及び総務企画部職員をメンバーとしている。 今後、オブザーバーの方々から証券業に係る最近の状況等についてヒアリングを実施するなど、できる限り早期に策定作業を進め、本事務年度中に「証券検査マニュアル」を策定することを予定している。 |
|||||||||||||||
・ |
検査の質的水準の向上や手続きの透明性の向上を図るためには、検査監理機能を充実させることが不可欠であり、これまでも研修の充実、指導・審査態勢の強化等に努めてきたところである。 こうした諸施策を補完するものとして、検査において検査官と被検査金融機関との間に意見相違が生じた場合に、立入検査終了後一定期間に限り、金融機関から本庁検査部長宛に意見申出ができる制度を、本年1月から「金融検査マニュアル」を適用した銀行等検査について試行的に導入したところである。 本事務年度においては、12年3月期決算を対象とする信用組合集中検査や信用金庫検査についても金融検査マニュアルが適用されることから、意見申出制度の対象となる検査が大幅に増加することとなる。また、保険会社検査についても、保険検査マニュアルが適用され、意見申出制度の対象となるところである。 こうした意見申出制度の本格的な実施を踏まえ、本年7月、当該事務処理を担う検査指導官が配置され、体制整備が図られているところである。 |
|||||||||||||||
・ |
デリバティブ取引や電子金融取引の拡大など、金融環境の急速な変化に的確に対応するため、検査体制の強化策のひとつの核として、民間から専門家の登用を図っているところである。これまでに常勤職員として公認会計士を採用するほか、金融実務経験者等の非常勤職員を選抜により常勤職員として採用している。本事務年度においても、専門性の高い深度ある検査の実施を目指し、民間専門家の積極的な登用を方針として掲げている。 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(解説) |
||||||||||||||||
| ・ | 検査の効率的な運営や被検査金融機関の負担の軽減を図る観点から、オフサイト・モニタリングを通じて得られた諸情報や検査結果等の整理・分析に努め、それらを踏まえ、検査頻度について弾力的に運用するとともに、検査内容についても、特定のリスクカテゴリーを重点的に検査するなど濃淡をつけた検査を実施することとしている。 こうした方針に基づき、例えば、主要行、地方銀行、第二地方銀行については、金融監督庁発足後、二巡目の検査になることを踏まえ、前回検査における指摘事項の改善状況について、重点的に確認しているところである。 また、本年4月に都道府県から検査監督事務の移管を受けた信用組合について、資産内容等の実態把握を速やかに行うため、平成13年3月末までに立入検査を一巡することを目途として、財務局を中心として集中検査を順次実施しているところである。 |
|||||||||||||||
| ・ | 平成10年12月に金融システム改革法が施行され、これにより連結自己資本比率規制や連結ベースでのディスクロージャーが導入されたところである。こうした流れを踏まえ、平成11検査事務年度に引き続き、金融グループ・コングロマリットの一体的な実態把握を方針として掲げているところである。 こうした方針に基づき、平成10検査事務年度においては、外国金融機関等2グループ、平成11検査事務年度においては、本邦金融機関等3グループ、外国金融機関等4グループに対してグループ検査を実施したところである。 本事務年度においても、既に、本邦金融機関等2グループ、外国金融機関等1グループに対して検査を実施しているところである。 |
|||||||||||||||
4 |
.検査基本計画のポイント 平成12検査事務年度の主な業態に対する検査実施予定数を定めた検査基本計画、及び10、11検査事務年度における検査基本計画と実績の対比は、別表のとおり。 本事務年度の検査実施予定数を昨事務年度の実績と比較すると、信用組合集中検査に重点的に検査要員を投入するため、信用組合の検査実施予定数が大幅に増加している一方、その結果、他業態は概ね減少しており、合計では若干の増加となっている。 なお、検査実施計画は、当初計画として設定しているものであり、金融機関等を取り巻く現下の厳しい経営環境下において適時の実態把握に的確に対応するため、弾力的な運用を行うこととしていることから、実施予定数は変動することがあり得る。 【別表】検査計画と実績の対比 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|||
| 3日(木) | ・ | 「新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応(運用上の指針)」発表 | |
| 4日(金) | ・ | 金融審議会総会開催 | |
| 11日(金) | ・ | 第一生命保険相互会社に対する行政処分 | |
| 21日(月) | ・ | 事務ガイドライン改正(災害時における金融に関する措置) | |
| 23日(水) | ・ | 「金融庁における行政委託型法人等の総点検の実施結果」発表 | |
| ・ | 事務ガイドライン改正(証券会社等…産業活力再生特別措置法関係) | ||
| 28日(月) | ・ | 「証券会社に係る検査マニュアルの整備に向けて」発表 | |
| ・ | 「金融機関における実効性ある内部監査・外部監査態勢の確立に向けて」発表 | ||
| ・ | 大正生命保険株式会社に対する業務の一部停止命令(長官談話及び検査結果) | ||
| 29日(火) | ・ | 大正生命保険株式会社に対する保険管理人による業務及び財産の管理命令等 | |
| 30日(水) | ・ | 「金融庁の平成13年度機構・定員及び予算要求について」発表 | |
| ・ | 「金融庁の平成13年度税制改正要望について」発表 | ||
| 31日(木) | ・ | 「預金取扱金融機関の自己資本比率告示の改正について」発表 | |