|
||||
| 1 2 3
4 |
. . .
. |
日 時: 平成11年7月12日(月) 9時33分〜11時51分 場 所: 法務省会議室 議 題: (1)フランスの証券決済に関する法制度 (2)今後の主な検討事項 議事内容 |
||
○ |
始めに、池田教授からフランスの証券決済に関する法制度について説明があり、質疑が行われた。 |
|||
○ |
次に、今後の研究会の主な検討事項(ペーパーレス化されたCPの商品性、ペーパーレス化されたCPの発行、流通、償還システムの評価基準等)について、メンバー及びオブザーバーから意見が述べられ、またそれらについて質疑が行われた。 |
|||
5 |
. |
メンバーからの主な意見等 |
||
○ |
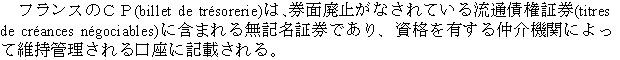 |
|||
○ |
米国のように顧客の所有証券と売買資金とを一括管理するカストディアンの仕組みが存在しない我が国では、DVPの実現において、金融機関相互での段階と、発行体や投資家での段階とを区別して考える必要がある。 |
|||
○ |
電子署名あるいは電子認証を活用して新しい仕組みを作る場合、売掛債権の証券化や貿易決済の合理化にも応用できることが望ましい。 |
|||
○ |
CPに限らず、他の有価証券のペーパーレス化も念頭に置いて法制を考えるべきではないか。 |
|||
○ |
効率の面では他の証券を含めた統一的決済制度が望ましいが、CPの決済システムの早期実現のため、新たな決済システムの構築も検討する必要があろう。 |
|||
○ |
既存の証券決済制度とは一線を画す制度とする。ただし、新決済システムが使い勝手のよいものとなれば、他の証券の決済システムへの拡張を検討する。 |
|||
○ |
新しいCP決済システムを検討する場合、インターバンク市場としての性格が強い現状を前提にするのか、事業法人による直接金融の手段という本来のあり方を想定するのかで評価基準が異なってくる。 |
|||
○ |
具体的な立法化にあたっては、将来の技術革新を制約しないよう、法令で規定すべき事項と市場参加者の自主的なルール設定に委ねるべき事項との峻別に留意する必要があろう。 |
|||
○ |
2000年末の日銀システムのRTGS化と同時期の稼動が必要である。 |
|||
○ |
大切なのはどのようにCPのペーパーレス化を実現するかであり、日銀システムのRTGS化に多少遅れても許容範囲内である。 |
|||
○ |
発行・流通・償還システムは、運営コストを考慮し、極力軽いものにすべき。 |
|||
○ |
発行・流通・償還システムの運営母体としては市場参加者が自主的に運営する「CP協会」的なものを考える必要があるのではないか。 |
|||
○ |
電子署名あるいは電子認証を活用して新しい仕組みを作る場合、対抗要件を確保するため、通知又は登録を受けるセンター的なものが必要になるだろう。 |
|||
○ |
「手形」や「社債」であることによる既存のしがらみをすべて断ち切る意味においても、電子登録を効力要件とする「電子債権契約に基づき発生する特殊な債権」として法的に構成する方法がベストと思われる。 |
|||
○ |
電子登録を効力要件とすると電子債権契約の内容及び手続が厳重になり、社債契約と変わらなくなる。両者の合意の証拠だけで登録可能とし、また未登録でも効力くらいは認めることとしてはどうか。 |
|||
○ |
有価証券の移転の効力要件は引渡しであり、ペーパーレス化されたCPでも移転の効力要件は意思表示ではなく登録とした方が明快ではないか。 |
|||
○ |
「電子登録を効力要件とする電子債権契約に基づき発生する特殊な債権」と構成した場合、差押え等について一般の指名債権についてルールを排除し、特例のみに服させることが可能となる。 |
|||
|
||||