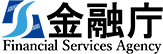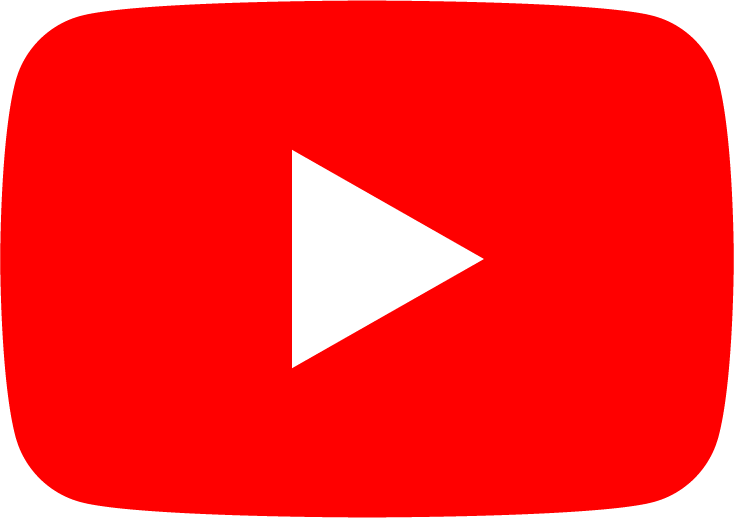平成13年10月25日
金融庁
企業会計審議会第13回第一部会議事録について
企業会計審議会第13回第一部会(平成13年10月5日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第13回第一部会議事録
日時:平成13年10月5日(金)午後2時00分~午後4時05分
場所:中央合同庁舎第4号館11階共用第一特別会議室
- ○斎藤部会長
-
それでは、定刻になりましたので、ただいまから第13回の第一部会を開催いたします。
委員の皆様には、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、わが国の企業結合の事例につきましてご報告をいただいた後、意見交換を行う予定でおりますけれども、事例のご報告をいただくために、株式会社みずほホールディングスより畠山参考人、小泉参考人、小杉参考人、米沢参考人にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。
また、本日は、IASBの企業結合会計の最近の審議状況について、山田委員からご報告いただく予定にしております。
それでは、まず山田委員から、IASBの最近の審議状況についてご報告をお願いいたします。
- ○山田委員
-
それでは、資料1に基づきましてご説明させていただきます。
資料1の1番目で2つの企業結合プロジェクトということで、IAS第22号の見直しの全体像について簡単に触れ、そのあとで、この9月に開かれました会議での最近の検討状況についてご説明するという二段でお話をさせていただきたいと思います。
最初に、「2つの企業結合プロジェクト」というタイトルで書いてある部分でございますが、プロジェクトを第1フェーズと第2フェーズの2つに分けております。
現在取り組んでいるのは第1フェーズでございますが、ここでは企業結合の定義を見直し、明確化しようということを考えております。
それから、2番目の企業結合に関する会計処理方法。現在IAS第22号では持分プーリング法とパーチェス法の両者が許容されておりますが、現在の審議状況ですと、プーリング法についてはこれを削除し、パーチェス法一本にする方向でほぼ議論が収束しそうな状況でございます。
3番目が、のれんの会計処理及びこれに関連する無形資産の会計処理ですが、これも、アメリカの会計基準が7月にできたことを受けまして、のれんについては現在償却を行わずに減損処理という形で対応するという方向で議論されております。のれんの処理と無形資産の会計処理が密接に絡むことから、あわせて無形資産の会計処理の見直しについても検討する予定になっております。
4番目としまして、被合併会社で仕掛中の研究開発費があった場合――これを企業結合で取得した場合に、それを資産計上すべきかどうか。資産計上する方向で検討しております。
 のリストラ引当金計上の是非は、被合併会社の事業を取得した後に、その一部を、例えばたたんでしまうという場合に、現在のIAS第22号では例外としてそのような引当の方式を認めているわけですが、それを今後も引き続き認めるべきかどうかについて――特にIAS第37号の引当金の基準との関連で、要はリストラ引当金は負債の要件を満たさないのではないかという議論がありまして――検討を進める予定にしております。
のリストラ引当金計上の是非は、被合併会社の事業を取得した後に、その一部を、例えばたたんでしまうという場合に、現在のIAS第22号では例外としてそのような引当の方式を認めているわけですが、それを今後も引き続き認めるべきかどうかについて――特にIAS第37号の引当金の基準との関連で、要はリストラ引当金は負債の要件を満たさないのではないかという議論がありまして――検討を進める予定にしております。 それから、
 の標準処理と認められる代替処理の削除の要否ですが、少数株主持分があるときに受け入れた資産を、部分時価評価法をするか全面時価評価法でやるか――現在両方認められているわけですが、これを一つにすべきではないかということを検討する予定にしております。
の標準処理と認められる代替処理の削除の要否ですが、少数株主持分があるときに受け入れた資産を、部分時価評価法をするか全面時価評価法でやるか――現在両方認められているわけですが、これを一つにすべきではないかということを検討する予定にしております。 それから、7番目の少数株主持分の取得の会計処理。少数株主持分を資本に入れるべきなのか、それとも負債にすべきなのかという議論も含めて、今後議論することになっています。スタッフの方からは、少数株主持分を資本の一部として計上するようにしてはどうか、それに伴って、
 の処理についても全面時価評価法的なものの方がいいのではないかというような提案がとりあえず来ております。このようなものについて議論を進めることを第1フェーズとして考えております。
の処理についても全面時価評価法的なものの方がいいのではないかというような提案がとりあえず来ております。このようなものについて議論を進めることを第1フェーズとして考えております。 第2フェーズとしましては、ジョイント・ベンチャーの会計処理。このジョイント・ベンチャーの定義をどうするかということですけれども、ベンチャラーと言われる人たちが例えば3者いるときに、その3者全員が合意しなければ意思決定できないような仕組みになっているものというような形で定義した上で、それらの会計処理についてフレッシュ・スタート法を中心に議論してはどうかという暫定的な方向性が示されております。
それから、共通支配下の企業結合についても、これは現在IAS第22号では扱っておりませんので、これも第2フェーズの中で議論してはどうか。
それから、パーチェス法の適用に関する問題。これは2社以上の相互会社が絡む企業結合について何らかの検討すべき点がないか少し議論しようと考えております。
以上が第1フェーズ、第2フェーズですが、第2フェーズについては、第1フェーズが終了した以降に行う。場合によっては、アメリカのFASBも同じようなテーマについて検討しようとしておりますので、場合によるとFASBとジョイントプロジェクトという形で進める可能性も残っております。
次に、大きな2番目の、9月に開催された会議の状況でございますけれども、次の議論が行われたということで、幾つかあるのですが、企業結合に関する公開草案公表までのスケジュールの検討。それから、日本における企業結合の例の紹介――取得者が特定できない企業結合の例を紹介しまして、それについての議論をしました。それから、IAS第22号の、目的、範囲、定義、それから企業結合の性格の部分について、公開草案の改定案が提示されまして、それについて議論しました。それから、のれんと仕掛中の研究開発費を除く無形資産の会計処理、仕掛中の研究開発費の会計処理、のれんの会計処理と、このような点について議論いたしました。
次の2ページでございますが、今後の議論は、FASBから出されました基準書第141号・第142号を軸にして、既にアメリカがプーリングとパーチェスと認めていたものをパーチェス一本にした、のれんについては減損処理ということで一本にした、これと余り大きく違わない形で議論を進めていこうという方向で議論が進むものと予想されます。したがいまして、プーリング法がこのまま残る可能性はかなり少なくなっております。また、のれんの処理についても、IAS第36号の減損の考え方と、第142号ないしは第121号の減損の処理とは少し考え方が違うのですが、これを何とか融合する形にしようという方向でございます。
次に、2番目の公開草案公表までのスケジュールでございますけれども、9月の会議では、結論の根拠も含む公開草案の完全なドラフトの検討を今年の11月に行う予定でございましたけれども、この9月で随分議論して問題点が出てきたこともありまして、この10月用に送られてきた資料の中では、この11月で検討しようとしていたものが来年の1月ぐらいにずれそうだという形で、スケジュールがおくれるという連絡が入っております。
10月については次のような項目――ここで5つ挙げてございますが、1番目は、先ほど申し上げたリストラ引当金の問題。それから2番目は、一たん認識した減損を振り戻しを認めるかどうかという問題。それから3番目として、負ののれんの会計処理。それから4番目としまして、被合併法人の資産・負債の受け入れに際して、部分時価評価法ないしは全面時価評価法のどのようなものにしたらよいか。それから、少数株主持分を負債または資本のいずれに計上するか――このような問題について議論する予定になっております。
11月には、さらに、購入対価として発行された株式の測定――株でもって購入したときの評価について議論しようということになっております。それから、支配の取得に関する問題の中で、個人のグループが正式契約に基づいて共同行動を行う。このような複数の個人が共同して幾つかの企業を支配下に置くような場合に、どのような状況のときに個人がそのような支配力を持つと考えるかといった問題について議論する予定になっています。それから3番目は、完全親会社を設立するタイプの企業結合において取得者をどう考えるか。完全親会社を取得したと考えますと、その下の子会社は全部時価評価だという処理になりますし、完全親会社は形だけだと考えて、被合併企業のどれか一つを取得者として、残りを被取得企業と考えるか。これによって随分会計処理が違いますし、オーストラリアとアメリカ等でこのあたりについては考え方が違うものですから、この辺について今後議論しよう。さらに、開示の問題と、それから経過措置の問題を今後検討することが今予定されております。
それから、続きまして、9月のときに日本からレジュメをつくりまして、日本における企業結合の例の紹介と議論を実は行いまして、それについて若干、ご説明申し上げますと、IASBの議論では、持分プーリング法が適用される持分の結合と言われるケースは非常に少ないと考えられていまして、そのようなケースのためにわざわざ会計処理を規定する必要はなくて、すべての企業結合は買収とみなして、パーチェス法を適用するということでいいのではないかという方向性が実は出ております。これに対して、わが国の企業結合では必ずしもそういうケースばかりではなく、持分の結合に該当するケースが比較的多く存在することから、このような例を検討することをかねてから要求しておりまして、日本のいろいろな関係者、SACにおける八木委員のご発言とか、日本の企業会計基準委員会も9月のリエゾン国会議において日本の状況をきちんと検討すべきだという主張をしていまして、それを受ける形で行われました。
その資料、次の3ページでございますけれども、日本から提示しましたのは、3つの銀行による持株会社の設立という事例を中心としまして、全部で5つの例を提示してございます。この5つの例は、IAS第22号で規定する持分の結合と言われる、相互にリスクと便益を共有する結合に該当し、これらの取り引きは決してまれにしかあり得ないというものではなく、少なくとも、国際会計基準が国際的な基準として機能する限りは、日本で広く行われているようなものが受け入れられるような基準にすべきではないかという主張を一応しました。
パーチェス法と持分プーリング法という2つの方法の選択に当たっての会計処理の適合性を議論する限り、取得者が特定できない企業結合においては、当事者のいずれにとっても――つまり、それぞれの企業にとってそれぞれの薄価が引き継がれる会計処理が行われることが論理的帰結であるという主張をしまして、このような場合には、どちらにとってもそれぞれ企業が継続企業として存在していて、その簿価を引き継ぐという形がベストではないかという議論をしたわけでございますけれども、これに関しては、取得者が特定できない企業結合によって誕生した事業体では、むしろ、それ以前の事業体のリスクと便益とは異なるリスクと便益が新たに生み出されたと考えるのが妥当ではないかということを主張するボードメンバーが結構多うございまして、このような場合には、当事者すべての資産・負債をその時点の公正価値で測定するフレッシュ・スタート法が最もいいのではないかというような主張をする方が多くいました。いろいろ議論したのですが、なかなか説得に至りませんで、このような意見を変えていただくのは非常に難しい状況でした。
取得者が特定できない場合には、日本が主張したような場合においても、何らかの指標を用いて、どのような形でか取得者をとにかく特定して、パーチェス法を適用するのが妥当であるというのが結論だったわけですけれども、それに対しては恣意性が働く余地がある、つまり、どちらを取得者とするかによって結果が異なることになるという問題点があることも指摘しましたが、それについて賛同する方は少なく、日本において取得者を特定することが困難な状況があるというのは一応わかったので、結論は変えないけれども、日本にそういう状況があるようなことについて、ひとつパラグラフをつくるので、そこに文言を入れてはどうかということになり、残念ながら、今の時点では説得するという状況にはなかなか至りませんでした。
次の4の無形資産でございますけれども、これについても、企業結合に伴って受け入れる無形資産とのれんとは密接に関係することから、ここで取り扱っております。今回、次の点で合意されたということですが、まず、有限な耐用年数を持つ無形資産は、IAS第38号の規定に従って、20年を超えない範囲の耐用年数で償却を行う。無形資産が企業にキャッシュ・フローをもたらすと予想される耐用年数が明確に決められない場合には、IAS第38号に基づく償却を行わずに、IAS第36号に基づく減損の処理を行うという、無形資産についてもそのような考え方を適用しましょうということになりました。
次の5でございますが、仕掛中の研究開発費でございますが、これについていろいろな議論があったわけですが、基本的には、仕掛中の研究開発費については資産として計上する。したがって、受け入れる時点でこれを独立した項目として計上し、のれんに含めることはしないということが一応決まりました。
それから、6番目ののれんの部分でございますけれども、まず、議論としましては、のれんの資産性という議論が行われまして、のれんは残存価値ではなく、積極的にIASBのフレームワークで言うところの資産に該当するのではないか。これはFASBが展開しているのと全く同じロジックでございますけれども、資産を構成する要素をここに黒丸で幾つか挙げてございます。
例えば、3つ目にございます継続企業要素。結合後の企業が純資産を個別に取得するときに期待される収益率より、組み合わされた集団として取得することによって高い収益率を得られる能力。それから、シナジー要素。結合する企業及び結合される企業の純資産や事業を結合することによって期待されるシナジーやその他の便益の公正価値、このようなものが積極的に資産として評価できるのではないかという点について、基本的にこのようなことを前提にして考えようということが確認されました。
 ののれんの会計処理でございますけれども、多くののれんでは耐用年数を明確に決定することができないので、耐用年数とのれんの費消のパターンを見積もることは困難であり、適切な減損処理のためのルールが規定されれば、のれんの会計処理として、償却を行うよりは減損処理によった方がよりよい結果が得られるのではないかというのが一応合意された認識でございます。
ののれんの会計処理でございますけれども、多くののれんでは耐用年数を明確に決定することができないので、耐用年数とのれんの費消のパターンを見積もることは困難であり、適切な減損処理のためのルールが規定されれば、のれんの会計処理として、償却を行うよりは減損処理によった方がよりよい結果が得られるのではないかというのが一応合意された認識でございます。 それに基づいて、次の最後のページの
 の減損処理でございますが、のれんの減損処理は、基本的に現行IAS第36号の「現金生成単位」をベースとするのれんの減損認識規準をそのまま適用する形でルール化するという、基本的な合意が一応成立しております。ただ、現実には、アメリカ基準と合わせるために、随分IAS第36号と変わるのではないかと思われるのですが、9月の時点ではこのような前提で議論されておりまして、のれんの償却は禁止し、減損テストを基本的には毎年行う、減損テストの目的は、のれんが回収可能額以上で貸借対照表に計上されることがないようにすることである。減損テストは、のれんを合理的継続的に配賦することができる現金生成単位の最小単位で基本的には行う。減損テストは、現金生成単位の「回収可能額」と認識されている純資産の簿価とを比較して行われる。この比較は、減損があるかどうかの判定と減損として認識すべき金額の決定という、双方に同じ指標を用いることになっております。
の減損処理でございますが、のれんの減損処理は、基本的に現行IAS第36号の「現金生成単位」をベースとするのれんの減損認識規準をそのまま適用する形でルール化するという、基本的な合意が一応成立しております。ただ、現実には、アメリカ基準と合わせるために、随分IAS第36号と変わるのではないかと思われるのですが、9月の時点ではこのような前提で議論されておりまして、のれんの償却は禁止し、減損テストを基本的には毎年行う、減損テストの目的は、のれんが回収可能額以上で貸借対照表に計上されることがないようにすることである。減損テストは、のれんを合理的継続的に配賦することができる現金生成単位の最小単位で基本的には行う。減損テストは、現金生成単位の「回収可能額」と認識されている純資産の簿価とを比較して行われる。この比較は、減損があるかどうかの判定と減損として認識すべき金額の決定という、双方に同じ指標を用いることになっております。 次でございますが、回収可能額は使用価値に基づくものと想定されるので、IAS第36号と同様なキャッシュ・フローを見積もるためのガイダンスを設ける必要があるだろう――つまり、回収可能額を出すときのネット・セリング・プライスは多分ほとんど適用できないので、いわゆるバリュー・イン・ユースという考え方で回収可能額を考えることになるのではないか。
最後でございますが、のれんの減損を認識した後は、予想キャッシュ・フローと実際キャッシュ・フローとの一致度合いのテストを事後的にやるべきではないか――5年程度やるべきではないかと、このような点について基本的な方向として議論され、合意されたということでございます。
以上が9月の議論でございまして、先ほど申し上げましたように、10月、11月と引き続きこの議論が進みますが、おくれても、1月には公開草案のドラフトまで持っていきたいという状況でございます。
以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
それでは、ただいまのご報告につきましてご質問等がございましたら、ご発言ください。
中島委員、どうぞ。
- ○中島委員
-
IASBの方での議論の雰囲気というか、流れはよくわかりましたが、先ほど3のところでご説明があった、基準の中に日本のような状況があることを示唆するパラグラフを挿入するというのは、どのような意味合いを持つのでしょうか。
- ○山田委員
-
具体的にはまだ文言がきちんと決まってはいないのですが、例えば、ある国ないしはある地域においては、持分プーリングが適用されるような、つまり取得者が特定できないようなものがかなり広く存在するというようなことを基本的には書く――ただ、その場合でも、IASBとしては取得者が特定できると信じるというクローズがどこかに入るとは思いますけれども、そうはさりながら、そうでないことを広く信じる国があるといいますか、そのような形の文言が入るということで、かなり主張した結果、何かを残してはあげるという、そのような感じかと思います。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はございますか。
どうぞ。
- ○若杉会長
-
6のれんの
 の4つ目に、シナジー要素というのがありますね。これは言っていることはわかりますし、私もこのようなものにすごく関心を持っているのですが、これから審議するのでしょうけれども、具体的にどんな方向で眺めていこうとするのですか。
の4つ目に、シナジー要素というのがありますね。これは言っていることはわかりますし、私もこのようなものにすごく関心を持っているのですが、これから審議するのでしょうけれども、具体的にどんな方向で眺めていこうとするのですか。 - ○山田委員
-
ここに今6つほど挙がっていますが、これがシナジー要素だというように個々に分けることは不可能でございますし、それはできない。ただ、このような6つの要素の――6つの中でも、最後の方の取得者の支払対価の過大評価などは通常は存在しないと思われますが、幾つかの要素が存在していて、個別にはピックアップできないけれども、このようなものがあることが残存価値ではなくて、積極的に資産として計上できる根拠を提供すると、そういう概念的な分析をしたということだけだろうと思います。
- ○若杉会長
-
もう前からアクリションという概念がありますよね、自然増加と訳していますが。自然というのは必ずしもナチュラルだけではないわけですが、そういうものが今、またこうやって考慮されるようになったというのは非常に興味深いのですけれども、何かいい、具体的な方向が出てくることを期待しております。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
ほかにご発言はないでしょうか。
八木委員、どうぞ。
- ○八木委員
-
質問ですが、アメリカがいろいろ検討した結果、このようなルールに帰結したというのはわかったのですが、ヨーロッパあたりの各国で、例えば実務界からは我々に近い議論というのは何かあったのでしょうか。
- ○山田委員
-
委員の中には、ドイツの方は――プリペアラの方なんですけれども、それからスイスの方もプリペアラなんですが、そういう方から、実は日本のような主張は聞かれないんですね。むしろ、理論的にはといいますか、アメリカがそちらへ行っていて、その方向でいいのではないか。むしろ、ヨーロッパの一部の企業の方はアメリカの減損の基準が緩いとみているのですが、IASがアメリカと同じような基準を持たなければ、もうIASの利用をやめるというような主張が出ているのです。ですから、どちらかというと、アメリカのようなものを前提にして、そちらへ行こうというような話がヨーロッバの一部の大企業で行われていて、日本のような議論は余り見られないというのが私が受けた印象でございます。
- ○八木委員
-
すると、1月ごろにその公開草案が出て、我々が意見を言うという、またこのようなステップを踏んでいくんですね。その過程で、我々がここで検討しているような日本の意見というのは改めてまた意見として主張すると、このようなステップを踏んでいくんだと思いますが、そこにおいて、さっきの一部書くよというぐらいのものではなくて、もう一つ強く押せる可能性というか、そういう方向というのはどのようにお感じでございますか。SACの委員としても非常に関心があるところなので。
- ○山田委員
-
この前のプレゼンの結果、多くの人はフレッシュ・スタートのような形がいいのではないかという、むしろ何かそれが再確認されたような状況が少しありまして、こちらから提示した例についても、もしも何かするとしたらこっちだねというような議論になった部分がございます。したがって、私としては、日本での今のこの状況について、もう一度、採決するときにも引き続き言っていくつもりですけれども、やはりコメントがたくさんそういう方向で出る必要があるかなとは思います。それから、それが日本からだけではなくて、もう少し――本当はヨーロッバからも出てくると検討の余地はあるかと思うのですが、正直なところ、プーリングが残る可能性というのはかなり少ないというのが実態ではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はございますか。
西川委員、どうぞ。
- ○西川委員
-
減損処理のところで、のれんの償却を禁止を前提にしているのですが、それは非常に大きな方向転換ですけれども、その禁止する理由というか、合理、ラショナルみたいなものが全然示されていないような感じですけれども、なぜ禁止しなければいけないのか。一応、私どもASBの方でこちらの企業結合についてのコメントをまとめようとしているのですけれども、その中では、のれんの非償却に対して、どうしてそういうことになるのかを相当言っているわけです。それが減損の具体的な処理をどうするかという前にあるのではないかという立場で検討しているわけですけれども、そこのところがほとんど議論されていないようにこのペーパーでは見える。
それから、それに少し関連しますけれども、例えば、これからリストラ引当金を議論するときに、リストラ引当金が何で出てきたかというと、これは、主としてつくる側の要望といいますか、リストラ引当金を立ててしまうと、その分のれんが大きくなるのですけれども、のれんはある程度年数をかけて償却できる。けれども、もしそれを立てなければリストラ費用が即時に落ちるということで、どうしても実態として即時費用は嫌だということでリストラ引当金を立てるという考えがあったかと思いますが、もしのれんを償却しなくていいということであれば、リストラ引当金を立てなくていいというようなことになるのかどうか、そのあたりを少しお伺いしたいのですが。
- ○山田委員
-
まず、1点目の減損処理だけにして償却を禁止する論拠ですが、これは、4ページの
 のところで少し触れているように、多くののれんでは耐用年数を明確に決定することができなくて、20年とか何年という恣意的に決められた年数で償却するのは不合理であるということに基づいて、ある厳格なルールで、減損を認識するルールを明確化して、その減損が認識されたときに落とすのが合理的ではないかという理由づけがされていまして、IASBでもそれで基本的にはいいのではないかということになっております。
のところで少し触れているように、多くののれんでは耐用年数を明確に決定することができなくて、20年とか何年という恣意的に決められた年数で償却するのは不合理であるということに基づいて、ある厳格なルールで、減損を認識するルールを明確化して、その減損が認識されたときに落とすのが合理的ではないかという理由づけがされていまして、IASBでもそれで基本的にはいいのではないかということになっております。 それから、リストラ引当金の問題ですけれども、リストラ引当金は、のれんの償却とひもつけるというよりは、IAS第37号の引当金の計上の根拠としては、基本的には、過去の事象の結果として、現在、債務性がある、ただし、金額の支払い等について不確実性があるというような状況が前提として存在していなければいけないわけですけれども、リストラ引当金の場合には、被取得企業で引当金が計上されているわけでもなくて、取得する側でも債務性があるわけではないので、そのまま原則を適用すると多分計上できないだろう。それに対して、IAS第22号をつくったとき、西川さんがおっしゃったように、ある例外としてそれを認めたわけですけれども、やはりできるだけ例外を少なくする方がいいのではないかということで、それをなくす。つまりIAS第37号の原則へ持っていく。そうしますと、リストラ引当金の計上ができませんので、その分対価が安くなっている場合には、負ののれんが生じてくるような事態に多分なるのではないか。議論の方向は、原則に対する例外をできるだけ減らすという視点でどうも提案されているようです。したがって、私個人としては、西川さんがおっしゃったような方向で議論しようと考えております。
- ○西川委員
-
さっき少し言い間違えていますけれども、リストラ引当金を立てると、反対側にのれんが膨らむわけですけれども、今度はのれんを償却しなくていいとなると、のれんは償却しないし、リストラ費用も出ないということになってしまうと、それはまずいから、ではリストラ引当金はやめさせた方がいいというような話になるのではないか。これは推測ですけれども。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
恐らくアメリカのルールが手本になっているので、多分クレームを言うんだったらアメリカへ言った方がいいと思いますので、クレームは言いませんが、減損の判定単位についてお聞きしたいのですけれども。合併で生じたのれんを、その後、減損しているか判定する場合の単位は、被合併会社を単位としてやらないと、合併会社が生み出したのれんが紛れ込んで、自己創設のれんの計上になりかねない。例えば、抽象的だとわかりにくいので大変失礼かもしれませんが、銀行のさくらと住友の例でいいますと、さくらについて仮にのれんを計上した。その後、三井住友の減損の判定単位は、その旧さくらの単位としてキャッシュ・フローを推定すべきであって、住友側と結合されたキャッシュ・フローを使ってしまうと、住友側の自己創設のれんの計上につながる。ところが、同業で結合していますから、それは多分事実上不可能な話ですね。そうすると、これは恐らく、減損テストというのがもう必然的に持っている自己創設のれんの計上という問題を内包しているのではないかと思うのですが、その点は議論にならなかったのでしょうか。
- ○山田委員
-
今回、実は10月に多分議論することになると思います。おっしゃるとおりだと思います。基本的には、アメリカがレポーティングユニット、それからIASの場合ものれんがひもつく――キャッシュジェネレーティングユニットと1対1でひもつけばそれでいいんですが、ひもつかない場合にはキャッシュジェネレーティングユニットを2つ、3つ合わせて、のれんとひもつく単位まで上げていくという基本的な方向、考え方を持っていますので、そういう意味では、被合併会社単位のところまで引き上げる可能性があるのですが、ただ一つ問題点は、そういう単位が日常的な収益、管理の単位と一致するかどうかという問題がありまして、そことの絡みで、今、大日方先生が言われた点がきちんと担保されるのかどうか、今度議論したい点だと私は考えております。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
のれんの償却をしないという方法を選択したときには、結合後ののれんを維持するための支出がのれんの勘定に振りかわって、自己創設のれんを計上する結果になるということ自体は、そのことだけであれば、これはアメリカも既に認めているわけですが、今の大日方委員のご指摘は、合併した側、取得した側が結合時点以前からつくり出していたのれんが、結果的に結合後ののれん勘定に計上されるという、そういう意味の自己創設のれんの可能性をおっしゃっているわけで、それを排除することは、実はアメリカの減損テストのやり方では、事実上不可能に近いだろうということをおっしゃっているわけですね。そういう点はぜひきちんとお伝えいただければと思います。
それでは、少し時間をとりましたけれども、次へ進めさせていただきます。
わが国の企業結合の事例の報告を今度はお願いいたします。
まず、梅山委員から、三井住友銀行の事例についてご報告をお願いいたします。よろしくどうぞ。
- ○梅山委員
-
梅山でございます。
私からは、本年4月にさくら銀行と住友銀行の合併によりまして発足いたしました三井住友銀行の合併に至る経緯、合併の概要等をご報告いたします。
説明資料は、これまでに記者会見、アナリスト向けの会社説明会等で配付した資料を原則としてそのまま使っております。したがいまして、計算している計数データはやや古いものがありましたり、比較参照しておりますほかの都市銀行の状況も、この金融再編途上でありますので現在の状況と異なるケースもありますが、その時点でのファクトを示す資料ということでご理解をお願いいたします。
まず、合併の骨子でありますが、2ページをごらんください。
統合の形態は合併であります。存続会社は株式会社住友銀行、解散会社はさくら銀行ということで、法手続上、このような形になっております。商号は株式会社三井住友銀行に変更いたしました。英文名称は、そこに書いてありますとおり、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 、SMBCと略称しております。合併期日は平成13年4月1日。合併比率につきましては、さくら銀行の普通株式1株につき、住友銀行の普通株式0.6株を割り当て交付しております。また、さくら銀行の優先株式につきましては、期中転換、満期一斉転換型の優先株でありますので、転換価格の適用ルールの調整をした上で、住友銀行が新たに発行いたします優先株と1対1の割合で割り当て交付をしております。本店所在地は、旧さくら銀行の東京営業部がありましたところを本店としております。住友銀行の本店は大阪市でございました。経営トップでありますが、取締役会長にさくら銀行頭取の岡田、頭取に、住友銀行の頭取、西川が就任しております。
次に、合併までのスケジュールでございますが、平成11年10月14日に、さくら銀行と住友銀行は、将来の統合を前提とした全面提携の実施につきまして基本合意し、公表しております。この時点におきましては、さくら銀行と住友銀行の両行は、将来の統合までに、それぞれの責任におきまして、既に公表しております経営健全化計画に織り込んだリストラの加速、不良債権処理、政策投資株式の圧縮、財務の健全性と、そういう課題をそれぞれ達成した上で、平成14年4月までに、合併を基本として対等の精神で完全統合するということで合意しております。言いかえますと、合併後、経営のスピードがスローダウンしないように、平成13年3月までに統合の作業を完了し、平成13年4月からは双子銀行として1年間業務提携の実を上げていく。そして、そのスピードを落とさずに、平成14年4月までに名実ともに合併するという考え方でございました。
しかし、グローバルな競争に勝ち抜いて、本邦金融界におけるトップランナーの座をいち早く確保していくためには、当初の計画に対し1年前倒しで法律上も一つの銀行となり、新体制のもとで統合の実を上げていくということが必要だと判断いたしまして、また、全面提携発表後、半年の間に、合併に向けた作業が順調に進んできたということも踏まえまして、2行目にありますが、平成12年4月21日に合併に関する基本合意、合併期日を平成13年4月とする合併の前倒しと、経営トップ、合併比率の決定を行いました。5月に合併契約書の調印、6月に定時株主総会での合併承認、その後の当局による合併認可等を経て、本年4月に合併となったものでございます。
次に、合併の目的、その意義、効果についてでありますが、4ページ以降に取りまとめております。
まず、合併の目的でありますが、株主価値・資本効率の極大化のために、営業基盤の強化、財務力の強化を迅速に実現する方法として、この合併を位置づけております。
合併の意義につきましては、強固な営業基盤の確立という戦略的な意義と経営の効率化という財務上の意義の両面から、さくら銀行と住友銀行の合併は最適な組み合わせと考えております。具体的には次ページ以降で説明いたしますが、まず、営業基盤の面では、さくら銀行と住友銀行がそれぞれ培ってきましたお客様基盤、商品、サービス、チャネルの提供力が一体となることによりまして、マーケットシェアの獲得、潜在的に収益化が可能なお客様基盤の獲得、さらに、それぞれの強みを投入することによる収益の極大化によりまして、強固な営業基盤の確立、向上が期待できるということであります。また、財務面では、経営健全化計画においてそれぞれ銀行が計画しているリストラによる経営の効率化に加えまして、合併によりさらに一層の合理化による財務面の効果が期待できるということでございます。
まず、強固な営業基盤の確立という点につきましては、次の5ページから7ページにまとめております。お客様の基盤ということでありますが、表の一番左側にございますように、個人取引、中小企業取引、中堅・大企業取引におけます。具体的には、例えば、収益性・収益機会に優れた中小企業メーン先の基盤の確立――この基盤が国内銀行のトップとなるということがあるわけですが、このような形でお客様基盤が圧倒的に拡大すること。そういうお客様の基盤に対しまして、競争力のある商品、サービス、チャネル、グループ会社を含めました金融ソリューション提供力をもって、強固な営業基盤の確立・向上を図ろうというものでございます。
具体的な数字につきましては、6ページと7ページにございます。
6ページにつきましては、リーテイルのお客様の基盤でございます。
表の一番上につきましては、中小企業のメーン先数、それから成長法人のメーン先数等がございます。この計数につきましては、欄外の注にございますように帝国データバンクのデータによるものでございますが、国内におきましてトップの地位となるものが多いということでございます。
真中の表は、消費者ローン、住宅ローン、個人預金等の個人の取引でございますが、これにつきましても基盤が相当拡大されるということでございます。
チャネルにつきましては、一番下のところでございます。国内の店舗数、ATM・CDの設置台数等々でございますが、こういった国内トップとなるということでございます。
次に、ホールセールと証券顧客基盤ということでまとめたのが次の7ページでございまして、一番上の表が上場会社・店頭企業取引に係る貸出先数等でございます。
真中の表は、アジアにおけるシンジケートローン。これは特にアジアに注力しているということから、アジアのシンジケートローンのアレンジャー件数等を書いております。また、外国為替の取扱高。
一番下の表につきましては、子会社、関連会社――証券子会社ですね。関連会社を含めましたグループベースでの証券関係のお客様基盤を整理したものでございます。国内の普通社債の主幹事件数、証券子会社、関連会社を通じた東京証券取引所の株式取り扱いシェア等の順位を示しております。これが合併に伴う顧客基盤の拡大の状況ということでございます。
次に、財務面の意義ということで、8ページ、9ページに経費面の動向を書いております。財務面の意義ということにつきましては、単独の銀行でなし得る以上の経営の効率化によりまして、経費の一層の削減が図れるということを整理したものでございます。
8ページには、経費の削減効果を取りまとめております。冒頭に申し上げましたように、両行とも経営健全化計画に基づきましてそれぞれリストラを進めてきておりますが、それに合併による合理化効果を加えたものが、資料にありますように、一番上のところでございますが、平成10年度から平成16年度までに年間の経費で1,000億円削減するということでございます。このうち、合併による合理化効果を、その半分の500億円を見込んでいるということでございます。この期間中にIT関連投資の積み増しが200億円含まれておりますので、実際の経費の削減は1,200億円程度を見込んでおります。合理化によります経費削減効果の内容は、一番下のところに書いておりますが、平成16年度までに人員の合理化で250億円、店舗の合理化で50億円、システムの合理化で約200億円、締めて500億円を見込んでいるということでございます。平成16年度以降に実現する効果を含めた平年度ベースでの効果は、約600億円ということでございます。そのリストラの中身につきましては、9ページに整理しておりますのでごらんください。
先ほどから申し上げています経営健全化計画というものが、この表の中ほどにございます。この経営健全化計画では――平成14年度末までの計画でございますが、両行の単純合算で、人員が6,300名の削減、国内支店151カ店、海外支店32カ店の削減を計画しておりました。これに、合併による追加合理化といたしまして、平成15年度末までに、さらに3,000名の削減、国内支店を約100カ店、海外支店6カ店の削減を計画しております。これによりまして、平成9年度末の合算人員――これは左の上に書いてございますが、3万2,531名が、約3割の9,300名減少いたしまして、平成15年度末には2万3,200名程度になるというイメージでございます。
なお、合併後におきまして、さらに一層の合理化に向けた見直しを開始いたしまして、その追加の施策がほぼでき上がったところでありますが、本日の資料でお示ししている経費削減計画は、合併前までの平成12年12月に公表いたしました三井住友銀行としての経営健全化計画によるもので、合併後に新たに策定した一層の合理化策は含んでおりません。
次に、経営の組織でございますが、銀行の組織につきましては、住友銀行とさくら銀行、それぞれ営業組織においてその強み、弱みがあるわけですが、おおむね同様の営業組織を持っておりますので大きな変更はございません。営業部門は、個人、法人、企業金融、国際、市場営業、投資銀行の6部門でございます。経営につきましては執行役員制度を採用しており、経営会議は、ほぼ真中にございますが、頭取の主催で、営業部門のトップ、本社部門の統括役員等の頭取の指名する執行役員で構成しております。取締役につきましては、社外取締役2名を含め26名で構成され、取締役会の中にリスク管理委員会、報酬委員会、人事委員会が置かれております。社外取締役は、それぞれの委員会のメンバーとなり、かつ報酬委員会の委員長になっております。
なお、別途、欄外にございますが、企業経営者、経営コンサルタント、学識経験者から成るアドバイザリーボードを設置し、経営についてのアドバイスをいただくことになっております。
以上が、経営の組織でございます。
次に、合併当事者の概要。それぞれの概要についてはご存じだと思いますので、後ほど議論になります承継資本とか規模にかかわるところを簡単にご説明いたします。
まず、資本金でありますが、5番目のところにございますように、さくら銀行が1兆427億円、住友銀行は7,528億円でございます。このうち公的資金によります優先株発行にかかわる資本金の増加額が、さくら銀行で4,000億円、住友銀行で2,505億円ございますので、それを除いた資本金は、さくら銀行で6,427億円、住友銀行で5,023億円となっております。この公的資金による優先株式につきましては、6番目の発行済株式数のところでは、さくら銀行では第3回の優先株式8億株、住友銀行では第1回と第2回の優先株式、合計しまして1億6,700万株でございます。大株主の株式会社整理回収機構が、それに当たるものでございます。
普通株式の発行済株式数につきましては、(6)のところでございますが、さくら銀行が41億1,700万株、住友銀行が31億4,100万株でございます。後ほどご説明いたしますが、さくら銀行からの承継資本金は5,239億円となっておりますが、これは、さくら銀行の普通株式41億1,700万株に対しまして、住友銀行の株式を1対0.6の割合で割り当て交付することによりまして発行される株式数24億7,100万株、これに額面の50円を乗じた金額、これが約1,239億円になりますが、これに、公的資金による優先株式の資本組み入れ分4,000億円、これを加算した金額でございます。
株主資本でありますが、7番のところにございますように、さくら銀行が2兆2,522億円、住友銀行は1兆8,806億円でございます。この中には、公的資金による資本の増加額、さくら銀行で8,000億円、住友銀行で5,010億円ございますので、それを除きますと、それぞれさくら銀行が1兆4,522億円、住友銀行は1兆3,796億円と、ほぼ同規模の水準でございます。
その他、総資産、従業員数、大株主状況はごらんのとおりでございます。従業員数につきましては、10番にございますが、平成12年3月末時点でともに1万4,000名台ということで、同程度の水準になっております。バブル崩壊以降、これまでの相当のリストラを進めてきた結果、このような人員でございまして、例えば5年前、平成7年3月末の人員とこの平成12年3月末の人員との比較で見ますと、さくら銀行で見てみますと、平成7年3月末が2万1,600名。これから約6,700名の減少。住友銀行では、平成7年3月末が1万7,247名で、約2,800名の減少ということでございます。
次の12ページには、過去3年間の業績が掲載されております。
一番上の行は経常収益でございますが、過去3年間の規模においては、ほぼ同程度の経常収益の規模ということでございます。一番下の行の1株当たり純資産で見ますと、平成12年3月期、これは合併合意の直前期でありますが、さくら銀行が1株当たり純資産が351円38銭、住友銀行が439円23銭と、若干の乖離がございます。
以上が、両行の概要でございます。
次に、合併比率算定の方法についてまとめております。合併比率につきましては、平成12年4月21日の合併に関する基本合意時点で1対0.6で決定しております。合併比率は、両行の株価を基本に、純資産や将来的な成長性、こういったもの、いわゆる市場において一般的に受け入れられています調整方法も考慮に入れて決定いたしました。この資料は、さくら銀行と住友銀行、両行が、それぞれ合併比率算定に係る意見書の作成を第三者に依頼しまして、報告を受けたものでございまして、両行の株主総会の招集通知に添付された合併比率決定理由書から抜粋したものでございます。
算定方法につきましては、それぞれ5つぐらいの分析をしておりますが、いずれも、株価のほか、純資産、将来の利益の計画、貢献度をその分析の対象としたということでございます。
最後に、合併時の資産・負債・資本の承継処理につきましてご説明いたします。14ページでございますが、承継の考え方につきましては上の方に文章で書いております。4月の合併に際しまして、平成13年3月末のさくら銀行の貸借対照表をベースにいたしまして、新銀行の財務体質を強固なものとする観点から、まず、平成13年度から時価会計を適用いたしますその他有価証券。このうち含み損のある銘柄について時価で承継したということが第1点。2番目には、土地再評価法のもとで再評価を実施済みの事業用の土地のうち、その後、地価の値下がりで含み損となっているものについて時価受け入れをしたということが2点。第3番目は、平成12年度から採用いたしました退職給付会計のもとで生じております未認識債務相当額について、退職給付引当金の計上を行っております。
この処理の背景でございますが、平成13年度の法人税制改正によりまして、適格合併に係る被合併会社からの資産負債の承継につきましては、税務上は簿価引き継ぎとなりましたので、平成12年度までの合併であれば、税務上、引き継ぎが容認されていなかった税務欠損金の引き継ぎ、有価証券の有税償却分の税務否認金の引き継ぎ、減価償却の無税限度超過額の引き継ぎ、こういったものが可能になりました。これと同様の考えで、平成13年4月1日の合併受け入れにおきましては、時価が簿価を下回るものについて、税務上の簿価を留保した上で、会計上は時価による受け入れを行ったということでございます。
なお、この結果といたしまして、被合併会社からの資産・負債等の承継については、税務上の引き継ぎ価格と会計上の受け入れ価格に差異が生じております。この差異は、税効果会計で言うところの将来減算一時差異となりますので、承継時に繰延税金資産を計上しております。
以上の結果の計数は下の表にありますとおりでございまして、資産の部では、有価証券のところで、合併処理といたしまして4,563億円の資産の減少、動産不動産勘定で292億円の減少。負債の部では、退職給付引当金の計上2,102億円。以上、合計した総額6,957億円に対しまして繰延税金資産2,687億円の計上を行い、結果として、資本勘定は、差し引き4,270億円を減少させて承継しております。
資本勘定の中身は、承継資本金は、先ほどもご説明いたしましたように、合併契約書で決めておりまして、5,239億円を計上しております。また、利益準備金、再評価差額金、剰余金につきましては、さくら銀行の最終貸借対照表の金額を承継しておりますので差し引きが資本準備金の承継ということになりまして、承継資本勘定は1兆8,542億円。その内訳は、その表に記載のとおりでございます。
ご参考までに、財務上のその他の情報を15ページに取りまとめております。
まず、(2)は含み損益の状況でございまして、表の中ほどに、その他有価証券の含み損益がございます。旧さくら銀行の平成13年3月末時点の数字をごらんいただきますと、含み損益はネットでマイナスでございました。ネットで2,517億円のマイナスということでございます。このうち含み益が、その右側にありますように2,046億円、含み損が4,563億円という内訳でございまして、この4,563億円を時価受け入れしたということでございます。その結果、含み益の2,046億円を承継したということになります。ちなみに、住友銀行では、その他有価証券は42億円のマイナスでございますので、合併時点、4月1日時点の含み損益につきましては2,004億円のプラスとなった計算でございます。
なお、この資料にはないわけですが、合併合意直前期であります、1年前の平成12年3月末時点の有価証券の含み損益につきましては両行ともプラスでございまして、さくら銀行で6,627億円のプラス、住友銀行で9,013億円のプラスとなっておりました。
表の下の方、土地でございますが、これは土地の再評価法に基づく再評価後の土地の含み損益でございます。それはバランスシートの注記の数字でございますが、ごらんのような姿でございます。このうち、土地の292億円を評価を落として引き継いだということでございます。
表の一番下でございますが、退職給付会計に係る未認識債務でございまして、退職給付会計導入時の会計基準変更時差異の未償却額、これが1,454億円。それから、平成12年度におけます厚生年金基金の運用収益の劣化によりまして発生した数理計算上の差異648億円。この合計2,102億円に対しまして退職給付引当金を計上したということでございます。
以上のように資本勘定を4,270億円減らして承継したわけですが、その結果の連結自己資本比率、これは合併時、4月1日時点という計算でありますが、0.4%ほどマイナス要因となりまして、ごらんのとおり10.8%の水準でスタートしたということでございます。
簡単ではございますが、以上で報告を終わります。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
それでは、ご質問があれば承りたいと存じます。
どうぞ、黒川委員。
- ○黒川委員
-
土地についてご質問させていただきます。土地については、例の再評価法にかかわる土地について、その後の時価減少分についてというご説明でしたけれども、再評価法の適用の土地は、すべての店舗と本社等について全部時価評価されたのか、あるいは一部の土地についてでしょうか。
- ○梅山委員
-
ほとんどすべてでございます。一部、処分が予定されているものについては再評価しておりませんが、それ以外についてはすべてでございます。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。
特にないようでしたら畠山参考人から、みずほフィナンシャルグループの事例につきましてご報告をお願いいたします。よろしくどうぞ。
- ○畠山参考人
-
かしこまりました。私は、みずほホールディングスの畠山と申します。このような貴重な会にお呼びいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、私どもの株式移転制度を利用した企業結合の事例ということで、第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の3行によるフィナンシャルグループの創設についてご説明させていただければと存じます。
今、お手元に、「株式移転による企業結合について」という五、六枚のレジュメと、なかなかこのような会議にはなじまないかもしれませんが、いわゆるディスクロージャー誌をお持ちいたしました。そこで、もしご参考になればということで、ところどころで使わせていただければということで存じます。
ここの会のポイントは、持分プーリングで、いわゆる取得者が識別できるかできないかということかと存じますが、みずほの場合、結論から申しますと、取得でなかった、識別できなかったということでございます。それの最大の顕著な事例ということで本日お呼びいただいているということと、これからいろいろな一般の事業会社の業界再編を考えますと、今、シェアの回帰というようなことが行われておりまして、シェアの回帰を目指す一般事業会社でも、低いシェアのものがトップに返り咲くということで、対等で株式移転、持株会社制度を使ってそのような、いわゆるプーリングをやるというケースが必ずしもないかというと、100%ないだろうとはなかなか言いがたいということで、日本の業界の事例の中には、私どもが顕著でございますが、そのようなものもあるのではないかということの一つの事例としてご説明させていただければということでございます。
私ども、株式移転制度を使って持株会社をつくったわけですが、その当時の金融の環境がどうだったかということでございます。経済がグローバル化している、金融ビックバンの進展ということで、もう古い言葉になりましたが、フェア、フリー、グローバルというような言葉もございました。それから、金融技術・情報通信技術の発展、いわゆるIT、FTが発展してきたということと、やはり金融機関の競争が激化してきたと、これが非常に大きゅうございます。特に、90年代の米銀でございますが、彼らは買収合併でマーケットシェアを非常に拡大して、相当大きくなってきたということでございます。例えば、マニファニはケミカルになり、チェース・マンハッタンと一緒になって、今はJPモルガン・チェースと、このような形で銀行界が再編して、大型化、集約化、シェアの回帰と、このようなことが行われてきたというのが、やはり大きな背景にあったということでございます。
それから、ブティック化ということよりも、金融コングロマリットという形で、いろいろな多面的にお客様と取り引きしていくという対応力が求められる。いわゆるワンストップショッピング的に何でもできるということが一つ必要になってきて、格付けがいろいろなところでやはり大きく影響を受けてくるようになったということから、財務体制に支えられた「信用力」――金融というのはやはり信用力の世界でございまして、一つそのようなグループをつくる必要があったということで、総合金融グループの結成に至ったということでございます。
統合の目標、将来像ということで、最先端の総合金融サービスで時代をリードしていきたいということで、経営目標が幾つか書いてございます。トップファイブになりたい。それから、カスタマーサティスファクションということでもお客様から評価されたい。それから、IT、FTでも非常に先を走っていきたいとか、いろいろなことを考えているということでございます。経営体制もその時々のベストプラクティスということで、昔、GEのウェルチの前の会長が、経営というのは変化への対応力だというようなことも言っていましたが、正しくジャッジしていくことも必要ということで、経営体制も挙げております。5つの基本理念ということで、お客様から信頼される、トップバンクでいきたい、社員にとってもいいというようなことを持ったグループをつくりたいということで動き出したということが、我々みずほの背景にあったということでございます。
それで、事業戦略でございますが、統合によりまして実現される「三つの強み」ということで、各事業分野のトップクラスかつバランスのとれたポートフォリオを構築したいということで、国内マーケットにおける圧倒的な顧客基盤と、それからトップクラスの総合金融力とITの投資力の拡大と、この3つでございますが、大変恐縮でございますが、IRの資料の見開きをあけていただきますと、フィナンシャルグループの数字がございます。それをまた少しめくっていただきますと、このような形になってあるところがあろうかと存じます。
3つの銀行が一つになったということなので、当たり前と言えばそうなんですが、お客様の取引でいきますと、決済口座で大体100万社。それから貸出先、大企業が1万5,000社、中堅・中小17万社。上場企業の7割と貸出取引を行い、10社に4社がメーンバンク。そのような大きなものができ上がっております。個人預金も大体3,000万口座。それから、金融法人、地域の金融機関、保険、公社公団、それから東京都まで入っているという、非常に大きな金融グループが結果としてでき上がっているということでございます。
IT投資についてはやはり3行が一つになりましたから、大体1,500億円程度の投資力が出てきているということでございます。
3ページをおあけいただけますでしょうか。私ども、どのような形でみずほというものをやっていこうかということでございまして、左側が統合前、それから真中がフェーズ1。ここは、いわゆる商法第364条の株式移転を使った。それから、今度、フェーズ2ということで、来年4月以降、会社分割で会社を切り出していくということでございます。
先ほど申しましたように、いろいろな金融環境を背景といたしまして、平成11年8月20日に、いわゆる3行で統合を発表したということでございます。それで、契約書に調印いたしましたのが、その年の12月22日でございました。そのとき、大体3行はどのような状況になっておったかと申し上げますと、第一勧銀、富士銀行、日本興業銀行と、この3つがございまして、その下に、いわゆる銀行が持つ証券子会社、第一勧業証券、富士証券、興銀証券がございました。それとは別に、信託業務への参入ということもありまして、富士銀行と第一勧銀がそれぞれ50%出資した第一勧業富士信託と興銀信託銀行、このようなグループを持っていたということでございます。これを受けまして、平成12年5月に予備認可の承認をいただいて、その後の総会で、いわゆる株式移転を認めてもらったということでございます。
それで、このフェーズ1でございますが、平成12年9月29日から、純粋な金融持株会社の下に、いわゆる3行を100%子会社としてぶら下げたということでございます。金融持株会社は基本的に、グループの経営管理と、それに附帯する業務ということしかやってございません。資本金は2兆5,720億円、見合いは子会社株、このような形になってございます。ホールディングスの中は、企画管理の部分と、それから、いわゆる子銀行をフェーズ2に向けて横を縦にしていくという形のビジネスユニット部分を持ってございます。これは、各第一勧銀、富士銀行、日本興業銀行が、中の営業を分けますと、個人、中堅・中小、大企業、金融法人、いわゆる公共法人、国際、それから市場・ALM、決済、いわゆるセツルメント・マルチメディア、それから証券・インベストメントバンクと、それから資産運用・信託と、このようないわゆる銀行の機能があるだろうということで、これを横串でそれぞれ管理するセクションが、その上にあるビジネスユニットというものでございます。その下に、いわゆるみずほ証券とみずほ信託という、証券子会社、信託子会社がぶら下がっておるという形でございます。
本日のご説明は、この株式移転で持分プーリングを使っておるということが本題ですが、その後、平成14年4月に、いわゆる会社分割制度を使って吸収分割で個人部門と法人部門、大企業部門を切り出して、機能別の、顧客、セグメント別の法的分社経営をやるというのが私どものフェーズ2という形になってございます。
それで、みずほ銀行、みずほコーポ、証券、信託ということでございまして、個人的に、非常にわかりやすく申し上げますと、このみずほ銀行はリテイルとセツルメント、いわゆる小売と決済を軸とする。コーポレートは、ホールセールスのインターメディアリー、いわゆる仲介ですか、リスクを仲介したりスワップを仲介する。それから、証券はアンダーライティング。それから、信託はトラストカストディアン。ある意味で銀行の機能をばらばらにして、それぞれ特質で切り出した、このような形が今回のフェーズ2でございます。
恐縮ですが、ディスクロージャー誌の34ページをおあけいただけますでしょうか。このような形のみずほ銀行、みずほコーポレート銀行ができるということでございます。片方が個人、国内法人、それから地方公共団体をお客様とし、反対側のコーポレートが大企業、海外、公共法人の公団・事業団をお客様とすると、このような大きな機能に2つに分けようということでございます。
これが大体みずほのフェーズ1、フェーズ2に向けてということでございまして、次に、経営体制でございますが、次の3番、経営体制をおあけいただけますでしょうか。
これが、私どもホールディングスの、持株会社の中の経営体制ということでございますが、経営と執行の分離ということで、いわゆる執行役員制度を入れておりまして、取締役は9名。今回の総会で社外取締役の方3名が入りまして、今現在は12名になってございますが、取締役会。その下に、執行役員を含めた経営会議があるということでございます。
それで、企画管理の中は6つのグループに分かれています。いわゆる企画グループ。これは、先ほど申しましたような形で法的分社に至るような統合を推進するような部門がございますし、財務・主計、全体の収益管理をどうするとか、全体の連結決算をどうするかといったような、まさに私どもが属しているところがここでございます。それから、リスク管理。リスクキャピタルに基づいた資産配分などをいろいろ考え、全体を総括していく。それから、人事。3万人近くの行員がいて、これを、いろいろ動かしていかなければいけないのですが、そういったものを管理する。それからIT、コンプライアンスと、このような大きな機能がございまして、その下に、先ほど申しましたような形のビジネスユニットがございます。
ディスクロージャー誌の158ページに役員が載ってございます。左上から西村、山本、杉田――興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行のそれぞれの頭取。その下、奥本、小倉、酒井――同様に興業銀行、富士銀行、それから第一勧業銀行と、このような形で役員が構成されております。
それで、この一番左の下に3人いらっしゃいます、荒木様、松田様、グレン・フクシマ様。先ほど申しました社外取締役でご招聘した方でございます。
次に、4番、いわゆる割り当て比率、株式移転でどのように割り当てを行ったかということでございます。ここは全部、招集通知に書いてございますとおりでございますが、株式移転に際して、まず、公平性と妥当性を確保するということで、第三者機関であるアーサーアンダーセンにお願いしたということでございます。アーサーアンダーセンに我々がお願いした理由というのは2つございます。1つは、私どもは国際業務を営んでいるということから、海外にも知名度がある。それからもう一つは、それぞれ3行の監査法人以外のところにお願いして、フェアネスオピニオンを出していただくということから、最終的にアーサーアンダーセンに至ったということでございます。
それで、そのアーサーアンダーセンに3行の普通株式1に対して、それぞれ一体どうなりますかと、いわゆる統合比率の算定をお願いしたということでございます。結果、この下の表がございますように、いわゆる市場株価。これは、平成11年4月1日から統合の前日の発表、8月18日までの終値平均を一つ持ってきたと。それから、収益方式ということで、将来収益を資本還元率か何かで割り引く収益方式を使っている。それからもう一つ、修正純資産ということで、簿価と時価の差額の乖離を何らかの形で載せたということで、この5、3、2という加重割合で出した統合比率を、仮に富士銀行を1とすると、第一勧業銀行が1.0323、日本興業銀行が1.0369という非常に僅差、ある幅の中に入っているということだったわけでございます。それで、3行は、アーサーアンダーセンのその統合比率をもとに結果等を協議いたしまして、この統合比率は1対1対1という経営判断をなしたということでございます。
したがいまして、3行の普通株式1,000株・額面50にホールディングスの普通株、額面金額が5万円、当時、商法第166条でまだ額面がございましたので、額面を割り当てたということでございます。
また、3行は同じように公的資金を導入する際の優先株もございましたので、その比率も同じような比率で割り当てたということでございます。
それから、本日の本題でございますが、プーリング法を私どもは採用いたしました。これは、取得会社を識別できないということで、第一勧業銀行が富士銀行と興銀を買った、ないしは富士銀行が一勧と興銀を買った、興銀が富士と一勧を買ったということが、正直申し上げて判別できないということでございまして持分プーリング法の適用に至ったということで、ここに書いてございますことは、日本公認会計士協会の研究報告の中に、いわゆる持分の結合の判断に至る判定根拠を記載してくださいという記載がございます。そこに書いてあることに準拠して記載したということで、研究報告に準拠してプーリング法を適用したということでございます。
次に書いてございますように、企業結合を持分の結合と判定した根拠ということで、リスクと便益が共有され、取得会社を判別できないということで、その1つ目の理由が、3行の議決権付普通株式がほとんどすべて実質同一的だということで、普通株式と交換されて、交換後の株式に制約がございませんということでございます。
それから、3行の公正な評価額が著しく異なっていないということで、8月18日、まさに統合発表の前日の終値に発行済総数を乗じるということで、それを比べてみたということで、興銀を1とすると、第一勧銀が1.09、富士銀行が1.25ということであった。
それからもう一つ、ある一時点をとるのでなく、幅、その分散みたいな乖離はどうかということで、先ほどアーサーアンダーセンが統合比率を出したのと同じような形で、4月1日から統合の発表の前日までの平均を見て、その幅におさまるかというチェックをかけたということでございます。その結果、第一勧銀が1.078、富士が1.192、興業銀行が1.00と、このような形である範囲の中におさまっているという認識をしたということでございます。
それから、3行のいずれも契約等により親会社の財務とか営業、そういったものを支配する権利を有していないと。それから、いずれも取締役会等の意思決定機関を支配する事実がないということで、先ほど申しましたような形で取得会社を識別できないと、かように判断したということでございます。
それで、最後のところに数字がございますが、これはご参考までということでございますので、詳しくは、今お配りいたしましたディスクロージャー誌の中にあるということでございます。
大変駆け足でございますが、みずほからの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
それでは、ただいま頂戴いたしましたご報告につきまして、ご質問があればお伺いいたします。
先ほどの三井住友のケースとあわせてご質問を出していただいて結構でございます。
西川委員、どうぞ。
- ○西川委員
-
質問ですが、比率の算定でアーサーアンダーセンがやった市場株価方式の行のところと終値平均値を比較したところの違いは何でしたか、少し教えていただきたい。
- ○畠山参考人
-
アーサーアンダーセンの方は、株式移転するに際してそれぞれどうするかという比率でございますよね。それで、もう一つの方は、企業結合を判断するに際して、公正な評価額がどうだろうかという判断をしなければいけないというプロセスの中の一つの判断基準ということではないかというふうに理解しておるのですが。
- ○斎藤部会長
-
西川委員、よろしゅうございますか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
今の点で、確認でございますが、アーサーアンダーセンの方は、言ってみれば1株当たりの評価額。合併比率算定の根拠ですから、それに近い。それから、もう一つの方のプーリングの方は、言ってみればこれは時価総額ですから、規模の格差。それを比較して、総体で規模の格差を比較しているということでよろしいでしょうか。
- ○畠山参考人
-
結構です。そのとおりです。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご質問はございますか。
どうぞ、山田委員。
- ○山田委員
-
三井住友銀行の合併のところですけれども、ここでの時価総額が合併の直前でどのような関係だったかお聞きできますでしょうか。
- ○梅山委員
-
時価総額、スポットで見るのが妥当かどうかはわからないのですが、例えば、合併の合意が平成12年4月21日でございまして、その前日、平成12年4月20日でさくら銀行の株価が730円、住友銀行の株価が1,558円でございます。株数を掛けました時価総額ですが、概数で申し上げますと、さくら銀行が約3兆円、住友銀行が約4兆8,900億円でございます。単純に住友銀行を1としますと、さくら銀行は0.61という計算結果になっております。ただ、スポットの評価は、合併比率算定上は使っておりません。もう少し長いレンジを使っておりますので、これは、単に計算したらそうなったということでございます。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
それでは、もし数字がわかればということですが、この合併期日近辺の株価、あるいは株式時価総額がわかりますでしょうか。特に、さくら銀行の方の株式時価総額というのは今わかりますでしょうか。
- ○梅山委員
-
3月の二十何日かでなくなってしまいましたので、それは手元にはないのですが、3月末の旧住友銀行の株価が1,270円でございまして、それからさかのぼる約1カ月間は、ほとんど合併比率に対応した1,270円の約6掛けといいましょうか、くらいでございました。今、計算機がないので計算できませんが。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。
- ○黒川委員
-
はい。
- ○斎藤部会長
-
八木委員、どうぞ。
- ○八木委員
-
直截な質問で恐縮ですが、特にみずほさんのケースですが、もし、パーチェス法が強制されたとしたらどのような不都合が生じたかというようなことを、少し実務家として聞きたいところですが。
- ○畠山参考人
-
今申しましたように、パーチェスというのは取得したということですよね。正直申し上げて、では第一勧銀が興銀と富士を買ったかということ、ないしは富士が一勧と興銀を買ったかと、興銀がだれを買ったかというのは、だれかがだれかを取得したかは一概に言えないと、決められないと。これは全く私の個人的な意見になりますが、それぞれの事業特性を持った会社があったわけで、だれかがだれかを買ったかというのはなかなか言いにくい。機能面でもそうなっていないということで、八木委員の質問へのお答になるかどうかわかりませんが、正直申し上げて、実務的にはそれは判別しにくいということでございます。
- ○八木委員
-
ということは、本当にパーチェスだけという場合だと、このような組み合わせがやりにくかったろうなというようなことになるのでしょうかね、現実に。
- ○畠山参考人
-
そうですね。多分できなかったのではないかと言うと言い過ぎかもしれませんけれども、いわゆるアメリカの合併ですと、だれかがだれかを取得したということできちっと株の純資産価値を出して、株の純資産価値に似た、経営陣で3人対3人、1人というような形にするということは極めて一般的ですし、非常にわかりやすいですよね。そういう意味からいって、これは日本的な慣行だというと、必ずしも褒められたことではないのかもしれませんけれども、事実としてそういう形になっているのかなということでございます。
- ○八木委員
-
非常によくわかりました。ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
もう既にご質問というところは脱却しておりまして、きょうのメーンテーマ、つまり事例をご報告していただく主な目的が、プーリングの可否とか取得側企業の特定の問題、あるいは承継する資産負債の評価の問題ということでありますので、きょうの事例のご報告を承った上で、そういう一般的な問題に絡めてご議論いただければと思いますが。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどさくら銀行の普通株式の時価総額がどのぐらいになるのかお聞きしたのは、もし仮に、ここはパーチェスであれば、どのぐらいのれんが発生する可能性があったのかというようなことを推定し、そして、そののれんの中身が、先ほど6つか7つ山田委員がおっしゃったものとどのような関係があるのかということを少し頭の中で想像してみたいという意図があったからです。その辺、かなり土地とか、それから有価証券について時価評価していますから、それとの関係でのれんが少しは概算で推定できるかなと思うのですけれども、どうでございましょうか。
- ○梅山委員
-
まず、先ほどの時価総額ですが、少し住友銀行の株価を言い間違えまして、3月末が1,120円でございました。したがいまして、計算からいいますと、その6割で、672円見当がさくら銀行の理論株価のはずでございまして、先ほど昨年の4月20日時点、さくら銀行の株価が730円で、時価総額約3兆円と申し上げましたので、ざっと計算いたしますと、2兆7,000億円前後が計算上の時価総額ではなかったかと思います。
以上が時価総額でございまして、もう一つご質問の趣旨がわからないのですが。
- ○黒川委員
-
合併期日の普通株式の時価総額が幾らぐらいになって、優先株の時価総額と合わせて概算で仮に合併対価を測定したとして、それから土地はほぼ時価ということになっていて、有価証券について、若干、含み益が2,000億円ありましたので、そのようなものを差し引くと差額が出てくるのではないかと思ったのです。そこで、今ざっと考えてみると、普通株式数が、約40億株ぐらいですか。40億株に約670円ぐらいを掛けてみると、大体2兆円ぐらいになりますか。
- ○梅山委員
-
40億円掛ける約670円ぐらいですので、2兆7,000億円ぐらいかと思いますが。
- ○黒川委員
-
それに優先株の時価というのは幾らぐらいですか。
- ○梅山委員
-
発行価格が8,000億円です。1株当たり1,000円で、8億株を発行しているということでございます。
- ○黒川委員
-
そうすると、今の概算でいくと3兆5,000億円ぐらいが資本の時価総額もどきの数字になるかもしれない。それから引き継ぎ資産のわかっている範囲内での時価総額を引くと、どのぐらいになるのでしょうか。
- ○梅山委員
-
14ページに承継資産、純資産が書いてございます。これは資本金が5,239億円。その他を含めました資本勘定が1兆8,542億円ということでございますね。
- ○黒川委員
-
そうか。そうすると、約1兆7,000億円ぐらいは差額が出てきてしまう可能性があるということですか。
- ○梅山委員
-
今の計算ですと、そうなります。
- ○黒川委員
-
ありがとうございます。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はございますか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
いずれの方でも結構ですけれども、少し常識的な想定で、借方のれんが生じるようなケースで、仮にパーチェスを採用したとした場合ですけれども。そのときに、会計ルールで償却しなくてよろしい。ノーマルのケースで、そんなに早々、簡単には減損しないという場合にはかなり資本が大きくできるわけですが、銀行にとって自己資本比率規制という制約があるので、その点から、アメリカのようなルールであれば、パーチェスが魅力的な選択肢になるのかならないのかということをお伺いしたいのですが。
- ○梅山委員
-
まず、事実関係として、のれんの部分は、自己資本算出上、資本から控除されておるのではないかと思うんですが。したがって、自己資本比率計算上、たしか効果がないというか、マイナスというか、今は正確なところがわかりません。
- ○斎藤部会長
-
規制上、カウントされないということですね。
- ○畠山委員
-
はい。いわゆるBIS比率を出すときに、いわゆる資本であるTier1という部分と補完的なTier2というのがございますが、のれんについてはこのTier1の控除項目という形で、その分を落として資本をみると、このような形に今のBIS規制上はなってございます。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
そうすると、プーリングとパーチェスの選択に当たって、自己資本比率という観点からいうと、それはニュートラルであると考えてよろしいわけでしょうか。
もう少しつけ加えますが、時価が容易にわかるようなものは基本的に時価評価しておりますし、多くの銀行も改正土地再評価法を使って再評価してしまっているので、この他にどんな選択肢が一体あったのだろうか。事実上、余り変わらないような感じもしているのですが、特にこのパーチェスとプーリングは、そうなると全く違いはなかったというように聞こえるのですが、いかがでしょうか。
- ○畠山参考人
-
これはまた個人的な意見になりますが、結局、経営としてどのようなビジネスモデルで、何をしていくかという判断が一つあるということではないか。今、この企業会計審議会の中で、三井住友さんの合併と、みずほは、多分、企業会計上、対極、両極にある部分なのか――一つは合併で全部の機能が一つになっている、片や、将来的に分社してばらばらにする、機能ごとに何とかするという――というように私はこのそれぞれのビジネスモデルを理解しているのですけれども、その中で、今おっしゃられたような、どちらがどちらという判断はなかなかつけにくいのか。要は、会社経営として何を目指していくんだ。いわゆる機能としてこうしたい、ないしは一つの固まりとしてこうしたいという、その判断の中に会社があって、そこからやはり何らかの形の処理だとか会計だとかというものを選んでいく――選んでいくと言うと言葉が悪いのですが、模索していくというような形になるのかなというように私は思いますけれども。
- ○梅山委員
-
なかなか答えにはならないと思うのですが、例えば、銀行の資産の50%を超える部分というのは貸出金でございまして、この貸出金の日本における売買市場というのがほとんど未成熟で、マーケット価格はないに等しいということを考えますと、評価するもの、例えば有価証券とか土地というのは評価が極めて容易かと思いますが、評価ができない部分も極めて多いのかなという感じがいたします。
- ○斎藤部会長
-
もう少し具体的に、そのインプリケーションをご説明願います。
- ○梅山委員
-
バランスシートは業種によって違いますが、銀行の価値を計算するときに、客観的な時価を評価する資産というのは限られてくるのではないかと思っております。
- ○斎藤部会長
-
それは、パーチェスを使ってもプーリングを使っても、その部分に関しては特に違いはないということでしょうか。
- ○梅山委員
-
パーチェスで価値が幾らあるのかという計算ができないので、パーチェス法の適用は困難ではないかと個人的には思っております。
- ○斎藤部会長
-
そうですか。
ほかにご発言はないでしょうか。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
畠山さんに少しお伺いしたいんですけれども、このようなケースにフレッシュ・スタートがいいという議論があるわけですけれども、そういうことを主張される方に対して、実務で実際に、先ほどおっしゃられた若干日本的な要素といいながらも、どこがどちらを買ったわけでもないということをおっしゃっているのですが、それは新しいリスクをつくり出した、今までと違うものをつくり出したという観点から、ではフレッシュ・スタートはいかがですかということについては、どのようなご感想をお持ちでしょうか。
- ○畠山参考人
-
大変難しい質問でして、フレッシュ・スタートは、ある意味でプーリングだけれども、全部時価評価してみなさいね的な感じがあるかと思うのですけれども、これはもう、正直申し上げて、学術の世界を離れた実務の世界というお答えでしか多分できないと思うのですが、仮に今、私どものみずほというのは、先ほど梅山委員もおっしゃられましたように、貸出金が80兆円ぐらいあります。それで、連結子会社は400社ぶら下がっているという膨大な――資産規模が世界一ですが、それをフレッシュ・スタートの時価評価を行うという、その実務的な大変さというんですかね、それをどのように考えたらいいんだろうかと。例えば、アメリカ、貸金一つにとっても、アメリカのように売却マーケットがあるわけでもありませんし、アメリカの貸金の評価というのは、担保処分するなら担保処分の価格にしなさい、貸金のマーケットで値付できるものは値付する。何か3つぐらい選択があって、そのどれかにしなさいというぐらい、やはり貸金の評価は難しい世界なんですね。そのままですと、まず80兆円の貸金をどう見積もるか。それから、有価証券にして値があるとすれば値があるということですが、そういう意味で、答えになるかどうかわかりませんが、実務的なハードルは極めて高いということではないか。実務での制約が、我々、実業界に身を置く者とすると、まず一つ、非常に難しいのではないだろうかというのが本音のところでございます。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。もし、みずほからご出席くださったほかの参考人の方でご発言があれば承りますけれども。
- ○米沢参考人
-
今、山田委員の方からご質問があったフレッシュ・スタートのところですが、私ども、まさに株式移転で企業結合した当事者ということで申し上げますと、みずほフィナンシャルグループという新しい企業体を結成するということにはなっているわけですが、銀行の経営を、例えば人の面、あるいは経営資源の面、それからそれの執行体制の面と、3つの面から見ていった場合に、いずれの要素につきましても、全く新たなものがスタートしたということを本当に言い切れるのかなというのが感想としてございます。
例えば、事業の特性なども、それぞれの銀行でこれまで営んできたものを、そのまま引き継ぎ、いいところを再編成、統合して、継続していくということですし、執行体制につきましても、いずれの銀行の流儀を色濃く残してということではなくて、それぞれの長所を持ち寄るということでございます。それから、まさに如実にあらわれておりますのは、現在の役員の構成であるとか、あるいは執行役員の構成なども、そういったところを十分踏まえた上で決めて運営していっているところですので、必ずしもすべてが新しく変わったものとして、これまでずっと認識してきた、会計的な基礎と申しましょうか、そういったものまですべてここで一種の断絶が起こるような形というのが実態として本当になじむのかどうかというところについては、当事者としまして感想めいたことで申し上げますと、少し実感と異なるのではなかろうかなという印象を持っております。
以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
米沢参考人に少しお聞きしたいのですけれども、そうしますと、企業内の体制としては、それぞれの以前の1行ずつが持っていた体制、リスク等をそのまま引き継いだのが実感というように理解しました。それぞれの銀行の株主という観点にたってみると、それぞれが持っていたリテイルに対するリスクですとか、インベストメントバンクに対するリスクというのは、このようなものができることによってやはり変わったと言わざるを得ないのか。その辺はどのようにお考えでしょうか。
- ○米沢参考人
-
私どもの例よりもはるかにわかりやすい例で、例えば米国でもこういった再編が多くございますが、先般、新聞にありましたGEとハネウェルのように、それまで、例えば全く違う会社、事業を持っているところが、結合の当事者となることによって投資の質が完全に変わってしまうというケースであれば、今おっしゃられたようなこともあると思います。ただ、私どもの例で申し上げますと、業態として金融業という一つの枠の中にあるということ。それから、完全にそれもセパレートされた形でこれまでおのおの独立してやっていたというわけではありませんで、それぞれ強み、特色はありますけれども、先ほどの説明のとおり、個人から法人までの一通りのラインは持っていてやっていたわけですので、今までの投資対象の事業分野が完全に変わってしまうとか、そういったことを言い切るというほど変わったという感想は当事者としては持っておりません。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。
ほかにご発言はございますでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
直接この例ではなくて、山田委員にお願いということですが、このケースで恐らくフレッシュ・スタート法を使うと、明らかに自分が発行する株式価値総額で自分の純資産を評価することになるわけですが、この場合、論理的には際限なく広がりかねなくて、例えば業務提携をやったときにも、それによってどのような形のつながりをもって再評価のチャンスとするかということですが、それは、実は、形式より実質といいながら、形式上、法律上、統合の形をとっているときだけ再評価する。そうではなくて、契約あるいは業務提携クラスだとやらないということになると、ある意味で逆のアービトレージョンを生みかねない。つまり、そこはやはり形式を重視してしまっていて、実と離れたことをやる――すべてのケースということではないのですけれども、そういう危険を持っているのではないかということをぜひ海外に向かって言っていただきたいと思います。
- ○山田委員
-
今のようなケースがオーストラリアであるような話がありまして、その辺の問題意識は一応持っています。今回、どこまで議論できるかわからないのですが、多分正しく理解したとすれば、実質が同じであれば、形態ないしは契約というだけでも同じことが起こり得ることをカバーしなければいけないという問題点。よくわかりました。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はございますか。
では、黒川委員、それから辻山委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどのフレッシュ・スタートに関連しますが、フレッシュ・スタート法の場合は、のれんを所有主から控除するやり方が普通は念頭に置かれる方が多い。要するに、公正価値プーリングが多いと思います。そこで、三井住友さんの例の場合ですとわかりやすかったのですが、不動産と、それから有価証券についてはほぼ時価。有価証券については約2,000億円、逆に資産を増加しなければならないのだろうと思います。先ほど概算で、1兆円以上ののれんが出るのかなと思ったのですが、所有主持分からの控除説でいけばその分は資本から控除しますから、そうすると、実際に資産の時価をどの程度正確に測定することができるかということがポイントになってくるだろうと思います。そこで、先ほど委員の方から、貸付金について非常に時価の算定が難しいというようなご意見が出たのは、私としては新たな知見というか、新たな論点だったように思ったわけですけれども、そのほかに、実行上の問題で時価評価が難しいようなところが特に金融業の場合はございますでしょうか。あったら教えていただきたいと思います。
- ○梅山委員
-
反対側の預金の方が一番――最近、金融商品の全面時価会計の議論もありますが、これは日本の銀行だけではなくて、世界の銀行において調達、特に預金の時価評価は困難ではないかと思っております。資産の方では、多分貸出金が相当部分だと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
では、辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
山田委員へのご質問ですが、先ほどIASBの今後の議論の中で、現行では特に減損処理がFASB方式とかなり違う方式の議論がされているようですが、一方で、FASB方式の方が緩いのではないかという受けとめ方もあるということですが、FASBは、のれんの減損処理方式に変えると同時に、今回FASBの中で言っていますのは、無形資産に計上する部分というのをかなり厳格にしていくと、結果的に、従来ののれんの償却方式より一時的には償却部分が多くなるのではないかということも議論されていて、無形資産の問題は今後FASBではかなり重要な問題に上がってくると思うのですが、IASBでは、その辺はどのような感じでしょうか。
- ○山田委員
-
無形資産の問題も基本的に同じロジックで取り上げております。ですから、議論している枠組みは、今回出た第141号、第142号の枠組みをそのままほとんどすっと受け入れているということです。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
本日の部会はこれで終了させていただきます。参考人としてご出席いただきまして、大変ありがとうございました。
次回の部会は、11月30日金曜日の午後を予定しておりますが、詳細につきましては改めて事務局からご連絡申し上げます。
次回も、今回同様に、わが国の企業結合の事例につきまして関係者からヒアリングを実施することを考えております。
本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。これで散会させていただきます。