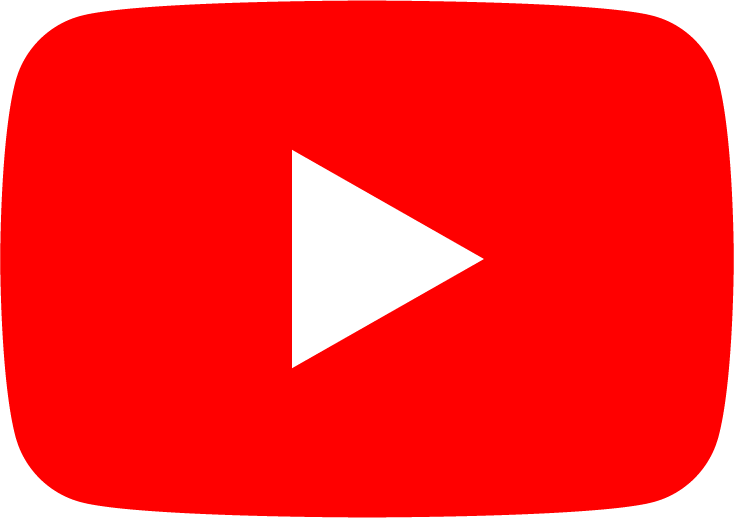- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「第一部会」
- 企業会計審議会第20回第一部…
平成14年7月30日
金融庁
企業会計審議会第20回第一部会議事録について
企業会計審議会第20回第一部会(平成14年6月7日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第20回第一部会議事録
日時:平成14年6月7日(金)午後4時00分~午後6時09分
場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室
- ○斎藤部会長
-
定刻になりましたので、ただいまから第20回の第一部会を開催いたします。
委員の皆様方には、お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
前回までの審議におきまして、パーチェス法とプーリング法のそれぞれについて意見交換を行ってまいりましたが、そこでご指摘を受けました論点のうち、商法と関係のある論点などについては、なお検討すべき課題として残されているところであります。
そこで、本日は、商法に関係する論点について神田部会長代理に整理をお願いしておりますので、ご報告をいただいた後に意見交換をお願いしたいと考えております。
また、パーチェス法における被取得企業の資産・負債の評価に関する論点につきましても、松岡委員に整理をお願いしておりますので、こちらについても同様に意見交換をお願いしたいと存じます。
なお、商法に関係する論点の方に時間を多く配分した方がよいであろうと思われますので、進行の都合上、パーチェス法における被取得企業の資産・負債の評価方法に係る論点の方からご審議をいただきたいと思います。
それでは、松岡委員から、よろしくお願いいたします。
- ○松岡委員
-
それでは、お手元にございます資料1のレジュメに従いまして、お話をさせていただきたいと思います。
大別いたしますと、評価する際の大原則、あるいは大前提と表現した方が適切かもしれませんが、そちらの点と、今までの部会で取り上げられたか、あるいは今後、議論がもう少し必要と思われる個別論点に関する考察という2段階でお話しさせていただきたいと思います。
まず初めに、評価する際の大前提がどのようなものであるかということでございますが、まず、記載のとおり、企業結合取引は等価交換の取引であって、取得企業による被取得企業の事業の購入取引と捉えるということでございます。
そして、購入した資産・負債はその購入取引時点での公正価値で測定を行うということでございまして、このような考え方は会計の一般原則と整合的であると考えられているようでございます。
そして、具体的に対象資産・負債に関して活発な取引市場が存在する場合には、その市場価値が通常は最も客観的な価値であろうというように考える。したがいまして、逆に活発な取引市場が存在しないような場合には、その価値を何らかの方法により見積もることが必要となってきます。そのような場合には、原則といたしまして、市場参加者が利用するであろう情報ですとか前提等に基礎を置くという考え方でございます。そうではなくて、具体的には市場参加者が利用するであろう情報ですとか前提等を入手できないような場合、あるいは通常の市場参加者が知り得ないような情報等を見積もりを行う企業のみが知っているような場合には、見積もりを行う企業が利用可能な独自の情報や前提等に基礎を置くということも考えられているようでございます。
今、申し上げたことが大きな前提でございまして、そのような前提に立った上で、今まで部会で取り上げられた個別論点、具体的には棚卸資産、固定資産、繰延税金資産・負債の三つの点に関してお話し申し上げます。
まず、棚卸資産に関してでございますが、取得企業は被取得企業の事業を購入し、その事業を継続的に営むことが前提にされていると考えますと、取引日現在の事業投下過程における公正な評価額で評価をすることが首尾一貫するであろうと考えられます。そのような前提に立ちますと、その場合の公正な評価額は、原材料については再調達原価、仕掛品や製品等につきましては材料代等に加工代を加えたコストと考えられるように思われます。
国際的な会計基準におきましては、今、申し上げた仕掛品ですとか製品等については、算定の便宜上、売価から処分費用、正常利益、完成までの必要なコストを控除した額というような指針の表現となっているのではないかと考えられます。
続きまして、固定資産に移らせていただきます。
固定資産は、例えば工場の建屋ですとか機械のようにキャッシュ・フローを生み出すのに直接貢献するものですとか、あるいは本社の建物のようにキャッシュ・フローを直接には生み出さないようなものなど、その形態は多種多様でございまして、とりわけ後者のキャッシュ・フローに直接貢献しないものについては、将来キャッシュ・フローの現在価値を算定することは困難な場合が多いように思われます。
恐らく今、申し上げたような事情等を勘案いたしまして、国際的な会計基準では、一般的な評価の指針といたしまして「市場価値」という表現を使用しているのではないかと考えられます。また、市場価値と申しましても、とりわけ土地につきましては専門的な知識を有しない者が算定することは非常に困難でございまして、また、客観性も確保し難いことから、専門家による鑑定評価額を利用することも想定されているようでございます。
その一方で、コストベネフィットの観点からは、そのような鑑定評価額を強制はしていないというような実務になっているのではなかろうかと考えます。
2枚目に移りまして、今度はわが国に目を向けてみますと、ご承知のとおり、土地を取り巻く環境等の特殊性がございまして、例えば大規模工場ですとか近郊が開発されていない郊外地のようなものについては、すべて比較参考とすべき適切な土地が存在する保証はございません。また、客観的な評価額を算定することが非常に困難な状況にあるように考えられていようかと思います。
仮に今、申し上げたような客観的な評価が非常に困難な固定資産を、実際あるいは合理的に予想したキャッシュ・フローに基づいて算定した評価額と、これは結果といたしまして大幅に乖離することとなるような他の評価額で算定した場合、可能性としてどのようなことが考えられるかと申し上げますと、その後の減損判定に当たって直ちに減損が認識されてしまうような場合――これは結果として、その評価額が過度に高かったというような場合ではなかろうかと思います。逆に減損が半永久的に認識されないような事態――これは結果として、使用された評価額が過度に低かった場合が該当するのではないかと思いますが、そのような事態が生じないとは必ずしも言い切れないのではないかと考えます。
したがいまして、固定資産の評価方法につきましては、例えば汎用性のある機械装置ですとか、キャッシュ・フローの獲得に直接貢献はしませんが活発な市場が存在する特定の土地や建物のようなカテゴリーと、もう一つといたしましては、特殊な機械装置や大規模工場のように活発な市場が通常は存在しないようなカテゴリーに大別した上で、前者については市場価値を参照とする、後者については見積キャッシュ・フロー等に基づくですとか、基準においてはその程度の基本的な考え方を示すという方法も考えられるのではないかと思います。
最後に、繰延税金資産・負債に関して申し上げさせていただきます。
まず、企業結合に関する国際的な会計基準におきましては、企業結合の際に受入処理した被取得企業の資産・負債――この中には取得企業が企業結合後において利用可能な、企業結合前に発生した被取得企業の繰越欠損金ですとか繰越税額控除等が含まれますが、そのようなものに係る繰延税金資産・負債の認識に当たりまして、企業結合後の合理的な予測に基づいて決定するというような程度の内容だけが規定されているようでございます。
例えば、米国基準におきましては、企業結合の際に被取得企業に関連して認識した繰延税金資産の回収可能性が、具体的にはその後、高まりまして、その結果として企業結合前に発生した被取得企業の繰越欠損金等に関して認識される繰延税金資産が増加するような場合には、その増加額を、その企業結合に関連して発生したのれん、次に非流動区分の無形資産、そして、その期の法人税等の費用の順に減額していくというような規定など、企業結合に関連する詳細な規定は、企業結合に関する会計基準ではなくて、法人所得税等に関する会計基準の中で整備されているようでございます。
簡単ではございますが、以上が今までの議論の中で取り上げられたものに関する考察の結果でございます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
ただいまのご報告につきまして、ご質問等がございましたらご発言いただきたいと存じます。
- ○山田委員
-
これに関連して、今、IASBでは偶発債務自体の評価を考えておりまして、企業結合時に被買収企業から引き継ぐことになる偶発債務については、その公正価値を見積もって、その見積もりで負債を認識するという考え方をとっています。今日の松岡委員のご説明では、その辺については特段触れられていなかったのですが、その辺はどうお考えでございましょうか。
- ○松岡委員
-
全く考えていないわけではございませんが、今日は今までの議論の中で、現行の実務に既にあるような論点に関連して申し上げさせていただきました。今のような偶発債務の問題につきましては非常に難しい問題でございますので、基準自体で取り上げるべき問題かどうか私の方でも判断がつかなかったので、割愛させていただいたわけでございます。
- ○山田委員
-
ということは、今後、検討されると理解してよろしいのでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
問題提起があれば、もちろん検討いたします。
- ○辻前企業会計専門官
-
偶発債務等につきましては、以前、2月の部会で金井委員にご説明いただいておりまして、特に何かございましたら、また機会を設けて検討したいと思います。
- ○山田委員
-
ほかに、ここでの議論にも影響があるかもしれませんので、最近IASBで議論されている事項について、若干ご紹介だけさせていただきたいと思います。
IASBの方では、パーチェス法一本にするという方向で、今、基準をつくっていますが、基準ができ上がったことを前提にしまして、パーチェス法を適用するに当たっていくつかの具体的な会計処理について企業結合の第2フェーズという形でFASBと検討を進めております。
その中で、今日ここでは直接触れられていないものに、アクイジション・リレイテッド・コストという、企業結合に関連して発生する、例えば弁護士に払う費用ですとか投資アドバイザーに払う費用ですとかについて、従来は、企業結合の対価の一部として配賦計算の中に含めるという考え方をとっていたわけですが、最近、FASBの方では、このようなコストは発生時のコストとして原価には入れないという方向に、従来の考え方を変更しようとしています。その前提には、今日も松岡委員のレジュメの最初にございますが、評価に対する大原則という中で、等価交換で行うということから、被買収企業の株主に払ったものが直接の費用、ないしはそこから出てくる資産の公正価値だけが企業結合の対価を構成し、直接、被買収企業の株主以外のアドバイザーなどに払ったものは対価を構成しないのではないかという考え方に基づいて、従来の考え方を変更しようとしています。
これについては先月、議論がありまして、IASBの中でも意見が分かれましたが、僅差で多数を占めているのはアメリカと同じように関連費用を発生時に費用処理するという方法で、今その方向で議論をしております。
この辺は、場合によっては議論が変わる可能性がございますので、まだはっきりとはいえませんが、従来のIAS22号の考え方を変える方向で検討しているということをご報告させていただきたいと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
アメリカの基準も国際会計基準も、例えば新株発行費については新株式の払い込みと相殺しているわけなので、場合によってはコンセプチュアルにそれと矛盾する可能性もあり得る議論になっているわけですね。ですから、場合によってはひっくり返る可能性もないとはいえないということでしょうか。
- ○山田委員
-
実は、今でき上がっているIASのドラフトでは、そのような発行費は直接それによって得た対価と相殺するというクローズが入れてありまして、そこの部分は従来の考え方を採用しておりますので、将来どうなるかわかりません。
- ○小宮山委員
-
これは松岡委員に聞いた方がいいのか、辻山委員に聞いた方がいいのかよくわかりませんが、固定資産のところで、最近は救済型の買収とか、つぶれた会社を買い取るというケースが結構ありますよね。そこで、減損会計とパーチェス法での、特に資産の評価の関係をどう考えるのかですが、土地・建物は市場価格でやるというお考えで、その後、機械その他については見積キャッシュ・フローという要素が入っているので、固定資産の取得価格とのれん相当額の関係をどう捉えるのかがよくわからないのですが、何かお考えはありますか。
- ○辻山委員
-
実は私も、今、小宮山委員の質問の前に、そこのところを松岡委員に質問しようとしていたんです。
評価する際の大原則の2に、購入した資産・負債はその時点での公正価値で測定する、そのような大原則が掲げられているわけですが、この場合の公正価値というのは、いわゆる市場価格であると考えられるわけです。その一方で、今ご指摘の固定資産のところになってくると、むしろ市場価値というのは種々、資産の経済価値といいますか、「企業にとっての価値」というと特殊な固有名詞というか、国際会計基準の中で別な意味がありますので、ここでは「経済価値」といっておきますが、経済価値が算定困難であるから市場価値が使用されているのではないかという指摘があるんですね。
ただ、上の前提あるいはパーチェス法、買収ということを考えますと、資産・負債については本来、市場価値をつける。実際に超過収益力というか、個々の資産にのれんがあるのかどうかわかりませんし、また、グルーピングの問題ともかかわってくると思いますが、そのようなものを資産の単位で認識して、それを個々の資産の取得価格とするのかということについては少し疑問がありますので、質問させていただこうと思った次第です。何をいっているのかというと、資産・負債については公正価値、いわゆる一般的な期待に基づく市場価格が付されるということからすると、キャッシュ・フローの見積もりが下の方で出てくるのはなぜでしょうかという質問ですが。
- ○松岡委員
-
まず、大原則のところで書かせていただいた二番目の公正価値というのは、私のイメージとしてはフェアバリューでございまして、原則的には、仮にそのような市場がすべて対象資産・負債にあれば、そのような一般的な収益力を反映した、いわゆるフェアバリューで評価すべきであろう、このようなことが大原則であろうということでございます。
現実問題として、そのような市場があるものについては、このような考え方に基づいて評価は可能だと思いますが、現実には必ずしもそうでないわけでございまして、そうしますと、そのような場合には何らかの方法で評価せざるを得ない。下の方、第四番目の「その価値」というのは、公正価値・フェアバリューという意味ではございませんで、フェアバリューの代替となり得るかどうかわかりませんが、そのような評価をする場合の価値という意味で使わせていただいています。したがいまして、将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値イコール、フェアバリューだとは私は当然考えておりませんが、結果として、何らかの方法で公正な評価額を算定する際には、そのようなものについては将来キャッシュ・フローを割り引く、例えばそのような方法あるいは要素を考慮せざるを得ないのではないかというような前提でお話しさせていただきました。
- ○辻山委員
-
わかりました。ありがとうございました。
公正価値といった場合には、市場価格プラス、その市場価格が観察できない場合にはそのほかの方法に基づいて算定された価値。これは今のご説明でわかったわけですが、割引現在価値には二種類ありまして、一つは、公正価値を導く代替的手段としてのキャッシュ・フローの割引現在価値。もう一つは、のれん含みといいますか、企業に固有のキャッシュ・フローを見積もって、それを企業にとっての主観価値に割り引く。ここでおっしゃっていることは、原則は公正価値である。市場がある場合にはそこで観察する。それ以外には、公正価値を導き出すための割引現在価値。このような理解でよろしいということがわかりました。
ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
よろしいわけですね。
- ○辻山委員
-
はい、結構でございます。
- ○斎藤部会長
-
基本的にはフェアバリューのプロクシーを話しているのであって、ザ・ファーム・スペシフィック・バリューをいっているのではないということでよろしゅうございますね。
ほかにご発言ございますか。よろしゅうございましょうか。
それでは、後で戻っていただいても結構でありますが、次へ進ませていただきます。
神田部会長代理に、合併と商法の会計制度についてのご報告をお願いいたします。
- ○神田部会長代理
-
まず、この会合に欠席を重ねておりまして、深くおわび申し上げます。
これまで皆様方の過去のご議論を議事録等で拝読させていただきまして、その中で、商法の問題に関係するのではないかと思われる論点がいくつかありました。したがいまして、それらをいわば論点という形でいくつか取り上げて、私の現時点における考え方を、お手元に資料2として配付させていただきましたレジュメに沿って、お話しさせていただきたいと思います。
まず、前提ですが、この部会が、合併会計の部会なのか企業結合会計の部会なのかという難しい問題があろうかと思いますが、本日は合併に限らせていただきたいと思います。また、その合併の中でも、わかりやすいという意味で、吸収合併という法的形態の方を取り上げさせていただきます。
もう一点、前置きといたしまして、自己株式に関連する論点がいろいろあるわけですが、これにつきましては相当複雑な論点もありますし、また、本筋からいいますと少し特殊な分野になるように思われますので、本日は省略させていただきます。
そのようなことで、以下、いわゆるパーチェス法関係についていくつかの論点、プーリング法関係についていくつかの論点、そして最後に、共通すると思われるものについて若干申し上げたいと思います。
まず、パーチェス法関係でありますが、一番目といたしまして、逆取得についてであります。
論点といたしましては、実際には被買収会社である、つまり買われる方の会社であるわけですが、これを法律的に商法上の存続会社、すなわち買収会社としたような場合に、この存続会社の資産・負債を時価評価することができるかという点であります。
この点につきましては、抽象論を申し上げますと、資産評価規定で時価評価が認められているもの以外を時価評価することはできないというのが現在の商法の立場であります。ただ、括弧内に書きましたように、資産評価規定といいますのは、平成14年改正と書きましたが、ついこの5月22日に国会で成立し、29日に官報に公布されました商法改正――これを「平成14年改正」とここでは呼ばせていただきますが――この改正によりまして、省令に委任されることになりました。
今日はお手元に条文をお配りしていなくて、大変申しわけありませんが、従来、商法には株式会社について、第285条以下に資産評価についての規定があったわけですが、資産評価についての規定はすべて削除されました。新しい第285条をご参考までに口頭で読み上げさせていただきますと、「会社ノ会計帳簿ニ記載又ハ記録スベキ財産ニ付テハ、第三十四条――これは残るわけですが――ノ規定ニ拘ラズ法務省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ価額ヲ付スルコトヲ要ス」と、このような規定に置き換えられました。したがいまして、平成14年改正が施行されますと、資産評価に関する規定は商法本体から法務省令に落ちるというか、委任されることになります。
しかし、当面は、考え方の変更がない限り、現在、商法本体で書かれていたものが法務省令に規定されることになると思いますので、考え方の変更があればともかく、現在の商法の考え方が当面そのまま省令になると仮定いたしますと、繰り返しになりますが、存続会社の資産・負債を時価評価することは認められません。
なお、以上とは別に、商法第413条の2という規定がございます。この規定は平成9年の商法改正で新設された規定で、この規定は今回の改正でも特に省令に変わったとか、そのようなことはありませんが、この第413条の2では規定上、何を決めているかといいますと、存続会社の資本の金額をどのように決めるか、どの限度で増加することができるかということを決めております。存続会社における増加する資本金の最大限度額を決めている規定ということになります。
その内容は、条文に即して簡単にいいますと、財産の価額から、まず消滅会社から承継する債務を引く、次に合併交付金を引く、最後に、いわゆる代用自己株として渡した分の簿価を引く、それらを引いたものが存続会社において増加する、あるいは増加することができる資本金の最大限度額だということを定めています。
この規定はどのような考え方に立っているかといいますと、消滅する会社から財産、あるいは負債を引けば純資産といってもよいと思いますが、それが引き継がれて、いわばそれを対価に存続会社が新株、あるいは代用自己株の場合もありますが、典型的には新株を発行する――このような考え方に立っているわけですから、いうまでもないことですが、そこで存続会社の方の財産を、例えば資産・負債を時価評価することは想定していないということにならざるを得ないように思います。
この辺は詰めて考えなければならないところですが、私には、どうも現時点での感触としましては、存続会社の資産・負債の時価評価を認めるためには、商法第413条の2を改正する必要があるように思われます。
次の論点に移らせていただきます。
次は、のれんの償却年限ということでして、5年を超える償却年限を設定したり、あるいは償却しないとしたり、あるいは償却しないとして減損処理のみ等としてよいかということであります。
この点につきましては、そこに書きましたように、仮に企業会計の方のルールがそのようになったということであれば、商法の方は、今、省令に落ちておりますが、この改正を検討することになると思われます。ご存じのように、今回の改正までは商法第285条の7という規定がありまして、念のため口頭で読ませていただきますと「暖簾ハ有償ニテ譲受ケ又ハ吸収分割若ハ合併――合併が今の場合ですが――ニ因リ取得シタル場合ニ限リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得」続きまして「此ノ場合ニ於テハ其ノ取得価額ヲ付シ其ノ取得ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」というわけであります。この規定は今回の改正で削除されました。しかし、通常であれば、省令にはこれと同じ規定が設けられることになると予想されます。
しかし、今、申し上げましたように、企業会計の方のルールが変更されるということであれば、省令も、企業会計のルールに合わせる形で改正がなされるのではないかと予想されます。
なお、ついでですが、そのようになった場合に配当規制との関係をどうするかという問題がございます。現在は、第285条の7ののれんについては何ら配当制限はありません。しかし、一定の繰延資産に配当制限がありますのと同様の配当制限を設けるということも、十分考えられるのではないかと思います。
ついでに、余計なことかもしれませんが、配当規制についての第290条第1項という規定自体は、今回の商法改正でもそのまま残っています。ただ、配当制限の対象となる項目は三つだけが現行法のまま残りまして、それ以外は法務省令に委任されています。具体的に申しますと、第290条第1項の1号から3号、これは資本金、法定準備金、それからその期に積み立てるべき利益準備金ですが、これらを差し引く。何から差し引くかというと純資産額ですが、これは法律上、残っておりますが、現在の規定では、このほかに4号と6号というのが商法上あります。この4号が、一定の開業費等の繰延資産が多額にある場合の制限でして、6号が、いわゆる株式等評価差額金と呼んでいる有価証券の時価評価した差額金であります。このほか自己株式は控除方式ですから、条文上はあらわれておりませんが、自動的に配当制限がかかる、このような構造になっております。
このうちの、一定の繰延資産が多額にある場合を含めて、評価差額金の部分も今回の商法改正で条文上からは削除されまして、そのかわり、新しい第290条第1項4号として、法文の言葉を読み上げますと「其ノ他法務省令ニ定ムル額」という表現になりました。したがいまして、繰延資産あるいはこの時価評価差額金等、今、法律上定められているほかに、何をさらに配当制限の対象とするか、すなわち配当可能な限度額から差し引くかというものは、すべて法務省令、現在、商法施行規則と呼んでいますが、それで定められることになったわけです。
したがいまして、こののれんが改正される場合には、一方で、現在の第285条の7に相当する省令の規定の改正が、多分、企業会計のルールに従ってなされると思いますが、他方、商法の配当規制の立場から、現在の一定の繰延資産にかけられているのと同様の配当制限というものが設けられる可能性があると考えられます。ただ、これも省令の改正という形で行われることになります。
以上が二番目です。
次に三番目でして、差額のれんの計上。私も、どうもこの意味が昔からよくわからないでいるのですが、のれんを被合併会社の時価純資産と発行株式時価の差額としてもよいかということであります。
この点については、私は昔から、差額のれんというのは特に問題ないと考えておりましたし、実際問題として差額、どの資産にも割り振れないようなものこそがのれんではないかといってよいのではないかと思ってきております。
そこに「被合併会社の時価純資産」と書きましたので、先ほどの逆取得との関係で、被合併会社の純資産額は時価評価するのか、簿価で引き継ぐのかということについて一言だけ申し上げたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、商法は消滅会社の方の、いわゆる純資産額を引き継ぐことを予定しているわけです。問題は、この純資産額は簿価なのか、時価なのかという問題であります。
この点については、直接これを正面から規定した商法の規定はありません。しかし、先ほど申しました規定等から、この純資産額をいわば引き当てにして、その対価として新株を発行する、そのような考え方に立っていることは間違いないわけです。
そこで、一般の新株発行の場合を考えてみますと、いうまでもないことですが、その資産は公正な価値に対して、公正な価値分の新株を発行しなければならないわけでありまして、そうでないと、もちろん新株発行が不足することになるわけです。したがいまして、消滅会社の純資産額、もう少し正確にいうと資産・負債の額になると思いますが、これを合併に当たって公正価値――ここでは時価と同じ意味で使っていますが――で評価して、それに対して存続会社が新株を発行するということは、これは商法は、当然認めているという表現がよいかどうかよくわかりませんが、認めていることであります。
そこで、差額のれんというのも、ここに書いてありますが、その時価純資産とそれに対して発行される時価の差額を、のれんという形で計上することも差し支えないと考えられます。
次に、四番目といたしまして、いわゆる「負ののれん」などといわれていると思いますが、その会計処理の問題であります。
被合併会社の純資産額が発行株式の額を超える場合、この差額を、いわゆる資本準備金としない処理を採用してよいかという論点があろうかと思います。論点をうまくここに書けていないかもしれませんが、要するに、個々の資産に割り振ったりしてよいかどうかということであります。といいますのは、現在の商法の規定では、後ろの方に書きましたように、結局、受け入れた純資産額というものがありまして、合併交付金とか若干引くものはありますが、これが原則、先ほど申しました規定で増加する資本金の最大限度額になります。それまで資本金を増加しない場合にはどうなるかといいますと、その差額は資本準備金にしなければならないという規定があります。これは第288条の2という資本準備金を定めている規定の、第1項5号であります。ただ、その例外は、配当可能利益を引き継ぐ場合はそこは引き継げますよ、すなわち資本準備金にしなくていいですよというように、さらに第 288条の2の第5項で定めている、そのような構造になっております。したがいまして、差があると、原則、資本準備金にいってしまうのではないかというのがここの論点であります。
ただ、この点につきまして商法では、どのような純資産額を受け入れるかということは、企業会計に委ねられていると思われます。したがって、そこの表現がよいかどうかはよくわかりませんので、最後に受け入れた純資産額が問題であるという表現を使ってしまいましたが、要は、企業会計で何をもって受入純資産額とするかということは、企業会計の方で決まれば、それは公正な会計慣行として斟酌されると思います。
したがいまして、個々の資産に割り振ったり、まとめて控除したり、負債に計上したり、どのような処理であっても、企業会計の方でそれが認められればよいと思います。
その結果、最終的にというか、最後にといいますか、受け入れた純資産額が決まります。そうしますと先ほどの第413条の2で、それから合併交付金等――とそこには書きましたが、合併交付金等の「等」は代用自己株のある場合の代用自己株の簿価です――を減額しますと、これが増加する資本金の最大限度ということになります。なお、最小限度の規制はありません。
最大限度まで資本金を増加しないとどうなるかといいますと、その差額は資本準備金としなければなりません。先ほど申しましたこれが原則のルールでありまして、例外として、配当可能利益を消滅会社から引き継ぐ場合の例外が――その部分については利益準備金とあわせて引き継がなければなりませんが、第288条の2の第5項で例外が認められている。このような構造になっています。
次に、プーリング法関係についてであります。
まず第一に、このような論点でよいのかどうかはっきりしないのですが、資産の含み損の引き継ぎということで、被合併会社の資産の含み損をそのまま引き継いでよいかということです。この点については、問題なしと書きましたが、これは企業会計でよいといっていれば問題ないという意味で書いています。先ほどの、消滅会社の純資産額をどのような形で引き継ぐかについては、商法は何もいっておりません。そのようなことでありますので、含み益があれ含み損があれ、企業会計の方でその引き継ぎがよろしいということになれば、商法上も、それで受け入れてよいということになると思われます。
2ページに行かせていただきます。
同じような問題かと思いますが、合併時の欠損金の引き継ぎといたしまして、被合併会社の欠損金をそのまま引き継いでよいかということであります。この欠損金というのは、会計上の定義と法律上の定義と多少違うのかもしれませんが、いずれにしても、関連する論点としましては、被合併会社が債務超過の場合に合併できるかという点、あるいは表現はよくないかもしれませんが、合併直前に欠損填補ができるかといったような論点があるようであります。
そこで、まとめてそこに書いてみましたが、まず第一に、いわゆる債務超過会社の合併ですが、これは認められないと解されています。全く例外がないかというと、若干異論の余地はありますが、債務超過会社というのはマイナスの会社ですから、マイナスの会社に新株を発行するのは論理矛盾でありまして、それから商法で、いわゆる資本充実原則などといわれていますが、株式を発行する以上、それはプラスの資産が入ってくるということが前提になっていますので、トータルとしてマイナスであるという場合には、これは合併はできないというのが従来の考え方であります。
そうでなければ欠損金の引き継ぎは可能というのは、ここでの欠損金の定義は、全部時価評価した場合にはマイナスではないという意味です。会計上の欠損金を引き継ぐことは可能であります。「可能であります」という意味は、繰り返しになりますが、企業会計がそれを認めるのであれば商法上も可能。そのような意味です。
それから、合併直前に欠損填補ができるかということですが、これも欠損填補の意味ですが、いわゆる欠損の填補――といういい方は少しはっきりしませんが、例えば、法定準備金の取り崩しによる欠損の填補というようなものは定時総会での損失処理によるというのが商法上の一般の理解であります。したがって、これは定時総会で行うというのが普通の考え方であります。
この辺は少し、法律上の定義と会計実務上の定義と、私がいろいろな場合を混在させてものを申しているように思いますが、合併の際に消滅会社の資産の評価益を出しまして、それによって実際に生じている欠損を填補することは認められています。商法上は、これは欠損填補とは呼んでおりませんで、先ほど申しました、純資産額の受け入れに際して消滅会社の資産を時価で評価するということにすぎないからであります。
これまでも、もとの税法の規定ですね、新しい企業再編税制になる前までは、大体このようにして合併をするというのが普通の実務だったように思います。
次へ移らせていただきます。
過年度計算の修正再表示。これはたしか前にもこの場でご質問をいただいて、うまく答えられなかったわけでして、今日もうまく答えられないのですが、論点といたしましては、結合以前の決算を合算して表示してよいか、あるいはもう少しいいますと、派生論点として掲げました、会計処理を遡及してよいかということであります。
この問題は、大きく分けますと「遡及させる」という方が主として問題になりますが、情報提供の面と配当規制の面とに区別して考える必要があるように思います。
情報提供、すなわち開示の面では、これは遡及しても、より真実を伝えた方がよいわけですから、それは商法上も可能であるように思われます。ただ、商法上は、開示面も含めて計算書類には確定という手続がありますので、既に確定された計算書類を直すと、そこまで遡るような場合には、そこについて少なくとも直す時点で再確定の手続をする必要があると考えられます。
これに対して、配当規制の面ではどうか。これもどこまで遡るかという問題に関係しますが、既に利益処分がなされてしまったというような場合には、既になされた利益処分を遡って計算し直してみたら配当可能利益がなかったとか、仮にそのようなことになったとしても、これは既になされたものの効力に影響を与えるというわけには、法的にはいかないと思います。これは中間配当も同じですが、そこまで遡らないのであれば問題ないと思います。
そのようなことになりますので、開示面では、考え方としては可能。配当の面では、既になされた利益処分や中間配当の効力には影響を及ぼさない。ここが今、矛盾なく、調和してできるかどうかという点が私もまだ詰め切れておりませんので、大変申しわけありませんが「詳細はなお検討が必要である」などと書いているのですが、考え方の基本は、前にもこの点は申し上げたかと思いますが、今、申し上げたようなことであります。
大体以上ですが、共通する点として二点申し上げたいと思います。一点は私が気になっている点でして、もう一点は、過去の議事録を読ませていただいたらこのようなご指摘がありましたので、それについてのお答えといっては何ですが、商法の観点であります。
まず第一点目、これは私が少し気になっている点ですが、商法は、先ほどの条文で、配当可能利益の引き継ぎを認めています。すなわち消滅会社に100なら100の配当可能利益、配当可能な限度額があった場合には、これは合併後もその100は存続会社が引き継げますよと認めています。ですから、平たくいえば、存続会社の方に例えば200の配当可能利益があって、消滅会社の方に100があった場合には、合併後は300を配当可能とできますよということを認めています。これは、なぜそのようなことを認めているかといいますと、合併することによって配当できる額が減ってしまうのは問題であって、それは、その範囲で配当可能利益の引き継ぎを認めてよいという判断に基づいているからであります。
この判断は、パーチェス法かプーリング法かという話とは別の次元の判断であります。したがって、仮にパーチェス法をとったとしても、この配当可能利益の引き継ぎは認めざるを得ない――という表現がよいかどうかわかりませんが、商法上は認められることになります。
このようなものを引き継ぐものは、そもそもプーリング法と呼ぶんだというのが、あるいは皆様方の認識なのかもしれません。ここはもう用語の問題だと思いますが、今この部会で議論している意味におけるパーチェス法が採用されたとしても、商法は配当可能利益の引き継ぎを認め続けるでしょうし、その趣旨は、今、申し上げましたように商法の方の趣旨があるからであって、それが変わるのは、私は適当であるとは思いませんし、したがって、商法の引き継ぎの規定というのは多分、引き続き存続するのではないかと思います。
もう一点ですが、過去のこの部会の議事録を読ませていただきまして、次のようなご指摘があったように記憶します。私の誤解かもしれませんが、いわゆる合併交付金を払うのですが、これはなぜ消滅会社の株主にだけ払うのですか、また配当可能利益がないのに合併交付金を払ってしまったら、多大な資産――資産というか、現金で払う場合でいいますと現金――の流出ではないでしょうかというようなご指摘があったように思います。
その点についてですが、商法の考え方では、合併交付金というのは通常、合併比率の調整のために支払われます。実務では、このほか「配当見合い」あるいは「配当に代えて」という表現をよく使いますが、私にいわせれば、配当見合いの部分というのは、広い意味での比率調整に含まれると考えていまして、理屈はどうでもよいのかもしれません。つまり、決算が確定していないので配当はまだできないわけですから、将来の配当部分をどうするかですが、それは本来、比率に織り込むこともできる。しかし、計算がややこしくなるから比率調整で、交付金で払うというように私は頭の中を整理しています。
概念論はともかくとしまして、合併比率の調整のために支払うというのはどのようなことかといいますと、それまで消滅会社の株主が持っていた何株かに対して、存続会社の株式を何株か与えます。1株に対して1株なら何の調整も要りませんが、1対1.02というようになったときに、では、0.02の部分は現金で払いましょうという考え方です。したがいまして、消滅会社の株主にだけ支払われることになります。存続会社の株主には支払われません。
それから、現在の商法の体系では、合併交付金は配当あるいは利益処分というようにはしてありませんので、やや形式論になりますが、例えば消滅会社に配当可能利益がなくても、また存続会社に配当可能利益がなくても、これを支払うことが可能です。
この点については、合併交付金の支払限度を設けるという法制度もあります。EUですね、ヨーロッパ諸国は対価の10分の1とか、少し違った切り口ですが、そのような形で合併交付金の限度を設けていますが、日本の商法は、法文上は合併交付金の支払限度額を設けておりません。したがって、商法学者の中には対価全額合併交付金でもよい、このようなものをキャッシュアウト・マージャーなどといっておりまして、そのような見解もないわけではありませんが、それは多数説とは私には思えませんので、従来の多くの考え方がどのように考えてきたかと申しますと、合併交付金というのは合併比率の調整のために支払われるんだと、それには先ほど申しました配当見合いというのも含んでの意味ですが、それを超えて合併交付金を支払うことはできないというのが従来の商法の考え方です。明文の規定は、今、申し上げた点についてはありませんが、そのような考え方でこれまでやってきたように思われます。
皆様方にとってお役に立つ点は全然ないのではないかと思いますが、以上で私からの報告を終えさせていただきます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
今の神田部会長代理のご報告について、まず、ご質問があれば先に承ります。
- ○山田委員
-
2ページの3。矢印のついた回答のところで、「開示面では可能であると思われる(計算書類の再確定の手続が必要と考えられる)。」この再確定の手続というのはどのようなことをお考えでしょうか。
- ○神田部会長代理
-
特に遡及した場合の話ですが、計算書類というのは、貸借対照表などですが、現在の商法は、確定という手続を要求しているんですね。それは、原則は株主総会の決議ですが、いわゆる大会社であって会計監査人及び監査役の適正意見がある場合には、取締役会限りで確定することができます。したがって、そのような手続で確定したものを後から修正するような場合、ひととおり手続を経てしまったものについて後から遡及的に修正するような場合には、一度確定したものをそこでもう一度確定し直すというか、「このようにしますよ」という手続を踏む必要があるのではないかということです。具体的には、大会社の場合であれば取締役会の決議になると思いますが。
- ○山田委員
-
そうしますと、今のご説明は、例えば、一たん去年の3月に確定した財務諸表を、今年になって再確定の手続をすることによって変えることができるというご趣旨ですか。
- ○神田部会長代理
-
企業会計の方でそのような遡及的修正が認められれば、商法上も開示の方は、情報提供の面ではですが、そのように考えることは可能だと思います。
ただ、変えるときにその時点で、「再確定」と私はとりあえず呼んだのですが、そのような手続が少なくとも必要だということであります。
- ○西川委員
-
全くわからないのでお聞きするのですが、確定というのは、変わらないから確定だと思っていたのですが、再確定というのはあるという理解でよいわけですか。
- ○神田部会長代理
-
概念の問題だと思いますが、情報開示に限っていいますと、なぜ情報開示のために確定するかということだと思うんですね。それは、大会社の例でいいますと、適正意見があります、取締役会はこれでよい、これが会社の経営成績及び財政状態を正しく表示しているとして決めるというのを開示面では「確定」と呼んでいるわけですね。ただ、配当面ではまた別で、それに基づいて利益処分案があり、それを承認しますから、少し話は別になります。
ところが、その後、何かがあって、変えた方がより真実を伝えるんだと。すなわち経営成績・財政状態をよりベターに示すんだということが出てきて、この先の企業会計の部分は私もよくわかりませんが、企業会計上、合併があるからそのようなことが出てくるのでしょうが、その方がよいのだということになれば、これは情報開示の面からいえば、ある意味ではアップデートでもあるわけでありまして、ですからそれは事後的に修正する。「確定」という言葉は、そのような意味ではそれほど重いものではなくて、修正したものをもって、より真実を示していますということにしてよいのではないかということです。
一点ついでに補足させていただいてよろしいでしょうか。
合併会計については、前から遡及的な処理ができないかとか、計算について商法でもう少し規定を設けるべきではないかという議論がありまして、平成9年の改正のときに随分議論して、規定の案までいったのですが、最終的には規定を置かないことにしまして、そこは実務に委ねることになりました。そのときの遡及的処理というのは、むしろドイツ法などがいっているような処理で、どこで合併してもたとえば1月1日まで遡って、そこで財務諸表をつくり直したものとみなすということで、私の理解では、ここで議論しておられる話とは少し違うように理解しています。
ですから、もともと商法が合併会計について規定を置いて、合併した場合にはどこかの時点まで遡って財務諸表をつくり直す――という表現がよいかどうかよくわかりませんが、そのようなものとして扱うかどうかという議論はあったのですが、少しそれとは切り離して考えていまして、ここでの問題は、まさに企業会計の方でこのような表示の変更のようなことが問題になった場合に、それを商法はどう受けとめるのか。遡及して表示を変えるというようなことが求められるような場合に、商法はそれにどのようにこたえるか、そのような観点で理解したのですが、あるいは問題点を取り違えているかもしれません。
- ○若杉会長
-
大変参考になるお話、ありがとうございました。
その中で、例えば1ページの一番下のプーリング法関係というところで、被合併会社の資産の含み損をそのまま引き継いでよいかということにつきましては、問題なしと。その意味は、会計上それでよければ商法上もよいというお話でしたが、その辺の論理といいますか、会計上その筋が認められるものならば、商法上は別にそれについて特定な考え方を持っていないという趣旨なのか、少しお聞きしたいと思います。
- ○神田部会長代理
-
形式論と実質論とあると思いますが、形式論は、消滅会社から引き継ぐ純資産額とは何ぞやというのは、商法上は解釈問題なのですね。したがって、例の公正な会計慣行を斟酌して解釈することになりますので、そこで公正な会計慣行は、形式論ですが、含み損の引き継ぎを認めていればそれでよいし、認めていなければだめだということになる。
実質論ですが、引き継ぐ純資産額というのは、先ほども少し申しましたが簿価か時価かという問題で、時価でよいということはいえますが、簿価はだめだということはいえないと思うんですね。これは結局、プーリング法はそうではないかということと、あるいはトートロジカルなのかもしれませんが。したがって、実質論から申しますと、この引き継ぐ純資産額、これは含み損があるものもあれば含み益があるものもあるかと思いますが、そのようなものについて、現在の商法の考え方というのは、それはそのまま引き継いでもいいですよ、あるいはそれを、何といいましょうか、評価し直してもいいですよという考え方に立っていると考えるのが素直だと思います。
- ○若杉会長
-
よくわかりました。
- ○斎藤部会長
-
最初に商法を習うときには、合併などのケースでは時価以下であるというように昔、習ったような気がしますが、含み損がある場合、時価よりも高い額で引き継がれているわけですが、それはもうそれで差し支えないと考えてよいわけですね。
- ○神田部会長代理
-
部会長が習われた頃がいつだという問題が一つありますが、昭和49年、財産目録がまだあった頃までは時価以下主義という思想が非常に強かったものですから、そのような点があるかと思います。
- ○西川委員
-
今の続きなのですが、心配性のような話かもしれませんが、今の形式論・実質論でいうと、実質論という考え方をとったときに、確かに減損会計が仮に今、既にあるとしても、含み損があり得る。そうすると、資本充実の原則というのは被合併企業全体の純資産をみるというように考えると、全体として資本充実がどのようなことを意味するかという、商法の意味がわからないなりに考えると、全体をトータルすると、それなりに大きくなっていることもあるのではないかという心配が常にあると思います。それを形式論の方では公正な会計慣行に行き着いてOKということで安心していてよいのかが、会計サイドでは、ずっと心配は心配なのですが。
- ○神田部会長代理
-
それほど私も自信があるわけではないのですが、恐らく商法の考え方は、むしろ2ページに書いた話でして、実際に純資産額の時価で評価した場合、トータルでマイナスだったと、債務超過といっていますが、この場合は合併はできないんですね。ですから、含み損といっても、そのような意味では限度があって、含み損と含み益を全部足したら含み損の方が多い、それでトータルで債務超過だったという場合には、これは合併はできない。これは実質論は資本充実でして、形式論は、先ほど申しましたようにマイナスの資産に株式を発行していたのではおかしいという両方の意味から、そこは抑えているのだと思います。したがいまして、個々の資産の含み損をそのまま引き継げるかどうかは、公正な会計慣行に委ねていると解したとしても、そこの抑えは効いている、つまりトータルでの抑えは効いているということだと思いますし、また逆に、実際に何株発行すべきかを決めるときは、これは本来、公正価値というか、時価ベースで考えるべきものですよね。というのは、そのような価値があるものが入ってきて、それに対して対価を払うわけですから、会計処理は別にしても、当然払うものは含み益・含み損を全部含めた意味での公正な純資産額に対して新株を発行する。「対して」というか「引き当てとして」といわないと、資産が入ってきて新株を発行する相手は株主ですから、そのような意味においては、そこで見合っているというのでしょうかね、そこでの抑えは効いていると考えられるというのが今の資本充実の考え方だと思います。つまり、個々の資産の会計処理にはこだわらないということだと思います。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございましょうか。
私自身、少し細かなところだけ念のためにお伺いさせていただきたいのですが、1ページの2でのれんについて、場合によっては配当規制をかけることも考えられるというご説明がございました。これはパーチェスのケースですので、本来は、のれん相当額は資本もしくは資本準備金に入っておりますので、自動的に配当制限がかかっておりますね。ですから、このケースは、のれんに相当する額の一部が配当可能利益として引き継がれた場合のことだと理解してよろしゅうございますね。
- ○神田部会長代理
-
おっしゃるとおりです。
- ○斎藤部会長
-
二点目、三点目は、傍目八目的なご質問で恐縮ですが、2ページの2、債務超過会社の合併は認められないというお話で、債務超過ですから純資産はマイナスであって、それに対して対価としての株式を交付するというのはおかしな話であるというご説明でありましたが、債務超過になっているというのは過去の事実でありまして、株価がどうつくかというのは将来の見込みで決まりますので、現実に債務超過の会社でも、株価がプラスについていることはいくらもございますね。ですから、それに対して対価を発行するということは、理屈でいえば必ずしもおかしくないのですが、商法上は、やはりそれはだめだというのが通念であると理解してよろしいのですね。
- ○神田部会長代理
-
法律では、多分、そのような債務超過とは何ぞやという定義の問題に落ち込んでしまうんですね。ですから、形式的にはバランスシート上、債務超過であっても、実際に、例えば今おっしゃったように株価がプラスについている会社があるというのは、やはり会社の財産、公正価値というのは何かといわれたら、企業は債務超過ではなくてプラスの価値があると考えられるわけですね。そのような場合には、ここでいう債務超過とはみないと思います。すなわち、ここでの債務超過というのは形式概念ではなくて、むしろ実質概念と捉えるのだと思います。
- ○斎藤部会長
-
わかりました。それならば納得できます。
もう一点は、もっと傍目八目で恐縮ですが、一番最後から二番目のところで、プーリングであれパーチェスであれ、共通した問題として配当可能利益の引き継ぎが認められると。これはパーチェスであっても何の問題もないケースであるというようなことをおっしゃられたように記憶していますが、仮にフレッシュ・スタートという概念を持ち込んできた場合はどうでしょうか。今、仮の議論として、新しいエンティティが構成されてそこからフレッシュ・スタートしたという考え方が国際的にございますね。そのケースですと、新しい会社がスタートするときに初めから配当可能利益があるのは妙だという感覚を持つのですが、将来の可能性として、神田部会長代理のご見解を承れれば大変ありがたいのですが。
- ○神田部会長代理
-
二点申し上げたいと思いますが、まず第一点として、一般的な考え方として、配当可能利益の引き継ぎは当然認められるべきであると、そこまで強くは申し上げませんでして、これは場合によっては、先ほどおっしゃったのれんの話と同じですが、商法の考え方というのは、合併することによって、それまで配当できていた額が配当できなくなるのはおかしいではないかと、だから、せめて同じ額まで配当できるということを認めましょうというのが、配当可能利益の引き継ぎなんですね。
しかし、引き継いだ純資産額に、どうも当てにならないといういい方がよいかどうかわかりませんが、そのようなものがある場合には、それは配当制限しますというのは、その一部についてはあり得るわけですね。のれんの場合の例ですけれども。ただ、基本の考え方、すなわち合併することによって、それまで配当できていた金額――最高限度額にすぎませんが、それが配当できなくなるというのは、いわゆる株主と会社債権者の間の利害調整のルールというか、線引きの基準としてはおかしいのではないか。これは引き継ぎを認めてよいのではないか。ただ、これもあくまで当事者が望めばであって、繰り返しになりますが、原則のルールではありません。原則は、資本準備金になるというのがルールですから。そのような考え方なのですね。
そうだとすると、フレッシュ・スタート法と呼ばれるものをとったときに、さあどう考えるかというのは、そこをどう考えるかという問題ですので、これはフレッシュ・スタート法という考え方と多少異なる次元の問題だと思うんですね。すなわちフレッシュ・スタート法をとったときに、株主と会社債権者の利益調整の線引き基準として、それまで配当可能だったという線引きがありまして、それはゼロですというところから出直すのだと。すなわちフレッシュ・スタート法というのは、そのような意味で、会社債権者と株主との間の仮定的交渉というか、合意をも反映しているんだと考えれば、これは商法上もゼロにしますという考え方も、もちろん成り立ち得ると思います。
ただ、私の直感は、フレッシュ・スタート法というのは会計の考え方であって、株主と会社債権者の利害調整とか線引き基準ということからいえば、従来の商法の考え方、すなわち配当可能な限度額として従来設定されていたものの引き継ぎはあり得るという考え方の方が整合的なような気が、現時点ではしています。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
「質問」というように限定しておりますと話が進まない可能性がありますので、この段階で、質問に限らずご意見を頂戴できればと思います。
本日のご報告、松岡委員、神田部会長代理、お二方のご報告をまとめて、ご意見があればご発言いただきたいと思います。
- ○梅山委員
-
直接これに関係しないのですが、よろしいでしょうか。
先般、AOLタイムワーナーののれんの償却が話題になって、4月下旬に2002年第1四半期の決算のプレスリリースが出たものですから、少し財務諸表を眺めていたのですが、われわれ財務諸表作成者側からみると、やや不安な面があるものですから、その印象を述べさせていただきたいということでございます。
新聞報道等でご存じだと思いますが、AOL、タイムワーナーが合併をして、初年度、2002年第1四半期のところでパーチェス法の会計処理――のれんについては基本的には償却しないで減損法をとるということで、その結果として、第1四半期で 542億円ドルほどの減損を行ったわけでございます。これは新聞で報道されているとおりです。
ざっくりとですが財務諸表をみてみますと、ほぼのれんの償却に見合う部分がネットのロスに反映しております。そののれんの償却の金額の背景は何かというところについては、主に合併公表日以降の株価の下落を反映したものだという表現になっておりまして、その減損額をセグメント別にどう配賦するかというところについては、例えばディスカウント・キャッシュ・フロー法とか、あと類似取引の比較法を使うとか、そのような説明がなされているように読めました。
そのネットロス540億ドルほどを償却した結果として、いわゆる資本の部の中身をみてみますと、資本の部に約980億ドルぐらいの残高があるのですが、このうちコモンストックが4,000万ドルぐらいと極めて少額でして、資本準備金に当たるものが1,550億ドルぐらいございました。一方でネットロスを反映して、いわゆるリテインドアーニングス、剰余金というのでしょうか、これが570億ドルほどのマイナスになっております。もともとこの会社の四半期前、2001年の第4四半期ですが、この期の剰余金も若干のマイナスでございました。
この会社は、合併を発表したときにSECにファイリングをしているのですが、その段階で配当政策については、普通株式については現在配当する予定はないと、ただし、優先株式については約定に従って配当しますというようなことが書かれておりまして、この第1四半期のキャッシュ・フロー表を見てみますと、ディビデンドというところに若干ですが、2,000万ドルぐらい配当金が載っております。
アメリカの配当規制がどうなのか、よくわからないのですが、州法によって、欠損金があってもある一定の期間、損益があれば配当できるところもあると聞いたことはありますが、このAOLタイムワーナーについては、少なくとも欠損金があって、片々若干の、多分優先株式の配当ですが、実施しているということからすると、米国では、このような大きなのれんの償却をした結果、資本の部の中で、資本準備金と剰余金で大きな入り繰りがあったとしても、配当制限の問題は、ある意味では慣行としてクリアになっているのかと思われるのですが、例えば日本でこのような大規模な処理が起こったときに、配当問題はどう考えたらいいのかというところが、財務諸表作成者としては大変悩ましいなと思っております。
日本の場合は、当然ながら配当規制があるわけですので、これは多分、配当はできないだろうと思うわけですが、ただ、昨年10月の商法改正で、いわゆる法定準備金についてはその必要額を上回る部分については減少することができるという規定ができまして、株主総会の議決と債権者保護手続ですか、これを経た上で資本の減少手続ができるわけです。ただ、その資本減少したものを原資とした配当というのは、この前、日本では決まったわけですが、配当を受け取る側は出資の払い戻しという格好になるわけですね。したがって、ある意味では、このような大きな減損というものが日本でも出てくるとすれば、配当に対するカルチャーも、日本の場合、大分変わらざるを得ないのかなという気がいたします。
このように考えてくると、果たして日本の配当規制というものを考えるときに――これはすごく乱暴ないい方ですが、このような合併の会計に、新たに二つになるか一つなのかわかりませんが、パーチェス法とプーリング法というものが認められて、パーチェス法の場合には一定ののれんの償却が起こるわけですが、そのようなものの資本、特に剰余金に与える影響を考えた場合には、配当規制についてももう少し、従来の考え方からジャンプすることができないものかなと思いましたので、作成者側の印象ですが、このような場で恐縮ですが、発言させていただきました。
- ○斎藤部会長
-
ご発言の趣旨が、一つは配当規制のあり方ということであります。遡っていえば、そもそも合併の会計方法のあり方につながっているわけですが、差し当たって合併の会計方法を所与といたしますと、直接には配当規制のあり方の議論になりますので、これはやはり、もしご発言があれば神田部会長代理にお願いするしかないと思いますが。
- ○神田部会長代理
-
とてもお答えできるような準備はありませんが、配当規制のあり方というのは、まず抽象的に申しますと非常に難しい問題で、日本のようなやり方は、万国普遍でもありませんし、また、理論的に考えても、唯一考えられる方法であるわけではありません。
抽象的に申しますと、先ほど少し申し上げましたように、配当規制というのは会社債権者と株主の利害調整の線をどこに引くかということですから、一つの考え方としては、法律は何もしなくて合意に任せておけばよい、現に社債発行などは配当制限条項が入っています。つまり、会社債権者が会社と契約する中で、配当制限というのは契約条項として設けているわけですね。アメリカなどでは州法上、配当制限もありますが、そのような社債あるいは借入等で銀行とか社債契約において配当制限が契約で設けられ、それが債権者と株主の利害調整の線をつくっているケースが多いわけです。
これに対して大陸法系というか、日本を含めた考え方としては、これは法律で配当可能な最高限度額を定めましょう――それを配当可能利益と呼んでいるのですが、それで複雑な第 290条第1項があるのですが、これをあえて理論づけるとすると、株主と会社債権者の仮定的合意とでもいうのでしょうか、合意したならばそのようなところで合意したであろうというところを推測して、線を引いているわけです。
繰り返しになりますが、日本のような法制が、合併の場合であれ一般論としてであれば、唯一無二あるいはベストだという保証はありません。しかし、日本の法制もある種の合理性はあって、そのようなことでこれまで来たわけですね。
そこから先はなかなか難しいのですが、タイムワーナーのケースは私も何法かわかりませんが、もしデラウェア州の州法だとしますと、デラウェア州の州法では、英語でニンブル・ディビデンドといっておりまして、直訳すると迅速配当。つまり、過去の累積した配当可能利益がなくても、当期が黒字であれば、当期の黒字の範囲内でその期の配当をすることができる、そのような州会社法の配当規制をとっています。
その点は非常に特色がありますが、ただ、言葉を変えていえば、利益から配当しなさいという考え方をとっている点では伝統的な部類に属します。といいますのは、ほかの州などでは、もう利益から配当規制をかけることをやめてしまって、例えば流動性比率ですとかバランスシート上の比率をベースに配当規制をかけるという手法も――カリフォルニア州などがそうなのですが、あるからであります。そのようなところは配当可能利益があって、それは配当してよろしいという発想とは全然違う配当規制をかけています。
いずれにしても、日本と比べますとアメリカは、総体的には州レベルの配当規制は緩くて、したがって、先ほど申しましたように、さらに契約レベルでかかっている配当制限から、実際配当の制限がかかる場合が多いと私は承知しています。
そこで、さあ日本をどうするかということですが、差し当たり合併の場合に限って申しますと、この際、思い切ってジャンプすることを検討するのは大変結構だと思いますが、どちら向きにどうジャンプするかというところだと思います。ですから、この話はなかなか難しいのですが、二点だけ直観的な感想を申し上げますと、一つは、パーチェス法一本で行くことを日本も基本的に決断するかということが、やはりあると思います。プーリング法にもそれなりの合理性があることは、ロジカルにも、また実際にも、日本の立場からすればそうだし、私もそうだと思いますが、しかし、どこかの時点では、やはり世の流れもありますし、プーリング法を残すとしても極めて例外的な場合としてパーチェス法とするか、その辺の判断をどうするか。これは間接的な話ですけれども、この問題が一つあると思います。
第二点として、パーチェス法が非常に広がった場合、今パーチェス法で処理していない場合もパーチェス法で処理するようにした場合に、配当可能利益の問題をどう取り扱うかという問題がありまして、この話はのれんとも非常に密接に関連してくるわけですが、その中で、これまで配当していた、私の言葉でいう共通の論点ということになりますが、これまでそれぞれの会社に存在していた配当可能な限度額があるわけですから、それを足し合わせた分だけは配当可能にしましょうというのが現在の商法の考え方なわけです。ですから、その考え方を最大限尊重しようということになれば、これはもうのれん等についても配当制限をかけないということで、そこの部分はもう最大限度配当可能にしましょうという判断になると思います。
それから、パーチェス法というのは、私はあくまで手段にすぎないと思いますが、やはり合併ということが起きた以上は、先ほどの抽象的な表現でいいますと、株主と会社債権者の利害を調整する線引きは、そこで見直すのだという考え方に立ちますと、合併後に配当可能利益が減ったり、あるいは増えたりということが起きても不思議はないわけですから、それは、そのような考え方から問題を考え直す必要があると思います。
ですから全体として、今後どうなのかということであれば、これはどうあるべきかという議論だと思いますので、非常に幅広く「どうあるべきか」という議論をすべきであって、その結果を、この配当規制という観点からいえば、現在、法技術的にいえばかなりの部分は、一部法律、一部省令ということにはなっているわけですが、省令で手当てする部分であればフレキシブルな対応が可能である。もちろん、それでよいという判断がなされればですけれども。
そのようなことだと思いますので、そこは多分、この場に限らないと思いますが、前向きな議論をしていただく方が私はよいと思います。「こうあるべきではないか」というご提案があれば、ジャンプするご提案であっても、ぜひそれをしていただいた方が、そして、それが商法の今までの考え方とどうなのか。そのような議論をしていった方が、議論の仕方としては建設的だと私は思います。
長くなってすみません。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
今の梅山委員のご質問ですと、AOLタイムワーナーのケースのように、パーチェスを使って多額ののれんを計上した、それが一発で減損したというケースでありますと、いくら従来の会社が持っていた配当可能利益を引き継いでも、それは一遍で飛んでしまう。そのときにどうするかというお話だと思います。
そうしますと、基本的には、もう現在のようなタイトな配当規制は全部やめてしまって、勝手に配当させるようにしろ、そのようなご趣旨にも聞こえるのですが。
- ○梅山委員
-
日本の場合、そのようなことが起こるかどうかわかりませんので、ただ、もし仮にそのようなことがこれから実際に、企業の買収、例えば時価総額が数兆円の会社というのは日本にもたくさんありますから、そのような会社の買収が起これば理屈としてはあり得るかなと思いますので、そのような動きがこれから出てくるのであれば、やはり考えておくことかなと思っています。
現在では、話はよくわかりましたので結構です。
- ○斎藤部会長
-
おっしゃるとおりなのですが、今、神田部会長代理のお話にありましたように、例えば現在の日本の商法の配当規制というものも、ある見方をすれば、市場の当事者の合理的な交渉結果の最大公約数だとみることもできるわけですね。ですから、それを外して仮に契約ベースに委ねても、結果は似たようなタイトなものになる可能性はあって、それをもっと大きく緩めたいというのは自由ですが、その場合には資本の調達コストが非常に上がる。その会社については投資家のリスクの評価が非常にコンサバティブになって、資金コストが上がるということは十分予想されるわけですね。そのような問題も一緒に考えないと、多分なかなか難しいんだろうとは思います。
ほかにご発言ありませんでしょうか。
- ○大日方委員
-
神田部会長代理と松岡委員、二人に共通のご質問なのですが、別に引っかけ問題ではありませんので。
私の興味の焦点は、償却性資産というか、継承したオンバランスされている資産と、そこに配分し切れないのれん、合併対価をいずれにせよその二つに分けるとしたときに、その評価額の割り振り方に、裁量に委ねる部分が残るのですが、アービトレージといいますか、中立的なルールになるかどうかという点でお伺いしたいんです。
どのようなことかと申しますと、まずのれんについて、仮定の話なので何ともいえないということかもしれませんが、償却しなくてよい、減損処理のみにするとなると、これまでの議論に出てまいりましたように、実は本来、合併時に取得したのれんは減っていて、その後、新たにつくり出された部分がそれを埋め合わせているにすぎないような場合がある。そうすると、通常、合併によらないで自己創設のれんを計上して評価益を配当することは許されていないわけですが、それとの整合性を考えて、ひょっとすると、のれん非償却という企業会計のルールをとるのであれば、商法側は、自己創設のれんの禁止との整合性をとるために配当規制をかける可能性もあるのかな、そのような趣旨かなと最初、読んだのですが、そうなりますと、企業の側は、配当可能限度額を確保する上で、のれんを多くしたらよいか少なくしたらよいかということで、一応問題が出てくるというのが一つなんですね。
もう一つは、これは専ら企業会計の側ですが、仮に減損処理というものが、プロジェクトに使われている資産及びそれから生じている合併ののれん総体にチェックがかかって、スタート時点での資産の評価額の割り振りとはニュートラルに、とにかく減損損失が出てくるというのであれば、償却性資産と非償却ののれんにアービトレージは働かないだろうと思いますが、その割り振りいかんによってその後の減損が変わるということになると、出発時点でどうやったら得か損かということが出てくるので、評価規定をかなり詳細に決めないと混乱が出てくるのではないかということなんです。
その辺の見通しという点で、神田部会長代理には、自己創設のれんの計上禁止という点で、のれんを非償却にした場合には配当規制をかける可能性があるかどうかという点です。
松岡委員には、減損規定を想定したときに、どの部分を建物等の償却資産に割り振り、どの部分をのれんにするかということで、その後の減損損失の大小に影響が出てくるのかどうかという点について。これは松岡委員より辻山委員に聞いた方がよいのかもしれませんが、可能性という点で結構ですので、教えてください。
- ○斎藤部会長
-
方々に球をばらまいているので、どなたにお願いしてよいかわかりませんが、まず松岡委員、お願いします。
- ○松岡委員
-
非常に難しい問題だと思いますが、私の感覚的には、商法の規定いかんもそうですが、のれんについては、恐らく実際には税法の取り扱いの方が影響が強いのではないかなと思います。
適格、非適格の別はありますが、仮に確定決算主義を貫いて多額なのれんを会計上、償却しない場合に、税務上、一切損金として認められない、仮にそのようなケースが出てくるとしたならば、実態経済に与える影響は、恐らくそちらの方が大きいのではないかなと思いますので、まずのれんと、それ以外の償却性資産との配分については、アービトレージはある程度は働き得るというのが当然ではないかなと思いますが、その場合に、減損規定のみという前提で、実際問題どの程度のれんとそれ以外の償却性資産とに評価を割り振るかというのは、理論的な方法による限りは、その範囲であれば、もうある程度はしようがないということになるのではないかと個人的には考えています。
- ○辻山委員
-
この問題は、先ほど小宮山委員から質問がありまして、私自身はお答えしたと判断していますが、減損規定について、償却性資産の減損の問題と、今ご指摘の、のれんを償却せずに減損で行う場合というようにとりあえず考えますと、先ほど松岡委員にもご質問をしたのですが、本来は償却性資産の受入評価のときには、その償却性資産についてはのれんを含ませない。ですから、公正価値で受け入れて、受入時の超過部分というのはのれんに配分されるはずだ、これが考え方になるのかなということです。
ところが、のれんの方が減損だけで償却をしないということになると、もちろんどちらかに張りつけるということはありますが、考え方としては、先ほど小宮山委員の質問にありましたが、パーチェス法のもとで受け入れる資産・負債にのれん部分を張りつけることはないというのが、先ほどお答えしたとおりなのですが。
- ○神田部会長代理
-
どのようにお答えしてよいか私もずっと考えていたのですが、私の感じでは、自家創設のれんだから配当規制をかけるというロジックではないと思います。現在の商法は自家創設のれんは認めていないわけですが、有償取得、合併・分割で取得した場合にのみ、のれんの計上を認める、そのような考え方を変えないとしても、のれんが非償却資産になった場合には配当規制をかけることが考えられるということだと思います。
それはなぜかですが、これは、やはりのれんは何かという議論をしないと答えは出てこないのだと思います。現在の商法が、なぜのれんに5年内の償却を求めているかということですが、これはいろいろ議論はあると思いますが、のれんというのは、そのときは認識したのだけれども、いつまでも続くものでないというのか、とって代わっていかれるものだというのか、そういうものであるので、とにかく償却しなさいと。商法の配当規制との関係でいうと、不安定なものであるという考え方に立っているわけですね。したがって、その考え方の延長として、一方で会計処理の方で償却しません、減損のみですとなった場合には、それはそのような処理として受け入れましょうと。しかし、商法の従来の考え方からすると、では、減損処理が行われるまでは目いっぱい配当してよいのかというと、少しそこは抵抗がある。したがって、そこは配当規制をかけることも考えられます、そのようなロジックだと思います。
もう一点、関連してよろしゅうございますでしょうか。
商法の方も、実はのれんがどのような金額になるかは非常に重大な問題でして、なぜかというと、程度問題かもしれませんが、5年で償却するか、あるいは他の償却資産に割り振れば、例えば10年か20年かというのがあります。したがって、そのアービトレージというのは今でもある問題で、これは程度問題ですね。一方が非償却資産になれば、今は償却資産の間でアービトレージがあるわけですが、のれんが非償却になれば非償却資産と償却資産との間にアービトレージが生ずるということです。そこは考え方としては、辻山委員がおっしゃったように、企業会計の方でというとかえってご迷惑かもしれませんが、企業会計の方でどのような考え方で会計処理をするのかが決まって、どうも「全く自由裁量でございます」という筋合いのものではないような気がしています。これは私はよくわかりません。
しかし、全くの自由裁量ではなくて、何かの会計処理方法が企業会計の方で決まって、先ほど大日方委員が詳細に決める必要があるのではないかとおっしゃった――ひょっとするとそうかもしれませんが、それが決まれば、その後で商法として、先ほど申しましたような考え方から配当規制をかけるのが適切なのか、そこまでしなくてよいのかという問題が、多分その次に出てくる、その時点での判断でできるような感じがしています。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
大日方委員、よろしゅうございますか。
- ○大日方委員
-
はい。
- ○安藤委員
-
先ほど株式会社の配当規制のあり方の話が出まして、私も非常に関心を持っておりますので、神田部会長代理のご説明に加えて私の認識をお話ししたいと思います。
今の日本の商法の配当規制はヨーロッパから持ち込んでいる考え方ですが、これは19世紀中頃に確立した一つの理念なんですよね。要するに、その根本にあるのは資本維持なんですね。あるいはその背後には企業の維持が根元にあり、その上に資本維持というものがあって、その資本維持制度の上に乗って株主と会社債権者の利害の調整を行ってきたというのが私の研究で得られた結論です。
アメリカでは、最近、会社法で資本制度を取り払った州会社法がたくさんあります。ですから資本の部についての規定が何もない。ということは、言い換えれば、アメリカではもう資本維持とか企業維持という理念は、少なくとも会社法上は放棄したとみられるのではないかという気がいたします。
では、それに代わって会社債権者をどうするかといったら、これは先ほど神田部会長代理がいわれたように、一言でいえば、資本維持ベースから破産法ベースに切り換えているといういい方が、少し暴論かもしれませんが、いえるのではないかという気がいたします。
企業会計原則でも資本と利益の峻別ということをいっていますから、企業会計原則でも、一応この資本維持という考え方は入っているとみることができると思います。ですから、これを、従来型の資本維持をベースとした配当規制を今後ともやるのか、あるいはアメリカのようにもう企業の維持とか資本の維持にはこだわらない、もう市場に任せようというようになるのか、ここが大きな分かれ目だと私は認識しております。
- ○長坂委員
-
神田部会長代理にお伺いしたいのですが、海外でもこのようなものがあるのかどうかわかりませんが、商法で今、どこまで検討されているのかわかりませんが、連結財務諸表の導入も視野に入っているのではないかという気がしますが、配当規制も連結財務諸表ベースでやられるというようなお考えは、これから先、出てくるのでしょうか。というのは、私の会社などはだんだん単独の親会社で利益を出すのが難しくなってきていまして、毎年配当可能利益はあるのですが、その年度の利益から配当することがだんだん難しい状況になっていまして、それを連結全体でみていただくとあまり問題はないという状況ですが、商法の方で、そこら辺の考えというのは出てこないのかなと思いまして。
- ○神田部会長代理
-
そのような考え方が全く出てこないかといわれますと、出てくる余地が全くないとはいえないと思いますが、これまで既に若干議論されてきまして、現在のところ、そのような考え方は難しいのではないかというのが商法の分野での議論だと思いますので、少しそれを申し上げたいと思います。
ちなみに、そのような国があるかということについては、アメリカの一部では会社法上、そもそも何が利益かという概念を決めておりませんので、そのような利益の概念は全部企業会計の方から来ます。そうすると、結果的にという表現がよいかどうかわかりませんが、連結ベースでの利益がその会社の利益だということになって、したがって、会社法は配当規制を決めてはいるのですが、その利益とは何ぞやといったときに会社法上、定義がありませんので、これが連結ベースでの利益になっているところがあります。
日本の場合、まず、連結財務諸表は今回の商法改正で導入されます。商法は連結計算書類と呼んでいますが、ただ、これは情報提供面、開示面だけであって、配当規制の面では単独です。
配当の方も連結ベースですべきではないかというときに、いくつか論点がありますが、まず一つ出てきますのは、先ほど申しましたように、配当規制を会社債権者と株主の利害調整の線引きだとしますと、会社債権者というのは、普通はその会社の債権者ですから、常識的に考えますと単体でみることが素直ですよね。そうすると、親会社が赤の場合に、親会社の債権者と株主の利害調整というようにみると、やはりほかをみないというのが普通の考え方で、逆に今度は子会社の方も同じようなことがいえるのかもしれません。
ただ、さらに進んで考えれば、いや、親会社は赤字かもしれないけれども子会社の黒字があって、これはいつでも吸い上げられるんだと。そうだとすれば、それはトータルにみて親会社の債権者は、いわばそのような線引き、すなわち配当してよいという点に仮に合意を求められれば、合意するでしょうということも当然考えられるわけですね。
しかし、これまでの商法の考え方というのは、私の理解では、それは実際に子会社から親会社に利益が配当されて、親会社の利益になれば、それはそこで配当可能利益ができるわけですから、そこは実際そのような行為が行われていない限り、開示の面では連結しますが、配当の面ではあくまでも個別の、先ほどの安藤委員の言葉でいえば、その会社の資本維持というか、それをベースに会社債権者と株主との利害調整の線を考えましょうという考え方でしたので、それを変えるということは、やはり大きな発想の転換が必要になると思います。
したがいまして、将来全く不可能かといわれますと、それは全く不可能とはいえませんが――それこそ資本制度もなくなるかもしれないわけで、それはそうですが、今の体制の延長で物事を考えている限り、連結開示の方は今回、商法上も実現しましたが、連結ベースでの配当可能利益というのは、やはり現状のルールからは相当隔たりがあって、難しい問題のように思います。
ついでに、この際といっては申しわけありませんが、安藤委員のおっしゃったことと私も基本的に同じですが、アメリカで、やはり気をつけた方がよいと思いますのは、アメリカで資本金を撤廃した最初の立法というのは、カリフォルニア州法の1975年でして、その後、模範事業会社法が撤廃されまして、それに従った州が大分ありますので、州を数えていきますと、資本金概念というのは会社法上、撤廃されている州の方が多いのですが、上場会社の半数ぐらいが設立されているデラウェア州の会社法では依然として資本金概念があり、したがって、英語でキャピタル・メンテナンスといっていますが、先ほどの資本維持ということをベースに配当規制が行われています。
ただ、例外として、先ほど申しましたように、当期黒字であればその範囲内で払ってよいというニンブル・ディビデンド・ルールというものが定められているために、結果として配当規制が緩んでいるわけです。しかし、つくり方としては、資本維持というベースのつくり方でデラウェア州の会社法はできていますので、少なくとも上場会社の半分は、そのルールで動いています。そして、結果として緩くなっているために、これは契約での縛りをかけられるケースが結構多い、そのようなのがアメリカの状況だと思います。
ついでにもう一ついいますと、キャピタル・メンテナンスという考え方は維持しながらも、何を資本とみるかというところについては、日本も考え方が多く変遷していまして、まさに去年6月の改正での法定準備金の減少という考え方は、その考え方を反映しているものです。つまり、これもどこが会社債権者と株主の利害調整の線引きかですが、法定準備金は資本金の4分の1あればいいでしょうという考え方に変更したわけですね。
それは、上場会社の多くが戦後、時価発行を重ねた結果、平均すると資本準備金が資本金と大体同額ぐらい積み上がっていて、あるいは同額以上の企業もあるようですが、そうだとしますと、法定準備金というものは、本来は資本金があって、その上の補助的なものであって、バッファであるのに、バッファの方が本来あるべき資本金を超えてしまった。これは先ほどの利害調整の線引きとしても、少し行き過ぎであって、まあ4分の1ぐらいで、これは目の子といわれたらそれまでですが、4分の1までは下げていいでしょうと。そしてこの下げた結果は、翌期にならないと配当できませんが、配当可能というところで、すなわち株主と会社債権者の利害調整の線引き基準は、そこに変更してもいいでしょうと。
これは大きな変更といえば大きな変更ですが、資本維持という思想を維持しながら、その線引きの考え方を従来と変えた、そのようなことであります。したがって、理屈をいえば、そもそも資本維持という考え方を全廃しましょうという考え方とは違います。これに対して、全く違った考え方、例えば安藤委員がおっしゃったように倒産基準だけだ、簡単にいえば会社が潰れない限り配当してもよろしい、このようなルールにしてもよいではないか、という考え方もあり得ると思いますが、まだそこまでの合意は、日本ではすぐできそうには思えないということではないかと思います。
- ○金井委員
-
神田部会長代理にご質問させていただきたいのですが、本日ご説明いただいた資料の1ページの3、差額のれんの計上の中で、のれんを被合併会社の時価純資産と発行株式時価の差額としてもよいかという点に対して、問題なしということでございましたが、このとき、時価純資産という概念そのものの中に、のれんというものは含まれないのでしょうか。
といいますのは、ここのご説明をそのままとってしまうと、含まれないというような考えになってしまうかと思いますが、次のページでご説明いただいた合併時の欠損金の引き継ぎのときには、これはもう実質ベースで考えましょう、全部時価評価してプラスならOKですねというように理解させていただいたのですが、そことの整合性をどのように考えたらよろしいでしょうか。
- ○神田部会長代理
-
ご指摘のとおりでして、私の1ページの論点の書き方は、日本語が悪いということに尽きるのですが、この際、法律家がこの問題をどう考えてきたかということを、少しだけ補足させていただけますでしょうか。
多分、このあたりの問題について法律をやる者は二つの面から考えてきたと思います。私は結論のところだけを申し上げまして、それは、私はずっと、差額をもってのれんとするという考え方でよいという見解をとってきたものですから、あまり抵抗なく「イエス」といったのですが、実は従来は「のれんとは何ぞや」というときに、やはりのれんというのは何か実体があるんだという考え方が非常に強かったのですね。
特に法律家の間でそれが強かったのは、これは税法の営業権という概念に関するものなのですが、最高裁判所の判例が、税法上の営業権とは何ぞやということについて抽象的な定義をしているのですね。今日は持って来なくて申しわけないのですが、いっていただければお送りします。
その最高裁判所いわく、のれんというのは、超過収益力を生む事実関係だと。得意先とか何とかもう少しいろいろいっていますが、そのような事実関係があるのだと。簡単にいいますと、やはり実体があるのだというのが最高裁判所の判例です。そこで、商法の場合も、商法第285条の7にいうのれんというのは、やはり何か実体があるからこそ、それをのれんとして評価するんだというように考えないと、これはあくまで税法の判例ですが、最高裁判所の判例と一貫しないのではないかという意識が強かったということはあります。
私が、いや、差額でよいのではないかというのは、実体がなくても差額でよいというのではなくて、ここは物事の強調の仕方で、基本的には適正な会計ルールで個々の資産に割り振っていく。割り振っていくといういい方がよいかどうか、よくわかりませんが、対価を割り振っていくのが正しい。しかし、どこの資産にも割り振れないものが出たら、それは差額である。しかし、なぜ差額という対価を払うのかというと、これは実体のないところに払っているわけではなくて、払うからには、やはりそこには何かがあるはずであるという程度の考え方がよいのではないかというのが差額という考え方でして、何もまず初めに実体ありきで、その実体を評価したらX円となります、このX円というがのれんの評価でございます、そのような発想をする必要はないのではないか、そのような意味にすぎないのですね。
これが従来、法律の分野では結構議論したし、悩まれてきたことだと思います。さらにそれを進めていくと、なぜ有償の場合に限るのかとか、そのような話にも発展していく話です。したがって、差額でよいという意味は、そのような意味にすぎないわけですが、ご指摘の論点の「時価純資産」というのは、当然それぞれの資産という意味です。
- ○長坂委員
-
今の3の差額のれんの計上のところで、私が聞き逃したのかもしれませんが、のれんを時価純資産と発行株式の時価の差額としてよいということですが、その場合、発行株式時価の部分が、これは資本勘定に資本金と資本準備金として行くことでよいという理解なのでしょうか。
今の商法ですと、多分、受入純資産とかそのようなことになるので、もっと小さい金額になるのではないかと思いますが、大きな、発行株式のそのときの時価ということで、資本金と資本準備金を増加させるということでよろしいのでしょうか。
- ○神田部会長代理
-
現在の商法はそうではありませんで、おっしゃったように、第413条の2という規定ですが、増加させる資本金の最大限度は、あくまで受け入れる純資産額で決まります。したがいまして、受け入れる純資産額が増加する資本金の最大限度になります。ですから、受け入れる純資産額を全部時価で評価するということになると、これは資本金の最大限度がイコールになる。その全部まで資本金を増加しない場合には、差額は資本準備金ということになります。
したがって、いくら資本が増えますか、資本準備金が増えますかという話は、専ら純資産額の方を基準に決まりますので、商法上の言葉を使わせていただければ、通常の増資では新株の発行価額という概念で普通は増加する資本金を決めている。しかし、普通の新株発行の場合と異なり、合併の場合は発行価額という概念はなくて、合併の場合には、専ら第413条の2の規定の方で資本金が決まるということです。正確にいうと、第413条の2は増える資本金の最大限度を定めているだけです。最大限度まで資本金を増やさないときには差額は資本準備金になるというのは、また別の規定があって、しかし、さらにその例外として配当可能利益が引き継げる、このような構造になっていますので、資本の部をどうするかは、そちらの方の条文で決まっていく、商法的にはそのようなことになります。
- ○長坂委員
-
会計上は時価で資本金もしくは資本準備金を増加させるという話になると、そこは、やはり差額は残るということになるのでしょうか。発行した株式の、発行時なり株式交換を決めたときの時価で資本金を増加させるかどうか、そのような議論がされていますので――例えばアメリカの会計基準等もそうなっていますので、今、商法と会計で少し差額が出ているのですが、要は、会計上、株式の発行時の実際に流通している株価で、資本金もしくは資本準備金の合計額を増加させてしまうとすると、商法上の受入純資産とは当然差額が出てくる。
- ○神田部会長代理
-
現在の商法では、それはできないということですよね。
なぜできないかというと、対価がないものは認識できない。それを法律家は普通、資本充実といっていますが、ですから、純資産額として仮に100入ってきたというときに、発行対価として200の株を発行するのはそもそもおかしい。100入ってくるのであれば100しか発行できないという考え方で、そこは揃うはずという考え方なのですね。現金の場合はどちらでみても同じですが、それを発行する方の株を時価でみると危険が生じますので、ですから入ってくる100の方をみましょうと。100入ってくる以上、やはり100しか出せない、だから資本金の最大限度額は100だと、増加する資本金ですけれども、それが第413条の2の考え方なんですね。
したがって、100入ってくるものに対して200、300の価値のある株式を渡しました、だからそれだけ資本金を増やしますというのは、いわば現在の商法の考え方に正面から反することになります。
- ○斎藤部会長
-
現在の商法の考え方では問題があるということですが、1ページの3に書いてある差額のれんの計上について問題なしというのは、これは商法の考え方で問題なしとおっしゃっているのか、神田部会長代理は問題なしとお考えになっているのかというところだと思いますが。
- ○神田部会長代理
-
すみません、そのような意味では、ここは論点を誤解していたかもしれませんね。先ほど申しましたように、私は個々の資産に割り振らないものをのれんとして受け入れてよいかというように考えていましたので、今の例でいいますと、100の純資産を受け入れます、のれんは別にです。のれんは別という表現がよいかどうか、よくわかりませんが、それに対して、例えば与えた株式の流通市場における時価が200だったとしますね。そのときの200と受け入れた個々の純資産の合計額との差額、これは100になるのですが、それをのれんとしてよいですかというご質問だと、まず文字どおり受け取ったのですね。
その意味は、受け取るべき被買収会社というか、商法の言葉でいえば消滅会社の純資産の価値というのは、やはり200なのだと。しかし、そのうち個々の資産に割り振れるのは100なのだと。したがって、先ほどの話で割り振れない部分というのは、100はのれんとして認識してよいですかという質問だと私は解釈したんです。したがって、答えがイエスになりますのは、今の例でいいますと、受け入れる純資産は200ということになります。
- ○斎藤部会長
-
それは神田部会長代理個人のご見解というよりは、商法上、それが一般の通念であると考えてよいわけですね。
- ○神田部会長代理
-
それはそうだと私は理解しています。
- ○斎藤部会長
-
だとすると、長坂委員が当初おっしゃったように、対価として発行した株式の時価と受け入れた純資産の時価ではかった積み上げとの差分をのれんとして計上することは差し支えない、そのような話になりますね。
- ○辻山委員
-
必ずしもそうではないと思います。
今の神田部会長代理のお話は、発行株式時価と独立して時価純資産といいますか、のれん含みのその買収先の評価が先に決まる。それが発行株式の方では決まるのではなくて、それ自体がのれんを含めて実質は決まるというお話なのではないのでしょうか。
ですから、発行株式が取得側の企業の純資産の時価を自動的に決めるというお話ではなくて、純資産の取得側の方が独立に決まっていて、それが資本の部を決める。まず資本が決まって、相手が決まって差額がのれんではなくて、買収側の実質価値が決まっているはずだというのが今のご説明だと思います。
- ○斎藤部会長
-
そうしますと、買収の実質価値が決まったときに対価として発行する株式の価値は、それとは違うということですね。
- ○神田部会長代理
-
大体そうですが、違ってはならないということをいいたかったのですが。
ロジカルには辻山委員のおっしゃるとおりで、それは要するに、いくらのものが会社に財産として入ってくるかが問題なわけですから。しかし、それに見合うだけの株式以外のものを発行しては、本当はならないはずですね。ですから、現金の場合で考えると一番わかりやすいと思うのですが、1,000円入ってきた場合には1,000円の株を渡すべきですよね。現在の商法の考え方は、この場合は1,000円が発行価額であって、流通市場における株価がいくらかはどうでもよいことなんですね。1,000円をベースに資本と資本準備金が――全額資本が原則ですが、これが決まるわけです。
同じように、今の場合ですと1,000という価値かどうかというのは、辻山委員の言葉でいうとのれん含みであって、本来、個々の資産に割り振って、割り振れない部分があればのれんも含まれて1,000という数字が決まって、それに対して対価である新株が発行されるのですが、商法は、合併の場合は発行価額という言葉を使いませんで、逆にその1,000をベースに資本を決めましょうということをいっているわけですね。
ただ、この質問をいただいたときに私が問題なしといったのは、普通はどうするかというと、普通、対価は現金で払うわけではなくて、今の場合ですと株で払いますし、入ってくる方は資産ですから、やはりわからない要素があるのですよね。ですから実際問題としては、ロジカルには今おっしゃったとおりなので、1,000に対して1,200払ってはならないのですが、実際1,200払われているということは、普通はどう考えるかというと、やはり1,200受け入れていると考えるのだと思うのですね。
そうだとしますと、1,200のうちの800が個々の資産に割り振られているとすると、残りの400はのれんというように認識するほかないでしょうということになるのだと思います。したがって、そこは斎藤部会長がおっしゃったように、普通はそこは一致するので、一致しなければおかしいと考えるのだと思います。ただ、ロジカルには辻山委員がおっしゃったとおりだと思います。これは現金の場合、一般の場合もそうだと思いますが。
- ○長坂委員
-
そうしますと、買い取った会社の通常みた純資産、プラス評価できればのれんということで、そこで資本が決まってくると思っていたのですが、基本的にはそれが発行した時価と一致するはずですから、結局、発行した株価で資本を決めて、評価された純資産プラスその差額ののれんというものがそこで出てくるという理解でよいということでしたら、パーチェス法で議論されていた、アメリカなどで行われている、実務と一致するようなイメージなのですが、そのようなことでよろしいのでしょうか。
- ○黒川委員
-
今のは卵が先かニワトリが先かという議論だと思いますが、流通株式の問題であれば、対価もわかっているということがありますよね。非流通で株式の価格が一体いくらなんだと、こちらの渡す方がですね。そのような場合に、先ほど辻山委員がおっしゃったように、純資産とのれんの部分を別個に見積もって、それで企業価値がいくらということを評価して、それを分割して何株というようなことになるのかなという気もするんですよね。
ですから、先ほどから神田部会長代理が「ロジカルには」とおっしゃっているのは、そのようなことも含めてなんだろうと理解したんですが、それでよろしいでしょうか。
- ○神田部会長代理
-
おっしゃるとおりで、ロジカルには現金の場合を考えるとわかると思いますが、資本金とは何かといったら、1,000円払い込まれたら1,000円が資本金であって、渡した株式が流通市場でいくらかは資本金と関係ないのですね。
ですから、今の例でいいますと、入ってきた方が1,000円のキャッシュなら1,000円のキャッシュが資本金になるのと同じことで、入ってくるのが企業ですから、それが先ほどのお話で、それがのれん含みの企業であるというのは辻山委員がおっしゃったことですが、それが資本金になるというのが基本の考え方であって、渡した株式が流通市場でいくらかというのはプロクシーにはなりますが、しかし、公正価値であれば同額分を渡すべきだということです。ですが、黒川委員がおっしゃるように株式の方に流通価値がなければわからないわけですから、その場合は、やはり原則に返って物事をロジカルに考えれば、そのようなことだと思います。それで、結果として市場性のある株式を渡したような場合には、これはアメリカにおける処理と同じようになるというのは、そのとおりだと思います。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
まだいろいろご発言のあることと存じますが、予定した時間を少し過ぎておりますので、どうしても今、発言したい方はいらっしゃいますか。
- ○辻山委員
-
恐縮です。次回になると、少し今日の議論とずれてしまいますので。
先ほどAOLの話が出ましたので念のためですが、先ほどのご説明にもありましたように、減損が適用されたということですが、減損というのは本来――計上されたのれんに価値があるかどうかは、やはり企業の将来キャッシュ・フローを見込んで、それに減損が生じているかどうかで減損が判定されるはずなのですが、これは株価の下落を反映して減損が決まったというケースで、会計情報が何かということを考える場合の典型的な問題点になるのかなということなので、少し念のため申し上げました。
- ○斎藤部会長
-
要するに、極めて馬鹿げたケースだとおっしゃりたいわけですね。
ほかに、よろしゅうございましょうか。
それでは、大変ありがとうございました。多少時間を超過いたしましたことをおわび申し上げます。
本日の部会はこれで終了いたしますが、次回の部会につきましては改めて事務局からご連絡いたします。
本日はお忙しいところ、まことにありがとうございました。
散会させていただきます。

 検索
検索