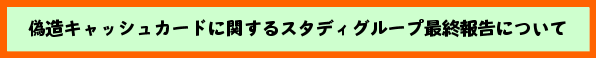 |
金融庁において開催している「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」(座長 岩原 紳作 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、先般(6月24日)、「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ最終報告書 〜偽造・盗難キャッシュカード被害発生の予防策・被害拡大の抑止策を中心として〜 」を取りまとめ、公表しました。 |
|||||||||||
1 |
.被害発生の予防策等に関する基本的考え方 被害発生の予防策等に関する基本的考え方として、最終報告書において、次のような考え方が示されております。 |
||||||||||
|
|||||||||||
2 |
.具体的な被害発生の予防策等 具体的な被害発生の予防策等については、まず顧客サービスに直結する事項として、 |
||||||||||
|
|||||||||||
| との考え方が示されています。また、主として金融機関サイドで取り組む事項として、 | |||||||||||
|
|||||||||||
| との考え方が示されています。そして、監督サイドで取り組む事項として | |||||||||||
|
|||||||||||
| との考え方が示されています。 最後に、犯罪技術について常に巧妙化が進んでいる状況の中で、金融機関は、随時、必要なシステム・セキュリティ対策を講じていく必要がある。また、システム・セキュリティ対策は金融機関に一方的に求めるものではなく、預金者のカード等の管理意識の向上等も重要な課題であり、より安全なATMシステムを実現するためには、金融機関、金融関係団体、預金者、行政当局が相互に協力して対応することが望まれる。 とまとめております。 この最終報告を踏まえて金融関係団体等及び各金融機関においては、被害発生の予防策等について、真剣な検討を行っていただきたいと考えています。 |
|||||||||||
※ |
同最終取りまとめについて、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の最終報告書の公表について」(平成17年6月24日)にアクセスしてください。 |
||||||||||
金融庁は去る6月17日、「保険会社向けの総合的な監督指針(案)」を作成・公表し、パブリックコメントに付しました。 保険会社は、顧客利便の向上、顧客保護を図る観点から、自己責任原則に基づく適切な経営管理の下で、財務の健全性の確保、コンプライアンス等業務の適切性の確保が求められているところであります。 また、保険分野においては、近年、多様化、高度化する消費者ニーズに柔軟に応えられる商品開発等が行われる態勢の整備、保険契約者等が多様なチャネルを通して、適切かつ十分な情報に基づいて、保険商品を購入できるような環境の整備などが求められているところであります。 「保険会社向けの総合的な監督指針(案)」については、このような観点も踏まえ、保険監督の目的などの基本的考え方、保険会社の財務の健全性及び業務の適切性等を確保していくための監督上の評価項目、保険商品審査上の留意点等について、従来の事務ガイドラインをベースに体系的に整理したものであります。 今回新たに整理した項目として、例えば |
||||||||
|
||||||||
| などがあります。 本監督指針については、いただいたご意見等を踏まえ、最終的なとりまとめ進め、公表する予定としております。 |
※ |
平成17年6月17日に公表した「保険会社向けの総合的な監督指針(案)」の全文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「保険会社向けの総合的な監督指針(案)に対する意見募集の実施について」(平成17年6月17日)にアクセスしてください(意見募集は〆切ました)。 |
金融庁では、「利用者のライフサイクルに応じ、身近な実例に即した金融経済教育の拡充」をうたった「金融改革プログラム」の趣旨を受け、本年3月以来、大臣の私的懇談会である「金融経済教育懇談会」において、懇談会委員の先生方に計7回にわたって金融経済教育のあり方について議論をして頂きました。 先般(6月30日)、「金融経済教育に関する論点整理」としてこの間の議論を取りまとめて頂いたところです。 この懇談会での議論の過程ですべての参加者が共有するに至った確信は、金融経済教育の充実は、時代の急務である、ということです。 ここで言う「金融経済教育」とは、国民一人一人に、金融やその背景となる経済についての基礎知識と、日々の生活の中でこうした基礎知識に立脚しつつ自立した個人として判断し意思決定する能力、つまり金融経済リテラシーを身につけてもらい、また、必要に応じその知識を充実する機会を提供することをイメージしています。 金融経済教育については、これまでも金融庁のほか、特に金融広報中央委員会をはじめ関係諸団体において様々な取組みが行われてきています。また、かつての貯蓄増強から「貯蓄から投資へ」と時代の流れが変化する中、投資教育、金融消費者教育など、その様々な側面が強調されるようになってきています。 本懇談会では、こうした流れを踏まえながら、時代の変化に対応した金融経済教育全体のコンセプトを改めて整理し共有する試みを行いました。具体的には、様々な立場からこの広義の金融経済教育に携わってきた本懇談会の委員が一堂に集まる中で、金融経済教育全体に関わる以下の3つの整理を行ったものです。 その第一は、時代の変化、具体的にはバブル崩壊後の経済・社会の構造変化や、これに伴う金融環境の変化を踏まえて、金融経済教育の今日的な意義・必要性を再確認したということです。 右肩上がり経済の終わり、高齢社会の到来、終身雇用・年功制の変容といった経済・社会の変化の中で、個人が金融資産の運用について、自らの責任で意思決定する期間・機会が人生の中で格段に増加しています。また、ペイオフ解禁、金融商品の多様化・高度化、IT化と販売チャネル多様化といった金融環境の変化の中で、個々人が情報を活用して利便性・価値を向上させる機会が増大する一方、なかには金融商品の持つリスクに気付かなかったり、騙されて損をする事例も生じています。こうした時代の変化により、金融経済教育の充実は、今や社会が要請するところとなっています。 第二は、様々な立場で金融経済教育にこれまで携わってきた各委員の豊富な体験に基づく意見・情報交換を中心に、金融広報中央委員会、文部科学省、金融庁からも情報提供を受けながら、金融経済教育の現状の問題点と今後の課題について、まずは大きく初等中等教育段階と社会人・高齢者段階の2つのライフステージに分けて実情の把握を行い、さらにはその中から、今後官民の協力の下に解決すべき共通の事項を抽出したということです。 そこで改めて認識された初等中等教育段階の現状は、教材自体は豊富に提供され、学習指導要領にも相応の記述はあり、また教育方法についても、学習指導要領の基本を押さえれば具体的な方法には現場の自由裁量がありながら、学習指導要領の記述と現場の実践との間にはギャップがあるというものでした。その要因としては、授業時間等の制約もさることながら、特に投資と投機も区別なく「金儲け」の話をタブー視する傾向、勤労を尊ぶあまり「労働なしのお金は不正」といった意識が強く見られることや、学習指導要領を消化しつつ先生自体が金融経済をイメージできる教材がなお不足していることが挙げられ、これらを変えていくべきことが課題として認識されました。具体的な教育方法については、金融や投資の社会的意義を見据えながら、疑似体験を通じて実践的、体験的な教育を行うことの重要性が指摘されました。 |
||||||
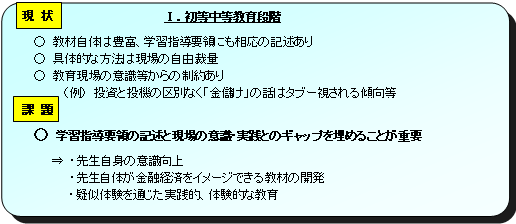 |
||||||
他方、社会人・高齢者段階の現状については、教育機会は多様であり、教育内容も対象者のニーズによって多様だが、多くの社会人・高齢者に、リスクの概念、投資と投機の区別、分散投資の基本も、知識として共有されていないことが認識されました。社会人・高齢者段階では、ニーズの多様性に応じ、主体的に学ぼうとする個人の応援、動機付けが特に重要になりますが、このような現状を踏まえると、多くの社会人・高齢者の目線に沿って上記の基本を中心に教えること、ニュース性やエンターテイメント性を持たせる工夫が必要であることが課題として指摘されました。 |
||||||
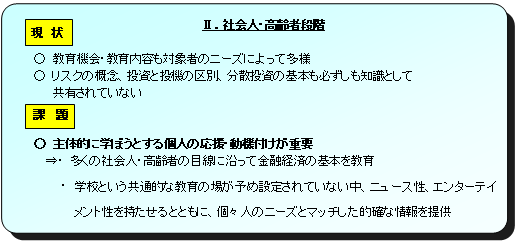 |
||||||
これら両ライフステージにまたがる様々な課題を、おおくくりに整理すれば、 |
||||||
|
||||||
| の3点が官民共通の課題であると言えます。 第三は、これら抽出された課題に応えるべく、米国・英国の事例も参考にしつつ、今後の官民連携、特にその中で金融庁の果たすべき役割について、検討し提言を行ったことです。 上記3つの課題について、特に政府には、それぞれ、 |
||||||
|
||||||
| が期待されます。これを、金融庁について具体化したものが以下に掲げる「直ちに実施すべき事項」です。 |
||||||
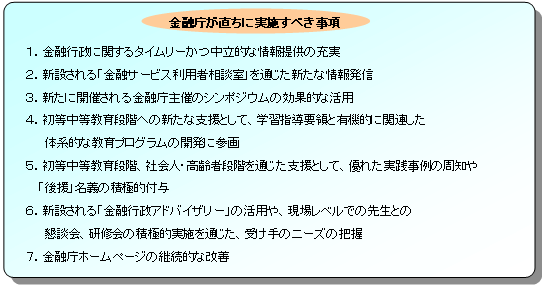 |
||||||
さらに、本懇談会は幅広い議論・検討を要する以下の諸点についても、あえて踏み込んで議論を行いました。 |
||||||
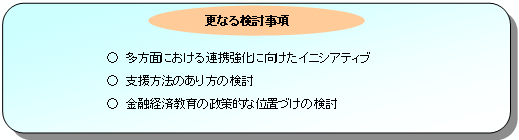 |
||||||
金融庁としては、当庁が「直ちに実施すべき事項」としてまとめて頂いた7項目にスピード感をもって取り組むとともに、今後幅広い議論・検討を要するものとしてご提起された諸点につきましても、真剣に検討していきたいと考えています。 また、今回の論点整理は、金融経済教育の現状を大枠において捉えるとともに、官民連携や金融庁の役割についても検討しようとする初めての試みであり、その意味で、決してゴールではなく、将来に向けたスタートラインです。本懇談会としては、このような議論が行われていること自体、またその内容を、できるだけ多くの学校教育や社会人・高齢者教育の現場の方々に知ってもらい、意識向上や新たな取組みの素材として役立ててほしいと考えております。 7月9日(土)には内閣府主催の経済教育サミットが開かれ、伊藤大臣も竹中大臣、福井日銀総裁とともに参加しました。金融庁としては、こうした場も活用しながら、本懇談会の提言を踏まえて、広く国民各層にこの運動への理解と積極的な参加を求めるとともに、今後とも折々の時期に同種の議論の場が金融庁において確保され、再度各関係省庁や民間・NPO団体の取組状況を検証できる機会が与えられることを希望したいと思います。 |
||||||
|
1 |
.今般、保険業法施行規則が改正され、平成17年12月から、銀行等が生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人として取り扱うことのできる保険商品の範囲が拡大されることとなりました。さらに、その後2年間、銀行等による保険募集の実施状況(既解禁分を含む。)や新たに講じることとしている弊害防止措置の実効性等をモニタリングしながら、全面解禁(平成19年12月)に移行することとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.保険業法施行規則改正内容は以下のとおりです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令について」にアクセスしてください。 |