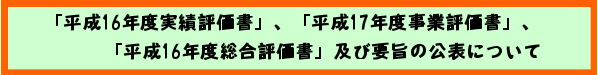 |
1 |
.はじめに 金融庁においては、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、 |
||||||
|
|||||||
| を目指しています。 これまで、金融庁においては、政策評価に係る基本計画や実施計画などを策定の上、政策評価に鋭意取り組んでおり、実績評価に関しては、平成13年度(13年7月〜14年6月)、14年度(14年7月〜15年6月)及び15年度(15年7月〜16年6月)を対象とする実績評価書を作成・公表しました。また、事業評価(事前評価)に関しては、政策評価をより一層予算に活用する観点から、一昨年、昨年とそれぞれ予算措置を伴う事業のうち新規あるいは拡充を予定している主なものを対象とする事業評価書を作成・公表しました。 |
|||||||
2 |
.平成16年度実績評価書の内容 今回は、平成16年度(16年7月〜17年6月)を対象とする政策評価実施計画に定めた43の政策について、実績評価を実施しました。 具体的には、43の政策について予め目標を定め、それぞれ目標の達成に向けて行った業務内容等を分析し、各政策の評価を行うとともに、評価結果がわかり易くなるよう、パターン化した基本類型を参考に、政策毎に「端的な結論」を付しています。 |
||||||
3 |
.平成17年度事業評価書の内容 今回は、情報等の分野の事業で、平成18年度に予算措置を伴う事業のうち新規あるいは拡充を予定している主なものを対象に、一昨年、昨年と同様、事業評価を実施しました。 事業評価の実施に当たっては、事業の目標、目的及び内容を明らかにするとともに、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行っています。 |
||||||
4 |
.平成16年度総合評価書の内容 平成15年度から着手した「電子金融取引への金融行政上の対応」について、総合評価を実施しました。 総合評価の実施に当たっては、政策の目的、政策の背景及び現状把握、政策評価の観点、評価結果、今後の課題等について説明を行っています。 |
||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「平成16年度実績評価書」、「平成17年度事業評価書」、「平成16年度総合評価書」及びそれらの要旨の公表について」(平成17年8月31日)にアクセスしてください。 |
去る8月31日、金融庁は「平成18年度税制改正要望」を財務省及び総務省に提出しました。 本年の税制改正要望は、主に 1.多様な投資家の市場参加を促進する 2.金融機関の競争力を強化する 3.国際的に開かれた金融システムを構築する との3つの観点から要望を行っています。 |
|||||
1 |
.多様な投資家の市場参加を促進するための税制 投資家がリスク資産への投資を行いやすい環境を整備することにより、「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、多様な投資家の市場参加を促す観点から |
||||
|
|||||
2 |
.金融機関の競争力を強化するための税制 金融機関におけるITの戦略的投資を促進することなどにより、金融機関の競争力の強化を図る観点から |
||||
|
|||||
3 |
.国際的に開かれた金融システムを構築するための税制 国内企業の外貨調達や海外投資家の市場参加が容易に行われる環境を整備することにより、国際的に開かれた金融システムを構築する観点から、必要な税制上の措置を要望しています。 |
||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成18年度 税制改正要望について」(平成17年8月30日)にアクセスしてください。 |
||||
1 |
.はじめに 我が国の金融システムを巡る局面の転換を踏まえつつ、金融庁の任務を引き続き的確に果たすため、利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底、ITの戦略的活用等による金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備など、「金融改革プログラム」(平成16年12月24日公表)・同「工程表」(平成17年3月29日公表)に盛り込まれた諸施策等を着実に実施するために必要な機構・定員及び予算の要求を行っています。 |
||||||||
2 |
.機構・定員要求の内容 金融庁としては、「金融改革プログラム」を着実に実施するため、平成18年度機構・定員要求においては、市場行政体制の強化を中心に、「利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底」、「ITの戦略的活用等による金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備」、「国際的に開かれた他金融システムの構築と金融行政の国際化」及び「信頼される金融行政の確立等」の四つを体制整備の重点化項目としています。 |
||||||||
|
|||||||||
(参考 平成18年度定員要求) |
|||||||||
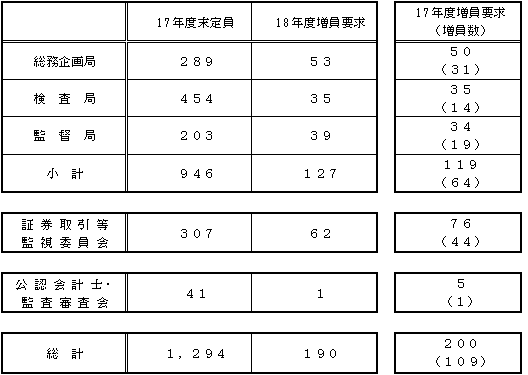 |
|||||||||
3 |
.予算要求の内容 平成18年度予算要求については、「金融改革プログラム」を着実に実施するため、予算と執行実績の乖離を是正しつつ、新たな行政需要に対応するための定員の増員に伴う経費の他、「成果重視事業」への自主的な取組み、機動的な検査・監視の実施、海外当局との連携強化、利用者の利便性向上・業務効率化のための情報システムの整備等に必要な経費を織り込み、総額で約228億円の要求を行っています。 なお、預金保険機構に係る政府保証枠については、金融システムの安定を引き続き揺るぎないものとするとの考え方に基づき、50兆1,500億円を要求しています。 |
||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から |
平成16年12月に公表した「金融改革プログラム」等では、金融専門人材の確保等のためのスキームを構築することが検討課題の一つとして挙げられました。このような課題に対応するため、金融庁と民間の業界団体とが共同で「人材ネットワーク」の基本スキームを取りまとめ、本年8月26日、金融庁から同スキームを公表しました。以下、その概要について紹介します。 |
|||||||||||||
1 |
.経緯等 昨年12月に公表した「金融改革プログラム」においては、「金融機関のガバナンスの向上とリスク管理の高度化を通じた健全な競争の促進」を図る観点から、また、本年3月に公表した「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)」においては、中小・地域金融機関による中小企業の「事業再生に向けた積極的取組み」の一環として、金融専門人材の確保等のためのスキームの構築が検討課題の一つとして掲げられました。 その背景には、金融機関が主体的な経営判断に基づき戦略的な取組みを行うに当たり、金融に関して専門的な知識を有する外部人材の積極的活用を図ることとした場合に、その候補者となり得る人材についての情報入手が必ずしも容易でないという現状があります。同スキームの構築は、こうした情報入手を容易にする仕組みを提供することにより、金融機関の自発的な取組みを支援することを目的としたものです。 このような課題に対応するため、金融改革プログラムの「工程表」に基づき、本年3月以降、金融庁と預金取扱金融機関を会員とする5つの業態別協会(具体的には、全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会及び全国信用組合中央協会)とが共同で、具体的内容について検討を続けてきました。その結果、先般、基本スキームが「人材ネットワーク」としてまとまったことから、これを公表しました。 |
||||||||||||
2 |
.スキームの具体的内容 「人材ネットワーク」は、その名にあるとおり、5つの業態別協会の間の「ネットワーク」です。個別の金融機関が業態横断的に外部人材の積極的活用を図ろうとする場合に、当該金融機関は、その所属する協会を経由してネットワークを活用することにより、ニーズに合った候補者の有無について他の業界に打診することが可能となります。各業態別協会は、会員のニーズに応じていつでも情報伝達が行えるよう、相互のネットワークをインフラとして整備することとなります。 本スキームは、具体的には以下のように機能します。 ここでは、一例として、Aという業態の金融機関「甲」に、「Cという業態の金融機関から、○○の専門家を招聘したい」というニーズがあるケースを想定してみます( |
||||||||||||
|
|||||||||||||
なお、本スキームを構成する5業態(主要行等、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合)は、それぞれが求人側となり得るとともに、求人側は、複数の業態に対してニーズを打診することができます。 |
|||||||||||||
3 |
.本スキームの意義等 上述のとおり、金融機関が主体的な経営判断に基づき戦略的な取組みを行うに当たり、金融に関して専門的な知識を有する外部人材の積極的活用を図ることとした場合、現状、その候補者となり得る人材についての情報を入手することは、必ずしも容易ではありません。本スキームは、こうした状況の下、ネットワークを通じて潜在的な人材提供側の金融機関に対してニーズ情報を伝達することにより、候補者となり得る人材の有無を比較的短期間で確認できるようにするものであり、金融機関の積極的な取組みを支援する上で意義があるものと考えています。 本スキームを実際に利用するかどうかは個別金融機関の自主的な判断によることとなりますが、今後、各金融機関が主体的な経営判断に基づき、外部の金融専門家の活用を図りつつ、戦略的な取組みを行っていくに当たり、本スキームが新たな選択肢として活用されることを期待しています。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「人材ネットワーク」の構築について」(平成17年8月26日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||
(別紙) |
|||||||||||||
早期健全化法は、資本増強行において、経営健全化計画とその履行状況を公表することにより、パブリック・プレッシャーの下で金融機関の経営の健全化を促進していくこととしています。この健全化計画については、策定後2年経過したものについて、原則、見直しを行うこととしています。 8月12日に、健全化計画の見直し対象となる18行のうち、10行において新経営健全化計画が策定されました。 他方、当期利益が経営健全化計画対比で大幅に下振れた三井住友フィナンシャルグループ、もみじホールディングス、九州親和ホールディングスに対しては、7月22日付で収益改善策を含む業務改善計画の策定・履行等を求める旨の業務改善命令を発出して、銀行の収益力の強化を推進することとしました。 この業務改善計画は、経営健全化計画の見直しに織り込まれ、9月6日に3行において新経営健全化計画が策定されました。 以上の新経営健全化計画については、各金融機関においてその内容を公表していますが、金融庁においても集計ベースで公表を行っております。 |
(注 |
)経営健全化計画とは、資本増強の申請を行った金融機関に対して早期健全化法第5条第1項に基づき提出を求めるものであり、経営の合理化のための方策等を含んだ4年分の計画となっています。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況」から、「経営健全化計画」(「経営健全化計画」の「平成17年8月12日見直し」及び「平成17年9月6日見直し」にアクセスしてください。 |
早期健全化法に基づき資本増強を行った金融機関については、優先株の消却等を行うまでの間、経営健全化計画の履行状況について報告を求め、これを公表することとされています。 8月12日に、各金融機関より平成17年3月期決算に基づく履行状況の報告がなされ、各金融機関においてその内容が公表されました。金融庁においても集計ベースで公表を行っております。 |
(注 |
)経営健全化計画とは、資本増強の申請を行った金融機関に対して早期健全化法第5条第1項に基づき提出を求めるものであり、経営の合理化のための方策等を含んだ4年分の計画となっています。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況」から、「経営健全化計画」(「経営健全化計画フォローアップ」の「平成17年3月期(平成17年8月公表)」にアクセスしてください。 |