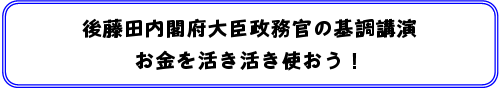 |
| |
 こんにちは。ご紹介をいただきました内閣府大臣政務官の後藤田正純でございます。本日は土曜日であり、お仕事、またはお休みのおくつろぎのところ、大勢の皆様にお集まりをいただき、金融庁を代表いたしまして心から御礼を申し上げたいと思います。本日は長時間のシンポジウムでございますが、この後は、生島さんをはじめとした各界のご専門家の方々のコーディネーションのもと、ディスカッションがございます。それに先立ちまして、私のほうから全体の流れをご説明させていただければと思っております。 こんにちは。ご紹介をいただきました内閣府大臣政務官の後藤田正純でございます。本日は土曜日であり、お仕事、またはお休みのおくつろぎのところ、大勢の皆様にお集まりをいただき、金融庁を代表いたしまして心から御礼を申し上げたいと思います。本日は長時間のシンポジウムでございますが、この後は、生島さんをはじめとした各界のご専門家の方々のコーディネーションのもと、ディスカッションがございます。それに先立ちまして、私のほうから全体の流れをご説明させていただければと思っております。
|
私は徳島県の選挙区出身でございまして、大阪の方々には阿波座をはじめ徳島にゆかりのある名前があり、また、徳島出身の方々が近畿圏には約130万人いらっしゃると言われております。先ほども徳島にゆかりのある方にご挨拶をしていただき、そういう意味では、淡路島を通じて大阪と大変近い仲で、今日こうしてお邪魔できたことを大変うれしく思っております。本当は大阪の皆様というよりは、徳島で熱心にこのようなことをやったほうがいいのかなと思います。なぜなら、今、徳島県は、1人当たりの貯蓄額が東京に次いで2番目に高く、同じ四国でも、高知の人は宵越しのお金は持たない、あったら全部使ってしまうということですが、徳島の場合は貯蓄にいそしむという県民性がございます。ひとつは、低いリスクであるがリターンも少ないという選択なのだと思います。しかしながら、皆様方に今日ご理解いただきたいのは、日本の経済全体とご当地大阪の地域経済、地域再生におきまして、今ある貯金を含めた家計の資産がいろいろなものに投資をされたり、使われたりすることが、いかに日本国内の経済の発展、ご当地大阪の地域発展、地域再生に役立つかということです。また、そのリターンが投資家に返ってくることにより、家計の資産と経済がさらに密接に結びつく時代に是非もっていきたいというのが政府はじめ金融庁の考え方でございます。一言で言うと、貯蓄から投資へという大きな政策目標を掲げているわけでございます。
今日、もうひとつ申し上げたいことは、当然ローリスク・ローリターンの預金や貯金から、投資を行えば、ある意味でミドルリスク・ミドルリターン、そしてまたハイリスク・ハイリターンとそれぞれにリスクが高まってくることは否めません。しかし、そのリスクには個人で対応していただきたい、自己責任でお願いをしたいということです。しかし、悪意に満ちた金融商品を売る方々や、組織的にされる方々については、我々、金融当局としてはしっかりと監視、監督して、しっかりとした厳正な処分も我々はやっていくということです。つまり、保護はしっかりといたしますが、過保護はいたしません。そういったこともぜひご理解をいただきたいと思っております。
そして、「どこに相談したらいいのか」「誰に聞いたらいいのか」ということについてですが、今日、スライドの最後と、資料にもご提示させていただきましたが、財務局をはじめ、大阪府、大阪市を中心としたいろいろな消費者センターに皆様方はしっかりと確認をしてください。そして、知っているものに対して投資をしていただきたいと思います。知らないものについては、しっかりと「NO」と言ってください。そして万が一、騙されそうになったら、今申し上げた専門的な機関、組織にしっかりと確認をしていただきたいということが、今日、私が申し上げたい大きな点でございます。
それでは、これから資料に沿ってお話をいたしますが、まず冒頭に申し上げたいのは、今、日本の国民の皆様の金融に対する知識がどれだけ乏しいかということでございます。預貯金については、皆さんご承知ですし、保険や年金につきましても、保険料等についての知識はもう十分お持ちになっていると思います。しかし、株式や債券等の証券投資について、またその他のいろいろな新しい金融商品については、50%を越えるパーセンテージで「知識がない」という実態が把握されています。
では、家計の金融資産の保有状況を海外と比較するとどうでしょうか。日本は、いわゆる家計の金融資産のうちの半数以上が現金・預金でございます。しかし、米国やドイツは、その比率が米国は13.3%、ドイツは35.7%でございます。これは裏返せば、日本では、預金・現金以外の株式をはじめとした投信・信託、その他の金融商品に対して、投資を十分にしていない状況であることは明確でございます。今、日本の家計の金融資産総額は合計1,479兆円という数字ですが、つい先日、日銀が出した9月末の家計の資産残高は過去最高となり、この数字が1,499兆円になったという状況でございます。その中身についてみますと、お示ししたそれぞれのパーセンテージは若干の変化がありますが、株式に対して投資をするようになってきたという数字がでております。そういう意味におきましては、徐々に預金から投資へ加速し始めたかなという現状認識をしているところです。
では、世の中のいわゆるお金の流れ、資金の流れはどうなっているのでしょうか。皆さんご承知のとおり、日本では総理大臣を直接選ぶ制度にはなっておりません。これは間接民主主義ということでございます。大統領選は、直接大統領を選べます。しかし日本では、まず、国会議員を選んで、国会議員が総理大臣を選ぶということでして、自分の思う人が総理になっていないこともあります。それと同じように、皆さんが現金を銀行に預ける場合には、そこから先に誰に貸しているのか、どういう使い方をしているのかが分かりません。分からないままに今までは戦後の高度経済成長の中で、ある一定の金利を得てきました。しかし今の日本の現状をみれば、ようやく不良債権処理を終える過程にありますが、預金金利は低いままであり未だ回復傾向にありません。デフレも徐々に徐々に良くなってきている状況において、皆様方の資金を預貯金のみならず、直接顔の見える企業の株や社債を買う、また地域再生、地域のいろいろなNPO等をはじめとしたいろいろなところにお金が流れたら、それが地域活性化につながります。そこで雇用が創出されれば、皆さんのご親族や身内の方もそこで働くことができます。そこで給料をいただいたら、またそれが投資に向かう、個人消費に向かいます。そうするとまた景気、経済が活性化していきます。やはり、我々は国という大きな経済の活性化はもとより、皆様が今後、地域の中で地域再生に使う、顔の見える投資をこれからさらにしていただきたいという意味合いもあるのです。 |
 そういうことの中で、皆様方に改めてリスクとリターンという点について、もう一度、説明いたします。預貯金は低リスク・低リターンですが、ハイリターンの商品に金融派生商品というものがありまして、アメリカをはじめとして金融先進国におきましては、こうした金融商品が開発され、経済が活性化されていくという側面もありますが、やはりそれにはリスクが伴います。皆様方のもとにもいろいろな金融商品を売りに来る方がいらっしゃいます。しかし、すべてが「ダメ」「悪い人」ではありません。すべてそれをシャットアウトしたら、いわゆる低リスク・低リターンの預貯金のままで終わってしまいますが、日本の経済、地域再生のためには、新しいこういった商品もどんどんこれから出てくるので、しっかりとご自分の金融知識、経済知識をこれから持っていただいて、しっかりと自己責任に基づいて、こういったものにもご関心を持っていただきたいという思いがございます。 そういうことの中で、皆様方に改めてリスクとリターンという点について、もう一度、説明いたします。預貯金は低リスク・低リターンですが、ハイリターンの商品に金融派生商品というものがありまして、アメリカをはじめとして金融先進国におきましては、こうした金融商品が開発され、経済が活性化されていくという側面もありますが、やはりそれにはリスクが伴います。皆様方のもとにもいろいろな金融商品を売りに来る方がいらっしゃいます。しかし、すべてが「ダメ」「悪い人」ではありません。すべてそれをシャットアウトしたら、いわゆる低リスク・低リターンの預貯金のままで終わってしまいますが、日本の経済、地域再生のためには、新しいこういった商品もどんどんこれから出てくるので、しっかりとご自分の金融知識、経済知識をこれから持っていただいて、しっかりと自己責任に基づいて、こういったものにもご関心を持っていただきたいという思いがございます。
次に資料にございますが、「自己責任を求めるための環境整備」について話をします。我々、金融庁は、先ほど申し上げましたとおり、保護はいたしますが過保護はいたしません。過保護はいたさないということは、自己責任でお願いしたいということです。しっかりとした保護として、まず金融機関等に対する厳正な検査・監督をしっかりとやらせていただいております。また、基礎的な金融経済知識や詐欺的な行為に対する警告情報などを我々もしっかりと提供していきますが、皆さんもぜひ、相談室やそういったところに必ずおかしいと思ったら相談をしてください。こう言っても必ずだまされてしまう人がいるのです。校長先生を辞めて、結構お金を持っている人がよくだまされやすいというような話がよく聞こえてきますが、ぜひ相談室に電話を入れていただきたいと思います。
また、「適合性原則」、「不招請勧誘の禁止」について説明をします。まず、適合性の原則という言葉です。こんな言葉は私も最近、知ったわけですが、簡単に言いますと、いわゆるお金を持っているか持っていないかを、その金融機関もしくは金融商品を売る人がしっかりと確認した上でものを売りなさいということなのです。持っていない人に高度なものを売ったりしてはいけませんということを、我々はこれからしっかり規制をかけていこうではないか、法律を整えていこうではないかということなのです。 「不招請勧誘」とは、文字どおり、招かざる勧誘なのです。「そんなものは求めてない」と言うのに売ることを禁止するということで、我々は一部の商品についてそうした法律や制度を運用しておりますので、こういうことがあったら「それは不招請勧誘の禁止にあたるではないか」ということをしっかりと言ってください。今日はこの2つだけでも、覚えていっていただければありがたいと思っております。 適合性の原則においては、金融機関、または金融商品を売る会社は、顧客シートというものを持っており、どのぐらいの所得があって、どういう経験があって、どういう金融商品を他に持っているかなどをアンケート等でしっかり把握した上で、それに合ったものを売るようにしております。金融機関にそういった顧客管理をしっかりと行うように、我々は厳正に指導をしていきたいと思っています。
次に、お金を運用する際の心構え、5つのポイントについてお話します。「知っているもの、分かるもので運用しましょう。」「目的に合った運用を行いましょう。」「リスクを分散して運用しましょう。」「信頼できるプロを活用しましょう。」「だまされたら泣き寝入りするのはやめましょう。」ということです。資料に信頼できるプロ、そして大阪地域での主な照会先を書かせていただいておりますので、ぜひ皆様方にはそのことをしっかりご認識、ご理解をいただきたいと思います。
|
 最後になりますが、地域社会とのかかわりという部分についてお話します。地域の企業は、企業自身やその製品になじみがあり実態が肌身で分かるため、「知っている、分かる」運用対象となり得ます。次に、地域のお金が地域で使われることにより、社会的リターンが生まれる可能性があります。これも先ほど申し上げましたとおりでございます。また、何度も申し上げますが、金融経済知識の普及・習得の場となるということでございます。先ほども府知事代理、また財務局からもお話がありましたとおり、これからは我々当局ももちろんですが、現場のNPOをはじめとしていろいろな方が金融情報、金融知識、いい意味での知識を皆様方にこれからもどんどん与えさせていただくと同時に、皆様方もしっかりとその認識をしていただきたいということでございます。 最後になりますが、地域社会とのかかわりという部分についてお話します。地域の企業は、企業自身やその製品になじみがあり実態が肌身で分かるため、「知っている、分かる」運用対象となり得ます。次に、地域のお金が地域で使われることにより、社会的リターンが生まれる可能性があります。これも先ほど申し上げましたとおりでございます。また、何度も申し上げますが、金融経済知識の普及・習得の場となるということでございます。先ほども府知事代理、また財務局からもお話がありましたとおり、これからは我々当局ももちろんですが、現場のNPOをはじめとしていろいろな方が金融情報、金融知識、いい意味での知識を皆様方にこれからもどんどん与えさせていただくと同時に、皆様方もしっかりとその認識をしていただきたいということでございます。
この後に、シンポジウムの中でいろいろな具体的な例示や、いろいろな消費者団体の代表の方や、同志社大学の先生の専門的なお話をしっかりと聞いていただいて、これからの政府または国家が、預金・貯金から投資へという流れの中で、さらに日本経済を活性化させようという思いを皆様方にご理解をいただきたいということを最後にお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
|
| 以下、次号以降のパネルディスカッションに続きます。 |