| 【国際会議入門】 |
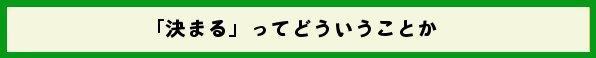 |
| 【国際会議入門】 |
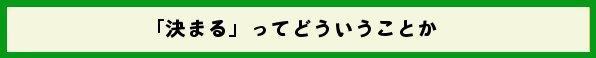 |
| |
| 「最近の国際的議論の動向について」といったテーマで講演をしたところ、「ところで国際会議でものが決まるっていうのは、どういうことを言うのですか。」という質問を受けたことがあります。組織内での会議のように最後は組織の長の判断によるのではなく、といって決定の都度投票を行っているわけでもなく、一言ではどうもうまく説明できないものです。 そこで、本稿では、「初めて国際的な委員会に出席することとなった課長補佐T君へのアドバイス」という形式で、国際会議がどんなふうに展開するかの紹介を試みました。読者の皆さんに、会議の様子に思いをはせ、そして、多くの「T補佐」達の奮闘を応援していただければ幸いです。 |
|||||||||||||||
1 |
.デビューする |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 |
.主張する |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
3 |
.交渉する |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
4 |
.最後に |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 国際業務とはある意味孤独なものです。基本的に、日本のことを知らず、発想方法も違う相手に議論をし、海外事情を知らない(理解しようとしない)国内の人に説明することの繰り返しです。 各国の情報を収集し、ここぞと思う発言・立ち回りをしても、会議の様子がわからない国内の人からは「最初から弱気の打ち出し」「いきなり譲歩しすぎ」と非難されるかもしれません。 T君のような補佐の規定の旅費では斡旋されたホテルの宿泊料には足らず、差額も大蔵省主計局通達(昭和27年蔵計922号)により支給されず自己負担になってしまうこともままあるでしょう。 国内受けをする華々しい主張をしたい、他のメンバーと違う旅費で賄えるホテルに泊まりたいという誘惑にかられることもあるかもしれません。でも、新米補佐のT君も会議に出れば日本の金融監督者の代表、そんな誘惑に負けずに、いかに良い結果を出すかに気持ちを集中して活躍してくれることを祈っています。 |
|||||||||||||||
1 |
.はじめに |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 金融審議会金融分科会第一部会(部会長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、平成17年12月22日、「投資サービス法(仮称)に向けて」と題する報告をとりまとめました。 第一部会は、平成17年7月7日に、投資サービス法(仮称)(以下「投資サービス法」)の基本的考え方等を示した「中間整理」をとりまとめました。同年9月中に、「中間整理」について広く意見募集を行ったところ、金融関係団体や弁護士会等の意見も含め、100を超える意見が寄せられました。第一部会では、昨年10月5日に審議を再開し、これらの意見も参考としつつ、「中間整理」を踏まえ、投資サービス法の法制化に向けて主要論点等に関する検討が行われました。今回の報告は、3か月の間に合計9回に及ぶ公開の会合を開催し、活発な議論を経て、とりまとめるに至ったものです。 本稿では、本報告の概要のうち、別稿で解説が行われている公開買付制度及び大量保有報告制度に関する事項以外について解説します。 |
|||||||||||||
2 |
.投資サービス法の背景と趣旨・目的 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
3 |
.投資サービス法の対象範囲 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
4 |
.投資サービス業(仮称)の業規制 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
5 |
.投資サービス業の行為規制 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
6 |
.その他 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
7 |
.おわりに |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 金融・投資サービスに関する包括的・横断的法制である投資サービス法の早期法制化は、金融・資本市場の構造改革を一層促進し、活力ある金融システムを創造していく上での喫緊の課題です。このため、本年の通常国会に関係法案(証券取引法等の一部を改正する法律案及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称))を提出することを目指して作業を進めているところです。 | |||||||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「−投資サービス法(仮称)に向けて−金融審議会金融分科会第一部会報告の公表について」(平成17年12月22日)及び「第42回金融審議会金融分科会第一部会資料」(平成17年12月22日開催)(平成17年12月22日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||
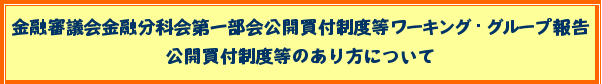 |
近年の企業の合併・買収件数の急速に伸びや、その多様化等を踏まえ、昨年7月に公開買付制度等のあり方について審議を行う公開買付制度等ワーキング・グループが金融審議会第一部会の下に設置されました。同ワーキング・グループにおいては11回にわたる精力的な審議が行われ、その検討結果は12月22日に金融審議会第一部会へ報告がなされました。以下、同報告の概要について、現行制度の見直しが必要となる部分を中心にご紹介します。 |
|
1 |
.公開買付規制の適用対象に関する提言 現行制度上、著しく少数の者からの買付けであっても、買付け後の所有割合が3分の1を超えるような場合には公開買付けによることが義務付けられていますが、このいわゆる3分の1ルールを巡っては、例えば、32%までの株式を市場外で買い付け、その後、市場内で2%の株式を買い付ける、といった態様の取引を行うことにより、公開買付けによらずに3分の1超の株券等を所有するに至る者が出てくることが想定されます。例えば一定期間に行われる取引所市場外での取引と、取引所内での取引等とを合計すると株券等所有割合が3分の1を超えるような場合に、公開買付規制の対象となることが明確なものとなるよう、所要の手当てを講じることが適当です。 |
2 |
.公開買付規制における透明性の確保と公開買付期間等のあり方に関する提言 公開買付けの手続における公開買付者からの情報開示は、株主・投資者が的確な投資判断を行う上で重要な役割を果たしており、公開買付届出書等における公開買付者による情報開示について、更なる充実を図っていくことが適当です。 また、公開買付けについて、その対象会社がいかなる意見を有しているかも、株主・投資者が的確な投資判断を行う上で重要な情報であることから、対象会社による意見の表明は義務化していくことが適当です。 さらに、対象会社による意見表明に際して公開買付者に対する質問がある場合には、意見表明報告書の中で、その点についての言及も行うなど公開買付者に対する対象会社からの質問の機会について一定の制度的枠組みを付与することが適当です。 |
3 |
.公開買付期間に関する提言 公開買付期間は、現行制度上、20日から60日の間で公開買付者の選択により決定されることとされているが、株主・投資者による十分な熟慮期間の確保等の観点から、連休等が重なる時期の公開買付けを念頭に、営業日ベースと改めることが適当です。 また、例えば、対象会社が対抗提案を提示し、株主に十分な熟慮期間を与えるために必要な場合には、30営業日を上限に対象会社による公開買付期間の伸長を認めることが適当です。 |
4 |
.いわゆる買収防衛策と公開買付規制のあり方に関する提言 現行制度上、公開買付けの撤回は、対象会社の破産や合併等限定された場合にのみ認められていますが、いわゆる買収防衛策との関連において、例えば対象会社やその子会社が新株・新株予約権の発行を決定した場合や、重要な資産の売却を決定した場合、あるいは、いわゆる買収防衛策が解除されないことが確実な場合等において、公開買付けの目的の達成に重大な支障となるようなときは、公開買付けの撤回を認めることが考えられます。 さらに、買付条件の変更についても、現行制度上、買付価格の引下げ等、応募株主に不利となる方向での変更は禁止されていますが、例えば対象会社による株式分割等により株価が希釈化された場合に、当該希釈分に対応した公開買付価格の引下げを認めることが適当です。 |
5 |
.公開買付けにおける投資者間の公平性確保、株主の保護に関する提言 現行制度上、公開買付者は、応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、按分比例の方法により、その超える部分の全部又は一部の買付けをしないことが認められています。 しかし、上場廃止等に至るような公開買付けの局面においては、手残り株をかかえることになる零細な株主が著しく不安定な地位に置かれる場合が想定されるため、例えば公開買付け後における株券等所有割合が3分の2を超えるような場合については、公開買付者に全部買付義務を課すことが適当です。 |
6 |
.買付けが競合する局面における投資者の保護に関する提言 ある者が公開買付けを実施している期間中に、他の者が取引所市場内で当該株券等を大量に買い進めるなど、会社支配権に影響のある株式の買付けが競合するような場合について、公開買付けを義務付けることが考えられますが、過剰規制とならないよう、相当厳格な要件の下での義務付けを検討することが適当です。 |
以上に加えて、大量保有報告制度について、証券市場に与える影響などには十分配意しつつ、証券取引の透明性、公正性の向上の観点から、そのあり方について所要の見直しを行っていくことが適当であるとの提言がなされています。 具体的には、機関投資家の事務負担が過大とならないよう報告頻度の軽減を認めている特例報告制度に係る報告期限・頻度等については、例えば2週間ごとの基準日における保有状況を5営業日以内に報告するなど可能な限りの短縮等を図っていくことが適当であるとされています。なお、この点については、特例報告に係る報告期限・頻度等の短縮等は基本的に行うべきでないとの指摘もありました。報告期限・頻度等の短縮等に当たっては、併せて、保有目的などに応じて機関投資家であっても的確に一般報告が提出されるよう、規定の整備等の余地がないか、更なる検討が進められるべきです。また、大量保有報告書の提出義務の有無の判断に当たって、共同保有者間の重複計上をネットアウトして保有割合を算出することを認めるなどの合理化を図っていくことが適当です。 なお、現状、保有割合が10%を上回る取引を行った際には、特例対象者であっても一般の報告が求められていますが、10%超保有の状態から保有割合が10%を下回る取引を行った場合についても、一般の報告が行われるよう所要の見直しが必要です。 これらの提言には、法律事項に係るものが多く含まれており、金融庁としては、通常国会への提出を目指している「投資サービス法案」(仮称)の取扱いと併せて、今後鋭意作業を進めていくことを予定しています。 |
|
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「第42回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨」(平成17年12月22日開催)(平成18年1月24日)及び「第42回金融審議会金融分科会第一部会資料」(平成17年12月22日開催)(平成17年12月22日)にアクセスしてください。 |
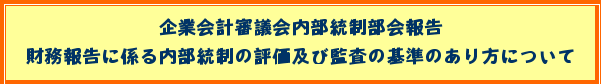 |
昨今のディスクロージャーをめぐる不適正な事例については、その要因の一つとして、ディスクロージャーの信頼性を確保するための内部統制が有効に機能していなかったことが指摘されています。また、米国においては、企業改革法(サーベンス=オクスリー法)により、平成16年から財務報告に係る内部統制について経営者による評価と公認会計士による監査が義務づけられています。こうした動きを受け、企業会計審議会内部統制部会(部会長:八田 進ニ 青山学院大学大学院教授)では、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の評価及び公認会計士等による監査の基準について審議が進められ、平成17年12月8日に内部統制部会報告「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方」が取りまとめられました。 本報告で示した基準案は、(a)経営者が整備・運用する役割と責任を有している内部統制それ自体についての定義、概念的な枠組みを示す「I内部統制の基本的枠組み」、(b)財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価についての考え方を示す「II財務報告に係る内部統制の評価及び報告」、(c)公認会計士等による監査の基準についての考え方を示す「III財務報告に係る内部統制の監査」の3部から構成されています。 |
|
1 |
.内部統制の基本的枠組み 内部統制は、基本的に、企業等の4つの目的((a)業務の有効性及び効率性、(b)財務報告の信頼性、(c)事業活動に関わる法令等の遵守、(d)資産の保全)の達成のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスで、6つの基本的要素((a)統制環境、(b)リスクと評価と対応、(c)統制活動、(d)情報と伝達、(e)モニタリング、(f)ITへの対応)から構成されます。このうち、財務報告の信頼性を確保するための内部統制を「財務報告に係る内部統制」と定義して、本基準案における評価及び監査の対象としています。 |
2 |
.財務報告に係る内部統制の評価及び報告 経営者は、内部統制を整備・運用する役割と責任を有しており、財務報告に係る内部統制については、その有効性を自ら評価し、その結果を内部統制報告書として外部に報告することが求められます。経営者が内部統制の有効性を評価するに当たっては、まず、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)について評価を行い、その結果を踏まえて、業務に係る内部統制について評価を行うこととなります。 |
3 |
.財務報告に係る内部統制の監査 経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価について、その評価結果が適正であるかどうかについて、当該企業の財務諸表の監査を行っている監査人が監査を行います。監査人は、監査の結果を内部統制監査報告書として作成し、経営者に提出することとなります。 本報告においては、我が国の会社法制と整合的で、かつ、国際的にも説明可能な実効性ある基準のあり方が示されるとともに、財務報告に係る内部統制について経営者による評価及び監査人の監査を求めることが過度の負担になるのではないかとの議論を踏まえ、先行して制度が導入された米国の運用状況等も検証し、コスト等が過大とならないための方策が盛り込まれています。 また、同報告において示された基準案に対しては、これを実務に適用していくとした場合のより詳細な実務上の指針(実施基準)の整備を求める声が多く寄せられたことから、同部会では今後、さらに実施基準の検討を進めることとされ、昨年12月に同部会の下に作業部会(座長・橋本 尚 青山学院大学大学院教授)が設置されました。 なお、昨年12月22日の金融審議会第一部会報告において、上場会社における財務報告の適正性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制に関する経営者による評価と公認会計士による監査について、本報告を踏まえ、その義務化を図ることが提言されています。また、その際、有価証券報告書の記載内容の適正性についての経営者の確認を求める制度についても、併せて導入することが提言されています。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「企業会計審議会内部統制部会の報告書のとりまとめについて」(平成17年12月8日)にアクセスしてください。 |