|
はじめに 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布されました。また、この法律に基づき「金融商品の販売等に関する法律施行令」(政令)が11月17日に公布されました。これらの法律・政令は平成13年4月1日から施行されることになりますが、このコーナーでは、それらの概要などについてご紹介します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
.法律の制定にあたって 我が国では近年、人々の日常生活における預金、保険、年金などの金融取引の重要性が次第に高まり、そうした金融取引への人々の関心が以前にも増して大きくなってきています。また、情報技術の急速な高度化等によって、極めて多様で複雑な金融商品が開発され、人々に提供されるようになっています。 これに伴い、顧客の金融商品に対する知識の不十分さ等から、金融取引を巡る訴訟が問題となってきており、とりわけワラント(新株引受権)や変額保険に関する取引については、投資家・保険契約者等から証券会社・保険会社等に対して訴訟が提起されています。 他方、経済のストック化や高齢社会への移行に伴い、国民の金融資産の有利な運用が求められるようになっています。また、積極的なリスク負担を伴う新規産業への円滑な資金供給も重要な課題となっています。さらに、通信技術の発展や経済のグローバル化により多様化しつつある課題に応えるためには国民の市場への信頼確保が不可欠となっています。 こうした状況に鑑み、金融審議会第一部会(部会長:蝋山昌一高岡短期大学長)では、21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融サービスの利用者の保護を図るため、今後予想される多様な金融商品の登場等にも備える横断的な販売・勧誘に関するルールの整備等について審議し、その結果を平成11年7月及び12月にそれぞれ「中間整理(第一次)」及び「中間整理(第二次)」として取りまとめ、公表しました。 これを受け、大蔵省においてその速やかな法制化に向けて検討を行った結果、平成12年3月24日、「金融商品の販売等に関する法律案」(金融商品販売法案)として閣議決定され、同日第147回通常国会に提出されました。同法案は衆参両院における審議を経て、5月23日に可決・成立、同31日に平成12年法律第101号をもって公布され、平成13年4月1日から施行されることになりました。 平成12年7月1日、それまで大蔵省が有していた金融に関する制度の企画・立案に関する機能を統合し、新たに金融庁が発足しました。金融庁では、引き続き本法律に基づく政令の策定を進め、その案を10月6日に公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、合計21件の意見の提出があり、それらも参考として、「金融商品の販売等に関する法律施行令」が11月17日に平成12年政令第484号をもって公布され、本法律の施行の日である平成13年4月1日から施行されることになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II |
.法律の基本的な考え方について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III |
.金融商品の販売等に関する法律の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【金融商品販売業者の説明義務の明確化及び説明義務違反に対する損害賠償責任】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【金融商品販売業者の勧誘の適正の確保】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇本法律は、平成13年4月1日から施行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | .金融商品の販売等に関する法律の意義 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
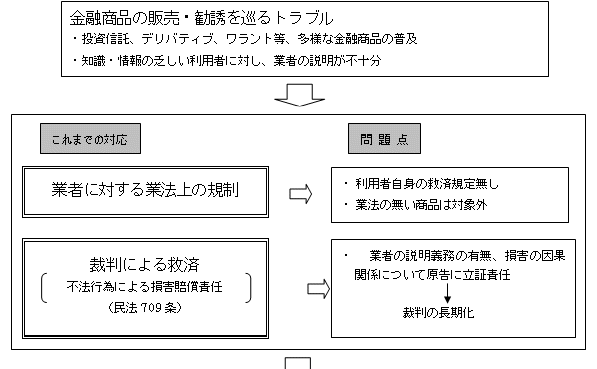 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
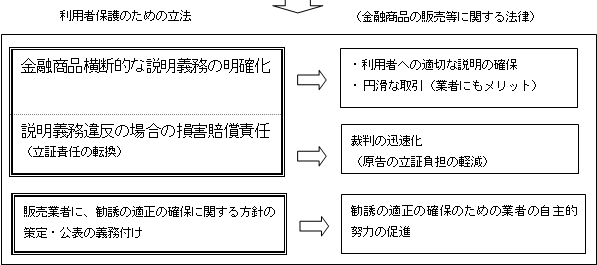 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V |
.金融商品の販売等に関する法律 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
要綱 二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するため、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一 |
目的 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとする。 (第1条関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二 |
定義 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
三 |
金融商品販売業者等の説明義務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四 |
金融商品販売業者等の損害賠償責任 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
五 |
勧誘の適正の確保 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
六 |
過料 上記五2.又は3.の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処することとする。(第9条関係) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
七 |
附則 この法律は、平成13年4月1日から施行し、施行後に金融商品販売業者等が行った金融商品の販売等について適用するほか、所要の経過措置を整備することとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本文 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 一条 この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (定義) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 二条 この法律において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | この法律において「顧客」とは、金融商品の販売の相手方をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金融商品販売業者等の説明義務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項第一号から第三号までの「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利であって政令で定めるもの(以下この項及び第五条第二項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の物又は権利がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれがあることをいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第一項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金融商品販売業者等の損害賠償責任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 四条 金融商品販売業者等は、顧客に対し前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において、当該重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (損害の額の推定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 五条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (民法の適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 六条 重要事項について説明をしなかったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (勧誘の適正の確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 七条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (勧誘方針の策定等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (過料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 九条 前条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (施行期日等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に金融商品販売業者等が業として行った金融商品の販売等について適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (重要事項についての説明に関する経過措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行後に業として行われる金融商品の販売等について、顧客に対し、この法律の施行前に重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該金融商品の販売等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (政令への委任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI |
.金融商品の販売等に関する法律施行令の概要 |
||||||||
|
|||||||||
【金融商品の販売の定義関係】 以下については、法の対象とする。 |
|||||||||
|
|||||||||
【金融商品販売業者等の説明義務関係】 特定顧客(いわゆるプロ)の範囲は、金融商品販売業者等とする。 |
|||||||||
【勧誘方針の策定・公表関係】 勧誘方針は、金融商品販売業者等の本店(主たる事務所等)において、掲示又は閲覧に供する方法により公表することを義務付ける。さらに、 |
|||||||||
|
|||||||||
◇本政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行。 |
VII |
.金融商品の販売等に関する法律施行令 |
|
要綱 金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、次によりこの政令を制定することとする。 |
|
1 |
.定義 金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客及び勧誘方針について定義することとする。(第1条関係) |
2 |
.金銭の信託の要件 金銭の信託の要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。(第2条関係) |
3 |
.保険又は共済に係る契約 保険契約に類する保険又は共済に係る契約は、健康保険法、森林国営保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、簡易生命保険法、貿易保険法、中小企業信用保険法、中小漁業融資保証法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(第130条の2第1項等を除く。)、住宅融資保険法、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律、農林漁業団体職員共済組合法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、国民年金法(第10章を除く。)、中小企業退職金共済法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、機械類信用保険法、農業信用保証保険法、地方公務員等共済組合法、小規模企業共済法、農業者年金基金法、預金保険法、農水産業協同組合貯金保険法、雇用保険法、中小企業倒産防止共済法、日本体育・学校健康センター法、介護保険法又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とすることとする。(第3条関係) |
4 |
.差金の授受を約する取引 差金の授受を約する取引は、銀行法第10条第2項第14号(金融等デリバティブ取引)等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)に該当するものとすることとする。(第4条関係) |
5 |
.金融商品の販売となる行為 金融商品の販売となる行為は、(a)金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約の委託者との締結、(b)不動産の信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約の匿名組合員との締結及び(c)上記4.の取引以外の取引であって銀行法第10条第2項第14号等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)又は当該取引の取次ぎとすることとする。(第5条関係) |
6 |
.金銭相当物の範囲 金銭相当物は、上記5.(a)の信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とすることとする。(第6条関係) |
7 |
.重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者 重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者は、顧客の行う行為を代理する者とすることとする。(第7条関係) |
8 |
.特定顧客 特定顧客は、金融商品販売業者等とすることとする。(第8条関係) |
9 |
.勧誘方針の策定を要しない者 勧誘方針の策定を要しない者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とすることとする。(第9条関係) |
10 |
.勧誘方針の公表の方法 勧誘方針の公表の方法は、金融商品販売業者等の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び(a)金融商品販売業者等が、その本店等以外の営業所等において金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、当該営業所等ごとに勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法、(b)金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、勧誘方針を自動送信する方法とすることとする。(第10条関係) |
11 |
.施行期日 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行することとする。 |
|
本文 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号) 内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十三号、第三条第二項、第三項ただし書及び第四項第一号並びに第八条第一項ただし書及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (定義) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 一条 この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第四項まで又は第八条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金銭の信託の要件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 二条 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (保険又は共済に係る契約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 三条 法第二条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (差金の授受を約する取引) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 四条 法第二条第一項第十二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる規定により行われる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引及び同法第百四十五条の五第一項に規定する店頭商品先物取引(次条第三号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)に該当するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金融商品の販売となる行為) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 五条 法第二条第一項第十三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金銭相当物の範囲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 六条 法第三条第二項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 七条 法第三条第三項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特定顧客) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 八条 法第三条第四項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (勧誘方針の策定を要しない者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 九条 法第八条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (勧誘方針の公表の方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 十条 法第八条第三項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第一号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII |
.関連リンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する集団的な投資の仕組み(いわゆる集団投資スキーム)について、資金調達者の選択肢を拡大し投資者に対する多様な商品の提供を可能にする観点から法制の整備を図ることを目的とする「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布された。この法律により、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」及び「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」が「資産の流動化に関する法律」(以下「SPC法」という。)及び「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」という。)にそれぞれ改正され、同年11月30日に施行された。また、この法律の施行に伴い、「資産の流動化に関する法律施行令」、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」等の関係政令・府令が11月17日に公布、11月30日に施行された。 現在、我が国においては、経済のストック化や高齢化社会を背景とする国民の金融資産の運用ニーズの高まり、経済が成熟化するなかでの新規産業への円滑な資金供給も重要な課題となっている。 今回の法整備は、このような課題に対して重要な機能を果たすことが期待される集団投資スキームについて、金融審議会第一部会報告(平成12年12月21日)を踏まえ、適切な利用者保護を前提としつつ金融仲介者による創意工夫が発揮できる仕組みを整備するものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | .「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の改正について 98年9月に施行された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」は、指名金銭債権及び不動産を特定目的会社(以下「SPC」という。)を利用して流動化する仕組みを定めたものであり、特定資産を投資の唯一のよりどころとする資産流動化の特質を踏まえてスキームの変動防止などの投資者保護の枠組みを定める一方、流動化の器であるSPC自体は簡素な組織となるよう定めていた。 今回の改正は、流動化対象資産を財産権一般に拡大するとともに、SPCに関する規制を簡素・合理化して、より使い勝手のよい制度に改めた。また、流動化の器として信託も利用可能とした。これに伴い法律名を「資産の流動化に関する法律」に改めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II |
.「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正について 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」は、有価証券の発行により広く一般投資家から資金を集め、これを投資法人または信託という器を利用して、主として有価証券に投資運用する仕組みを定めていた。 今回の改正は、主として有価証券に運用するための仕組みを定めた証券投資信託法を改正し、不動産を含めた幅広い資産に投資運用できるよう規定を整備した。これに伴い法律名を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正の概要】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .運用制限の緩和 主たる運用対象を有価証券、不動産その他の政令で定める資産に拡大した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .投資信託委託業者(運用業者)に関する規定の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .信託スキームに係る規定の整備 信託会社等が自ら資産運用を行う仕組みを整備した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
関係政令の概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .資産の流動化に関する法律施行令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.投資信託及び投資法人に関する法律施行令 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
.その他関係政令の整備等 証券取引法施行令及び外国証券業者に関する法律施行令等の資産流動化法及び投信法関係政令の整備を行った。また、資産流動化法の施行の後もなお効力を有する旧特定目的会社法に係る経過措置を定めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記政令の要綱・本文については下記をクリックして下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
関係府令の概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
.資産の流動化に関する法律施行規則 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
.その他関係府令 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、証券取引所及び金融先物取引所の組織形態に株式会社形態を導入する「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布、12月1日に施行された(同法では、このほかに企業内容等の開示手続の電子化も行われ、平成13年6月1日以降段階的に施行されることとなっている)。 また、この法律の施行に伴い、「証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令」及び「証券取引所の設立等に関する総理府令の一部を改正する総理府令」が11月17日に公布された。 本コーナーでは証券取引法(証券取引所の株式会社化)を中心に改正の概要を解説する(なお、金融先物取引法についても、基本的に証券取引法と同一の考え方、スキームにより、法改正が行われた)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I |
.証券取引法改正の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
II |
.政令改正の概要 |
||||
|
III |
.総理府令改正の概要 総理府令の改正は、法律の施行に伴う改正に合わせて、その他の所要の改正も行った。法律の施行に伴う改正のうち、主な点は以下のとおりである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令案に係る概要の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 証券取引所の設立等に関する総理府令等の一部を改正する総理府令案に係る概要の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
第147回国会における大蔵省関連成立法律(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最近、金融システム改革における取引所集中義務の撤廃やインターネット証券取引の発展等を背景に、証券会社等による私設電子取引市場の開設の動きが見られる。こうした動きは市場間競争を通じて有価証券市場全体の効率を向上させるとともに、流動性の低い有価証券の流通市場を整備すること等を通じて、投資者の利便性の向上にも寄与するものである。 他方、こうした新たな形態の証券業については、公正な取引の確保、投資者保護の観点から、従来の伝統的な証券業においては想定していなかった様々な問題が予想される。 従って金融庁として、投資者保護等の観点も踏まえ、有価証券取引の電子化を進めるため、「私設取引システム(PTS)の開設に係る指針」を策定し、11月16日に公表するとともに、当指針に基づき関係総理府令及び事務ガイドラインの改正を行った。 PTS業務における売買価格の決定方法として、従来の「市場価格売買方式」、「顧客間交渉方式」に加え、更に「顧客注文対当方式(顧客同志の注文を対当させることにより取引を成立させる方法)」と「売買気配提示方式(証券会社が売り気配及び買い気配を提示し、当該気配に基づき自己の計算で顧客との間で売買を行う方法)」を認めることとした。 一方、売買価格の決定方法を拡充したこと等により、PTSに一定の価格形成機能が生ずることとなるため、価格情報の外部公表や取引高シェアに応じて一定の措置を講ずることを義務付けるといった公正な取引の確保のためのルールの整備を行った。 また、投資者保護等の観点から、新しい形態のPTS業務に対する認可審査や監督上の対応として、認可基準や定期報告について所要の見直しを行った。 本指針に基づく認可申請の受付は12月1日に開始した。今後、新たな形態のPTSが開設されることにより、市場間競争が促進され、投資者の利便性の向上が図られることが期待される。 |
関連リンク |
|
| ○ | 私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について |
| ○ | パブリックコメントに対する回答 |
| ○ | 私設取引システム(PTS)開設等に係る指針の公表について(パブリックコメントに付した案) |
| ○ | 関係総理府令 |
| ○ | 関係ガイドライン |
| ○ | 証券取引審議会市場WP主査報告(金融システム改革時におけるPTS導入の議論) |
|
|||
| 6日(月) | ・ | 金融税制に関する研究会開催(第2回) | |
| 8日(水) | ・ | 金融審議会第一部会開催(第31回) | |
| ・ | 金融トラブル連絡調整協議会開催(第2回) | ||
| 9日(木) | ・ | 企業会計審議会第二部会開催(第11回) | |
| 10日(金) | ・ | 企業会計審議会第一部会開催(第3回) | |
| ・ | 証券会社に関する総理府令等の一部改正案に係る概要の公表(パブリック・コメント) | ||
| ・ | 「金融商品の販売等に関する法律施行令案」に対するパブリックコメントの結果公表 | ||
| 13日(月) | ・ | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果公表 | |
| ・ | 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う政令案」に対するパブリック・コメントの結果公表 | ||
| 15日(水) | ・ | 金融審議会第二部会開催(第21回) | |
| ・ | 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の公表(パブリック・コメント) | ||
| 16日(木) | ・ | 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う総理府令案」に対するパブリック・コメントの結果公表 | |
| ・ | 「私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について」発表 | ||
| 17日(金) | ・ | 企業会計審議会固定資産部会開催(第3回) | |
| ・ | 「金融商品の販売等に関する法律施行令」公布 | ||
| ・ | 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律関係政令・府令」公布 | ||
| ・ | 「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律関係政令・府令」公布 | ||
| 22日(水) | ・ | 事務ガイドライン改正(SPC関連) | |
| 24日(金) | ・ | 「商法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う金融関係政令案の概要の公表(パブリック・コメント) | |
| 28日(火) | ・ | 事務ガイドライン改正(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項」) | |
| 30日(金) | ・ | 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」及び関係政令・府令施行 | |