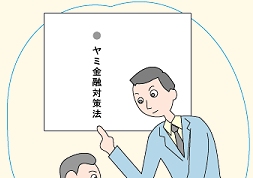4.取立行為等に対する規制の強化 |
|||||||||
(1) |
貸金業規制法では、債権の取立てにあたり、人をおどかしたり困惑させることは禁止されていますが、その具体例が法律で明記されるとともに、罰則が引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象)。 |
||||||||
|
|||||||||
(2) |
貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いてはなりません。年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどが禁止されます。 |
||||||||
(3) |
貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければなりません。 |
||||||||
(4) |
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはなりません。 |
||||||||
(5) |
貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはなりません。 |
||||||||
5.貸金業務取扱主任者制度の創設 |
|||||||||
|
|||||||||
6.高金利を定めた貸付契約の無効 |
|||||||||
貸金業を営む者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、当該貸付契約は無効となります。この場合、利息は一切支払う必要はありません。 |
|||||||||
7.罰則の大幅な引上げ |
|||||||||
(1) |
出資法に違反する高金利での貸付け、無登録営業に対する罰則の大幅な引上げ。 |
||||||||
|
|||||||||
(2) |
出資法に違反する高金利の支払の要求、無登録業者の広告・勧誘など処罰の範囲の拡大。 |
||||||||