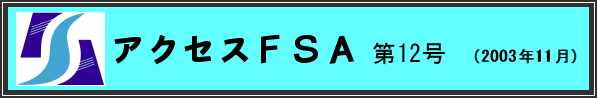 |
 |
 |
| 加古企業会計審議会会長より竹中大臣に対し、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」の手交 | 中小企業金融に関するシンポジウムを関東(10/14)・近畿(10/21)・東海(10/23)の各財務局で開催 |
| (10月31日) | |
| →関連記事 | →関連記事 |
| 目 次 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業会計審議会(会長 加古宜士 早稲田大学教授)は、去る10月31日、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下、「意見書」といいます。)をとりまとめ、公表しました。以下、意見書及びそれに含まれる「企業結合に係る会計基準」(以下、「基準」といいます。)の内容について簡単に説明します。 |
|||||
○ |
審議会における審議状況 企業会計審議会第一部会(部会長 斎藤静樹 明治学院大学教授)における企業結合会計の審議は、平成12年9月に開始されました。第一部会は、まず、論点の整理に着手し、平成13年7月に「企業結合に係る会計処理基準に関する論点整理」を公表しました。 その後、第一部会では、論点整理に対して寄せられた意見を参考にしながら審議を継続しました。この間、海外で行われていたパーチェス法(※1)と持分プーリング法(※2)の取扱いを巡る議論を睨みながら、国際的調和の観点も踏まえ、パーチェス法と持分プーリング法の取扱いを検討の主軸に置いて審議が進められ、その成果が本年8月1日に公開草案として取りまとめられ公表されました。さらに、本年9月以降、公開草案に寄せられた意見を踏まえ、第一部会において審議が進められ、公開草案を一部修正の上、総会に意見書案として提出されました。その案が、今回の総会において意見書として確定され、公表に至った次第です。 |
||||
|
|||||
○ |
「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」の内容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
「意見書」の本文等をご欄になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「企業会計審議会の意見書の公表について」(平成15年10月31日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融庁は、去る10月7日、学校における金融教育の一層の推進を図るために開発してきた副教材「インターネットで学ぼう わたしたちの生活と金融の働き」をホームページに掲載しました。 |
|
【 |
副教材開発のねらい】 近年、金融を取り巻く環境は大きく変化し、多様な金融商品や取引形態が登場するとともに、金融はより身近な存在になりつつあります。このような状況の下、消費者として将来を見据えた賢明な生活設計を行うためには、金融に関する幅広い知識や判断力を養う必要があります。このため、金融庁では、金融の仕組みや働きなどについて基礎的な知識が得られるようにするとともに、自分たちの身近な生活と金融との結びつきを理解し、金融についての関心を高めることをねらいとして、中学生及び高校生を主な対象とする副教材を開発したものです。 |
【 |
副教材は学習指導要領に対応】 副教材は、平成10年改訂の中学校学習指導要領(社会科、技術・家庭科)及び平成11年改訂の高等学校学習指導要領(公民科[現代社会、政治・経済]、家庭科[家庭基礎、家庭総合、生活技術])に対応した内容になっています。 |
【 |
副教材の内容】 副教材の構成は、「生徒用ページ」、「教師用ページ」及び「資料集」などからなっています。 このうち、生徒用ページの「入門編」は、中学・高校生に向けての「金融」への入門的な内容としており、日常生活は「金融」を通じてお金(資金)が移動して取引が結了すること、あるいは「金融」は企業等の生産活動の根幹であり、資金の借り手(企業等)と資金の貸し手(家計)との間をお金を介してつなぐものであることなど、経済社会の中で「金融」の果たす役割や働きが国民生活にとって重要な部分を占めていることを分かり易く解説しています。 更に「基礎編」は、主に高校生を対象に「金融」を通じて現代社会についての関心を高めてもらい、経済社会の発展の基礎である金融・資本市場に対する正しい認識を持つとともに、将来、社会に出た場合に金融機関や金融商品・サービスの仕組みや内容を理解し、選択をする際の手助けになるよう意図した構成・内容にしております。 「教師用」については、副教材の学習指導に当たっての取り扱い上の留意点等、指導・手引書的な内容としています。 |
金融庁では、今後、副教材が、学校教育現場などにおいて、より一層の利用が図られるようPRを行うとともに、変化の激しい金融分野の動きに対応するため、年1回程度見直しを行っていくこととしています。更に、投資教育の必要性・重要性をアピールするため、「金融経済教育」をテーマとしたシンポジウムを開催することも考えています。これらを通じて、金融についての理解をより深めてもらうよう努めていきたいと考えています。 |
|
※ |
副教材をご欄になりたい方は、金融庁ホームページの「インターネットで学ぼうわたしたちの生活と金融の働き」にアクセスしてください。 |
1 |
.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」とは 金融庁では、中小企業等への金融の円滑化に向けた取組みの一環として、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設しています。これは、中小企業が、金融検査マニュアルなどを理由に金融機関から不当な扱いを受けた場合等に、金融庁等に直接通報できるよう、ファックスや電子メールの受付窓口を設けたものです。 |
||||||||||||
2 |
.ホットラインに寄せられた情報の受付と活用の状況(平成15年9月末現在) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
※ |
平成15年9月末のホットライン受付・活用状況等について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」(平成15年10月24日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||
| ※ | 平成15年3月末まで及び平成15年6月末までの受付・活用状況については、それぞれ金融庁ホームページの「報道発表など」から「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」(平成15年4月21日)、「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」(平成15年7月29日)にアクセスしてください。 |
平成15年7月28日に発表された金融審議会金融分科会第二部会・自己資本比率規制に関するワーキンググループの「経過報告」においては、「繰延税金資産の算入根拠と計算手続きに関して、繰延税金資産の計上額に対する信頼性を高めるための情報開示の拡充等について、(中略)有効な方策を実施することを求めたい」とされているところです。 これを受けて、10月31日(金)に、主要行に対し、15年9月期の中間決算短信の公表時から、繰延税金資産の情報開示の拡充を行うよう要請しました。なお、今般の措置は、繰延税金資産の計上額に対する信頼性を高めることを目的としていることから、開示する計数等をもとに計算手続き等に即した分かり易い説明を行うことを併せて要請したところです。 |
|||||||||||||||||||||||
( |
参 考)開示項目 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※ |
本文や自己資本比率規制に関するワーキンググループの「経過報告」をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「繰延税金資産の情報開示の拡充について」(平成15年10月31日)にアクセスしてください。 |
1 |
.金融活動作業部会(FATF)とは何か 金融活動作業部会(FATF)とは、マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために組織された政府間機関で、現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関(欧州委員会及び湾岸協力理事会)から構成されています(「FATF」は、通常「ファトフ」と呼ばれます)。 FATFでは、主な活動として、マネー・ローンダリングに関する「40の勧告」及びテロ資金供与に関するFATF特別勧告を策定し、これら勧告の実施状況を把握したうえで、マネー・ローンダリング対策あるいはテロ資金対策が十分でない国や地域に対して改善を促しています。 |
※ |
FATF及び「40の勧告」について、詳しくは金融庁ホームページの「マネー・ローンダリング」から「国際会議」にアクセスしてください。 |
2 |
.テロ資金供与に関するFATF特別勧告とは何か 2001年9月11日の米国における同時多発テロの翌月、FATFは8つの勧告からなる「テロ資金供与に関する特別勧告」を採択しました。これが、テロ資金供与に関するFATF特別勧告と言われるものです。 テロ資金供与に関するFATF特別勧告の主な内容は、テロ資金供与防止条約等の国際連合諸文書の批准及び履行、テロリストの資産の凍結及び没収、テロに関する疑わしい取引の届出、代替的送金システム(いわゆる「地下銀行」)に対する規制、非営利団体に対する監視強化などで、これらのひとつに今回のお知らせの対象であるFATF特別勧告VII、つまり「電信送金における送金人情報の付記」があります。 |
※ |
「テロ資金供与に関する特別勧告」について、本文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「マネー・ローンダリング」から「国際会議」に入り、FATFの活動状況「3.テロ資金対策」にアクセスしてください。 |
3 |
.FATF特別勧告VII(電信送金)の実施について FATF特別勧告VIIにおいては、金融機関がその顧客のために電信送金を行う場合に送金人の情報(氏名、口座番号、住所)を付記することとしています。本年2月、この勧告についての実施の細則となる「解釈ノート」が作成されました。この解釈ノートには、送金人情報に不備があるときの取引の取扱いについて、被仕向金融機関は当該仕向金融機関に対する取引の縮小又は終了を考慮すべき旨の記述があり、また、遅くとも平成17年2月までに同勧告及び解釈ノートに従った措置を実施することとされています。 これら勧告及び解釈ノートについては、既に実施している金融機関も海外に散見されるところ、こうした海外の金融機関においては、同解釈ノートに従い、本邦から国外への送金の際に付記が求められている送金人の情報に不備が認められる場合、当該送金を行った本邦の金融機関が特別勧告VIIを遵守しない金融機関として、取引を縮小又は終了されるか、あるいは送金そのものの受領を拒否されるおそれがあります。 また、今後、同勧告及び解釈ノートに従った措置を実施する金融機関が増加してくる可能性があります。 したがって、海外への金融機関へ電信送金を行う場合は、個々の金融機関において同勧告及び解釈ノートの内容にあらかじめご留意いただき、円滑な金融取引を行う際のご参考となるように、10月31日、お知らせを発出しました。 |
※ |
金融活動作業部会(FATF)特別勧告VII(電信送金)の実施に関するお知らせをご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「金融活動作業部会(FATF)特別勧告VII(電信送金)の実施に関するお知らせ」の発出について」(平成15年10月31日)にアクセスしてください。 |