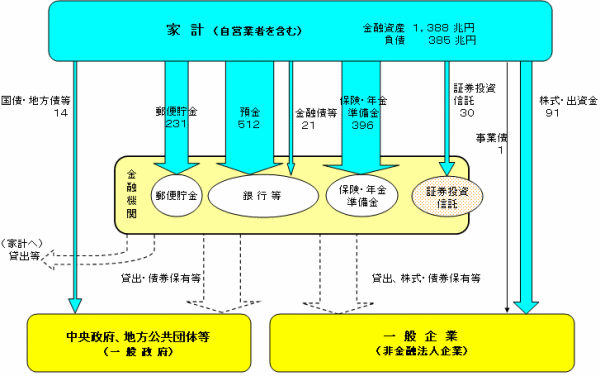
|
1 |
.はじめに 本年1月31日、「金融経済教育を考えるシンポジウム」が開催された。これは金融研究研修センターが初めて主催するシンポジウムでもあり、私も参加させていただいたが、会合でのやり取りをお聞きする中で、金融経済教育には「株を買わせるための教育」というネガティブなイメージがつきまとっており、金融経済教育に携わる関係者の方々の御苦労も、この点に起因するところが大きいのではないかという印象を受けた。 そこで、今回は、このように株式投資が多くの人にとって敬遠されがちな背景、そして金融経済教育の意味などについて、改めて考えてみたい。 |
||
2 |
.株式投資をしたいと思わない理由 平成14年5月に内閣府から公表された「証券投資に関する世論調査」によると、全体の約83%の人が「今後株式投資を行うつもりがない」と答えており、そう答えた人に更にその理由を尋ねたところ、回答の上位5位は以下のとおりであった(複数回答)。 1「株式投資に関する知識を持っていないから」(33.3%) 2「株価の下落により損失が発生するリスクがあるから」(32.5%) 3「まとまったお金がないと購入できないから」(32.4%) 4「株式投資を行うのに十分な資産や収入がないから」(25.5%) 5「資産運用は預貯金で十分だから」(14.6%) これを見ると、株式投資が敬遠されがちな要因として、知識の問題は大きいようである。しかしながら、このほか、「リスクがとれない」「十分な資産や収入がない」といった回答の背景にある家計の財産状況にも注意する必要がありそうだ。 |
||
3 |
.家計の財産状況 |
||
|
|||
(図1) |
|||
| 家計の金融資産はどのように使われているか(平成15年6月末) | |||
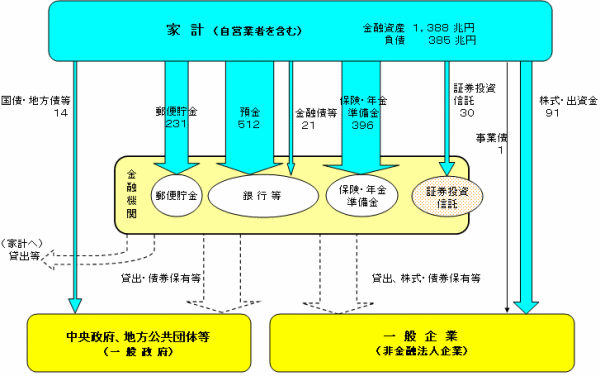
|
|||||||||
|
|||||||||
(図2) |
| 世帯主の年齢階級別1世帯当たり貯蓄・負債及び株式等保有状況 |
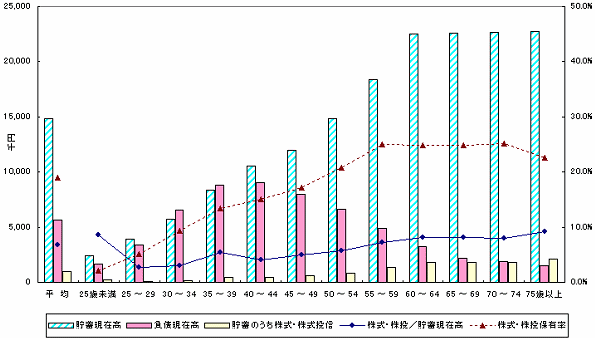
|
|||||||
|
|||||||
4 |
.金融経済教育の意味 2.の世論調査で見られた「十分な資産や収入がない」「リスクがとれない」といった回答の背景には、家計の財産状況に対する厳しい認識があり、その1例として、上記のような住宅ローン負担の存在があると考えられる。そのため、金融経済教育について「株を買わせるための教育」といったイメージが先行すると、無理なことを強いられるといったネガティブな受け止め方がなされてしまうのかもしれない。 しかし、当然ながら、金融経済教育は「株を買わせるための教育」ではない。家計の資産運用と関連付けて考えてみると、例えば、次のような意味があると思われる。 |
||||||
|
|||||||
5 |
.おわりに かくいう私も、これまでの資産選択は極めて「日本的」で、預貯金に著しく偏っており、本稿は自戒もこめて書いている。今後は、幅広い選択肢・機会費用を意識しつつ、ウマイ話にはだまされないよう身を守り、企業活動や金融証券市場の問題にも関心を持ちながら、大事な財産を上手に築いていきたいと思う。 |
||||||
(文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解である) |
|
※ |
金融研究研修センターは、平成13年7月、金融庁における「研究と研修の効果的な連携」を目的として発足し、金融理論・金融技術等に関する研究を通じて専門的な知識を蓄積しつつ、それを活かした研修等により不断に職員のレベルアップを図っていくための活動を行っています。センターの概要や活動内容等については、ホームページ(http://www.fsa.go.jp/frtc/index.html)をご覧下さい。 |
1 |
.はじめに 平成16年度税制改正(案)については、先般1月16日、「平成16年度税制改正の要綱」が閣議決定されました。今般の改正においては、当庁の要望を踏まえ、公募株式投資信託に係る税制が上場株式並みに整備されるなど、金融・証券税制を中心に、種々の措置が講じられることとされています。ここでは、その主なものについて説明します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.税制改正(案)の概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年12月24日に取りまとめられた金融審議会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」について、前号の第1回においては「市場間競争の制度的枠組み」「ディスクロージャー制度の整備」を紹介しましたが、今回は「市場監視機能・体制の強化」「投資サービスにおける投資家保護のあり方」について紹介します。 「市場監視機能・体制の強化」については、(i)市場監視機能の強化として課徴金制度の導入等、(ii)市場監視体制の強化として証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大等という2つの大きな柱からなっています。 |
|||||||
|
|||||||
| 以下、両項目について報告の詳細を紹介します。 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| 1 | .市場監視機能 | ||||||
|
|||||||
|
2 |
.市場監視体制 |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| 1 |
.基本認識 様々な投資サービスは、その名称やスキームの形態を問わず、投資家にとって経済効果が同じであれば、同じように保護されるべきであり、サービスを提供する事業者側から言えば、同じように規制に服すべきであります。こうした環境が整うことにより、名称やスキームの形態を問わず安心して投資できるようになり、貯蓄から投資への流れの加速にも寄与することになります。 近年、組合型投資スキームを活用し、業務執行組合員(営業者)が運用を一任される形態の公募型商品が販売されるようになっており、一部には詐欺的なものもみられます。また、これまでは中小企業の未公開株式などを対象に、事業を共同して行うことを前提としていた中小企業等投資事業有限責任組合制度において、上場株式や金銭債権への投資といった対象・機能の拡充が検討されており、これを活用すれば、運用を業務執行組合員に委任する一般的な投資信託やSPCに類似する商品も組成できるようになる見通しであります。こうした現状を踏まえれば、これらの組合型投資スキームについても投資信託やSPCなどの有価証券法制と同等の投資家保護の仕組みを整備することが必要であります。 米国でのリミテッド・パートナーシップは、Howey基準(共同出資して他者の努力による収益獲得を期待するもの)に該当すれば、証券法上の投資契約として、開示、販売、不公正取引規制が課されて投資家保護が図られるし、EUではパートナーシップを用いた証券投資は、それ自体認可制で、開示義務に加え、許可を受けた販売業者だけが行えることになっています。 一方、ベンチャー・キャピタルなどが、これまでも自由度の高い組合型投資スキームを用いることにより、産業に貴重なリスク・マネーを効果的に供給してきていることは積極的に評価でき、引き続きリスク・マネーの担い手としての役割が期待されます。業務執行組合員に運用を一任することなく、特定少数の出資者が共同で投資判断を行うベンチャー・ファンドなどについては、これまでどおり、過度な規制が課されないよう配慮すべきであります。また、投資家保護の仕組みの整備は、ファンドの課税上の取扱いが変わるような組合の性質の変化をもたらす筋合はないことに留意すべきであります。 |
||||||
|
2 |
.改革の方向性 組合型投資スキームについても、一般投資家に販売するのであれば、投資信託やSPCなどの有価証券規制と同様の開示は必要であるし、販売時において事前・事後の書面交付や、断定的判断の提供による勧誘の禁止、適合性原則の遵守などの投資家保護策を講じていくべきであります。 販売業者と当局の関係は、組合型スキームを含む商品ファンドや不動産特定共同事業のファンドでは許可制となっていますが、今回投資家保護を講じようとしているのが主として有価証券その他の金融商品に投資するものであることに鑑みれば、やはり投資信託やSPCのような登録制と同等のものとすることが考えられます。また、風説を流布したり偽計を用いるといった行為は、いかなる投資サービスにおいても禁止されるべきことは当然であります。 こうした投資家保護策は、基本認識を踏まえ、当面、証券取引法において措置することが適当であります。投資家にとって経済効果が同じサービスは同じように保護するシステムを確立するとともに、詐欺的な業者を排除するための手段を用意しておくことが、組合型投資スキームを発展させる上で必要であると考えられます。 但し、部外者にとっては、証券取引法における有価証券とか証券業といった概念は馴染みが薄く、違和感を覚えるであろうし、証券取引法そのものが累次にわたる改正により言わばパッチワーク状態になっていることも否定できません。そこで、当審議会において、今後、これまで投資家保護策の講じられていない投資サービスや、新たに登場するであろう投資サービスにつき、証券取引法を中心とした有効な投資家保護のあり方について検討することとしたいと考えます。また、証券取引法の投資サービス法への改組の可能性も含めたより幅広い投資家保護の枠組みについて、中期的課題として検討を継続していくこととしたいと考えます。 |
||||||
※ |
金融審議会金融分科会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」の本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「答申・報告書等」のうち、平成15年12月24日「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(金融審議会金融分科会第一部会報告)にアクセスしてください。 |
||||||