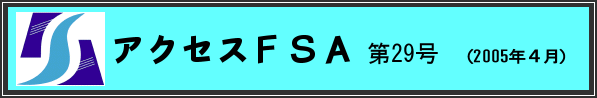 |
 |
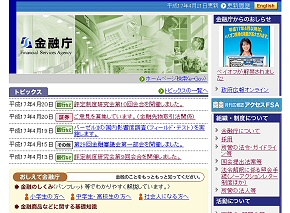 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融庁において開催している「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」(座長:岩原 紳作 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、先般(3月31日)、「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ中間取りまとめ 〜偽造キャッシュカード被害に対する補償を中心として〜 」を取りまとめ、公表しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
.偽造キャッシュカード被害に関する補償の現状及び問題点 現行のキャッシュカード約款では、金融機関は、ATMの操作の際に、カードの磁気ストライプ上の情報により、当該カードを銀行が顧客に交付したものであると確認した上で、入力された暗証番号と届出られている暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをすれば免責されることとなっています(全国銀行協会カード規定[試案]第10条第2項本文)。 同時に約款では偽造キャッシュカードによる払戻しについては、金融機関がカード及び暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを確認できた場合にはこの限りではないとしています(全国銀行協会カード規定[試案]第10条第2項但書)。しかし、その確認が困難であるため、実際には預金者が補償を受けられないケースが多いのではないかとの批判があるところです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.我が国における損失負担ルールの考え方 スタディグループの中間取りまとめでは、原則的な偽造キャッシュカードによる損失補償のあり方として、次のような考え方が示されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
その上で、金融機関による対応に差が出ることを防止するため、具体的にいかなる場合に預金者が損失を負担するのかを、ルール上明示すべきとの考えが示されました。具体的には以下の事例が考えられます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
.損失負担ルールの前提としての環境整備 損失負担ルールを検討するにあたっては、 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| との考え方も示されています。新たな損失負担ルールのための環境整備として、金融機関は | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 等の対応が求められています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
.今後の対応 金融関係団体等及び各金融機関においては、中間取りまとめを踏まえ、約款の改定を含め、被害者への補償のあり方について、真剣な検討を行っていただきたいと考えています。 金融庁としては預金被害者への補償のあり方について更なる対策を検討し、実施に移していきたいと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
同中間取りまとめについて、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の中間取りまとめの公表について」(平成17年3月31日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
昨年1月に施行された「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」(いわゆる「ヤミ金融対策法」)の附則第12条においては、 |
||||
|
||||
| と規定されています。 金融庁では、この見直し条項を踏まえ、貸金業制度等について幅広く勉強するため、金融庁総務企画局長の私的懇談会として、3月30日に「貸金業制度等に関する懇談会」(座長:吉野直行 慶應義塾大学経済学部教授)の第1回会合を開催しました。 当懇談会のメンバーは、金融審議会金融分科会第二部会の委員・臨時委員が中心となっており、オブザーバーとして、ノンバンクの各業態から6名の参加をいただいています。そのほか、関係省庁等から、貸金業制度等と関係のある警察庁、法務省、経済産業省及び日本銀行の参加をいただいています。 当懇談会の今後の開催については、基本的に月1回のペースで開催することを考えており、次回からは、当面、消費者団体や業界等の関係者からのヒアリングを行うことにしています。 |
※ |
「貸金業制度等に関する懇談会」のメンバー、資料、議事要旨をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」から「貸金業制度等に関する懇談会」にアクセスしてください。 |
先般(4月1日)、保険商品の販売勧誘のあり方について検討するため、「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長:野村修也 中央大学法科大学院教授)の第1回検討会を開催しました。 |
||||||||||||||||
|
※ |
検討チームのメンバー、議事要旨等については、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」から「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」にアクセスしてください。 |
我が国金融を巡る局面は、不良債権問題への緊急対応から、将来の望ましい金融システムを目指す未来志向の局面に転換しつつあります。個人を取り巻く金融環境についても、様々な金融商品が入手可能となるなど、一層複雑化しております。このような中、人生をより豊かなものとするため、お金との付き合い方や金融との関わりを学ぶことは、益々重要となってきています。 我々行政に当る者にとっても、ライフステージの各段階で金融について学ぶ機会を提供すべく、金融経済教育の充実を図っていくことは、大切な課題であると考えており、「金融改革プログラム」にも、「利用者のライフサイクルに応じ、身近な実例に即した金融経済教育の拡充」を盛り込んだところです。 ライフステージの各段階において金融について考える機会をどのような形で広げていけば良いのか、その際どのような形で金融経済教育の内容をより充実していけば良いのか、また、金融庁として何ができるのかといった点について、幅広く外部有識者の皆様及び関係各団体の皆様から御意見などを伺えればと考え、金融担当大臣の私的懇談会として「金融経済教育懇談会」を設置し、平成17年3月3日(木)に第一回会合を開催しました。今後も月一回ペースで実施する予定です。 金融庁と致しましては、本懇談会の場における皆様方の御議論を踏まえ、金融経済教育に取り組む関係各団体との連携等を通じて、「金融経済教育」の一層の推進・充実が図られるよう、積極的に取り組んで参りたいと考えております。 |
※ |
金融経済教育懇談会の資料等については、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」から「金融経済教育懇談会」にアクセスしてください。 |
公認会計士監査の充実・強化を趣旨とする「公認会計士法の一部を改正する法律」が昨年4月から施行されました。 旧法での懲戒処分等では、故意・過失による虚偽証明、法令違反、著しく不当な運営の場合、戒告、一年以内の業務停止、設立認可取消・登録抹消が可能でしたが、改正法では、懲戒処分等の適切な実施を図る観点から、業務停止期間の上限を二年としたほか、監督の手段を多様化し、品質管理レビューのモニタリングによる公認会計士・監査審査会の具体的勧告内容を監査法人等の運営に反映させるため、金融庁長官は、法令違反、著しい不当運営の場合、監査法人等の業務改善の指示をすることができることとされました。 また、行政手続法第12条では、 |
||||
|
||||
| と不利益処分の具体化・明確化が求められています。 こうしたことから、公認会計士・監査法人の処分の基準をできるだけ具体化・明確化することにより、処分の透明性・公平性を高め、改正法に基づく公認会計士・監査法人の懲戒処分等の適切な実施を図るため、基本的な考え方を「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」として整理し、本年3月31日に公表いたしました。 「基本的な考え方」として、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等を虚偽証明・不当証明に対する懲戒処分等と法令違反に対する懲戒処分等の2つに分け、「基本となる処分の量定」を定め(個々の事案に係る個別事情・周辺事情等により加重又は軽減)、その上で、公認会計士法第32条の定めるところに従い、公認会計士・監査審査会(同法第41条の2に規定する勧告に基づく場合を除きます。)の意見を聴いて行うこととされています。また、監査の充実・強化のために改正法で新たに導入された業務改善の指示を有効に活用することとされています。 |
※ |
平成17年3月31日に公表した「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の全文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」(平成17年3月31日)にアクセスしてください。 |