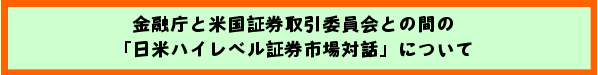 |
1 |
.平成18年6月23日、金融庁と米国証券取引委員会(SEC)との間の定期的な政策対話である「日米ハイレベル証券市場対話」が、米国ワシントンDCにおいて、開催され、五味金融庁長官及びコックスSEC委員長をはじめとするハイレベル職員が参加しました。 |
||
|
|||
2 |
.今回の「日米ハイレベル証券市場対話」においては、会計・監査基準、内部統制、コーポレートガバナンス、証券会社等に対する監督のあり方(投資ファンドに対する規制などを含む)、自主規制機関及び格付機関に対する対応(クロスボーダーでの取引所の再編・統合に伴う取引所監督などを含む)、証券市場における技術革新の促進、クロスボーダーでの法務執行など、幅広い課題について、意見交換を行い、両当局の関係者の相互理解を深めたところです。 |
||
3 |
.証券取引のクロスボーダー化が進む中、金融庁とSECが共通して取り組むべき監督上の課題は多く、今回の対話において、意見交換と相互理解を深めたことは、非常に有益かつ必要なことです。また、金融庁とSECのハイレベル職員が互いに顔を合わせる機会は限られていることから、今回の「対話」は、両当局の友好・協力関係の発展に役立ったものであり、金融庁とSECは、今後もこの「ハイレベル対話」を定期的に開催していくことを確認しました。 |
||
※ |
詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融庁と米国証券取引委員会(SEC)との間の「日米ハイレベル証券市場対話」の開催について」(平成18年6月26日)にアクセスしてください。 |
1 |
.昨年12月、公正取引委員会が独占禁止法(優越的地位の濫用)違反として金融機関に排除勧告・審決を行う事案(以下「勧告事案」)が生じ、当該勧告事案を踏まえ、当局は、本年1月5日付で、「取引等の適切性確保への取組みについて」(以下「前回要請」)を発出しました。 この前回要請は、各預金等取扱金融機関に、以下の対応を求めたものです。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
2 |
.今般、公正取引委員会より新たに 前回要請にも関わらず、取引等の適切性確保への取組みを真摯に行っていない金融機関が存在するとすれば、極めて遺憾であります。そうした金融機関は、経営管理(ガバナンス)態勢、法令等遵守(コンプライアンス)態勢上にも深刻な問題があると考えざるを得ません。 |
||||||||||||
3 |
.金融商品・サービスが多様化する中、金融機関が優越的地位濫用防止のための適切な態勢を構築することは、金融機関への信頼性確保の上からも極めて重要であります。 当局は、今回報告書も踏まえ、取引等の適切性に万全を期すべく、経営の責任において一層迅速に取り組まれるよう、あらためて要請を行いました。具体的には、以下の点につき、再度の徹底を要請したところです。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
4 |
.なお、前回要請でも申し添えたとおり、当局としては、各金融機関が既にこのような対応を十分に行っていることを当然の前提として対応していくこととなります。具体的には、当局の定例検査に際して重点的に検証するとともに、把握された内容や当局の利用者相談室等へ寄せられた情報等を踏まえ、監督上の対応を行っていくこととなります。 |
||||||||||||
※ |
詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「取引等の適切性確保への取組みの最徹底に付いて」(平成18年6月22日)にアクセスしてください。 |
金融庁において開催している「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長:野村 修也中央大学法科大学院教授)は、先般(平成18年6月19日)、「最終報告〜ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方〜」を取りまとめ、公表しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
.検討の経緯 保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること等の指摘がなされていることを踏まえ、利用者保護及び利用者利便の向上の観点から、専門的・実務的に上記の指摘に対応するため、有識者・サービス利用者等をメンバーとする「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を開催し、検討を行ってきました。 本年3月からニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方を中心に検討を進めてきたところですが、今般、以下のとおり最終報告として取りまとめを行いました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.最終報告の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「最終報告〜ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方〜」(平成18年6月19日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融庁は、平成18年3月、監督局内に「情報セキュリティに関する検討会」を立ち上げました。本検討会は、ATMシステム及びインターネットバンキングに関連した犯罪や様々なリスクについて、金融業界や警察庁との間で詳細な情報の共有を図るとともに、各種対策とその有効性を検証することを目的としています。具体的には、ATMシステム、インターネットバンキングのそれぞれにおいて、体制の構築時、利用時、被害発生時などの各段階におけるリスクについて、国内外の犯罪事例や現時点において想定し得る犯罪手口に関する詳細情報を網羅的に収集し、その上で各種対策の有効性について検証してきました。 検討会は、これまでに計3回(第1回:3月9日、第2回:4月10日、第3回:6月1日)開催され、議論を行ってきましたが、今般、その検討結果を取りまとめ公表しました。 検討会での検討内容には、犯罪手口に関する情報等が含まれていますので、その全てを公表することはできませんが、例えば、 |
||||||
|
||||||
| など、金融機関における検討のあり方、具体的なリスク、対策のあり方などについて、同検討会で共通の認識を得るに至った事項を可能な限り公表を行ったものです。 なお、本検討会の検討結果については、参加各団体がそれぞれの基準・標準の改訂に活用するとともに、金融庁としては、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に盛り込むこととしました。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」または「審議会・研究会等」から「第3回情報セキュリティに関する検討会議(6月1日開催)」(平成18年6月12日)にアクセスしてください。 |
有価証券報告書の重点審査については、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)において、開示上の重要な事項等に関して、提出会社より調査票の提出を頂き、これを基に記載内容等に係る審査を実施してきております。 |
||||||||||||
| 平成18年3月期有価証券報告書に係る重点審査については、下記審査項目に係る有価証券報告書の開示状況等について実施することといたしますので、提出会社におかれましては、調査票に適宜記載のうえ、財務局等に提出することとなります。 | ||||||||||||
|
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」または「市場の信頼性確保」から「平成18年3月期有価証券報告書に係る重点審査について」(平成18年6月16日) にアクセスしてください。 |
「ストック・オプション等に関する会計基準」等の会計基準の導入及び「会社法」等の施行に伴い、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則(以下「財務諸表等規則等」という)、企業内容等の開示に関する内閣府令等が改正(平成18年5月1日施行)されています。これらの改正等に伴う留意点は以下のとおりです。 |
|
I |
.財務諸表等規則等の改正等について 「ストック・オプション等に関する会計基準」等の会計基準の導入及び「会社法」の施行に伴う財務諸表等規則等の改正(平成18年4月25日公布)については、平成18年5月1日以後終了する事業年度(連結会計年度)から適用されます。 また、「企業結合に係る会計基準」及び「事業分離等に関する会計基準」の導入に伴う財務諸表等規則等の改正(平成18年4月26日公布)については、平成18年4月1日以後開始する事業年度(連結会計年度)から適用されます。 上記改正のうち「企業結合に係る会計基準」及び「事業分離等に関する会計基準」の導入に伴う改正後の財務諸表等規則等は、平成18年5月1日以後提出する有価証券報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表から、早期に適用することができることとされています。 |
II |
.固定資産の減損会計の適用について 固定資産の減損会計について、平成17年4月1日以降開始する事業年度から全ての会社に適用となっております。 |
III |
.企業内容等の開示に関する内閣府令の改正について 改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令については、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用するとしていますが、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書についても、改正内容の一部等が適用されています。 |
IV |
.添付書類(代表者による適正性の確認)について 代表者による適正性の確認については、平成14年12月の金融審議会第一部会報告において、「市場において、有価証券報告書等の適正性の一層の確保に向けた経営者の姿勢を自らの判断において明確に示すことにより、投資家などによる信認の向上が図られ、ひいては、市場への信頼を高めることとなるものと考えられる。この観点から、有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する代表者の確認を求めることが適切である。」とされたことを受け、制度の整備が図られたものです。 この確認書の提出については任意のものとなっておりますが、経営者自らが市場における信頼性の向上を積極的に図っていくためにも、この制度の一層の活用をお願いいたします。 |
※ |
詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」または「市場の信頼性確保」から「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成18年3月期版)」(平成18年6月8日)にアクセスしてください。 |