 |
 |
 |
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年(平成16年)10月中旬以降、証券取引法上のディスクロージャーをめぐり、不適正な事例が相次いで判明しました。これはディスクロージャー制度に対する国民の信頼を揺るがしかねない事態であるとの認識に立ち、金融庁では、昨年11月16日、ディスクロージャー制度に対する信頼性の確保に向けた対応策を取りまとめ、公表しました。更に、この対応策の公表後、約1か月が経過した12月24日には、それまでの作業の進捗状況や全開示企業による自主的点検の回答状況等を踏まえ、更なるディスクロージャー制度に対する信頼性の確保に向けた対応策を取りまとめ、公表したところです。 これらの対応策の概要は次のとおりです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応」(平成16年11月16日) この対応策は、(a)有価証券報告書等の審査体制の充実・強化、(b)公認会計士等に対する監督等の充実・強化、(c)開示制度の整備、(d)市場開設者に対する要請の四つの柱からなっており、その主な内容は次のとおりです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
これらの対応策のうち、ディスクロージャー・ホットラインの開設や、全開示企業に対する自主点検の指示、市場開設者に対する対応要請などは、直ちに実施に移されました。また、開示制度の整備についても、金融審議会第一部会のディスクロージャー・ワーキング・グループでは、検討要請のあった事項につき、他の審議項目と切り離して審議・検討を進められ、その検討結果は、昨年12月24日に開催された金融審議会第一部会において報告・審議が行われ、同第一部会報告「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けて」として公表されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
.「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)」(平成16年12月24日) この対応策は、(a)全開示企業による自主的点検を受けた対応、(b)有価証券報告書等の審査体制、(c)開示制度の整備、(d)公認会計士等に対する監督、(e)市場開設者に対する要請からなっており、その主な内容は次のとおりです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について」(平成16年11月16日)及び「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)について」(平成16年12月24日)にアクセスしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
EDINETについては、アクセスFSA第19号(2004年6月発行)の「金融便利帳:EDINET」で解説しておりますので、アクセスしてみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
変額年金保険等に係る責任準備金積立ルール等については、平成16年10月22日に改正した関係府令及び告示(※1)において積み残されていた事項を12月2日から12月15日までの間、パブリックコメントに付し、その結果とそれらを踏まえた告示及び事務ガイドラインの改正内容(※2)を12月27日に公表しました。 |
|||||||
|
|||||||
1 |
.デリバティブを使用したヘッジに関する取扱い 次の(a)から(c)の要件を満たす場合に限り、ソルベンシー・マージン基準における最低保証リスクを減殺することができます。(平成8年大蔵省告示第50号の改正) |
||||||
|
|||||||
2 |
.再保険に関する取扱い 出再割合が50%を超える場合は、50%を超える部分についての再保険リスクのリスク係数を2%とします。(平成8年大蔵省告示第50号の改正) |
||||||
3 |
.代替的方式の使用条件 期待収益率及びボラティリティが次の(a)から(c)の要件を満たす場合に、代替的方式を使用することができます。(事務ガイドラインの改正) |
||||||
|
|||||||
4 |
.その他 |
||||||
|
|||||||
5 |
.適用時期 保険料積立金に関するものは平成17年4月1日以降に締結する保険契約(平成16年4月1日以降に締結する保険契約を含めることも可能。)に適用します。危険準備金及びソルベンシー・マージン基準に関するものは過去の全ての保険契約を対象とし、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。 |
||||||
昨年12月24日、金融庁は、高校3年生を対象とした金融取引等の基礎的知識に関するパンフレットを作成し、金融庁のホームページに掲載しました。 |
|||||||
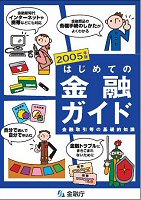 高校3年生が、新社会人として社会に出た時に「賢い消費者」として生活していくためには、学校教育段階から、「金融」の仕組み・働きを理解し、また金融取引に関する基礎的な知識を習得していることが大変重要になってきています。 高校3年生が、新社会人として社会に出た時に「賢い消費者」として生活していくためには、学校教育段階から、「金融」の仕組み・働きを理解し、また金融取引に関する基礎的な知識を習得していることが大変重要になってきています。しかしながら、現状においては、生徒が十分な知識を得ることなく実社会に出ていることから、金融取引に関連するトラブルに見舞われやすい状況となっています。とりわけ、最近、「ヤミ金融問題」や「振り込め詐欺問題」といったことが社会問題化しています。 これらの未然防止の観点からも、教育現場において、高校卒業を控えた高校3年生を対象とした金融経済教育を積極的に実践してもらうためのパンフレットを作成しました。 |
|||||||
金融庁としては、引き続き、教育段階における金融経済教育の推進に積極的に取り組んでいきたいと考えています。 |
|||||||
○ |
本パンフレットについて |
||||||
|
|||||||
金融庁では従来から、小学生向けパンフレット、中学・高校生向け副教材を作成しています。今回の高校3年生向けパンフレットの作成により、金融経済教育に関する副教材・パンフレットが、一通り整備されることとなリました。金融庁としては、今後、これら副教材などの配布を通じて金融経済教育のより一層の推進を図っていきたいと考えています。 |
|||||||
※ |
高校3年生を対象とした金融取引等の基礎的知識に関するパンフレットについて、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「高校3年生を対象とした金融取引等の基礎的知識に関するパンフレットの作成について」(平成16年12月24日)にアクセスしてください。 |
||||||