|
このコーナーでは、先に閉会した第159回国会で成立した金融庁関連の法律について、その経緯や内容を詳細に説明します。本号は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」についてです。 |
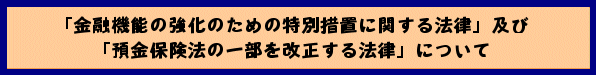 |
|
このコーナーでは、先に閉会した第159回国会で成立した金融庁関連の法律について、その経緯や内容を詳細に説明します。本号は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」についてです。 |
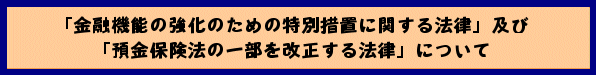 |
前述のとおり、第159回国会において「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(以下、「金融機能強化法」という)が成立し、地域等における金融の円滑化に向けた金融機関の取組みに対し国が資本参加することを通じて金融機能の強化を図る新たな公的資金制度が創設されました。本稿においては、同時に成立した預金保険法の一部を改正する法律(以下、「預金保険法一部改正」という)の概要とあわせてこの新たな公的資金制度の概要を紹介します。 I 立法の背景・経緯等 新たな公的資金制度は、平成14年10月30日に公表された「金融再生プログラム」において「迅速に公的資金を投入することを可能にする新たな制度の創設の必要性などについて検討し、必要な場合は法的措置を講ずる」とされたことを受け、金融審議会(会長:貝塚啓明中央大学教授)の金融分科会第二部会(部会長:堀内昭義中央大学教授)において検討が開始されたものです。 同部会は、公的資金制度に関するワーキング・グループを設置して精力的に検討を進め、平成15年7月28日には「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」と題する報告をとりまとめ、その中で新たな公的資金制度の「考え得る枠組み」も示されました。これを踏まえ、金融庁において更に実務的な検討が加えられ、本年2月6日に新たな公的資金制度の創設を内容とする「金融機能の強化のための特別措置に関する法律案」が国会に提出されるに至ったところです。 この新たな公的資金制度の目的や意義を広く説明すると、次のとおりです。 現下の経済情勢をみると、企業収益が改善し、設備投資が増加するなど、民需が主導する形で我が国経済は着実に回復しており、こうした明るい兆しを地域経済や中小企業にも浸透させ、持続的な経済成長につなげていくことが重要な課題となっています。このためには、地域経済の活性化に向けた改革の取組みを着実に推進するとともに、資金供給の担い手として民間の経済活動を支える金融機関が一層リスク対応能力を高め、地域等における金融が十分な安心感をもって円滑に行われるよう、その環境整備に万全を尽くしていくことが重要となっています。新たな公的資金制度は、金融機関の資本の自力調達が必ずしも容易でない中で、地域における金融機能の強化に向けた金融機関の取組みに対し公的な支援を行う時限的な制度を創設するものであり、地域経済の活性化や金融システムの安定・強化に資することが期待されています。 なお、新たな公的資金制度の枠組みとの整合性を図る等のため、金融危機に対応するための公的資金制度である預金保険法第102条第1号措置について銀行持株会社等を通じた資本増強を可能とする等所要の制度整備を行う「預金保険法の一部を改正する法律案」が本年2月6日にあわせて国会に提出されました。 両法案は、4月23日には衆議院で可決、6月14日には参議院で可決・成立し、同月18日に公布されています(平成16年法律第128号、第129号)。 II 立法の概要 以下金融機能強化法及び預金保険法一部改正の概要を順を追ってご紹介します。 なお、金融機能強化法及び預金保険法一部改正法は平成16年8月1日に施行されます。 |
|||||||||||
1 |
.金融機能強化法の概要(図1参照) |
||||||||||
|
|||||||||||
2 |
.預金保険法一部改正の概要 |
||||||||||
|
|||||||||||
| ※ |
|
||||||||||||||||||
※ |
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」関係政令(案)等に対するパブリックコメントの結果について、詳しくは金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から「「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」関係政令(案)等に対するパブリックコメントの結果について(平成16年7月23日)」にアクセスしてください。 |
※ |
このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「繰延税金資産」です。 |
繰延税金資産とは・・・ 税効果会計という会計基準を適用することにより生じる貸借対照表上の資産項目です。税効果会計は、簡潔に言えば、収益や費用の計上時期が企業会計と税務上の取り扱いで相違する場合に、これを調整するための会計処理のルールです。税効果会計は、米国会計基準、国際会計基準など国際的に広く採用されている会計基準のひとつです。 |
|
貸付金を例にとれば、企業会計上のルールに従って貸倒引当金を当期の費用として計上しても、税法上は認定されず当期では損金として認められない場合があります。このように、企業会計上は費用として計上されるが税法上損金として認められない費用で、将来、税法上損金として容認されるものを、いわば法人税の前払いとして「繰延税金資産」として資産に計上することになります。将来、税務上も貸し倒れが認められた場合には課税所得から減算されることとなり、「繰延税金資産」も取り崩されることになります。また、反対に、税金の後払いに相当するような差異がある場合は、「繰延税金負債」として負債に計上することになります。 |
|
なお、「繰延税金資産」は、将来、税務上損金として認められたときに、その事業年度の課税所得から減算されることになります。したがって、「繰延税金資産」は、課税所得が将来にわたって見込まれることを前提に計上することができるとされており、日本公認会計士協会から、その判断指針(「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」監査委員会報告第66号)が公表されています。 |
〇 |
金融庁「子ども見学デー」への参加者の募集について 子どもたちに対し業務説明や職場見学などを行うことにより、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会として、中央省庁等が業務説明や職場見学などを行う「子ども見学デー」(文部科学省主催)については、本年も各省庁等が連携して、8月25日(水)〜26日(木)に実施されます。 金融庁としても、この機会にあわせて暮らしの中の金融の働きや金融庁の仕事についての理解を深めてもらうことを目的として、以下のプログラム(事前予約制)等により実施を予定しています。 プログラムの詳細や応募方法等について、詳しくは金融庁ホームページの「お知らせ」のコーナーから「金融庁の『子ども見学デー』」にアクセスしてください。 皆様のご応募をお待ちしております。 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
〇 |
行政立法手続に関する意見募集について 政府では、行政立法を行う際の手続の法制化を含めた行政手続法の見直しを進めており、現在、総務大臣の下に行政手続法検討会を開催し、検討を行っています。 この議論の参考とするため、行政立法手続等に関する論点についての意見を募集します。 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
〇 |
大臣・副大臣への質問募集中 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えする【竹中大臣に質問!】、【伊藤副大臣に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣又は副大臣の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣への質問募集中」にもアクセスしてみてください。 |
||||||||||||||||||
〇 |
新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。 |
||||||||||||||||||
| ※ |