「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」の開催について
金融研究研修センターでは、2006年12月13日に統計数理研究所リスク解析戦略研究センターとの共催により、「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」を開催しました。本シンポジウムは、我が国におけるデフォルト時損失率(LGD)計量化の高度化とバーゼル II のうち特に先進的内部格付け手法の円滑な導入に役立たせることを目的としたものです。
当日のプログラム及び概要、各発表概要は以下をご覧ください。
<問合せ先>
金融庁 金融研究センター
(総務企画局企画課研究開発室)
TEL 03-3506-6000(内線3551、3293)
電子メール:kenkyuu@fsa.go.jp
「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」
プログラム
[ 開会挨拶 吉野直行金融研究研修センター長 ]
- 「回収率モデルの系統とそれぞれの長短所」
 (発表概要)(PDF:119KB)
(発表概要)(PDF:119KB)
山下 智志(金融研究研修センター特別研究員、統計数理研究所助教授) - 「バーゼル II におけるLGDの扱い」
 (発表概要)(PDF:154KB)
(発表概要)(PDF:154KB)
上野 大(金融庁監督局バーゼル II 推進室課長補佐)
(休憩) - 「構造型モデルにおけるEAD、LGD、PDとEL、ULの関係」
 (発表概要)(PDF:113KB)
(発表概要)(PDF:113KB)
吉羽 要直(日本銀行金融研究所企画役) - 「誘導型モデルによるハザード・回収率期間構造の同時推定--格付け・財務データを用いて」
 (発表概要)(PDF:116KB)
(発表概要)(PDF:116KB)
安道 知寛(慶應義塾大学大学院経営管理研究科 慶應ビジネススクール専任講師) - 「リテール向けローンのLGD推定」
 (発表概要)(PDF:263KB)
(発表概要)(PDF:263KB)
青沼 君明(三菱東京UFJ銀行 融資企画部 バーゼル II 準備室チーフクオンツ/上席調査役 博士(数理科学))
[ 閉会 ]
当日の概要
信用リスク管理の高度化や新BIS規制の適用に伴い、デフォルト確率の推計だけでなく、回収率(もしくはLGD)の推計が重要な課題となっている。回収率の数理モデルについては学会レベルでは2000年以降様々なアプローチが提案され、実務的にも2004年前後よりいくつかのモデルが提案されている。しかし、理論・方法論の整理がなされていないことやデータベースの不足などから、回収率モデルの開発に多くの障害が発生している。
本シンポジウムでは回収率モデルの代表的な方法について、それぞれの具体的な研究例を紹介し、具体的にリスク管理を行う場合についての長短所について解説した。また、モデル構築と新BIS規制の関係について説明した。
まず、統計数理研究所山下氏より、LGDモデルは構造モデル、誘導モデル、統計モデルに分類可能で、それぞれの特徴についての説明があった。続いて金融庁上野氏より、新BIS規制におけるLGDモデルの位置づけと、LGDモデル作成にあたっての方法論に関する解説があった。次に日本銀行吉羽氏より、構造モデルの研究例として、追加融資がLGDに与える影響についての分析結果の報告があった。その後、慶應義塾大学の安道氏より、誘導モデルの研究例として、デフォルトの期間構造と回収率の同時推計モデルの提案がなされた。最後に三菱東京UFJ銀行の青沼氏より、統計モデルを用いたリテールローンのLGDモデルの紹介があった。
これらの講演を通して、我が国における回収率モデルの高度化と新BIS規制、とくに先進的内部格付けモデルのスムーズな導入に役立つことが期待される。なお、シンポジウムには金融機関のリスク管理担当者を中心に、約300名の参加があった。

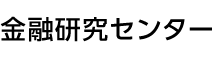
 検索
検索