ディスカッションペーパー
ディスカッションペーパーとは
金融研究センターにおける「ディスカッションペーパー(DP)」とは、当センター所属の研究官等が、研究成果を取りまとめたものです。随時掲載しますので、ご高覧いただき、幅広くコメントを歓迎します。電子メールでのコメントは、frtc_comments★fsa.go.jp宛(注:★を@記号に置き換えて下さい)にお寄せ下さい。
なお、DPの内容はすべて執筆者の個人的見解であり、金融庁あるいは金融研究センターの公式見解を示すものではありません。
令和7年度ディスカッションペーパー
(「ファイル」をクリックして本文を、「題名」をクリックして要旨を閲覧することができます。)
| ファイル | 題名 | 執筆者 | 年月 |
|---|---|---|---|
| デジタル金融資産の私法上の取扱い | 加藤 貴仁 加毛 明 |
2025年12月 | |
| ASEAN主要国の金融システムの構造 タイ、マレーシア、インドネシアをベンチマークに | 三重野 文晴 平田 礼王 |
2025年10月 | |
| 本邦国債レポ市場における 中央清算機関(CCP)の役割とヘアカット |
秋元 虹輝 冨田 絢子 服部 孝洋 深見 健太 |
2025年10月 | |
| 住宅市場と金融システム・経済の関係を分析するモデルの構築及び当該モデルに基づくマクロ・プルーデンス政策の分析 | 小畑 崇弘 | 2025年10月 | |
| 取引市場不安定化の予兆検知を目的とした詳細時系列データへのDNM理論の適用 | 伊藤 真利子 羽佐田 紘之 大西 立顕 本間 裕大 |
2025年9月 | |
(PDF:1,168KB) |
主要国における保険仲立人(ブローカー)に関する 制度の現状 |
小塚 荘一郎 榊 素寛 内藤 和美 |
2025年8月 |
(PDF:1,287KB) |
保険契約者のニーズを踏まえた保険商品開発に係る 規制の在り方 |
中出 哲 星野 明雄 |
2025年8月 |
(PDF:1,046KB) |
監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察 | 野間 幹晴 | 2025年7月 |
(PDF:1,336KB) |
国際動向を踏まえた金融機関における実効性のある TLPT に関する考察 | 北原 幸彦 | 2025年7月 |
(PDF:2,143KB) |
保険代理店にかかる海外制度調査 -大規模乗合代理店を中心として- |
中出 哲 山下 徹哉 𡈽岐 孝宏 鄭 燦玉 |
2025年6月 |
ディスカッションペーパー要旨
DP2025-10
「デジタル金融資産の私法上の取扱い」
加藤 貴仁 金融庁金融研究センター特別研究員
加毛 明 金融庁金融研究センター特別研究員
社会経済全体のデジタル化の進展を背景として、金融分野では、ブロックチェーンに代表される分散台帳技術を活用した新たな資産(デジタル金融資産)が登場している。暗号資産、ス テーブルコイン、セキュリティ・トークンなどのデジタル金融資産については、監督法(資金決済法、銀行法、金融商品取引法など)による規制が進展する一方で、私法上のルールの整備は必ずしも進んでいない。そこで本研究では、わが国におけるデジタル金融資産に関する法的不確実性を低減する観点から、海外の立法や国際的モデル法の動向も踏まえ、デジタル金融資産に関する私法上の課題やその解決方法について検討を行った。
第1部は決済目的で利用されるデジタル金融資産について、第2部は投資目的で取引されるデジタル金融資産についての研究成果となる。
キーワード:デジタル金融資産、金融規制、ブロックチェーン、暗号資産、ステーブルコイン、セキュリティ・トークン
DP2025-9
「ASEAN主要国の金融システムの構造 タイ、マレーシア、インドネシアをベンチマークに」
三重野 文晴 金融庁金融研究センター専門研究員
平田 礼王 金融庁金融研究センター専門研究員
ASEAN諸国の金融システムの実態把握を目指して、主にタイ、マレーシア、インドネシアを対象に、1997年アジア金融危機からの30年の間で銀行信用、株式市場、債券市場の3つの資金チャンネルで生じた変化を観察した。最初に国際収支を観察し、危機以降は貿易収支黒字の定着によって海外への対外投資が海外からの対内投資に比肩するほどの水準になっている一方で、第一次所得収支の赤字が拡大し、国内貯蓄が収益率の高い国内投資機会を逸して海外投資に向かっている可能性を指摘した。それぞれの資金チャンネルを観察すると、銀行信用は危機後の回復が緩やかで、回復の過程では製造業部門への貸出から後退し、消費部門に大きく傾斜している。企業の資金調達側では負債や銀行借入への依存は元来低かったものが、2010年代以降さらに低下している。株式市場の成長は比較的順調で時価総額、上場企業数は拡大しつつあるが、市場の包摂性はなお不透明である。債券市場は社債に限ってみればGDP比でみた発行残高に目立った動きは少なく、また金融部門や建設・不動産部門、消費金融などに資金需要が偏在している。これらを踏まえて、企業財務データによる企業の資金調達行動の実証分析を行ったところ、負債・銀行信用と自己資金の間の代替性、設備投資資金における負債・銀行信用の需要の存在、負債比率や銀行借入比率の低下傾向が確認された。また、社債ファイナンスと自己資金の間には代替性が見られず、それぞれの資金需要の質が異なることが示唆され、また社債の発行行動は長期性の資金の需要をもとめたものであることも検出された。3つの資金チャンネルそれぞれに資金供給機能に強い偏りがあり、国内貯蓄を国内投資につなぐ経路が十分に機能していない可能性がある。これが必ずしも収益性の高くない海外投資を必要以上に活発にしている遠因と考えられる。ASEANの金融システムの一層の発展には、その産業構造の発展変化に対応した資金需要のありかを探る観点が重要であろう。
キーワード:ASEAN、金融システム、資金調達
DP2025-8
「本邦国債レポ市場における中央清算機関(CCP)の役割とヘアカット」
秋元 虹輝 元金融庁職員
冨田 絢子 金融庁総合政策局リスク分析総括課暗号資産・ブロックチェーン・イノベーション
参事官室課長補佐
服部 孝洋 金融庁金融研究センター専門研究員
深見 健太 金融庁監督局銀行第二課総括補佐
DP2025-7
「住宅市場と金融システム・経済の関係を分析するモデルの構築及び当該モデルに基づくマクロ・プルーデンス政策の分析」
小畑 崇弘 金融庁金融研究センター専門研究員
2024 年 3 月の日本銀行によるゼロ金利解除などを受けて、長らく低位安定推移していた国内金利に上昇傾向がみられるようになった。金利上昇が大きく影響する市場として住宅市場がある。住宅市場において、金利上昇がもたらす住宅ローン利用者への悪影響を緩和するためのマクロ・プルーデンス規制があるが、日本国内では金利の低位安定が続いたことから実証的にその効果を分析することが難しい。そこで本稿では、日本の住宅市場を対象に、エージェントベースモデル(ABM:Agent-based Model)を用いて分析モデルを構築し、金利上昇シナリオを基にしたシミュレーションを通して住宅関連の貸出に関する規制の影響・効果を分析する。具体的には、日本国内で住宅取引が特に集中している東京都の住宅市場を模したモデルを想定し、まずベースとなる住宅市場 ABM を構築したのちに可能な限り東京都の関連データに基づいてキャリブレーションを行って分析モデルを準備した。そのうえで、複数の金利上昇シナリオを基にしたシミュレーション等を実行して、実際の住宅ローン支払額増加に一定期間猶予を設ける施策等(いわゆる 5 年ルール、125%ルール)の効果を分析した。分析結果の一部からは施策の有効性が確認できたものの、分析モデルや手法には課題も残った。
キーワード:住宅市場、マクロ・プルーデンス政策の検討、エージェントベースモデル
DP2025-6
「取引市場不安定化の予兆検知を目的とした詳細時系列データへのDNM理論の適用」
伊藤 真利子 金融庁金融研究センター専門研究員
羽佐田 紘之 金融庁金融研究センター専門研究員
大西 立顕 金融庁金融研究センター専門研究員
本間 裕大 金融庁金融研究センター専門研究員
DP2025-5
「主要国における保険仲立人(ブローカー)に関する 制度の現状」
小塚 荘一郎 金融庁金融研究センター特別研究員
榊 素寛 金融庁金融研究センター特別研究員
内藤 和美 金融庁金融研究センター特別研究員
日本では伝統的に、保険会社により保険募集の委託を受けた保険代理店が保険商品の販売ルートとなってきた。そのような状況の下で、保険契約者の側に立って保険商品の仲介を行う仲介者が必要であるという考え方から、平成 7 年の保険業法改正において、欧米の保険市場に存在する「保険ブローカー」と同様の制度として、保険商品の新しい仲介者として保険仲立人が創設された。
現在、保険仲立人の創設より 30 年ほどが経過したにもかかわらず、市場におけるシェアは保険料の割合で 0.9%にとどまるなど 、保険仲立人の活用は進んでおらず、その活用促進が課題とされる状況にある。そこで、本調査研究では、保険仲立人が活発に活動する海外市場における規制や理論研究等から、日本の保険仲立人制度に対する示唆を得るべく、保険仲立人に対する規制等に関して、それぞれの市場で保険仲介者が果たしている役割に注意しつつ、保険仲立人制度の改革の先駆けとなった米国、保険ブローカーが高度に発達した市場を有する英国及び日本の保険監督制度に大きな影響を及ぼし、かつ、EU による保険監督の枠組の下にあるドイツの法制度を調査した。
キーワード:保険、保険仲立人、保険業法、保険ブローカー、保険商品流通規制
DP2025-4
「保険契約者のニーズを踏まえた保険商品開発に 係る規制の在り方」
中出 哲 金融庁金融研究センター特別研究員
星野 明雄 金融庁金融研究センター特別研究員
我が国では、少子高齢化、大規模災害の頻発、新技術の急速な進展等の社会環境変化に対応した保険商品の開発を促すため、適切な環境整備が求められている。時代に即した保険商品開発に係る規制の在り方の検討の一助とすべく、イギリス、ドイツおよび米国(ニューヨーク州)の保険商品審査制度と、保険会社等における実務の状況を調査した。これら 3 国を対象とした理由は、保険の先進的な市場のうち、伝統的に商品と料率に関する自由度の高いイギリス、過去には審査が厳格であり、EU 統合に伴い自由化が進んだドイツ、州単位に厳格な審査のある米国それぞれの事情に照らすことで、望ましい審査の在り方について幅広い論点を浮き彫りにできると考えるためである。
イギリスおよびドイツでは、保険約款および保険料率の事前認可を要しない。米国では、州ごとに監督制度が異なるが、基本的に商品および料率を事前届出制としている。本稿では、その中でも審査が厳格といわれるニューヨーク州の制度を検討の対象とする。
ニューヨーク州では、州法に基づく免許制度の下で、商品および料率の審査が行われる。ただし、契約者がリスク管理体制の整った企業である場合等に、審査不要とする複数の制度がある。審査不要制度の対象領域の市場は、企業分野の保険を中心に、拡大していると考えられる。
ドイツおよび米国において、業界団体あるいは専門の事業者の提供する拘束力のない標準的な契約条項が、複数の会社で利用される例がある。また、保険料算定の基礎となるロス・コストのデータが提供されている。
キーワード:保険、保険代理店、保険業法、保険募集制度
DP2025-3
「監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察」
野間 幹晴 金融庁金融研究センター特別研究員
生成AIを含むAIは、技術的な急速な発展を遂げており、社会のさまざまな分野に大きな影響を与えている。監査業界においても、生成AI等の導入や活用、その検討が浸透しつつある。監査業務における生成AI等の利活用は、効率化等により監査品質や監査の担い手不足などに対してポジティブな帰結をもたらすことが期待されている。一方、AIへの過度な依存やブラックボックス化、情報漏洩、ハルシネーションなど、監査人の能力や監査品質などの低減に繋がり得る課題があることも想定される。
監査における生成AI等の利活用に係る可能性や課題については、監査法人、業界団体、監査監督当局、国際機関等において議論されているほか、学術分野においても、監査実務における生成AIの活用可能性、AIが監査法人の人材採用に与えうる影響等に関する先行研究が行われている。例えば、Law and Shen (2025)では、AIが監査人の業務職務を代替するのか、それとも補完するのかという論点について分析が行われ、Fedyk et al. (2022)では、AIが監査品質と効率に対して与える影響について実態調査を行っている。
本研究では、これらの先行研究に加え、生成AI等の利活用の実態、各国の監査監督当局、国際機関の動向等を踏まえたうえで、監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題について考察する。
キーワード:生成AI、監査、監査品質
DP2025-2
「国際動向を踏まえた金融機関における実効性のある TLPT に関する考察」
北原 幸彦 金融庁金融研究センター研究官
昨今、金融機関を狙ったサイバー攻撃の脅威が増加しており、また、攻撃手法も日々高度化・巧妙化を続けている。金融機関においては、このような巧妙化し続けるサイバー攻撃に対応すべく、日ごろから自機関におけるサイバー攻撃リスクを把握するとともに、そのようなサイバー攻撃に対して単にシステム面での対策を行うだけでなく、攻撃に対する人の動きや対応プロセスの整備も含めて強化していくことが重要である。
こうした背景の中、現実に起こりうるサイバー攻撃に対して金融機関の対応態勢がどの程度有効に機能するかを検証し、その改善と、更なる高度化に向けた教訓を得るためのアプローチとして、脅威ベースのペネトレーションテスト(Threat-Led Penetration Testing、以下、「TLPT」)の有効性の評価が高まっている。日本国内においては、特に大手金融機関を中心に TLPT の実施が増えてきている一方で、海外では、欧米を中心に先行して TLPT の取組みが進められているとともに、関連した法制度や各種フレームワークの整備などが進んでいる。
本稿では、こうした諸外国の金融機関における TLPT の取組みに関連した動向や、法令・各種フレームワーク等の整備状況をまとめるとともに、そうした諸外国の動向を踏まえ、日本の金融機関が TLPT を実施するにあたって、そのあるべき姿や留意すべきポイントなどについて考察する。
キーワード:サイバー攻撃、サイバーセキュリティ、TLPT、脅威ベースのペネトレーションテスト
DP2025-1
「保険代理店にかかる海外制度調査 -大規模乗合代理店を中心として-」
中出 哲 金融庁金融研究センター特別研究員
山下 徹哉 金融庁金融研究センター特別研究員
𡈽岐 孝宏 金融庁金融研究センター特別研究員
鄭 燦玉 金融庁金融研究センター特別研究員
昨今、保険業界において、大規模な乗合損害保険代理店による保険金不正請求といった不祥事案が相次いでいる。こうした不祥事案への対応策の一つとして、金融庁は令和7年に保険業法改正案を国会へ提出した。今般の不祥事案に限らず、これまで、日本の保険募集制度は不祥事案等の過去の経験を踏まえて進化してきた。こうした流れは海外でも同様であり、それぞれの事情を踏まえて発展してきた諸外国の制度設計には、我が国の保険代理店制度の更なる進化に向けた検討にあたり参考となる点が存在すると考えられる。
本調査では、今般の不祥事案への対応のみならず、中長期的視点に立った検討にも資するべく、大規模乗合代理店を中心に、保険代理店における免許・登録制度や態勢整備規制、行為規制といった保険募集制度等に関し、米国、イギリス、ドイツ及び韓国の保険代理店制度を調査した。各国で共通する部分もあれば、背景に存在する市場の特徴や他の経済制度等による違いがある場合もあるので、外国の制度が日本にも適合するかは慎重に検討する必要はある。しかし、上記4か国の状況を知ることで世界の潮流を知ることができるとともに、我が国の制度の特徴も明らかになり、我が国における保険代理店制度のあり方を検討する上での示唆を得ることができた。そのため、まとめにおいて、本調査の中で特に興味深い点について取り上げた。
キーワード:保険、保険代理店、保険業法、保険募集制度

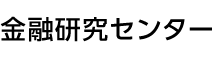
 検索
検索