ディスカッションペーパー
ディスカッションペーパーとは
金融研究センターにおける「ディスカッションペーパー(DP)」とは、当センター所属の研究官等が、研究成果を取りまとめたものです。随時掲載しますので、ご高覧いただき、幅広くコメントを歓迎します。
なお、DPの内容はすべて執筆者の個人的見解であり、金融庁あるいは金融研究センターの公式見解を示すものではありません。
27年度ディスカッションペーパー
(「ファイル」をクリックして本文を、「題名」をクリックして要旨を閲覧することができます。)
| ファイル | 題名 | 執筆者 | 年月 |
|---|---|---|---|
| (PDF:1,769KB) |
「行動経済学の金融経済教育への応用 -行動バイアスからマインドセット・バイアスへ-」 |
川西 諭 橋長 真紀子 |
2016年1月 |
| (PDF:5,793KB) |
「銀行勘定の金利リスク管理モデル -修正期間収益アプローチと経済価値アプローチの比較-」 |
枇々木 規雄 岩熊 淳太 |
2015年7月 |
| (PDF:1,831KB) |
「ASEAN地域統合における金融分野自由化進展に向けて-WTO金融サービス分野の自由化約束をベースとした分析-」 | 國見 真理子 | 2015年6月 |
ディスカッションペーパー要旨
DP2015-3
「行動経済学の金融経済教育への応用
-行動バイアスからマインドセット・バイアスへ-」
| 川西 諭 | 金融庁金融研究センター特別研究員 (上智大学経済学部教授) |
|---|---|
| 橋長 真紀子 | 長岡大学経済経営学部専任講師 |
本論文では、行動経済学の知見をより効果的な金融経済教育を行うために応用する研究を調査した。先行事例調査では、消費者の問題行動を改善するために、人間行動のバイアスを巧みに活用する介入事例を紹介する。また、行動経済学の応用の新しい方向性としてマインドセット(金融に対する印象や考え方)の重要性に注目し、その金融教育への影響を明らかにするためのアンケート調査を行った。その結果、 金融教育は学生のマインドセットに多様な影響を与えていること、
金融教育は学生のマインドセットに多様な影響を与えていること、 金融に対して肯定的なマインドセットを持つ学生ほど金融教育の成果(知識、積極性、注意深さ、関心)が高くなる傾向があること、
金融に対して肯定的なマインドセットを持つ学生ほど金融教育の成果(知識、積極性、注意深さ、関心)が高くなる傾向があること、 金融に対する恐怖感のある学生は金融に関する行動に消極的な態度を示す傾向があることが確かめられた。この結果の含意として、教員は学生のマインドセットにバイアスがあれば、それを修正することでより効果的な金融教育を提供できるようになると考えられる。
金融に対する恐怖感のある学生は金融に関する行動に消極的な態度を示す傾向があることが確かめられた。この結果の含意として、教員は学生のマインドセットにバイアスがあれば、それを修正することでより効果的な金融教育を提供できるようになると考えられる。
キーワード:行動経済学、行動バイアス、マインドセット
DP2015-2
「銀行勘定の金利リスク管理モデル
-修正期間収益アプローチと経済価値アプローチの比較-」
| 枇々木 規雄 | 金融庁金融研究センター特別研究員 (慶應義塾大学理工学部教授) |
|---|---|
| 岩熊 淳太 | 金融庁金融研究センター専門研究員 |
預金を原資として貸出や有価証券で資金運用を行い収益を獲得している銀行にとって、銀行勘定の金利リスク管理は非常に重要な問題である。実務において、銀行勘定の金利リスク管理は大きく経済価値と期間収益の両面から捉えられ、議論がされてきた。しかし、経済価値と期間収益のどちらで捉えるべきかという点については未だ明確なコンセンサスが得られていない状況である。そこで、銀行勘定の金利リスクを管理するために、複雑な銀行勘定の特性や信用リスクなどとの依存関係も考慮した銀行勘定全体のモデルを構築する。そして、モンテカルロ・シミュレーションを用いた様々な感度分析を通して、期間収益アプローチと経済価値アプローチの関係について分析する。著者たちの知る限り、包括的な分析結果をもとに検討が行われた研究は存在しない。
分析の結果、銀行勘定のリスク管理において銀行勘定の特性を十分に反映させるためには、経済価値だけでなく期間収益も合わせて管理する必要があることを示す。
キーワード:銀行勘定、金利リスク、修正期間収益アプローチ、経済価値アプローチ、コア預金
DP2015-1
「ASEAN地域統合における金融分野自由化進展に向けて
-WTO金融サービス分野の自由化約束をベースとした分析-」
國見 真理子 金融庁金融研究センター特別研究員
(田園調布学園大学人間福祉学部専任講師)
近年、ASEANの経済発展及び地域統合の進展に伴い、域内の金融サービス貿易量は急激に増加しており、域内各国での金融サービスのプレゼンスが高まっている。2015年末に発足する予定のAECにおいては、域内金融市場統合等の目標に向けて、各国の金融サービス自由化を進めることは必要不可欠である。
そこで、本稿では、日本政府が行っている対外金融協力・支援の今後のために、ASEAN域内にある重点支援対象国の中で、タイとインドネシアを取り上げて事例分析を行う。
両国の共通点としては、過去20年に2度の金融危機で国内経済が大きな影響を受けるなど金融サービス分野の脆弱性がみられることである。相違点としては、タイは域内では相対的に金融先進国に位置付けられるものの、今後の自由化進展のためには、国内金融サービス業界が抱える幾つかの課題克服が必要である。他方、インドネシアの場合、金融インフラ整備自体が未だ不十分であり、(BCLMVを抜かしたASEAN5の中では)金融発展途上国といえる。
今回は、金融サービスの中核をなす銀行セクターに着目し、WTOやASEANにおける市場開放のための自由化約束の検討や国内事情等の分析を通じ、支援対象国に対する今後の金融インフラ支援に関する試論提示を目指している。
キーワード:金融サービス自由化、AEC、外資規制、GATS、ASEAN
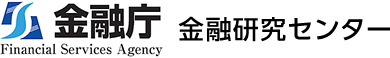
 検索
検索