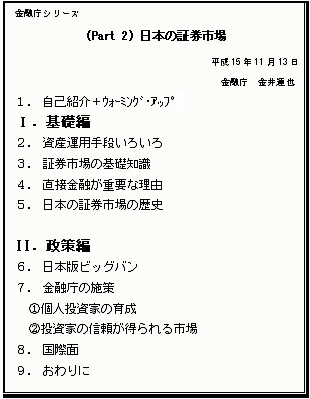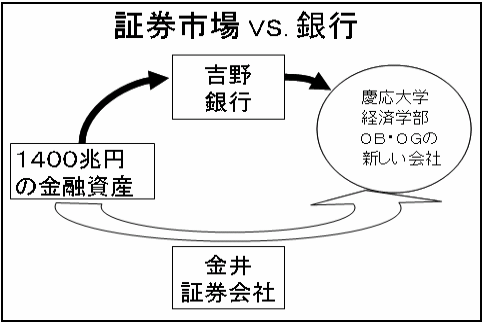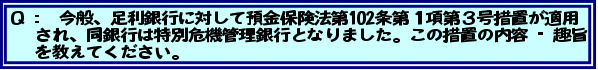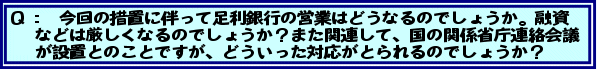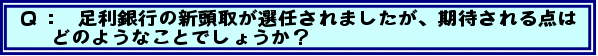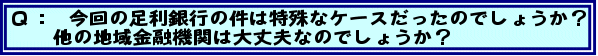|
日常的に銀行を利用されている方でも、「預金口座」とは何か?と改まって考えることは余りないかも知れません。「預金口座」の定義は、預金取引先別に預金勘定を記入した元帳区分のこと、ということになるようです。口座には必ず口座番号が付いており、金融機関の内部では預金の種類や取引先別に分類整理がなされるのが通常です。 |
 |
預金の基本的な種類としては、例えば以下のようなものが挙げられます。 |
| |
当座預金・・・・ |
預金者が振り出した手形・小切手の支払資金として用いられる預金で、利息は付きません。 |
普通預金・・・・ |
預金者が必要に応じ、自由に預金を預け入れたり、払い戻しを請求できる預金で、当座預金のように手形・小切手の支払いには使えませんが、口座振替など資金決済にも多く用いられます。 |
通知預金・・・・ |
預金を預け入れた後、一定の据置期間(払い出しできない期間)が決められ、払い戻す際にもあらかじめ予告が必要となることを条件として、普通預金より高い利率の利息が付く預金で、法人の余裕資金の一時的な運用に利用されることが多いようです。 |
納税準備預金・・ |
納税に充てる資金をプールしておくための預金で、預金利率や課税上の優遇措置が講じられています。 |
貯蓄預金・・・・ |
口座振替に使えないことなどを条件として、普通預金より高い利率の利息が付く預金です。 |
定期預金・・・・ |
あらかじめ期間を決めて預け入れ、その期間が満了するまでは原則として払い戻しができない預金です。普通預金などと比べて高い金利が付くため、貯蓄を目的として利用されることが多いようです。 |
別段預金・・・・ |
雑預金とも呼ばれ、本来は預金商品ではなく、金融機関が一時的な保管金や整理金などをプールしておくためのもので、通常は利息は付きません。 |
注 |
)(1)要求払いであること、(2)決済サービスを提供できること、(3)金利をつけないことの3つの条件を満たす預金を「決済用預金」といいます。例えば、当座預金や無利子の普通預金のようにこれらの条件を全て満たす預金は、決済用預金として預金保険法上全額が保護されます。 |
|
|
| |
※ |
新しい預金保険制度について、もっと詳しくお知りになりたい方は、アクセスFSA第2号の「金融便利帳:ペイオフ」にアクセスしてください。 |
|
 |
近年では、金融機関も顧客のニーズに合わせた独自の商品を開発するなど商品も多様となり、窓口でも多彩な名称の預金商品が販売されていますが、この名称は金融機関独自の商品名、いわば愛称であることが多いと思われますので、それが上記の種類のうちどれに該当するのかは、直接金融機関の窓口でお尋ねください。 |
 |
金融商品としての預金の特徴は、原則として元本保証がある(外貨建てで行う預金、いわゆる外貨預金の場合、為替差損により結果的に元本割れとなることがあり得ます)ことです。また仮に、金融機関が経営破たんに陥った場合でも、一定範囲までは預金保険制度により保護がなされています。
なお、金融機関以外の者が預金の受け入れを行うことは、法律(「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」)により禁じられています。 |
 |
一方、最近、使用してもいないアダルトサイトの料金の支払いや、借りてもいないお金の返済を求める脅迫的な内容の文書を送りつけ、指定した口座に振り込ませてお金を騙し取る「架空請求」や、高齢者のお宅に電話し、氏名は名乗らず「おれ(私)だけど」といって息子や孫だと思わせ、「交通事故を起こしてしまってお金が必要」などと話して、これも振り込ませてお金を騙し取る「オレオレ詐欺」といった悪質な犯罪が多く発生しています。これらの手口には、被害者からお金を受け取る手段として金融機関の預金口座を悪用しているという共通点があります。 |
 |
また、近年深刻化するテロリズム対策や、麻薬・銃器等犯罪を防止するためのマネー・ローンダリング対策が国際的な緊急の課題となっていることを受けて、これらを防止するため、平成15年1月6日から施行された「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」により、金融機関は顧客の預金口座の開設等を行うに際して、運転免許証などの公的証明書により顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は当該顧客の氏名、住居及び生年月日、顧客が法人である場合は当該顧客の名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認することが義務付けられています。 |
| |
※ |
本人確認法について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「本人確認法について」のコーナーにアクセスしてください。 |
|
 |
なお、マネー・ローンダリング(資金洗浄)とは、犯罪で得た『汚れた資金』(犯罪収益)を、あたかも正当な取引で得た『きれいな資金』であるように見せかけるため、その出所を隠したりする行為であり、金融機関等を利用して行われることが多いのが特徴です。中でも銀行口座(預金口座)を利用して行われることが多く、例えば、 |
| |
| ・ |
前述の「架空請求」、「オレオレ詐欺」等の事案では、被害者からの入金を受け取るために特定の口座を指定し、その口座にお金を振り込ませ、振り込まれたお金を直後にATM等で出金したり、他の口座に振込・振替等を行う |
| ・ |
自分の名前や住所等を第三者、特に捜査機関等には知られたくない犯罪者が、架空の名前で偽の健康保険証等を作成したり、実在する他人の名前を無断で騙るなどして口座を開設したり、あるいは他人が正規に開設した口座を買う(口座売買)などして、他人名義の口座を手に入れ、その口座に犯罪収益を振り込む |
|
| |
といったことが行われています。
こうしたマネー・ローンダリングを防止するための主要な手段の一つとして、マネー・ローンダリングと疑われる取引の届出を金融機関等に義務付ける「疑わしい取引の届出制度」がありますが、金融庁では、マネー・ローンダリングと疑われる取引の典型例を「疑わしい取引の参考事例」として公表しており、先の違法な行為等に関連して |
| |
| ・ |
「多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。」特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。 |
| ・ |
「架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金」 |
| ・ |
「匿名又は架空名義と思われる取引と思われる名義での送金を受ける口座に係る取引」 |
|
|
についても、特に注意を払うべき取引として例示しています。 |
 |
また、金融機関に対しては、本人確認の厳格化以外にも、口座の名義人が存在しない(つまり架空預金である)ことが明らかになった場合や、口座の売買が行われている場合、また法令や公序良俗に反する行為に利用され、若しくはその恐れがあると認められた場合には、預金規定に基づき迅速かつ適切に預金取引を停止したり、または預金口座を解約するなどの取組みを行うよう求めています。 |
| |
注 |
)預金規定とは、預金者と金融機関との間に預金取引が成立した場合に双方が遵守すべき事項をまとめた、いわば預金取引契約書とでもいうべきものです。 |
|
 |
預金口座は、資金決済や貯蓄の手段として大きな社会的役割を担っており、金融庁はこれまで述べましたような取組みを通じ、関係各機関とも連携を図りながら、預金口座の不正利用などに対して厳正に対応しているところです。 |
| |
※ |
口座の不正利用に対する金融庁の取組みについてもっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について(平成15年9月12日)」より「“ヤミ金融業者等による不正な預金口座の利用をなくすために”」のページへアクセスしてください。 |
|
 金融研究研修センターは、毎年夏、新シーズンの初めに1年間の目標を決めますが、2003-2004は「外への情報発信」をテーマに掲げました(詳しくは先月のアクセスFSA第12号の吉野直行センター長のインタビューをご覧ください)。その具体策の第一弾として慶應義塾大学経済学部で10月11月に行った講義についてレポートします。
金融研究研修センターは、毎年夏、新シーズンの初めに1年間の目標を決めますが、2003-2004は「外への情報発信」をテーマに掲げました(詳しくは先月のアクセスFSA第12号の吉野直行センター長のインタビューをご覧ください)。その具体策の第一弾として慶應義塾大学経済学部で10月11月に行った講義についてレポートします。