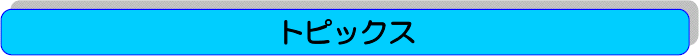アクセスFSA 第155号(2016年5月)

トピックス
(1) 「平成28年熊本地震関連情報」について
平成28年熊本地震によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆さまに対して心よりお見舞いを申し上げます。
金融庁では、ウェブサイト上に「平成28年熊本地震関連情報」ページを開設し、以下のような被災者の皆さまに役立つ情報を提供しています。
(1)預金者の皆さまへ
○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。
○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。
(2)お金を借りておられる皆さまへ
○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。
○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分(銀行等の取引停止処分等)は猶予されます。
○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
○住宅ローンの返済ができなくなったなどの場合は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
※ガイドラインの適用要件や手続等の詳細については、全銀協ウェブサイト「平成28年熊本地震に関する全銀協の対応について
 」にアクセスしてください。
」にアクセスしてください。
(3)保険に加入されている皆さまへ
○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。
○保険証券や届出印鑑等を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じた柔軟な対応を行っています。契約している保険会社が分からない場合については、生命保険協会又は日本損害保険協会にご照会ください。
○被災された方からの申し出があれば、保険料の払込みの猶予等を行っています。
(4)上場企業等の皆さまへ
○震災の影響により本来の期限までに提出できない有価証券報告書等については、特例措置により、本年7月29日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
○さらに、各取引所では、被災した会社の上場管理や、新規上場に係る審査等について、各種の取組みを行い、柔軟に対応することとしています。
(5)金融機関の皆さまへ
○被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対応することとしています。
○貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。
-
○被災者の皆さまからの相談を受け付ける「平成28年熊本地震金融庁相談ダイヤル」(フリーダイヤル)を設置しています。
※フリーダイヤル0120-156811(IP電話からは03-5251-6813)
その他、当ページでは、金融庁・金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該情報は、日々更新しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「平成28年熊本地震関連情報」にアクセスしてください。
また、情報を更新した際には、金融庁Twitterでも情報発信を行っております。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁Twitter![]() 」にアクセスしてください。
」にアクセスしてください。
(2) 「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」の設置・開催について
近年、FinTechの動きが注目を集めていますが、日本では、欧米等に比べて先進的なFinTechベンチャー企業やベンチャーキャピタルの登場が未だ必ずしも実現していないとの指摘があります。
日本の強みを活かしつつ、海外展開を視野に入れたFinTechベンチャー企業の創出を図っていくためには、技術の担い手(研究者、技術者等)とビジネスの担い手(企業、資金供給者、法律・会計実務家等)など、幅広い分野の人材が集積し、これらの連携の中で、FinTechベンチャー企業の登場・成長が進んでいく環境(エコシステム)を整備していくことが重要です。
こうした観点から、有識者による検討の場として、「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」(座長:福田慎一 東京大学大学院経済学研究科教授)を設置し、5月16日に第1回会合を、6月14日に第2回会合を開催しました。
それぞれの会合では、伊藤穣一MITメディアラボ所長や、松尾豊東京大学准教授、金子恭規スカイラインベンチャーズ社代表の各委員からヒアリングを行い、ブロックチェーン技術や人工知能などの先端技術が金融業に与える影響や、シリコンバレーの事例も参考に、FinTechエコシステムの実現に向けた方策などについて、ご議論頂いております。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」にアクセスしてください。
(3) 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第1回)の開催について
平成28年4月、第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合が開催され、麻生金融担当大臣より、「市場・取引所を巡る諸問題に関する検討」として、「情報技術の進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について、幅広く検討を行うこと」との諮問がなされました。この諮問を受けて、神田秀樹学習院大学教授を座長とする、市場ワーキング・グループが設置されました。
5月13日(金)に第1回会合が開催され、取引の高速化について、幅広く議論がなされました。
なお、第1回会合にかかる議事録につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から、「市場ワーキング・グループ」にアクセスしてください。
(4) 「金融仲介の改善に向けた検討会議」(第4回)の開催について
「金融仲介の改善に向けた検討会議」は昨年12月21日に第1回、本年2月22日に第2回、4月4日に第3回会合が開催されたところ、同年5月23日に第4回会合が開催されました。同会合では、企業ヒアリング・アンケート調査の結果や企業ヒアリングを踏まえた地域銀行との対話の結果に対して議論が行われました。
なお、会議は非公開ですが、会議後、議事要旨を金融庁ウェブサイトにて公表しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「金融仲介の改善に向けた検討会議」にアクセスしてください。
(5) 「第7回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」の開催について
平成28年5月24日に第7回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会を開催しました。
当懇談会は、改正貸金業法完全施行後の貸し手・借り手の状況をフォローしつつ、今後取り組むべき施策等について検討するため、平成24年9月に多重債務者対策本部の下に設置されたものです。
第7回懇談会においては、多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向について報告が行われた後、財務局における金融経済教育への取組等についての紹介や有識者で構成される各委員から報告があり、その後、自由討議が行われました。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「第7回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会の開催について」及び首相官邸ウェブサイトの「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会![]() 」 にアクセスしてください。
」 にアクセスしてください。
(6) 「地域の成長マネー供給促進フォーラム」金沢開催について
平成28年6月10日に、北陸財務局(金沢市)において、「地域の成長マネー供給促進フォーラム」が開催されました。
「地域の成長マネー供給促進フォーラム」は、地元ベンチャー企業の経営者をはじめとし、地域金融機関、ベンチャーキャピタル、証券取引所、証券会社、行政当局等の関係者が一堂に会し、資本市場をめぐる現状や課題について幅広く意見交換を行うとともに、地域への成長マネー供給に係る取組事例の紹介・共有等を図るため、各地域で開催しています。過去には平成27年6月に福岡および大阪、同年12月に仙台、平成28年2月に名古屋で開催されました。
今回の金沢開催では、北陸地方のベンチャー企業など地元企業から企業の成長フェーズに応じた資金調達について、ベンチャーキャピタルや地域金融機関等から地域のベンチャー企業等に対する成長マネー供給について、幅広い経験に基づく事例や課題が示され、活発な意見交換が行われました。例えば、「事業の拡大など成長段階に応じて、自己資金中心からIPOを目指すなど資本政策の考え方が変わってきた」、「地方では情報量や出会いが少ないため、資金調達等について広く相談できるコーディネーターのような役割が求められる」、「北陸地方のIPO件数や開業率は全国的に少ないものの、潜在的には魅力的な企業が出てきており、今後の展開が期待される」などの意見が聞かれました。
(7) 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第8回)について
「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」は2月18日に第6回会合を、4月26日に第7回会合を開催したところですが、6月1日(水)に第8回会合を開催しました。同会合では、第7回に引き続き「企業と機関投資家の間の建設的な対話」を議題とし、これまでのフォローアップ会議における意見や、機関投資家からのヒアリングを踏まえ、議決権行使をめぐる利益相反等について議論が行われました。
本会議では、今後の会合において議論・検証されるべきと考えられる事項、その他コーポレートガバナンスの更なる充実等に関して、広く意見を募集しております。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「公表物」→「審議会・研究会等」→「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」にアクセスしてください。
(8) シンポジウム「日本及びアジアにおける地方創生に貢献する金融業のあり方」について
金融庁金融研究センター、グローバル金融連携センターでは、神戸大学大学院経営学研究科、京都大学経済研究所、大阪大学社会経済研究所及びアジア開発銀行研究所(ADBI)との共催により、シンポジウム「日本及びアジアにおける地方創生に貢献する金融業のあり方」を、平成28年5月19日(木)に開催しました。本シンポジウムでは、地域の金融機関がどのように地方創生や顧客企業の事業承継に関与しているか、また地方創生に貢献する金融を進めるための金融庁の施策、地方創生に資するアジアの金融業の事例について議論等を行いました。本シンポジウムには、金融機関関係者や研究者など、総勢130名を越える参加があり、活発な議論が展開されました。
冒頭の西田直樹 金融庁監督局審議官の開会挨拶に続き、4つのセッションにおいて、「地方創生、事業承継、事業転換における地域金融の関わり方」、「地方創生・一億総活躍に資する金融の実現に向けた金融庁の取組み」、「地域におけるリスクマネー供給の仕組み」、「地方創生に資するアジア諸国の金融業の事例」について、報告や議論が行われました。(各セッションの発表者やコメンテーター及び発表資料については、金融研究センターウェブページ(http://www.fsa.go.jp/frtc/index.html![]() )に掲載予定です。)
)に掲載予定です。)
-
セッション1: 地方創生、事業承継、事業転換における地域金融の関わり方
セッション1(司会:内田浩史 神戸大学大学院経営学研究科教授)では、地域金融機関による中小企業の事業承継や事業活性化の取組みについて議論が行われました。
まず、地域金融機関より、事業承継の事例やコンサルティングを通じた事業支援の取組みについて紹介がありました。その後、学識者より、人口減少など社会状況が変わる中でも、地域金融機関は地域における金融取引のコアとして存在し、地方創生においても役割は大きいとの報告があり、また、金融機関自身も収益力を高める必要があることについて指摘がありました。金融庁からは、地域金融機関による地方創生への関わり方について、その規模や特性、役割に応じた取引先支援が重要であると説明がありました。
-
セッション2: 地方創生・一億総活躍に資する金融の実現に向けた金融庁の取組み
セッション2(司会:森知也 京都大学経済研究所教授)では、金融システムを通じて地方創生・一億総活躍を促していく金融庁の取組みについて議論が行われました。
金融庁からの発表では、金融機関に対して事業性評価に基づく融資・本業支援を推進するよう促すことにより、金融仲介機能の質を改善し、地方創生に貢献する金融業の実現を目指しており、この一環として行っている融資先企業へのヒアリングや外部有識者による検討会議について紹介がありました。また、市町村民税データや経済センサスデータを活用した東北地方の産業分析事例を紹介し、地域の産業構造をふまえた取組みから地方創生に繋げることが可能であるとの報告がありました。学識者からは、地方創生において地域金融機関に期待される役割とは、取引先企業が必要としている情報の提供とコンサルティングを行い、ガバナンスを強化したうえでリスクテイクしていくことであるとの言及がありました。
-
セッション3: 地域におけるリスクマネー供給の仕組み
セッション3(司会:尾崎弘之 神戸大学大学院経営学研究科教授)では、地域における直接金融を通じたリスクマネー供給の仕組みについて議論が行われました。
まず、インターネット上で投資型クラウドファンディングの枠組みを提供している金融商品取引業者より、金融機関、ベンチャーキャピタルに加え、第3の資金供給・調達手段として、個人(家計)からの「資本性資金の提供」について、具体的な事例を踏まえながら紹介がありました。続いて、金融庁より、投資型クラウドファンディングの利用を促進するための制度整備や株主コミュニティ制度の導入などについて紹介がありました。その後、学識者から、神戸大学に本年4月に新設された研究科における、大学発ベンチャー企業への創業支援、人材育成の取組みについて報告が行われました。
-
特別講演、セッション4: 地方創生に資するアジア諸国の金融業の事例
河野正道 金融庁金融国際審議官・グローバル金融連携センター長より、アジア諸国における金融包摂及び長期投資の活性化について特別講演が行われました。
アジア諸国がインフラ整備のために要する膨大な資金を調達するには、金融包摂を推進し、域内の貯蓄が効率的に生産的投資に用いられるようにすることが重要であると指摘し、日本の長期信用銀行や協同組織金融機関が高度成長期に長期資金の供給で果たした役割について紹介がありました。また、FinTechのような新しい金融技術の発展も金融包摂や投資資金の供給に資するが、利用者保護のために必要な規制とのバランスに配慮すべきとの言及がありました。
特別講演に続いて行われたセッション4(司会:吉野直行 金融庁金融研究センター顧問、ADBI所長)では、アジア諸国における金融業の現状や規制のあり方について、議論が行われました。
まず、元金融庁アジア金融連携センター研究員であるタイとカンボジアの当局者より、両国における金融包摂・マイクロファイナンスの歴史や実情について紹介がありました。その後、国際機関より、アジア地域全般における金融包摂の状況やマイクロファイナンスに対する規制のあり方について報告が行われました。同報告では、マイクロファイナンスを提供する金融機関に対する規制を検討するに当たっては、リスクに応じた規制であるか、また規制導入のコストが考慮されるべきであるとの指摘がありました。
(9) NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について
金融庁では、NISA(少額投資非課税制度)について、今般、「NISA口座の開設・利用状況調査」を実施し、平成28年5月27日、その結果について公表しました。
【調査結果の概要】
○総口座数(平成27年12月31日現在)は、987万6,361口座
- 前回調査時点(平成27年9月30日)から、約30万口座、約3.1%増加
- 年代別の内訳の割合は、20~30歳代14.4%、60歳代以上53.9%
○総買付額(制度導入時点~平成27年12月31日)は、6兆4,444億8,391万円
- 商品別の内訳の割合は、上場株式33.6%、投資信託64.1%、ETF1.5%、REIT0.8%
- 年代別の内訳の割合は、20~30歳代10.8%、60歳代以上59.8%
NISAは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、中長期的な資産形成を促進していくとともに、日本経済の成長資金の供給拡大を図ることを目的として、平成26年1月から導入されました。
こうした中、制度導入から2年が経過し、NISAの総口座数は約988万件となり、総買付額は約6兆4,445億円になるなど、NISAの普及は着実に進んでいると考えられます。
NISAの口座を開設した顧客の年齢層を見ると、60歳代以上の割合が依然として半数以上を占める一方で、50歳代以下の割合については、平成27年12月末時点で約46%となっており、制度を開始した平成26年1月末時点では約37%であったことを踏まえれば、着実に増加しているものと言えます。
※詳しくは、金融庁ウェブサイト内の「NISA特設ウェブサイト」から「NISAとは?」→「データ集」→「平成27年12月末時点(確報値)(平成28年5月27日公表)」にアクセスしてください。
(10)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成28年1月1日~同年3月31日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成28年1月1日から同年3月31日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成28年1月1日から同年3月31日までの間に、9,122件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均150件となっており、平成27年10月1日から同年12月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績146件と、ほぼ同水準となっています。
事前相談の受付件数は、上記9,122件のうち281件となっています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,817件(構成比31%)うち事前相談45件、投資商品等に関する相談等の受付件数2,656件(同29%)うち事前相談178件、保険商品等に関する相談等の受付件数2,408件(同26%)うち事前相談2件、貸金等に関する相談等の受付件数889件(同10%)うち事前相談53件、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数352件(同2%)うち事前相談3件となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、一般的な照会・質問に関する相談等が増加したことから、前期に比べ、やや増加しています。
(2)保険商品等については、前期とほぼ同水準となっています。
(3)投資商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが387件あり、そのうち223件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(251件)のうち、70代が81件(32%)、60代以上が40件(16%)、80代が30件(12%)と高齢者についての相談が大部分を占めております。
(4)貸金等については、行政に対する要望等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)無登録営業に関するもの
(12)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、口座開設拒否、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの
(13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(14)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、157の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、15の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成28年1月1日~同年3月31日)(平成28年4月28日)にアクセスしてください。

 検索
検索