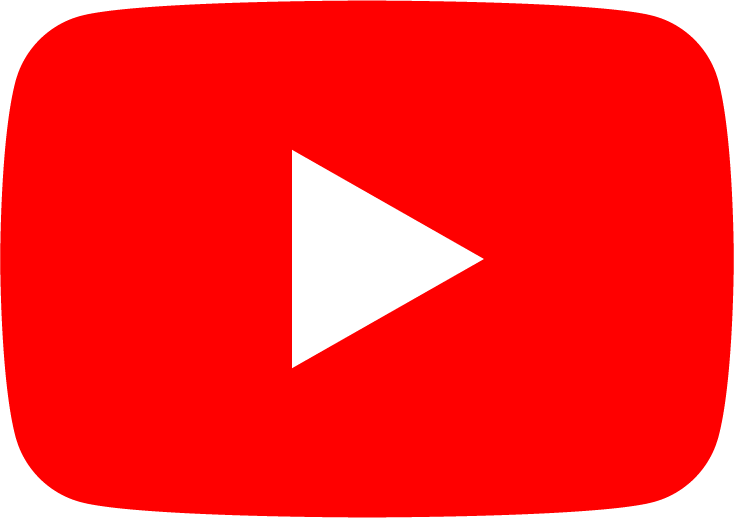- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「第一部会」
- 企業会計審議会第17回第一部…
平成14年3月18日
金融庁
企業会計審議会第17回第一部会議事録について
企業会計審議会第17回第一部会(平成14年2月22日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第17回第一部会議事録
日時:平成14年2月22日(金)午後3時31分~午後5時28分
場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室
- ○斎藤部会長
-
それでは、定刻になりましたので、これより第17回の第一部会を開催いたします。
委員の皆様には、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、パーチェス法に関して、特にのれんを中心とする論点についてご審議をいただく予定にしております。
ただ、その前に、前回の部会の最後に辻山委員からご質問がございまして、時間の関係で私が一方的に打ち切ってしまいましたが、その後、辻山委員からその際のご質問の趣旨を補足するメモが提出されました。辻山委員は本日、海外出張でご欠席でありますけれども、私の方からごく簡単にメモの趣旨をお伝えして、責めを塞ぎたいと思います。
辻山委員のご指摘は、前回の部会の資料のコメントの中に段階法と全面時価法との組み合わせのもとで評価差額が認識されてくるというようになっているのですが、実は、評価差額が認識されるのは段階法に固有の特徴であって、必ずしも全面時価評価法と組み合わせないで、部分時価評価法と組み合わせた場合でも認識されるはずである。そのような趣旨のことを配られた数値例に則して説明されようとしたということであります。その点は多分、前回の審議の中で大日方委員のご指摘に対しまして私がお答えしたことに部分的には含まれるわけであります。つまり、段階法を採用した場合、段階取得のインターバルにおいて、被投資会社の剰余金が増えた分のうちの投資会社の持分相当額は消去されずに残るわけです。それが評価差額として出てくるわけでございます。その趣旨をもう少し別な角度から厳密に指摘されようとした。そのようなことでありますので、辻山委員のメモをそのようにお伝えして私の責任を塞ぎたいと思います。特にこの点はご質問よろしゅうございますね。
ありがとうございました。
それでは、本日の審議に入りたいと思いますが、まず金井委員からパーチェス法の検討その2についてご報告をお願いいたします。よろしくお願いします。
- ○金井委員
-
金井でございます。それでは、パーチェス法の検討2という題目でご説明させていただきます。
本日、お配りいたしました資料が三つございまして、資料1が主たる説明の資料でございます。それから資料2が「のれんの償却方法(各方法のメリット・デメリット)」でございますけれども、これは正ののれんの償却方法につきましていろいろな方法が考えられますので、その各方法のメリット、デメリットを表にまとめたものでございます。
それから資料3が、今回ご説明させていただくにあたりましてビジュアルにご理解いただこうと思いまして、いくつか作成してまいりました資料になります。説明が進むにしたがいましてごらんいただけたらと思います。
資料1の「パーチェス法の検討2」の方に戻っていただきまして、本日は大きく五つのトピックがございます。一つ目が「正ののれんの取扱い」、その中に「のれんの本質」、「のれんの償却方法」、「のれんの償却期間」、「今後の要検討事項」が含まれます。
それから二つ目が「研究開発用資産」、研究開発用の有形・無形資産の対価に相当する金額の企業結合会計における取扱いでございます。
それから三つ目が「予想される将来の損失に対する引当金の会計処理方法」、予想される将来の損失に対する引当金として大きく考えられますのが、「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」、「十分な信頼性をもって測定することができない偶発事象に対する費用、または損失」、それから「被取得企業の引当金計上もれ、取得企業の会計処理方法にしたがった場合に生じる差額」。これらの三つの取扱いについてお話させていただけたらと思います。
それから四つ目が「負ののれんの取扱い」です。負ののれんにつきまして、「発生原因の検討」、「会計処理の検討」、それから「今後の要検討事項」でございます。
最後に五つ目に「無形資産の識別基準と償却期間」といたしまして、「会計処理の検討」、および「振替対象となる無形資産の範囲」についてご説明させていただきたいと思います。
それでは2ページ目をめくっていただけますでしょうか。一つ目の「正ののれんの取扱い」という中で、のれんの本質につきまして簡単にご説明させていただけたらと思います。これは資料3では1枚目の図1です。1(1)「のれんの本質」というところと対応してございます。
のれんの本質ですけれども、のれんとなり得る要素としては一般に以下の七つが考えられるかと思います。
一つ目が、被結合会社の買収時点における簿価と時価の差額です。資料3の図1をみていただけたらと思いますが、左上にありますのが簡単な被結合会社の貸借対照表でございます。そして右下に斜線で純資産があります。この純資産が被結合会社の簿価となると思いますけれども、いちばん右端が買収価額です。実際に支払われた金額でございます。この被結合会社の簿価と買収価額の高さの差額が、これからご説明する
 から
から のどこかに該当するという意味で記載いたしました。
のどこかに該当するという意味で記載いたしました。1番目の被結合会社の買収時点における簿価と時価の差額というのが、資料3図1にあります
 の時価が簿価を少し超えているところでございます。
の時価が簿価を少し超えているところでございます。それから2番目の買収時に会計上認識されていなかった被結合会社純資産の時価。これは
 の白くなっているところでございますけれども、例えば会計基準において資産ですとか負債として認識することが認められていないような場合に、このような買収時に会計上認識されなかった被結合会社の純資産の時価という部分が生じてまいります。
の白くなっているところでございますけれども、例えば会計基準において資産ですとか負債として認識することが認められていないような場合に、このような買収時に会計上認識されなかった被結合会社の純資産の時価という部分が生じてまいります。それから
 は時価のところを超える部分ですけれども、被結合会社の事業の超過収益力です。
は時価のところを超える部分ですけれども、被結合会社の事業の超過収益力です。 は結合当事会社、すなわち、結合会社と被結合会社の両方の事業の結合によるシナジー効果でございます。
は結合当事会社、すなわち、結合会社と被結合会社の両方の事業の結合によるシナジー効果でございます。それから
 が、株式交換の場合における買収価額の過大評価でございます。これはどのようなことかと申しますと、例えば株式交換の場合で結合会社の株式のトレードボリュームが非常に低い場合、可能性として株価が高めに評価されていることがあるかと思います。株式交換で新株を発行したときにその株式数に対して、この高めの株価を適用すると対価の額が過大に評価されてしまうという意味でございます。そのような意味で資料3の図1の右端の買収価額が、あるべき姿よりは高めになってしまったという意味で
が、株式交換の場合における買収価額の過大評価でございます。これはどのようなことかと申しますと、例えば株式交換の場合で結合会社の株式のトレードボリュームが非常に低い場合、可能性として株価が高めに評価されていることがあるかと思います。株式交換で新株を発行したときにその株式数に対して、この高めの株価を適用すると対価の額が過大に評価されてしまうという意味でございます。そのような意味で資料3の図1の右端の買収価額が、あるべき姿よりは高めになってしまったという意味で が右の上に記載されているわけでございます。
が右の上に記載されているわけでございます。それから
 が結合会社による過払い、もしくは過少払いもこれにあたるかと思いますが、具体例としましては例えば入札プロセスとかがございまして、余分に、そのときの状況に応じて高めに払ってしまったような部分がこれに該当します。
が結合会社による過払い、もしくは過少払いもこれにあたるかと思いますが、具体例としましては例えば入札プロセスとかがございまして、余分に、そのときの状況に応じて高めに払ってしまったような部分がこれに該当します。7番目が結合会社の既存事業の超過収益力です。これは結合会社の方の超過収益力でございます。これにつきましては、また下にも記載してございますのでそのときに説明させてください。
この本質という点でございますけれども、
 、
、 の時価にあたる部分については、そもそものれんとなるべきものではございません。それから
の時価にあたる部分については、そもそものれんとなるべきものではございません。それから の高めの株価をつけてしまったというところは、測定エラーであります。また、
の高めの株価をつけてしまったというところは、測定エラーであります。また、 は取得に伴う利益または損失であることから理論的にのれんとなるものではありません。したがいまして、ここで申し上げた
は取得に伴う利益または損失であることから理論的にのれんとなるものではありません。したがいまして、ここで申し上げた と
と ですね、「被結合会社の事業の超過収益力」と「結合当事会社の事業の結合によるシナジー効果」がコアののれんと言えるものかと思います。
ですね、「被結合会社の事業の超過収益力」と「結合当事会社の事業の結合によるシナジー効果」がコアののれんと言えるものかと思います。 結合会社の既存事業の超過収益力ですが、特に株式交換による企業結合に際して、プレミアムが被結合会社の株主に与えられるケースで生じることが多いといわれます。
結合会社の既存事業の超過収益力ですが、特に株式交換による企業結合に際して、プレミアムが被結合会社の株主に与えられるケースで生じることが多いといわれます。 の要素が企業結合で生じる貸借差額に含まれる場合、それを資産計上することは自己創設のれんを計上することに等しく、かつ、その相当額が評価益ではなく、資本に算入されることを意味します。
の要素が企業結合で生じる貸借差額に含まれる場合、それを資産計上することは自己創設のれんを計上することに等しく、かつ、その相当額が評価益ではなく、資本に算入されることを意味します。どのようなことかと申しますと、以前この委員会でもご説明がありましたかと思いますが、株式交換のときは現金による買収のときよりも高めに支払われる、もしくは株式が交付される傾向があるということで、その要素が結合会社の既存事業の超過収益力と考えることができるかと思います。ということで、払われる・交付される株式の価値が高めに支払われる、もしくは発行されるということは、増加資本が多くなり、結果として、借方ののれんの部分が多くなるわけです。そののれんの性格が何かといいますと自己創設のれんを資産計上したのと同じようなことを意味するのではないかという意味でございます。
ということで、
 から
から までの要素がございますけれども、
までの要素がございますけれども、 、
、 がコアののれんと言えるものと考えます。
がコアののれんと言えるものと考えます。次に二つ目として「のれんの償却方法」に移らさせていただきます。「可能な選択肢」としては、大きくA、B、Cの三つございます。Aは「払込資本(拠出資本)から控除する」、Bは「留保利益から控除する」、Cは「年度の純利益から控除する」ですが、その中にC1として「即時に償却する」、C2「規則的に期間配分して償却する」、C3「通常は償却せず、減損処理をする」という三つの方法が考えられるかと思います。
次に移りまして、「各方法のメリット・デメリット」ですが、これが本日お配りいたしました資料2でございます。2ページございまして、1ページ目の方がA・Bの払込資本・拠出資本から控除する方法と、留保利益から控除する方法に関するメリット・デメリットを記載してございます。簡単にご説明させていただきますと、A・Bの方法のメリットといたしましては、先ほど申し上げたのれんの本質
 の「結合会社による過払い」や
の「結合会社による過払い」や の「結合会社の既存事業の超過収益力」を要因とするのれんの額が含まれている場合に、これは資本等から控除することになりますのでその影響額を排除することができます。
の「結合会社の既存事業の超過収益力」を要因とするのれんの額が含まれている場合に、これは資本等から控除することになりますのでその影響額を排除することができます。また、貸借対照表という観点からみますと、自己創設のれんと貸借対照表上の取扱いが一致することになります。のれんが計上されないという意味でございます。
かたやデメリットでございます。1番目として、企業結合における投資対価のすべてが費用性支出とみなされ、その全額がいずれかの会計期間で費用になるというのが、現在の一般的な考え方といえると思いますが、この投資支出を費用に配分して年度の業績を測定するという企業会計の基本的枠組みに合致していないという問題があるかと思います。
二つ目は、自己創設のれんと貸借対照表上の取扱いは一致するが、損益計算書上の処理が異なるという点が残ってしまいます。その結果として買収により成長した会社の方が、組織的に成長してきた会社よりも利益率が高くみえるということがあると思います。これはどのようなことかといいますと、組織的に成長した会社の場合は、のれんの自己創設のためのコストが費用に落ちるわけでございますが、買収の場合はその相当額が資本から直接控除されてしまうということで、損益計算書に通る金額が違ってくるということになるかと思います。
三つ目としまして、のれんに対する経営者の責任を正しく表さないこととなります。
四つ目、買収会社の純資産が減少してしまったという印象を与えます。
五つ目、のれんとその他の無形資産について異なる会計処理を求めることにより、極力その他の無形資産として会計処理をする恣意性が入りやすくなります。これは資産を減らすよりは長期にわたって償却した方がいいというインセンティブがあるということが前提となっていますけれども、しかしながら、そもそも両者は性格の近似したものであり、またその区分も主観的なものであることから、異なる会計処理を求めることの妥当性に疑問が残るというデメリットがございます。
次にページをめくっていただきまして、Cの年度の純利益から控除する三つ方法についてのメリット・デメリットでございます。
一つ目が「即時に償却する」方法のメリットですけれども、自己創設のれんと購入のれんの取扱いが基本的に整合する、すなわち、支出額が費用化されるという意味で貸借対照表と損益計算書の両方が整合するということです。当然費用化されるタイミングが違いますので、基本的ということで完全にではございません。
それからデメリットの方が、のれんの第一の要素である被結合会社の超過収益力が時間の経過とともに減少するとしても、即時に消失する性格ではないという点、すなわち収益との対応という観点から問題が残ります。
次に二つ目、「規則的に期間配分して償却する」方法のメリットです。一つ目が超過収益の実現パターンに応じて資産を償却することは現在の企業会計では行われておらず、あらかじめ定めた一定の計画にしたがって規則的に償却するのが原則とされています。また、規則的償却に替わるのれんの減損額の算定方法を、別途に定める必要はないというメリットが考えられます。
デメリットですけれども、償却年限をどのように決めたらよいかという論点があります。のれんの償却費の持つ意味は投資家にとって乏しく、また、のれんは減価するとしても規則的なものではなく、その有効経済年数を予測することは困難であります。四つ目として、自己創設のれんと購入のれんの取扱いが異なってしまうという問題が残ります。
最後にC3、「通常は償却せず、減損処理をする」という方法でございます。メリットとしましては、のれんの価値が維持されているということは、経営者がのれんの価値を維持し、投資に対するリターンを生んでいるという事実を適正に表します。また、先ほどのC2で主張してきたことに対するものですけれども、十分厳格で適用可能な減損レビューの方法は、確立可能であります。
デメリットとしましては、のれんが超過収益力を表すとみるならば、競争の進展によって通常はその価値が減耗するはずであり、非償却の処理はその点を無視します。二つ目、たとえ超過収益力が維持される場合でも、それは結合後の追加的な投資や企業の追加的な努力によって補完されているのであり、のれんを償却しないのは、追加投資による自己創設のれんを計上するのに実質的に等しいと考えられるというデメリットがございます。三つ目、自己創設のれんとの会計処理の不整合という点は、やはりこの方法でも残るかと思います。
というのが各方法のメリット・デメリットでございます。
資料1に戻っていただきまして、次に「考え方」でございますけれども、この資料の中では本日の議論のために、考えられる一つの方法を記載させていただいております。
一つの考え方としましては、株式を取得した後の連結財務諸表作成手続き――連結調整勘定の償却と、直接資産・負債を受け入れ、当該会社を消滅させた場合――企業結合とが本質的に同一であるとしますと、正ののれんと投資差額の会計処理との整合性を重視する考え方があるのではないかと考えます。
すなわち、規則的に期間配分してはどうかということでございますけれども、また、規則的に期間配分して償却する方法には、以下の論拠もあるのではないかと考えられます。
一つ目が、収益と費用の対応のためには償却が必要ではないか。
二つ目として、取得したのれんは時間の経過とともに自己創設のれんに替わるが、取得のれんを償却しなければ自己創設のれんを計上したことになってしまうのではないか。
三つ目として、のれんの効果のおよぶ期間及びその減価パターンは予測可能なものではなく、一定期間にわたる償却が可能な選択肢の中ではもっとも合理的と考えられるのではないか。
四つ目として、のれんのうち価値の減価しない部分があったとしても、その部分だけを切り出すのは困難と言えるのではないか――という点でございます。
但し書きといたしまして、米国・カナダの新基準及びIASBの暫定的結論では、C3の「通常は償却せず、減損処理をする」方法が採用され、もしくは採用される予定のようです。
次に、この正ののれんの償却期間ですが「一般に20年以内の期間にわたる償却」を一つ本日の議論のためにおかせていただいて、この方法を採用する理由として以下の点が挙げられており、一つの選択肢になるものと考えられます。
諸外国の既存の会計基準で広く採用されてきたと言えるのではないか。
長期計画の期間が20年を超えることはまれであるのではないか。
それから、割引率を考慮した場合、20年目以降の現在価値の重要性は低いと言えるのではないか。
四つ目として、20年を超える期間にわたる償却は、実質的に「非償却」の要素が強くなり、別途その場合の減損規定の必要性が生じるのではないか、ということでございます。
これらの正ののれんの会計処理を行ったうえで、今後さらに要検討事項が残ってしまいますけれども、考えられる範囲内で二つあると思います。
一つは、「合併のれんの償却期間」です。商法285条の7によれば、正ののれんは、有償譲受け、吸収分割及び合併により取得した場合に限って資産計上することが認められており、その場合は取得後5年以内に均等額以上を償却することとされています。会計基準として「20年以内の期間にわたる償却」を採用した場合、現行商法との調整が必要となります。
それから二つ目として、のれんを規則償却とした場合、例えばのれんの本質
 、
、 ですね。先ほどの買収価額の高い株価を適用したことによる過大評価ですとか、結合会社による過払い、すなわち、入札プロセスの存在による過払い等に起因するのれんが発生したときに、のれんの減損が適正に認識される規定・仕組みを設ける必要があるか検討を要するものと考えます。
ですね。先ほどの買収価額の高い株価を適用したことによる過大評価ですとか、結合会社による過払い、すなわち、入札プロセスの存在による過払い等に起因するのれんが発生したときに、のれんの減損が適正に認識される規定・仕組みを設ける必要があるか検討を要するものと考えます。例えば、これは採用されなかったのですけれども、1999年9月に公表された米国新基準の公開草案では、取得企業は、以下の一つ以上に該当する事象が取得日現在で存在する場合には、取得日後2年以内にのれんの回収可能性の検討を実施しなければならないとしておりました。
その事象というのが四つございまして、一つ目として、取得が議論される以前における被取得会社の時価総額を超える多額のプレミアムが支払われていた。
二つ目が、取得価額に比べて相対的に多額ののれんが計上されている。
三つ目として、取得時に明らかに識別可能なオークションまたは入札プロセスが存在していた。入札等によって価格がつり上げられた可能性がある場合ですね。
それから取得対価の支払が、主に取得会社の株式で行われた場合です。株式交換で行われる場合、やはり多めに支払われる可能性があるということを前提にしているかと思います。
以上で、一つ目の論点の正ののれんの処理に関しますご説明を終わらせていただきまして、次に二つ目「研究開発用資産の取扱い」でございます。研究開発用の有形・無形資産の対価に相当する金額を企業結合会計においてどのように処理するのがよいかということでございます。お手元の資料3の図2を開いていただけますでしょうか。
会計処理方法の検討でございますけれども、企業結合会計において研究開発用の有形・無形資産を受入時に時価評価する、しないということで、このA・B二つの会計処理が考えられるかと思います。
一つ目は、時価評価しない場合です。これは資料3の図2をみていただくと、時価評価しないわけですから簿価と受入資産の時価がイコールになりまして、結果として研究開発用資産がのれんの中に含まれるという会計処理になります。これがAでございます。
それからBとしては、差額のうち研究開発の対価に相当するものは、購入対価の一部を構成するが、取得後の取扱いについてはその性質により、「研究開発等に係る会計基準」にしたがうこととなるというものです。これは図2をみていただくと、研究開発用資産ということで時価で認識されまして、のれんの額は先ほどのAの場合よりは少なくなるわけです。ところが、この研究開発用資産として受け入れた金額については、「研究開発等に係る会計基準」が存在しますので、これにしたがって費用処理等の会計処理が行われることとなるということでございます。
一つの考え方でございますけれども、わが国の場合、研究開発費の基準が米国基準と近いと思われますので、自社研究開発の場合の処理との整合性、すなわち研究開発費の意見書の考え方――意見書前文三2にしたがうとBの方法が妥当かもしれないと思われます。
これが二つ目の研究開発用資産の取扱いでございます。
それから三つ目、「予想される将来の損失に対する引当金(偶発損失引当金や利益留保に近い性質をもった引当金など)」の会計処理方法です。これはまた、お手元の資料3の図3になりますのでごらんください。
一つ目が発生原因でございますけれども、発生原因としましては
 、
、 、
、 と三つ考えられるかと思います。
と三つ考えられるかと思います。一つ目が、将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないものの存在。例えばよくいわれているのがリストラ引当金などでございます。
それから、偶発損失。将来の費用または損失となり得るが、十分な信頼性をもって測定できない可能性があるものでございます。
三つ目が、条件付負債。被取得企業の引当金計上もれ、取得企業の会計処理方法にしたがった場合に生じる差額でございます。
ここで、IASBが現在進めております改訂でこの辺をどのように取り扱っているかということについてなのですけれども、まず一つ目の「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」につきましては、現行基準ではリストラ引当金など、ある例外を認めていたのですけれども、改訂案では負債・引当金認識基準の一般原則にしたがって処理し、リストラ引当金だけについての例外は認めないという考え方で整理が進んでいるかと思います。
二つ目の偶発損失については、信頼性をもって測定可能な限り計上すべきという考え方で進んでおります。なぜ
 と
と で違った整理をしているかといいますと、ここに記載しましたように、IASBの定義によりますと、企業結合時点における原因事実の発生の有無、すなわち将来の支出となる可能性がある原因の事実が企業結合時点で既に発生しているか、それから将来の費用・損失の発生に取得企業の意思が反映されるかどうかで両者の性質は違うというように区別しております。例えば偶発損失につきましては、原因は発生しているけれども取得企業の意思で支出がなされるわけではありません。かたや将来予測される費用または損失で負債の認識基準を満たさないものといいますのは、原因事実はまだ発生しておらず、ただ将来支出するかどうかというのは人・企業の意思で決まるものということです。ということで、前者の方を計上する。逆に「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」については、計上しないという方向で整理が進んでいるのだと思います。
で違った整理をしているかといいますと、ここに記載しましたように、IASBの定義によりますと、企業結合時点における原因事実の発生の有無、すなわち将来の支出となる可能性がある原因の事実が企業結合時点で既に発生しているか、それから将来の費用・損失の発生に取得企業の意思が反映されるかどうかで両者の性質は違うというように区別しております。例えば偶発損失につきましては、原因は発生しているけれども取得企業の意思で支出がなされるわけではありません。かたや将来予測される費用または損失で負債の認識基準を満たさないものといいますのは、原因事実はまだ発生しておらず、ただ将来支出するかどうかというのは人・企業の意思で決まるものということです。ということで、前者の方を計上する。逆に「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」については、計上しないという方向で整理が進んでいるのだと思います。続きまして、「会計処理方法の検討」でございますけれども、今申し上げました
 、
、 、
、 それぞれについて検討してまいりたいと思います。
それぞれについて検討してまいりたいと思います。一つ目が、「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」でございますけれども、可能な選択肢といたしまして大きく五つございます。
一つ目は、将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもののうち、リストラ引当金についてだけ別途定める一定の条件――例えば取得企業の取得計画において識別され、かつ、信頼性をもって測定できる将来の損失や費用の予測に関連するものであること等――を満たす限りにおいて、取得企業は取得日時点において負債として認識するというのが一つの考え方だと思います。
2番目の選択としましては、これと内容的には同じなのですが、ただ、負ののれんの発生する場合においてのみ、かつ、負ののれんの額を限度として行うという考え方があるかと思います。
それから三つ目として、将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないものについては、その発生の可能性が取得対価の額に反映される場合には負債として認識し、認識の対象となった事象が発生した期に戻し入れるということです。これは
 とどう違うかといいますと、
とどう違うかといいますと、 の場合は、まずリストラ引当金についてだけというように限定していました。そのような意味で
の場合は、まずリストラ引当金についてだけというように限定していました。そのような意味で の場合はリストラ引当金に限定していない場合です。ただ、何もかもやみくもというわけではなくて、その発生の可能性が買収等の交渉材料の中で取得対価として反映される場合には、その金額でもって負債として認識してはいかがでしょうかということでございます。
の場合はリストラ引当金に限定していない場合です。ただ、何もかもやみくもというわけではなくて、その発生の可能性が買収等の交渉材料の中で取得対価として反映される場合には、その金額でもって負債として認識してはいかがでしょうかということでございます。四つ目は、
 の処理を
の処理を と同様、負ののれんが発生する場合において、負ののれんの額を限度として行うということでございます。
と同様、負ののれんが発生する場合において、負ののれんの額を限度として行うということでございます。それから五つ目が、負債の認識基準を満たさないものは計上すべきではないという筋を通した考え方でございます。
この引当金を計上する、計上しないがどのような影響を与えるかということなのですが、これについては先ほどの図3をみていただけますでしょうか。ごく簡単な例でございますけれども、Aの方は引当金を認識しない場合です。取得企業の純資産額と取得価額を比べまして、この差額が負ののれんになります。Aの場合、引当金として認識しないことから、当然のことながら差額全額が負ののれんになるわけです。
そしてBの方が認識する場合です。認識する場合は、引当金の認識された部分は負債が増加いたしますので、負ののれんが少なくなって引当金がその分増加します。この引当金は最終的にその原因となる支出が行われたときに戻し入れられることになるかと思います。
「考え方」といたしまして、先ほどの資料1に戻っていただきまして、計上金額の客観性の確保、負ののれんが発生する場合とそれ以外の場合で異なる会計処理方法を規定する積極的な理由がないとすると、負ののれんが発生する場合にかかわらず、また、リストラ引当金に限定せず、将来予測される費用・損失であって負債の認識基準を満たさないものについては、その発生の可能性が取得対価の額に反映されている場合には負債として認識し、認識の対象となった事象が発生した期に戻し入れる方法が考えられます。
先ほど述べさせていただいた選択肢の中では
 になるかと思いますけれども、
になるかと思いますけれども、 が一つの考え方としてあるのではないかと考えております。
が一つの考え方としてあるのではないかと考えております。次に二つ目といたしまして、「十分な信頼性をもって測定することができない偶発事象に対する費用、または損失」ということでございますけれども、「可能な選択肢」としまして、以下の三つが考えられるかと思います。
将来予測される費用または損失と異なり、偶発事象はすでに存在する、または発生の可能性がある支払い義務であり、主として企業のコントロール外の要因で確定します。先ほどと同じような考え方で、その発生の可能性が取得対価の額に反映されている場合には負債として認識すべきではないかと考えます。
二つ目の選択肢は、この処理を負ののれんが発生する場合においてのみ、かつ、負ののれんの額を限度として行う方法でございます。
三つ目の方法は、十分な信頼性をもって測定することができない偶発事象に対する費用または損失は計上すべきではないという考え方です。
一つの考え方でございますが、その発生の可能性が取得対価の額に反映されている場合は
 ――すなわち負債としての認識を選択する余地はあるのかと考えております。
――すなわち負債としての認識を選択する余地はあるのかと考えております。次に三つ目でございますけれども、被取得企業の引当金計上もれ、取得企業の会計処理方法にしたがった場合に生じる差額についてです。これは考え方として簡単に入れさせていただきまして、取得企業において負債として認識する方法が合理的ではないかと考えております。
次に四つ目のトピックでございますが、負のれんの取扱いです。お手元の図の4になります。
まず、一つ目としまして、負ののれんの発生原因を簡単に検討いたしました。負ののれんの発生する原因としては、以下の四つの場合が考えられるかと思います。
一つ目が、バーゲンパーチェスです。被取得企業が知り得ないような公正価値があったということです。
二つ目、将来予測される費用・損失であって負債の認識を満たさないものの存在です。先ほどの三つの目のトピックの将来予測される費用・損失であってその認識基準を満たさなかったものが存在したわけで、図3でみていただいたとおり、これが存在して、なおかつ、負債・引当金として認識されませんと、負ののれんの額が生じてくる、もしくは大きくなるということでございます。
三つ目が偶発損失の存在。先ほどのと同じ内容です。
四つ目が識別可能資産・負債の公正価値測定上の不備であり、具体的には資産を過大評価したですとか負債を過小評価した場合です。
次に会計処理方法の検討ですが、検討する場合の一つの要素としましては、一つ目のトピックで正ののれんのことをお話させていただきましたけれども、それと対称的に処理すべきであるかもしくは負ののれんに固有の会計処理を認めるかという整理があるかと思います。
次に可能な選択肢については、先ほど III でご説明させていただきました将来予測される費用・損失や偶発損失の取扱いについては III の方で整理させていただいて、こちらの IV の中ではそれ以外について、その要素は控除した内容についてご説明させていただきたいと思います。
まず、一つ目の選択肢Aですけれども、企業の取得によって購入した非流動資産に負ののれんを比例的に配分し、残額が生じれば繰延利益として計上する方法です。これがどのようなことかと言いますと、図4をみていただけますでしょうか。まず、Aですけれども、貸借対照表がございまして、取得価額と比べて負ののれん――比例配分前という長いところです、ここが比例配分前の負ののれんです。この左側に
 とございますけれども、非流動資産に負ののれんを比例的に配分することによって、非流動資産が少なくなりまして持ち上がるわけです。負ののれん自体も
とございますけれども、非流動資産に負ののれんを比例的に配分することによって、非流動資産が少なくなりまして持ち上がるわけです。負ののれん自体も の比例配分後、非流動資産分だけオフセットされることによって、負ののれんが少なくなるというところをこの図が表してございます。
の比例配分後、非流動資産分だけオフセットされることによって、負ののれんが少なくなるというところをこの図が表してございます。なぜこのような考え方が出てくるかというと、先ほどの発生原因のうち
 に関連します。識別可能資産・負債の公正価値の測定上の不備に起因するわけですから、ここでは資産ですけれども、測定上の不備が起こりそうな資産・負債を調整し、残額については繰り延べて償却していきましょうという考え方です。
に関連します。識別可能資産・負債の公正価値の測定上の不備に起因するわけですから、ここでは資産ですけれども、測定上の不備が起こりそうな資産・負債を調整し、残額については繰り延べて償却していきましょうという考え方です。次にBですね。企業取得後の適切な期間に配分するため繰延利益として負債計上する。これは上の
 、
、 、
、 、
、 いずれにも対応しているといいますか、どちらかというと正ののれんとの対称性を重視し、規則償却するという考え方でございます。
いずれにも対応しているといいますか、どちらかというと正ののれんとの対称性を重視し、規則償却するという考え方でございます。図4でいきますと、少なくなる比例配分前の大きい金額の負ののれんを規則的に償却していくということになるかと思います。
それからC。全額をバーゲンパーチェスとみなし、発生時に利益計上する方法です。この発生原因との関連では一つ目のバーゲンパーチェスと関連するわけですけれども、この場合も負ののれんの総額・比例配分前の金額を発生時に利益計上するということです。
それからDとしまして、AとCの二つのコンビネーションが考えられるかと思います。コンビネーションとはどのようなことかといいますと、まず、バーゲンパーチェスと判断される額については発生時に利益計上する。それから将来予測される費用・損失、偶発損失については先ほど III の検討結果にしたがいまして、例えば負債認識したりするわけです。これはもう先ほどの III の検討結果をそのまま受けるということです。それから
 、
、 の残額は取得した非流動資産に比例的に配分するというような、AとCを折衷的に取る方法でございます。
の残額は取得した非流動資産に比例的に配分するというような、AとCを折衷的に取る方法でございます。「各方法の論拠」ですけれども、どの方法を採用するかは、負ののれんの発生原因、正ののれんとの対称性と結びついています。
Aは負ののれんは、本来生じるはずがないので、識別可能資産の公正価値の測定に不備があると仮定すると、そこで測定を誤る可能性の高い資産から比例的に控除しましょうという考え方です。
二つ目Bは、先ほど四つの選択肢にありますA・Cは正ののれんの処理方法と対称性を欠くこと。またCは基本的に第三者との取引でバーゲンパーチェスは起こり得ないという点で、適切な処理方法とは言えないということで、Bは正ののれんとの対称性を重視するという考え方でございます。
それからCでございます。負ののれんの性格は、時価評価が適切に行われているとすれば、認識不能な債務やバーゲンパーチェスであります。現実的に異常かつ発生の可能性が低いことから、異常利益としての処理が妥当であるとするものです。また、異常利益として処理させることにより、時価評価を適切に行うインセンティブがはたらきます。これは異常利益とすることによって――経常的な利益ではないものですから――時価評価をきちんとやって、将来の償却費を少なくしていく方に会計処理としてはインセンティブがはたらくのではないかということでございます。
最後にDですが、これはAとCの折衷的な方法でA・Cそれぞれの論拠にあてはまるかと思います。
ここで一つの「考え方」ですけれども、正ののれんとの対称性、取得後直ちに利益を計上することの適否を考えると、繰延利益として負債計上する――発生要因に応じて期間配分を行うのが合理的かもしれません。先ほど申し上げたものの中ではBの方法です。
発生時に利益に計上する方法Cは、基本的に第三者との取引でバーゲンパーチェスは起こり得ないこと、正ののれんとの対称性を欠く点で適切ではないかもしれません。また、DはA・Cの折衷的方法ですが、実際の適用が困難であるということも予測されます。
今後の負ののれんに関する要検討事項でございますけれども、一つ目は、商法上の論点が残ります。商法上は負ののれんという概念そのものが存在せず、負ののれんに相当する金額は資本金または資本準備金の増加額に含められ、合併差益として取り扱われることになります。上記AからCのいずれの方法を採用した場合も、現行商法との調整が必要となるのではないかと考えます。
それから二つ目、具体的処理方法ですが、上記B法を採用するとした場合には、正ののれんの会計処理方法との具体的整合性――償却期間ですとか償却方法ですとか、繰延利益の処理――取り崩し時期についての検討が必要となるのではないかと考えます。
これで四つ目の負ののれんが終わりまして、最後に五つ目「無形資産の識別基準と償却期間」についてでございます。
まず、会計処理の検討でございますけれども、可能な選択肢としまして、企業結合時に生じる借方差額のうち、識別可能な無形資産について、法律上の権利ではなくとも、無形資産への振り替えを義務づけるべきであるかについては、以下の三つの対応が考えられます。「振り替えを義務づける」、「容認にとどめる」、「禁止する」というところです。
「考え方」として整理いたしましたのは、無形資産一般の会計処理との整合性を踏まえつつ、差額から無形資産への振替は行わないが、客観的な評価額・時価があれば企業結合会計適用時に認識することを認容するのが合理的かもしれません。
償却期間については、以下にA、Bとして記載しました理由から基本的にはのれんと同様、「20年以内の期間にわたる償却」が、合理的であるとの見解に立つといたしましても、反証可能な場合には20年を超えることを認める余地はあるように思われます。これは法律上の権利について、明らかに20年を超える期間にわたってその権利等が存続し、収益に貢献することが考えられるからであります。
この理由は、のれんと同様の理由から、20年という最長期間を定めることにメリットはあると思いますが、しかし、まったくのれんと同様の20年以内とすると、のれんから他の無形資産を切り出すインセンティブがなくなってしまうということが考えられるかと思います。
ただし、20年を超える期間にわたる償却は、実質的に「非償却」の要素が強くなり、別途その場合には、現行の米国会計基準・SFAS142にあるような減損規定の必要性が生じるかもしれません。
それから二つ目としまして、振替対象となる無形資産の範囲ですが、以下のいずれかに該当する無形資産についてのみ、のれんと区別して資産認識することが適当かもしれません。契約もしくは法律上の権利であるとか既存のビジネスと切り離し、売却、賃貸、交換等が可能なものについてだけということでございます。
以上で、私からのご報告を終わらさせていただきます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。それでは意見の交換はあとに回しまして、まず、ただいまのご報告についてご質問がございましたら、ご発言ください。
中島委員どうぞ。
- ○中島委員
-
私の理解が少し間違っているのかもしれませんけれども、資料3をみていただきますと、普通、のれんといった場合に被結合会社の純資産の時価と、それから買収価額の差額をのれんと言うとすると、この
 の部分がのれんの中に入ってくるということは、そもそもないのではないかという気がしたのですけれども、その点はどうでしょうか。
の部分がのれんの中に入ってくるということは、そもそもないのではないかという気がしたのですけれども、その点はどうでしょうか。 - ○金井委員
-
そのとおりだと思います。この
 から
から に挙げさせていただきましたのは、あくまでのれんとなり得る要素ということでございます。その中で結果としていろいろな理由からのれんの中に含まれてしまう可能性はございますけれども、本来的にのれんとなるのは、この
に挙げさせていただきましたのは、あくまでのれんとなり得る要素ということでございます。その中で結果としていろいろな理由からのれんの中に含まれてしまう可能性はございますけれども、本来的にのれんとなるのは、この 、
、 ではないかという趣旨でございます。
ではないかという趣旨でございます。 - ○中島委員
-
例えば時価が本来なら100のところを80ぐらいにしか評価しなかったとすると、その差額の20はのれんとなる場合があるということですね。
- ○金井委員
-
そうですね。
- ○中島委員
-
わかりました。
- ○斎藤部会長
-
こののれんの要素を
 から
から まで列挙しているのは、これは出典は何ですか。
まで列挙しているのは、これは出典は何ですか。 - ○金井委員
-
これは主として米国基準の公開草案の中に記載されてございます。
- ○斎藤部会長
-
一応それを承継して説明されたということですね。
ほかにご質問ございますか。
それでは、全体という形をとらずに、もう少し全体を細かいパーツに分けて意見交換をしてまいりたいと思います。そうですね、どのように分けてもいいのですけれども、まず2ページから3ページにかけての I の部分ですね。「正ののれんの取扱い」に限定して、まずご意見をうけたまわりたいと思います。
これはご承知のように、現在のアメリカの基準との関係とか、それからIASの基準がおそらくアメリカ基準にコンバージいたしますので、それとの関係もございます。非常に重要な論点になると思いますけれども、特にご発言ないでしょうか。どうぞ長坂委員
- ○長坂委員
-
こののれんの構成要素の中の
 、
、 、
、 というのは理論的にのれんとなるのではありませんということですけれども、結局そうなると会計処理はどうすべきだというところはここに書いてあるのでしょうか。私には理解できなかったのですけれども。
というのは理論的にのれんとなるのではありませんということですけれども、結局そうなると会計処理はどうすべきだというところはここに書いてあるのでしょうか。私には理解できなかったのですけれども。 - ○金井委員
-
書いてはございませんけれども、そもそものれんとなるものではないということは、少し書かせていただきました。「本来は、資産計上されるべきものではない」ということで何らかの形で費用処理なり損失処理が必要ではないかと個人的には考えます。
- ○斎藤部会長
-
今のお答えでよろしゅうございましょうか。
- ○長坂委員
-
多分、理論的にはきっちり挙げようとするとこのようになるのでしょうが、実務的には多分、非常にむずかしいだろうなというイメージはあります。
- ○斎藤部会長
-
これは例えば仮にのれんを計上して、規則的に償却する方法をとった場合でもその埒外になりますので、例えば、もし、のれんとして計上した場合には減損処理が必要でしょうし、それ以外にそもそものれんとして出る前の対処は必要かもしれないというお話ですよね。
ご発言ないでしょうか。どうぞ引頭委員。
- ○引頭委員
-
二つ発言というか質問ですけれども、のれんは規則的に償却していく場合、20年以内ということでこれは別に反対ではないのですが、企業さんが何年で償却するかといった場合、選べるわけですよね。1年でやるところと20年でやるところと、またずいぶん利益も違ってきてしまうのですけれども、そのような期間についてどのように考えているのかという点です。
もう1点は、のれんの償却方法のメリット・デメリットの表でC3の方、いわゆる減損処理、アメリカの会計基準でいう減損レビューのところですけれども、「減損レビューの方法は、確立可能である」というようにこちらの方ではメリットとして書いてあったのですけれども、本当にそうでしょうかという素朴な疑問です。
以上です。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、金井委員。
- ○金井委員
-
まず、20年の期間でございますけれども、任意の期間を選べるというわけでは当然ございませんで、先ほどのれんの本質のところでご説明させていただきましたとおり、事業の超過収益力ですとかシナジー効果というのがその本質でございまして、当然その効果の及ぶ期間を何らかの形で見積もって、その期間にわたる償却というのが原則的な考え方ではないかと思います。
それから二つ目の減損レビューができるかどうかということなのですけれども、ご存じのとおり米国で新しい基準が採用される段階で減損処理を非難する立場の方は「そんなことできるか」と言われていたわけで、かたや最終的にそれを採用したということは、客観的な方法が採用可能だと、その方がいい方法だというのがFASBの最終的な意見だったということです。12月決算の場合はこの事業年度から適用されますので、厳密に実務はどのようになっていくかということはあるかと思うのですけれども、FASBはとりあえずできると言っているわけでございます。
- ○斎藤部会長
-
つまり、この表におけるレビュー方法、減損レビューの方法が確立可能だというのは、差し当たってFASBはそう言っていると、そのようなことになるのですね。
- ○金井委員
-
そうです。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ないでしょうか。万代委員どうぞ。
- ○万代委員
-
今日のご報告でいろいろな考え方ができますというあとで、「考え方」ということで多分報告者の方の考え方をまとめられているのだと思うのですが、それは基本的には期間利益計算の観点からのれんを位置づけようという、そのような観点だとまずとらえてよろしいのでしょうか。それを一つ確認させていただきたいと思います。
- ○金井委員
-
そうですね、規則的に償却という裏側にはやはり収益との対応関係を重視していると申し上げてよいかと思います。
- ○斎藤部会長
-
万代委員に逆におうかがいいたしますが、利益でなければどのような観点を想定してのご質問でしょうか。
- ○万代委員
-
私はアメリカの基準は全然勉強不足でよくわからないのですけれども、あるいはのれんを土地のようなものと同じように考えて、期間利益は重視していても土地と同じあればそれに見合うコストはかからない、だから減損をしたときだけのれんも償却すればいいと、このような考え方なのか、それとも減損処理をすればいいというのはもう少し別の考え方から、もっと言えばあまり期間損益計算を考えないで、そのような考え方にいたっているのか。そのあたりをもしご存じでしたら教えていただきたいというのが趣旨でございます。
- ○斎藤部会長
-
金井委員、先ほどのお答えに追加してご発言することがございますか。
- ○金井委員
-
私が考えますのは減損処理といえども、やはり収益との対応関係はあると思います。といいますのは、事業活動を行っていって、そののれんといわれるものがあって、ある一定期間に価値の減価があった。その減価した部分は収益額に貢献して、その間に減価したということです。規則償却するか減損処理をするかというのと、収益の対応関係というのは違う論点であるような気がするのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
まず、ただいまのお答えでいいかどうかということと、さらに続けてご質問があるかどうかということですが。
- ○万代委員
-
減損処理するということは、減損を認識したところだけに費用を計上するということになるわけですね。そうすると、本来前のも少しずつは減ってきていたんだというように考えれば、あまり期間損益を重視したやり方とは私には思えないということがあります。
それと、もしかするとアメリカはB/S重視といいますか、資産負債アプローチといいますか、そのような観点から減損処理を積極的に考えているのか。そのあたりもしご存じでしたらお教えいただきたいのですが。
- ○金井委員
-
米国基準がツーステップアプローチになっていますので、必ずしもこれから申し上げることがダイレクトに適用されるわけではないと思うのですが、ワンステップ目はレポーティングユニット全体として価値の減価があったかどうかというのがありまして、価値の減価があった場合はのれんの時価を出して、簿価と比較して下がった部分を落としましょうということで、発想は時価評価なわけなんですね。ですからおっしゃられたように、減損といいますと何年かに一度どさっと落とすというイメージがあるのですけれども、非償却資産の原則といいますのはどちらかというと時価評価をしていくというのが前提でございまして、ただ、たまたまステップ1、ステップ2があるもので、必ずしも直接的な時価評価にはなっていないのですけれども、発想は無形資産の償却にしろ、それからのれんの償却にしろ、非償却のものの減損という場合には時価評価と言い換えても私はいいように考えております。
- ○斎藤部会長
-
時価評価といってもダウンサイドだけですから、少し時価評価とは違いますね。
- ○金井委員
-
はい。
- ○万代委員
-
ありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ございますでしょうか。中島委員どうぞ。
- ○中島委員
-
償却方法のメリット・デメリットを比較してある表の中で、自己創設のれんと購入のれんの取扱いは基本的に整合する、あるいは両者の取扱いが異なるというように書いてあります。比較すればそれはそのとおりだと思うのですけれども、整合しなければいけない理由あるいは取扱いが異なってはいけないという理由は何なのでしょうか。
- ○金井委員
-
今日のご報告の中では別にそれをどうこうと申し上げているわけではございません。整合しなければいけないとしたならばこうですね、といいますか、整合した方がいいでしょうという大前提に立ちまして、それをメリット・デメリットという形でまとめさせていただいたというようにご理解をいただいていいかと思います。
- ○中島委員
-
わかりました。
- ○斎藤部会長
-
伊藤委員どうぞ。
- ○伊藤委員
-
少しおうかがいしたいのですが、具体例があまりないので文章ばかりだとわかりにくいのですが、例えば、ハイテク企業であったわけですね。数年前はハイテクブームがあって、そのときには赤字であっても株価はものすごく高くなった。このITバブルも、要するにそのような株価を反映して株式交換をみんなやったわけですね。JDSユニフェーズとかみんなそうですけれどもね。それが今の段階においてはものすごく暴落してしまっているわけですね。そのようなものはこの場合の中の5番目に入るのですか。つまり、過大評価だったというのが結果としてわかるわけですね。
その段階においては、つまり直だという認識のもとに株式交換にこだわられるんですね。このあたりは少し私は専門ではないのでよくわからないのですけれども、どのようにこの
 、
、 、
、 、
、 、
、 というのを考えて――この5番とかいうのはどのように理解するんですかね。つまり、通常の日本の企業では土地があって土地の資産価値があって、それを時価評価してですね、先ほどの期間利益ではないけれどもわれわれも会社を買収するときに将来のその会社の持っている収益力はどのくらいかというのを想定して、10年先を想定してディスカウントキャッシュで計算して、これをやりますけれどもね。それは通常のビジネスであって、ハイテクビジネスというのは、ITというのはまったくそうではないんですね。
というのを考えて――この5番とかいうのはどのように理解するんですかね。つまり、通常の日本の企業では土地があって土地の資産価値があって、それを時価評価してですね、先ほどの期間利益ではないけれどもわれわれも会社を買収するときに将来のその会社の持っている収益力はどのくらいかというのを想定して、10年先を想定してディスカウントキャッシュで計算して、これをやりますけれどもね。それは通常のビジネスであって、ハイテクビジネスというのは、ITというのはまったくそうではないんですね。スタンダードを持っている企業というのは、それがいつまで続いていくというものですからものすごい価値を生んで、今は赤字なのですが、おそらく3年たったら大幅な黒字を生むだろうということで株価はものすごくついたわけですね。そのようなものはどのように理解して整理をしていっているのでしょうかね。少し教えていただきたいのですけれども。
- ○金井委員
-
投資された時点では私はこの
 か
か だと思います。そのとき見込まれていた超過収益力が結果としてなくなってしまったということであって、
だと思います。そのとき見込まれていた超過収益力が結果としてなくなってしまったということであって、 、
、 とは基本的に違うものだと思います。
とは基本的に違うものだと思います。 - ○伊藤委員
-
そうすると、JDSユニフェーズは5兆円ぐらい落としたんですよね。のれんの償却をやったと。その場合は、その償却をやったというのは過大評価ではなくて正常なモデルの償却をしたと、このような考え方ですか。
- ○金井委員
-
多分投資された時点で、その投資会社の方は超過収益力がありますからそれだけ価値があると、それに見合ったリターンがあるのだとお考えになられて投資されたわけですけれども、時間の経過とともに、またマーケット等が変わりまして、結果としてそれが過剰投資になってしまったということで、事後的に価値が減価したということではないでしょうか。
- ○伊藤委員
-
どうもありがとうございました。
- ○斎藤部会長
-
例えばこの間のAOLとタイムワーナーのように、膨大なのれんを計上したけれども1年もしないでやはり株価下がったから一発で落とすということは十分あり得るわけです。しかし買われた時点ではそれは将来の成長なり何なりを見込んだベースだと。
西川委員、ご発言ございますか。
- ○西川委員
-
先ほどの中島委員のお話の中でC2の自己創設のれんと購入のれんの取扱いは異なるという部分ですけれども、これは見方によっては異ならないわけで、自己創設のれんも購入のれんもメンテナンスに要したものは費用になる、そして購入のれんについては買う前の人のした努力部分ですけれども、それは自己創設のれんの方にはないわけで、それは別の処理として償却されるということだから、取扱いが異なるというよりも対象物が少し広いというだけのことで、違うという言い方もできるということだろうと思うのです。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。ほかにご発言はないでしょうか。
よろしゅうございますか。多少私は心配しているのですけれども。つまり、ここでの議論は正論だと思いますけれども、少なくとも今のご時世からすればアメリカと違う。アメリカと違うことをやるというのはかなり勇気のいることでありますので、皆さん方がそれでいいとおっしゃるのなら、非常に意を強くするというだけの話になる。どうぞ、市川委員。
- ○市川委員
-
のれんの償却の関連なのですが、先ほど万代委員から土地と同じような格好で考えたらという話がありましたけれども、私は、会計を最初に理解したときは土地は非償却だと、価値が下がらないから非償却性資産だというように理解していたのですけれども、昨今下落しているわけですね。そうすると、土地というのは、そもそも償却しなくていいという理論的な根拠というのは何なのかというように考えると、要するに土地はなくならないといいますか、そこにあるというようにすると、例えばのれんはなくすこともできる。事業をやめてしまえばすぐできる。ただ、事業を継続するとやれば当面は残る。何というのでしょうか、償却・非償却の切り口の理論的な根拠というのを先生方に少し教えていただきたいなと思っているですけれども。
- ○斎藤部会長
-
ご自分は先生ではないのですか。
- ○市川委員
-
いや、私は実務家ですから。
- ○斎藤部会長
-
どの先生方でも結構ですからどうぞ。
土地というのは、例えば設備のように使うことによって物理的な減耗はないというのがまず第1点ですね。それからのれんとの関係になりますが、のれんというのは将来の超過リターンの期待でありますから、超過リターンが実現した分は当然その部分の減が生じますね。その意味では少し性質が違うというのが差し当たっての私のレスポンスですけれども。
- ○斎藤部会長
-
北村委員どうぞ。
- ○北村委員
-
今のに関連しまして少し疑問に思っていることについて教えていただきたいのですが、のれんが発生するときというのは、まず借方とか貸方に差額として出てきたもののうちですね、例えば、今ののれんの本質のところで7件上がっていますけれども、これは貸借差額を言っているのだと思うんですね――その貸借差額のうち、例えば純資産の時価差額に該当するものは除いて、残りをのれんとして考えるのか。あるいはのれんとして計上するものについては、この減損の計上時におけるように、今、部会長がおっしゃられましたように、将来の超過収益力のようなものをのれんとしてのせるのか。そうすると、取得したときに超過収益力というようになってきますと、そのときにまだ何か残りはわけのわからないものがあるよと。それは費用として計上する余地があるのかどうなのか。何か私はそこのところが、初めの計上のときには何か残りの部分というようにもってきてしまって、規則的な償却はある程度行って、減損などが生じたときには資産の概念なり認識基準なりにマッチしたものだけをもってきて、差額をボンと落としましょうと、そのような処理が考えられているのかなというように思うのですが。そもそも、のれんというものを資産ですよとか、あるいは資産の概念にあてはまって、認識基準にもあてはまるからこそのせるんですよというようにもってくるのか。どうしても残りの部分で説明できないものも資産としてのせるというようにもってくるのか。そこのところを教えていただきたいのです。
- ○金井委員
-
多分のれんの定義にもよるかと思うのですけれども、おっしゃられたとおり結果として差額になるのだと思います。例えばのれんの時価評価をするというときにでも、どうやって出しているかというと、結局差額で、コーポレートバリューからそれ以外の資産・負債の時価を引いて残ったのがのれんの時価ですねと言っているわけですね。ですから、時価評価するときも、それから最初のときも結果として差額になってしまうのではないかと思っております。
- ○斎藤部会長
-
のれんがそれ自体で単独で売買できるマーケットがあるわけではないですから、それはしようがないですよ。
- ○北村委員
-
いや、でも初めは何か差額でもってきているのですが、途中の減損経理の場合はもう少し純粋に考えているのではないかなという気がしたんですね。単なる差額としてもってくるよりももう少し確実なものというのか、そういったようなものが減価の考え方の中にあるのかなと思ったのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
最初は差額のうち、この
 、
、 のコアに該当しない部分については別途に処理をして多分落としていますよね。それから例えば残ったコアの部分について、のれんではない他の無形資産に振り替えられるものがあれば多分振り替えてしまうのですね。それで、残ったものについて多分価値が現在なおかつ存在しているかどうかという減損テストをやっているということだと思うんですね。
のコアに該当しない部分については別途に処理をして多分落としていますよね。それから例えば残ったコアの部分について、のれんではない他の無形資産に振り替えられるものがあれば多分振り替えてしまうのですね。それで、残ったものについて多分価値が現在なおかつ存在しているかどうかという減損テストをやっているということだと思うんですね。 - ○北村委員
-
ということですね。そうすると、はじめに計上するときにも減損テストはもちろん行って計上するということですか。
- ○斎藤部会長
-
いや、最初は減損は確かやっていないですね。
- ○北村委員
-
最初はやっていませんよね、そこなんですよ。
- ○斎藤部会長
-
そこというのはどのような意味ですか。
- ○北村委員
-
最初は減損テストをやりませんよね。とにかく全部振り分けてしまって残りの部分がのれんですねというように計上してしまうことについて、少し疑問があるんですが。
- ○斎藤部会長
-
しかし、ほかに振り替えられなければしようがないですよね。
- ○北村委員
-
そうなんですね。だから、最初に減損テストをやってしまって、出てきた差額については費用計上ですよというと、私の頭ではすごくわかりやすくなってくるんですけれども。
- ○斎藤部会長
-
ただ、最初に減損テストとはどのような意味でしょうか。対価は払っているわけですね。ですから、その時点ではマーケットバリューは認識されているわけですよね。
- ○北村委員
-
だからそれと一致するということですね。そののれんとして計上する大きさは一致するはずであろうと。
- ○斎藤部会長
-
本来一致するはずだと思いますね。
- ○北村委員
-
議論としてはそうだとは思うのですが、いろいろと交渉の過程で。
- ○斎藤部会長
-
複雑な話はわかりませんけれども。
西川委員どうぞ。
- ○西川委員
-
幅があることは確かだと思いますが、高過ぎれば買わないというそれだけのことなのではないかと思いますけれども。
- ○斎藤部会長
-
引頭委員どうぞ。
- ○引頭委員
-
全然違う話ですが、償却の方法ですけれども、個人的な意見なのですが、P/Lをやはり通した形での償却が望ましいと考えています。
私の本当に個人的な意見は、年度の純利益からということでC1、C2、C3あるのですが、C2とC3を一緒に使えないかなという感じなんです。つまり、一応その期間を決めて償却はしていきますよと、ただし、一方で急に減損することがあるわけですよね、先ほどおっしゃったようにマーケットの期待収益率が大きく変化しましたと。そうなると、従前から申し上げているように株価が半分になったり3分の1になったりすることはままあることで、これは完全に計算間違いなり業界の動向が変わってしまったということですので、そのときにはやはり減損はするべきなのだろうと思うのです。
何を心配しているかと言いますと、今アメリカのマーケットでもそうなのですが、ご案内のとおり株価はものすごく下がりますよね。ところがバランスシート、いわゆるBPSというのですか、1株当たり純資産と株価の差というのがどんどん広がっていく傾向に、要するにバランスシートが株価の下落に追いついていかないわけなんですね。これはやはり投資家等にとってはすごくミスリードする材料になってしまう。それをなるたけ時間的な差が、ラグがないような形で処理するにはどうしたらいいかなというと、今申し上げた期間償却とそれから減損の組み合わせというのが何となくいいのかなと、私たちからすれば使いやすいということになるのです。
- ○斎藤部会長
-
金井委員、このC2というのは規則的に期間配分して償却するだけで減損は行わないという意味ではないですね。
- ○金井委員
-
ではないですね。それと例えば今度の新しい米国基準が出る前の米国基準でも40年以内の償却というのがありまして、プラスアルファ、いわゆる減損会計の基準の中でのれんはカバーされていましたので、そこでの一時処理というのは可能であったわけです。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ございますか。
- ○辻前専門官
-
先ほどの北村先生のご発言の関係なのですが、3ページの「今後の要検討事項」の
 のいちばん下のところに、米国の公開草案での工夫ということで書かれているのですけれども、このようなaからdに挙げるようなコアのれん以外の部分が発生したときには、直ちに対応する。その時点ではないにしろ、例えばその年度中に処理してしまうという、処理すべきだというような、例えばそういう考え方に基づいた何か工夫というのですか、アメリカではそのような規定が例としてあったということです。
のいちばん下のところに、米国の公開草案での工夫ということで書かれているのですけれども、このようなaからdに挙げるようなコアのれん以外の部分が発生したときには、直ちに対応する。その時点ではないにしろ、例えばその年度中に処理してしまうという、処理すべきだというような、例えばそういう考え方に基づいた何か工夫というのですか、アメリカではそのような規定が例としてあったということです。 - ○斎藤部会長
-
どうぞ若杉会長。
- ○若杉会長
-
北村委員の提起された問題というのは非常に重要な問題であると思いまして、まだ話がついていないような気がするものですから。これはまったく私的な感覚をお話するだけなのですけれども。
通常、われわれが会計処理をするというような場合には、まず概念規定をしておいて、その概念の趣旨に沿う測定法を選び出してきて処理するものですけれども、のれんにつきましてはまず先に計算的な差額が出てきて、その差額がいったい何に起因するのだろうかということで逆に数字的なものからその本質を探っていく問題だと思うのです。
そのときに例えば資料1の2ページのところで七つのこのような差額の解釈があると。例えば
 、
、 というのは本来の仕方だと思うのです。この
というのは本来の仕方だと思うのです。この 、
、 、
、 、
、 から
から までのところというのは、その差額の性格を何とかしていこうというその努力の成果なんですね。そのような概念的なとらえ方をした場合にそれにもっとも整合的な処理は何か。つまり償却とか減損処理とかそれと関わらせてみてきていると思うのです。
までのところというのは、その差額の性格を何とかしていこうというその努力の成果なんですね。そのような概念的なとらえ方をした場合にそれにもっとも整合的な処理は何か。つまり償却とか減損処理とかそれと関わらせてみてきていると思うのです。ですから、まとめて言えば、まず差額というものが計算的に出てきて、売買するときにはそこまで考えていないと思うんですね。出てきたそれを概念規定して、その概念規定したものに整合的な性格とか費用化とかその他の処理法が考えられていると。そのような形で私は理解しているのですけれども。それが妥当かどうか知りませんが、いかがでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
特に今日は神田先生がいらっしゃらないので、商法の話をするのは非常にむずかしい。私ごときは変な商法の話はしない方がいいのですけれども、商法上の規定では現金を払って取得した場合にはのれんを取得したケースに該当しますし、そうでなくて株式交換、株式の交換で取得した場合ですね。これはのれんを取得したとみられる場合には計上できるわけですね。
ですから、北村先生おっしゃったように取得した時点で本来のれんとみるべきでないものがあるとしたら、その分は最初から資本勘定を増やしてはいけないというのが、多分商法の本来の趣旨だと思うです。ただ、企業会計のこのようなルールでどうなっているかということは、私は正確には申し上げられないという状態です。
ほかにご発言ないですか。安藤委員どうぞ。
- ○安藤委員
-
全然違った観点から、先ほど斎藤部会長が大変大切なことを言われたのですが、要するに世界の潮流と今日のここで議論しているようなことが食い違ってしまったときにどうするか。
私は例えば会計研究学会とか学会レベルであれば、このように理論を詰めてやっていくというのは当然そうだと思うし、また学会であれば多数決を取るわけでもないんですよ。おそらく自然界のルールであれば理論的・学問的に真実かどうかというのはわかるのですが、われわれがやっている会計というのはやはり人間界というか社会のルールの話なんですね。そうすると、議論というのはいつ変わるかもしれないし、また理論レベルの話、いわば学会レベルの話と、あと政治というのか、国際関係レベルの配慮というもの、おそらくこの審議会というのは学会ではないからそのような政治的な、国際環境的な配慮というものも加えて議論すると、これは非常にむずかしい話なんです。
しかし、だれかがこのようなことを言わないと、学会レベルだけで論議を進めてしまうと、外に出たときに「おまえ、違うよ」と言われるのでは少し惨めすぎるから、部会長はわかっておられるのですけれども、やはりだれか一人、例えば山田委員が仮にここにいればおそらくすると思い――彼が来ていないのであえて、これは私の本心であるかどうかは別にして、やはり委員としてだれかこのような発言はする必要があるのではないかと思い、あえて発言しました。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
- ○伊藤委員
-
それに関連して、少し実際の経営をやっている場でいろいろ経験したことを申し上げますと、株式交換というのがITバブルのときにものすごく行われたんです。今は下火になったわけですね。ITのそういった実態のない企業に対する見方が大変厳しい。それから土地に対してもバブルがはげて、先ほど土地についても私も同じような感じをもったのですが、事業についての土地の位置づけはものすごくあると思います。会社の名前を言ってはいけないのですが、例えばイトーヨーカ堂とダイエーとの経営のやり方というのは極めて違う。つまり土地を介してそれをテコにしてやっていくやり方と、要するに事業そのものを――土地とかそういったものを評価しないで借物の上で事業だけやっていく経営のやり方の方が、今やより評価されている時代にきているということになってきています。
そのような点ではこののれんの考え方についても私はよくさぼっていて恐縮なのですけれども、アメリカがこのようなのれんの償却についての考え方を変えた。そのあたりの経営の実態とどう結びついているか。これはもう政治問題だと解釈するのか、経営の実態とこのような会計の理論というのは相当やはり相関関係があるのかどうかについても、これはこの場で今すぐではなくてもいいですけれども、よく検討する必要があるのではないかというように感じますけれどもね。
以上です。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。こののれんの問題について直接のきっかけは既にご承知のとおりであって、FASBが持分プーリングを廃止してパーチェスに一本化しようとしたときに議会によって止められた。その状況を打開するために政治的な妥協として、パーチェス一本化を進めさせてもらう代わりにのれんの償却については勘弁してもらう、それはやらなくていいと。そのような一種の取引をしたというのが政治的な状況ではあります。ただ、おっしゃられたように、それでは政治的な取引だから何でもでたらめなことができるかというと、やはりそれは周囲を説得しなければいけませんから、何か理屈があったのかもしれない。それは十分慎重に考える必要が私はあると思いますね。
FASBの理屈は投資家はのれんの償却などというのは無視している。それを除いた利益をみているからあんなものやらなくていいと。そのようなロジックなんですね。ところが、最近のアメリカで、のれんの償却を考慮しない利益とのれんの償却を考慮した利益の情報開示を比較し、実証した結果はまったく逆で、必ずしもFASBの言うことはサポートはされていないという話も聞いています。ですから、そのような問題は本当はきちんと検討していかなければいけないのだろうと思いますね。
- ○辻前専門官
-
今は特に準備はしていないのですが、昨年の部会で参考人として渡辺さんというM&Aの実務をされている方が来られて、そのときに部会でもご発言があったのですけれども、例えば米国の実務の場合は、事業は買いはするけれどもそれで成長すれば、また外部に売ってそれで売却収入を得る、そのようなビジネスモデルもある。そのような中においては、例えば短期間、短期間というか10年以内というような期間で、買ってまた売るというときを考えると、その間ののれんの償却、最初ののれんというのは回収してしまう、当然そういう前提に立っているので、その間ののれんの償却というのは実務家としてみたときはどうなのだろうかと。実務家としてみる限りはのれんを償却しないというのは、実態には合っているのではないかというような、そのようなご発言がありましたのを思い出しましたので、参考までに申し上げました。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言ありませんでしょうか。
これは大変むずかしくて安藤委員が言ってくださったので、私は非常に気が楽になったのですけれども、一方でのれんの非償却というアメリカにコンバージするスタイルの意味あるいは適否というものを検討するということは非常に大事なわけであります。先ほども少し申しましたように、もしまったく理屈が通らなければなかなか実際に情報開示する方々を説得できないわけですね。そこが大変むずかしいところで、アメリカのFASBの基準もIASBの会議等では理屈の上ではもうほとんどだめですね。完全にアメリカは敗北でだれもそんなものは評価していない。恐らく完全にアメリカは四面楚歌だと思います。
ただ、実際に結果はどうなるかというとアメリカにコンバージしている。アメリカの言うとおりなんですね。だからそこがなかなかむずかしいところで、よく私も申しますけれども、グローバライゼーションというのはたとえ変なやつでもいちばん強いやつに合わせるということなのです。これは大変むずかしい選択をわれわれはしなければいけないという局面になると思うんですね。ただ、われわれもゆっくり国際的な状況の模様眺めでいつまでも決めないというわけにいきませんので、どこかで決断をしなければいけない。その決断に結びつくようなご議論をぜひお願いしたいということです。
特にここだけにこだわっていますと、なかなか先へ進みませんので、次に4ページの II の「研究開発用資産」の部分に関連してご発言があればうけたまわりたいと思うのです。
ここはよろしゅうございますか。そこはあまりないといたしますと、次の4ページから6ページにかけて III の「予想される将来の損失に対する引当金」の部分ですが、この部分に関連してご発言はありませんでしょうか。
- ○若杉会長
-
例えば4ページのローマ数字の III の(1)発生原因の検討、
 「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準」という使い方をされていますけれども、またその次の
「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準」という使い方をされていますけれども、またその次の のところで「条件付負債」とありますけれども、この負債というのは債務とはまた別の概念としての負債ですか。つまり、債務というのが法律上の概念であり、負債は会計上の概念とわれわれは認識しているのですけれども、あまり使われない言葉づかいなものですから。
のところで「条件付負債」とありますけれども、この負債というのは債務とはまた別の概念としての負債ですか。つまり、債務というのが法律上の概念であり、負債は会計上の概念とわれわれは認識しているのですけれども、あまり使われない言葉づかいなものですから。 - ○金井委員
-
そのような意味では債務と、それから私は引当金などもイメージしておりましたので、そのような意味で債務というよりは広い概念ではないかと思いました。
- ○若杉会長
-
例えば条件付負債というような言葉もよく使われますか。
- ○金井委員
-
そのような意味ではそこまで深く考えてございませんでした。
- ○若杉会長
-
はい、わかりました。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はないでしょうか。
- ○長坂委員
-
すみません。少し戻ってしまいますけれども、研究開発用資産のところなのですけれども、この研究開発への対価に相当するものといった場合に、具体的に買収の場合にどのようにそこに相当する金額は算定されるのか。少しイメージがわかないのですが。
- ○金井委員
-
ここで考えておりますのは研究開発用であろうとそれ以外の一般用の資産であろうと、そもそも資産としての認識基準があると思うのですけれども、その認識基準にしたがって、ただ研究開発に使われる資産等につきましては、研究開発等に係る会計基準がございますので、その認識基準の問題とそれから研究開発に係る会計基準とどう整合性をとっていくかということが論点になるかと思いまして、ということでございます。
- ○長坂委員
-
これは有形な固定資産なのでしょうか。それとも研究開発の結果できた権利とか、そういった無形のものをイメージしているのか。
- ○金井委員
-
ここに書いてありますとおり、有形・無形両方を意図してございます。
- ○長坂委員
-
これは資産としての認識される可能性が高いのですか。それとも、買収のときに一括で償却される可能性が高いと。
- ○金井委員
-
ここで意図しておりますのは資産認識基準を満たす限りにおいては資産として認識しまして、そのあと、研究開発等に係る会計基準にしたがって処理すべきものは処理するという流れを想定してございます。ですから、どちらかといいますと、Aの方は最初から本来研究用に使われるような資産は費用処理されるべきなのですから、最初から費用処理すべきなのではないかという議論もあるかと。そうしますと、結果としてのれんの額がふくらんで、より長期にわたって例えば償却されるとか非償却になるとかということになるわけですね。
- ○長坂委員
-
以前に、アメリカの企業は最初の買収のときに、研究開発のものとして一度に費用処理しているケースが結構あるというような話は何か聞いたことがあるのですけれども。
- ○金井委員
-
その処理自体は結果としてこの流れにあるわけです。ですから、資産として一回計上しませんと、のれんになってしまって長期にわたる償却になってしまうわけです。それを資産として計上することによって、その資産をどう取り扱うか。ここに書きましたように日米の基準が非常に近くなっておりますので、研究開発等に係る会計基準にしたがうと、今おっしゃられたとおり一括処理になるという扱いになるかと思います。
- ○北村委員
-
引当金のところですけれども、取得対価を決定するときに、その算出に対する引当金が考慮されているときには計上していいような考え方が書かれていると思うのですけれども、それはどうしてそのような考えが出てくるのですか。というのは、それが考慮されているということは取得対価が小さいということですよね。その小さい部分がなぜ小さくなったのかというとことは、この引当金を認めましたと、しかし、その引当金というのは、通常の今の会計でいけば引当金の概念には入らなくても、考慮されていればそれはいいでしょう。そこはどうしてなのでしょうか。
- ○金井委員
-
私が考えましたのは、例えば将来予測される費用とか損失については、2年後、3年後に支出される可能性が高く、支出が見込まれるから交渉の過程の中である意味で前受金のような形でもらわれたわけですね。ですから、2年後、3年後に、それが引当金になるか負債になるか、前受金になるかは別としまして、実際に支出されたときにそれをリバースすることによって、実際の支出とそれから戻しがオフセットされて、うまく会計処理されるということになるのではないかと思いました。ただ、それがいわゆる負債の計上基準を満たしているかどうかということに関しては、少し問題が存在するのではないかということでございます。
- ○北村委員
-
ただ、確実性はないわけですよね。今の引当金の概念にはあてはまっていないわけですから。それは確実性がないということはそうなるかもしれないし、ならないかもしれないというのが今の現状であるということですよね。
- ○金井委員
-
まさにおっしゃられるとおりです。ですから、確実性はないのですけれども、交渉等の過程で対価がもらわれたわけですね。それが結局判明して実際に使われないということになれば、当然それを戻して利益計上するということになるでしょうし、使われれば使われた期に支出と対応させられるということで、そこがまさに論点になるところかと思います。
- ○斎藤部会長
-
確実ということは、先ほど金井委員がおっしゃられたように意図があるかどうか。つまり、リストラならリストラをするという意思にも依存しますけれども、そのような点で負債として首を傾げるという意見があればそれはもちろんそうですし、逆にリストラならリストラの計画を見込んで取得の対価が決まっているのであれば、その分を繰り延べて、将来リストラに要するコストと利益をマッチさせるという方法もあるのではないかと、そのような話です。
- ○北村委員
-
この合併とかした場合には会計基準がそこのところは違っていいと、例えば時価評価をやるといっても、買う方はやっていないわけですが、そこで入れてきますよね。そうすると、そのように入れてくるものが何かといったときに、この引当金というようなものもそれを入れてくるとか。だからそれはどこまで許容されるのかということだと思うんですね。そのようなことはあとではっきりされるのでしょうか。例えばこれとこれとこれというようなものが、そのときには認められますよというようなこと、例えば繰延利益でしたか、それも出てきたと思うのですけれども、繰延利益という概念も今どうなのかというのは一つ問題になっている部分ではないかなというように思いまして、それもここではもってくるんですよというような形を取るという、そこのところのはっきりとした、入れてくるなら入れてくるだけの根拠があるかどうかというところ。
- ○西川委員
-
大体 I 、 II のところは金井委員と考え方というところは一致していたので、あまり言うこともなかったのですけれども、この III についてもあとで議論するところになろうかと思うので、今言わなくてもいいのかと思うのですが、確かにおっしゃるようにリストラ引当金ということであれば非常に限定的にできるのだろうと思うのです。しかし、「それに限定せず」ということを示されてしまうと、例えば本当に将来売却するまでの間の事業損失も入れるというような感じになってしまうと、将来損失を引き当てるというのは普通の会計ではないですから、これは少しむずかしいのかなという、感想ですけれども、そのような感じがしております。
- ○斎藤部会長
-
北村委員と西川委員のご発言に対して一括して金井委員からご回答をお願いします。
- ○金井委員
-
まさに今日その辺をご議論していただきたいということだけでございます。私としては、ここで今日一貫して申し上げさせていただきましたように、一つの考え方としてはその発生の可能性が取得対価の中に反映されているという基準を設けまして、これで整理するとこのような形になったということでございますけれども、各委員の皆さま方がおっしゃられたように、それぞれの考え方に対するメリット、デメリットが当然あるわけでございまして、その辺のご議論を逆におうかがいしたいということでございます。
- ○斎藤部会長
-
先ほどの北村委員のご発言については、基本的にこれはパーチェーズの話をしておりますので、要するに通常のゴーイング・コンサーンが例えば生きている会社を買ってくるという場合の処理と、それから同じ事業を新たにスタートさせるために、それらの資産等々に投資をするというケースとを整合的に扱いたいと、そのような発想ですよね。ですから、取得した資産を時価で評価するのは、もし新たに設備投資をすれば時価で買ってくるわけですから、それにそろえるということでありますし、多分リストラ引当金のような先ほど出てきた話もそのようなリストラを前提とすることで、その含みで資産を安く買っているというのであれば、その分を新規の投資の会計処理の一環として取り込んだ。そのようなフィロソフィーではなかったかと思うのです。
ただ、西川委員が言われましたように、今でいうリストラ引当金のようなものすら、アメリカでは大問題になっているわけでありますけれども、それをさらに拡張した概念になってくると、だんだん危なくなってくるということは、もう指摘されるとおりでありまして、その点についてもぜひここでご議論をいただきたいと思っております。
- ○北村委員
-
新規の事業を始めるということと合併とを同じように考える。これは私はいいと思うのです。ただ、その新規にやるときでしたら今認められていないものというのは、やはり認められないのではないかなと思うんですね。ですから、時価評価のことは私はよく了解しているのです。
ただ、その概念に関わってくる部分で新たな何かがポンと認められるというのは、やはり問題なのかなと。だからリストラ引当金でしたら、引当金の中にそのような認められるものがあるのかないのかというようなものも少し考えてみる必要があるのかなというように思ったのです。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。小宮山委員どうぞ。
- ○小宮山委員
-
これを引当金として例えば認められないものとか、負債として認められないものを挙げてしまうということで議論すると、何かわけのわからない話なのですけれども、基本的にあるものを買ったときに、それをどう利用するということはそのときにまた別な意思決定が行われるはずなのです。その部分について反映するのが、この引当金なり負債なりということではないかなというように思っているのですけれども。
そうすると、今まで認められた、認められないという整合性はそこでブツと切れるのです。そのような性格のものの話はここはしているのではないかなと思っているのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
いかがですか。特にご発言ありますか。
- ○北村委員
-
そのように考えていきますと、新しいものが出てくるという可能性はありますよね。そこをどこまでなら許すという、そこが今度必要になりますね。すみません、わからないのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
一応課題としてうけたまわったということで、ほかにご発言ございませんでしょうか。
そうしますと、その次に6ページから7ページにかけての IV でありますが、ネガティブ・グッドウィルですね。負ののれんの取扱いに関連してご発言ございますでしょうか。
今、議論しました引当金の問題と部分的にオーバーラップしていますけれども。特にそこはないですか。
最後になりますが、7ページから8ページにかけての V であります。無形資産の識別基準と償却期間に関連してご意見があればうけたまわりたいと思います。
黒川委員どうぞ。
- ○黒川委員
-
遅れてまいりまして、とんちんかんな質問をするかもしれませんが、先の IV でもいいですか。負ののれんで、もしかしてご説明があったのかもしれないのですけれども、少し確認で、契約時点、契約というか対価を双方で交渉している時点と、実際に会計測定上、資本の増加と資産負債の測定時点との期間のずれということについてご説明があったのかないのかということに関連してお聞きしたかったわけです。
仮に、交渉時点において我が方の株式の交換だと考えて、我が方・買う方の株価が比較的高くて発行株式数が少なくて、交渉が妥結した。ところが、測定時点が仮にずれていて、測定時点になって株価が下がりますとその分だけ株式数は少なかったわけですから、資本の増加が少なかった。そうすると負ののれんというか、差額として負ののれんもどきなものが出てくる可能性がありますよね。その場合にどれに相当するのか。そのようなものはこの発生原因の検討のどれに相当していたのか、お聞きしたかったわけです。適切な質問になったのかどうかなんですけれども。
- ○斎藤部会長
-
金井委員からご発言ありますか。
- ○金井委員
-
そのような意味では今思いつく限りではこの中にはあてはまらないような気がいたします。
- ○斎藤部会長
-
おそらく金井委員がこれを作成される段階の暗黙の前提は、契約時点で対価を測定するという発想だったと思うんですね。FASBがまた態度を変えましたので少しやっかいなのですけれども。今おっしゃられたように約定日から実際の合併、取得時点まで間をおいて対価を測定することになりますと、おっしゃられた論点は新しく出てまいります。
もう部分的に区切って議論する意味がありません。時間もだいぶ残り少なくなってまいりましたので、全体をとおしてご自由にご発言いただきたいと思います。
松岡委員どうぞ。
- ○松岡委員
-
非常に今日の議論はむずかしい問題で、おそらくパーチェス法と持分プーリング法との関係ですとか、アメリカの議論の経緯から先ほど来お話のありましたように、のれんの会計処理は今の二つの方法の選択、あるいは無形資産の会計処理をどの程度カバーするかというように、すべて密接に関わっているかと思います。
私は必ずしもパーチェス法を採用することが必ずしも不利な面が多いとは言い切れないのかなというような感じもございまして、おそらく産業界の一部の方にはパーチェス法で処理したいという方も、もしかしたらいらっしゃるのかもしれないというように考えています。
特に、今思いついたのは、アメリカの方は税法ですけれども確定決算主義をとっておりませんので、課税取引でのれんが出た場合は確か15年間で損金算入が認められるような記憶をしております。日本の場合で適格企業再編に該当しない場合ですね。のれんも税務上、損金算入として認められる余地は当然あると思うのですが、仮にのれんの償却をしないというような会計ルールができますと、確定決算主義のもとでは日本の場合、損金算入できないというようなことも生じ兼ねないのではないかと思いますし、いつか損金として認められるとしたならば、金利部分の影響はあるかもしれませんが本当に利益体質のいい会社を買収して、翌年度から利益が出るのであればその時点で税金を払って、償却費が上がっても翌年度以降損金として、簿価で引き継ぐよりは多く損金算入できるわけですから、そのような選択肢を選択される、したいというような企業の方もいらっしゃるのではないかなと思うのですが。
とりとめのない話になってしまいましたが、アメリカでは議会を巻き込んで産業界の方から相当要望なり、経済実態ですとか経営の実態を反映した相当な希望ですとか、そのようなことがあったように記憶しているのですが、そのような議論はあるいはご意見もこういったような場でもう少し必要ではないかと。そういったものがなければ意思決定をするトリガーにはなかなかなり得ない。むずかしいような感じを受けましたので、そういったような観点がもう少しほしいのかなというように感じたことだけ言わせていただきます。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。意思決定というのはその会計基準の選択をめぐる意思決定ですね。
- ○松岡委員
-
はい、そうです。
- ○斎藤部会長
-
今のお話の中で税制上のインセンティブ、つまり損金算入のインセンティブと開示用のインセンティブは通常ベクトルの方向は逆向きですので、少しやっかいですね。
ほかにご発言ないでしょうか。特に今のお話の中でプーリングとの関連も出てまいりまして、このあと今度はそのプーリングの問題がひかえておりますので、それを視野に入れてどうか積極的にご発言いただきたいと思います。
特にないでしょうか。大変やっかいなのは例えば先ほどののれんの償却問題に戻りますと、アメリカの基準は償却を禁止するわけです。仮にその減損処理に一本化するということになりますと、当然現在、審議会の固定資産部会で検討されている減損の中ののれんの取扱いではカバーできません。新たに企業結合との関係でのれんの減損のルールを検討しなければいけないという問題であります。それが当然一部会の問題として出てくる可能性もあるわけですね。それは考えただけで頭が痛くなるようなやっかいな問題でありまして、少し悩ましいところです。
- ○黒川委員
-
先ほど引頭委員がおっしゃったところですけれども、償却をしてそれで、なおかつ減損というルールをしたときに国際的にみて、臨時償却のような形で減損もやっていますよと、アドホックとは言わないけれども、ままありますよと、でも、償却は粛々としてやっていますよと、そのような、ある意味ではより減損だけよりも産業界にとっては厳しいかもしれないけれども、会計的にみればより保守的なというか慎重な会計処理をする。このような基準をわが国でとった場合にどれだけ国際的に批判をされるのだろうか。あるいはむしろあっぱれであると、このように言われるのであろうか。このようなことはあり得ると思うのです。その辺の見通しも考えておく必要があるのだろうと思うのですけれどもいかがでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
まったくおっしゃるとおりだと思いますね。現時点で、私はその見通しがわかりません。ただ、償却もし、かつ減損もやるということになりますと、非常によく聞こえますが、規則的に償却をしたうえで適用する減損のルールは、アメリカのように償却をやめて適用する減損のルールとおのずから違ってまいりますので、どちらが厳しくなるかというのはやってみなければわからないということがございます。
西川委員どうぞ。
- ○西川委員
-
国際的にみられる部分というのはやはり持分プーリングを禁止するかどうかのセットでおそらくみられると思うので、この部分だけであっぱれというような話にはならないのではないか、そのような感じがしていますけれども。
- ○斎藤部会長
-
当然そのとおりですね。ただ、恐らく黒川委員の意図を少し拡張して言えば、仮定の話として持分プーリングは日本で完全には全滅しなかった、どこかに残ったというときに、プーリングもどこかで残っていて、かつのれんの減損のルールはアメリカにちゃっかり便乗しているというようなものに比べれば、もしかしたらましかもしれない。そのようなご趣旨にも聞こえますね。
ほかにご発言ないでしょうか。
- ○多賀谷課長補佐
-
レベルの低い質問で申しわけないのですが、例えば今日の資料3の絵がわかりやすいので、この絵で
 、
、 、
、 という部分がもちろん考え得るのですけれども、現実に会計だけの問題ではないのですけれども、例えばわが国の商法の考え方ですと、まず純資産額を出してそれを超える資本増加はないということですから、買収価格はいくらであろうと純資産額を超えることは恐らく違法になるのだとしますと、
という部分がもちろん考え得るのですけれども、現実に会計だけの問題ではないのですけれども、例えばわが国の商法の考え方ですと、まず純資産額を出してそれを超える資本増加はないということですから、買収価格はいくらであろうと純資産額を超えることは恐らく違法になるのだとしますと、 と
と は考え方としては合っているんです。現実にはそこもつまり何らかの価値がその時点はあるものとしてとらえるというように整理をしておかないと、この
は考え方としては合っているんです。現実にはそこもつまり何らかの価値がその時点はあるものとしてとらえるというように整理をしておかないと、この 、
、 、
、 は考え方としてはあり得るのですが、現実にはあってはいけないものではないのかなというような気がするのですけれども、実際にルールをつくる際に
は考え方としてはあり得るのですが、現実にはあってはいけないものではないのかなというような気がするのですけれども、実際にルールをつくる際に があった場合どうするということは書けないのではないかなというような気がするので、それは私の個人的な感覚でございます。
があった場合どうするということは書けないのではないかなというような気がするので、それは私の個人的な感覚でございます。 - ○斎藤部会長
-
おっしゃるとおりなんですけれどもね。ただ、商法はおっしゃるように取得した純資産の評価が優先するわけですね。対価というのはあとから決まるわけですよね。では、その取得した純資産の中にのれんも取得しているというときに、のれんはどう評価するかということを商法の専門家に聞いたら、やはり差額なんですよ。その意味では
 や
や が入ってくる可能性というのは結果的には否定できない。ただ、あってはいけないと思っているという、そのようなことだと思うんですね。
が入ってくる可能性というのは結果的には否定できない。ただ、あってはいけないと思っているという、そのようなことだと思うんですね。ほかにご発言ないでしょうか。
それでは、何度も申しておりますようにだんだん議論が大詰めになってまいりますので、どこかでわれわれとしては基準を設定するという意味のディシジョンをしなければいけないわけであります。先ほど来、出ていますように国際的な、特にアメリカ基準やIAS基準とのコンバージェンスをどう考えるかという問題と、それからやはり日本が単にアメリカやIASの基準をそっくりそのまま導入するというわけではなくて、日本の基準を設定する議論をここでしているという観点からみたときに、やはりあまり理屈の通らない議論をするわけにもいかない。その辺のバランスをこれから、ある種の実質判断をしなければいけないわけです。そのようなことが近々の検討課題であるということをぜひお含みいただいて、ご議論を進めていただきたいと思います。
大体時間がまいりましたので、本日の部会はこれで終了させていただきます。次回の部会は3月29日金曜日の16時からを予定いたしておりますのでよろしくお願いいたします。詳細につきましては改めて事務局からご連絡いたします。
本日はお忙しいところをまことにありがとうございました。これにて散会とさせていただきます。

 検索
検索