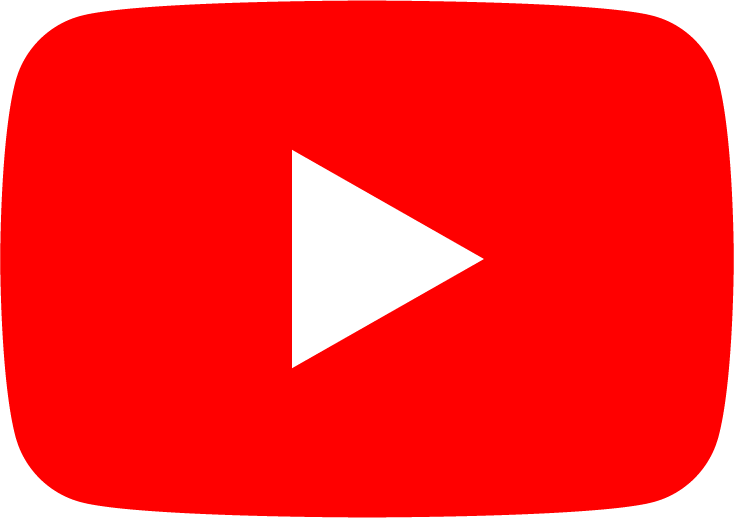- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「第一部会」
- 企業会計審議会第18回第一部…
平成14年4月22日
金融庁
企業会計審議会第18回第一部会議事録について
企業会計審議会第18回第一部会(平成14年3月29日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第18回第一部会議事録
日時:平成14年3月29日(金)午後4時00分~午後5時54分
場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室
- ○斎藤部会長
-
それでは、定刻になりましたので、これより第18回第一部会を開催させていただきます。委員の皆様には、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、前回の審議に関連いたしまして、金井委員から補足的なご報告をいただきます。その後、山田委員からIASBの企業結合プロジェクトの状況についてご報告をいただいた後に、意見交換をお願いする予定にしております。
それでは、まず、金井委員からご報告をお願いいたします。
- ○金井委員
-
それでは、お手元の「企業結合に関する米国基準・IASの比較」という資料をごらんいただけますでしょうか。本日ご用意いたしましたのは、前回の部会でご説明申し上げました、「正ののれんの取扱い」、「研究開発用資産」、「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」、「十分な信頼性をもって測定することができない偶発事象に対する費用または損失」、「負ののれんの取扱い」、「無形資産の識別基準」に関しまして、米国の新基準、すなわちSFAS 141と142、その基になりました1999年9月7日に公表されました公開草案、現行の国際会計基準といたしましてIAS22号、および現在審議中のIAS22号の改訂案につきまして、簡単な比較表を作成してまいりました。IAS22号の改訂案につきましては、最近また進展がございましたでしょうし、本日は山田委員からご説明があるということですので、不足している事項につきましては山田委員にご説明をお願いしたいと思います。
それでは、1ページ目の「正ののれんの取扱い」でございます。
まず、米国の新基準。表左側から参ります。通常は償却せず、減損処理をするということで、2段階の減損テストとなっております。第1ステップは、のれんを含むレポーティングユニット――通常、セグメントよりも一つ下の概念と言われておりますけれども――の帳簿価額と公正価値を比較しまして、帳簿価額の方が大きい場合に第2ステップに行きます。第2ステップでは、のれんの帳簿価額と推定公正価値を比較しまして、この差額が減損額として認識されます。
二つ目に、米国基準の公開草案ですが、公開草案の段階では、20年を超えない期間で規則的に期間配分して償却すると定められていました。また、以下の一つ以上に該当する事象が存在する場合には、取得日後2年以内にのれんの回収可能性を検討する必要があり、多額のプレミアムの支払い、多額ののれんの計上、取得時にオークションまたは入札プロセスが存在した場合、主に株式による対価の支払いが行われた場合、という内容が列挙されておりました。
次に、現行の国際会計基準でございますけれども、原則は、規則的に期間配分して償却するということで、20年が反証可能な上限となっております。反証可能な場合には、そののれんを最善の見積り期間(20年を超える期間)にわたって償却し、この場合には、のれんが減損している兆候がない場合であっても、IAS36「資産の減損」に従い、当該のれんの回収可能額を少なくとも各決算期ごとに見積もることとなっています。
他方、現在進行中の改訂案では、米国基準と同様、通常は償却せず、減損処理の要否を判断するための2段階の減損テストを行うこととなっております。第1ステップとしまして、現金生成単位、すなわち、現金が生成される最小の単位の純資産の簿価とその回収可能額を比較しまして、純資産の簿価が大きい場合に第2ステップに行きます。米国基準と同様に第2ステップでは、のれんの帳簿価額と推定公正価値の差額を減損額として認識するということでございます。
次に、ページをめくっていただきまして、「研究開発用資産」の取扱いです。
まず米国新基準ですけれども、これは右側に「同左」と書いてありますように、公開草案とは変わってございません。企業取得の原価は、研究開発の対価に相当するもの、すなわち、有形・無形の両方を含んだ研究開発活動の結果生じた識別可能資産、及び結合存続会社の研究開発活動に用いる予定の識別可能資産は、購入対価の一部分を構成するということです。前回ご説明申し上げたとおり、購入対価の一部分を構成しますと、のれんには含まれないこととなります。そのうち特定の研究開発活動以外の代替的用途のあるものは資産に計上し、特定の研究開発活動以外に利用できないものは取得時の費用として計上されます。公開草案も同様です。
現行のIAS22号に関しましては、買収価額の配分と研究開発費の処理との関係については言及されておりません。したがって、「無形資産」の会計処理基準によることとなり、取得日時点で存在する被取得企業の識別可能資産のうち、一定の要件を満たす開発費については資産として計上されることとなると思います。
現在の改訂案ですけれども、取得日時点で存在する被取得企業の無形資産のうち、識別可能、信頼性をもって測定可能、かつ、関連する将来の経済的利益が取得者に帰属するという条件を満たす場合には、仕掛研究開発費についても資産計上するというようになっておりまして、逆にこれを満たさない場合にはのれんとして処理されるということになります。
続いて、下に参りまして、 III -1です。「将来予測される費用・損失であって、負債の認識基準を満たさないもの」の取扱いです。
米国新基準ですが、この扱いは具体的には新基準の中には含まれておりませんで、別の基準が存在しております。その基準自体は変わっておりませんので、公開草案の時点と同様というようにご理解ください。事業廃止のためのコスト、被取得企業の従業員の解雇・再配置のためのコストについて、負債として認識するための条件が別途定められております。
IAS22号につきましては、取得企業は所定の条件をすべて満たす場合は、その場合に限り、取得時点では被取得企業の負債ではない引当金を、取得日時点において認識することが可能になります。この条件ですけれども、(a)、(b)、(c)と三つございまして、(a)事業活動の廃止または縮小の計画であり、その大綱を取得日時点で決定していた、(b)当該計画が実行される明確な期待を関係者に抱かせている、(c)当該計画の大綱に基づいて詳細な計画を作成しているという場合です。
次に改訂案ですが、買収に伴うリストラ引当金の計上に特に例外規定は設けず、計上の要否はIAS37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」に基づき判断することとなります。ということで、例外は設けないというのが現在の改訂案でございます。
続きまして、ページをめくっていただきまして、 III -2「十分な信頼性をもって測定することができない偶発事象に対する費用または損失」です。
これにつきましては、米国新基準の中で新たに加わりまして、配分期間内に偶発事象の時価が算定可能な場合には、公正価値で貸借対照表上負債として計上するとなってございます。公開草案のときには、これに関する記載はございませんでした。
次に、IAS22号です。負債の認識基準を満たさない偶発事象に対する費用または損失は計上すべきではないという立場をとっておりましたけれども、現在の改訂案では、いかなる買収――これは正ののれんが発生する場合、負ののれんが発生する場合にかかわらずということです――であっても、偶発債務は信頼性をもって測定可能な限り公正価値で貸借対照表上負債として計上するというように手が加えられております。
続きまして4番目、「負ののれんの取扱い」です。
米国新基準では、負ののれんは、以下の資産を除くすべての取得資産に割当てられた金額から比例減額するということになっています。除かれる資産、すなわち、減額されない資産が(a)~(e)です。これらは、持分法が適用される投資以外の金融資産、売却処分予定資産、繰延税金資産、年金又はその他の退職後給付制度に係る前払資産及びその他の流動資産です。次に、これらの資産に割当てるべき金額がゼロになっても超過額が残っている場合には、その残りの超過額を異常利益として認識するということになります。
公開草案の段階ですけれども、これは微妙に違っておりまして、こちらの方の規定の仕方は、「負ののれんは以下の資産の順に配分し」ということで、先ほどは「除く」でしたけれども、こちらの規定の仕方は引く項目を列挙してございます。その残額は異常利益として認識することになっておりました。最初に除くのは市場性のない無形資産、それから2番目として、償却資産及び市場性のある無形資産となっておりました。
続きまして、IAS22号です。まず第1に、取得日現在の識別可能負債ではないが、取得企業の取得計画において識別され、かつ信頼性をもって測定できる将来の損失や費用の予測に関連するものである場合には、負ののれんのうちその部分は、その将来の損失や費用が認識される時点で、利益として認識します。ある意味で引当金等の形で繰り延べられます。それ以外の部分、すなわち、負債として、もしくは引当金として繰り延べられた部分以外の金額については、第2で規定してございます。第1以外の場合には、負ののれんは、次のように損益計算書において利益として認識されなければなりません。(a)取得した識別可能な非貨幣性資産の公正価値を超えない部分の負ののれんは、その取得した識別可能な償却性資産の残存加重平均耐用年数にわたって規則的な方法で利益として認識されます。(b)取得した識別可能な非貨幣性資産の公正価値を超える部分の負ののれんは、利益として直ちに認識されることになっています。
次に、現在の改訂案です。改訂案では、負ののれんが発生する場合には、識別可能純資産の識別・測定を再度実施します。測定後も、負ののれんが発生する場合には、即時利益として計上することとなります。
最後に5番目の「無形資産の識別基準」についてです。新米国基準では、
 契約もしくは法律上の権利であるか、もしくは、
契約もしくは法律上の権利であるか、もしくは、 分離可能、すなわち、既存のビジネスと切り離し、売却、賃貸、交換等が可能なものについて公正価値で評価するとなっております。
分離可能、すなわち、既存のビジネスと切り離し、売却、賃貸、交換等が可能なものについて公正価値で評価するとなっております。公開草案の段階におきましては、信頼性をもって測定可能な識別可能無形資産は公正価値で評価するとなっておりました。
現行のIAS22号では、資産に起因する将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、かつ、資産の取得原価を信頼性をもって測定することができる場合に、公正価値で評価するとなってございましたけれども、改訂案では、
 契約もしくは法律上の権利であるか、
契約もしくは法律上の権利であるか、 事業から分離可能であり、かつ、信頼性をもって測定可能なものを公正価値で評価するというように手を加えております。このIASの改訂案と米国の新基準を比べますと、文言の上では、「信頼性をもって測定可能」という文言がIASの方は米国基準にプラスアルファされてございます。
事業から分離可能であり、かつ、信頼性をもって測定可能なものを公正価値で評価するというように手を加えております。このIASの改訂案と米国の新基準を比べますと、文言の上では、「信頼性をもって測定可能」という文言がIASの方は米国基準にプラスアルファされてございます。私の方からは以上でございます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
前回、パーチェスを適用した場合の問題点について金井委員からご説明いただいたわけですが、ただいまのご説明はその補足でございます。これについてご質問等がございましたらご発言ください。
特にないでしょうか。
山田委員がいらっしゃいますので後でご説明いただいてもいいのですが、この IV の「負ののれんの取扱い」の今回のIASの改訂案というところの1番で、負ののれんが生じた場合に、識別可能純資産の識別・測定を再度実施するというのは、これはどのような意味でしょうか。
- ○山田委員
-
負ののれんが生じるのは、場合によると、認識の仕方と当初の測定が間違っているのではないかということからもう一回これらを見直すという趣旨です。
- ○斎藤部会長
-
そのようなことですか。恐れ入りました。
- ○山田委員
-
結局、このプロセスを通じてきちんとチェックしますと、残るのは本当のバーゲニングか、計算の間違いかということになります。認識上の割当て間違いというケースは、もう一回見直すことによってできるだけ排除しましょう、その上でもさらに負ののれんが残れば、基本的には本当にバーゲニングで買えたのではないかということから収益計上をしていいのではないかという、そのような論理になっております。
- ○斎藤部会長
-
正ののれんは間違ってもいいということでしょうか。
- ○山田委員
-
正ののれんにつきましては、余りそのような議論が出ておりませんでした。
- ○斎藤部会長
-
わかりました。ありがとうございました。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
それでは、5番目の「無形資産の識別基準」で、米国基準とIAS改訂案の違いでございますけれども、少し会計理論の話になるかもしれませんけれども、分離可能性と信頼性の問題はしばしば議論になります。それで、あえてここでこの文言だけをみますと、「分離可能であり、かつ、信頼性をもって」というようにIAS改訂案では「信頼性」という言葉も「かつ」という言葉で追加されておりますけれども、この辺はどのように解釈したらいいのか教えていただければと思います。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
実は先週ありました理事会で、この「信頼をもって測定可能なもの」というところを米国基準に合わせて削ってはどうかという議論が出ております。もともとアメリカの場合のこの公正価値で測定しなければならないというのは、公正価値を把握するためには、信頼をもって測定ができるという前提が置かれています。IASBの場合はそれをあえて挙げていたわけですけれども、コンバージェンスという観点から削ってもいいのではないかという意見が出て、今のところ暫定的に、では削ってみようかということにとりあえずなっております。
- ○斎藤部会長
-
コンバージェンスというのは、IASがアメリカにコンバージするという意味ですか。
- ○山田委員
-
はい。
- ○斎藤部会長
-
それは驚きです。ほかにご発言はないでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
正ののれんにせよ、負ののれんにせよ、基本的に貸借差額なわけですが、パーチェスにおいて増加する資本部分を発行株式のフェアバリューで測定するということであれば、基本的にその測定上のエラーというものは余り起きない。もしも測定上のエラーによって貸借差額が生じているとすると、増加する資産の評価に絡んでいるわけだと思うのですが、その場合、正ののれんについては、基本的に一たん差額が出た後、本来資産に計上されるべきものはないかというチェックをして残額が最終的にはのれんという手法をとって漏れがないわけですけれども、負ののれんの方については、一たん差額が出た後、本来負債になるべきものはないかというチェックを経ることなく、既存の会計基準、偶発債務やリストラ引当金ということにディペンドしてしまっていて、実ははっきり言えばいいかげんな漏れがあるかもしれないわけですが、その非対称性というのがなぜ生じているのかが私には少し不思議であって、本来同じ手法をとるとしたら、負ののれんについては積極的に振り替えるというスペックとそうでない場合にはどうするかということを考えなければならないのですが、何かアメリカもIASもそこが正の方ときれいにパラレルになっていないという気がするので、それに根拠があるのかどうか、どなたかおわかりであればお答えいただきたいのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
まず金井委員の方に伺うのがいいのですけれども。
- ○金井委員
-
お答えになっていないかも知れませんが、取得純資産の時価評価というときには、当然資産も負債も入っていると思います。ですから、今、大日方委員がおっしゃられたのは、取得資産の方は時価評価をきちんとみていますけれども、取得負債の方はきちんとみていないというご趣旨のようにお伺いしましたが、手続の上では私は負債も当然含まれているのではないかと理解しています。いかがでしょうか。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
IASに関しては負債も含んで、つまり、一たん割りつけますけれども、負ののれんが出ればもう一度アセットもライアビリティーも両方見直すというたてつけになっております。
- ○斎藤部会長
-
よろしいですか、大日方委員。
- ○大日方委員
-
パーチェスのこれは根幹にかかわるわけですが、対価の方はもちろん自由意志をもってマーケットでつくであろうフェアバリューという意味で疑いがないわけですけれども、その承継する純資産については、当事者の評価とはかかわりなく、基本的にフェアバリューと言っているわけです。つまり、ある種、たとえフェアバリューがあっても、合併において無価値だと判断すれば、そこに対価は払わないというケースや、基本的にはマーケットではほとんどその値段がついていないようなものでも高く評価するということは当然あり得るわけですね。したがって、そこのずれが当然のれんのところに入ってきているはずなんです。そこのチェックをきちんとして本来はのれんとそうでないものを分けなければならないのですが、承継した資産の評価が当事者の意思とは無関係になされるマーケットバリューあるいはフェアバリューであるから、それが会計上正確な測定であって、したがって、それさえきちんとやれば残って出てくる差額は全部エラーなんだというのは議論としておかしくて、それはパーチェスといえども当事者の意思は反映されてしかるべきであって、そこにのれんが出たときの評価問題というのは重要な問題を含んでいると私は思っているわけであります。その点が多少アメリカにせよIASにせよ楽観的であるという気がいたします。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
今の大日方委員の、その差額に関して当事者の意思を反映するというご指摘があったかと思うのですけれども、もう少し具体的にはどのようなことをお考えなのでしょうか。
- ○大日方委員
-
例えば銀行が合併するというときに、例えば支店で言えば、旧来の支店をそのまま合併後も使い続けるというのであれば非常に単純なのですけれども、双方を例えばリストラとか整理・統廃合するといったときに、対価――対価というか株式の数の方――に反映されているのがわかりやすいと思うんですね。ところが、受け入れた側のその後の資産の評価にどう反映されているかというのは非常に難しくて、それがここではリストラという形で全部拾えているのかわかりませんが、当事者間での双務契約ですから、双方の対価に反映されているという認識と会計上で識別可能という形式基準がひょっとしたらミスマッチするケースがそのようなところでは出てくるのではないかということです。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
現在の取扱いの中でも、IASに関して言えば、リストラ引当金の計上は認めておりませんので、例えばリストラ引当金の方が対価の方に反映されているとしますと、その分が実は負ののれんとして出てきて、その結果、それに対して何の配慮もしませんので、事前に利益が出てしまうという問題が実は――先ほど申し上げませんでしたけれども――この中に含まれている。大日方委員がおっしゃったのは、今のようなケースのときに、これはそのような部分が歪んでいるので、その分について経営者の意図で――IASは否定していますが――リストラ引当金とかそのようなものをやはり設定すべきだと、そのようなことだと理解してよろしいのでしょうか。
- ○大日方委員
-
最終的には、非常に難しいものがあって、多分、形式基準で100%押し通すことはできないだろうと思うんですね。ところが、昨今の大事なゴールというか目的としてやられている意思の排除とか透明性ということからすると、原則部分は比較的だれがみても明らかであるというような基準でつくる必要があると思うんです。ところが、それだけではやはりはみ出す部分とか足りない部分があるので、その受皿を使って実態にマッチさせないと逆にわかりにくく――最終的な結果、わかりやすく言えば、純利益の段階での結果――がわかりにくくなるのではないか。ただ、そこで全面的に当事者の意思をもって主観的な評価をしろと言うとこれは大混乱になると思うのでそのようなことを言うつもりはないのですが、形式だとか客観基準で押し通していったときに、やはりどこかつじつまが合わない、会計処理で言えば差額が出てしまう。そこになぜ差額が出たかというところまでさらに客観性を要求するとなると、どうしようもないという気がするんですね。そこをどのような受皿で拾ってくるかということが重大なポイントになるのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
私はIASのことしか申しませんが、それについては、その部分についてリストラ引当金の計上ということでかなり長い議論をずっとしましたけれども、最終的には、そのような結合前の企業の負債ではないものについて、結合を契機として負債計上はやはりできないのではないかということから、先ほど言ったリストラ引当金のようなアノマリーについては今のところそのまま損益に出てきてしまうというたてつけになっていまして、少なくとも資産と負債の定義というアプローチからいきますとそれに対応する対策がとれないんですね。それが私には結構困ったなというように感じております。
- ○大日方委員
-
しつこいようですが確認しておきますけれども、本来パーチェスはマーケットで、極端な言い方をすれば、新品を買って自分で買いそろえたのと同じようにするというわけですが、実際に例えば企業結合するときに、スピード感が要求される場合には、リストラをし終わっているとか、資産整理をし終わった状態で、では結合しましょうというようになればいいのですけれども、そうならないのが多いわけですよね。あるいは、それを待っていると実はその企業が倒れてしまうという危険もあるわけで、そうすると、本来パーチェスとは違う状況にパーチェスを適用せざるを得ないわけですよね。つまり、マーケットでは新品を買うとか、ある意味では汚れているとか負担付の商品を買ってこなければならないという状況になっているわけですよね。ですから、それをきちんと反映できないのであれば、やはり原点に帰って、パーチェスのフィクションには無理があるということになってしまうと思うんですね。そうすると、元の木阿弥というか、議論が出発点に戻ってしまうので、どうしても現実的に考えた場合に、新品を買ってくるわけではないとか、途中でリストラが済んでいないような状況、あるいは途中進行形、あるいは合併を契機としなければできないリストラも当然出てくるわけですけれども、そこをやはり踏まえた形で組み立てないと現実には適用しにくいのではないかと思います。
- ○斎藤部会長
-
よろしいでしょうか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
二つ今のことに関連していると思いますけれども、申し上げます。
まず一つ目を確認させていただいてからなのですが、今のリストラ引当金の問題のところで、山田委員の方から、一応IASでは認めないということになっているわけですけれども、偶発債務については可能な限り貸借対照表に負債として計上するということも言われておりまして、「可能な限り」というところはどの程度のニュアンスの違いをとるかにもよりますけれども、偶発債務ということではやはりリストラ引当金は認められないと、要するに、原因性が事前にはないからという解釈でございますか。
- ○山田委員
-
はい、そうです。
- ○黒川委員
-
わかりました。それでは、偶発債務のところでは引き受けられないということを前提としますと、この負ののれんの問題に移るわけですけれども、負ののれんは再度もう一回見直しをして、それで割り振るとも何とも言っていませんが、何かみつけられたらそこに何とか吸収しようということでしょうけれども、結局、残ってしまうと即時利益として計上すると、これは一つのやり方としてあったと思います。
そこで、負ののれんの原因――負ののれんというのはどのようなものなのかと――発生原因はいろいろあろうかと思うのですけれども、即時利益として計上したということは、IASBとしては負ののれんの本質は何だったのかというところをどのように解釈されたのかを教えていただきたいと思います。
- ○斎藤部会長
-
どうぞ、山田委員。
- ○山田委員
-
余り本質の議論を踏まえているとも思えない部分があるのでなかなか難しいご質問なのですけれども、基本的には、負ののれんが生じるようなケースというのは、そう起こるケースではないのではないかということから、その原因として幾つか考えられる中で、特に認識の仕方、測定の金額の誤り、これをチェックしまして、さらに、いわゆる偶発債務等でそれが価格に織り込まれている場合には、そのようなものをきちんと識別することによってかなりの程度差額が解消できるのではないか。したがって、多額な負ののれんが生じる余地というのは非常に少ないのではないかということを多くのボードのメンバーが考えております。
一つは、先ほど私が言ったリストラ引当金の問題は私は大きいと実は言っているのですけれども、なかなか賛同する方が少なくて、この問題は少し横に寄っている感じなのですけれども。したがいまして、そのようなプロセスを経て見直すことによって出てくる差額は、先ほど言いましたように、バーゲニングというような形のものと考えていいのではないかというのが基本的な下敷きになっている考え方だと思います。
- ○斎藤部会長
-
黒川委員。
- ○黒川委員
-
もう少しお話ししていいですか。
- ○斎藤部会長
-
どういたしましょうか。山田委員から国際会計基準についてのご報告を受けた後の方がいいのか、それともその前に多少論点を片づけたいということでしょうか。
- ○黒川委員
-
今のところなのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
それでは、続けてください。
- ○黒川委員
-
今、バーゲニングというように最後に山田委員がおっしゃったので、確かにこのような処理だとバーゲニングのときの購入時のところに原因があると、バーゲニングで原因があるということだったと思うのですけれども、正ののれんの本質がもし仮に超過収益力の源泉であるというように認識した場合には、負ののれんが、その対称性から言えば、超過収益力ではなくて、マイナスの超過収益力と言うのでしょうか、それの源泉であると、単純にこのように言えるわけですね。
そうなった場合に、先ほど大日方委員が質問されていたところなのでございますけれども、結局、マイナスのシナジー効果というのがあるはず、合併をして膨れてしまうとか、人員が多くなってしまうとか、ダブる部分があるとか、そのようなことがあった場合には、マイナスのシナジー効果というのが当然予想されるわけですね。そこでリストラ引当金というものは認めないんだと、原因性は合併後にあるからだと、このようなことになると、そのようなマイナスのシナジー効果というようなものを吸収するところがない、吸収というか、そこはどうしようもないんですね。そこで、即時利益というのがバーゲニングのところの話だということになると、今言ったようなマイナスのシナジー効果というようなものがやはりあると思うのですけれども、それについては全く議論されないのでしょうか。そこを教えていただきたいのですが。
- ○山田委員
-
マイナスのシナジー効果ということで黒川先生がおっしゃっていることがよくわからないのですが、申しわけありません。
- ○斎藤部会長
-
要するに、フェアリターンを下回るリターンしか得られない期待という意味ですね。
- ○黒川委員
-
そうです。
- ○山田委員
-
そのような論点での議論はしておりません。
- ○斎藤部会長
-
辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
今のケースなのですが、たまたまIASBのSAC会議でもこの議論がかなり出まして、各委員から、正ののれんと負ののれんというのはミラーイメージのような関係にあるので、整合的な処理が必要だという意見はかなり出ましたけれども、ほとんど机に置かれたというか・・・。ただ、世界の中でもこのことについては矛盾があるという指摘はかなり出ております。山田委員もその席にいらっしゃったので、多分、賛同されていたと思うのですが。
- ○斎藤部会長
-
差し当たりよろしゅうございますか。
それでは、時間の都合もございますので、山田委員からご報告を続けてお願いいたします。よろしくどうぞ。
- ○山田委員
-
それでは、本日の資料2に基づきましてご説明させていただきます。私が資料を作成するのが遅れまして事前に配布できませんでしたので、今日が初見となることをお許しください。
それで、全体で三つに分けて書いておりまして、 I は、第1フェーズの概要について簡単にまとめております。 II が、これまでに達した暫定的結論の概要ということで、これが本日の大宗を占めておりまして、最後は5ページから2ページほど、国際会計基準を初めて適用する企業、財務諸表の作成基準として国際会計基準を初めて採用する場合の移行措置について議論しているプロジェクトがあるわけですが、その中に企業結合について特例的な取扱いがございますので、それを簡単にご紹介するという形でお話しをさせていただきたいと思います。
1ページに戻っていただきまして、第1フェーズの方ではまずどのような項目を検討しているか、中身はこれから申し上げますけれども、一つは、企業結合の定義に関する部分、それから、企業結合に関する会計処理、特にこの持分プーリング法の廃止という問題、のれんの会計処理及びこれに関係する無形資産の会計処理、被合併会社で仕掛中の研究開発費の資産計上の問題、リストラ引当金関連の問題、さらに、受け入れてくる資産の評価に当たりまして、現在、少数株主が存在するときに、部分時価評価法的な処理と全面時価評価法的な処理と二つの処理が認められているわけですが、これをどうしようかと、それから、少数株主持分が現在は「資本と負債の間」という表示になっているわけですが、これをどのようにしようかと、このような点が大きな論点としてこれまで議論されてきました。
議論は大体収束してまいりまして、ここの2にございますように、来月で議論を一応終える予定にしております。来月は経過措置に関連する議論を中心に、さらにボードが何かの問題を提起すれば、そのような問題について基本的にはここで議論をしよう、それから、その後、早ければ今年の7月末をめどに公開草案の準備に入ろうということになっております。ただし、これはかなり楽観的なスケジュールだと考えておりまして、個人的には、遅れる可能性が結構あるのではないかというように考えております。最終案の承認は、当初は年内という話もあったのですけれども、多分、現実的なところでは来年の第1四半期あたりということになるのではないかというように考えております。
一つ、これまでのボードでの経験からいきますと、これから申し上げます暫定的結論には達しているわけですけれども、基本的に、基準案の形になって公開草案の様式で議論をしますと、また議論が結構ぶり返して、その結果、結論がいろいろ変わるということも十分予想されますので、まだまだ最後の公開草案が出るまでその辺の議論の進展については予断を許さない部分が結構あるという感じがしております。
次に、「これまでに達した暫定的結論の概要」ということで、幾つかのポイントを取り上げましてこれからお話をさせていただきたいと思います。
まず、「持分プーリング法の廃止」の問題ですけれども、現在のIAS22号では、極稀な場合にのみ持分プーリング法の適用を認めております。したがって、現状のIAS22号でも持分プーリング法が適用できるケースというのはかなり狭いことになっているわけですが、それをさらに廃止してパーチェス法に一本化すべきだということで、これはほとんどのボードメンバーがこの結論でいいと考えておりますので、この方向というのは多分このまま続くのではないかというように思います。
取得者が特定できないような企業結合においても、持分プーリング法を適用するのではなく、いずれかの当事者を取得者と指定してパーチェス法を適用する、幾つかのクライテリア・規準を適用して、いずれが取得者かということは基本的には把握できるのではないかということを前提としております。
さらに、今回の第1フェーズとは直接関係しないのですけれども、取得者が特定できないような企業結合では、当事者双方を公正価値で測定するという意味のフレッシュスタート法が適当ではないかと考えるボードメンバーがかなり多いという状況です。つまり、どちらがどちらを買ったということがわからないことは、その時点で真に新しい事業体がクリエイトされたのではないか――ということになれば、その時点でその新しい事業をフレッシュスタートという形で時価評価していいのではないかということを言う方が多うございます。もちろん過去に日本の方から少なくともそのような考え方というのはおかしいという主張もしているのですけれども、今のところ、ここにありますように、多くのボードメンバーはフレッシュスタートがいいのではないかという感じでございます。
次に、2ページに行きまして、「のれんの非償却(減損会計の適用)」の問題でございますけれども、これも基本的にアメリカの基準と似たような考え方をとっておりますが、のれんの償却を禁止し、代わりに減損会計を導入する。これは先ほどの金井委員からのご説明のとおりでございます。
多くののれんでは耐用年数を明確に決定することができず、耐用年数とのれんの費消のパターンを見積もることは困難であり、適切な減損処理のルールが規定されれば、のれんの会計処理として、償却を行うよりは、減損処理によってよりよい情報が提供できるというのが、現在これを支持する考え方の根底にある考え方です。
のれんの減損は、先ほど金井委員からもありましたように、基本的には現金生成単位なのですけれども、それが一番最小単位でのれんが割付られない場合には、社内管理上の採算単位、セグメントまたはそれより小さい現金生成単位のグループ等ということなのですが、基本的にはこのような概念をとることによって、アメリカのセグメントより一つ下というものと実質的に同じグルーピングを念頭に置くというか、そのようなものになるように考えております。
ただ、基本的にこの減損会計についてはIAS36号がございまして、この36号全体を見直さないという考え方をとっておりますので、36号の基本となる考え方の枠を踏み出すわけにいかないわけでして、それで36号の枠の上に立ってアメリカの会計基準とできるだけ同じような結果がもたらされるようにしようというのが努力している点でございます。実は、決定的に違う面があり、後ほど申し上げますけれども、回収可能額という概念をIAS36号はとっておりますので、公正価値という概念をとっているアメリカの考え方とは基本的に違いまして、そのような回収可能額をとっている中に公正価値的な考え方を入れていますので、木に竹を接ぐというか、そのような不整合的なところがある意味では随所にみられるというのが現状でございます。
四つ目の黒丸ですけれども、大体ここは今申し上げたわけですが、減損テストは現金生成単位の回収可能額を用いるということで、実際に正味売却価額を用いることはほとんどないのではないかと想定されますので、現実には使用価値が実質的には用いられる基準になるのではないかと思います。
それで、先ほども金井委員の方から説明がありました、のれんの非償却のときの処理なのですけれども、一応ここに設例を挙げております。下の表の方でみていただきますと、下の表のA欄に、「現金生成単位内の資産構成」が書いてありまして、のれんとのれん以外の資産、さらに、未認識の資産で合計を取る、このような区分を縦に持っております。
それで、B欄のところは簿価でございまして、現在この現金生成単位内で合計で400の価値がある、その中で、のれんに100、のれん以外の資産に300という数字が割当てられているという前提で考えますと、C欄の一番下に300とございますけれども、この時点で減損の計算をしますと、回収可能額が300だと計算されたとします。そうしますと、400と300の差の100が今、減損で生じているわけですけれども、この減損をどのような形でのれんに割り付けていくかというのがD欄以降のプロセスでございます。
D欄のところでは、現在の36号による計算を示しておりまして、現在の36号の現金生成単位という考え方は、キャッシュ・フローの見積りはこの現金生成単位でしかできないので、その中を構成しているのれん・のれん以外の資産というのは、基本的に個々にキャッシュ・フローを割り付けて回収可能額を計算できないという前提が置かれておりまして、現在のルールでは割り付けられたのれんを最初に落として、その後さらにまだ減損額があればのれん以外の資産に基本的には比例的に配分をして差し引くという考え方をとっております。今、このD欄の場合は、100という数字がちょうどのれんの100と同じでございますので、IAS36号の現在の規定によれば、のれんがまずゼロになって、のれん以外の資産が300という形で、これで減損の処理が終わるということになります。
ところが、今考えておりますところでは、E欄のところでございますけれども、基本的にはここが第2段階の処理になってくるわけです。のれんに割当てられるべき推定価値をどのように算出するかというプロセスですけれども、この「注」のところにございますように、この欄の計算はのれんの推定価値を算出するために、あたかも新たな企業結合によって現金生成単位が購入されたかのように計算し、未認識資産の公正価値も計算に含めるという前提を置いておりまして、したがって、仮定計算はこの時点で買収という形で買ってくるという前提を置きますので、そうしますと、未認識になっている何か資産があれば、それの価値もこののれんの推定価値を出す計算のためのみに算出するということで、ここの欄にありますように、未認識の資産に20が割当てられて、それぞれが計算された結果――このところでのれん以外の資産の価値の230と未認識の資産20がわかったという前提で計算しているわけですけれども、これがわかりますと300という回収可能額から230と20を引いて差額としての50を算出するということになります。こののれん以外の資産に230という数字がつけられておりまして、簿価である300と違う数字がついているわけですけれども、これはのれんの推定価値を出すためだけの計算なので、その価値は230に基づいて300を修正するということは基本的にはしないということになります。
それで、次のF欄のところですけれども、この今のE欄で結局のれんの50が計算されますので、そうすると、Fの欄で、今度は残っている現金生成単位の方で50がのれんの新しい価値として割り付けられますので、そうしますと、合計欄の300、これは回収可能額で確定しますので、差額ののれん以外の資産には250という価値がつけられます。そうすると、このような計算をしますと、Eの欄にある20が結果としてのれん以外の資産の価値に紛れ込んでしまう計算が実は起こってしまいます。結局、企業結合をしたというE欄の仮定のときだけ計算されてくるものが、本来はのれん以外の資産の時価が230であるにもかかわらず、それを250という形で表示されるということがこの計算だと出てくるわけですが、これはこれで仕方がないということで現在は割り切っております。したがいまして、一番右のF欄にございますように、300という回収可能額、これはギブンとして押さえまして、のれんの推定価値50、差額がそれ以外の資産という形で割付が行われるということになります。
したがいまして、先ほど来言っておりますように、第1段階、第2段階――第1段階は回収可能額の300との100の差額を出すという段階ですけれども、ここで回収可能額の概念を入れているのが米国基準と違う形になっていまして、先ほど言いましたように、木に竹を接ぐような処理をしながら米国基準と非常に類似した2段階の計算構造を一応つくり出しているという状況でございます。
次の3ページへ行きまして、先ほど来話題になっております「負ののれん」でございますけれども、基本的に、負ののれんは貸借対照表には計上しないということになります。
負ののれんが生じる場合には、資産・負債の識別及び測定の見直しを行い、それでも差額がある場合には収益計上を行う。これは先ほどのとおりでございます。
それから、「負ののれん」という用語はまずいのではないかということで、一応、基準案では、「取得した識別可能純資産の公正価値が取得コストを上回る金額」というような表現を用いようということが暫定的に合意されております。
4番目で、「少数株主持分」の関係でございますけれども、少数株主持分は、資本の構成要素として表示するということで、現在の負債と資本の中間的な位置づけという位置づけをやめまして、資本の部の中に入れて、資本の部を支配株主の持分と少数株主の持分ということで、表示だけ今回はそのようなことにするということで合意しております。そうしますと、少数株主持分に対する考え方が変わりまして、場合によれば少数株主持分の関係する会計処理が影響を受ける可能性があるわけですけれども、それについては第2フェーズで包括的に見直すということで、とりあえず表示のところだけ資本の部に移すということが暫定的に決まっております。これについては今までずっと中間的な位置づけにしておきながら、何で今回表示だけを第1フェーズで変えるんだと、第2フェーズまで待って処理してもいいのではないかという意見もあったのですけれども、行くべき方向としては、少なくとも少数株主持分は負債の定義を満たさないので資本ではないかと、そのような方向で今後議論するということを示す意味でもここだけ表示を変えてはどうかという考え方を支持するボードメンバーが多うございまして、このような形の、表示だけ変えるということを考えております。
これに伴って、現在、別にIASの改善プロジェクトというものをやっておりますが、その中で出てくるIAS27号――連結のことを扱っている基準があるのですが、そこもこれと整合的な修正を行う公開草案を準備しております。
次の5番目でございますが、「被取得企業の資産・負債」でございますけれども、少数株主持分が存在する場合における被取得企業の資産・負債の取得原価の測定でございますけれども、これは基本的に全面時価評価法の考え方を採用するということで、現在、先ほども言いましたIAS22号が認めているもう一つの処理――現在は部分時価評価法的なものが標準処理で、全面時価評価法が認められる代替処理なのですが、この関係を逆転させまして、部分時価評価法的なものは禁止するというか削除するということで、会計処理の一本化を考えております。
6番目でございますが、「リストラ引当金の計上の禁止」という問題、先ほど来も議論しましたので詳しくは触れませんが、現在のIASでは、先ほどご紹介がありましたように、一定の条件を満たした場合に引当金を定めるIAS37号の例外としてリストラ引当金の計上を認めているわけですが、このような例外処理を今回は削除するという形になっております。
それから、「偶発債務の認識」でございますが、取得企業の偶発債務は、もし公正価値が信頼をもって測定できる場合には、取得者によって取得コストの配賦の一環として識別され、公正価値で認識されなければならないということが一応合意されております。さらに、当初認識後の測定においても、IAS37号の規定を適用せずに、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益計算書で認識するということで、いずれにしてもこの企業結合に伴う偶発債務の認識の処理はIAS37号の例外処理という形で取扱うということで暫定的に合意されております。
それから、「無形資産」でございますけれども、企業結合に伴い受け入れる無形資産とのれんとは密接に関係するので、基本的にこのプロジェクトで扱うということで、次のページでございますが、のれんから区分して無形資産を認識するための条件として、それらが契約または法律によって成立しているものであること、または分離可能であることのいずれかの条件を満たす必要があるということで、先ほどご指摘がありましたように、ここで信頼をもって測定するというのはとりあえず除くという形で合意に達しております。
それから三つ目のところで、無形資産が企業にキャッシュ・フローをもたらすと予想される耐用年数が明確に決められない場合には、IAS38号に基づく償却を行わず、36号に基づいて減損を認識する会計処理を行うということで、つまり、企業にキャッシュ・フローをもたらす期間が将来終わるということが今時点で明確にわからない場合には、基本的にはそれは耐用年数が明確に定められないという範疇に該当するので、したがって減損の処理をしようというたてつけで基準を作るように考えております。
それから、一番最後の黒丸でございますが、耐用年数が明確に決められない無形資産に対して、IAS38号が現在認めている再評価という認められる代替処理がございますが、これは基本的に適用を認めるということで、これを例外にする必要はないという考えに達しています。ただ、実際問題としてこれが適用できるケースは極めて限られているのではないかというのが合意でございます。
「仕掛中の研究開発費」に関しては、先ほど金井委員の方から説明されたことでほぼ同じ内容がカバーされておりますので、ここでは一番最後の黒丸だけを申し上げます。
仕掛の研究開発費――ある要件を満たした場合は一たん受け入れて資産に計上するわけですけれども――の取得後に発生する追加費用は、基本的にIAS38号に基づいて、すなわち、研究活動の部分は費用、開発活動の部分については資産に計上するということを考えております。
次は、先ほども少し申し上げましたように、現在、この1番のところでございますけれども、IFRSの適用初年度の取扱いに関するプロジェクトが別途進んでおります。その中で何を考えているかというと、新たにIFRSを正式な財務諸表作成基準として採用する企業が増加しつつあることから、このような新規採用企業の適用初年度におけるIFRSの簡易な適用ルールの作成を行おうというプロジェクトでございまして、原則的には、初めてIFRSを適用するときは、すべて過去まで遡及してつくるということが原則なのですが、そこまですることはないということで、幾つかの例外が定められております。現在、このプロジェクトが急がれているのは、2005年からヨーロッパで上場企業の連結でIFRSが強制されるので、それに合わせるように今かなり急いでやっておりますけれども、これはヨーロッパだけの問題ではございませんで、日本で今後、国際会計基準を採用するところが出てきますと、この基準の適用を受けるということになります。
細かいことは置きまして、2番の「取扱い」の中で、まず
 でございますが、旧会計基準に基づく財務諸表で採用されている分類、例えば買収とか持分の結合とかといったものを、基本的には新たなIASの下でも引き継いで、つまり、それを新たにIASの下で見直すことを要求するということは基本的に考えておりません。したがいまして、プーリングで処理をしていれば、基本的にはそのプーリングの処理を新たにIFRSに移行しても継続してそれを使うことはできる。
でございますが、旧会計基準に基づく財務諸表で採用されている分類、例えば買収とか持分の結合とかといったものを、基本的には新たなIASの下でも引き継いで、つまり、それを新たにIASの下で見直すことを要求するということは基本的に考えておりません。したがいまして、プーリングで処理をしていれば、基本的にはそのプーリングの処理を新たにIFRSに移行しても継続してそれを使うことはできる。ただ、IFRSに移行する開始残高でございますけれども、これはIFRSにおける資産・負債の定義と認識基準を満たしたもののみとするということですので、何かローカル基準の方で、IFRSでは資産計上が認められないようなものが例えば資産として計上することが認められていれば、これを調整し、資産としては計上しないようにし、その結果出てくる調整額は期首剰余金の修正額として処理し、のれんの調整とはしないというのが基本的な考え方です。ただし、旧の会計基準で買収として処理された企業結合で認識された無形項目で、IFRSの無形資産の定義を満たさないものがあったとしますと、これはのれんに振り替える。ここだけ一つ特例的な処理を認めております。
もう一つ、
 企業結合で取得した資産・負債で、IFRSが取得原価での測定を認めているものについて、企業結合時点で旧会計基準の下で付された取得原価をIFRSの下でその時点でのみなし原価とするということにしております。したがって、旧基準の下で取得原価として計上されていた金額というのは、基本的にIFRSの下でみなし原価として以後ずっと引き継がれるということになります。
企業結合で取得した資産・負債で、IFRSが取得原価での測定を認めているものについて、企業結合時点で旧会計基準の下で付された取得原価をIFRSの下でその時点でのみなし原価とするということにしております。したがって、旧基準の下で取得原価として計上されていた金額というのは、基本的にIFRSの下でみなし原価として以後ずっと引き継がれるということになります。あとはかなり細かい規定で、これはまだ最終版ではございませんので、あとは参考までにおつけしたということで、少し長くなりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。
- ○斎藤部会長
-
大変ありがとうございました。
それでは、ただいまの山田委員のご報告についてご質問等がございましたらご発言ください。
どうぞ、引頭委員。
- ○引頭委員
-
ご説明の2番の「のれんの減損会計」についてなのですけれども、セグメントまたはそれより小さい現金生成単位で行うということですが、実際に企業を担当していますと、企業のセグメントというのがかなり変わってきているわけですね、組織変更とか、あるいは経営環境が変わってしまったので、組織を洗い直すとかするわけですね。そうした中で、ではどれだけ監査の立場で追えるのか。合併当時の――恐らく二、三年は大丈夫だと思いますが、では何年間この減損テストを追っていけるのかとか、そうした担保を――この時点ではオーケーなのですけれども、継続性という点での担保についてのお考えを教えてください。
- ○山田委員
-
今日ここではご紹介していないのですけれども、一応そのような企業分割があったときには、基本的には移った先に比例的に配分していく。例えば今ある事業部門が三つに分かれてどこかへくっついていくとしますと、基本的には三つに割り振られたアセットに比例的に計算すると多分思いますが、そのような形で例えば割り振るというようなルールをつくる予定にしております。
- ○引頭委員
-
何年間ぐらい追っていくことになるのでしょうか。というのは、2回ぐらいまでだったらいけると思うのですけれども、もっと人の移動やアセットの移動がかなり激しくて、特に今日本はすごく問題国だと言われているように、これからは企業のリストラは物すごいと思うんですね、そうした中でどうでしょうか。
- ○山田委員
-
特に年限は定めておりませんので、のれんの残高がある限り、基本的にはずっと何らかの方法でその分割に伴って割り付けていくというのが前提になっております。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
ほかにご発言はないでしょうか。
八木委員、どうぞ。
- ○八木委員
-
少し教えてください。この少数株主持分についてですけれども、今度、資本の構成要素として表示するということは、まだアメリカ基準は変わっていないと思うので、アメリカ基準とこれとのコンバージェンスというのはここで断ち切るというか、そのようなことになるのかなというのが一つ。
それから、資本の部に含まれるのだけれども、P/Lの少数株主持分損益がなくなってしまうので、その辺の整合はどのようにとるのかなということで、少数株主持分見合いの利益というのは業績としてどうなるのか、この辺を少し教えていただきたいと思います。
- ○山田委員
-
まず米国基準とのコンバージェンスのご質問ですけれども、アメリカも基本的には資本に入れる方向で議論するという方向性のようですので、方向性については差異はない、ただ、今回はこちらが先になりますので、短期的にはこの基準が適用される期間、アメリカの基準が変わるまでの間は、そのような意味での差異が生じるということになります。
それから、P/Lの方は、基本的に、当期利益は少数株主持分を除く前のところで出して、その後を二つに分けるように提案されていまして、最終のバロットの案を今みていないので、それに問題を言うボードメンバーがいたものですから最後のところは覚えていないのですけれども、最初の提案では、当期利益のうち少数株主持分に帰属する利益と支配株主に帰属する利益という形を一応考えておりました。最後のところは少しチェックをさせてください。
- ○八木委員
-
少数株主持分というのは結構微妙なものがあって、われわれがグループをマネジしていくときに、まずわれわれの経営の成果というのは少数株主持分があろうとなかろうと大きなグループの全体が一つの成果なんですね。ただ会計的に持分をこうやっていくと残るのは今の当期利益のマイノリティーを除いた分だということで。われわれはいろいろなところで、例えば引頭委員のようなアナリストさんと議論をするときは、われわれの活動の成果というのはこの上のところにも一つあるんだよと、今おっしゃったその二つのところでみるというのは、われわれにもそのような考え方はあるんですよね、ただ、会計的にこうみると、USとの関係とかということになると、ここはやはり整合性をとらなければならないなという感じはもちろんしております。
- ○斎藤部会長
-
要するに、100%支配していても、6割支配していても、あるいは実質支配力ということから言えば、ほとんど株式を持っていなくても連結範囲に入り得ますから、その持株の比率のいかんにかかわらず、まず差し当たりは全部まとめたものを業績とみようと。
- ○山田委員
-
そのようなことになると思います。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はないでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
少し減損のことでお聞きしたいのですが。一応、第一部会の守備範囲ということで、確認だけにとどめますけれども。
減損の判定単位なのですけれども、合併で生じたのれんについてですが、2点だけ確認したいのですが。まず、合併前の被合併企業と合併企業というその境界線というのは関係ないのかどうか。この前もお話ししましたけれども、例えば銀行や何かのときに、例えばA銀行の支店とB銀行の支店というのは合併前は当然別の単位になっているわけですが、合併後はそれは関係なく、くくり直すことは可能かという点が一つ。
もう一つは、連結上ですが、個別上でみたときの法人格が異なる企業、そのような企業をまとめて連結上で一つの単位とすることが可能か否か。つまり、個別で減損テストを行っておいて、その結合結果が連結上ならないと、単純にならない、全然別の次元で考えるということなのかどうかなのですが。連結のことしか考えていないと思うので何ですが、個別上の法人格の単位をまたがることは可能か、あるいは、分断することも可能か、つまり、それが制約にならないかどうかということを確認したいと思います。
- ○山田委員
-
まず最初の点ですけれども、どのようなキャッシュ・ジェネレーティング・ユニットを合併の後に組成するかということについては会計基準の領域ではございませんので、それは経営者が決めるということになります。その結果、随分前のここの席でも大日方先生からご指摘がありましたように、取得企業が合併前から持っていた自己創設のれん的なものが被合併企業ののれんの減損計算に影響を与えるかということについては、影響は与えます。それをクッションとかという呼び方をしておりまして、そのようなことが起こることを基本的には是認しているというか、それが前提になっております。
それから、2点目の法人格が異なる企業が一つのセグメントになって、そのときに生じたのれんを法人格は無視して考えるかということなのですけれども、これだけを取り出しては実は議論はしていないのですけれども、例えばある会社が、国際的なお菓子部門、チョコレート部門と何かを持っていて、世界的に展開している会社のチョコレート部門を買ったというときに、例えばその会社にアメリカとイギリスと日本で別法人があったときには、それ全体を一まとめで買えますので、それに対してのれんが出てくるわけです。そののれんを全く割り振らないで考えるか、それぞれ、アメリカ、イギリス、日本という形で割り振るかということなのですが、今は原則的にはそれぞれに――買うのはどのような塊で買っても構わないわけですけれども、それをその中の少なくとも今の意味では法人格がわかるようなところに基本的には割り振るという考え方をとって議論をしております。それは不可能だということで実は反対しているボードメンバーがいるのですけれども。ただ、なかなか難しいのはIAS21号の外貨換算の問題と実は絡んできて、そのようなのれんを割り付けられるのかという現実の問題があるのですけれども、考え方としては、それぞれの企業をのれんを割り付けた上で処理をするのが多分前提になっております。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
パーチェス法とプーリング法の問題に絡んで、プーリング法が米国基準の場合にはなくなったわけですけれども、その過程で、公開草案の段階では、パーチェス法に一本化した上で償却するという、そのことが通らなかったために償却しなくなって減損が取り入れられたと、それが本当にその理屈が合っているのかどうかという、これはSACのときにもそのような発言が出たわけですけれども、コンバージェンスの問題を別にすると、こののれんの減損ということがそもそも論で、それをのみましょうと、コンバージェンスと別に議論があったのかどうか。そこのところが初めに減損ありきということだとあちこちでいろいろな問題が出てくるということで、少し不思議に思いますのは、例えばこののれんの減損ということを言い出した場合、同じことが例えば固定資産の問題で、減損するから償却はストップしてよろしいというのと同じ理屈にならないのかなと疑問に思うのですが、どうなんでしょうか。
- ○山田委員
-
私は同じ質問を実はボードでしました。そのような意味では同じ考え方のベースかなと思うのですけれども。ただ、私はアメリカの会計基準ができた経緯というのはつまびらかに存じ上げていないのでわかりませんが、先週、IASがここで開かれた際に行われたシンポジウムの席で、アメリカの当時のFASBのボードメンバーで、現在のIASBのボードメンバーの方が言っていたのは、彼は、公開草案の段階で減損一本に絞らないから反対をしたと、つまり、公開草案を決める以前に既に償却ではなくて減損一本に絞るべきであると言う考え方が存在していたということで、それは政治的妥協ではないということを言っていました。私はその審議のほどがわかりませんので、そのようなやり取りがあったということをとりあえずご報告させていただきます。
IASBの中での議論は、耐用年数というか、どれだけの期間、企業にキャッシュ・フローをもたらすかどうかがわからないのれんに10年とか20年とかという期間を決めてその期間で償却するというのは、やはり恣意的ではないかということを考える方は非常に多いです。それで、やはりどの期間キャッシュ・フローが続くかがわからないので、予想されていたキャッシュ・フローが得られなくなった時点で落とすという考え方が合理的なのではないかというのがそのような方が支持している――よく言われているとおりですけれども――考え方です。
あと、有形固定資産にも減価償却をやめて減損という考え方が適用できるのではないかという話はしましたが、それは余り深い議論にならずに、そこは考えていないという形で何か肩透かしのように議論が終わってしまったので、ボード全体がどう考えているかは私は今の段階では情報を持ち合わせておりません。
- ○斎藤部会長
-
よろしゅうございますか。
確かに私も、今、山田委員がおっしゃられた話はシンポジウムの席上で伺っておりました。アメリカの基準でパーチェスを適用した場合にのれんの償却をしないということは、決して政治的な妥協ではなくて、その前からある考え方だという発言はございました。それは当たり前でありまして、昔、カナダでこのような議論をしたことがあるんですね。ですから、考え方はあるわけで、それは決して間違った発言ではないのですが、前からあるということだけでは答えにならないと思いますね。
それから、恐らく辻山委員が言われたご議論を少し敷衍すれば、のれんについてどこまで有用性があるかわからない、何年持つかわからないということは、固定資産も同じなんですね。やってみなければわからないわけで、だから事後的に処分したときに差額を調整するわけなんですね。のれんというのは基本的には将来の超過リターンの期待でありますから、その期待されたものは1年たって超過リターンが1年分実現すればその価値は下がるわけで、無限でない限り必ず価値は下がるんですね。ですから、無限であるということを立証しない限りは本来は非償却という議論は出ないはずだと思うのですが、それをここで言ってみてもしようがない話なので、IASに対して何かものを申すということよりは、われわれの基準を考える上でそれをどう考えるかという議論として承りたいと思います。
ほかにご発言はありませんか。
山田委員、どうぞ。
- ○山田委員
-
今の点に関して、IASBの中で、のれんは永久に価値が続くということは必ずしも意味しておりませんで、どこかで価値は減じる、その減じた時点でそれを認識しようということを考えていますので、減損を主張する人が永久に価値が続くと思ってはいないということだけは少し確認させていただきたいと思います。
- ○斎藤部会長
-
それは当然だと思いますね。ただ、その議論をしてしまうと固定資産と区別がつかなくなってしまいますね。小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
少し聞き漏らしたのかもしれないのですけれども、のれんの非償却のところで、IAS36を直さないということですよね。ということは、戻し入れは可ということですか。
- ○山田委員
-
それは申し上げませんでしたが、のれんの減損については戻し入れしないという方向です。
- ○小宮山委員
-
あともう1点いいですか。
最後のさっと駆け足でやった初年度適用のところですけれども、IFRS以外の会計基準で企業結合の会計処理を行っている場合の移行の取扱いで、IFRS以外の会計基準ということは、これは何でもいいということですか。
- ○山田委員
-
はい。
- ○小宮山委員
-
ということは、例えば日本基準で連結を作っていますと、この2005年の初年度適用時に過去の分がどうなるのか少しわからないのですけれども、そのときには過去の分はそのまま引き継ぐから、例えばIAS22のように、非常にプーリングが制限されるような基準を持っていたとすると、ほとんどの例については、例えばのれんの非償却はしませんという選択をしない限りは、実質的に同じような処理になると考えていいんですか。
日本の過去のものはずっと引っ張るとすると、例えば、このIAS22をほとんどそのまま残したようなルールを作って、企業結合を処理した場合には、実質的にプーリングにぴったり合うような事例が出てこない限りは、2005年ぐらいに、かなりの場合はこのIFRSに近いような処理になると考えていいんですか。
- ○山田委員
-
少し質問の趣旨がよくわからないのですが。
- ○小宮山委員
-
もっと簡単に言うと、のれんを非償却にしましょう、減損処理をしますと、ただ、プーリングとパーチェスの識別規準はIAS22と同じですというように日本基準を作った場合、実際にはプーリングに当てはまるような事例はほとんど出てこないということになると、基本的にはどの国でも適用初年度より前については過去の基準を引き継ぐ以上、IFRSの規定とほかの国で行われていることと余り違わない財務諸表が出てくるということになりますか。
- ○山田委員
-
そのようなことは旧基準がどのようなたてつけになっているかによりますけれども、その可能性はあります。ただ、ここで考えているのは、移行時に過去に遡って企業結合を全部新しいIFRSに基づいてやるということはほとんど不可能なので、それで例外的にこの時点でカットオフしてということです。ここで言っている開始残高というのは、比較財務諸表を出すときの一番最初の時点なので、ただ、2005年1月1日から導入した場合は、1年比較情報を出すときは2004年の1月1日時点の残高からスタートということになります。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はないでしょうか。
安藤委員、どうぞ。
- ○安藤委員
-
先ほど出た3ページの4の「少数株主持分」と、その次の5の「被取得企業の資産・負債」、これをひっくるめて概念的に整理すると、何か親会社説から経済的単一体説に乗りかえようというのか、舵を切りかえようというように少し感じるのですけれども、そのような概念、親会社説とか経済的単一体説という言葉を使って議論されていますか。
- ○山田委員
-
大分前にそのような形で議論をこちらから提起をしました。それで、それに対して多少のペーパーが実は出てきているのですけれども、むしろ、今の考え方はそのような議論をできるだけしないようにしていて、少数株主持分が負債の定義を満たさないという――私は好きな議論ではないのですけれども、その1点をとらえている部分が少しあります。第2フェーズでその辺のところはきちんとやろうということで、今は振り替える論拠をフレームワークの負債に合わないという1点に求めているように私には受け取れます。
- ○安藤委員
-
5の方はどうなんですか。これの理由は、要するに、今はなるべく選択不可能にしてしまおうという、一本化しようという論理ですか。
- ○山田委員
-
現在、これとは別にIASの改善プロジェクトが進んでおりますけれども、その中では、これは主としてIOSCOからの要請なのですけれども、一つの事象に二つ以上の選択肢があるものをできるだけ一つに削るように検討してほしいという要請がありまして、それにこたえて検討していることの一つで、その中で、全面時価評価法的な方がいいというボードメンバーが多いという実情です。
- ○斎藤部会長
-
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどの、固定資産については減損もあり得るのではないかということに関連して、これは建設的にご質問させていただきたいのですけれども。
もし仮にこのようなやり方で減価償却もどきのものを見積もるとどうなるかということですけれども、毎年毎年あと何年使用期間があるのかしらということを経済的に見積もるということをしまして、それで、分母に過去の経過年数と新たなあと何年もつのかということを足したのを持ってくる、要するに、毎期末における過去から将来にわたる見積総耐用年数というものを持ってきて、分子にあと何年もつというものを持ってきたとき、それを取得原価に掛けて未償却残高とするという方法をとったときに、これは毎年毎年あと何年使えるからということで見直しをしているというようなことになるので、これは減損の適用と呼んでいいのか、あるいは、やはりこのようなやり方も減価償却のうちだと、このようなことなのでしょうか。そこをもし議論されていたら教えていただきたいのですけれども。差し当たって山田委員に教えていただきたいということです。
- ○山田委員
-
そのような形での議論はしておりません。
- ○斎藤部会長
-
それは、耐用年数の見積りが変わるケースですね。伸びれば償却のカーブをなだらかにするというだけですね。
- ○黒川委員
-
そうすると、やはり今のようなものは減損とは呼ばない、ただ耐用年数の見積りとすると、もしかして固定資産について減損があるとすると、どのような方法が減損と呼べるのかということにもなるのですけれども。
- ○斎藤部会長
-
それは、さきほどの別にあるのではないかとおっしゃったものではないでしょう。辻山先生は、固定資産について減損を考えるということがかなり滑稽であると同じように、のれんについて減損を考えるのも同じように滑稽だということをおっしゃったのではないですか。
- ○辻山委員
-
そうです。固定資産については、要するに、将来キャッシュ・フローを見積もって回収可能額で減損というものを適用すれば、それによって償却をストップできるという理屈がこののれんのことについても言えないのかと。要するに、減損を判定すれば償却をしなくていいというのは同じ理屈になりませんかという、そのような質問なのですけれども。耐用年数の問題とは少し異なります。
- ○黒川委員
-
今、差し当たって、将来のキャッシュ・フローということに変えて、もし仮に耐用年数のようなもので毎期毎期見直しをするという、そのようなことをもって減損というように、固定資産の減損がもし仮にあるならばということで質問しただけであって、それは減損と呼べるのかというところに質問の趣旨があったので、部会長から、それは減損ではないという答えでわかったわけです。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はないでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
企業結合プロジェクトでありながら、企業結合以外のところに随分張り出した部分があって、それが将来齟齬を来すのではないかという気もするのですが。少し気になる点を確認しておきたいのですけれども。
3ページの7の「偶発債務の認識」のところで、実は認識と言いながら、その後の測定について触れているわけですが、これは継続的フェアバリュー評価でそれをダイレクトに利益に入れるということのようですけれども、少し脱線ぎみなので確認だけにしますけれども、これは偶発債務だからですか、それとも、もともと負債であればそのようなことをやりたいということがあって、これはチャンスだから一気に、変えるのだから手始めにやりたいという程度のことなのか、非常に重要なことなので確認しておきたいのですけれども。
- ○山田委員
-
まず後者ではないと信じておりますけれども。ここで基本的にあるのは、企業結合してお互いに対価を決め合うときに、例えば訴訟が起こっていて、その訴訟で負けてお金を払わなければならない可能性が幾らかあって、合併会社がそれを引き受けるから、被合併会社はその対価として何がしかの金額に合意するとすると、どのような基準を算定根拠にするかは別として、そこでそのようなものが対価に反映されているのであれば、それはつかまえるべきではないかというのが基本的な発想として、この処理の根底にある考え方です。ですから、37号では偶発債務の認識は禁止しておりますので、この企業結合のときだけに限って対価のやり取りがあるということが明確な場合について、まずそれを認識しようというのが第1点です。
それで、この事後の測定ですけれども、これについては37号ではベスト・エスティメイトという考え方をとっておりますので、これと公正価値という考え方は基本的には違うわけですけれども、それで、以後は37号に戻るべきだと主張する方と、いや、そうではないんだという考え方の方がいまして、採決した結果、やはり違うものとして公正価値で引き続きやるべきだ考える人が多かったというのが結論です。一つの指摘された根拠は、ベスト・エスティメイトと公正価値というのは違う可能性があるので、当初測定時に公正価値で行っておいて、事後測定でベスト・エスティメイトにすると、その途端に差額が出てくる可能性があるので、ここは首尾一貫した方がいいのではないかというのが公正価値を支持する方の主張の根拠です。
- ○斎藤部会長
-
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
その点で少しお願いがあるのですが。このフェアバリューの意味が――ここでということではないのですが、将来伝えていただきたいという意味なのですけれども、偶発債務のフェアバリューの変動を大ざっぱに分ければ、見積りの変動部分とマーケットの環境による部分というのがあろうかと思うんですね。割引を使うということになると、どの変動のことを考えているのか、そっくりそのまま割引率も改定されるということを見込んでいるのかで随分話が違ってくると思うんですね。割引率は固定したまま見積りのところだけの変動ということなのか、それがはっきりしない。例えば長期性資産のコストや何かのところは分けていると思いますが、今回はいいですけれども、ぜひご確認いただきたいと思います。
- ○山田委員
-
わかりました。この前採決したときはそこまで議論を深く行っていませんでしたけれども、多分、公正価値を支持する方はどちらかというと金利割引率についての変動もその時点で考えているように私には感じられました。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はないでしょうか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほどの、負ののれんの即時利益認識と、リストラ引当金の問題についてですが。これは、結局、今のままですと、負ののれんの即時認識がもしあった場合には、利益の方が先に認識され、その後になってリストラ引当金が計上されるということは当然あるものなので、先に利益が認識されて後から引当金認識ということは費用が多くなるわけですから、これは今までの会計上のやり方からすれば少し奇異に感じる、あるいは、危険なやり方ということも言えるかもしれないので、ぜひともその点についてはもしIASB等がございましたら指摘していただいて、本当にこれでいいのかということをもう一度確認していただきたいと思います。
- ○斎藤部会長
-
辻山委員、どうぞ。
- ○辻山委員
-
山田委員からも先ほどご指摘がありましたけれども、山田委員もそうだと思いますが、SACでも全く同じ議論がありまして、ボードは全員それを聞いていて、なるほどなという反応は全然なしということでございます。基本的なフレームワークが、何のために何を計算しようとしているのかというそこから異なっておりますので、この議論は届かないということなんですね。ですから、そこのところの、最初の、何のために何を計算しようとしているのかというところ以外のところでは、彼らの耳には日本が間違ったことを発言あるいは議論しているということになる。山田理事にも繰り返し日本の考え方に沿って主張していただいているけれども、それが通じないという構造になっているのかなという感じを持っています。
- ○斎藤部会長
-
それはおっしゃるまでもなく、今のIASの議論というのはすべてそうですよね。すべてというのは、将来の利益を先取りしたような利益を計上したときに、言ってみれば、今利益を出せば必ず将来損失が出るというセットになっているわけですが、それは今利益を計上して将来は将来で損失を出せばいいという考え方ですべて一貫しているわけですよね。
八木委員、お待たせいたしました。
- ○八木委員
-
確認なのですけれども、山田委員の4ページ目の無形資産の減損のところに、減損の振戻しを行うというように書いてあるのですけれども、これは、アメリカでも減損の振戻しというのはない、われわれも、これは実務が大変になるので、減損をやる以上は慎重かつ着実にといいますかそのような実務でそこに踏み切ってやる、その振戻しがよしんばそのような状況にこれからなっても、ここら辺は変わらないのでしょうか。要するに、かなり確定的にこうなのかというところなのですが。
- ○山田委員
-
この振戻しについては、現在の36号が振戻しの規定を持っていまして、それをあえてこのケースについて否定する必要はないという程度の考え方だと私は理解していますので、今の八木委員の方からありました、実務上のことを考えると、むしろこれは非常に煩雑で必要ないということは私は存じ上げておりませんでしたので、機会があればそれを伝えたいと思います。
- ○八木委員
-
結局、ある決断で減損を行う。もちろん経営環境はどんどん変わるのであるわけですけれども、例えば振戻しをやるということは、定期的にそのようなものについてのある種の認識というか兆候の変化というそのようなものを絶えずフォローしていくのかということになると、ある段階で減損をやった、われわれはその段階でいろいろな責任においてそれをやるわけですが、そこから先はやはりまた次のことを前向きにいろいろ考えていくわけなので、減損の振戻しということがあるというのは、そのような別の実務がまた生まれるような感じも少しするものですから。絶えずそのようなものが義務づけられるわけではないと思うのですけれども、例外的なことなのかなとは思うのですが、この辺をよくご確認いただければなというように思います。
- ○山田委員
-
わかりました。これはあくまでも36号の枠の中なので、36というのは米国基準に比べますと減損を早く認識して、そのかわり原因がなくなったらもう一回戻すという考え方をとっていますので、そこと異なるということで、少し考えて、次回のときに問題提起できればしたいと思います。
- ○八木委員
-
のれんは償却しないということになっているわけですけれども、実務に携わっていてわれわれも減損をやらざるを得ないケースというのが一つ過去にあったわけです。それは10年近く償却した後だったのでその被害は半分ぐらいでとどまっていたのですけれども、実際このようなことになってみると、いろいろなものの考え方で非常に保守的な、ということは、ある意味では健全性を欠くようなものをずっとキープしておく、それと、今度は非保守的なある種の乱暴な、こうなんだ、こうなんだと思うことによって、早く減損を適用してしまう、そういった保守的なものと非保守的なものの振幅が非常に、経営者の感覚とか、そのようなものが広がっていくことが、この企業を今後は投資対象としてみられる方々にとって幸せなことなのかどうかというような感じもあるわけですね。
私は定期的な償却というのはやるべきだと思っているのですが、さっき少し斎藤部会長がお話になったように、私も無形も有形も今は例えば税務上の耐用年数で粛々と実務を行っているけれども、現実は大事にしてその倍ぐらい使っているものがあれば、こと志と違って、増加償却、臨時償却で償却してしまうのもあれば、いろいろなものがあるわけなので、そこら辺はのれんに耐用年数はつけられないだろうといっても、つけようと思えば私は理屈でつけられると思います。あるビジネスで買ったときに、必ずそのようなもので永久に持つものはありません。必ずある年数の中で回収していかなければならないと思って買収なんかもやるわけなので、そこのところが方法論的に無理だからやらないというのは理屈にならないだろうと基本的には思っています。この辺はアメリカなんかでもまたこのようなものというのはいろいろ変わっていくでしょうから、そのように主張し続けたいなというように思います。
- ○斎藤部会長
-
ほかにご発言はよろしいでしょうか。
黒川委員、どうぞ。
- ○黒川委員
-
先ほど私が言った、経済的耐用年数でみたらというのは、もし仮にわが国の償却というような実務、臨時償却あるいは経済的耐用年数の短縮というような実務と、もし仮にIASBが将来ずっと減損会計でいったときにそれをみなすことはできないのかというようなアイデアで言ったので、のれんについても同じようなことが言えないのかと思った――ただし、のれんには初めから耐用年数があるわけではないので、何かそのような年数のようなもので対応ができないのか。要するに、のれんを償却していって、でも臨時償却も含んでいるよ、あるいは、毎年もし仮に何年というようなものの短縮があるようなものでということでいけば、償却という手段と減損というものは何か読み替えることができないのかしらという意図もあって少し積極的というようなことを言った次第です。
- ○斎藤部会長
-
わかりました。要するに、今のご議論を多少カリカチャライズして言えば、仮に耐用年数の見通しが短くなったというときに、減損の考え方は、まずその年度で落としておいて、従来と同じ償却のペースを短くなった耐用年数まで続けるというやり方、それが減損ですね。それに対して、今、黒川委員がおっしゃったのは、その年度に一気に落とさないで、短くなった耐用年数に合わせてその勾配を変えていくということですので、それは普通は償却の範疇に入るだろうということを先ほど申し上げただけであります。
ほかはよろしゅうございますでしょうか。
大日方委員、どうぞ。
- ○大日方委員
-
これももう既に繰り返されていることなので確認なのですけれども、今後の日本の議論を左右するので確認しておきますが。
プーリング、パーチェスの適用範囲を巡る論点ということと、パーチェス法におけるのれんの会計処理ということを切り離して議論が可能というか、そのような意識――のれんのそういった方法とセットではなくて、プーリング、パーチェスの適用範囲という問題とのれんの償却問題というのは分かれて議論が可能かという点が一つ。
もう一つは、のれんの減損会計適用ということがここで繰り返されていますけれども、償却をした上で減損テストをするということはかなり受け入れがたい、海外からみておかしなことなのかどうか。つまり、減損をやるやらないということではなくて、やると、償却をした上でやるということに対して、海外ではオルタナティブにしてしまっているわけですが、償却するか減損するか。どちらかというとある意味では相当厳しめの方法になるのかもしれませんが、それは厳しいのだからそれなりにいいという評価を受けそうな気配があるのかどうかという、そのことがわかれば教えてください。
- ○山田委員
-
まず1点目のプーリングとパーチェス法の区分の議論はのれんの償却の議論と分けてできるのか、私はできると思っていますけれども、今のこのIASBの議論はプーリングをなくした後で議論していますので、結果としてイコールになっていますので、そのような観点での議論というのはほとんどしていないというのがお答えです。
2点目の、償却をした上で減損をやるということはいかがかということについては、まず償却の年数を決めること自身がアービトラリーだという主張が基本的にはありますので、この議論は――実は私は言っているのですけれども、ほとんど無理です。結局は、アービトラリーで決めて償却するとそれは意味がないので、価値が落ちたときに認識するのが妥当だと言っていますので、それをミックスするというのは、多分、最初の償却年数を決めるというところが障害になるのではないかと推測します。
- ○大日方委員
-
これも確認ですが、耐用年数を見積もることができないのに規則的償却をするというのはかなり弊害が大きいと、それで減損テストをやると、そのときにキャッシュ・ジェネレーティング・ユニットに多少裁量が入っても、そのことの弊害は規則的償却をする場合の弊害よりも小さいという理解ですか。
- ○山田委員
-
そこまで深い議論をしていないので、どう考えているかは私は推測の域を出ませんので何とも言えません。私が申し上げていたのはどのようなことかというと、のれんを減損するという処理だけだと、先ほど出ましたように、取得企業の自己創設のれんで置き換わっていて、置き換わったのがどの程度だったか全然情報がなくて、結果としてのれんの金額がそのままあがっていて、わからない人がみると、この結合は成功だったんだというようにみえてしまうことはないですかということが一つと、それをなくすためにはアービトラリーでもこの期間にわたってこの金額で償却しているということがわかった上で、さらにその減損を――その減損を行ってしまうとまた実は同じ問題が返ってくるのですけれども、しかし、少なくとも何年で償却するかということを決めておくと、どのような影響を損益計算書の中に与えているかは少なくともより透明性があるのではないのかなと考えているのですが、なかなかそのような考え方はいいと言う方はいません。
- ○斎藤部会長
-
ありがとうございました。
よろしゅうございますか。
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
今の大日方委員と同じようなことにも関連するのですけれども、アービトラリーという話が出たので。
のれんの場合は有効期限なしで減損適用で、戻し入れなしですね。似たようなもので、例えばトレードマークなどは法的な権利だから多分インタンジブルになると思うんですよね。そうすると償却年数が無限であるといったら減損適用で戻し入れ有りですよね。ある程度短い法的な権利というのは、償却年数が短くて償却可で、減損適用で戻し入れ有りですよね。非常にアービトラリーだと私は思いますが、このような議論は実際にボードでされているのですか。
- ○山田委員
-
されておりません。
- ○斎藤部会長
-
ですから、気がつかないで議論をしているのか、結論ありきで議論しているのか、そこはわからないわけですよね。
ほかにご発言は、よろしゅうございますでしょうか。
それでは、おおむね時間になりましたので、本日の部会はこれで終了させていただきます。次回の部会は4月19日(金)午後を予定しておりますが、詳細につきましては改めて事務局からご連絡申し上げます。
本日は、お忙しいところ、まことにありがとうございました。
これで散会させていただきます。

 検索
検索