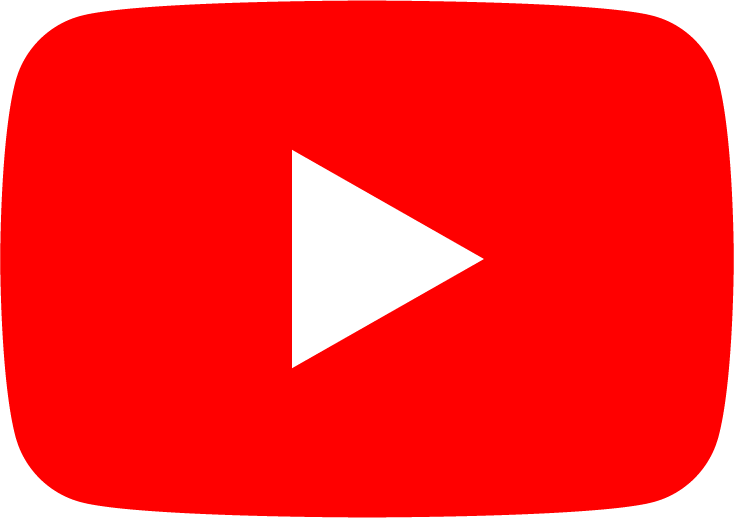- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「監査部会」
- 企業会計審議会第27回監査部会議事録
企業会計審議会第27回監査部会議事録
1.日時:平成24年6月27日(水曜日)16時30分~18時30分
2.場所:中央合同庁舎第7号館 13階 金融庁共用第一特別会議室
- ○脇田部会長
-
定刻になりましたので、これより第27回監査部会を開催いたします。皆様にはお忙しいところをご参集いただきまして、ありがとうございました。
まず、会議の公開についてお諮りしたいと思います。本日の監査部会も企業会計審議会の議事規則にのっとり、公開することとしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。ご了解いただきましたので、そのように取り扱わせていただきます。
それでは議事に入ります。前回はお2人の委員からご説明をいただきました。それを踏まえまして、近時の会計不正に対応するための公認会計士監査に関する論点につきまして、委員の皆様からご意見を伺いました。本日もお2人の委員と事務局から説明を行っていただいた上で、会計不正に対応するための、公認会計士監査に関する論点についての意見交換等を行ってまいりたいと思っております。
初めに、青山学院大学教授の八田委員より「企業不正に対する監査人の取り組みと課題」ということで、ご説明をお願いしたいと思います。
早速でございますけれども、八田委員、よろしくお願いいたします。
- ○八田委員
-
よろしくお願いいたします。
お手元に配付していただいております資料1に基づきまして、お話をさせていただきます。
話のポイントとしては、大きく3つの柱を考えております。その1つは、いわゆる企業不正をめぐる諸問題に対して、日本が範としている米国の会計監査対応はどうであったのかという、少し歴史を振り返るということがあります。そして2つ目の柱は、近時の我が国の不正問題に対する動向が、どのような状況にあるかということを確認させていただきます。そして最後に、前回から始まりましたこの部会が、今後検討するのではないかと思われる基準等の見直し、あるいはそれを見ていく場合の視点ないしは留意事項について、私見を述べさせていただきます。こういうことでお話をさせていただきます。
米国におきまして、この不正の問題がいわゆる表沙汰といいますか政治経済の場において議論になったのは、この2枚目に書いてありますように1977年の海外不正支払防止法の制定をもたらした、1970年代初頭のまさに政治スキャンダルとも言われましたウォーターゲート事件にありました。これがやはり米国経済社会における不正問題を考えていく場合の、嚆矢であろうと理解しております。
この1977年の法律では、いわゆる贈賄禁止規定に加えて、まさに会計と内部統制に関する規定をおいて、企業の健全なディスクロージャーを担保しようという流れがあったと理解しております。実はこれを踏まえてその後、金融機関におきまして内部統制の法規制が入り、ずっと時が下って、後でも出てまいりますが2002年の企業改革法において、公開会社における内部統制関連規定が入ったという、そのスタートになった事案なのであります。
3枚目に入りますが、米国の監査制度の流れを見る場合には、アメリカ公認会計士協会が主導的に担ってきた監査基準の設定における対応、これを見ていくことが必要であろうと考えます。ただ米国におきましては、1978年以降は監査基準審議会というところが制定していますが、その前は監査基準執行委員会というところが監査基準の解説書である監査基準書、いわゆるSASというものを制定しており、とりわけ不正をめぐる問題に対しての対応は、ここにも書いておきましたが、SAS第16号から始まって、その後第99号の説明にも入りますが、そこまでに順次、対応措置が高度化しているといいますか、あるいは取り組みについての詳細な規定が盛られるようになったというふうに理解しております。
前回の部会でも議論の対象になりました、例の「期待ギャップ」という議論がありますが、これが少なくとも正式に学術的な報告書において登場したのは、1978年にアメリカ公認会計士協会の中において設置された、監査人の責任に関する委員会、通称は議長の名前をとってコーエン委員会と言っておりますが、ここが公表した報告書の中で、それを認識したわけであります。そのギャップ、つまり齟齬はどこにあるのかという問題の一つが、不正問題に対する監査人側の考えと利用者側の考えに、違いがあるということです。
それと平行して、1977年にまずこの不正の議論を始めるに当たっての最初の監査基準書とも思われる、第16号が公表されております。これはコーエン委員会の作業と並行して財務諸表の不正の摘発を検討していた、今申し上げました監査基準執行委員会、監査基準審議会の前の設定母体でありますが、ここが公表しているわけであります。ここで特筆すべきは、確かに財務諸表の誤謬とか異常事項の発見に、独立監査人が一定の責任を有しなければいけないということは言っているのですが、その大前提として、少なくとも財務諸表の作成責任者である経営者は、まず正直なのだという前提で議論が進められていたということです。したがって、そこに監査プロセス固有の限界を強調したわけであります。
同様に、監査基準書第17号は、被監査会社の違法行為の問題を取り扱っております。ここでもほぼ同じように監査人は、専門家としての技術と注意を行使するならば通常発見し得るであろう、財務諸表に重要な虚偽記載をもたらす違法行為または疑わしき行為を摘発することはみずからの責任であるということで、一応監査人が全くこういった問題と無縁ではないということは表明しているわけでありますけれども、必ずしもそれ以上の深掘りした対応にはなっていなかったというのが、この1970年代の事案なのであります。
時が下りまして1988年、パワーポイントの5枚目でありますが、例の「期待ギャップ」というのが顕在したこともありまして、アメリカでは前の年、1987年という年が、アメリカ公認会計士協会創設、ちょうど100周年を迎えた年でありました。したがってこのころアメリカ公認会計士協会は、自分たちの協会が第二の世紀、つまり101年目を迎えるに当たって、さまざまな課題を克服しなければいけないということがあって、一つはアメリカ公認会計士協会の倫理規程の大改定をしたのであります。あるいは1988年には、9つの新しい監査基準書の公表を一気に行っております。このときのプロジェクトは、先般も出たと思いますが、いわゆる期待ギャッププロジェクトということで、その期待ギャップをいかに狭めるかということで複数の監査基準書が公表され、その中でも今日問題になっております不正に絡むのは第53号、第54号、第55号であります。
この第53号は、先ほどの第16号の延長線上にあります。したがってその違いだけを明確にしますと、ここで書いておきましたが、経営者は正直であるという従来の前提を取り払って、では、正直でないと言うのかというとそうではなくて、正直であるとか、ないとか、こういった予断を持ってはならないということ。言うならば、中立的な視点で監査を行わなければならないという方向が示されたわけです。その意味では監査人はより積極的な責任を負うことが、監査基準書上は要求されたというふうに指摘することができます。
ただ問題は、もう一つ第55号で、新しく内部統制の規定が盛られたことであります。これはその後、ご案内のとおりCOSOの内部統制の議論が始まってから役割は終えるわけでありますけれども、少なくとも、先ほど一番最初にご説明申し上げました海外不正支払防止法の中に、公開会社に対して内部統制関連規定が盛られたということがありまして、やはり不正問題はまずもって企業側において、内部統制との絡みでもって対応することが不可欠だという視点があり、それを踏まえて監査人も対応していくんだということがありますので、監査人は、財務諸表監査上はこの内部統制の有効性の評価が必要なんだということを、この第55号でもうたったわけであります。
この不正の問題はさらに1997年、少し飛びますが第82号という監査基準書においてさらに見直しがなされます。なおここでは、第16号あるいは第53号で用いられていたirregularityという言葉にかわりまして、fraudという言葉が使われるようになりました。第53号との違いを先に見ておきますと、第82号では、合理的な保証を得るためにより具体的な手続の実施を要求するとともに、明確に職業専門家としての懐疑心というもの、これを堅持することの重要性がうたわれたということです。
それと、先ほどのirregularityからfraudという言葉にかわったその理由は、幾つかの文献ではそれなりの評価等をしていますが、基本的にはより広いテーマで議論を進めようとした点があると思います。ただ、内容によってはこのirregularity、つまり異常事項が、投資家にとって財務諸表の不正を通じて損害を与えられるような状態になった場合、これがfraudなんだということで、仮にirregularityといっても、それが旧来のfraudと理解しても間違いではないという解釈もしているようであります。ただ、このfraudの議論というのは、後でも出てまいりますが1987年に公表された不正な財務報告全米委員会において、この「不正な財務報告」という言葉を示すときに、fraudという言葉が全面的に使われるようになりました。それを踏まえて、ここで置きかえがなされたのではないかという理解をしているところであります。
7枚目にまいります。時が下りまして21世紀、まさにエンロン事件あるいはワールドコム事件という、公開会社における会計不正事件が相次いで露呈したことを受けて、2002年7月には例の企業改革法が制定されるわけですが、それと平行する形で、監査基準書の第99号というのが公表になっております。ここの理解は、後ほどもご説明申し上げますが、日本の監査基準委員会報告書あるいは国際監査基準にも大きな影響を及ぼすことになっているということで、少なくとも旧来にも増して企業不正というものを根底から見直しをする、つまり不正とは一体何なのか、もっと言うならば不正を摘発することよりも防止するためには、どのような要因あるいは要素を抽出することで、それを防止するための施策を講ずるべきなのかという議論もありました。そこでは、それまで既にある程度年限をかけて研究されてきた1988年に創設の米国における公認不正検査士協会、ACFEが示してきている考え方が盛られています。次の8枚目に出てまいりますように、不正な財務報告全米委員会、通称、トレッドウェイ委員会が、止むことのない証券市場における不正をいかにして抑止、防止ないしは早期に摘発、発見できるかということのための検討を行って公表した報告書が1987年にあるわけですが、これを踏まえて、当時FBIの元捜査官の1人であるジョセフ・ウェルズという方が、経済社会における不正の抑止、防止ないしは発見に向けた、専門的知識を持った専門官の養成が必要だという認識から始まって創設に至ったのが、この公認不正検査士協会だということです。
ここが、これまで培ってきた不正に対する考え方の一つの仮定として、不正のトライアングルという考えがありますが、これは日本ではよく不正の三角形と呼ばれているもので、不正をもたらす3つの要因が結びついたときに不正というものが起きるというものです。その3つとは、よく知られているように、動機・プレッシャーがまずある。ただ、動機があってもそれを行うようなチャンスがなければなかなか不正を行わないが、そういった機会が与えられること。ただ、人間というのはやはり全員が悪人ではないですから、こういう問題が起きたときも、やはり自制心が働く。でも自分の中に、何かそれを正当化するような姿勢とかあるいは論拠があった場合には、それが不正に至ってしまう。こういう議論で、たまたまこの3つの視点を結びつけると三角形になるということから、不正の三角形というふうに言われています。もともとは1950年代に犯罪心理学者のクレッシーという方が考案したものを、その後ある程度汎用する形でつくられてきた考え方を導入したということもありまして、このSAS第99号の付録の部分でありますが、ここにこの考え方が示され、一気に監査の世界にこの考え方が伝播するわけであります。
日本も、基本的には今、この考え方を全面的に受け入れているわけであります。ただ後で申し上げますが、実はこれは個人犯罪をベースにした考え方であって、例えば組織的な犯罪とか、もっと専門的な知識を持っていなければできないような粉飾といった問題には、必ずしも十分に対応できないのではないかという視点もあって、もう一つ要素が加わるのではないかということで、例えば専門的知識を持った者がそこに介在しなきゃいけない、などということになると、今度は要素が4つになりますから、これをもって不正のダイヤモンドなどという議論も示されているところであります。
8枚目にまいります。今申し上げたように、アメリカでは止むことのない不正をいかにして防止するかという議論がありまして、「不正な財務報告」という報告書が出ました。ここでは、47項目にわたる改善勧告が発せられました。公認会計士協会に対して、あるいは規制当局に対して、あるいは教育機関に対して、あるいは企業に対してということでの勧告です。そのうち企業に対しての勧告の1つに、企業サイドは、統一的な視点での内部統制の整備・運用を推し進めなければだめなんだという議論があって、実は1992年、COSOと略称されるところの、いわゆるトレッドウェイ委員会を支えている団体ですが、ここが内部統制に関する統合的な報告書を出して、その後一気に全世界に伝播するという流れになったわけであります。
ただ1987年に「不正な財務報告」という報告書が出てから、ほんとうに米国の公開会社をめぐる環境の中で不正が減ったのか、あるいは監査上不正を見逃している状況は少なくなったのかということを集計した分析が、その後示されております。ここでは監査上の問題が中心になりますので、その一部だけをご紹介申し上げますが、9枚目をちょっと見ていただきます。
これは1987年から1997年、ちょうど「不正な財務報告」の全米委員会報告書が出た後、11年間にわたるSECの執行処分を受けた、つまり監査の問題が指摘された案件、これを理由によって分類したものであります。抽出された案件は全部で45件あります。そのうち監査上、不正が見抜けなかったということで欠陥が指摘された第1順位は、不十分な監査証拠の入手によって対応できなかった事案。簡単に言うならば、手抜きの監査をしていたということだと思います。そして2番目が、正当な注意の行使に対しての欠陥があること。これもよく言われるように、日本でも監査基準の一般基準にもあります、あるいは民法上の善管注意義務とか、これはもうプロとしてならば一丁目一番地的な議論で、注意義務を行使しなければいけないということですから、これが行使されていない場合には、やはり十分な監査が履行できていないということになります。
ここまではわかるわけですが、ここで特筆すべきは、3番目として、しかるべき水準の職業的懐疑心の保持に関して欠陥があったという事案が、半数以上あったということであります。これは1997年に示されているわけでありますが、まだまだ我が国では監査上、こういった監査人の精神的な議論、つまり職業的懐疑心とは一体何なのかよくわからないような、それによっても行政処分が下されているという事案があるということです。
実は正当な注意と違ってこの懐疑心の部分は、他のプロフェッションではあまり議論されていないものであり、最近でこそ監査人の行動のルールとして議論されていますが、なかなかそのレベル感がわからない、したがってこれはやはり明確にすべきではないかということが一つ、この不正の問題を議論していくときには出てくるのではないかなという気がするわけです。ただ、これは余談でありますけれども、我が国の公認会計士・監査審査会が、5年前でしょうか、私の理解によると1件だけでありますけれども、処分勧告をした文書の中に、この職業的懐疑心を保持していなかったという事案も指摘しているようですので、おそらく我が国においても監査上は現実の問題として、これは処分の対象になってくると理解せざるを得ないと思っております。
10枚目です。やはり監査制度のみならず、会計の議論をしていく場合にどうしても忘れてはならないのは、21世紀が始まって2001年から2002年に起きたエンロン、ワールドコムといった、まさに歴史に残る会計不正事件であります。これらからいろいろな教訓を、我々は得たわけであります。
一つは、やはりこの問題によってリスク・アプローチに対しての反省が起きたということも指摘できると思います。リスク・アプローチという、我が国でもこれまでの監査基準の改訂の一つの目玉として議論されてきていますが、その後米国で出ている幾つかの報告書によりますと、実はリスク・アプローチというのは、監査の効率性をかなり意識した考え方であって、有効性というものを少し度外視しているのではないか、それで結果的に十分な監査に至らなかったのではないか、というような議論も出ています。あるいは、やはりもっとリスクというものを検討して、それに応じた監査手続あるいは監査の対応をしなければいけないということから、このころから言われ始めたのがいわゆるForensic type Audit、これは日本では不正捜索型監査と訳しているようですが、これが正しいかどうかわかりませんが、このようなもう少し深掘りをした対応、まさにこれは先ほどのSAS第99号でも、そういう理解を示したわけであります。
先ほど申し上げましたようにこの第99号は、そういった意味ではまさに監査人をめぐる対応として、不正というものが監査人にとってもう無縁のものではないということを明確にしたという点では、その後の監査基準に関しても大きな影響を及ぼしているというふうに理解できます。それは我が国の監査基準委員会報告書、あるいは国際監査基準にも同じような問題があるということ、それから先ほど申し上げました例の不正の三角形に加えて、不正のダイヤモンドという仮定も今議論されていますので、今後日本でもこの議論は検証する必要があるのかなと思います。
ただ一つおもしろいことに、やはりこの企業不正をめぐる問題というのは、11枚目でありますが、ひとり会計士、監査人のみが議論する話ではないんだということ。やはり企業社会における健全化を担保するためには、各関係者の密な連携あるいは情報交換が必要だということがあって、アメリカではすべて民間組織でありますが、公認会計士協会、内部監査人協会(IIA)、そして先ほどご紹介申し上げた公認不正検査士協会(ACFE)、これらが2008年、共同提案という形でManaging the Business Risk of Fraud : A practical Guideということで、企業の不正リスクをいかに管理するかというための実務的なガイド、まさにこれは手続書と言ってもいいんですが、実務指針を公表しており、その中での中心的なテーマは、監査関係者の連携の必要性をうたっているわけであります。
最後に申し上げますのは、日本でもやはり企業開示、あるいは企業経営をめぐる監視の視点、モニタリングの視点からいくと、おそらく企業の内部で言うならば監査役もしくは監査委員会、それから内部監査、そして外部監査の会計監査人、こういったところの単なる言葉での三様監査ではなくて、もっと実効性ある対応が必要なのではないかと思います。ただこの企業不正リスク管理のためのガイドは、不正というものをもっと広く、会計だけに限定しているわけではありません。そんな議論があるということであります。
そこで大きな2つ目の柱の話としまして、日本の状況があります。これは、申し上げるまでもないと思いますが、日本公認会計士協会の監査基準書第35号ですが、これは2006年に制定され、今年の3月31日まで適用だったんですが、その後つい先般、監査基準委員会は新起草方針のもとにすべての体系を組みかえて、見直しをした結果、これは第240号のところに入っております。この第35号そのものは、2005年改訂の監査基準、それから一連の監査リスクモデルに関連しての委員会報告書を踏まえて、かつ国際監査基準をも参考にして対応されているものであるということ、そして公認会計士協会はさらに実務対応ということで、監査・保証実務委員会研究報告第19号も出して、それなりの対応もしてきたというふうに理解をしているところであります。
13枚目、監査基準委員会報告書第240号の特徴と背景であります。
特徴は、先ほどSAS第99号のところでもご説明申し上げましたように、不正に対応する特別に強い職業的懐疑心の保持について強調をしているところであります。それから、経営者等が信頼できても、不正の可能性を認識して監査手続を実施せよということが期待されていること、さらにはリスクの識別のための具体的かつ広範な評価手続を規定しているということもあります。
すでに申し上げましたので、この背景については、申し上げることはいたしません。要するにSAS第99号の流れ、また、第240号との関連です。
そこで私が考える、残されている監査規範の課題ということで、14枚目をご覧ください。我が国における不正問題に対する監査規範も、ご案内のとおりエンロン事件を経て制定された、国際的な監査規範へのキャッチアップに努めてきていることは事実であります。ただ、海外ではその後金融危機が起き、米国の監査基準は改訂され、また今まさに金融危機において監査人は果たすべき役割を果たしていたのか、監査のあり方を変える必要があるのかといった議論が行われているところであります。と同時に、国内でも昨年のオリンパス事件等を踏まえて、不正に対する監査がどうあるべきかといったことについて、改めて検討を行うことが必要ではないかと思われます。あわせて、近年指摘のあります循環取引といったものに係る、会計不正事案に対する監査人側の対応等についても、何がしか明確な取り組みを検討すべきではないかと思われます。これについては一部、日本公認会計士協会が会長通牒を発しておりますが、少なくともより規範性の高い形の基準として、議論することがあっていいのかなという気がするわけであります。
ただその場合に一つ懸念すべきこと、あるいは検討しなければならないのは、旧来私たち研究のレベルでも、教育のレベルでも考えていた監査というものの基礎概念、これをそのまま受け入れる形で見直しが可能なのかどうかということです。簡単に申し上げるならば、まさに従来の監査、とりわけ財務諸表監査は、いわゆる会計情報の信頼性の保証の監査であったということです。もっと簡単に言うならば、その背後に介在するであろう行為者あるいは経営者の社会から付託された受託責任、こういったものに対する整合性を十分に見てきたのかどうか、こういった行動、活動の結果、それらの写像すなわち会計の世界ではサロゲートなどという言葉を使う場合がありますが、その映し出されたものが会計情報であるならば、その背後に存する事象にまで監査対応が求められるのではないかという議論も考えられます。そうなってくると、監査概念の再定義が必要になるのではないか。そんなこともありますので、ここでは一応15枚目に、いわゆる、かなり古いですけれども監査に対する一般的な定義として、今でも教科書的には用いられておりますASOBAC、監査の基礎的概念報告書の中で示された議論を示しています。
これを踏まえますと、およそ監査というのはどういう特徴、意義、ないしは要件を持っているかというと、この16枚目にも該当しますが、共有すべき特質としては、やはり担当者の独立性、専門性、そして基準との整合性を検証するための基準準拠性に対する判断がどうあるべきか。そのための確たる基準が存在しているということが、重要な要因になるのではないか。それともう一つが、そこで示される意見表明が合理的な保証を持つということ。となってくると、少なくとも現在、不正という問題に対して、まだまだこれは今後議論が進んでいくと思いますが、明確な基準があるわけではない。そうすると、今回の部会でもしもこれを掘り下げていくならば、ある程度見える形の基準というものをつくり上げていく、これもひとつ求められるのではないかという気がするわけであります。
と同時に16枚目の下、ただこういった不正に対応するような監査というものが仮に求められ、そういう方向が是とされた場合であっても、担当者の側における不正教育、研修というのは当然に必要になってくる。ここに書きました4つの項目、会計的知識、法律的知識、不正調査の知識及び技法、犯罪学知識あるいは倫理関連知識、実はこれは先ほどから申し上げている公認不正検査士の、資格取得のための基本的教科項目の4つの柱であります。
17枚目、今後の見直しの視点であります。監査人の役割として、不正に起因する財務諸表の虚偽記載の有無を検証することにあるということを再確認すべきではないかと思います。
それから、監査人が不正に起因する財務諸表の虚偽記載を発見できるようにするため、監査人が行うべき監査手続を包括的に整理して、基準として示すことも一法なのかもしれないと考えられます。ただこの基準として整備する場合には、現行の監査基準を改訂するということも考えられますが、仮にこの監査基準に十分におさまり切らないというものがあるならば、会計リスク等に対応した監査の基準、あえてこれを不正対応基準ともし言うならば、そういうものとして整備し、それを日本の監査の基準として、いわゆる監査基準と一体のものとして適用するということも考えられる。その一つのヒントといいますか考え方は、2005年でしょうか、我が国における監査の品質管理に関する基準、これができたことで、より監査の質が高まったというふうに理解しておりますので、そのような取り組みもあるのかなという気がするわけであります。
18枚目。ただその場合であっても、監査関係者の連携の強化、これは当事者の意識にもかかわるわけでありますが、それが極めて重要であるということです。我が国の監査制度全体の実効性を高めるために、公認会計士、監査役、及び内部監査人の連携を強化すること。旧来から言われているように、単に三様監査という言葉で流れるのではなくて、個々人の能力と姿勢と感性、それから懐疑心、こういったものを十分に踏まえた上での強化という意味であります。
さらに、昨今指摘のある循環取引等、企業サイドでの共謀等に対処するためには、それに向かう監査人側においても連携等のあり方を検討すべきではないのか。ただこれは、同じ事務所でも担当者によって守秘義務があるかもしれない、あるいは事務所が異なればコミュニケーションのチャネルすらないという場合もあるかもしれない、さらには当然ながら、監査人の守秘義務というものが大前提になります。これがどのような場合に解除されるのか。これもやはり検討に値する問題ではないかと思うわけであります。
そして最後です。もしも基準を検討していく場合、幾つか留意事項があるのではないかということで、思いつくままに列挙いたしました。
1番目は、今日後半のほうでもご説明があるようですが、アメリカのPCAOB、2002年の企業改革法によって、正式にアメリカの監査基準設定機関として2003年以降制定しておりますが、米国PCAOBが、会計不正等への対応を含むリスク評価に関する監査基準ということで、監査基準の第8号から第15号までをセットとして公表しておりますので、当然これは我が国においても今後の検討対象になってくるだろうと思うところであります。
さらに先ほどから何度も申し上げていますように、不正リスクの要因分析に関する最新の研究成果についても、やはり参照が求められるのではないかということであります。
そして3つ目ですが、個々の監査人の行う監査手続にとどまらず、会計不正に対する知識の蓄積、ノウハウの集積、審査、不正対応の専門家、例えばフォレンジックの専門家、不正検査士などの活用など、事務所レベルでの対応を促進することも必要なのかなと思います。
と同時に、よく内部統制の議論がなされたときも言われたんですが、日本の企業風土とか監査の実態で、やはり国際的に一部違うところがあるということ。その辺を監査上も見極めるためには、日本公認会計士協会の監査実務指針等は、国際的整合性が重視されているとは言いますが、我が国の経済環境や企業風土、監査の実態等を踏まえた、我が国独自の監査の側面を加味した対応も求められるのではないか。
私は他にこれほど先駆的な不正に対する議論をしている場について、少なくとも浅学の身でありますが、知りません。しかし企業社会、あるいは社会の人々がこれほど不正に対する感度を持って期待をしているならば、一歩先行く日本の監査ということで、この議論を進めてもいいのではないかという気がします。
以上です。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
数多くの議論を呼ぶ論点を含み、ご説明をいただきました。時間に限りがあるので残念でございますけれども、ただいまのご説明へのご意見、ご質問は、これから林委員にご説明いただき、また事務局からもご説明いたしますので、それらと合わせてお願いしたいと思います。
米国では、2010年8月にPCAOB、米国公開会社会計監督委員会が、不正会計への対応を含むリスク評価に関する新しい監査基準を公表しております。つきましては関西学院大学教授の林委員より、新しい監査基準のポイント等につきましてご説明をいただきたいと思います。
林委員、よろしくお願いいたします。
- ○林委員
-
関西学院大学の林です。どうぞよろしくお願いいたします。
私からは、お手元の資料に基づきまして、先ほどの八田委員のご報告にございましたアメリカの公開会社会計監督委員会、PCAOBが2010年8月に公表した8つの監査基準の内容のうち、不正対応に関する規定を、日本の基準と比較するという形式でご紹介したいと思います。
早速ですが、スライドの1をごらんください。今回取り上げます8つの監査基準は、重要な虚偽表示のリスクの評価と、評価したリスクに対応した監査手続の実施に関連する基準ですが、この中に不正対応に関する規定が組み込まれております。
資料の中の太字の括弧書きは凡例を示しております。【pCAOB Release】といいますのは、これらの8つの基準公表の背景、それから監査基準第8号から第15号そのもの、それに対して議論、審議の過程で寄せられたコメントの紹介と解説などを含む文書です。
それから3つ目の【AU Section 316】は、これも先ほど八田委員からご紹介がありましたアメリカ公認会計士協会の監査基準書第99号です。この基準は、現在PCAOBの暫定的な監査基準として位置づけられております。これらを適宜参照しながら、ご紹介を進めてまいります。また日本の比較対象となります基準は、主に監査基準委員会報告書第240号でございまして、お手元に資料として配付されております。
それでは次のスライドに進みます。これらのリスク評価・対応監査基準の目的と背景でございますが、これら8つの基準は、国際監査基準や我が国の監査基準で既に導入されている事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチ、これを導入することを目的とするものでした。その背景は4つ挙げられるかと思いますが、グローバル金融危機や監査のグローバル化、あるいは4つ目に掲げておりますけれどもPCAOBのインスペクションによる検出事項というものが、念頭に置かれているようです。
スライドの3枚目には、監査基準書第8号から第15号のタイトルと、主な内容を要約して示しております。
これら一連の監査基準は、重要な虚偽表示のリスクを適切に識別・評価し、リスクの程度に応じた監査を実施するということを要求するものです。なおPCAOBは、不正を原因とする重要な虚偽表示のリスクを、不正リスクと呼んでおります。先ほども申し上げましたように、PCAOBは不正対応基準であるAU Section 316の要求事項の一部を、これらのリスクの評価と対応に関する基準に組み込んでおります。これは、不正リスクの評価とそれへの対応は、PCAOB基準に準拠した監査の必須の部分でありまして、別個の検討事項ではないということを強調することを意図したものと考えられます。この背景には、PCAOBがその検査活動において、監査人が個々の監査業務に応じた不正リスクへの対応を行わず、AU Section 316において要求されている監査手続を機械的に実施したのではないか、あるいは識別した不正リスクに適切に対応できなかったのではないか、こういう事例を確認したことによるというふうに言われております。
これ以降は、基準ごと、規定ごとに日本基準との比較を行っていきたいと思います。スライドの4にお進みください。これ以降は、最初に日米の比較に基づくポイント、特徴というものをお示しし、その下に関連する日米の基準を引用するという形をとっております。
まずここでは、監査計画に関する基準におきまして、米国では不正調査、フォレンジックの専門家を利用する必要があるかどうかを決定するということが、明示的に求められております。日本の基準にも、下に書いておりますとおり不正調査の専門家という文言はございますが、例示の域を出ておりません。ただしこの要求は、すべての財務諸表監査に一律に不正の専門家を関与させることを意味しているわけではございません。PCAOBのリリースにおきましても、どのような種類の専門家が必要であるかは、個々の監査業務あるいは個々の監査チームの状況に左右されるものであるという考えが述べられております。また実態としましては、各事務所が定める一定の条件に当てはまる場合に、専門家の関与を求めるということになっているようでございます。
スライド5にお進みください。次に監査業務の監督についてですが、アメリカでは業務担当パートナー及びその他の監査業務を監督する役割を担う者の責任が、明確に示されております。アメリカの基準に示されている3つの事項が箇条書きになっておりますが、このうち日本と米国の基準が異なるのは、2つ目の太字でアンダーラインを付しているところでございます。これは、スタッフレベルで重要なことを判断せずに、パートナーレベルと情報を共有せよということでございます。日本では、おそらくこれは監査チーム内での一般的なコミュニケーションに包含されているのではないかと思われますが、明確な指示の規定はございません。またアメリカでは、冒頭にも書いておりますとおり、業務担当パートナーの責任だけではなくて、監査業務を監督する役割を担う者の責任としても、これらが明示されております。日本の監査基準では、監査業務を監督する役割を担う者に関する規定は、ほとんど用意されておりません。
次のスライド6は、日米に共通する対応でございます。業務担当チームの主要なメンバーは、不正による重要な虚偽の表示の可能性について協議せよということが、明確に求められております。その内容としましては、不正リスクに関する意見の交換、ブレーンストーミングを行うこと、不正リスク要因を検討すること、経営者が内部統制を無効化するリスクを検討することなどが求められております。
ちなみに、しばらくこのAS12というのが続きますが、これは重要な虚偽表示のリスクの洗い出し、すなわち財務諸表のどの部分ないし項目に、どのような虚偽の表示が、どの程度の可能性で発生しそうか、ということを洗い出すプロセスに関する基準でございます。
次へお進みください。スライド7です。ここでは、不正に関する職業的懐疑心の発揮についての違いを示しております。アメリカでは、職業的懐疑心の発揮について具体的な事項が示され、その必要性が強調されております。スライドの3つの箇条書きのうち、2つ目と3つ目が特に相違点かと思います。日本には、職業的懐疑心の発揮に関する一般的な指示はありますが、具体的な対応というのは示されておりません。
なお、申しわけございませんが、1点修正をお願いいたします。3つの箇条書きの真ん中の文中の括弧書き「AS12」となっておりますが、これは「AS14」の間違いでございます。14にご訂正をお願いします。申しわけございません。
それでは、次のスライド8に進ませていただきます。ここはまだAS12、リスク評価の段階ですが、米国では不正による重要な虚偽表示のリスク、すなわち不正リスクの識別・評価に当たって、不正リスク要因を考慮するということが明確に求められております。不正リスク要因の例として、下に2つ挙げておりますのでごらんください。
米国では、監査人は、リスク評価手続により入手した情報が不正リスク要因の存在を示すかどうかを評価して、不正リスクの識別・評価に当たって当該不正リスク要因を考慮することが求められていますが、日本にはこの後段に相当する不正リスク要因を考慮せよという規定がないという違いでございます。おそらくこれは、当然考慮するという解釈ではないかと思うのですが、とにかく文言としては挙がっていないという差異でございます。
次へ進みます。スライド9からはAS13号でございます。これは、先ほどまでのリスク評価で洗い出したリスクに対応する、プロセスに関する規定でございます。ここは共通の内容でございますが、日米ともに重要な虚偽表示のリスクへの全般的対応として、被監査会社が予測不可能な要素を組み込むということが求められています。監査人は、重要な虚偽表示のリスクの評価に際して、経営者の主張ごとの重要な虚偽表示のリスクを評価するだけでなく、財務諸表レベルの重要な虚偽表示のリスクを評価することが求められています。そして全般的対応と申しますのは、財務諸表レベルの重要な虚偽表示のリスクへの対応を意味します。例えば、経営者の適正な財務報告や内部統制に対する態度、姿勢に問題がある場合、あるいは経営者による不正な財務報告のリスクがある場合には、そこから財務諸表レベルの重要な虚偽表示のリスクが生じるというふうに考えられます。
ここで言います予測不可能な要素の具体的な内容は、スライドに4つ、小さな箇条書きで示しておりますが、抜き打ちの監査手続の実施といいますのは、アメリカの基準にのみ示されている内容かと思います。
あと少し細かい点ですが、この規定は、内容は一緒なんですけれども、日本では「不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した全般的な対応」として求められておりますが、米国では「不正による」という言葉が抜けておりまして、一般的な重要な虚偽表示リスクへの対応という形での要求となっております。
スライド10にお進みください。日本もアメリカも、重要な虚偽表示のリスクへの監査人の対応において、懐疑心の重要性が強調されております。懐疑心が出てくるのは2回目となりますが、このように強調されております。ただし、スライド7でご紹介しましたとおり、アメリカではこの懐疑心の適用に関して、具体的な記載がなされております。
スライド11にまいります。重要な虚偽表示のリスク、不正リスクへの対応における職業的専門家としての懐疑心の適用に関して、ここでも米国のほうが厳格に記載を行っております。職業的専門家としての懐疑心の適用例としまして、米国では、より信頼できる監査証拠を入手するために、計画した監査手続を変更する、重要事項に関する経営者による説明を裏づけるために、第三者への確認、専門家の利用または独立の情報源からの文書資料の検証により、十分かつ適切な監査証拠を入手する、ということが示されております。日本の基準にもこれに相当する記述はございますが、米国に比べると少し弱い記述となっているというふうに評価できます。
スライド12にお進みください。ここで監査手続、実証手続のことが出てまいります。米国では、財務諸表監査における不正リスク対応として、不正リスクに明確に対応する実証手続、特に詳細テストの実施が強調されております。実証手続と申しますのは、アサーション・レベルの重要な虚偽表示を看過しないように立案、実施する監査手続を言いまして、詳細テストと分析的実証手続からなると定義されております。
日米の記述を比較しますと、アメリカでは不正リスクに明確に対応することと、詳細テストを実施することが強調されているという違いが確認できるかと思います。おそらくこれは、監査の有効性の向上を志向したものではないかと理解しております。
スライド13にお進みください。経営者不正に対応する監査手続の実施が、日米共通の不正対応として要求されております。監査人は、経営者が内部統制を無効化するリスクに対する評価にかかわらず、スライドに示しております3つの箇条書きのような監査手続を計画、実施しなければならない、このように要求されております。
スライド14にまいります。ここでリスクの評価と対応から少し先に進みまして、入手した情報の評価、監査結果の評価のプロセスに進みます。
米国では、監査実施の過程で入手した情報を踏まえて、不正リスクに対応するために監査手続を修正する必要があるかを検討することが、明示的に求められております。監査人は、監査手続の累積的な結果及びその他の所見が、監査を通じて行われる不正リスクの評価に影響するかどうか、それらの不正に対応するために、監査手続を修正する必要があるかを評価しなければならないと求められているのですが、日本にはこれに相当する規定はございません。ただ前ページ、スライド13で、経営者による内部統制の無効化のリスクを識別した場合には、監査手続の追加の必要性を決定することが求められておりまして、少しここに関係する内容かと思います。
スライド15をごらんください。これも監査結果の評価にかかわる規定でございます。日本もアメリカも、少しタイトルは異なるのですが、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況というものが、基準の中に例示されております。米国基準では、これを不正リスク評価において考慮せよと明示的に要求が示されておりますが、日本にはこれに対応する要求事項というのはございません。不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況としては、アメリカの例示をご紹介をしております。
次へお進みください。スライド16でございます。このスライドと次のスライドは、AS15、監査証拠というタイトルの基準でございます。文書、記録や証憑書類が真正ではないか、または文言が後から変更されているが監査人に開示されていない可能性、疑いがある場合、日米についての規定を比較いたしますと、計画した監査手続を変更するか、または監査手続を追加実施しなければならない、また監査の他の局面への影響を検討しなければならないという規定のうち、前段部分に違いがございまして、米国のほうはこの状況に関して明確な要求を示しております。
続きましてスライド17をごらんください。これも先ほどと同じく証拠の評価にかかわるものですが、米国で一つ重要な姿勢の変化が生じております。米国の規定では、監査の過程で入手した資料等を監査人が評価する際に、「監査証拠による反証がない限り、通常、記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる」という規定が削除されております。日本基準でも、あるいは国際監査基準でも、さらに従来のアメリカの基準でも、先ほど申し上げました反証のない限り真正なものとして受け入れるということが前提とされておりましたが、今般このAS15によりまして、このような表現は、より一層の不正対応を求めるという規定の要求を弱めることになるという理由で、削除されております。
最後のスライドになります、18枚目をごらんください。以上の内容を踏まえまして、PCAOBのリスク評価・対応基準の特徴を、私なりに3点指摘させていただきたいと思います。
まず1つは、財務諸表監査における不正に対する心構えが、より一層強調されているということです。米国基準では、不正対応は財務諸表監査における基本的考慮事項として明確に位置づけられました。また職業的懐疑心の発揮も、従来よりもさらに一層強調されております。
2つ目の特徴は、不正に対する具体的な対応が、かなり細かいところも含みますが、明示されたということでございます。例えば不正リスクの識別と評価、業務担当チーム内のコミュニケーション、不正調査の専門家の利用、詳細テストの実施などが書き込まれております。
最後、3つ目は、少し1つ目と重なる部分がありますが、不正対応に関する基準が、従来からの財務諸表監査に関する基準に組み込まれたという点です。AU Section 316「財務諸表監査における不正の検討」に規定されていた不正対応の内容が、ここでご紹介しましたリスク評価・対応の監査基準に組み込まれております。これはいわば本論と特論、原則と例外というような位置づけ、形式をやめることによって不正対応を強調するということが意図されているのではないかと考えております。ただし、実質的な監査手続への影響といいますと、不正リスクまたはその兆候が識別された場合のみに生じると考えられます。したがって、財務諸表監査の基本的な性格まで変更されたというわけではございません。あくまでも、リスク評価の結果に適切に対応するということが求められる規定となっております。
以上、簡単ですが、私からの報告を終わります。ありがとうございました。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
続きまして、公認会計士監査をめぐっては海外においても多様な動きがございます。事務局より公認会計士監査をめぐる海外の動向等について、説明をお願いしたいと思います。
- ○栗田企業開示課長
-
それでは私からは、資料3-1と資料3-2に基づいてご説明をさせていただきます。
まず資料3-1の表紙をめくっていただきまして、1ページ目でございます。これは会計監査をめぐる動向ということで、ここ20年余りの欧州、米国、日本における動きをまとめたものでございます。ざっくり申しますと、この監査に関しましては米国でいろいろなことがなされて、日本はそれをキャッチアップするような形で、これもまたいろいろな取り組みをやってきたということでございます。片や欧州のほうは、しばらくあまり動きがなかったんですけれども、ここに至って少し動きが出てきたということでございます。
私からは、この年表のうち欧州の下のほう、ECのグリーン・ペーパー以降の話と、米国の2011年のPCAOBのコンセプトリリースについて、ご説明させていただきます。
1枚めくっていただきまして、ECによる監査に関する規制案ということですが、これはまず2010年10月にいわゆるグリーン・ペーパーというものが公表されまして、市中協議を踏まえまして翌年の2011年11月に「財務諸表に対する信頼性を回復するための監査に関する規制案」というものが公表されております。その内容につきまして、参考資料の2ページをごらんいただければと思います。
ここにグリーン・ペーパーの中の主な提案を9つほど書かせていただいておりますけれども、このうち市中協議の段階で、共同監査の義務づけ、監査法人に対しての当局による監査報酬の支払い、過去の監査法人の合併の解消という3つが消えまして、残りの6つを中心としたものが新しい規制案として公表されており、現在それが欧州議会にかけられているという状況でございます。本監査部会の関連で申しますと、監査報告書の改訂、財務諸表の重要なリスク等に関して記載するというようなことが、このECの規制案には盛り込まれているということでございます。
それからそれに関連いたしまして、イギリスのほうでは2012年4月に、資料3-1の2ページの注に書かせていただいておりますけれども、FRCが、FTSE350企業を対象として、少なくとも10年に1度は監査契約を公開入札するか、入札をしないならばその理由を株主に説明せよという、いわゆるコンプライ・オア・エクスプレインの発想で改革案を公表して、コメントを募集しているところでございます。
1枚めくっていただきまして、次はイギリスの監査基準設定主体が出しております職業的懐疑心に関する報告書というものでございまして、これは2012年3月に公表されたものでございます。その概要はそこに3つほど書いてございますけれども、監査において職業的懐疑心を発揮するということが具体的にどのようなことを意味するのか、ということを例を挙げて説明している。それから2番目としまして、監査において職業的懐疑心が十分に発揮されるために、個々の監査人、監査チーム、監査法人等がとるべき対応について、具体的に列挙されている。さらにそれを踏まえてイギリスの監査基準設定主体として、今後の対応はどうするかということが説明されております。
参考資料のほうの5ページ目以下でございますが、若干中身をご説明させていただきますと、5ページの真ん中当たりに「詳細」と書いてあるところからでございます。まず職業的懐疑心の発揮は具体的にどのようなことを意味するのかということで、幾つか書いてございます。まず1番目として、重要な虚偽記載をもたらすリスクを積極的に発見すべく、リスク評価プロセスにおいて、監査人は経営者の主張を批判的に評価しなければならないということが書いてあります。それから4番目には、経営者の主張を裏づける証拠を経営者が見つけることができたか検証するための監査手続を監査人は立案するのではなく、経営者の主張と矛盾する証拠が存在していないか、積極的に検討するための監査手続を立案すべきであるというようなことが書かれております。
それから1枚めくっていただきまして(2)でございますけれども、こちらは職業的懐疑心が十分に発揮されるために、どういう対応がとられるべきかということにつきまして、個々の監査人、監査チーム、監査法人、会社の監査委員会ということで分けて書いてございます。ここにもかなり興味深いことが幾つか書いてございまして、例えば
 個々の監査人がすべきことということで、2番目以降、懐疑心を持ち、経営者の主張に説明を求めることに抵抗を持たない、監査の過程で入手した情報及び説明を批判的に評価し、それらを裏づける、財務諸表の虚偽記載をもたらす経営者の動機を理解する、認識された乖離や虚偽表示の内容や原因を詳細に調査する、他の監査証拠と矛盾したり、入手された文書や質問に対する回答の信頼性に疑義をもたらす監査証拠の存在に十分注意を払う、というようなことが言われております。
個々の監査人がすべきことということで、2番目以降、懐疑心を持ち、経営者の主張に説明を求めることに抵抗を持たない、監査の過程で入手した情報及び説明を批判的に評価し、それらを裏づける、財務諸表の虚偽記載をもたらす経営者の動機を理解する、認識された乖離や虚偽表示の内容や原因を詳細に調査する、他の監査証拠と矛盾したり、入手された文書や質問に対する回答の信頼性に疑義をもたらす監査証拠の存在に十分注意を払う、というようなことが言われております。それから監査チームがすべきことといたしましても幾つか書いております。例えば2番目でございますが、不正及び誤謬に基づく虚偽記載が、どのような状況で、どういった会計処理に基づき起こり得るのか積極的に検討する、異常な事象や取引を識別できるようになるため、企業及びそのビジネスに対する理解を含め、その情報を共有する、パートナーやマネジャーは企業及び企業環境の変化を考慮し、それを踏まえた監査手続を立案する、不正や関連当事者の悪用等による重要な虚偽記載の財務諸表への影響について議論するため、パートナーやマネジャーは監査計画段階のチームミーティングに参加し、積極的に議論をリードするということで、かなり詳細な手続を求めているということでございます。
それから監査法人がすべきこともいろいろ書かれておりますけれども、例えば2番目では、懐疑心は監査法人のトレーニングに組み込まれ、またパートナーやスタッフの業績評価基準に組み込まれているということを強調しております。さらに1つ飛んで、監査法人の監査メソドロジー及びレビュープロセスは以下の点の重要性を強調するということで、ここも幾つかポイントが書かれております。上のほうからいきますと、監査人が独自の視点で厳格なリスク評価を実施することが可能となるよう、企業のビジネス及び経営環境を深く理解する、監査計画の早い段階で問題を特定する、異常な取引を識別するために財務報告システムの規模及び複雑性に見合った手続を厳格に実行する、監査上の発見事項に対応する形でリスク評価、重要性の基準値、監査計画を見直す、そういうようなことが幾つか書いてございます。
それから1ページめくっていただきまして、企業サイドの監査委員会及び経営者の役割についても言及がございまして、例えば一番初めですと、監査人から質問を求められた際に、経営者や従業員が建設的に応対するような組織風土を促進するですとか、4つ目のところですと、監査委員会へ報告が行われた問題点について、監査委員会は監査人が十分深い検討を行ったか否かを理解するよう努めなければならないということで、企業サイドの対応も求めているということでございます。
それから(3)のイギリスの監査基準設定主体の今後の対応といたしましては、そこの2つ目のパラグラフにありますように、今後の対応として、短期的には財務諸表監査の過程で職業的懐疑心が一貫して発揮されるよう、監査人等の行動に大きな変化をもたらすことに重点が置かれるべきであると結論づけられております。
イギリスの報告書の概要はざっと以上でございまして、もう一度資料3-1の4ページに戻っていただきまして、今度はアメリカのほうでございます。
まず初めに、2011年6月に公表されました監査報告書の改訂に関するコンセプトリリースということで、ここでもかなり踏み込んだ提案がなされてございます。ここには4点ほど書かせていただいておりますが、監査人の検討と分析の記載を新たに求めるということで、具体的には、監査に関する情報として監査において識別された監査上のリスク、あるいは企業の財務諸表に関する監査人の見解として、経営者の判断、見積もり、会計方針等について記載することを求めている。それから強調事項パラグラフの義務づけと拡大を求める。3つ目といたしましては、財務諸表外のその他の情報に対する監査人の保証を求める。4つ目といたしまして、標準監査報告書の文言の明瞭化を求める。ということでございまして、かなり踏み込んだ提案がなされております。この点につきましては今後7月から9月に公開草案を公表して、来年の4月から6月に最終基準化、または再公開草案の公表が予定されているということでございます。
1ページめくっていただきまして5ページは、2011年8月に公表されました法定監査人の独立性及び監査法人のローテーションに関するコンセプトリリースでございます。法定監査人の独立性、客観性及び職業的懐疑心を強化するための方法に関して、関係者から意見を募集するということで、その具体的な方法の一つとして、監査法人のローテーション制度の導入を提示しているということでございます。
参考資料のほうに行っていただきまして、15ページ以下でございますが、これは前回の会議で若干議論がありました監査の報酬の関係について、日米の違いをまとめたものでございます。日本はどうなっているかと申しますと、日本公認会計士協会が作成されておりますひな形がございまして、それはこの後ろにつけてございますけれども、その中で、監査報酬の額は幾ら幾らと一般的に明示するような形になっております。監査において追加手続が発生したような場合の対応につきましては、監査約款の第13条に規定がございまして、「監査執務の時間数が予定を超えることとなった場合には、受嘱者はあらかじめ契約した報酬額の改定を申し出ることができるものとし、この場合には双方誠意をもって協議するものとする」という取り扱いになっております。
片や米国はどうなっているかといいますと16ページでございます。こちらも米国の公認会計士協会がつくっている一種のひな形のようなものがありまして、仮訳と書いてあるところでございますけれども、「監査報酬は監査の実施に必要となる時間を基準として算出される」ということが明示されておりまして、当初の契約書においては当初見積金額が記載されるというような取り扱いになっているようでございます。その後、監査人が想定外の状況に直面したような場合はどうなるかといいますと、17ページに仮訳をつけさせていただきましたけれども、こうこうこういうような事案が発生したので、追加的な手続が必要になったということが書かれていまして、その後に「追加の監査報酬は当法人の標準単価に基づき計算され、当初の監査契約書に記載された監査報酬に加算される」ということで、これだけ時間数が増えたので、これだけたくさんくださいという一種の請求書みたいなものが来るというような扱いになっておりまして、日本と違ってかなり、監査時間が延びるとオートマチックに監査報酬が増えるような形の契約体系になっているという形でございます。
私からは以上でございます。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
それぞれのご説明の中には、会計不正対応につきまして、いろいろと議論しなければならない多くの論点が含まれておりました。時間の許す限り、これにつきまして皆様方のご議論をいただくことになりますが、先ほどの八田委員、林委員、事務局からのご説明を踏まえまして、どうぞ委員の皆様方から、近時の会計不正に対応するための公認会計士監査に関する論点について、ご意見を伺ってまいりたいと思います。時間に限りがありますけれども、どうぞご自由にご発言を、順次お願いしたいと思います。いかがでございましょうか。
前回は私が終了時間を気にいたしまして、どうも委員の皆様方のご発言を見落としてしまったりしまして、大変失礼をしましておわびいたします。今日は林田委員がお見えになっておりませんけれども、前回林田委員からの問いかけのご発言がございました。この点につきましてご発言いただけるとありがたいのですが、いかがでございましょうか。
泉本委員、お願いいたします。
- ○泉本委員
-
ありがとうございます。
前回、林田委員から会計士の使命感ですとか、監査時間を増やしたら報酬が増えるのでしょうかというご発言がありましたので、簡単にご説明したいと思います。
まず使命感ですが、なかなか前回事例にありましたように、何か不正を見つけたときに使命感を感じるというよりは、不正というのは、そういつも、年がら年じゅう遭遇するわけではございません。基本的には公認会計士法の第1条と第1条の2のところに使命と職責が書かれていますが、その中で、「会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする」と書かれてございます。私自身は、実際に担当している目の前の会社が、内部統制の不備ですとか、内部統制の仕組みが悪くて効率が悪いということに遭遇したとき、それらの改善策を提案して、会社がよりよくなっていくというところに、監査業務のやりがいがあるなと感じてございます。
今申し上げましたように、不正事例について、最近は新聞記事やニュースが多いですけれども、実際の監査人が不正事例に遭遇するのはそう多くはないと思います。従業員不正や使い込みといった多額でない事例は時々ありますけれども、今回のO社の事案のような経営者不正は、多くはございません。逆に、多くあったら多分日本の証券市場が崩壊しますので、ないというように思います。
監査手続と報酬の関係ですが、例えば今申し上げたような従業員不正を監査人が発見した場合ですと、会社経営者は徹底的に見ていただきたいとか、内部統制の改善策を見てほしいということになります。先ほどご案内があったように日本の監査報酬は、まず最初に監査報酬は今年度幾らですと決めることからスタートするのが前提ですけれども、その上で監査時間の大幅な増加があったとしても、ここの分もしっかり見てくださいという経営者側の利害と一致した場合には、追加報酬の交渉ができることが多いのではないかと考えています。しかし、O社事案に代表されるような経営者不正になりますと、特定の部門だとか支店ぐるみで経営者不正があった場合には、監査人がたとえ、そのような不正の兆候をつかんで監査時間を増やそうとしても、監査を受ける側の会社とは立場が逆転していまして、会社はそれを隠そうとしますので、監査人の監査時間の増加が歓迎されないということになってしまうと思います。
もう一つの視点ですが、監査人が不正について兆候があるとつかむことができれば、私たちは監査意見の表明にどこまで影響するかわかりませんから、徹底的に監査時間を増やすことをしなければなりません。監査法人にも協力を得た上で手続を増やすことになると思いますが、それよりも実際の監査現場では、まずは、兆候なのかどうかということがわからない、何かおかしいということに気がついても、何が、どうなっているのか、どこがおかしいのかというところが判然としないというのが、多分一番もどかしいところだと思います。監査役がおかしいところに気がついて、私どもの監査に協力が得られる場合はよいのですが、会社ぐるみの経営者不正であれば、そのような協力も得られず、また入手した監査証拠が取引先との共謀や改ざんで誤ったものとなっているかも知れず、どのようなところにどこまで時間を増やしてよいのか、どういう手続を増やす必要があるのかというところがなかなか決め切れず、当初の監査計画よりも相当なところで手続を増やすようなことにもなるかもしれません。そこの部分の監査時間の増加は、経営者が会社は正しいと言い張っている間は、報酬の増加の交渉はできないと思います。
しかし不正の兆候をつかんだ限りは、先ほど申し上げたように私どもは徹底的に調査するしか、監査意見を出せなくなってしまいますので、報酬が得られないということをもって途中で監査をやめる、あきらめるということはございません。監査意見が出せると判断できるまでやるしかないという、それが翻ってみますと、会計士の使命感ではないかと考えています。
また、不正が明らかになって、過去の財務諸表を訂正すると会社が決めてくださると、それは楽になります、ただ、時間との勝負になりますが、徹底して過去の不適切な取引を洗い出しますので、そういう不正が明らかになってしまった後の訂正監査というのは、少し場面が違うと思います。訂正監査となると別契約でございますので、報酬は別の契約として、できるようになります。
ということで、通常の監査契約の中で不正の兆候を見つけたり、不正かなという怪しいサインを見つけたときには、なかなか監査手続も制約されて厳しいのではないかというところが、前回林田委員からいただいたことに関しての私の感想でございます。
以上です。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
積み残したようで、私として気になりましたので、ご発言いただきました。
それでは、布施委員どうぞ。
- ○布施委員
-
ありがとうございます。
前回の積み残しに関連するのですが、前回の審議会では林田委員から現場の視点からというお話もございましたので、私から現場の視点から経営者不正への監査対応の難しさについて、ご説明させていただきたいと思います。
基本的には2つの視点から述べますが、1つ目はそもそも経営者不正を発見することがなぜ難しいのかという点、それから不正の兆候を把握した後の監査対応の難しさの2点を中心にご説明させていただきたいと思います。
まず不正発見の難しさについてですけれども、通常このような経営者不正が行われるケースでは、監査人対策というのが会社側でできているということでございます。例えば取引の実在性を示す証憑類が整備されている、これは偽造されていることもありますけれども。また、口裏合わせが行われているとか、あるいは取引の相手が外観上は関連当事者に該当しない第三者であるけれども、経営者と何らかの関係を持っているというような場合、さらには形式上の第三者が取引の間に入ると、監査上はその形式上の第三者の先を見に行かなければいけないわけですけれども、この点、会計士は強制的な調査であるとか反面調査ができない、あるいは守秘義務の関係もあって、監査手続に一定の制約が生じてしまうのも事実だと思います。
このように証憑類が整備されている中で、監査人が経営者不正の兆候を把握するためには何が必要かということが問題になるわけですけれども、この点については先ほどから何度も用語として出てきていますけれども、職業的懐疑心が非常に大事だというふうには理解しております。職業的懐疑心を発揮し、監査証拠を批判的に見るためには、監査人は会社のビジネスを十分に理解し、経済合理性をしっかり検討する、その上で一連の取引の本質を見極めるということが極めて重要で、これは必要不可欠なことだと理解しております。このような観点から、職業的懐疑心を継続的なトレーニングによって高めるということは、非常に大事なことと考えます。
とはいえ、例えば支払った経費の妥当性の検討にあたっては、経営判断の領域の問題が関係しますし、反面調査が難しい中でのいわば状況証拠による対応ということになると、バツとは言い切れない場合も多いのではないかと推測しております。
次に、経営者不正の兆候を把握した場合の監査対応の難しさですけれども、このような場合には、監査人は意見不表明であるとか、限定意見を付すという対応が考えられるわけですけれども、上場廃止に直結する監査報告書の提出期限の問題であるとか、上場廃止の可能性が高いと思われる意見不表明について、監査人はバツとは言い切れない状況下で、非常に対応に苦慮することになります。特に四半期の提出期限については重要な問題であると思っております。この点を考えますと、監査人の対応が直ちに上場廃止に直結しないことが明らかにされるような、制度的な手当も必要なのではないかとは考えているところです。
最後に、経営者不正への対応に関して、先ほど八田先生からもございましたけれども、監査役との関係についてつけ加えさせていただきたいと思います。我々が行う会計監査というのは、基本的には事後チェックに該当するんだろうと思います。ただ本質的には、やはり不正を起こさないという意味で事前チェックが大事であると考えます。このような観点から、例えば、取締役会では、どのような雰囲気の中で、どのような議論がどの程度尽くされたのかとか、監査役はどのような取引に対して何を指摘して、どのような対応をとったのかといった取引の事前チェックというのは非常に重要で、これはガバナンスの問題にも関連してくるものと思っております。この点に関しては、本年4月から適用されています監査実務指針の中で、監査役との有効な双方向のコミュニケーションの実施が要求されていますので、監査人あるいは監査役が経営者不正の疑いがあるのではないかと感じたときは、双方向で連携しながら対応していくことが必要だと考えております。
以上でございます。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
それではどうぞ、順次ご発言をいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
どうぞ、八木委員。
- ○八木委員
-
今日のご説明は、会計不祥事等に関して、監査法人がどう対応すべきかということかと思います。前回、八田先生が指摘されたように、不正会計は最初は会社側が起こすものですが、やはり、オリンパスで起こった不正会計について、気がつかなかった監査法人というのは何をしているんだというのが、多分一般的な庶民感情だろうと思います。今回の検討に当たっても、監査部会に出席される方々は監査法人の方か、会計の先生方か、または我々事業法人という形になりますけれども、やはり一番重要なのは、利用者の立場に立ってどう考えるかということで、それぞれの立場では若干の壁とか現状の悩みもあるかもしれませんけれども、やはり最後は利用者の立場といいますか、結果的には財務データの品質管理という視点で思い切った提言になればいいかなというのが、問題意識です。
今日監査法人に関する期待(期待ギャップ)ということが出ましたけれども、現実に私自身も監査の現場を見ておりますと、やはりかなり大きな問題があるように思います。一つはパートナーの方はしっかりされていますが、その下の一線のレベルの実力がかなり落ちているのではないかという気がします。結果的には調書を作成するというのが監査だと、それを一生懸命やっているという、悪く言えば“調書作成アプローチ”といいますか、もうそれで終わってしまうということで、とても不正に気がつくということが一般レベルでできていないということで、やはり教育の問題は極めて重要だろうと思います。
それからもう一点は、企業の事業環境は変わっておりますので、過年度に認めたことを翌年度に修正すべきではないかということも出てきます。会計士の方は自分が前年度認めたことを翌年度変えることに対して極めて嫌がるということがあります。いわゆる“過年度処理の墨守型”といいますか。これは事業法人側から逆手にとられると去年認めたことを今年なぜ認めないということにもなりますので、こういったところは相当フレキシブルに考えていくことが、これから必要だろうと思います。
それから不正会計ということに関していえば、基本的に、正直言って不正会計はこれからも起こるだろうと思います。オリンパスのようなことがそう頻繁に起こるということはないですけれども、これはやはり尽きないものだと思います。但し、一方ではそれは極めてレアなケースだということとの組み合わせだと思います。今日は絶対やらない会社が、来年やるかもしれないということも含めて、すべての会社にリスクがあると同時に、実際に起こっている現象は極めてレアであるということからすると、やはり全ての会社を対象にして何か大きな工数(監査コスト)をかけるような仕掛けというのは、避けるべきだろうと考えます。
実務の段階で不正会計がどういう形で発見されたかというのは、私の知る限りでは、会計士の方が発見したということはほとんど聞いたことがないです。内部統制でも難しいです。実務の実態では、内部通報があってわかるというケースが多いと思います。結局1人ではできない仕掛けをつくって、複数の人間がチェックするというのが、内部統制の一つのあり方です。そうなればそこで必ず、その仕掛けの中で、先ほどのような機会を無くすことにつながります。複数でそれを外からも見ているということからすれば、だれかが気がついて内部通報することになります。
オリンパスのケースでも、最初に飛ばしたときには、実行犯のほかに相当気がついた人がいたと思いますけれども、彼らが内部通報しなかったということがあったのだろうと思います。ですから不正会計というのは、まず初期では内部通報以外で発見することはまず難しいのではないかと思っていますので、この辺のところはやはり企業サイドが、きちっと体制をつくっていくことが重要であろうと思います。これは、今回議論の対象かどうかは別として、そういう認識を持っております。
それとやはり、これもまた監査の基準とは違うかもしれませんけれども、予防といいますか抑止力ということを考えれば、やった企業当事者、経営者に厳罰で対応するということは、やはり必要だろうと思います。会計の場合には、過失も経営者の責任ではありますけれども、特に故意ということであれば、特段の厳しい厳罰で処置をするようなことも、やはり必要だろうと思っています。
それから先ほどの委員のご意見にもありましたけれども、意見表明ということについては前回も議論になったと思いますけれども、無限定適正意見というのが実態としてはかなりこの中に怪しいものも入っているということからすると、限定付適正意見という中に大きくレンジを持たせていくことが必要だろうと思います。
監査期限切れ関しては米国にはあると聞いておりますけれども、調査期間制度といったものも入れて、きちっと見ていくことが必要ではないか。監査意見表明が間に合わないからいきなりもう上場廃止ということではなくて、一たん調査期間制度ということを導入して、アドバルーンを上げて精査をするというようなことも、今後は必要になってくるのではないか。この場合には、間違いなく監査法人は、これを申請したときには、監査役に対してきちっと調査に協力してほしいということを出して、監査役がそれに対して当然責任を持って調査の必要性の要否について意見表明をする必要があると思います。結果的に調査ということからすると、先ほど冒頭の八田先生の意見にありましたけれども、調査権限を持っていないというのが会計士さんの一番のつらいところだろうと思いますので、ここについては、一定の条件がそろった場合には監査役がきちっと協力をする、協力ができないのであれば、できないという説明をすることをやはりルール化していくようなことも、この調査期間制度の中では必要ではないかなと思っております。
以上です。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
ここではどうぞ、枠にとらわれずにご発言くださいますように。
それでは、宮本委員どうぞ。
- ○宮本委員
-
八田委員からのお話にもございましたけれども、監査関係者との連携の強化は、皆様からの本日のお話あるいは前回のお話も踏まえて、極めて重要な事項だということは、私ども日本監査役協会としてもよく認識をしておりますし、この連携の強化に向けていろいろなことを考えていかなければいけないという認識を持っていることは、前回申し上げたところでございます。
なお、日本の企業統治制度の中では、取締役会の監督機能がございます。監査役(会)あるいは監査委員会がその職務を果たさないということで申し上げるのではなく、連携を強化していくことに加えまして、取締役会の監督機能をどのように考えていくか、あるいは監査人がこのことをどのようにお考えいただくか、こういった点も今後の議論の中に含めていただけるとありがたいと考えております。
以上でございます。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
ご発言、ございますでしょうか。清原委員どうぞ。
- ○清原委員
-
今日お話がいろいろあり、外国の議論とかもあるんですが、おそらく基準の改定議論の中でも考えていかなければならない日本の実情というのがあるかと思いますので、幾つか指摘させていただきたいと思います。
やはり監査の信頼性が高まっていく、不正に対する対応力が、監査の有効性が高まっていくという中で、やはり重要なのは懐疑心だというのはそれはそうだと思うんですけれども、ほんとうに現場の一線で活躍されている方々が、それを正当に保持して堅持されているかどうか、そこはちょっと私、疑義があるのかなというところがございます。あまり差しさわりがあるといけないんですけれども、監査・保証実務委員会研究報告第25号の「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」に関するある座談会の記事にこういう記述があって、あれっと思ったんですが、「公認会計士は、不適切な会計処理の発覚を想定して監査業務を行うことはありませんし、実際その必要もないと思いますが、不幸にもそういう事態に遭遇したときに公認会計士としてはどういうことをしていったらいいのか、きちんと理解することが重要」と。今、まさに監査基準などに既に埋め込まれているべきものがありながら、こういう発言が実際になされたりしています。どの雑誌かは差しさわりがあるといけないので明示いたしませんが、職業的な懐疑心というのが徹底しているのかどうか、これは、現実的な問題としては重要なのではないかと思います。
それから監査役などもしており、いろいろな場面で監査法人に触れることがあるんですが、監査法人の方が対象会社のことをクライアントと呼ぶことがあるんですけれども、素朴に非常に違和感があります。確かにお金が出てくるのはその会社であります。しかし、そのクライアントと言っているときに、果たしてその監査法人の担当の方は、独立した判断をほんとうに下せるのか。経営陣と対峙しなきゃいけないような場面において求められている対応がほんとうにできるのか、その姿勢にかかわってくるんじゃないかと。言葉だけの問題ということであればもちろんいいんですが、果たしてどうなのか。その意味でいうと、やはり基準の中でも、独立性をきちっと維持した上で対応していかなければいけないということは、一貫して明確に示されている必要があるのではないかなと思います。
それから、先ほど補足のところでもお話がありました監査報酬の関係で、やはりインセンティブのねじれという問題が日本の場合はありますけれども、監査人が必要な作業を追加的にしようとするときに、その工程数にかかる費用をだれがどう負担するか、もし報酬に反映されないのであれば、監査法人の側のインセンティブは非常に下がってしまうと。極端な話をすると、気がつかないほうがかえっていい、気がついたら作業が増えて余計なことになってしまう、もしそうだとすると、それではもう物事が前に進まないことになってしまうので、そこは非常に大きな問題です。インセンティブのねじれが会社法制部会のほうの議論だというのは承知しておりますが、非常に大きな問題ですので、監査契約の側からこの部分を見直していくというのは、まさに正鵠を得た重要なポイントではないかなと思うところであります。
あと1点追加させていただきたいんですけれども、先ほどのお話の中でありました日本とアメリカのASの違いのところで、AS15ですか、資料2の17ページで、日本の場合には「監査証拠による反証がない限り、通常、記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる」という引用があるのですが、ちょっとこれは、うがった見方をすれば、逃げに使われかねない規定がございまして、現実に起きているものの中に、おそらくこういうものがあるだろうと推測でちょっと申し上げるんですけれども、「こういう書類があれば監査意見が出ますよ」ということを、監査法人のほうから会社側に言っていることが現実にあるのではないかと。本来であったら会社から出てきた書類について、それが真正に成立しているかどうかを含めて職業的な懐疑心をもってチェックすべきところを、この書類があれば監査意見が出せる、と監査人の側から言っていくようなことが許されてしまうような基準になっていないか。そういう疑義があるのではないかと思います。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
ほかにどうぞ、ご発言いただけますか。はい、どうぞ、引頭委員。
- ○引頭委員
-
ありがとうございます。
質問でもよろしいですか。八田委員にご質問させていただきます。今回アメリカの不正に対する取り組みのお話は、大変興味深く伺わせていただきました。その中で、1988年創設の公認不正検査士協会というのが定着したというようなお話がありましたが、不勉強で恐縮ですが、私はこの協会の話を本日初めて伺いました。質問ですが、この公認不正検査士の方々と、例えばPCAOBであるとか、あるいは監査人の方々とどのような関係になっているのでしょうか。また、この公認不正検査士という方々の具体的な仕事内容はどういったもので、またその報酬はどこから出ているかについても教えてください。
- ○脇田部会長
-
この辺については、よろしいですか、不正監査の専門家という領域の問題でもありますので、八田委員、お答えいただけますか。
- ○八田委員
-
ありがとうございます。
まずこの団体は1988年に創設されており、資料1のパワーポイント8枚目にも書きましたように、出自はその前の年にトレッドウェイ委員会が「不正な財務報告」という報告書を出して、今後やはり不正に対する専門的な知見を備えたプロフェッションが必要であるということを理解した、ウェルズ氏を中心に創設された民間の団体です。ただ米国の場合には、ご案内のとおりほとんどのプロフェッションといいますか、資格取得者の団体は民間組織であります。アメリカ公認会計士協会も民間であり、内部監査人協会も民間であり、その一翼としてこれもあるということです。それ以外にも幾つか、企業の経営をめぐるいろいろな民間資格はあるわけですけれども、その一つがこれだということです。
彼らは何をしているのかというと、私の理解では一応2つあります。1つはほんとうに企業サイドから、当社のどこどこ支店でどうも帳尻が合わないとかいう形で、コンサルの一環として依頼されて、不正調査を専門に行うという、これが1つあります。それから今度は、企業の内部にいる内部監査部門の人たち、この方たちも大体CIAという公認内部監査人という資格を持っている方が多いですから、その一環としてダブルないしはトリプルのライセンスを持っている方が多くいます。あるいは外部の公認会計士の場合には、公認会計士の資格、会計の知識を持った者でありながら、かつ内部監査の知識を有してのCIA資格も、あるいはこれらを踏まえてこのCFEという資格を持つことで、それぞれ独立ないしは組織内専門家として対応するということがあります。
実は、日本では2005年でしょうか、このCFEのライセンスを付与する権限を民間の日本の組織が取得しまして、今、日本語でもこの資格を取得できるという制度になっており、もう既に数百名のCFEホルダーがいると理解しております。これはその前の内部監査人協会のIIAという組織も、ご案内のとおり日本内部監査協会がその正式な出先機関ということで認知されていますので、日本でも米国組織のこのCIAのライセンスが取得できるということで、これはおそらくもう国際ライセンスだと理解できます。
ただ私が知る限り、アメリカに次いでホルダーが多いのはカナダ、日本だということで、だんだんアジアのほうにも浸透してきている。おそらく経済が進展し、不正が巧妙になるところ、そしてこういったものが放置できないと考える経済の発展している国において、求められてくる専門知識ではないのかと思います。ですから私は、こういった知識を単にかりるのではなくて、会計士の先生方もこういった知見をうまく活用するようなトレーニングがあっていいのではないかということでご紹介申し上げました。
以上です。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。引頭委員、よろしゅうございますか。
- ○引頭委員
-
はい、ありがとうございます。
- ○脇田部会長
-
五十嵐委員、どうぞ。
- ○五十嵐委員
-
監査人が実施した監査結果についての利用者とのコミュニケーションは監査報告書になりますので、監査報告書の内容は非常に重要であると思います。先ほど資料3-1で事務局の方からご説明いただきましたように、現在、国際的に監査報告書の内容について議論されておりますので、関連してご説明させていただければと思います。
1ページ目の年表の中に記述されております国際監査・保証基準審議会は国際監査基準を策定しております。国際監査・保証基準審議会が先々週スコットランドで開催されましたので、出席してまいりました。本会議の主要議論は監査報告書の内容の変更でした。PCAOBが監査報告書の変更の議論を進めていると同様に、国際監査・保証基準審議会におきましても、監査報告書の改訂作業を進めており、その主要な内容は、PCAOBと同じように監査について利用者の理解に重要であると監査人が判断した事項などを、監査報告書に新たに記載させるという方向での検討であります。
こうした監査報告書の改訂内容は、ステークホールダーに大きな影響を与える可能性もあり、非常に重要な内容を持ちますので、国際監査・保証基準審議会は、今後のスケジュールとして、公開草案を公表して、広く世界の利害関係者の意見を聞くという予定にしております。我が国の監査基準は、国際監査基準も参考にして見直しを行ってきておりますので、我が国としましても監査報告書のあり方について検討を行って、必要に応じて国際監査・保証基準審議会における監査基準の検討に対しても、意見発信をしておくことが非常に重要ではないかと考えております。
また、秋には、北米、アジア、欧州でラウンドテーブルも行い、関係者の意見を聴取する予定となっております。国際監査・保証基準審議会の監査報告書の改訂は日本の監査報告書にも大きく影響を受ける可能性もありますので、今後の議論の参考に資するためにご説明させていただきました。
以上です。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
それでは引き続きまして、伊豫田委員どうぞ。
- ○伊豫田委員
-
先ほどの八田先生のご報告に関しましてご教授いただきたいんですけれども、今般の監査基準、改訂の方向性というのが、先生から配付されております資料1の17ページに記載されております。一つの方向性としては、現行の監査基準を改訂するということでありまして、少し先走ったことを言うかもしれませんけれども、その場合おそらく前文で不正への監査人のコミット、こういうものを強調するとともに、例えば一般基準で不正に関する記述を設けた上で、実施基準で不正摘発手続に関する包括的な規定を設けるというようなことが考えられるのかなと思います。
もう一つ、2つ目の方向性といたしまして、不正対応基準といったようなものを整備して、監査基準と一体のものとして適用するというような方向性が、ここで提案されております。現行の監査基準の枠組みを前提にして考えた場合、おそらくこの基準というのは、先生の先ほどご指摘にもありましたように、品質管理基準と同様の位置づけになってくるのかなという気がいたします。
そういたしますとこの不正対応基準というのは、つまり監査以外の多様な保証業務に対して、横ぐしを刺すといいますか、いわば横断的に適用されてくることになる、そういう位置づけになってくると思います。そうしますと、例えば四半期レビューであるとか、内部統制監査であるとか、そういったものに対してもこれがある意味適用されるということになると、それぞれの基準の中で明示されている、例えば四半期レビュー基準の中で明示されている四半期レビューに関する定義とか、そういったものに関しましても、不正というようなことが少し入ってくるのかなという気がします。つまりその限りにおいて、ほかの基準との整合性というか、見直しというのが必要になるのかなという気がするんですが、いかがでしょうか。
- ○脇田部会長
-
ただいまのご発言ですけれども、これは非常に大きな問題でありまして、この部会の一つのテーマ、これからの審議の方向だと思います。その辺で、八田委員からご説明をいただいたわけですけれども、今のようにどのように位置づけるか、そのこと自体、この部会でこれから吟味していかなければならない点だと思いますし、それ以前にまず監査基準との関係、品質管理基準との関係、いろいろございますので、皆様方からこれからご意見をいただく非常に重要な論点で、伊豫田先生、ご指摘いただいてありがとうございました。まさに課題を示していただいたと受けとめております。
八田委員、何かご発言ございますでしょうか。
- ○八田委員
-
結構です。
- ○脇田部会長
-
どうぞほかに、ご発言ございますでしょうか。
今のことでも早速にご発言いただいて結構でございますので。
住田委員、どうぞ。
- ○住田委員
-
今のことに関連するということではありませんが、先ほど清原委員からAS15の監査証拠の比較のところで、日本の監査基準委員会報告書第240号では、「監査証拠による反証がない限り、通常、記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる」という文言があり、これがどういう意味合いかというご質問をいただいたと受けとめまして、ちょっと補足させていただきたいことが一点あります。これは非常に重要な問題を示唆している点だと認識しておりますので、その辺もつけ加えさせていただきたいと思います。
この240号の12項は、ここだけ抜き出しますと監査手続は、会社から入手した資料について、何も信頼性を確かめることなく監査人がうのみにしているかのような印象をお持ちになるかもしれませんが、他の監査基準委員会報告書のほうで、監査手続を実施する際には、監査人は会社から入手した資料の信頼性を確かめた上で監査手続を実施しなければならないという要求事項が別途ございます。その上で、監査手続により入手する証拠は累積的に積み上げていきますので、たまたま前にやった監査手続で入手した証拠が、もしかしたら信頼できないのではないか、おかしいのではないかというような反証がない限りは、それはそのままでいいですよという趣旨で書いてあります。ですので、一義的には会社の資料の信頼性をチェックしたとき、あるいはほかの局面で実施する手続によって、いや、あれは間違っているのではないかというような反証が出たときには、もう一回立ちどまって考えなさいというような趣旨であります。
PCAOBのAS15にはここの部分の記載がないというのは、確かに先ほどご説明がありましたように、不正対応の部分を強化したというふうに言えるのかもしれないと考えてはいますが、これは、職業的懐疑心の捉え方の議論に関連するのではないかと思っています。先ほど栗田課長からご紹介いただいたUKのFRCの職業的懐疑心の報告書は非常に示唆に富んだ文書だと我々も思っておりまして、今日の概要説明の中では触れられてはいませんでしたが、報告書の冒頭で、職業的懐疑心というものは監査人のマインドセットというふうに書いてありまして、そのイニシャル・マインドセットをどこに置くかというのが非常に重要だという解説がされております。
先ほど八田先生からもUSのSASにおける不正への対応の歴史の中で、経営者は誠実だということから、ニュートラルという姿勢に変わったというご説明がありましたが、それが今、IAASBあるいはUSのほうでは、もう少し踏み込もうかというようなことを検討している段階かなと思います。ニュートラル/中立ということからもう一歩踏み込んで、会社の財務諸表あるいは経営者の主張が適正であることを証明する証拠を集めるという姿勢ではなくて、それが間違っているんだという前提に基づいて、虚偽があることを仮定して監査証拠を集めるべきではないかというようなところに、議論が今移っているような段階ではないかと理解しています。まだPCAOB基準にしても、ISAにしてもそこまで踏み込んだ記述はありませんが、世界中で会計不正が頻発しておりますので、そういう議論が今始まっているということかなというふうには考えております。
日本の監査基準における不正対応を考えていく上で、この懐疑心というのが非常に大事だというふうに認識しており、監査人のイニシャル・マインドセットをどこに置くか、どこに置くことが社会の期待なのかということを十分に議論していただいた上で、監査基準のあり方というようなものを議論いただけたらと考えております。
それから、資料1の八田先生のスライド17に、今後の見直しの視点を記載していただいているんですけれども、1つ目に「不正に起因する財務諸表の虚偽記載の有無を検証することにある」という大きな前提が書かれています。これは言葉のあやかもしれないんですが、不正による財務諸表の重要な虚偽表示の有無を検証するということが、財務諸表監査における監査人の責任だと思います。「重要な」というのが我々監査人にとってはキーターム中のキータームですので、ちょっとつけ加えさせていただけたらと思いました。
それから、2つ目の「不正に起因する財務諸表の虚偽記載を発見できるように」というところですが、どんなふうに監査基準をつくったとしても、不正による重要な虚偽表示を見逃すリスクというのはなくならないというのが、財務諸表監査のある意味宿命かなと思っておりますので、不正による重要な虚偽表示を発見する精度を高めるという意味の基準の改訂を、今回議論いただくというふうに考えております。
以上でございます。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
清原委員、いかがでございますか。特に証拠のことにつきましては、清原委員からお話がありましたら、どうぞ。
- ○清原委員
-
監査論についてまだそこまで詳しい知見を持ち合わせていないので、次回以降、またコメントがあればさせていただきたいと思います。
ただ1点、やはり監査証拠そのものの成立だとか内容の真正というのは、これは当然チェックをしなければならないのであって、外形上その書面があるからということだけで、よしとしてしまって次に進むということ、これは当然あってはいけないはずです。ただ現実にどうなのかというところでは、若干疑問に思う実情を見聞きしたことがあるので、その点をちょっと指摘させていただいた次第で、次回少し補足させていただきたいと思います。
- ○脇田部会長
-
監査論の中でも随分議論されたところでして、やはり証拠でございますから、法律的なご議論も、どうぞ活発にしていただければありがたいと思います。
よろしいでしょうか、住田委員。
どうぞ続けていただきたいと思いますが、一つ不正の中で、もうかなり古くなりましたけれども、循環取引をめぐる事件がかなり連続して起こっておりました。この点につきましても八田委員のご報告の中にあったかと思いますけれども、この辺につきまして、いわゆる監査人の間での、監査事務所間での何らかの連携がとれれば、循環取引等について対応できるのではないかというご意見も、ないわけではありません。ただ、守秘義務とか事務所間の関係を考えますと、私などなかなか難しいとは思いますけれども、そういうご発言もありますので、この辺についてご意見がございましたら、言及していただくとありがたいのですが。
先ほど、八田委員の報告にも循環取引はございましたよね。
- ○八田委員
-
はい。
- ○脇田部会長
-
唐突に申し上げてしまったのですけれども、何かご発言は、口火を切っていただけると。もしよろしければ関根委員、もしよろしければご発言ください。
- ○関根委員
-
ご指名ありがとうございます。
今のお話ですけれども、脇田部会長がおっしゃっているようになかなか難しい問題であると思っております。確かに監査人が、自分たちが調べている範囲を超えてここまで確認できればわかったのではないかと後になって思うことはありますけれども、企業に対する守秘義務の問題があります。またこれは不正があった場合に一般に言えることでもありますが、結果的に見れば不正があったのがわかったのではないかというのは言えるかもしれないですけれど、そこまでわからない状態で情報交換をほんとうにできるのかという問題があります。
だからこそ、今まで循環取引とかいろいろな問題が出ている中で、八田委員のほうで問題提起をされているのかと思いますが、これはまず、何に対する守秘義務かということ、また、不正の手続全てそう言えるかと思いますけれども、どういった場合にほんとうにここまで行うのか、ここまで行うことが許されるのか、ということを考えていかなければいけないと思っております。これは私自身の感想で、実はこういったことができたらどうなのかなという話を周りと話したこともあるのですけれども、いろいろな意見がでていましたので、これから議論していかないとなかなか難しいなと思っております。あまりお答えになっていなくて申しわけないですけれど、そのようなことを思っております。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
田中委員、どうぞ。
- ○田中委員
-
ごく一般論のみ申し上げさせていただきますが、守秘義務は基本的には監査人と企業との間の委任契約から生じる義務であると理解しておりますので、どのようなときに守秘義務が外れるかということは、根本的には契約によって決めることができると考えます。したがって今の論点は、例えば、A企業の監査人が、A企業が行っている取引に疑義を持っている、しかしその際、A企業が取引しているB企業の監査人にその情報を求めると、B企業の監査人は、B企業に対して負っている守秘義務に抵触する可能性があるということかと思います。
それについては、あらかじめ企業と監査人との間の監査契約において、そのような監査において必要になる場合、ほかの監査人に情報提供をすることができるという内容の契約条項を入れることによって、解決すべき問題ではないかと。そのような契約条項を乱用されるようなおそれのないように、情報提供ができる範囲をどのように特定していくかということが課題ではないかなと感じました。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。ご意見いただきました。
池田審議官、どうぞ。
- ○池田審議官
-
田中先生からコメントがありましたので、あえて発言する必要はないのですが、守秘義務は、ご案内のとおり公認会計士法上にも規定があります。しかし、公認会計士法上は正当な理由がなく情報を出してはいけないとされているので、何が正当な理由なのかということを考えていくこととなる。それは民事上、契約上も、何を正当と考え、契約上どう規定していくかということに関係するんだと思います。
次回事務局のほうで、若干実例も含めてご説明をしたほうがいいのかと思いますけれど、循環取引については私ども実際のケースを見ていますと、公認会計士の先生方も、会長通牒などがあって不正があるのではないかと疑いを持たれたときに、直接の取引先だけではなくて、最近はその川上までいろいろさかのぼって監査を実施し、残高確認等の作業をされるわけですけれども、循環取引の場合は共謀関係が強いこともあって、さかのぼっても、全てさかのぼって書類を偽造されて、結局発見に至らないというようなケースも少なくなく、そういうケースを見ていると、そこまで苦労するぐらいだったら、相手の企業の中には上場会社というのもあるので、その監査人に聞いたらもっと簡単じゃないのか。ケースによっては、相手企業の監査人が同じ監査事務所のケースも現実のケースとしては存在しているので、守秘義務だということを所与の前提にして、はじめから限界を感じる必要はないのではないかと感じるのです 。
さらに言えば、今日も布施先生のほうから、例えば反面調査がないということを大前提に議論がありましたけれども、もちろん反面調査をすることについてはいろいろ、副作用もあると思いますけれども、 反面調査がないということを大前提に決めて議論する必要は、議論としてはないのではないかという感想を持ちました。
- ○脇田部会長
-
ありがとうございました。
それでは終了の時間がまいりましたので、まだまだご発言いただかなければなりませんけれども、本日はここでお許しいただきまして、審議を終わらせていただきたいと思います。
次回の日程につきまして、事務局からご説明をさせていただきます。
- ○栗田企業開示課長
-
次回の日程につきましては、改めて事務局よりご連絡を差し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。
- ○脇田部会長
-
それでは本日の監査部会を終了させていただきます。
お忙しいところご参集いただきまして、まことにありがとうございました。閉会いたします。
以上
お問い合わせ先
金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3656)

 検索
検索