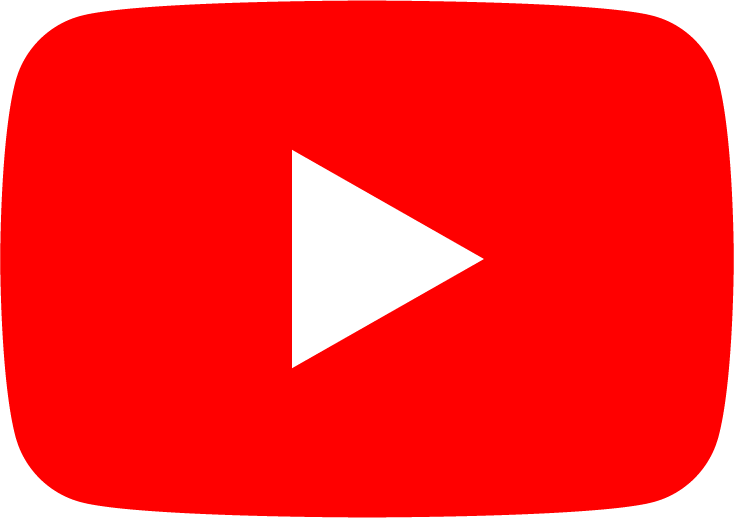- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「固定資産部会」
- 企業会計審議会第3回固定資…
平成12年12月1日
金融庁
企業会計審議会第3回固定資産部会議事録について
企業会計審議会第3回固定資産部会(平成12年11月17日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画部企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第3回固定資産部会議事録
日時:平成12年11月17日(金)午後3時30分~午後5時34分
場所:中央合同庁舎第4号館4階共用第一特別会議室
- ○辻山部会長
-
定刻になりましたので、ただいまから第3回固定資産部会を開催させていただきます。
本日は、皆様方お忙しいところを御参集いただき、ありがとうございます。
前回は、固定資産の減損会計のうち、主に減損の認識及び減損損失の測定の問題についてヒアリング及び意見交換を行いました。
まず、我が国の不動産等の取引実態や固定資産の会計処理等の実務から見て、米国基準や国際会計基準などの国際的な減損会計基準を適用するとした場合に、どのような問題が生じるのかなどについて、主に前回は財務諸表作成者側からということで、都委員及び岩田委員から御報告をいただき、議論を深めました。
また、土地につきましては、土地が非償却資産であること、我が国では固定資産の中での重要性が高いことから、秋葉委員から、土地の減損について御報告をいただき、意見交換を行いました。
本日は、お手元に議事次第がございますけれども、まず前回に引き続き、固定資産の減損会計のうち、主に減損の認識及び減損損失の測定問題についてヒアリング及び意見交換を行いたいと思います。
我が国の固定資産の会計処理、会計監査等の実務から見て、米国基準や国際会計基準などの国際的な減損会計基準を適用するとした場合に、どのような問題が生じ得るのかなどについて、主に会計監査人の立場からということで、太田委員にまず御報告をいただき、議論を深めてまいりたいと思います。
続きまして、減損の認識や減損損失の測定等の問題に関連して、川村委員から、将来キャッシュフローの見積もり方法や割引率について御報告をお願いしております。
最後に、中央青山監査法人の山田雅弘参考人から、主に英国における投資不動産の会計基準や会計処理について御報告をいただき、意見交換を行いたいと思います。
この問題については、本年6月に公表されました固定資産の会計処理に関する論点の整理に対する日本公認会計士協会のコメントにおきまして、投資不動産の検討に際して、英国等の公正価値による投資不動産の評価が既に導入済みの国、または業種における導入の背景及び適用状況を検討していただきたいとの要望がございましたので、そのことを踏まえまして、今回御報告をお願いしております。
それでは、本日の議事に入りたいと思います。
まず太田委員から、主として会計監査人として実務の観点から御報告をお願いしたいと思います。
では、太田委員、よろしくお願いいたします。
- ○太田委員
-
それでは、減損会計の実務に関して、会計士の立場から若干の事例を踏まえまして御報告させていただきたいと思います。
お手元の資料で、まず事例、それから事例のまとめについて簡単に触れさせていただきまして、それで最初のページに戻りたいというふうに思っております。恐れ入りますが、資料1-2という方を御参照ください。
初めに事例に関してなんですが、まず私がヒアリングベースでちょっと会計士仲間に聞いてみた範囲でございます。それで、まず米国基準の例しか聞くことができませんでした。それから、これら事例を集めるに当たって、やはり会計監査人というのはクライアントとの間で守秘義務がございますので、なかなかお話しいただけないというような部分がございまして、抽象化しているという点と、それから、ここで私が申し上げた事例が必ずしも当法人のクライアントに関するものではないという点、それから、ヒアリングベースですので、必ずしも論理的に整理されているとは限らないという点、御容赦願いたいというふうに思っております。
それでは、事例の方から資料1-2に従って、若干御説明させていただければと思います。
まず企業Aなんですが、米国基準によった場合の減損の試算についての事例でございます。この企業は、フランチャイズと直営で展開しているレストランでございまして、主たる固定資産は店舗の敷金保証金ですとか、内装の設備というようなものでございます。店舗別のPLは作成されておりました。ただし、そのPLに含まれている原価は、本社からの内部振替価格で売上原価を計上しています。ですので、本社の管理部門の方に利益が落ちるような仕組みになっているということです。この振替価格は外部でありますフランチャイジーに対する価格と同一でございました。将来5年程度の中期計画は会社として作成しておりましたが、中期計画が店舗別までには展開されてない状況でございました。これを検討している最中に次期の店舗別の予算が作成されたというような状況でございました。
検討の際に論点になったことというのは、これは何か疑問の点ですとか、そういうものが出たところを挙げていただいたんですが、例えば店舗とテストセンターみたいなものが同一ビルに入っている部分があるけれども、それはどう考えるのかですとか、一体何年分のキャッシュフローを考えるべきなのか。ちなみに、店舗が数が多いものですので、店舗別に年数を変えて検討していくのはちょっと実務上現実的ではないという実態がございました。それから、キャッシュフローについて、過去の実績を踏まえて引き延ばすべきなのか、予算をベースにしていくのかというようなところも議論になったそうです。もう一つは、内部振替価格を用いて店舗の損益計算書が作成されておりましたが、これで検討していいんでしょうかというような点も論点になったそうです。あとは割引率としてどんなものを用いるべきかというようなところだそうです。
結論としては、閉鎖が予定されている店舗と閉鎖が予定されていない店舗に分けて検討したということです。閉鎖が予定されている店舗については閉鎖時までのキャッシュフローをもって比較したということでございました。
閉鎖が予定されていない店舗は、2年間でしたか3年間でしたか、ちょっとその辺はあいまいなんですが、損失を出している店舗をピックアップして、特段の理由がある店舗以外について、インペアメントの検討を行ったということです。
割引率については、出店するときに会社として内部利益率を想定しているということなんですが、その最低の内部利益率を使用したということでした。
キャッシュフローについては、一律5年間を想定したとのことでした。これは会社の中期計画の算定の期間がたまたま5年であったということと、それから、固定資産の残存の耐用年数も大体5年ぐらいなのかなというところで、こういう試算をされたということです。
それから、試算は二通りについて行ったということで、1つは、過去2年間の実績の平均が5年間続くというふうに仮定した場合と、それから次が、次期の店舗の予算が5年間続くというふうにした場合の二通りについて試算を行ったそうで、結果は金額で2倍近く異なることになってしまったということです。
それから、検討は、内部振替価格が入ったままの店舗別PLを用いて行った。使用しない場合の情報はなかったので、算定はできなかったけれども、平均的な内部利益率を考えてみると、減損の金額というのは著しく少なくなるのではないかということです。これは何かどうも試算を行っただけのようですので、この辺のところをコメントとして報告したというふうに聞いております。
次に、監査上の論点なんですが、キャッシュフローの見積もりについてどういう監査手続をやっていくのかということを整理する必要があるのではないかというふうに思います。それから、監査上はやはり実績との比較というのが割と考え得る手続ということになってくるのかなというふうに思っております。それから、同じビルの中に店舗と全社資産に類するものが入っているような場合に、どういう考え方をするのかというあたりは若干論点になるのかなと。それから、最後に内部振替価格ですが、それを加味したままで減損を算定すべきなのか、あるいはそうではないのか、その辺は論点になるのかなというふうに考えております。
次に、企業Bの例にいきたいのですが、こちらも米国基準で連結財務諸表を作成している製造業のケースでございます。財務会計上は、場所別といいますか、工場別BS、PLを作成して、いわゆるマトリックスのような管理をされているということで、これのほかに事業部別の損益計算書もある、ただし、この細かい事業別PLと対応する区分のBSは必ずしも作成がされていないということでした。グループは製・販会社に分けて運営されているので、工場PLに含まれる売価はほぼ会社間の利益であるということです。ただ、グループ間ですので、販社で同じ商品の市場からの仕入れはないので、それが公正なのかという立証というのは不可能でしょうということでした。
それから、論点ですが、本社資産の取り扱いについて論点になったということです。それから、検討を事業別PLでやるべきなのか、工場別PLを用いるべきなのか。事業別PLを用いる場合、製造会社単体で判定すべきなのか、グループ全体で判定するのか、そのあたりが論点になったということです。ちなみに、事業別PLで判定するとすると、減損がここの事業なり製品グループなりにあるというふうにされた場合に、かなり関連してくる長期性資産を洗い出すのに実務上手間がかかるんではないかというようなところが議論に上ったそうです。
ただ、結論は余りおもしろくないものでございまして、工場別PLを用いても事業別PLを用いても、赤字というか問題があるようなものはなく、それ以上の検討はしなかったということでございます。それから、本社資産であるゴルフ会員権については、これはちょっと前の時点の検討というふうに聞いておりますが、時価が若干下落しているものがあったけれども、重要性がないということと、それから本社資産であるという論理構成ができるということから、そのまま据え置いたということを聞いております。
監査上の論点ですが、前の例と同じような部分は省きますと、やはりこのケースは減損の兆候が、事業別PLを用いても、場所別PLを用いてもなかったという結論でしたが、ある場合にどちらを採用すべきなのかというようなところはかなり悩ましいのではないかというふうに思います。ただ、基本的には組織ですとか管理の単位、あるいは会社の投資の意図等を考えて、会社にみずから決めていただくほかないのではないかというふうに考えております。
それから、米国基準のロジックからすれば、本社資産については、全社ベースで判定すればいいのではないかということですが、全社ベースで判定して減損を認識するに至らない場合であっても、土地・建物について著しく時価が下落している場合にどうするのかということは、ちょっと別の論点として議論していく必要があるのではないかと思いました。そのあたりでございます。
企業Cですけれども、こちらはどうも企業Bよりは若干規模が小さい会社のようで、やはり同様の製造業で連結財務諸表を作成している会社さんということですが、財務会計上は工場別BS、PL、場所別で財務諸表をつくっている、ただ、管理目的で製品グループ別のPLを作成して、これは売上、売上原価だけでなく、その下の販管費関係も大分配賦計算なんかをして管理上使用しているということです。ただし、やはり製品グループ別PLに対応する区分のBSは作成はされていないということでした。この会社の場合には、工場PL、何かどうも営業部門の方へ内部振替価格で売り上げているということのようですが、極力売価を反映させる努力はしているということですけれども、やはり政策的に決めている部分もあって、ちょっと言ってしまえば、割と原価管理目的で決めている側面もあるので、どちらかと言えば工場にきつい価格設定になっているんではないかということでした。
論点としましては、やはり前の例と同じように工場別PLなのか製品別PLで考えるべきなのかといったあたりですとか、事業別PLで判定した場合には、関連する長期性資産というのを洗い出すのに実務上手間がかかるんではないか。あるいは、ここの会社の場合には、全社資産として本社のほかに研究センターですとかITセンターがあるようなんですが、そこの土地をどうするんだというようなところが論点に上がってきたということです。それから、将来の工場拡張に備えて取得している土地はどうするんですとか、製品が市場ニーズに合わないということで、製品の仕様変更するべく転用を検討中であるというものはどうするんだというようなあたりが論点に上がってきたということです。
結論としては、これも結論は余りおもしろくないんですが、製品別PLをもっと細分化された製品種別のPLで見たところ、問題になるような製品グループとか何かは余りなかったので、それ以上検討は進めなかったということです。それから、土地については、何か全然キャッシュフローとは関係なく、簿価と時価の比較をしたけれども、大きく下落している部分はなかったので、それ以上の検討はしなかった。それから、転用を検討中の機械ですが、転用される可能性の方が高いという結論のようで、減損認識を行わなかったというふうに聞いております。
監査上の論点ですが、やはり同じような点が上がってくるんですが、こういうようなそれほどきちっとしたマトリックス管理とかがない場合に、製品グループ別PLなのか、場所別PLなのかというところは、やはり会社にとっては悩ましい問題なのかなというふうに思います。それから、全社資産についてはやはり全社で判定するのかなと。あとは、将来の取り扱いを検討中の機械設備をどうするのかということがありますが、これは検討しているのが2年も3年も検討しているということでしたら問題なんでしょうが、その期間が割と常識的な範囲であれば、それはその時点では据え置いていいのかなという形でございます。
次に企業Dですが、背景としては、こちらは製造業ではなくて、いろいろな事業を行っている会社ということで、問題になったのは不動産事業投資ということです。ちなみに、この会社については、不動産事業投資をどうしていくかということは経営上の大きな課題として認識されていたということです。管理としては事業別のBS、PLを作成しており、不動産については個別案件ごとの採算性の分析が可能な状況でした。
論点としては、すみません、これは余り論点とも言えないんですが、ここの会社の場合には詳細な分析を行うまでもなく、不動産事業投資について減損が出ているということは経営上認識されていた。疑問の点として持ち上がったのは、全社資産について時価がかなり下がっているものがあるけれども、どうなのかというようなところが論点になったそうです。ただ、この場合、反面そういうものもあるけれども、大幅な含み益を有している全社資産もあるので、一体それはどう考えるのかというようなところが議論に上がってきたということです。
結論といたしましては、賃貸中の不動産は、年間キャッシュフローを残存耐用年数を大体想定して、最終年度に売却したというふうに仮定して見積もって、時価、これは近隣の取引価格ないしは路線価等を用いた、大体これが時価なんじゃないかというふうに会社が判断された価格ということですが、それまで減損認識したということです。開発中のものは開発可能価格を見積もって、そこまで減損を認識。それから、全社資産については全社で判断をして認識はしてないということでございます。
監査上の論点としては、全社資産の取り扱いですが、最終的には全社で判断すべきだということで結論づけたというふうに聞いています。
次に、企業Eですが、こちらはサービス業ということで、問題になった固定資産は、基本的には事務スペースか賃貸物件だということでした。
論点としては、一体何年分のキャッシュフローを見積もるのかとか、賃貸ないしは使用を終了したときの土地の売却代金をキャッシュフローに織り込んで考えていいのかとか、あとは会社使用部分と賃貸部分が両方併設されている場合に、どういうふうに検討するべきかというようなところ、それから、不動産の時価が大きく下落しているけれども、割引前では回収可能という場合に減損を認識すべきなのか、あるいは逆に認識してはいけないのか、そういうところが論点になったというふうに聞いております。
結論としては、時価が下落していると思われるものをピックアップして、事務スペース使用部分については、5年間この会社はキャッシュフローを見積もったそうなんですが、5年見積もったところで減損認識すべき対象はなかったので、それ以上検討はしていないと。遊休で再利用の見込みがない土地については、減損を認識したということです。それから、賃貸ですとか使用終了時の土地代金はキャッシュフローに見込んでよいんではないかなというふうな結論ではないかと思います。それから、会社使用部分と賃貸部分について2つあるということなんですが、これはどうも当初から2つの目的で使用する意図で建てられたものだということもあって、分けて検討したということです。ただ、いずれも減損してないというような結論になったということでありました。
それから、会社監査上の論点ですが、会社の投資の意図とか投資回収の意図が減損判定の大きな要素になる場合があるんではないかなというふうに考えられます。それについて一体監査上どんな手続が可能なのかということを整理する必要があるんではないかと思います。ここのケースもそうですが、121の枠組みでは、不動産価格が下落したということだけで評価減をむしろ行わないのかなというのが結論でございました。
次に、今の事例のまとめを簡単にさせていただきますと、米国基準を前提に考えた場合に、いずれの企業においても、いろいろ方法は違いますが、直感的にやっているというものから、いろいろ管理上の体制を用いて把握しているというふうに分かれると思うんですが、何らかの方法で重要な減損があるかないかということは把握されているのではないかというふうに思います。
ただ問題は数値管理ができているのか、その方法とか制度がばらばらになっている部分があるのではないかというふうに思いました。ですので、減損把握の方法というのは、統一的に求めるのは、決めてしまうのは難しいだろう、会社によってさまざまなのではないかなというふうに思いました。資産のグルーピングについても同様ではないかというふうに思います。
それから、減損があるかなしかとか、金額を決めるに当たって投資の意図ですとか、あるいは見積もりの要素に左右されている部分がかなり多いように思いますので、特に製造設備については、金額算定をするとするんであれば、仮定を幾つも幾つも積み上げて結論を出すことになるんではないかというふうに思いました。これは製造業について、残念ながら実際に減損を認識したという事例を聞くことはできませんでしたので、このあたりはある程度の推定が入っております。
それから、不動産事業ですとか店舗については、キャッシュフローの把握は比較的簡単なのかなというふうに感じました。
それから、土地の価格の下落の影響ですが、これは日本独自の問題というふうに考えられる面もあって、特に全社資産に含まれる土地・建物についてどうするんだという論点として挙げた会社さんが多かったようですので、考え方を整理する必要があるように思いました。ただ、その際、含み損だけでなく含み益もあるんだというような会社さんもあるようですので、どう考えるかですとか、121号、米国基準の考え方を仮に前提にした場合には、それだけで評価減を行うという考え方はないので、別の論理が必要になるのかなというふうに思いました。
お手数ですが、ちょっと1枚目に戻っていただいて、以上が事例と事例のまとめですが、全体的な考え方としては、減損会計におきましては、将来のキャッシュフローによってその認識を行う。それから、場合によってはディスカウンテッド・キャッシュフローによって資産評価が行われるというのが米国基準、IASに見られる共通の点でございます。
特にそれについて、DCFによる資産評価は実務上かなり困難だというような意見も出ているということですが、確かに我が国の固定資産会計は過去かなり税法の影響も受けておりまして、客観性ですとか正確性をかなり重視している傾向があるというふうに思います。ただ、重要な減損が生じているということは、会社の経営上課題を抱えているということに結びつく場合がありますし、しかも、その会社はその存在を把握しているということだと思いますので、この客観性、正確性ということを重視する余り、企業会計のもう一つの目的であります企業実態の開示、適時開示を行うということを軽視するのは適切ではないのではないかというふうに考えます。見積もりの要素が多いことは確かですけれども、場合によっては客観性、正確性よりも妥当性を優先させることも必要なんではないかなというふうに考えております。
あともう一つは、減損については、米国基準もIASの方も減損の兆候がある場合にのみ、その資産とかグループについて検討を行うというふうにしているという、そういう面もあることを強調しておいてもよいのではないかというふうに考えております。
次に、減損の認識基準についてですが、日本の現行の固定資産会計との整合性ですとか、実務上の煩雑さですとか、それと用いる数値が必ずしも客観的で正確のものが算定可能ではないというような要素を考えますと、米国基準のような確率基準の採用とか、切り放し法の評価減が受け入れられる妥当なところではないかというふうに考えております。これは私個人の考え方ですので、これから議論していただければというふうに思いますが。
それから、次の将来キャッシュフローの把握ですとか資産のグルーピングについてですけれども、繰り返しになりますが、減損が生じているかどうかというような把握は各会社においてそれぞれいろいろな方法で行われているということであると思います。ですので、将来キャッシュフローの把握ですとか資産のグルーピングを減損会計のために特別に行うということではなくて、管理会計上把握している数値を加工して使うという例が多いのではないかと思います。資産のグルーピングについても同様で、経営上ですとか管理会計上のことを考えながら、各企業が決定していく以外の結論というのはなかなかないのではないかというふうに考えております。その際、算定するのは仮定を幾つも積み重ねた見積もりが必要になってくるんだということも共通認識として持っておく必要があるのではないかというふうに考えます。
若干繰り返しになってしまいますが、対象資産ごとについて簡単にコメントさせていただきたいと思っております。店舗につきましては、比較的独立したキャッシュフローが把握しやすく、扱いやすい例なのではないかというふうに考えます。ただ、この場合には、管理部門のコストの回収を店舗損益との関係でどう考えるのか、裏返して言えば、店舗のPLに内部利益が含まれているケースがほとんどであるというふうに思いますが、そういう場合にどういうふうな考え方をとっていくのかというあたりが論点になるのではないかと思います。
製造設備についてですが、製造設備については会社によって方法はさまざまだと思いますが、経営上、減損があるのかどうなのかというような把握はされているというふうに考えます。問題は、それをどのように数値化していくかというところに実務上の論点があるように思います。それについて厳密なものを求めることはできないけれども、ある程度妥当性のある方法とか結果は出せるんだという前提で、結局、各会社の決定に任せる以外ないのではないかというふうに考えております。
次に、賃貸不動産でありますが、こちらも比較的キャッシュフローが個別の資産に結びつけて把握しやすい例ではないかというふうに考えます。ただ、こちらの場合には、DCFによる以外でも公正価値とか時価とかいう、それに近いものが幾つか存在する、例えば路線価ですとか、税法上の評価額ですとか存在いたしますので、各会社が何を評価の際に用いるのかというところ、その選択に実務上の論点があるように考えます。
最後に、全社資産ですけれども、多くの事例で全社資産の土地・建物をどう取り扱うのかということは議論になったというふうに思います。米国基準のロジックからは、全社ベースで判断するということになるというのが大方の結論ですが、一方で、米国では土地価格が重要性がないケースが多いんではないかという声がヒアリングの際に聞かれました。不動産の著しい下落を理由に評価損の計上を求めるとするのであれば、米国基準とは別のロジックが必要になってくるのではないかというふうに考えます。その際に、ある年に損失を計上し、次期以降、利益が計上されるような、そういう利益操作をどのように排除していくかという点も考えていく必要があるのではないかというふうに思いました。
7番目ですが、これはちょっと繰り返しになってしまうんですが、土地の価格の下落の影響につきまして、米国の基準では、長期性資産の帳簿価額が公正価値を上回る状態を減損というふうに一応定義づけながら、ただ、それだけではなくて、帳簿価額が回収できなくなったときに初めて減損を認識すべきであるというふうに考えているようであります。
仮に米国基準と同様の考え方を採用するのであれば、減損は生じているけれども、帳簿価額は回収できる場合に、さらに日本独自の会計処理として、土地について評価損ないしは開示を求めるのかという論点が存在するように思います。すなわち、米国基準の考え方は、減損の存在、簿価が公正価値よりも高くなってしまったという状態、それと割引前で回収できないということ、この2つがそろうことが減損認識の条件というふうにしておりますので、土地の価格の下落だけをもって評価損を認識するためには、また別の理論、米国基準にはない理論を持ち込む必要があるのではないかというふうに考えます。
最後に、管理会計との関係ですが、減損の会計基準の導入に当たっては、事業の投資の意思決定過程ですとか、その後の投資の見通しが数値化されていることが前提になるように思います。当然、会社経営は事業を見通しながら意思決定されているわけですが、それをどのように数値化されていくかというところに減損会計を入れる、入れないというような論点があるように思います。ここで減損が議論されていくことによって、このような体制が整備されていけば、資産投資効率の向上にもつながるので、そういうような方向に持っていくことが副次的な目的にもなるのかなというふうに考えております。
以上でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの太田委員の御報告に関しまして、御意見、御質問がある方は、どうぞ御自由に御発言ください。品川委員、どうぞ。
- ○品川委員
-
御説明いただきました事例のところの関係でちょっとお伺いしたいんですが、6ページの企業Dのケースで、これは最後のまとめのところでもおっしゃった含み益と含み損がある場合に投資をどうするかということで、論点では「議論になった」としておいて、結論では「全社で判断し、減損認識しなかった」こういうふうに結論づけておりますけれども、この結論づけに至る議論はどういうふうに整理されたのかどうかということが1点と、それから、次のページの事例Eで、結論の下から2番目の「賃貸終了時の土地の売却代金をキャッシュフローに織り込んでよいか(織り込んでよいと考えられる)」、これは太田委員の御意見かと思うんですけれども、私も個人的にはそう思うんですが、こういうふうにちょっと疑問的に書いておられるのは反対意見があるのかどうか、この2点についてお伺いしたいと思います。
- ○太田委員
-
まず1点目なんですが、企業Dの全社資産の取り扱いですが、これは、全社資産について時価が半分以下に下がっているものがあるけれども、こういうのは損失計上しなくていいのかどうなのかというコメントがあったという意味でございます。割と深刻な論点というわけではございません。それに対して最終的な結論としては、この全社資産については、全社のキャッシュフローで回収できるという結論であったので、減損認識しなくてオーケーという結論を出したというふうに聞いております。
- ○品川委員
-
そうすると、含み益と含み損を調整してというか、ツーペイにしていいという、そういう考えでもないのですか。
- ○太田委員
-
そういう考えではございません、というふうに推定します。すみません。私がこれを直接やったわけではございません。
次のページのキャッシュフローに織り込んでよいかというところについての疑問ということですが、これは単に書き方だけの問題で、織り込んでよいという結論というふうに聞いております。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。品川委員、よろしいでしょうか。
- ○品川委員
-
はい。
- ○辻山部会長
-
そのほかございますでしょうか。
それでは、この段階では特に御質問、御意見等ございませんようですので、次の川村委員の御報告の方に入らせていただきまして、この問題は先ほどのDCFによる評価等にも深くかかわってまいりますので、後ほどまとめて、もう一度太田委員の御報告も含めて質疑を行いたいと思います。
それでは、次に川村委員から、主に将来キャッシュフローの見積もり、割引率につきまして、理論的な観点から御報告をいただきます。
では、川村委員、よろしくお願いいたします。
- ○川村委員
-
それでは、御報告申し上げます。
テーマにありますように、キャッシュフローと割引率については、どちらも見積もりの要素が極めて多岐にわたっておるわけで、ここで少し概念を整理しておこうというのが報告の趣旨でございます。
まずキャッシュフローの概念でございますが、共通する論点、国際会計基準ですとか、アメリカの現行の121号、あるいは公開草案などを調べてみておるわけですが、この点は共通する点で、利払い前でかつ税引き前。通常の設備投資の意思決定問題などについては税引き後で判断するわけですけれども、減損は税金を引く前のPLのセクションに載ってくる問題ですので、税引き前の計算になります。あと、将来の維持費用はキャッシュフローから控除しますし、在庫等の運転資本からのキャッシュフローも除かれます。つまり、設備から在庫へ価値が移転したとでも考えれば簡単に済む問題かと思います。
あと、2番の「最善の見積値」か「期待値」か。前者の方は英語でいうベストエスティメートという言葉の略なんですけれども、確率分布においてどういう位置づけになるのかという少し概念的な話をしますと、例えば、そこに書いてありますような確率分布、経済変数ではよく見られるような形なんですけれども、その一番てっぺんにある最も度数の高いところを通るのが最頻値でありまして、これが最善の見積値と理解されておるようです。期待値は、右の方がすそ野が長いので、こちらの方に引っ張られてしまいますので、期待値は若干右の方にずれる。これが期待値としてのキャッシュフローであります。いわゆる平均値です。
(2)で、例えば具体的にどんな違いが出てくるのかということで、1年後のキャッシュフローについて次のように例えば予測をしたと。ステートの1、2、3というものについて、それぞれ生起する確率、キャッシュフローを表にしてみました。それで、最善の見積値をとる場合には、一番度数の高いところをとるということになりますので、ステート2の60%をとって、キャッシュフローは200となります。それに対して期待値で計算するという場合であれば、それぞれ確率で加重平均して計算するわけですが、100×0.25+200×0.6+400×0.15で205というような計算になります。
このように期待キャッシュフロー、特にアメリカの公開草案で採用されている考え方でありますけれども、これを採用する理由ですが、幾つかメリットがあります。当然まず第1点に挙げられるのが、確率分布を反映しているということです。将来における特定の事象によってキャッシュフローが大きく左右されるケースなど有効であろうと。例えばある特定の条件が、どちらに転ぶかによってキャッシュフローの数値が大きく変わってしまうというようなケースにあっては、一つの数字を言えというのはなかなか厳しいわけで、こういう場合にはこうなる、ああいう場合にはこうなる、だったら、それを加重平均して求めましょうとなれば、実務的にもこういうのは言いやすいという面があるかと思います。
例えば(b)で書いてありますように、固定資産を継続して利用する確率が70%、もしかしたら処分する確率が30%、それぞれのキャッシュフローを計算して加重平均する。期待値が出てくる。そういうことになります。
また、期間でまたがるような確率分布も考えられるわけで、同じキャッシュフローが生じるとしても、1年後に生ずる確率が40%、2年後に生じる確率が60%などという場合にも対応できる、そういうメリットがあると言われております。
もちろん統計的といいますか、概念的に言えば、期待値が正しい数値かと思います。また、それが現実に実務上適用した場合に、かえってメリットがあるというのであれば、こちらをとるということになるかと思います。
ただ、よく例で挙げるんですけれども、ちょっと卑近な例ですけれども、宝くじを3,000円分買って、普通は10枚のうち1枚が当たって300円が返ってくる。これがベストエスティメートなんですけれども、例えば1億円当たる確率がありますから、それによって期待値というのは300円よりははるか上方に引っ張られて、例えば500円とか600円ぐらい。会計上、300という数値、多分恐らく300になるんだと思うんですけれども、その数値を載せるべきなのか、それとも上方に引っ張られた500とか600とかいう数字で足すのかというのは結構大きな分岐点であるかとは思います。
2ページ目にまいります。次の論点は、市場の見積もりと企業の見積もりという問題です。これは後でまとめて説明するところがありますけれども、目的の相違が反映しているわけで、公正価値か利用価値かという問題です。公正価値であれば市場の見積もり、利用価値であれば企業の見積もりということになります。
例えば、どういうときに差異が生じるのかということをアメリカの公開草案では挙げられていまして、自分のところが同業の他社よりも効率的に資産を利用できるとか、自分のつくっている製品が高く売れるとか、あるいは自分の方が材料費とか労務費を節約できるとか、そういうように同業他社に対して競争優位、あるいは競争劣位の関係にある場合に、そういうものを反映するかどうかという問題になってきます。
あと、見積もりに際しての仮定ですが、これは国際会計基準の方で多少具体的に述べているところがありますので、それをピックアップしておきました。基本的に(1)で述べている点はアメリカでも同様でありますけれども、合理的で支持できるような仮定でなければならない。余りにも非現実的なシナリオに基づいた見積もりでは当然排除されるわけです。
国際会計基準では、(2)で将来のキャッシュフローの予測を企業の予算に基づくとしても、せいぜい5年だというように数字を具体的に挙げております。5年を超えるようなものについては、その後一定の成長率を仮定して計算するということになっています。ただ、5年たった後の売り上げが、その後も例えば10%で伸びていくというような仮定は、やはりちょっと現実的ではありませんので、競争上優位にあるというのであれば、市場平均に収斂していくような成長率というものを想定して計算すべきだというようなことを言っております。
あと、土地の問題でございますけれども、これも先ほど太田委員の説明のときにも問題になった点であるかと思いますが、現在価値の計算式というのは、基本的にはそこにありますように、右辺の第1項が年度年度のキャッシュフローで、第2項が最終的な処分価値になります。そのVのところですけれども。これを割り引けば現在価値が出てきます。
土地については、よく言われることですけれども、永久資産だというふうに考えて、毎期毎期一定のキャッシュフローが生じて、利子率も毎期一定だというような状況を仮定すれば、簡単に年度のキャッシュフローを利子率で割れば、現在価値が出てくるわけです。
土地について、ただ、下の方の式で簡便に計算するというのは、いろいろと誤差が出てくる可能性が非常に高いので、不適当なケースが多いと思いますけれども、適当なプロジェクトの期間を設定して、最終的にその処分のときに得られる価値、不動産鑑定の世界では復帰価値というようですけれども、これについては現在の時価で代替するような形で計算してあげれば、大体の計算はできるのではないかなと思います。先ほど太田委員の説明でもこういう話だったのではないかと思います。
なお、公開草案で述べておる点なんですけれども、典型的な土地付き建物のようなケースでのプロジェクト期間については、建物の耐用年数ということになります。土地は永久に使えるからといっても、そのキャッシュフローの見積もりはあくまでも建物の耐用年数ではかって、土地については例えば20年後、30年後の時価をもって割引計算をすればいいということになります。ただ、20年、30年後の時価というのは、通常は今の時価をとらざるを得ない。国際会計基準では、インフレなどの要素があるのであれば、そういうものは当然反映してよいというようなことも書いてあります。
あと、割引率の方の問題でございますけれども、これも共通の要点として税引き前という点が挙げられます。理由は先ほどのキャッシュフローのケースと一緒です。
あと、期間構造の問題があります。長短の金利差をどう考えるかと。ある程度明確に金利の趨勢というものを想定できるのであれば、当然イールドカーブのようなものを想定して、毎期毎期のキャッシュフローに適用される利子率を区別して計算するということが、もちろん概念的には正しいということになります。
あと、この割引率の種類でありますけれども、まず資本コストというものがあります。これは設備投資の意思決定計算などで使われるものでありますけれども、企業固有の収益率と言いかえることができると思います。基本的には負債と自己資本に対する加重平均的な収益率ということになります。
あと、3ページの方にまいりますと、市場利子率ですが、これは大きく分ければ2つ。無リスクの利子率と資産固有のリスクに見合った市場の収益率、その2つであります。
以上述べましたようなキャッシュフローと利子率を組み合わせて、どういう現在価値を計算するのかという問題が次のところであります。この当審議会で議論していた中で出てきた概念というと、3つでいいのかなという気がしております。
1つは資本価値です。これは企業固有のキャッシュフローを資本コストで割り引くというのが基本だと思います。国際会計基準でいう利用価値は、厳密に考えると、これと違うと思うんです。これは企業固有のキャッシュフローを資産固有の市場の収益率で割り引くということになりますので、ちょっと意味が違う。
あと、公正価値については、これはいろいろバリエーションがあるんですが、基本的には市場のキャッシュフローを市場の割引率、収益率で割り引くということになります。
そこで、ちょっと下の図をごらんになっていただきたいんですが、比較してみました。公正価値、利用価値、資本価値と高目の棒が3つ並んでいますけれども、その間にキャッシュフローが入っています。これは単純に永久資産で年度のキャッシュフローが一定という想定です。そうしますと、公正価値に資産固有の収益率を掛ければ、市場の平均のキャッシュフローが出てきます。それと異なる固有のキャッシュフローを資産の固有の収益率で割り引けば、今度、利用価値が出てきます。利用価値に市場の収益率を掛ければ固有のキャッシュフローが出てきますし、その固有のキャッシュフローを資本コストで割り引けば資本価値になる。こんな関係かなと思われるわけです。ですので、いろいろと、例えば公正価値と利用価値は同じ収益率を前提としているようでありますし、利用価値と資本価値は同じキャッシュフローを想定しているんですけれども、割引率が違う。そんな関係にあるのかなという気がしております。
それで、次の問題なんですが、公正価値の概念について、アメリカの121号から公開草案へステップしていくプロセスで若干議論が変わってきていますので、それをちょっとお話しさせていただきます。
3ページの真ん中あたりのところに公正価値(FAS121)という式がございますけれども、ここで分子の方ですが、市場のキャッシュフローを見積もるんですが、121号で最善の見積値というものをとれというふうに言っています。なおかつ、これは一応リスク調整前の金額になります。リスク調整についてはまた後で詳しく述べます。これを市場の資産固有の収益率で割り引く。
公開草案では、分子にとるのは市場のキャッシュフローなんですけれども、先ほど申し上げましたような期待値をとるということになります。なおかつ、リスク調整を施した後、分母の無リスク利子率で割り引くということになります。
それで、この両者の比較なんですが、キャッシュフローについて最善の見積値か期待値かと言われれば、これは理論的には期待値をとるべきだ、これは間違いないと思います。ですので、ED、公開草案の方でとっている期待値というのは確かな結論であるかと思います。しかしながら、リスクの調整の仕方につきまして、キャッシュフローで調整するのか、割引率で調整するのかというのは当然議論のあるところになってきます。
その辺の説明を実はちょっと申し上げたのが4ページのところの図になってくるんですが、ちょっと子供だましのような図でありますけれども、同じ期待値を持っている確率分布であっても、立っているといいますか、狭い間隔で高くなっている方がリスクが低くて、横に広がっている方がリスクが高いということになります。同じ期待値でもこういうリスクの違いを価値にどうやって反映させるのかというのが問題点であります。方法は利子率によるもの、キャッシュフローによるもの、二通り考えられるということです。
そこで、ちょっと前の式の方に再び戻っていただきますと、少しインデントを入れてへこましたところがございますが、リスク調整後のキャッシュフローというのはリスク調整前のキャッシュフローに、いわゆる確実性等価係数と呼ばれるものを掛け算すると、一応概念的には求まる。その確実性等価係数をαとして式を展開すれば、当然このような関係になってくるわけです。
それで、これを先ほどのEDの公正価値の式に入れて展開してみますと、結局は言いたいことは何かというと、キャッシュフローを調整しても、割引率の方で調整しても、そんなに計算の中身が変わってくるわけではないということであります。同じようなものをやっぱり探しているということになります。とりわけ、αにt乗を掛けているところがありますが、確実性等価係数というのは1年後よりも2年後の方が、だんだんだんだんリスクが高まってきますから、変化してくるわけです。例えば1年間で0.9であったものは0.9×0.9で0.81とか、そういう計算になってきます。
理論的な式の上ではこうなってくるわけですけれども、実務で、ではどうなのかということなんですが、実務でもやはり全部割引率でやってしまうのと、キャッシュフローでやってしまうのと二通り、鑑定評価の世界なんかでは好き嫌いがあるようです。それで、割引率というのは一つの数字ですから、言ってみますと全体をまとめてリスク調整してしまうという考え方になります。しかし、キャッシュフローの方は細かく見るとほとんどリスクのないキャッシュフローから本当にリスクのあるキャッシュフローいろいろあるわけで、キャッシュフローを構成する要素それぞれについてリスクがどうなのかということを見て、例えば固定費なんか全然変わらないというのであれば調整する必要ありませんし、でも、その売り上げというのは非常にリスクがあるから、それについては調整するとか、そういったキャッシュフローに対して明確な形でリスク調整を施せるというメリットがあるというわけです。その辺をとらえまして、一応FASBではキャッシュフローを調整する方法というものが概念的にといいますか、そういう理由などから支持されるというような結論になっておるようです。
あと、4ページの真ん中以降は設例ということで一応つくってみました。ざっとだけ御説明しますと、固定資産の取得原価1,000で耐用年数10、残存価額100、5年経過時に減損の有無を判定するというような形です。定額法で減価償却、資本コスト12%、資産固有の収益率8%、無リスク利子率5%といった形で計算してみたんですが、当初の予測というのは設備投資の意思決定で行われるもので、公正価値1,000に対して資本価値、利用価値ともそれを上回っております。0年度のところを見ていただきますと、その関係がわかります。
しかしながら、5年経過時、次のページを見ていただきますと、例えばこんな状況であろうということなんですが、5年経過後の固定資産の簿価というのは、下から5つ目の行でちょっと黒く太く枠を入れているところですが、550になっていますが、割引前のキャッシュフロー総額というのは、ここの時点で494、要するに減損のトリガーが引かれたということになります。
ここの状態なんですが、理論的に説明は難しいという評価が一般的でありますけれども、あえてちょっと弁護をすれば、割引前のキャッシュフロー総額が簿価を下回っているというのは結局、将来ここでいう営業利益の額がマイナスになってしまうということになります。26-5-5-36-36、これを全部足しますとマイナスになってしまうわけです。実は4年度まではプラスになっていました。ですから、その割引前のキャッシュフロー総額が簿価を下回った時点で、将来の利益というのは必ず赤になるということになります。
あと、その際に、例えば利用価値をとったとき、公正価値をとったとき、以後の損益計算はどうなるかということが、その下の表の4の(1)、(2)で述べたところであります。
あともう1点、リスク調整のところも一応設例としてつくっておきました。これは0年度に、要するにスタート時点における公正価値の計算の仕方を一応とってみましたけれども、市場平均のキャッシュフローをリスクを調整しないまま割り引いても1,000になり、確実性等価係数を掛けてリスク調整後のキャッシュフローを無リスク利子率で割り引いても1,000になるというような、そういう調整をしてつくった表であります。具体的なところをイメージしていただければと思って作成しておきました。
以上、御報告申し上げました。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それではまず、ただいまの川村委員の御報告に関しまして、特に川村委員の御報告の中に関する御質問について、先に承りたいと思います。その後、先ほど申し上げましたように太田委員の御報告とあわせて御意見を承りたいと思いますけれども、まずただいまの川村委員の御報告に対する御質問ございますでしょうか。太田委員。
- ○太田委員
-
ちょっと理解ができているかどうかを確認させていただきたいというふうな趣旨なんですが、使用価値と公正価値の違いについてなんですが、例えばA社とB社と同じ資産を持って、同じ事業を営んでいる会社を想定したとして、A社の方は同業他社よりも効率的に資産を利用できるという会社、ただ、B社はそうではなくて、市場と同じぐらいの活用だという、そういう状況をちょっと想定した場合に、同じ時期に減損認識したというふうな場合、IASで認識したとすれば、その後の期間でA社とB社の利益は、その見積もりどおりいったと仮定してですけれども、同じ金額の利益が計上されるという結論になり、米国基準でいった場合には、A社の方が次期以降、利益がたくさん出て、B社はそうでもないという、そういうことになりますでしょうか。ちょっと事例がわかりにくくて申しわけないんですが。
- ○川村委員
-
国際会計基準によって利用価値まで切り下げたときの将来の損益計算への影響ですけれども、この場合はA社の方が利用価値は高くなってきます。割引率が一緒ですので、その利用価値からアンワインドといいますか、利用価値にその割引率を掛けて計算されるその年度のキャッシュフローというのは、多分Aの方が大きくなるのかなという気がしています。
後者はそれで、FASBの基準でやった場合はそれでよろしいんじゃないでしょうか。
- ○太田委員
-
評価される資産の金額についてはそうであると思うんですが、その減損認識した期以降の期についての利益の出方なんですが。すごく単純な頭をしておりますので、時間の要素と資産のリスクの要素のみがIASによった場合には、次の期以降、利益に計上されていくというように実はちょっと思ったんですね。ただし、逆に米国基準にいった場合には、一たん公正価値まで同じレベルまで資産の評価を落としますので、当然、次の期以降、A社の方が効率的に資産が利用できるので、A社の利益の方が多くなり、B社の方が利益が少ないという状況が続いていくということになるのかなというふうに考えたんですが、これは間違っておりますでしょうか。
- ○辻山部会長
-
ただいまの御質問ですけれども、先ほど川村委員の御報告の中で5ページでございますけれども、減損認識及びその後の損益計算というところで、公正価値によって減損を測定した場合、5期ですね。6期以降の利益額、これでただいまの御質問に対するお答えができるかと思いますけれども、ちょっとこの点、川村委員お願いいたします。
- ○川村委員
-
ありがとうございます。そうですね。Bの方は市場平均的なキャッシュフローしか得られないというのであれば、そこから得られる利用価値というのはイコール公正価値ということになりますので、今、部会長から御指摘あったように、その(1)のケースを今、設例でいうB社、(2)をA社というふうに想定すれば、まさにこのとおりになるわけです。したがいまして……。そうですね。減損の額がB社の方が大きく計上されますが、その後の利益はB社の方が大きくなると。
- ○太田委員
-
すみません。ちょっと何かややこしいので、持ち帰って考えてみます。申しわけありません。
- ○辻山部会長
-
A社、B社ということを除きますと、その5ページの例で、公正価値まで減損を下げたときに、先ほどの川村委員の御報告の図でございましたけれども、公正価値まで下げるということは、資産固有ののれんというものまで減損の中に含めるわけですよね。ですから、その後の利益というのは、その部分が実現してまいりますので、(1)のようなケースで、そののれんの実現分というのが利益計算に入ってくる。それに対して(2)の場合には、その部分が入らない。利用価値までですから。資産固有の収益率だけが減損後の、このほかの資産を無視しますと、営業利益に入ってくると。要するに収益率の部分、収益率で時間計算したものだけでして、のれんの部分というのは後に実現してこないわけですね。ということだと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
いわゆる利用価値によって評価をして、かつ減損を測定した場合は、その後の年度は利用価値をベースにした、いわゆる時間価値ですね。それが利益の中に入ってくるというのに対して、公正価値まで下げた場合は、今度コストがそこまで下がりますので、それを超える部分が利益に入ってくるということだと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
- ○川村委員
-
先ほどのお答え、ちょっと間違ったところがありますので、訂正させていただきたいんですが、この5ページの(1)と(2)は、先ほど太田委員がおっしゃられたような、(1)がB、(2)がAというふうに想定できません。というのは、この設例はどちらも売り上げは一緒、つまりキャッシュフローが一緒というような想定になっていますので、太田委員の想定だと、B社の方がキャッシュフローが小さいということになりますので、単純にこれとはならないかもしれません。
- ○辻山部会長
-
そうですね。ですから、どちらにまで減損を認識した場合に、その後の損益計算、減損認識と損益計算の関係がどうなるかというのは、この5ページの設例でかなりきれいに説明できていると思いますけれども。
そのほか、御質問ございますでしょうか。
それでは、御質問に限らず、もう一度太田委員、川村委員の御報告に関しまして、御意見も含めて承りたいと思います。特にございませんでしょうか。
ちょっと1点、それでは、先ほど品川委員の御質問と太田委員との質疑でございますけれども、含み益の問題をどのように処理したのかという事例の中で、この場合、含み益というものは影響を与えなかったというお答えだったように思うんですけれども、その問題は例えば全社資産のグルーピングの仕方によって関係は出ないでしょうか。
- ○太田委員
-
余りそういう厳密な議論で検討しているんではないと思うんですが、全社資産としてある資産が位置づけられて、それで、その土地・建物、多分土地だろうと思いますけれども、その時価が非常に下がっている、そういうものがありますという事実認識があったと思うんですね。それについて米国の基準は、全社の将来キャッシュフローで長期性資産部分を回収できれば、もっとありていに言ってしまえば、全社ベースで利益が出ていれば、それは全社資産について減損認識しなくてもいいということになっていると思いますので、そこの議論の中で含み益のところまでを含めて検討はしていないんではないかというふうに思います。
- ○辻山部会長
-
先ほどはそういうお答えだったんですけれども、ただ、その減損が出ているか、出ていないかというそもそものときに、グルーピングの中に含み益といいますか、例えば土地なんかのターミナルバリューが現在の時価で代替するとすると、そういうものが入ってまいりますと、認定のところで、グルーピングの仕方によっては含み損益が一つのグループに入ってくるということはないんでしょうか。そこの判定のところで効いてくるという解釈ができると思うんですけれども。グルーピングの外でしたら、それを相殺するということはちょっと別の議論ですけれども、グルーピングの仕方によって、そういう損益が出ているものが一つのグループになれば、お互いに相殺し合って減損そのものの認識から外れるという、そういう関係で先ほど御質問あったと思うんですけれども。
- ○太田委員
-
はい。ただ、多分そのときに聞いた私の受けた印象は、例えば東京にあるものと大阪にあるものというような形で、全くグルーピングが一緒にはならなそうな現実の土地建物でしたので、そこまでは多分検討の対象にはしてないということだと思います。理論的にどうすればいいのかということはちょっとわかりません。
- ○辻山部会長
-
わかりました。どうもありがとうございました。
- ○斎藤委員
-
先ほどの減損を公正価値まで切り下げるという方法をとったケースと、それから利用価値といいますか、資本価値といいますか、そこまで下げたケースとの比較ですが、これはここで議論するようなことではもちろんないと私は思いますが、先ほど部会長がおまとめになられたとおり、もし利用価値ないし資本価値まで切り下げた場合には、その後に生ずる期待される利益は、資本コストないしフェアリターンであります。もしそうではなくて、そういう資本価値よりも低い公正価値まで下げた場合には、その後に期待される利益はフェアリターン、プラス超過リターンということになるはずであります。それは数値例を確認するまでもなく明らかなことだと思います。
むしろ、この場で議論しなければならないのは、それぞれにどういう意味があるかということでありまして、差し当たって我々が今問題にしているのは投資家に対する情報開示でありますから、投資家の側から見て、その数字がどういう意味を持つかということを考えざるを得ないんですね。投資家の目から見て、企業の資産に減損が生じたという事実は、その資産の収益性が低下して、もはや超過リターンが望めなくなったということが第1点。第2点は、しかし、問題の資産を処分する状況ではないという意味で、フェアリターンないし資本コスト分の利益は期待できる。その2点なんですね。ですから、基本的には投資家にとって大事なことは、現在の減損後の簿価を、価値を一応知った上で、将来に期待されるフェアリターンがどこまで実現するかを確かめていくということであって、その確かめられた結果をさらに将来の期待形成にフィードバックさせるというのが投資家の意思決定なんですね。そういう脈絡を考えたときに問題は、フェアリターンのほかに、さらに加えて超過リターンを期待するような公正価値の評価ということ、公正価値への減損ということにどういう意味があるのかという、その経験的な解釈を私は知りたい、そっちを御質問申し上げたいと思います。
- ○辻山部会長
-
それでは川村委員。
- ○川村委員
-
FASBの議論の中で言っておりますことを紹介するにとどまってしまうんですけれども、一番わかりやすく言えば、再投資を仮定して、公正価値まで落とすことによって、それから将来生じるであろうエクセスリターンとおっしゃられた部分、FASBの方では競争優位とか競争劣位に相当する部分については、事後的なキャッシュフローの状況でもって確認していく必要があるということで、公正価値まで下げて、では本当に将来のれんがきちんと実現できるのかどうかということは、将来実際にこのキャッシュフローが入ってきたかどうかで確認していかざるを得ないということで、一たん公正価値まで落とすというのが一応の脈絡かと思います。
- ○斎藤委員
-
別にそれに反論する必要もないのですけれども、実際には再投資はしないわけですよね。要するに資産を廃棄しないという意思決定をしているということの意味が、その議論では完全に無視されているという感じはいたします。
- ○辻山部会長
-
この点は、かなり今後の議論の根幹にかかわることで、公正価値か、あるいは利用価値ないしは資本価値ですか、そのどちらかということなんですけれども、FASBのロジックは再投資を擬制している、その擬制というものがどれほど会計の全体の枠組みの中で一貫性を持ち得るのかという、その辺の議論に入っていくと思いますので、この場ではとりあえず先ほどの質問に関連しては、その後の利益にどういう影響が出るんでしょうかということで、その点は整理されたというふうなことでよろしいでしょうか。
それでは、非常に重要なところなので、この場では結論は出ないと思いますので、問題の所在ですね。その擬制がどれほど妥当性を持つのかという。再投資という擬制ですね。その辺についてはまた改めて議論になると思いますので、問題を確認したということでよろしいでしょうか。
それでは、少し先に進めさせていただきます。最後に山田参考人から、主に英国における投資不動産の会計基準、それから会計処理につきまして、御報告をお願いしたいと思いますが、この英国における投資不動産の会計基準でありますSSAPの第19号は、お手元の黒い表紙の資料集の中につづられておりますので、あわせて御参照いただければと思います。
それでは、山田参考人、お願いいたします。
- ○山田参考人
-
中央青山監査法人の山田と申します。
お手元にお配りしました横書きの「英国における投資不動産の公正価値評価」という資料と、それから追加でお配りしました財務諸表の幾つか、参考例ですけれども、それを参照しながらお話を進めさせていただきたいと思います。
今回議論となるイギリスのSSAPの19号、投資不動産に関する基準、これが通常の固定資産の減価償却とは異なる扱いを行っているということですけれども、この基準が形成されるに至った背景をまず先に説明させていただきたいと思います。
このSSAPの19号は1981年に制定されたわけですけれども、それ以前の1970年代中ごろから、固定資産の会計処理、特に減価償却の会計基準について、現在SSAPの12号、これはFRSの15号という新しい固定資産の会計基準ができましたけれども、当時、SSAPの12号という固定資産の減価償却をどのように扱うかという議論が行われていました。
このSSAPの12号は、基本的にすべての固定資産に対して減価償却を行うということを意図していたわけですけれども、それに対して反対意見を出したのが当時の不動産会社を中心とする不動産業界ということです。それ以前に、投資不動産として保有している資産に対してどのような会計処理を扱うかということについての明確な会計基準はなかったわけですけれども、それまでの会計慣行としては、投資目的で保有している不動産については減価償却を行わない、減価償却を行わずに、ルールがなかったですから何年というのはないんですが、何年かごとにその資産を再評価して、その資産でバランスシートに載せるという会計慣行が既に不動産業界において確立されていた。そういった中で、すべての固定資産について減価償却を行うとする12号の導入については、不動産業界の大きな反対があったということで、当時のSSAPの会計設定母体であったASC(Accounting standard committee )がいろいろ検討して、結局譲歩した結果として出てきたのがこのSSAPの19号と、こういう背景になっております。
そのときのASCのコメントとしては、この投資不動産の会計に関して減価償却を行わないという基準についての積極的な理由づけは特に明確な見解としては出してないんですね。どちらかというと妥協の産物的な考え方でこれが入った。最初はSSAPの12号につけ加える形で会計基準をつくることを検討していましたけれども、むしろ妥協的な産物ということから、あえてSSAP12号を改変せずに、別な会計基準19号としてつくったということだそうです。
それでは、具体的なSSAPの19号の中身についてお話をしたいと思いますけれども、お手元の2枚目の投資不動産に関する基準ということで、この中の主な内容は、投資不動産の範囲について、公正価値の算出方法、会計処理、開示項目、そして国際会計基準との相違点という形でお話ししたいと思います。
まず投資不動産の範囲ですけれども、皆さんのお手元にある資料集でいきますと、この黒いバインダーの中の原文で3枚目にありますパート2、Definition of terms という、パラグラフ番号でいいますとパラグラフの7と8がありますが、ここがいわゆるこのSSAPの19号が対象とする投資不動産の範囲を定義づけている箇所であります。
そこで定義されているのは、7号の方で、以下の要件を満たす土地・建物に対する権利ということで、1つは、その土地とか建物の建設工事及びその開発が完了しているということ、ですから、建設途上のものは含めないということですね、それから、賃貸収益を得る目的で所有しているという、この2つの要件を満たしたものが範囲ですと。
パラグラフの8番は、逆にこの定義には含めませんよということを明確に述べているんですけれども、投資不動産から除外するものとしては、会社が自分で使用するために所有かつ占有する不動産、これはいわゆる一般的に使用目的を持っている固定資産ですね、こういった建物とか土地等は含めません。それから、賃貸目的であっても、グループ内で他の会社に賃貸している投資不動産、これは含めませんということで、これがイギリスで会計実務として行われる投資不動産の範囲となっております。
では、具体的にどういう会計基準が行われているかということですけれども、原文の会計基準19号ですと、Part 3-Standard accounting practice 、パート3の部分ですが、まずパラグラフ10にありますように、ちょっと英文を読み上げますが、Investment properties should not be subject to periodic charges for depreciation on the basis set out in SSAP 12 except for ……とあるんですが、ここでいうSSAPの12号が規定している通常の減価償却費、この減価償却は投資不動産については適用しません、ですから、減価償却を行わないということがまず一つここでうたわれています。
その後ちょっとexcept forという例外があります。これはまた後で御説明します。
それから、パラグラフの11番、Investment properties should be included in the balance sheet at their open market value. とありますけれども、この投資不動産はオープンマーケットバリュー、公正な市場価値ではかってくださいということで、つまり、簿価マイナス減価償却累計額という形ではなくて、公正価値で計上していくということが、この2つが会計処理として行われています。
では、オープンマーケットバリュー、公正価値とは何ぞやという定義づけなんですけれども、これに関しては、このSSAPの19号の中には明確な定義づけはないんですが、最近出されたFRS15号、これは固定資産に関する会計基準ですが、その中のアペンディックスについて、不動産鑑定士協会の定義づけが一つ行われています。Royal institution of chartered surveyors、省略してRICSですか、ここはいわゆる不動産鑑定士協会というような形です。そこがそれぞれの不動産を評価するに当たってのガイドラインを出しています。それを会計基準のFRS15号、タンジブル・フィックス・アーテッドが引用しておりまして、そこでうたわれているオープンマーケットバリューというのは、すみません、ちょっと資料としては添付してないんですけれども、簡単に申し上げますと、ちょっとここも読み上げます。An opinion of the best price at which the sales of an interest in property would have been completed unconditionally for cash consideration on the date of valuation assuming…. ということで、1つは、取引を行うことにおいてキャッシュが動くであろう金額の最善の見積もりというんですかね、これにかかわる金額ですよと。
そのための条件が5つありますけれども、1つが、ア・ウイリング・セラーということで、自分から自発的に売りたいと思っている人がいるということ。それから、その評価に当たって、評価をする時期までと実際に取引、それを売ろうとする時期との間に時間的に十分な検討が行われているということ。それから、売買の行われている契約と評価をする日の間に大きな状況の変化がないということ。それから、この取引を変化させるような第三者的な評価人の追加がないということ。それから、その取引自体が十分な知識を持って、また誠実に行われるということ。こういった条件があるんですけれども、そういったものをもってオープンマーケットバリューとしますという定義があります。
ここでは、そういった概念的なオープンマーケットバリューの定義になるわけですけれども、では実際、実務でこの投資不動産会計を処理するときに、公正価値をどうやってはかっているんだということで、これは一緒に働いているイギリス人に聞いてみたんですけれども、その話からしますと、基本的にはやはり類似的な資産ですね、近辺にある不動産の実際の取引価格を参照したり、あるいは賃貸目的不動産ですから、将来キャッシュフローの現在割引価値ですか、こういった形で評価したものを持ってくることが一般的だねと。では、キャッシュフローとか行うときに、何らかのクオテーションというんですか、マーケットのようなものがあって、何か値づけのようなものがあるのかというふうに質問しましたら、特にそういうのはないようですので、評価によっては個々の不動産鑑定士の評価による部分が多いということのようです。
レジュメの方に戻りますと、評価方法として、専門的知識を有した鑑定人による評価ということなんですが、この鑑定人、どういう人でなければいけないかといいますと、会計基準として、実は必ずしも資格を持った鑑定人である必要はないんですね。それは会社内部の人であってもいいというふうにされています。ただし、だれが評価したかというのは必ず財務諸表の注記に載せなければいけない。
事例の方の、3枚ありますけれども、こちらを見てください。ここは比較的大きな会社なので、実際は不動産鑑定士が評価しているんですが、ちょっとこれを読み上げます。1枚目のHammerson plc という会社の事例、よろしいでしょうか。Hammerson plc という会社のアニュアルレポートですが、LAND AND BUILDINGSで、そのLAND AND BUILDINGSの中にInvestment properties が含まれていますと。Fully developed propertiesとして開発済みの不動産がありますということで、それに対する注記、そのすぐ下のパラグラフですが、Fully developed properties are stated at market value as at 31 December 1997,valued in each region by professionally qualified external valuers,Jones Lang Wootton,Chartered Surveyors. ということで、このジョーンズ・ウットソンという会社が評価をしております。
実は、これはイギリスの特徴として、だれが評価したかというのを明確にすることによって、読む人がその評価の信憑性について判断の資料としたいということなんですね。ただ、この会計基準の中にもあるんですが、大規模会社、特に上場会社に関しては認められた専門的資格を有し、かつ最近において当該不動産の所属する地区において、当該不動産と同一種類の不動産について、資格取得後の実務経験を積んだ鑑定人によって毎年及び少なくとも5年に1回は外部の鑑定人によって評価される必要があるということで、上場会社、リステッドカンパニーに関しては外部の評価が必要ですということです。
それから、実際の具体的会計処理の話ですけれども、貸借対照表に公正価値で計上しなさいと先ほどありましたが、それから、一たんそうやって公正価値で計上した後に、その公正価値部分が変動したらどうしますかということで、最初に公正価値で簿価から変動した部分については投資再評価積立金として開示するということで、損益計算書は通さず、直接資本の部に持っていくと。その後の増減もこの資本の部で計上しますけれども、逆に価値がまた下落した場合ですね。既に積み立てている部分については再評価積立金を減らしていきますが、それを超えて、つまり当初の原始取得価格を割り込んだ場合は損益計算書に持っていくと。通常の固定資産の評価損と同じように損益計算書に持っていくということです。
それから、先ほど例外部分は後で説明しますと申し上げたんですが、賃借契約により保有する不動産ということで、借りている側の会計処理ですが、リース等の賃借契約で保有する不動産に関しては、その賃借の契約期間が20年を下回る場合は減価償却を行うということで、これは例外のまた例外ということで行っています。この20年という期間がなぜ行われているかというのはちょっとよくわからないんですが、一つの説によりますと、まずイギリスではビルの賃貸賃借契約というのが非常に長いんですね。20年というのはむしろ短い方で、50年とか、あるいは99年とか、そういった非常に長期にわたるビルの賃借契約というのが結構一般的ということになっています。20年未満という場合は、20年たった時点でかなりそのビルの価値が下落するだろうということを想定して、そのようなことが想定されるような契約に関しては減価償却を行うべきだというような考えが働いているようです。
それから、開示項目としては、鑑定人の氏名または資格、評価に用いた基礎。さっきの設例を見ていただければ何ですけれども、不動産鑑定士協会の制定したガイドラインに基づいて評価しましたという、そういったくだりの説明があります。それから、評価を実施した者がその会社の従業員または役員であるか否かについて説明するということです。
あともう1点、ちょっとここで挙げなかったんですが、会社法との関係について一つ申し上げておいた方がいいと思うんですが、日本でいう商法と会計基準の整合性をどうするかということですが、イギリスの会社法は、基本的には固定資産はすべて減価償却をしなさいということになっておりますので、このIAS19号を適用することは、会社法とは基本的に相入れないことになっています。多分ここにいらっしゃる皆さんは御存じだと思うんですが、イギリスの会社法は基本的に会計基準が真実かつ公正な外観を呈する場合は、会社法を無視しても、無視してというか、より望ましい会計基準の方を採用しなさい、ただし、その場合はその採用している旨、及び会社法を適用した場合の影響額ですね、乖離の影響額について説明することが求められています。これも同じことが求められています。今、時間の関係で申し上げませんけれども、最後に載せた小さな注記だけの設例がありますけれども、会社法の開示と反している設例がここの部分です。
それから、国際会計基準との相違点ですけれども、国際会計基準においては、公正価値評価、また原価評価を選択することができますが、UK、イギリスの会計基準は基本的に公正価値評価が原則になっています。国際会計基準においては、これはどちらがベンチマークかというのは特に決まってなくて、公正価値評価及び原価評価の間、どちらでも対等の関係にある、ただし、原価評価を採用した場合は、当該投資不動産の公正価値を注記しなければならないということが大きな特徴と言えましょう。
それから、最後になりますけれども、我が国において投資不動産の会計を入れるに当たって一番ネックになると思われるのは2番目の公正価値評価の実施可能性ということで、どういった公正価値を、何をもって公正価値とするのかという部分、今までの議論にもなっていることと関係するんでしょうけれども、その数字をどうやってとるのかということが一番の大きな問題点になってくるのではないかなと思われます。
簡単ですけれども、以上にしたいと思います。
- ○辻山部会長
-
ありがとうございました。
ただいまの山田参考人の御報告に関しまして、御意見、御質問のある方はちょうだいしたいと思います。また、減損会計を最優先の課題としていることとの兼ね合いもございますので、この機会に投資不動産の問題について、もし御意見、御質問ございましたら、幅広くちょうだいしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
- ○逆瀬委員
-
山田先生に質問であります。イギリスのルールの御説明、レジュメの3枚目に投資不動産の範囲ということで定義の御説明をいただいていますが、一番下のラインで、グループ内という言葉で書かれているわけです。このグループ内という意味は、連結子会社とか持ち分法対象の関連会社とか、そういうふうに理解すればいいのかどうかというのがまず1点目であります。
もう一つは、後ろから4枚目ですね。会計処理、公正価値で評価するんだという御説明です。このときに会社法との関連の御説明をいただきまして、会社法とは違うんだということも御説明いただきました。そうしますと、処分利益にはなるのかならないのかという話がもう一つの質問で、もう一つ税の方は、これはどう扱っているんだろうかなというのが3つ目の質問であります。
以上でございます。
- ○山田参考人
-
まず第1点の御質問に対してですけれども、原文にもう一度立ち返ってみますと、先ほどごらんいただいたPart 2-Difinition of termsの中のパラグラフの8番の(b)がそれに該当するところですけれども、ちょっと読みますが、A property let to and occupied by another group company is not an investment property for the purposes of its own accounts or the group accounts. ということで、ここで想定しているのは、自分の単独の、単体の財務諸表にしろ、連結財務諸表にしろ、その中に含まれているグループ会社に対する投資不動産の賃貸は含めませんということですから、御指摘の質問に答えるとすれば、それは連結の対象になっている子会社、あるいは持ち分法適用会社ということになると思います。
- ○逆瀬委員
-
そういたしますと、身内に貸しているものは慮外になるということで、別のルールで減損の問題が処理されるのかどうか、すべてお目こぼしなのか、これだとちょっとまだわからないものですからね。そこなんですね。借りている例えば連結子会社は事業の用に供して使っているんでしょうね。又貸ししているかもわかりませんけどね。この辺のところなんですけれども。
- ○山田参考人
-
今お話がありましたように、では借りている側はその借りている資産を本社のビルとして使う、あるいは従業員の住宅として使う等々の、そういった何らかの事業の用に供しているのであれば、連結全体から見ると、それは投資不動産ではなくて、事業の用に供されている資産としてみなされるんじゃないかということだと思います。
ただ、それはこのSSAP19号の基準から外れるので、お目こぼしか、公正価値で評価減、あるいは評価増しといったことをしなくていいのかということに関しては、今度はこれは実質的に使用を目的とした資産ですから、通常の固定資産として減価償却をして、減損会計があれば、イギリスにも減損会計が今度新たに導入されましたけれども、その対象になると思われますが。よろしいでしょうか。
- ○逆瀬委員
-
はい、わかりました。
- ○山田参考人
-
それから、2番目の公正価値、会社法との違いということで、そこで計上された部分が配当可能利益を構成するのかどうかということですけれども、これに関しましては、私もはっきりこうですとはお話しできないんですけれども、これは私の推定ですけれども、恐らくイギリスの会計基準を適用して計上された利益ですので、これは配当可能利益を構成すると思われます。イギリスのもう一つの固定資産の再評価というのがまた別に会社法の制度としてあります。イギリスの会社法は、資産の評価としてヒストリカルコストか、オルタナティブバリュエーションかということで、原則は固定資産の取得原価がベースですけれども、代替的手続として固定資産の再評価を行うことが継続的な適用を前提として認められています。その場合の再評価は再評価積立金として同様に資本の部に持っていきますけれども、この部分は配当可能利益には加算されないんです。では、配当可能利益に関する会社法上の規定は何かというと、日本の商法上の配当可能限度額の計算のような細かい規定はなくて、基本的に会計上正しく計算された会計上の利益をベースにするというふうにありますので、これは私の私見ですけれども、恐らく配当可能利益を構成すると思いますが。
それからあと税務上の扱いですけれども、これもイギリスでは固定資産に関して会計上の扱いと税務上の扱いは全く別に行われています。会計は通常の適正な組織的な減価償却を行っていきなさいということですけれども、税務上はキャピタルアローアンスといいまして、似て非なるものなんですけれども、定率的に、税法が決めた資産の種類等にかかわらず、一定額で償却していく、あるいは25%で償却していくというような形で行っていますので、恐らくここの会計上のSSAPの19号の扱いとは全く別に、税務上は固定資産にかかわる認識というのは別に行われているんじゃないかなと、この点も申しわけありません、私の推察でしかないんですが、と思われますが。必要であればまた調べまして、部会長等を通してきちんと正式にお答えいたします。
- ○逆瀬委員
-
ありがとうございました。恐縮です。そうすると、再評価積立金は税効果の計算なんかを加味しないという感じですか。それはまた別なんですかね。会計上ですね。税効果をとって積み立てる。
- ○山田参考人
-
でも、税金との乖離を、PLは通しませんけれども、純資産額の変動に影響を与えますね。
- ○辻山部会長
-
その点に関しましてですけれども、ついでに恐縮なんですけれども、このレジュメの会計処理というところで、投資不動産の価値の変動部分というのの扱いでございますが、現在では、ここに損益計算書となっておりますけれども、総認識利得計算書との関係で、ただいまのことですけれども、総認識利得計算書経由のものも資本の部に現在、先ほど資本の部に直課ということでしたけれども、総認識利得計算書を通してということが一つありますね。
それから、再評価積立金のところは、資本の部が実現部分と未実現部分に分かれているということはないんでしょうか。それで区分しているという。ですから、この損益計算書の意味が何かという。そこで言っている利益が何かということなんですけれども、この点について今の税法、それから商法との関係が絡んできますので。
- ○山田参考人
-
まず、このSSAP19号を適用することによって損益計算書に影響が出てくるのは、原始取得価格を公正価値が下回った場合に関してだけですね。上回っている、あるいは上回ったものが原始取得価格まで下落していく過程においては、損益計算書を全く通さない形をとっていますから、ここで出てくる損益計算書に計上されるのはあくまで原始取得価格を下回った場合の評価損部分という形です。
- ○辻山部会長
-
そうなんですけれども、この損益計算書以外に総認識利得損益計算書というのがございますよね。そこで評価益が出た場合は、一応資本の部でも実現部分、損益計算書経由の部分とそうでない部分に区分されていますよね。実現部分について、他の法律と連動しているということはないんでしょうか。
- ○山田参考人
-
総認識利得計算書の出発点はPL上の利益が出発点ですね。その中に、さらにPL上認識されていない純資産を増減させる項目がこの総利得認識計算書の方に含まれてくる項目ですけれども。
- ○辻山部会長
-
それがBS上の資本の部で一たん投資再評価積立金に計上されますけれども、そのうち損益計算書に入ってくるものが資本の部でも別区分になっているのではないでしょうか。それが実現部分として配当可能利益であるとか税の対象になるという扱いはどうなんでしょうか。
- ○山田参考人
-
このケースですと結局、損益計算書に計上されるようなケースというのは、資本の部にある再評価積立金を全部食いつぶしてしまった状態ですね。ですから、資本の部に計上されているバランスとして残っている再評価積立金の中に実現、未実現があるんではないかということは……。
- ○辻山部会長
-
いえ、違うのです。残っている部分について、先ほど配当可能利益になり得るというお答えだったので、御質問しているんです。
- ○逆瀬委員
-
今のところ、我々作成者の方はぜひ他国の事例もよく勉強したいということもあって、大変恐縮なんですけれども、後刻でもお教えいただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。
- ○辻山部会長
-
その点についてはまた後日調べた結果をお伝えするということでよろしいでしょうか。
- ○辻前企業会計専門官
-
山田先生にちょっと教えていただきたいんですけれども、先ほど会計処理の中で賃借契約により使用する不動産の話があったんですけれども、それは例えばリース資産みたいなものですか。
- ○山田参考人
-
そうですね。この会計処理の前提としては、賃借不動産をリース資産、ファイナンスリースとしてバランスシートに載っけているということがまず前提にあります。ファイナンスリースを適用した結果、計上されているバランスシート上の賃借不動産の扱いをどうするかということで、その賃借期間が20年未満か20年を超えるかで扱いは異なってくる。20年を超えるものについては、このSSAP19号を適用して、恐らくリース会計を適用して計上されている帳簿上の価格と、その資産そのものの公正価値を比較して、このSSAP19号は適用されると思います。
- ○辻前企業会計専門官
-
それともう1点なんですけれども、最後のページに不動産鑑定評価人不足の現状というふうに書かれておられのですが、例えばイギリスと日本と比較した場合に、何か感じの違いというか、層の厚さの違いみたいな、そういったようなことははっきりしているんでしょうか。
- ○山田参考人
-
私も統計的数字が今手元にあるわけではないので、では具体的に対象となる会社に対して不動産鑑定士が何人いるかという情報は持ち合わせてないんですけれども、まずイギリスの会社というのが、基本的には株式会社であれば、どんな会社も監査の対象になります。すべての会社が公開会社であれ、非公開会社であれ、それは登記所と呼ばれるところに会計報告書をファイルしなければいけませんので、一たんファイルされた会計報告書はだれでも見ることができます。そういう意味では、もともとIASの19号自体が、だれを評価人にするのかについて少し柔軟な規定を持って、小規模会社に関してはあえて不動産鑑定士を使わなくてもいいでしょうと。
決め方としては逆で、基本的にまず不動産鑑定士の評価は自分でもいい、ただし、大規模会社に関しては不動産鑑定士を使ってくださいというような書き方になっているんですけれども、そういった現状において、では日本で、もし仮に投資不動産の会計基準を日本の会社に適用するときに、対象となる会社、仮に上場会社を対象とした場合と、それ以外の上場会社以外の大規模会社を対象にするのか、そういったことによっても鑑定士の数は変わってくる。あるいは日本の会計基準の中で、そういった身内の人ですね、社内の人を鑑定士というか、評価者として認めるのかどうかというのも議論の対象になってくるんじゃないかなと思いますけれども。評価を実施した者が当社の従業員または役員であるか否かということもありますので、役員自身が自分たちの所有している投資不動産の評価はこうですよということを決めることもできるんですね。ただ、その場合であっても、会社のダイレクターが評価しましたということを開示しなければいけないということです。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
小宮山委員、どうぞ。
- ○小宮山委員
-
時間がないので、手短に一つだけ。この本文の方に書いてありましたし、SSAPの7項にもあるんですけれども、開発が完了していることというのが要件になっていますですね。ここに示していただいたアニュアルレポートですか、わかりませんけれども、これを見ると開発中の不動産というのが2行目にありまして、会計方針の開示を見ると、インベストメントプロパティ全体がオープンマーケットバリューで評価されるというふうに書いてあるように思えるんですけれども、東京の都心の中に工事が途中でとまってしまった幽霊ビルとか、開発するつもりであったという土地はかなりたくさんあるんですけれども、プラクティスとして、これはどういうふうにイギリスでは考えられているんでしょうか。もしわかったら教えていただきたいと思うんですけれども。
- ○山田参考人
-
私も正直申し上げて、向こうに駐在していたのがかなり昔になりまして、特にこの投資不動産を持っていた会社ばかりをやっていたわけじゃないので、経験も限られているんですけれども、まずここの言い回しの整合性に関しては、恐らく書き方として、fully developed propertiesを意識して書いているんではないかなと思うんですが。
実際に、ではそういった開発途上の不動産、あるいは開発が継続的でなく、途中でとまったままずっと開発が継続されて行われない資産についてはどうするのかということですよね。多分、まずこの対象から外されるということは、恐らくこれはいわゆる通常の固定資産であれば、建設仮勘定ですか、コンストラクション・イン・プログレス的な扱いになる。通常の固定資産であれば、その建設仮勘定というのは減価償却の対象になりませんから、持っているままになっています。ただ、その開発がストップしたまま持っている建設仮勘定、将来開発が終わって事業の用に供せられることができないことはわかり切っている固定資産については、そこから何らかの減損を認識するのかどうかということについては、私の経験はないんですけれども、今新しく導入されたFRSの12号でしたか、11号でしたか、減損会計の中で議論されているのかなと思います。それもあわせて宿題とさせていただきます。
- ○辻山部会長
-
ありがとうございました。
それでは、よろしいでしょうか。そろそろ予定の時刻を若干超過しましたので、本日の部会はこれで終了とさせていただきたいと思います。
山田参考人には、本日お忙しいところ御報告をいただき、大変ありがとうございました。
なお、次回の当部会の日程ですけれども、12月8日(金)午後3時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。次回は、固定資産の減損会計のうち、資産のグルーピングの問題、さらに全社資産をどう扱うのか、のれんをどう扱うのかという問題について、引き続きヒアリング及び意見交換を予定しております。正式には改めて事務局より皆様に御案内させていただきたいと思います。
本日は、皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。これで散会とさせていただきます。

 検索
検索