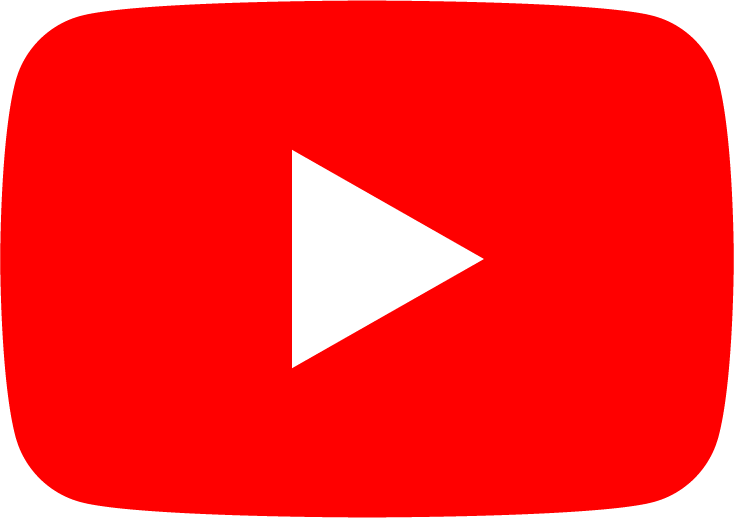- ホーム
- 審議会・研究会等
- 企業会計審議会
- 議事録・資料等
- 企業会計審議会「固定資産部会」
- 企業会計審議会第7回固定資…
平成13年5月10日
金融庁
企業会計審議会第7回固定資産部会議事録について
企業会計審議会第7回固定資産部会(平成13年4月13日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。
(問い合わせ・連絡先)
金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局
企業会計審議会第7回固定資産部会議事録
日時:平成13年4月13日(金)午後3時00分~午後4時58分
場所:中央合同庁舎第4号館10階共用第一特別会議室
- ○辻山部会長
-
定刻になりましたので、ただいまから第7回固定資産部会を開催させていただきます。本日は、皆様方お忙しいところをご参集いただき、ありがとうございました。
本日は、まず委員の異動についてご紹介します。
当部会では、昨年9月の第1回の部会以降、前回まで、固定資産の会計処理に関する論点の整理で整理された各論点に沿って審議を進めてきたところでございます。
今後、実務的、具体的な観点からさらに検討を深めるため、4月10日付で新たに6名の方が企業会計審議会幹事に任命され、当部会に参加されることになりましたので、ご紹介いたします。
まず、笠間達氏です。
- ○笠間委員
-
笠間でございます。よろしくお願いいたします。
- ○辻山部会長
-
次に、高野博信氏です。
- ○高野委員
-
高野でございます。よろしくお願いいたします。
- ○辻山部会長
-
次に、清水明彦氏です。
- ○清水委員
-
清水です。よろしくお願いいたします。
- ○辻山部会長
-
次に、田辺剛氏です。
- ○田辺委員
-
田辺でございます。よろしくお願いいたします。
- ○辻山部会長
-
増田悦佐氏はちょっと今遅れておりますけれども、後ほど到着されましたらご紹介させていただきます。
次に、奥田かつ枝氏です。
- ○奥田委員
-
奥田でございます。よろしくお願いします。
- ○辻山部会長
-
新しく加わられた方々には、今後の審議にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
なお、新しい当部会の名簿をお手元に配付しておりますのでごらんください。
それでは早速ですが議事に入りたいと思います。
前回は、投資不動産の問題、米国における減損会計の実例、のれんの会計処理に関する米国の動向について、ヒアリング及び意見交換を行いました。
本日はまず、奥田委員から、不動産鑑定の実務についてご報告いただき、意見交換をしたいと思います。
次に、増田委員から、アナリストの立場から不動産の会計や評価の問題等についてご報告いただき、意見交換をしたいと思います。
なお、奥田委員及び増田委員以外の今回新しく委員になられた笠間委員、高野委員、清水委員、田辺委員からは、次回以降、固定資産の減損会計や投資不動産の問題について詳しくご報告をいただきたいと思いますが、本日は時間の許す範囲内で一言ずつご発言いただきたいと思います。
ただいま増田委員が到着されましたので、改めてご紹介いたします。増田悦佐氏です。
- ○増田委員
-
増田です。よろしくお願いします。
- ○辻山部会長
-
よろしくお願いいたします。
それではまず、奥田委員から、不動産の鑑定評価の実務についてご報告いただき、意見交換をしたいと思います。
それでは、奥田委員、よろしくお願いいたします。
- ○奥田委員
-
奥田でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、不動産鑑定を行う立場から、鑑定につきましての基本的な考え方をご説明いたしたいと思います。ただ、本日ご説明いたしますものは、時価評価にそのまま当てはめてご説明するものではございませんので、その点についてはご承知おきをいただきたいというふうに思っております。
それではお手元の資料の方をごらんください。
「わが国における不動産鑑定評価の実務」ということで、まず不動産鑑定評価において求める価格についてご説明いたします。
鑑定評価におきましては、不動産鑑定評価基準という評価のよりどころとなる憲法のようなものがございまして、そこに鑑定評価において求める価格を3つ規定しております。1つがこのページにございます正常価格でございまして、あと2つが後ほど出てまいります限定価格、特定価格というものでございます。このうち、鑑定評価で求める価格の中心となっておりますのは、ここにございます正常価格ということになります。
では、正常価格とはどういうものかということなんですが、鑑定評価基準によりますと「正常価格とは、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格」ということになります。ここで合理的な市場ということなんですが、合理的な市場とはどういうことかと申しますと、「市場統制等がない公開の市場で、需要者及び供給者が売り急ぎ、買い進み等特別の動機によらないで行動する市場」というふうに定義されております。
もう少し説明いたしますと、下の
 になりますが、正常価格とは「対象不動産がその属する市場において現実に成立するであろう価格」ということになっております。普通、不動産市場につきましてはかなりいろいろの個別事情が反映されて価格が形成されるのが一般でございますので、その中で鑑定評価として求める価格は、あくまでも市場を前提としながらも、その市場において合理的な一定の条件を満たす価格という形で求められます。
になりますが、正常価格とは「対象不動産がその属する市場において現実に成立するであろう価格」ということになっております。普通、不動産市場につきましてはかなりいろいろの個別事情が反映されて価格が形成されるのが一般でございますので、その中で鑑定評価として求める価格は、あくまでも市場を前提としながらも、その市場において合理的な一定の条件を満たす価格という形で求められます。ここで合理的な条件、合理的な市場の条件ということになりますが、これはどういうものかと申しますと、先ほど申し上げましたように、市場統制等がない公開の市場であること、需要者及び供給者が売り急ぎ、買い進み等、特別の動機によらないということが明記されております。そのほかに、鑑定評価基準では明記されておりませんが、通常の販売期間、マーケティングタイムと言われているような、こういった期間市場にさらされていること、また価格時点において成立することなどが合理的な条件であるというふうに解釈されております。
この正常価格は鑑定評価において中心的に求められる価格でありまして、金融機関が融資を行う際の担保評価の掛け目をかける前の価格、こういった担保評価ですとか、あるいは各種の資産評価、一般の売買の参考価格、そのほかに地価公示ですとか路線価、固定資産税評価等の公的評価一般において求める価格というふうになっております。
次のページへまいりまして、次に、では正常価格と公正価値というものはどのような点で違うのか、また同じなのかという点について触れさせていただきます。ここで書いておりますのは皆様既にご存じのことかと思いますので、多少繰り返しになってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。
まず、国際会計基準によりますと、その中の定義で「公正価値とは、取引の知識のある自発的な当事者間で、独立第三者間取引条件により資産が交換され、又は負債が決済される価格をいう。」というふうになっております。
また、投資用不動産について書かれました第40号を見ますと、その29におきまして「投資用不動産の公正価値は、一般に市場価値である。公正価値は、」云々ということと、B53におきまして「IASCの考える公正価値概念は、IVSCの市場価値概念と類似している。」ということで、IVSCの市場価値のものが引用されているというような形になっております。
このように、公正価値が市場価値と同じということで考えれば、すなわち、正常価格と公正価値には違いはないということに解釈されるかと思います。
ただ一方で、次のページへまいりまして、昨年の7月1日に発行されました国際評価基準、この国際評価基準の方を見ますと、その中の基準2の「市場価値以外の価値の評価」というところの6.7というところで、「会計で用いられる公正価値という用語が、市場価値と異なるということは大事なことである。」ということで、「公正価値がIVS1の項目3.0において定義される市場価値の要件を満たしている場合は、公正価値と市場価値は等しくなる。」しかし「処分に必要とされる適切な時間があり、強制や強要の要素が全く存在しないという基準を公正価値が満たしているときは、公正価値は市場価値そのものである。」ということが書かれておりまして、この定義からいたしますと、処分に必要な適切な時間ですとか強制や強要の要素の存在ということが公正価値と市場価値を区別するポイントとして説明されております。
この考え方に従いますと、公正価値と我が国の鑑定評価基準における価格との関係は次のように考えることができるのではないかということです。
すなわち、公正価値には正常価格と特定価格の一部、特定価格については後ほどご説明いたします。例えば特定価格の一部に早期売却市場というものがございますけれども、早期売却市場価格というものが公正価値にも入ってくるということになります。すなわち、公正価値というものは、正常価格という一般に定義される市場価値よりも広い概念であって、公正価値定義を満たす限り、市場で成立するすべての価格を含むというふうに解釈することができるのではないかということです。ただ、ここに書かせていただきましたのはあくまで個人的な見解でございますので、鑑定協会としての見解ということではございません。
次に、鑑定評価基準に書かれております2番目の価格ですが、限定価格というものがございます。限定価格とはどういうものかと申しますと、ここに書いておりますが、「市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき合理的な市場で形成されるであろう市場価値が乖離することにより、市場が限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を表示する価格」であるということになります。
この部分を読んだだけではわかりにくいところもあるかと思いますので、具体的な例示をここに入れてございます。
1つが、例えば借地権者が底地を買う場合、あるいは隣接する不動産を併合する場合、あるいは経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買、このような場合には、価格が一般の市場価格とは乖離してまいりますので、そのような場合に成立するであろう価格を限定価格という形で定義しているわけでございます。
では、次のページの4ページをごらんください。3番目の価格は特定価格でございます。
特定価格とはどういうものかと申しますと、「特定価格とは、不動産の性格により一般的に取引の対象とはならない不動産又は依頼目的及び条件により一般的な市場性を考慮することが適当でない不動産の経済価値を適正に表示する価格」ということになります。すなわち、特定価格は必ずしも市場において成立することを前提としない価格が入ってまいります。
具体的にはどういう場合があるかというのを例示しておりますが、1つは宗教建築物等の特殊な建築物の鑑定評価を行う場合、不動産についての市場がない、あるいは極めて小さいというような場合でございます。
2つ目といたしましては、会社更生法による更生目的の財産の評価を行う場合、3番目として担保としての安全性を考慮することが特に要請される場合、ここまでが不動産の鑑定評価基準に例示として挙げられているものでございます。
それで、(ニ)(ホ)(ヘ)につきましては、今の鑑定評価基準には例示されておりませんが、昨今、鑑定評価ニーズにこたえまして、留意事項としてここ2~3年の間に作成され、その中で明示されている価格でございます。
1つが、会社更生法の場合以外の場合において、事業の継続を前提として鑑定評価を行う場合、民事再生法に基づく財産の処分を前提とする鑑定評価を行う場合、資産の流動化に関する法律ですとか投資信託及び投資法人に関する法律に基づく不動産の証券化に関し、投資採算価格というものを求める場合が挙げられます。
これらの特定価格と正常価格との具体的な違いは、先ほども申しましたように必ずしも市場で成立することを前提としていないということ、したがって、依頼目的や鑑定評価を行う目的によって、評価額決定のために必ずしも鑑定評価の3手法と言われております原価法、収益還元法、取引事例比較法によって求められた価格を比較考量する必要がない、すなわち1手法によって求められた価格でも鑑定評価額を決定することができるというようなことが違いとして挙げられます。
次に、5ページにまいりまして、先ほどの特定価格の中の1つの例示と、それから使用価値との関係でございますが、この点について触れさせていただきたいと思います。
まず、使用価値の定義ですが、これも皆様ご存じのことかと思いますが、まず国際評価基準、基準2 3.1によりますと、「使用価値とは、特定の使用者にとっての特定の使用方法における特定の資産の持つ価値」というふうに書かれております。一方、国際会計基準の第36号によりますと、「使用価値とは、資産の継続的使用とその耐用年数の終了時における処分によって生じると予測される見積将来キャッシュフローの現在価値」ということになります。
この定義から考えますと、使用価値は、前ページの特定価格の中で(ニ)として例示いたしました事業の継続を前提とする鑑定評価、これに近い形になってくるのではないかと思われます。ここで「近い」というふうに書かせていただきましたのは、事業の継続を前提とする鑑定評価にも実はいろいろございまして、1つは、その鑑定評価を行う場合に、市場の標準的な条件を採用する場合でございます。この場合には明らかに鑑定評価ということになってくるわけなんですが、特定の使用者の特定の使用方法に基づく方法、これに基づいて評価を行うということになりますと、これは鑑定評価であるのか、コンサルティングあるいは意見価格と言われているものですが、こうなるのかというところがはっきりしていないところでございます。
と申しますのは、鑑定評価基準におきましては、その中で明示されているわけではございませんが、解釈として鑑定評価で求める価格というのは、売り手ですとか買い手のどちらにも偏らない中立的な価格ということになりますので、あくまで前提とする条件は標準的なものであって、どちらかに偏った特定の条件ではないというふうに言われているためでございます。
この考え方からすると、使用者の特定の条件に基づく価格というのは鑑定評価額ではないのではないかというふうな考え方が出てくるわけです。ただあくまでこれは鑑定評価基準に基づく価格を鑑定士が鑑定評価としてできないということであって、鑑定士が評価できないというわけではございません。あくまでも鑑定評価基準に定める鑑定評価ではないということを言っているだけでございます。ただこの部分につきましては極めて線引きが難しいところもございますので、はっきりどちらというふうに現時点で申し上げることはできないということです。
また、
 として、国際会計基準によれば、使用価値は、「将来キャッシュフローの割引現在価値により求められる。」というふうになっておりますので、この手法自体は鑑定評価基準に定めるまさに収益還元法であるということが言えるのではないかというふうに書かせていただきました。
として、国際会計基準によれば、使用価値は、「将来キャッシュフローの割引現在価値により求められる。」というふうになっておりますので、この手法自体は鑑定評価基準に定めるまさに収益還元法であるということが言えるのではないかというふうに書かせていただきました。鑑定評価基準に定める価格についてのご説明はここまでといたしまして、後ほどご質問等がありました承りたいと思います。
次に、6ページの方にまいりまして、公示価格・路線価・固定資産税評価額等の公的評価と言われているものにつきまして若干説明させていただきたいと思います。
6ページをめくって7ページの方をごらんください。ここにあります「公的評価の概要」ということで一覧表にいたしましたのは、公認会計士協会の方で出された「監査委員会報告第69号付録2」に掲載されておりました表に部分的に加筆したものでございます。上から5行目の公表時期までは同じでございまして、次の地点数のところに*印、これがちょっと加筆した部分なんですが、公示価格、それから都道府県地価調査による価格というのは、これは鑑定士によってすべて鑑定評価が行われている。路線価、固定資産税評価額というものは、これすべての路線価、すべての固定資産税評価額が鑑定士による鑑定評価額ということではなくて、鑑定士が行う鑑定評価と申しますのは、その中で標準宅地として設定されたポイントについて何点か評価を行って、この評価額をもとに各担当機関において価格を決定しているという形になっております。
対象不動産の類型ですが、評価の対象とする類型はいずれも更地ということで、建物が全くないということを想定した価格になっております。路線価の方は、これは借地権割合を出す必要がございますので、借地権も評価対象になっているということです。
それから、1つ飛ばしまして不動産鑑定士等が行う鑑定評価の方法ですが、これはいずれも更地を求める場合には原則鑑定評価の3手法と言われております原価法、取引事例比較法、それから収益還元法の3手法を併用して求められた価格を比較考量して決定するという形になっております。
ただ既成市街地につきましては多くの場合原価法の適用が困難でございますので、取引事例比較法と収益還元法が適用されております。
価格水準につきましては、公示価格は更地の市場価格、都道府県地価調査による価格も公示価格と同水準ということになります。一方、路線価及び固定資産税評価額の方は、鑑定士が行う評価は公示価格や地価調査の価格と同じように更地の市場価格ということになりますが、この価格に基づいて各価格決定機関が公示価格の概ね80%ですとか70%の水準に具体的な価格を決めている、そういった形になっております。
次に、8ページにまいりまして、鑑定評価の手法についてご説明いたします。
鑑定評価の中には、価格を求めること以外に、賃料を求めることですとか借家権の権利の価格を出すこととか、いろいろあるわけなんですが、ここでは不動産の価格を求めるための手法についてご説明いたします。
まず原価法という手法がございます。これはどういうものかと申しますと、「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める」ということになっております。すなわち、価格時点において対象不動産と同等のものを新たに調達することを想定して、ここで求められた価格に対象不動産の実情に合わせて減価修正を行って価格を求めるということになります。減価の要因としては、機能的、物理的、経済的な減価要因というものがありまして、必ずしも耐用年数が何年だから幾らということでは決められないような形になっております。
この減価修正というのは、ここに入れてあります機能的、物理的、経済的というような各減価要因を総合的に分析することによって求められるものでございまして、期間的な損益計算を正確に行おうとする企業会計上の減価償却とは本質的に目的の異なるものとなっております。
次に、取引事例比較法ですが、「取引事例比較法とは、まず、多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。」ということです。
取引事例比較法というのは、類似の取引事例から対象不動産の価格を比準して求めましょうということで、まさにここに書いてあるとおりであって、なじみがある方法かと思いますので、これ以上の説明はここでは特にはいたしません。
次に、9ページにまいりまして、収益還元法でございます。「収益還元法とは、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法」でございます。そのうち収益還元法の具体的な手法として直接還元法ですとかDCF法などがあるということです。このほかにもインウッド法ですとかホスコルド法とか、細かい方法はございますが、大きく分けて直接還元法、DCF法があるということです。
まず、直接還元法でございますが、これは収益価格を単純に1年間の純収益を還元利回りで割ることによって求めるということです。すなわち、ここで予測された1年間の純収益が半永久的に続くとか、あるいは一定の趨勢を持って続くなどの予測を立てると直接還元法の式が導かれますので、こういった形で価格を求めようという方法でございます。
不動産鑑定評価における還元利回りの求め方ですが、ここに主な方法を3つ入れてございます。1つは取引事例ですね、取引利回りから求めるということです。取引利回りとは、取引事例の純収益を取引価格で割ったものでございます。ただ、一般に取引事例から得られるのはせいぜい求められて粗利回り、総収入を取引価格で割った粗利回りというものでございますので、これに対象不動産の状況に応じて経費率を考慮いたしまして、経費率を1マイナス経費率ということで掛けて還元利回りベースの取引利回りを求めるという方法をとります。
もう1つの方法は、割引率というものをまず求めまして、これから純収益の将来予測される平均変動率を控除して求めるという方法がございます。この方法は、先ほどご説明いたしました公的評価、地価公示などにおける土地の評価で収益還元法、土地残余法と言われている手法ですけれども、土地残余法と呼ばれる収益還元法を適用する場合の還元利回り、これはこの方法で求められております。
3番目の方法としては、これは対象不動産が土地と建物等から構成されている場合に、土地の還元利回りと建物の還元利回りをその価格割合で按分して一体の還元利回りを求めようということで、土地建物投資一団法というふうに言われているものでございます。
次に、DCF法ですが、DCF法も皆様ご存じのように、DCF法というのはここにありますような式であらわされまして、一定期間、n期間についての各年度の純収益を1つ1つ現在価値に割り引きまして、最後、n年度終わった時点の対象不動産の復帰価格、その時点における対象不動産の価格を同じく現在価値に直しまして、すべて合算して価格を求めようという手法でございます。
DCF法を適用する場合に、割引率というものを求めなければいけないのですが、不動産鑑定評価における割引率の求め方としては、まず1つが、取引利回り、IRRという形で求められますが、これから求める方法、2つ目としては、国債等の利回りに不動産のリスクプレミアム、個別あるいは全体、不動産一般のリスクプレミアムを加算して求める方法、それから、先ほどの割引率から求める方法の逆になりますが、還元利回りに純収益の将来平均変動率を加算して求める方法、また、借入金と自己資本のそれぞれの収益率を元本割合で按分して求めるという借入金・自己資本一団法というふうに鑑定評価では呼ばれております方法などがございます。
ただ、現在、DCF法につきましてはここ2~3年の間にかなり適用例がふえてきておりますけれども、まだ指数化されているようなものがございませんので、各鑑定士の方ではいろいろな手法を併用しながら比較考量して総合的に判断して適切な割引率を決めている、そういった形になっております。
ここでちょっと、ゴシックで書いておりますところなんですが、不動産の鑑定評価においては、その中心となる正常価格を求める場合において、市場における価格形成がどのように行われているのか、例えば収益価格で取引されているのであれば、採用される還元利回りや割引率が市場においてどのように決定されているのか、こういった分析を行うことが重要となるという、当たり前のことですが、入れてあります。
すなわち、例えば、還元利回りが市場において取引利回りから導かれているのであれば、やはりそれを重視する必要があるかと思いますし、そうではない土地建物一団法で価格が形成されているのであれば、そういった手法を重視することも重要になってくるのではないかということで、対象不動産の属する市場の分析を十分に行った上で利回りは算定する必要があるのではないかということをここでは言っているわけでございます。
それから、3つ目の*印といたしまして、DCF法を適用する場合には、n期間の純収益の予測を1つ1つやっていくことが必要になるわけなんですが、これは鑑定評価では対象不動産の過去の推移ですとか、それからその対象不動産の類型とか用途に応じた市場動向、その中に占める対象不動産の競争力、こういったものを鑑みながら予測していくということで、これもかなり難しい作業になっております。
純収益の予測の期間なんですが、当然これは対象不動産によっても変わってまいりまして、かなり将来予測が難しいものについて10年というような長期予測を立てても、それは作文をしているようなものでございますので、そういったものの場合にはかなり短期で見なければならないというようなことですとか、かなり予測期間と純収益の予測の正確性というのが密接な関係を持っているということでございます。
次に、将来の純収益予測と収益還元法の方法について補足ということなんですが、これはあくまでも原則としては、収益還元法というのは将来の純収益の予測ができなければ正確な価格が出ないものでございますので、原則としてはあくまでも詳細な予測を行って、それぞれに応じた割引率を適用し、収益価格を求めることが必要であるということでございます。
これは最近、投資用不動産の評価、証券化関係の評価で、投資家に対して十分な情報開示を行っていかなければいけないというような評価で、この原則的な考え方がクローズアップされております。
ただ、そうはいっても、個別の不動産では将来の予測がかなり難しいものがございますので、その他として、例えば土地(更地)の評価の場合であれば、先ほどの直接還元法というような、収益に一定の仮定を設けて、この短年間の収益が永久に続く、あるいは一定の趨勢で続くというふうに考えて直接還元法を適用することが実際としては行われております。
また、土地に収益用不動産ですとか、あるいは分譲の建物を建設することを想定する場合には、開発法と言われているような手法も適用されております。
次に、12ページの方をごらんください。「不動産の用途別評価の特徴」ということで幾つかの類型、用途に応じてこのような考え方をとっておりますというものを簡単に載せさせていただきました。
まず、不動産の評価をする場合に、当然に明確にすべき条件なんですが、求める価格はどのような価格であるのか。また対象不動産の最有効使用というものはどういうものであるのか。ここで最有効使用というのは、客観的に見て、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高、最善の使用方法というふうに言われておりますが、こういった対象不動産の最有効使用は何であるのか、また対象不動産の属する市場というものはどのようなものであるのかということで、これは市場分析の方につながってまいります。ここでは、価格が正常価格を求めるのだということを前提としてご説明させていただきます。
まず賃貸用の不動産ですが、賃貸不動産というのは、当然賃貸されておりますので収益性を重視した評価ということになります。そういたしますと、当然に収益還元法が中心になっております。ただ、適切な取引事例が得られれば取引事例比較法も有効でありますし、経済的、物理的、機能的減価というものが、特に中古建物の場合にこれが問題になってまいりますが、これが適切に把握できれば原価法も有効ということになります。
さらに詳細な調査に基づくキャッシュフローの予測と、不明事項、調査によってわからなかった部分、将来のキャッシュフロー予測が変動するかもしれないという不明事項、そういったものも含めまして、不明事項のリスク評価などが求められてくるということです。
普通、賃貸用不動産というと、土地と建物が一体となっている不動産ででございますので、収益還元法を適用する場合には当然に土地と建物を一体として評価するということになります。
次に、事業用不動産ですが、ここでは事業用不動産として工場、店舗、ホテルということで入れております。
 として事業収益に基づく収益還元法が重要となります。この場合、鑑定評価で行う対象不動産ですが、鑑定評価の対象はあくまで不動産ということになりますので、企業全体の価格を求めるということではなくて、そのうちの構成単位の1つである不動産の価格というものを求めることになります。また、さらに、複数の不動産を一体としての評価ではなくて、個々の不動産、1つ1つの不動産、単体での評価というものが鑑定評価ということになってまいります。
として事業収益に基づく収益還元法が重要となります。この場合、鑑定評価で行う対象不動産ですが、鑑定評価の対象はあくまで不動産ということになりますので、企業全体の価格を求めるということではなくて、そのうちの構成単位の1つである不動産の価格というものを求めることになります。また、さらに、複数の不動産を一体としての評価ではなくて、個々の不動産、1つ1つの不動産、単体での評価というものが鑑定評価ということになってまいります。複数不動産を一体とした評価も、これは鑑定士ができないということではなくて、この場合は例えば調査価格ですとか意見価格というような形で行われております。
そういたしますと、例えば事業全体の価格なり、事業全体から上がる純収益を不動産に配分することが必要になってくるわけなんですが、個々の不動産に配分する方法としては、大きく分けて2つの考え方がございます。
1つは、そもそも上がってくる全体の事業収益を各不動産に配分して個々の不動産について収益還元法を適用する。これはある程度独立して独立採算をとっているような形の不動産であればこういったものを適用することができるかもしれません。しかし多くの場合にはかなり個別の不動産に収益を配分することが難しいケースが多くなっておりますので、この場合には全体としてまず収益価格を求めまして、それを不動産に配分するという形になります。
この場合に、不動産に配分する場合の方法ですが、これは多く使われる方法が、1つは積算価格比で配分するというものでございます。これは大阪地裁の判例にもございますけれども、有効な収益配分ができないということであれば、積算価格比による配分もやむを得ないということがございまして、こういった形で使われることがございます。
次に、事業収益の場合の純収益の把握ですが、一応不動産に帰属する収益としては次のような考え方をとっております。すなわち、事業利益から不動産以外のほかの資産等に帰属する収益を控除した残余の利益として不動産に帰属する収益を把握するということでございまして、具体的には売上高から売上原価ですとか販売費、一般管理費、役員報酬、配当等経営者帰属利益、その他控除すべき項目を控除いたしまして不動産に帰属する収益を求めるということです。
この中で、例えば本社ビルのケースでございますけれども、事業利益全体の中から本社ビルに帰属する収益を把握するということは困難であります。したがいまして鑑定評価の実務では、一般に当該ビルを賃貸することを想定しまして、賃貸収入から上がる収益、これが不動産に帰属する収益であるとして収益還元法を適用するケースが多くなっております。
実際、鑑定評価の実務では、事業全体の中で本社ビルの資産評価を行うというよりも、本社ビルを会社から切り離して市場で売却するとしたら幾らかというような目的で評価を行うことが多くなっておりますので、そういったことからも賃貸を想定して評価を行うということが多いということが言えるかと思います。後は、類似の不動産の取引事例があれば、当然取引事例比較法も使います。
また、収益還元法や取引事例比較法の適用が困難な場合には原価法というのが重要な位置を占める形になるということでございます。
次に、更地ですが、更地の評価の場合には取引事例比較法というのが最も一般的に、標準的な手法として使われます。それ以外に、先ほども申しました土地残余法と言われる収益還元法、これは更地に最有効使用の建物を想定して、土地建物一体の不動産から上がる純収益のうち、土地に帰属する純収益を求め、これを還元利回りで還元して収益価格を求めるという方法でございます。
そのほかに、分譲を予定している敷地ですとか、あるいは収益用不動産の建設を想定した収益性を重視した価格を求めるということであれば開発法というような手法が使われます。
次に、建付地ですが、ここで建付地とはどういうものかと申しますと、「建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地」ということで定義しております。先ほどの更地が建物が全くないという前提であるのに対しまして、建付地は建物があることを前提とした土地の価格ということになります。
建付地の価格についての考え方ですけれども、そもそも建付地というのは、建設のための計画ですとか、建設という段階を経て稼働している建物の敷地でございますので、不動産の事業リスクというものが更地と比べて小さいというふうに考えることができます。
すなわち、建付地には、最有効使用の状態にするための時間やコストが既にかけられておりますので、その分開発利益が含まれている。したがって更地価格よりも高くなるというふうに考えられるわけです。
これは、下の矢印がありますが、左にありますように、使用方法が最有効使用の状態にあれば更地価格よりも高い価格を有するということになります。ただ、一方で不適切な、最有効使用とは認められないような不適切な利用ですとか管理運営がなされている場合には、それが資産価値を低めておりますので、これが土地にも当然反映しているということで、最有効使用の状態にない場合には更地の価格よりも低くなるケースも出てまいります。
評価方法としては、類似の建付地がありましたら取引事例比較法ができますし、あるいは収益還元法、更地価格との比較検討を行うということですとか、あと、ここにはございませんが、例えば土地建物一体の収益価格を土地建物の積算価格比で按分するというような価格も参考として使われます。
最後に開発途中の不動産ですけれども、この場合の考え方といたしましては、開発途中の不動産の場合は、建築途中の建物、これは不動産ではございませんので、これを除いた土地部分が不動産の鑑定評価になるという形になっております。
以上でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの奥田委員のご報告に関しましてご意見、ご質問のある方はご自由にご発言いただきたいと思います。品川委員どうぞ。
- ○品川委員
-
ちょっと何点かご質問したいのですが、ページの順番でさせていただきますが、4ページに特定価格を算定する場合の例示の中の(ヘ)で不動産の証券化の問題に関して、この辺、非常に関心のあるところなんですが、ここで投資採算価格を求める場合に特定価格となっておるのですが、投資採算価格というのは通常は収益還元価格と同じ概念ではないかと思われるのですけれども、ここに特定価格として特掲したということは、別であるということで出していると思うのですが、別であるとした場合に、還元率を何%に想定しているのか。
収益還元法について不動産鑑定士協会では、標準的な還元率を5%だというふうにかつて公表したことがあったかと思いますが、その還元率との異同がどうなっているのかということについて教えていただければと思います。
それからもう1点は、8ページにいきまして、不動産鑑定については取引事例比較法が一番重視されるかと思うのですが、これについては取引価格も必要に応じて時点修正を行うということが言われているのですけれども、最近のように地価がずっと10年間も下落しているような場合に、取引価格それ自体は評価時点から大体半年とか1年とか、かなり遡った前の取引価格をもとにして時点修正を行うと思うのですけれども、具体的にそういう地価が下落しているときにどのような時点修正を行うのかということについて教えていただければと思います。
それから、あと、全体的な問題で、今、3つの鑑定方法についてご説明があったわけですが、かつて鑑定評価基準では3つの評価額を算定して、それぞれ調整してその正常な価格を算定するというふうに解説等があったかと思うのですけれども、今のご説明ですと、資産に応じて適切な評価方法を適用させるようにというふうにも感ぜられたのですが、実際はこの3つの評価額というのはどういうふうに調整するのか、あるいは調整しないのか、あるいは先般の公示価格の公表に当たって、日本経済新聞で10年間公示価格が下落したとはいえ、収益還元価格からいくと東京の都心はまだ1.5倍高いとか、大阪の都心は1.8倍高いとか、名古屋は2倍するとかというようなことが新聞報道されていたのですが、そういうことと収益還元価格とどういうふうに調整しているのか、3点ほどちょっとご説明いただければと思うのですが。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
質問が3点にわたっておりますので、1点ずつよろしくお願いいたします。
- ○奥田委員
-
まず4ページのところの特定価格の例示にございます(ヘ)の投資採算価格でございますけれども、これはわかりやすいところで理解していただきますれば、投資採算価格というのは対象不動産から上がる、証券化の場合ですけれども、証券化というのは基本的に投資家は対象不動産から上がるキャッシュフロー、これを非常に重視することになりますので、このキャッシュフローに基づく価格のみで価格を求めようという形になっております。
一般に鑑定評価を行う場合には、先ほども先生おっしゃいましたけれども、3手法による価格を求めまして、それらを比較考量して決定するということになりますが、投資採算価格の場合には収益価格のみで価格を決めるという形になっております。そういたしますと、鑑定評価の目的等に照らしまして、これは特定価格になるということでございます。
ただ、この投資採算価格を求める場合には、そこで使う、例えば割引率ですとか、直接還元法に基づく還元利回りは、これは市場で使われている利回りを使いますので、特にこの場合に割引率なり還元利回りが高くなるというようなことではございません。あくまでも市場性を考慮した価格を求めるということです。
先ほど5%というお話がございましたけれども、5%というのは、これは土地残余法を適用する場合の基本利率と言われているものでございまして、これは土地の割引率の方に相当することになります。土地の収益還元法を適用する場合につきましては、むしろ基本利率から変動率を考慮する形になりますので、還元利回りとしては別の形で求められるということでございます。また土地建物を一体とした複合不動産の場合の還元利回りも必ずしも5%ということではございません。
- ○品川委員
-
そうしますと、この投資採算価格を求める場合の還元率は5%より低いのですか。今の市場金利でいくと相当に低くなりますが、具体的には何%ぐらいでやっているのですか。
- ○奥田委員
-
これは、証券化の対象になる不動産には実はいろいろ類型なり、所在地域、ばらばらございまして、必ずしも一律に何%というものがあるわけではございません。当然リスクの高い不動産であれば利回りが上がってまいりますし、そうではない安定したものということであれば低くなる、こういうことでございます。
- ○品川委員
-
利回りでなくて還元率を決めないと価格自体が決まらないですね。だから収益があることと、その収益を何%の市場金利で割り戻すかということとは別な話ですから、収益が高いということと還元率を何%にするということは別なことじゃないですか。
- ○奥田委員
-
収益がどれくらいあるかというのをまず予測いたしまして、利回りを決める場合にはその収益が将来どれぐらいぶれるリスクがあるのか、また価格がどれぐらい変動するリスクがあるのかということを考慮して利回りというものは決めてまいりますので、個別の不動産によって変わってくるということでございます。
- ○辻山部会長
-
では、2点目をお願いいたします。
- ○奥田委員
-
2番目ですけれども、8ページの取引事例比較法のところで、時点修正をどのようにということなんですが、確かに価格の下落がある場合には、将来どのようにという問題が出てくるわけなんですが、通常鑑定評価では価格時点に極めて近い取引事例を使うようにしております。そうするとぶれがまず小さくなるということと、それでも過去の事例になってしまいますので、その過去の時点から価格時点までの時点修正をどのようにするかということですが、価格時点がさらに過去であれば、その時点までの変動率というのは大体わかる。価格時点が将来の場合ですと、これは将来例えば1年後とか2年後というような鑑定評価は一般に受けません。これは全く予測の範囲外であるということですので、余り価格時点が将来先にある場合には鑑定評価そのものは受けないで、意見価格ですとかコンサルティング価格というような形で出します。
価格時点が例えば1カ月後ですとか2カ月後、あるいは3カ月後ということで、比較的近い時点であれば、過去の趨勢とそれからここ数カ月の間に起こるであろうことを想定して出します。ただその場合であっても、例えば1週間後に大地震が来るかもしれませんので、そういった予測できないことについては考慮外というような条件をつけて鑑定評価を行っております。
- ○品川委員
-
具体的に今年の公示価格について鑑定の対象になっていると思うのですが、1月1日の価格を鑑定する場合に、取引が半年前、7月1日の取引だとしますと、半年間のタイムラグがあるのですが、その場合はよく1月1日から1月1日間の1年間の価格変動率というのは、これは公表されるのですけれども、その1月1日の鑑定評価をするときには半年前の変動率がわからないわけですね。それはもう鑑定士の大体推測で調整して、ある程度の値下がりをするだろうということを織り込んでやるのですか。もしそれをやると、公示価格というのは際限なくどんどん下がっていくように、何か矛盾を抱えているように感じられるのですけれども、その辺はいかがですか。
- ○奥田委員
-
まず公示価格の場合ですが、価格時点が1月1日であれば、鑑定評価を行うのはその後になります。したがって1月1日というのは既に終わっているのですね。だから取引時点から1月1日までというのはもう既に現象としてわかりますので、その間、例えば取引事例等を分析して、どれぐらい変動率があるのじゃないかということで計算しております。
- ○品川委員
-
ちょっとしつこいようで申しわけないのですけれども、公示価格は1月1日の価格を公示するわけですから、それのためにはそれ以前の取引価格とか、あるいは取引事例の場合はそれ以前の取引価格ですから、当然半年とか1年前の取引価格を基準にして時点修正する。それで私が聞きたいのは、そういう今のような現状で時点修正を具体的に、仮に何%の下落率を見込んでやるのかどうか、そういう具体的な調整方法について教えていただければと思ったのですが。
- ○奥田委員
-
時点修正率は、普通取引事例を幾つか分析して、例えばこの地域のこういうような土地であれば大体幾らぐらい半年くらいで下がっているというのを、幾つか事例を見るわけですね。そこから対象不動産にそれを持ってきて当てはめて考えるということなんですけれども。もっと具体的というのは、例えば……。
- ○品川委員
-
私はかつて国税庁で相続税の路線価の責任者をしていた経験があるもので、こういう細かいことを聞いて恐縮なんですが、路線価をまとめるときに公示価格をもとにするのですけれども、公示価格に対しては余り批判がなくても、路線価に対してはものすごい批判があるわけですね。路線価に対して批判を言うなら公示価格に対してなぜ批判を言わないのかということをいつも疑問に思っていたのですが、それというのも、いろんな特定の地域で取引が生じている地域については取引価格に準じて公示価格を下げるのですが、余り取引がない地域については、値段が下がっていても前の年の取引価格をほとんど修正しないという、非常な矛盾があって、地域間のバランスを欠いているものがよく見受けられたものですから、実際時点修正がきちんと行われていればそういうアンバランスがないだろう、そういうふうに考えてちょっと細かい質問をさせていただきましたので。
- ○辻山部会長
-
この点についてはよろしいでしょうか。
- ○品川委員
-
結構です。
- ○辻山部会長
-
では第3点目のご質問。
- ○奥田委員
-
3点目のご質問として、鑑定評価の3手法によって求められた価格をどのように調整して鑑定評価額を決めるかということなんですが、これは基本的には市場分析が重視されるということになります。
対象不動産の市場を分析いたしまして、その中でどういう価格が重視されているのかということ、まずこれが第1点です。
後は評価を行うに当たって、当然そういった形で市場で重視されている価格であれば、得られている資料も信頼できる資料が得られておりますのでその価格が使える。そうすると資料が十分になかったような手法によって求められた価格というのは、これは余り重要視することができないというような形になっております。すなわち、要するに市場分析を行って、対象不動産の価格形成がどのようになされているのかということに基づいて3つの価格を調整するということになります。よろしいでしょうか。
- ○品川委員
-
必ず3つの価格を算定するのですか。
- ○奥田委員
-
原則として3つ行います。ただ、先ほども申しましたように、更地価格を出す場合には、原価法、土地の素地からそれにいろいろと造成をして宅地にするための原価法というのがあるわけなんですが、通常、既成市街地であれば既にもう宅地化されておりますので、原価法というのはほとんど適用されることはございません。そういったことで若干、2手法の場合もございますけれども、原則は3手法の適用ということになっております。
- ○品川委員
-
わかりました。どうも。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。そのほか奥田委員の報告に関してご意見、ご質問ございますでしょうか。太田委員。
- ○太田委員
-
12ページの不動産の用途別評価の特徴のところの事業用不動産の評価、こういうことができるのだなと思ったものですので、そうするとこの場合に、例えば事業用不動産として工場ですとか店舗、ホテルを評価されるということで、事業収益から評価額を出していくということではないかと思います。
この場合に出てくる評価というのは、例えば、工場であれば工場一体として、例えば、その中に含まれている設備ですとか、もうちょっと極端なことを言ってしまえば働いている人とか、そういうある意味での全体としての評価額が出てくるということでよろしいでしょうかという点と、このような評価を実際にやられる場合に、事業収益から多分評価額を出されるということかと思うのですが、具体的には事業収益というのはどういう方法をお採りになられるのか、教えていただければというふうに思います。
- ○奥田委員
-
まず最初のご質問ですけれども、先ほど申しましたように、鑑定評価で求める価格というのはあくまでも不動産の価格になりますので、不動産の価格に帰属しない収益というものは基本的には除かなければいけないということになります。従いまして、労働力ですとか、あるいは機械、設備につきましても、これらに帰属する収益がわかれば、まずそもそも収益を求める段階で控除するわけなんですが、これらがかなり求められないケースが多くなりますので、求められた価格から、例えばその機械等の簿価を引くとかいうような形をとりまして不動産の価格を求めるというような方法を採ることが多くなっております。
もう1つ、事業収益そのものの出し方ということかと思いますけれども、事業収益につきましては、こちらで不動産鑑定士としてわかる場合にはいただいた資料で把握するのですが、わからない場合には公認会計士の先生ですとか税理士の先生等にご相談をしながら、あるいは依頼者にご相談をしながら収益というものを全体として把握していくというような形をとっております。
- ○辻山部会長
-
よろしいですか。
- ○太田委員
-
済みません。そうするとあくまでも事業収益というのは所与のものとして進められるということですね。
- ○奥田委員
-
はい。
- ○太田委員
-
わかりました。
- ○辻山部会長
-
そのほかございますでしょうか。どうぞ、高野委員。
- ○高野委員
-
13ページの一番下のところなんですけれども、本社ビルの場合というところで、2行目のところで「当該ビルを賃貸することを想定し、」とありますけれども、この賃料というのはどんなふうに考えられるのでしょうか。その設定という意味でですけれども。
- ○奥田委員
-
鑑定評価で求める価格、正常価格の場合には市場価格を求めますので、賃料も市場の賃貸条件を対象不動産に比準いたしまして対象不動産の賃料を設定いたします。
- ○高野委員
-
そうすると、会社の収益とかは全く関係なく、通常そこの場所であればこのくらいの価格だというのから想定するということでしょうか。
- ○奥田委員
-
さようでございます。
- ○辻山部会長
-
そのほかございますでしょうか。品川委員。
- ○品川委員
-
質問ではないのですけれども、7ページの表について幾つか気になることがありますので確認していただければと思います。
この表で路線価のところですが、地点数は、これは数値で表わすべきだろうと思うのですが、現在約40万地点あると思うのですけれども、そういうふうに対比していただいた方がわかるかと思いますし、固定資産税の場合は、私の記憶では1億6,000万地点か何か、そのぐらいあるかと思います。
それから地点数の中の括弧書きの中で、相続税法について地方税法388条を引用しておりますけれども、元々、この路線価等は国税庁長官の通達によって行われるので、地方税法が引用されるということはあり得ないので、ちょっとここの記述は問題があるのじゃないかと思います。
以上です。
- ○辻山部会長
-
ただいまのはご指摘ということでよろしいでしょうか。
- ○奥田委員
-
ありがとうございました。
- ○辻山部会長
-
ほかにございますでしょうか。
それではまた後ほど質疑の時間もございますので、次に増田委員から、アナリストの立場から不動産の会計や評価の問題等についてご報告いただきたいと思います。増田委員よろしくお願いいたします。
- ○増田委員
-
それではご報告させていただきます。
私にご下命されたご質問というのは、基本的に証券アナリストが企業会計の資料を一体どういう形で、あるいはどういう目的のために使っているのかということとの絡みで、今の企業会計における資産の評価法についてどんな問題点を日々の活動で感じているのか、その辺のお話になりますので、緻密に法律論や何かを討議してというようなお話とは大分かけ離れた、実態的なお話が多くなるかということをあらかじめお断りしておきます。
まず、2ページ目を開いていただきますと、証券アナリストというのは一体何のために会計情報を使っているのかという、ある意味で非常に大きな問題なんですが、私はもう単純に言いまして、株主が投下した資金を増加させている企業なのか、横ばいに保っている程度の企業なのか、それとも減少させている企業なのかのふるい分けをするためにアナリストは会計情報を使っていると思います。
これについては実は色々と、企業会計の考え方と株式市場が企業会計をどう考えるかという、その接点みたいなところに思想潮流みたいなものがございまして、大体欧米では1970年代ぐらいまで、日本ではごく最近までは、企業会計で収益を出すところまでと株価水準というのは全く切り離された別個の外生変数というような形で見ていて、最後に例えばPER、これは株価収益率ですけれども、あるいはPBR、株価資産価格倍率、あるいは株価キャッシュフロー倍率、こういった比較指標を最後に持ってくることで、外生的に形成された企業収益とそれから株価とを最後に比べてみて、比較感、割安感、割高感の目安にするというような評価法を使っていたわけです。
ところが、欧米では80年代ごろから、日本でも最近3~4年ぐらい顕著になってきた傾向として、株価を企業収益の外生変数と考えるというのは非常にリアリティーのない話ではないのか。つまり株価が下落するということは、即その株を発行している企業にとって、時価発行をするときにできる資金調達量も下がるわけですし、社債、転換社債、ワラント債を出すときの条件も悪くなるわけですから、株価を外在変数として見て収益を構成するという考え方そのものが間違いである。
実は日本の企業会計の教科書なんかですと、今だに、自己資本というのはほとんどコストのない資金であって、コストはせいぜい配当原資ぐらいであるというような間違った考え方から、株価形成と収益との接点をなくしてしまったような発想をする教科書が見られますけれども、少なくとも株式市場の現在の潮流としては、そういう考え方は誤りであって、株価形成を自己資本のコストと考えない考え方というのはおかしいというのが主流となりつつあります。
次のページに移っていただきまして、そうすると一体どういう変化が起きてくるのかというと、例えばの話、自己資本比率は高ければ高いほどいいというような無借金経営を目指すべきという抽象的な理想論みたいなことを今だに振り回す例えば経営学者とか会計学者の方々もいらっしゃるのですけれども、現実の株式市場というのは、少しでも信用力のある企業はむしろレバレッジを効かせた方が評価も高い。どちらかといえば無借金経営というタイプの会社は、財務体質はいいのに何でこんなに万年割安に評価されているのだろうというような会社が多くなります。
これは、経済利益、つまり株価を評価するための企業分析の一番根本にあるのは、その企業が投下した資本の利益率として、その資本のコストに見合うものを上げているのか、コストに見合うもの以上上げているのか、あるいはその未満のものしか上げられないでいるのかという評価をする、それが一番大事な評価のポイントだという考え方をしますと、例えば万年割安株みたいなものというのは、実は自己資本のコストを0と考えているために、非常に膨大な固定資産に自己資本がずっと張りついていて、そこからの収益はほとんど0に近くても、全くそれがバランスシートにも損益計算書にも反映されていないので、見かけ上割安に見られるだけであって、実はその自己資本が張りついている固定資産のオポチュニティーコストは莫大であるというような場合が多いわけです。
次のページにいっていただきまして、自己資本のコストというのは実は配当原資とは全く無関係でして、株価が変動するリスクそのものが自己資本のコストなんですけれども、そういう考え方をすると、なぜ多くの無借金経営企業が割安に放置されているのかというのがよくわかります。
自己資本、他人資本を問わず、投下した資金量に対する収益が低い、あるいは収益成長率が低い企業は株価も下がる、あるいは株価上昇率が低いのが通例であって、それは株価評価が低ければ、時価発行増資、普通社債、転換社債、ワラント債を発行するときの条件が悪くなる、すなわち自己資本の調達コストが高くなるわけでして、そうなった企業が株価評価が低いのは、これはもう当たり前なことのわけです。一種、同義反復のようにお考えになるかもしれませんけれども、株式市場の実際の株価の値動きと企業のさまざまな財務活動、営業活動との組み合わせを見ているとこういう結論が出てくるわけです。
そこで問題なのが、自己資本というのは、実はそれ自体一義的に定義できるような概念ではなくて、残余概念だということです。つまり、自己資本というのは企業の総資産から他人資本を引いた残余という形でしか求めようがないわけです。ところがここで、日本の会計原則がいわゆる取得原価をいつまでも簿価にとどめ置いていいという、そういう原則によって立っているわけですから、一般論として日本の企業の自己資本を正確に推定するような方法はありません。つまり、バランスシートの貸方というか、資産側については、これは取得価額評価になっていて。現実の世の中でもしそれを例えば換金するとすればどういう金額になるかとはかけ離れたような金額がいつまでも続いていて、他人資本を幾ら使っているかというのが一番わかりやすくて、これはかなり正確に推定できるわけですけれども、そうすると全く現実性のない貸方の資産の合計額からかなり正確に推定できる他人資本の金額を引いた自己資本額というのは、非常に現実とはかけ離れたようなものになるわけです。
次のページにいっていただきまして、先ほど来申し上げています企業評価をするときに往々にして万年割安とか万年割高とかという銘柄があることの1つの理由は、企業のバランスシートを見ても、特に不稼働資産、低稼働資産が多いわけではないけれども、実は時価で評価すれば非常に不稼働資産、低稼働資産が多いような会社が往々にして万年割安になっていますし、他人資本をかなり大きく取り入れている会社というのは、早い話、毎年毎年金利を払わなければいけないわけですから、めったにそういう低稼働資産、不稼働資産を延々と抱えている場合はない。ただこれは、例えばバブル崩壊直後なんかには例外的な現象として非常に多く見られるということはありますけれども、基本的には、他人資本が多くてギアリングの高い会社ほど、必要に迫られて、低稼働資産、不稼働資産は少なくしているという一般論が成り立ちまして、ですから見かけ上のアノマリー、万年割安とか万年割高というのは、資産評価を正確にすればほぼ解決がつく問題であると思います。
それと同時に、我々が普通、経済活動で幾ら儲かったかということを考える場合に、基準とするのは決して売上高ではなくて、一体幾ら元手を投下して、その投下した元手に対して幾ら儲かったかという話をするわけですけれども、現在ただいまの企業会計というのは、損益計算書には一切その投下資本の概念は登場しませんし、バランスシートに出ている自己資本あるいは投下資本というのは、これはかなり大部分と言っていいものが、現実の市場価格とはほとんどかけ離れた簿価評価、取得原価評価になっている。従って、我々は、実は企業の分析をするときに、一体幾らの元手に対して幾ら儲かったのかということがわからないまま企業の業績を評価しているわけです。
これは非常に危険なことでして、特にバブルが膨張して崩壊する過程で、我々企業を分析している証券アナリストは非常に大きな世の中をミスリードするようなことを多々申し上げてきたわけですけれども、弁解ではなく、私はやはり、幾らの元手を投下したものに対して幾らの利益があったのかということがわからないで、これはもう暗闇でめくらめっぽう鉄砲を撃っているようなものですから、たまたま当たったときがラッキーであって、当たらない方が普通なのだという考え方をすべきじゃないかと思います。
世の中には、どうも証券アナリストという存在は、何らかの魔術的な方法を用いてそもそも資料としてわかってないものをイマジネーションで補正してきちっとした答えが出せる存在である、あるいは少なくともよい証券アナリストというのはそういう魔術的な力を持っている存在であるというような、そういう見解もあるようでして、これはアメリカなんかで証券アナリストで異様に高い社会的地位を占めていることと決して無関係ではない潮流だと思うのですが、ただ、ないところから有を生み出すことはもともとできないわけですから、まず企業が一体幾らの元手をかけて、その元手に対して幾らの儲けを得ているのかという評価をするためにも、資産の適正評価というのは、これはもう避けて通れない必要不可欠のステップだと思います。
次のページへいっていただきまして、具体的な話として、建設・不動産アナリストであれば、ほかの産業を担当しているアナリストよりは企業の資産価値について少しはましなguessをできるのじゃないかというような、そういうことを期待していらっしゃる皆さんもいますけれども、これもまた全く幻想としか言いようのない話でして、例えば、今の有価証券報告書には、賃貸不動産を大量に所有している不動産や建設会社であれば、必ずと言っていいぐらいに稼働中の物件についてかなり詳細な土地面積と取得地価、建物延床面積と建設費マイナス当該年度までの減価償却費累計、この一覧表は出ております。この一覧表が出ているから、その不動産会社、建設会社の賃貸不動産の時価を再構成することができるかというと、これは不可能です。
なぜ不可能かといいますと、まず、原則として建物自体を現場で見たことがなければ、具体的にどこにあるのかということがわかりません。不動産というのは、ここにいらっしゃる方に対してこういうことを申し上げるのは釈迦に説法でしょうが、もう道路1つ隔てているだけで全く価値が違うというようなことがよくあることでして、何丁目ぐらいまでの地名が出ていたとしても、それは実際にその物件の価値をはかるためにはほとんど役に立ちません。
もう1つは、取得時点の記載がありません。これは大きな物件については会社の沿革の中に、これこれの年に建物が竣工したとか、その建物を取得したとかいうのは記載はあるのですけれども、それよりもかなり重要な位置を占める土地の取得については原則として全く何の資料もないと考えた方がいいわけです。したがって、取得時の時価から現在の時価を推定する方法としては、たまたまその物件の個別開発地を知っていて、いつごろどの程度の土地を取得して、またその次の時点にどのぐらいの土地を取得して、実際には上物が建つまでにこういう土地取得史があって、その上にどういう建築費でどういうものを建てたかみたいなことまで知悉している必要があります。どんなに少数の企業しか担当してないアナリストにとっても、例えば2~3社しか担当してないアナリストにとっても、1企業の個別物件の開発史を網羅的に熟知しているというようなことはあり得ないわけです。
ということはどういうことになるかというと、賃貸物件というのは、恐らく有価証券報告書の中での不動産資産の情報開示の中では優等生というか模範生というか、一番詳しく細かく書いてあるものだと思います。それにしてこの状態ですから、もっと曖昧な、例えば固定資産の中に入っているけれども未稼働で、稼働する予定もない物件ですとか、あるいは分譲用不動産なんかの場合には、この程度の資料さえないというのが実情なわけです。
そうすると、先ほど申し上げましたように、特に例えば建設・不動産業界を長年担当していたアナリストだからといって、企業の資産価値を正確に推定する方法、魔法のようなものを持っているかというと、そんなものは全くないわけです。
以上申し上げてきたことをまとめますと、7ページに移りますけれども、原則論を申し上げれば、資産の時価会計というのは、これはもう焦眉、不可欠の課題でして、これをやらなければ、企業担当証券アナリストが、ある企業が一体儲けを出しているのか、それとも実は損をしているのか、その程度のことさえも正確にはわからないという、それだけ大きな問題なわけです。
ここまでは恐らくここにいらっしゃる皆様方にもそんなに大きな反論も疑問も招かずに申し上げることができたことだと思うのですけれども、これから先がちょっと問題になってきまして、例えば、今盛んに議論されている問題で、固定資産の時価評価について、まずとにかく減損分だけは強制的に評価を変えさせるけれども、キャピタルゲイン分についてはとりあえず放っておこうですとか、あるいは時価会計をするにしても、毎年毎年バランスシートを洗い替えして評価が変われば評価差損、評価益を立てろということまで強制するのか、それともバランスシート自体には取得価額評価を認めておいて、つまりは毎年の評価益、評価損は損益計算書に反映させないでもいいというような、ある意味で妥協案、便法を使ってもいいのか、そういうような議論については、これは私の全く個人的な見解で、証券アナリストの大多数がそう思っているであろうとか、あるいは証券アナリストの中にこういう見解をとるべきだという私自身が考えを持っているかというと、そうでもなくて、全くの私の個人的な見解なんですけれども、やはり時価評価を徹底させるのであれば、評価損だけは強制的に出させるけれども、評価益は出させないですとか、あるいは評価損、評価益は棚上げにして、バランスシートの注記事項だけで時価がどこにあるのかを推定はできるようにするというような便法はとるべきではない。
なぜとるべきではないのかというと、これはもう本当に原則論になってしまいますけれども、株式市場というのも企業会計というのも、究極の目的は希少な資源を有効利用、適正配分する、そのために存在するわけですから、例えばぎりぎり厳しい経営をしている中小企業ですとか、そういう会社が評価益を立てさせたら評価益倒産してしまうというようなことを考慮して、減損会計だけにとどめて評価益はとりあえず待ちましょうとか、あるいはバランスシートの注記事項だけにして、損益計算書には反映させないようにしましょうというのは、要するにその企業は、評価益が出た資産を持っているとすれば、そこで本来活用すべき機会を活用しないという機会費用を出しているわけですから、そういう機会費用をなるべき最小化するためにも、時価会計原則というのはバランスシートの付記事項ではなくて、やはりバランスシートそのものの洗い替えに発展するというか、そこまで透徹すべきであろうと思いますし、評価益、評価損というのは毎年毎年の損益計算書に出すべきであろうというふうに私は個人的に考えます。
次のページにいっていただきまして、そこまでは非常に時価会計を原則どおり、公式どおりに適用すべきだという威勢のいい話で済むのですけれども、それから先、例えば時価評価を一体いかなる会計原則に基づいて算出するのか、その算出された時価評価というものが一義的に確定するようなものであるのかということについては実は非常に多くの困難があって、私はこれは余り簡単には適用できない話ではないのかなという危惧、不安を抱いております。
その最大の理由は、先ほど来かなり詳細に、今、日本の不動産鑑定士の方々というのは、正当なというか、公正な不動産評価の方法というのは比較事例法、原価法、収益還元法を全部使った、その全体を組み合わせての算出だということをおっしゃったようですけれども、投資家の目から見ると、資産の評価として収益還元法以外の評価はあり得ないと思います。収益還元法以外に資産の評価法というのはないという点については、少なくともインベストメントコミュニティー、投資家の世界の間ではもう共通の見解となっていて、これ以外のことを主張する方々というのはめったにいらっしゃらないと思います。
ただ問題はその次のページなんですけれども、私は日本の賃貸不動産を、例えば収益還元法で評価するとします。そうすると一物四価とか一物五価とかいうようなことがよく言われていますけれども、実は日本の賃貸不動産というのは一物百価、一物千価の世界で、これは収拾のつかないことになりかねないという危惧を抱いております。
なぜこういう一見大げさにも見えるようなことを申し上げるのかといいますと、日本の稼働中の賃貸不動産というのは、同じビルの同じ床面積を実際に貸している金額が千差万別です。これはまたもう1つ遡って、なぜそういうことになっているかというと、現行の借地借家法が異常なまでにテナントの居住権を尊重する形になっておりますので、テナントはたった2年の1回きりの契約を結んだだけでも事実上は永続居住権を得たような状態になっておりまして、さらにそのテナントは実際上、家主の賃料値上げ提案に対して拒否権を持っております。拒否権を持っているために継続賃料というのは傾向的に新規賃料と全く違った動きをします。例えば、バブルのころ、新規賃料が年率で20%、30%上がった時代にも継続賃料の方は大体社会的良識の範囲内とされている2年間の契約更新時に10%から15%の範囲内に止められていたわけです。
こういった状態が5年とか10年続きますと、継続賃料は新規賃料の半分ですとか3分の1ですとか4分の1というようなことがあり得るわけです。これ自体も非常に大きな問題点なんですけれども、もう1つ派生的な問題がありまして、その派生的な問題は何かというと、日本の賃貸市場というのは非常に不思議な市場でして、次のページにいっていただきますけれども、大体普通、経済情報というのは取引の一方の当事者が秘匿することに利益を感じていれば、反対側の当事者は秘匿することに余り利益を感じていなくて、その結果何とか相対の取引の中で必要最低限の情報は開示されるというメカニズムが働くのですけれども、日本の個別の賃貸不動産に対して個別のテナントが幾らの賃料を払っているかという資料は、これは非常に不思議なことに、家主側もテナント側も開示することに何の利益も見出すことがなく、両方が秘匿することに利益を見出しておりますので、ほとんど外部からは伺い知ることができないブラックボックスになっております。
私はどちらがより深刻な問題かというと、千差万別の賃料設定が実際になされているということよりは、むしろお互いに、家主もテナントも、自分が幾らの賃料を特定の床面積に対して取っているか、払っているかを秘匿することに共通の利害の一致を見てしまうということの方がむしろはるかに深刻な弊害だと思うのですけれども、そういう状態ですので、日本の不動産会社の賃貸資産が幾らの利回りで運用されているかということは、賃貸不動産のポートフォリオで知ることはできますけれども、個別の物件の個別の、例えばこのビルの1階のこの床面積を占有しているこのテナントが幾ら払っているかということは全く伺い知ることができないわけです。
そこから派生してくるもう1つの問題点として、つまりは大家とテナントとの間の賃料設定はいかようにも恣意的に変えることができるということになります。例えば20年、30年ずっといるテナントの継続賃料が新規賃料よりもはるかに低いというのは、これは現行の法制度のもとではある程度いたし方がない面があるのですが、そういうふうにあっちこっちにいろんな賃料を払っているテナントが現に存在しているということがあるために、新規にスペースをとるテナントについても、そのテナント企業の例えば社会的な信用力ですとか、あるいは財閥グループ、メインバンクグループのかかわり合いですとかでいかような賃料設定をしてもそれが通る、そういう世界なわけです。
そこが私は、日本の賃貸不動産市場をこれから健全で流動性の高いものにしていくためには最大のネックになるのではないかと懸念しておりまして、そこから導き出される結論として、収益還元法を用いると、ありとあらゆる賃貸不動産が、例えば何年ごろ入居したどのテナントがいつごろ退室して、そこにどういう賃料で新しいテナントが決まるか次第でいかような収益をも想定することができて、つまりはどういう資産価値を計算することもできるというようなことさえも理論的には考えられるわけです。
そこまで問題を突き詰めて考えますと、私はやはり、収益還元法に基づく資産価値を一義的に定義することというのは、現行の借地借家法がテナントの持続的な占有権を余りにも過大に保護しているために、テナントが継続賃料値上げについて拒否権を持っているという状態が解消するまでは不可能なのではないのかなという気がします。
もう1つ具体的なエピソードというか、事例を紹介させていただきますと、先ほどの不動産鑑定士の方からのご説明の中に、本来であればもう既に開発が済んで実際に収益を出している物件というのは更地よりも評価が高くてしかるべきである、評価が低いのは、それは既に稼働している物件の使用方法が有効でなかったり、管理が悪かったりという状態であろうというお話があったのですが、実は日本の不動産市場を実際に見てきた目で考えますと、更地の方が稼働中の資産よりもはるかに価格が高く評価されてきたことの方がむしろ常態であって、バブルが崩壊してからは多少状況が変わってきましたけれども、ほぼ一貫して更地の方がむしろ稼働中物件よりも高い評価を市場ではしてきた。
それは決して単純に投機的な熱狂のために行き過ぎた買い焦りがあったということではなくて、実際に稼働している物件はそれぞれの稼働年代に応じて低い継続賃料で入居し続けているテナントが既についておりますから、そこから得られる賃貸収益というのは上限が非常に低く設定されざるを得ないわけです。それに対して更地というのはこれから開発すれば、原則として全部新規テナントの賃料で入れるというようなことで、万年、更地は割高、稼働中物件は割安というような価格形成がされてきたわけでして、こういうようなことも含めて、私は固定資産の評価というのは、収益還元法に基づく時価評価をする以外には、少なくとも企業会計を株式市場のアナリストとして見た場合にはあり得ないと信じているとともに、その時価評価のための収益還元法のもとになる賃料収入というのは、1つ1つのビルの1つ1つの床面積については全くのブラックボックスであって、これを外部から情報を開示させることが一体できるのかどうか、開示させた場合に、今の日本の賃貸市場というものが大混乱を起こすのではないのかというような、非常に実際的な危惧を抱いております。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。
それでは、次に、増田委員からのただいまのご報告に関しましてご意見、ご質問のある方はいただきたいと思います。品川委員どうぞ。
- ○品川委員
-
今のご報告、興味深くお聞きしたのですが、ちょっと体験的な話を交えてお伺いしたいのですけれども、今のご説明ですと不稼働の財産を抱えているような会社は当然株価は下がる、これは1つは右肩下がりのときはまさしくそのとおりだと思うのですが、かつて私は、株を買わないと経済がわからないと言われて、自分で一生懸命証券会社に通ったころのアナリストの説明ですと、どこそこの会社はどういう含み資産を持っている、稼働してない資産を持っている、これはいずれは株価に反映されて、今買っておくと大変得をするという、そういう甘いささやきを随分受けたことがありますが、今のご説明は右肩下がりのときに限定されるのか、右肩上がりになってもこういうご説明のような分析ができるのかどうかということと、もう1つは、7ページの真ん中辺に、何か税金がネックになって問題だというような指摘があるのですけれども、私は今大学で租税法を担当しているので、ここのところの趣旨がよく理解できない。法人税法では評価益は原則として課税してないわけですので、この指摘は何を意図しているのかということと、それから8ページのところに、増田委員のご本を見てないのが残念なんですが「地価暴落はこれからが本番だ」、どの程度地価が下がるのか、地価の下がり方によっては収益還元法それ自体も成り立たないわけですね。
これは前回の鑑定評価の問題で、n年後の処分価格をどういうふうに算定するかという質問をしたときに、それはn年後の処分価格なんかわかりようがないから、現在の処分価格で置き換えるしかないというご説明が確かあったかと思うのですが、そういうことになると、収益還元法それ自体も単なる単年度の賃料で、ただ還元率で分析するだけならともかく、その使用期間全体にわたるキャッシュフローが計算できないとなると、収益還元価格も所詮は相対的な問題であって、それほど確固たる評価方法とも思えないのですが、その3点についてご説明いただければと思いました。
- ○辻山部会長
-
それでは、増田委員。
- ○増田委員
-
まず第1点の含み資産がプラスに働く株価形成局面とマイナスに働く株価形成局面とが確かにあります。私は原則として含み資産というのもは株価にとってはマイナスであろうという考え方を持っておりまして、どういうことかといいますと、含み資産が膨大なのに実際の収益は低いという会社は、要するに自分が保有している資産の利用法が下手な会社なわけですから、ある意味で現実の収益と含み資産との乖離を見て、含み資産が非常に大きい割に現実の収益が低い会社を割安と見なすというのは、経営者の無能度をプラスとして株価形成に考えるわけでして、バブルのころ、あるいはバブルに至る、経済全体が膨張していた過剰流動性の局面ではそういう評価というのがある程度理屈がつくようにまことしやかに語られましたけれども、そういう理屈がつくためには、まず第1に、欧米の事例が必ずしもいつも正しいという発想は私は持っておりませんけれども、例えばアメリカのマーケットなんかの場合ですと、含み資産は膨大に持っているけれども活用できないような企業というのは、テイクオーバーがかかったり、経営者が解任されたりして、含み資産を活用する方向に強制的に持っていかれるような、そういう社会的なメカニズムが働いていますので、そこでは、含み資産がたまたま大きな会社のくせに実際の収益が低いという会社は、これはあくまでもいつかは解消されるアノマリーですので、そこで投資対象として魅力が出てくるということはありますけれども、少なくとも今までの日本の株式市場では、含み資産が膨大にあったとしても、それをペナルティーを課すための要因とは考えていなかったような市場でしたから、含み資産が膨大なまま、全く何の痛痒も感じずに同じ経営者が同じ経営方針で長いこと仕事ができてきたわけでして、そういう世の中では含み資産が膨大だというのが株価をプラスに持っていく要因だと考えると大間違いをするということで今のバブル崩壊後の株価形成になっているのじゃないのかなという気がします。
もう1つ、税制上の問題なんですが、これは私は確かに税制については非常に不案内でして、多々間違ったことを記述しているところがあるかと思いますけれども、評価益だけであれば課税は全くないということになっても、税効果会計の原則論をとりますと、評価益であろうが実現益であろうが、税務会計ではない株式市場を向いた企業会計ではそこから税負担が発生するということになる。そうなってくるとやはり、例えば余りにも膨大な含み資産は今までは隠してきたけれども、評価益として出さざるを得なくなった企業というのは非常に経営上困難に陥るのではないかという、そういう非常に雑駁な、税務を専門的に考えていらっしゃる方にとってはいろいろ穴があるような議論なんでしょうけれども、私はそういう個人的な見方をしているとお考えください。
それで「地価暴落はこれからが本番だ」という本を私は実は去年の4月に出しまして、その中で申し上げていることが幾つかあるのですが、まず都心の商業地については場所がよければそんなにこれからは下がることはない、むしろ例えば都心の中でも23区内で南西4分の1ぐらいの地域というのは実勢としてはもう値上がりに入っている。ただ都心でさえもちょっと方角が悪かったり立地が悪かったりすると、まだまだこれから5年から10年の射程で見ると20~30%ぐらいの値下がりはするであろう。住宅地については今まで余りにも過剰な政府による融資、税制上の優遇制度で人工的に需要が膨らんできたマーケットが過去もう十数年続いておりますので、この値下がり幅というのは商業地以上になるであろう。東京都内でも5年から10年だと40~50%、地方中核都市のような、経済的な実力に比べて物価も地価もやや割高になっているところではそれ以上の値下がりというようなことを考えております。
そういうことを考えると、収益還元法もまた1つの目安程度にすぎなくて、資産を評価する唯一の原則というような大上段な振りかぶり方をできないのじゃないかというご説は、確かに具体的な実務をされる方からするとそうなのかもしれませんが、私はそれでもやはり、収益そのものを的確に予想することによって、収益のストリームさえきちっとつかめれば、資産を評価する唯一の方法は収益還元法であろう、これはもう本当に同義反復みたいなもので、地価がそれだけ激動していれば収益そのものを正確に予測することができないじゃないかとおっしゃればそのとおりなんですが、ただやはり評価法というのは概念の話ですから、実務の話じゃなくて、どういう方法が正しくてどういう方法は正しくないという原則論はある程度意味のある話ではないかと思っています。
以上です。
- ○品川委員
-
結構です。
- ○辻山部会長
-
ちょっとついでですけれども、今、税の話で、場合によっては事実誤認があったのではないかということですが、バランスシートの不動産、資産等は借方に出ておりますが、ちょっとこの点は、多分ミスプリじゃないかと思うのですが。
- ○増田委員
-
そうです。済みません。
- ○辻山部会長
-
そのほかご意見等ございますでしょうか。どうぞ、小宮山委員。
- ○小宮山委員
-
この中で使われている時価ということの意味について確認させていただきたいのですけれども、これは例えば不動産会社なら不動産会社が自分で使っていることによる収益を反映している時価の話をされているのか、それとも市場の一般的なものの時価を考えられているのか。それとも先ほど不動産鑑定士の方からも説明ありましたけれども、理想状態で回すとこうなるという時価を反映しているのか、どの辺の概念のことを言われているのか、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども。
- ○増田委員
-
私は時価と言うときには、実際に取引が成立する価格と考えて使っておりまして、不動産鑑定の業界の中では時価ということを定義するについて、取引が例えばどちらかがどうしても買わなければいけないとか売らなければいけないとかというような特殊要因があるときには、それはたとえ取引が成立しても時価とはみなさないで、そういう特殊要因がなかったらどうなんであろうかというような抽象的な補正をする必要があることというふうにおっしゃっているようですが、私はそういう考え方というのはそもそも論理的によくわからないわけでして、取引をするときにはそれぞれ買い方も売り方も、売らなきゃいけない事情、買わなきゃいけない事情があるわけですから、実際に取引が成立した価格あるいはする価格、それ以外に時価というものはありませんし、その時価を実際に観察するときに、これは例えば売り手に特殊要因があったとか買い手に特殊要因があったとかという条件づけをして何らかの補正をするという考え方は余り意味がある考え方ではないのではないかと思っています。
- ○辻山部会長
-
奥田委員。
- ○奥田委員
-
先ほどから色々、鑑定評価についてご意見があるようなんですが、まず鑑定評価において求めます市場価値なんですが、先ほど、定義のところで申し上げましたように、あくまでも鑑定評価で求める正常価格というのは市場価値でございます。
市場価値というものにつきましては、例えばIVSにしても、アメリカの鑑定評価基準についても定義があるわけなんですが、同じように、当然合理的な市場条件というのをつけた上での市場価値というふうに定義されております。これは日本の鑑定評価も、各国共通のものでございます。
このように条件をつけますのは、確かに個別の取引というのは、先ほど増田委員がおっしゃいましたように、個別の事情に左右されるものが実際の取引価格でございます。この中から不動産鑑定士が求める価格というのは、個別の取引価格を求めるものではなくて、そもそも鑑定評価の在り方自体がそういった個別の事情に左右されがちな不動産価格に対して標準的な適正な市場価値であれば幾らかというのを求めるのが不動産鑑定評価の目的でございますので、若干その目的が違うのじゃないのかなと、あとまた時価の考え方自体が若干ちょっと違うのじゃないのかなというふうに思っております。
- ○辻山部会長
-
そのほかご質問。秋葉委員どうぞ。
- ○秋葉委員
-
お話を伺っていまして、アナリストの方が会計情報としては何が必要なのかというのがちょっとよくわからなかったものですから確認させていただきたいのですけれども、まず、お話の方は、不動産といいながら多分前提としては賃貸用の不動産、これを念頭に置いているのじゃないか、つまり工場とか本社ビルといったような事業用の資産ではないものを念頭に置いていると思うのですけれども、その場合、今ご説明の方の前半ですと、多分ROEの算定のために、分母の方が、自己資本が原価になっているとその過少に評価されているので、これをもうちょっと把握できるような形で、分母がいわゆる時価ベースじゃないと適切なROEが出ないということで時価評価が必要だというご説明というふうには理解したのですけれども、そうすると最後の方に、注記では不十分、お茶を濁すという言葉があったのですが、情報としては開示されていれば十分かと思いますので、BSに入れなきゃいけないのか、注記で十分なのかどうかというのは、多分情報の価値からすれば等価ではないかなと思いまして、その辺の趣旨がちょっとよくわからなかった面が1点と、あとは時価評価といっても、今のROEの分母・分子の関係からすれば、分子はいわゆる利益の概念で考えられてくる。つまり分子の利益の方に時価評価した差額を入れて、それで将来の企業のキャッシュフローを算定しようというふうにお考えになっている節が後半の方にあるのですが、そのような時価評価差額の利益という概念と、特に賃貸ビルであればそういう賃貸収益をベースにした利益、これがどちらが有用なのかということについて、いわゆる会計上の利益の方が有用じゃないかというふうに理解しているのですけれども、それとの関係が1つ、2つ目としてございます。
それからその時価の算定のところで収益還元というお話がされているのですけれども、ただ現状日本の借地借家法の関係からすれば、企業の持っているテナント情報での収益還元というのは本当の時価じゃないのじゃないかというようなお話が最後の方でされていて、賃料情報を開示することが困難かもしれないけれども有用だというお話がありましたけれども、そうすると逆に必要なものというのが時価ベースの話は先ほどのROEの分母の面で必要なんでしょうけれども、それをいわゆる市場価値として必要な話として考えられているのか、それとも固有の企業の持っているテナントとの契約の賃料、これが必要か。これは多分ROEの分子の方の利益に出てくると思うのですが、そこら辺、ちょっと私の理解が悪いのだと思いますけれども、何を必要とされているのかというところがちょっとよくわからなかったので、ご説明していただければと思います。
- ○辻山部会長
-
今の秋葉委員のご質問は、本日この部会の今議論しております減損会計のフレームワークにも関係するものなんですが、今ご質問は3点ございましたが、その前に語句の質問で、増田委員のご報告の中で不動産といった場合には賃貸用の不動産に限定されているのかどうか、そこの点だけ先に確認していただいた上で、3点秋葉委員のご質問にお答えいただきたいと思います。
- ○増田委員
-
まず、私は賃貸用と事業用には全く何の区別もないと思っております。事業用資産を評価するときには、もちろんその事業用資産が、もし賃貸物件として借りた場合に、あるいは貸した場合に幾らの収益を生み出すものかという、そのインピュテーションをして、同じ原則で収益還元法で考えるべきものだと思っています。
次に、バランスシートの中に毎年洗い替えをする必要があるのか、それとも注記事項でもいいのじゃないのかという話については、これは私はある意味で土俵を広げ過ぎているのだなということは感じながら言ってきたことなんです。
どういうことかといいますと、やはり日本の企業会計が今までずっとかなり現実味がない、リアリティーを失ったものになってきた1つの要因として、資産を抱えていながらその資産を有効活用しない企業に対するペナルティーがほとんどない社会だった、だからいつまでも全くのフィクションである取得原価だけの評価というのがまかり通ってきたのだという考え方をしていまして、そうすると実際に評価益であろうと実現益であろうと、バランスシートの中の資産が価値が高まったということは、バランスシートにももちろん本則として記述するし、損益計算書にもこれだけの評価益があったということを最終利益に貢献する要因として繰り込むべきであろう、そうすれば本来持っている資産の価値が高まって、その高まった価値に基づいて、より有効に活用しなければいけないはずの企業が損益計算書では評価益としてもう既に含まれているはずの利益を現実の企業会計では生み出してないということに対する社会的な監視が強まるであろうという、そういう私個人の希望的な見解を、会計原則をどうするかという話の中に強引に持ち込んでしまった、そういうことだとお考えいただきたいと思います。
テナント情報の開示がどうして必要なのか、全然必要ないというお考えなのかなというのが逆に私は質問された方にちょっと伺いたいのですけれども、要するに実際の企業の賃貸不動産からの収入というのは、個別のテナントにある特定のビルの特定の床面積を幾らで貸しているかの総額としてしか出てきようがないわけです。その同じ床面積を同じ時点で貸しているのに、あるテナントに貸している金額と別のテナントに貸している金額が非常に大きな格差があるというのは、これは制度的な要因を考えないと、経済合理性の全く成り立たないような話になるかと私は思います。
そういう経済合理性が成り立たないような、個別のテナントごとに同じ床面積の同じ利用価値を全く異なる対価で貸し続けているという、そういう状態が私は問題だと思っているわけでして、そうすると具体的に個別のテナントに関する賃貸情報が開示されないとどういう混乱が出てくるかといいますと、例えばあるテナントが退室してそこに新しいテナントが入るときに収益がどう変わるかということが、個別のテナントについての賃料情報がないと全く予想がつきません。退室したテナントはつい最近入居して現在の市場賃料と非常に近いところで占有していて、そこに新しいテナントがそれと似たような賃料で入って、ほとんど賃料に変化がないということもあれば、退室したテナントがたまたま20年、30年ずっと入居していたテナントだったりすると、実際に支払っていた賃料というのは非常に小さくて、そこに新しいテナントが市場賃料で入ると収益が上がるというようなこともあり得るわけですし、また逆の例としては、バブルのころに入居したテナントが退室して、現在の賃料で入居すると、全く賃料収入は激減するというようなこともあり得るわけでして、そこまでの情報がそもそも開示されていないと、1つのビルならビルの物件からいかなる賃料収入がこれから期待できるのかということについて合理的な予測の根拠を持たないということです。
- ○辻山部会長
-
ちょっとこの点についてはまだ議論の余地があると思いますけれども、冒頭ご説明しましたように本日新しい委員がご出席されていますので、とりあえず一言ずつご意見を伺うという予定になっております。もしよろしければ次回にも増田委員が出席されますので、この議論を若干続けてもいいと思いますけれども、秋葉委員よろしいでしょうか。
- ○秋葉委員
-
はい、結構です。
- ○辻山部会長
-
それでは、本日新しく出席していただいている委員から一言ずつご発言をいただきたいと思います。ちょっと時間が短くなってまいりましたけれども、まず笠間委員、高野委員、清水委員、田辺委員、それぞれもしございましたらご意見をいただきたいと思います。
では、笠間委員どうぞ。
- ○笠間委員
-
住友生命の笠間でございます。
業界のということで昨年8月の論点整理、パブリックコメントに対しまして生保協会から意見を出したわけでございますけれども、実務的に取りまとめました立場からお話しさせていただきたいということでございます。
生命保険会社では、保険事業の特殊性と申しますか、つまり保険契約から生じます負債というものが非常に長期にわたるということもありまして、資産運用の一貫として長期安定的な不動産賃料収入を得るという目的で、年々の増加資産の一定割合、増加資産というのは主に保険料からなるわけでございますけれども、不動産投資に振り向けているということでございます。不動産投資と申しますのは、今申しました主に土地を取得しまして賃貸用ビルを建設しまして賃料を得るということでございます。いわゆるバブル期には年々の増加資産が多かったということもありまして、現在の価格から見ますと結果的に高い価格で土地を取得しているというものがかなりあるというのが現状でございます。
一方、生保の財務構造の特徴といたしまして、相互会社という形態が主なわけでございますが、量的にはということでございますが、他業界に比しまして資本のバッファーというものが極端に薄いという特徴がございます。これは当期剰余、株式会社の当期利益に当たるものですが、このほとんど大部分をご契約者に配当として還元してきたという歴史があるため資本の部が薄いという、資産が大きい割に資本の部が薄いという特徴がございます。
従いまして、巷で減損会計の導入が平成14年度からという情報が流れますと、適用されれば単年度利益というものが吹き飛ぶというふうに推測される中で、現時点でどう対応していくかといえば、売却処分を進めていくしかないというのが現状でございます。
もちろん一部には未利用地等がございまして、これを処分していくのは当然のことというふうに考えております。問題なのは、立派なビルにそこそこテナントも入っておりまして、処分することは会社として必ずしも望んでいないのに、先ほどの状況から、減損会計を前に処分せざるを得ない物件も出ているということでございます。一方で買い手というものがなかなかいないという市場の特性もありまして、不動産価格がまた下がっていくといった悪循環もあるわけでございます。
以上のことから、要望といたしましては、導入以前の話といたしましては先ほどから話にございます減損の処理基準といいますか、手法といいますか、これは十分な検討、十分な広報とか準備期間を設定していただきたいとか、導入後の話として激変緩和措置というものを強く要望しております。詳細につきましてはまた資料、数字等を使いまして後日ご説明させていただきたいと考えております。
以上でございます。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。次回以降詳しいご報告をいただく予定でございますので、本日はとりあえず一言ずつということで、高野委員、よろしくお願いいたします。
- ○高野委員
-
鹿島建設の高野でございます。
建設業界でも昨年論点整理に対しましてはコメントを出させていただきました。当業界でも各社それぞれ保有している資産の内容とか、あるいは資産の質が違いますので、それぞれインパクトが違うかと思いますけれども、今回の基準については大変に注目しているところでございます。
私自身、勉強不足でありますけれども、よろしくお願いいたします。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。それでは、清水委員。
- ○清水委員
-
イトーヨーカ堂の清水です。
小売業ということで、減損会計がどのようになるかということで参加させていただいていると思いますが、やはり最近物件当たりの投資額が非常に大きくなっている一方で、昨今の消費低迷等で、対象店舗ごとというふうに考えた場合に、やはり成績の上がらない店等が今後また出てくるような状況になってきますと、小売業界におきましても減損の影響が非常に大きくなってくる可能性があるという心配があります。
また、その減損の対象になるのは自社所有物件のみならず、リース会計のいかんにもよりますけれども、賃借物件、いわゆるリースを受けている物件についても貸借対照表のオンバランス、オフバランスの問題もありますけれども、そういったものまでも対象になっていくのかどうかという問題がございます。
それから、判定の方法においても、将来キャッシュフローの算定というのは非常に難しい問題がございますし、割引率、そういったものも非常に課題があると思いますので、そういったことについて今後議論していきたいというふうに思っております。
以上です。
- ○辻山部会長
-
どうもありがとうございました。それでは、田辺委員。
- ○田辺委員
-
富士銀行の田辺でございます。
銀行業界からは昨年8月に全国銀行協会より論点整理に対して意見書を提出させていただいておりますので、今までのご審議の中でもご紹介いただいているものもあるかと思いますけれども、本日一言だけ挙げさせていただくとしますと、銀行の多くが土地再評価法に基づく事業用土地の再評価を行っておりますので、その立場といたしまして土地再評価と減損処理の関係についてがポイントの1つだと思っておりますので、今後この点を含めてご検討いただければ思っております。
- ○辻山部会長
-
ありがとうございました。
それでは、先ほどの増田委員と秋葉委員の質疑、少し途中で切らせていただいたような感じがありますけれども、また引き続き議論を続けてまいりたいと思います。
そろそろ予定の時刻がまいりましたので、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。
なお、次回の当部会の日程でございますが、4月23日月曜日、午後4時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。次回は月曜日となりますのでご注意ください。正式には改めて事務局から皆様方に連絡をさせていただきます。
本日は皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございました。
これにて散会とさせていただきます。

 検索
検索