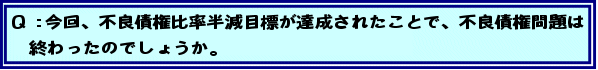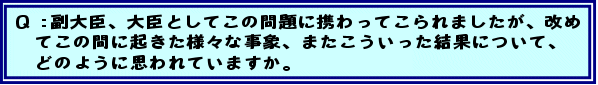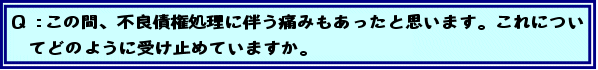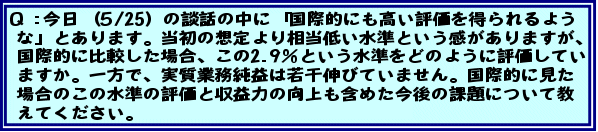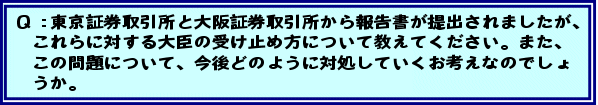| 3日(火) |
 |
・ |
伊藤金融担当大臣とドナルドソン米国証券取引委員会(SEC)委員長と会談 |
| |
| 5日(木) |
 |
・ |
香港証券先物委員会との証券分野の情報交換枠組みを構築 |
| |
| 10日(火) |
|
・ |
第13回偽造キャッシュカード問題に関するスタディーグループ開催 |
| |
| 11日(水) |
|
・ |
第12回評定制度研究会開催 |
| |
・ |
第4回保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム会合開催 |
| |
・ |
第14回偽造キャッシュカード問題に関するスタディーグループ開催 |
| |
| 12日(木) |
|
・ |
企業会計審議会内部統制部会開催 |
| |
| 13日(金) |
 |
・ |
偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループの第二次中間とりまとめ公表 |
 |
・ |
金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)等の公表(パブリック・コメント) |
| |
・ |
第15回偽造キャッシュカード問題に関するスタディーグループ開催 |
| |
| 16日(月) |
 |
・ |
CESR(欧州証券規制当局委員会)の公聴会への参加について(我が国会計基準の国際会計基準(IAS)との同一性問題への対応) |
| |
・ |
企業会計審議会監査部会開催 |
| |
| 18日(水) |
|
・ |
第13回評定制度研究会開催 |
| |
| 19日(木) |
 |
・ |
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出(追加要請その30)の発出 |
 |
・ |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表(パブリック・コメント) |
| |
・ |
第15回偽造キャッシュカード問題に関するスタディーグループ開催 |
| |
・ |
企業会計審議会内部統制部会開催 |
| |
| 20日(金) |
 |
・ |
株式会社山形しあわせ銀行に対する行政処分(東北財務局長処分) |
 |
・ |
株式会社みちのく銀行に対する行政処分(金融庁及び東北財務局長処分) |
| |
| 24日(火) |
|
・ |
第4回金融経済教育懇談会開催 |
| |
| 25日(水) |
 |
・ |
主要行の平成16年度決算《速報ベース》の公表 |
 |
・ |
足利銀行の経営に関する計画の履行状況の公表 |
| |
・ |
第14回評定制度研究会開催 |
| |
・ |
第19回金融問題タスクフォース開催 |
| |
| 26日(木) |
|
・ |
第5回保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム会合開催 |
| |
・ |
第16回偽造キャッシュカード問題に関するスタディーグループ開催 |
| |
・ |
企業会計審議会内部統制部会開催 |
| |
| 27日(金) |
 |
・ |
株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツに対する信託業の免許 |
 |
・ |
CESR(欧州証券規制当局委員会)の「特定第3国会計基準と国際会計基準(AIS)との同等性に関する助言案」へのパブリック・コメント・レターの発出 |
 |
・ |
疑わしい取引の参考事例の追加の発出 |
 |
・ |
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出(追加要請その31)の発出 |
 |
・ |
検査における評定制度(案)の公表(パブリック・コメント) |
| |
・ |
金融審議会第一部会開催 |
| |
・ |
第3回貸金業制度等に関する懇談会開催 |
| |
| 30日(月) |
|
・ |
企業会計審議会監査部会開催 |
| |
| 31日(火) |
 |
・ |
証券会社向けの総合的な監督指針(案)の公表(パブリック・コメント) |
 |
・ |
金融先物業者向けの総合的な監督指針(案)の公表(パブリック・コメント) |
 |
・ |
有価証券報告書等に関する業務の業務・システム見直し方針(案)の公表(パブリック・コメント) |