アクセスFSA 第78号(2009年5月)

 |
| 社団法人 不動産証券化協会の通常総会 で挨拶する谷本副大臣(5月21日) |
【談話・講演等】
※ このコーナーは、大臣、副大臣、大臣政務官、金融庁幹部が行った談話・講演等についての情報をお届けするものです。
●挨拶
●講演
【特集】
財務局長会議の開催について
金融庁では、4月23日、本事務年度(平成20年7月~平成21年6月)第4回目の財務局長会議を開催しました。
会議においては、谷本副大臣、宇野大臣政務官の挨拶に続き、財務局長等と副大臣、大臣政務官はじめ当庁幹部との意見交換を行いました。その後、副大臣、大臣政務官の挨拶の中で触れられている項目等について、当庁各局、証券取引等監視委員会事務局及び公認会計士・監査審査会事務局から所要の説明を行いました。

谷本副大臣からは、「世界の景気が急速に悪化する中で、中小企業はもとより、中堅・大企業等の業況や資金繰りも厳しさを増しており、新年度に入った後も、金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が一層重要となっている。財務局においては、現在の地域における非常に厳しい情勢を改めて認識し、検査・監督の第一線として更に尽力してもらいたい」という挨拶がありました。(谷本副大臣挨拶の全文はこちらをご参照ください。)
宇野大臣政務官からは、「民間金融機関においては、借り手企業が期待する金融仲介機能を適切かつ十分に果たしていくため、資本充実策についての幅広い検討が必要である。金融庁としては、引き続き、金融機関に対して、金融機能強化法の活用の積極的な検討を呼びかけてまいりたいと考えている。各財務局においては、企業等に対する円滑な金融は、金融機関の最も重要な役割の一つであるとの認識のもと、更に尽力してもらいたい」という挨拶がありました。(宇野大臣政務官挨拶の全文はこちらをご参照ください。)
財務局長等と副大臣、大臣政務官はじめ当庁幹部との質疑・意見交換においては、地域金融をめぐる現下の状況を踏まえた企業金融の円滑化について討議を行いました。
当庁各局による業務説明においては、各局における諸問題や活動について説明が行われ、その後、質疑・応答を行いました。
※ なお、各財務局等において、「中小企業をはじめとした企業金融の状況とその対応」に関する資料を公表していますのでご参照ください。
北海道財務局 http://hokkaido.mof.go.jp/kinyu/tyuusyou_kinyu/report_210423.pdf
東北財務局 ![]() http://tohoku.mof.go.jp/b2_kinyu/01_kinyukankei/pdf/kigyoukinyu21.pdf
http://tohoku.mof.go.jp/b2_kinyu/01_kinyukankei/pdf/kigyoukinyu21.pdf![]()
関東財務局 ![]() http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinyu/6723kinyuu0522.pdf
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinyu/6723kinyuu0522.pdf![]()
東海財務局 ![]() http://tokai.mof.go.jp/kinyuu/kinyuu/chuusyoukashidashi3.pdf
http://tokai.mof.go.jp/kinyuu/kinyuu/chuusyoukashidashi3.pdf![]()
北陸財務局 http://hokuriku.mof.go.jp/img/kinyuu/kigyoukinyuu210522.pdf
近畿財務局 ![]() http://kinki.mof.go.jp/other/chuushou-kinnyuu.pdf
http://kinki.mof.go.jp/other/chuushou-kinnyuu.pdf![]()
中国財務局 ![]() http://chugoku.mof.go.jp/kinyusyouken/kinchou/chushou/chushou2105.pdf
http://chugoku.mof.go.jp/kinyusyouken/kinchou/chushou/chushou2105.pdf![]()
四国財務局 http://shikoku.mof.go.jp/pubsys/public/mu1/bin/view.rbz?cd=4076![]()
福岡財務支局 http://fukuoka.mof.go.jp/library/data/kinyu/choseikan/210430kigyokinyu.pdf
九州財務局 ![]() http://kyusyu.mof.go.jp/kinyu/smaller/pdf/smaller_090522.pdf
http://kyusyu.mof.go.jp/kinyu/smaller/pdf/smaller_090522.pdf![]()
沖縄総合事務局 ![]() http://ogb.go.jp/okizaimu/kinyu/16.3.15/kigyokinyuu210522.pdf
http://ogb.go.jp/okizaimu/kinyu/16.3.15/kigyokinyuu210522.pdf![]()
【トピックス】
金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等について
金融サービス利用者相談室(以下「相談室」といいます。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期ごとに公表しています。平成21年1月1日から3月31日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。なお、今回の公表分とは別に、金融円滑化「大臣目安箱」情報として受け付け、大臣に直接届けられたものがあります。
1.平成21年1月1日から3月31日までの間に、12,445件の相談等(詳細については、「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(平成21年4月30日)をご参照ください。)が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均211件となっており、20年10月1日から12月31日までの間(以下「前期」)の実績(229件)と比べやや減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが4,310件(35%)、保険商品等に関するものが2,847件(23%)、投資商品等に関するものが3,581件(29%)、貸金等に関するものが1,472件(12%)、金融行政一般・その他が235件(2%)となっています。
3.分野別の特徴等としては、
(1) 預金・融資等については、全体の受付件数は前期に比べてやや減少していますが、個別取引など融資業務に関する相談等が増加しています。
(2) 保険商品等については、保険金の支払に関するもの、保険金請求時等における保険会社の対応に関するものについての相談等が寄せられています。
(3) 投資商品等については、全体の受付件数は前期に比べて大幅に減少していますが、未公開株に関する相談等が増加しています。
(4) 貸金等については、一般的な照会・質問に関するもの、個別取引・契約の結果に関するもの、不適正な行為に関するものについての相談等が寄せられています。
4.なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報(注)も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(注)検査・監督上参考となる情報の例
○預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢及び広告等の不適正な表示に関するもの
○預金取扱金融機関における本人確認や説明を求めた際の不適切な顧客対応に関するもの
○預金取扱金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの
○預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
○いわゆる貸し渋り・貸し剥がしに関するもの
○保険会社等の不払い等に関するもの
○保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約等)に関するもの
○損害保険会社の火災保険の保険料過徴収に関するもの
○金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
○証券会社の高齢者に対する勧誘に関するもの
○金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等)に関するもの
○貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反、取引履歴の不当な開示拒否等)に関するもの
○貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ14口座の情報提供を行っています。
さらに、平成20年10月1日から12月31日までの間における情報の活用状況は以下のとおりです。
i監督において行った326金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
ii金融庁が着手した16金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しています。今回、新たに追加する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」の項目・相談事例等は、以下のとおりです。
□ 預金・融資等
○ 本人確認に関する相談等
- 子供の入学金の振込みを行いたいのですが、本人確認はどのようにされるのでしょうか。
□ 保険商品等
○ 保険契約に関する相談等
- 保険契約にもクーリング・オフの適用はあるのでしょうか。
□ 投資商品等
○ 未公開株式の取引に関する相談等
- 金融庁等から許可を得て未公開株の買取りをしているという業者から連絡があり、高値で買い取るので未公開株を買ってほしいと言われて当該未公開株を購入しましたが、買い取ってもらえません。
- 金融庁等から委託されて未公開株の被害状況の把握や被害相談を行っているという団体から連絡があり、保有している未公開株を教えてしまいました。
- 金融庁等の所管法人として未公開株の保有者へ助言を行っているというNPO法人等から連絡があり、現在保有している未公開株は有望なので買い増すよう助言され、買い増してしまいました。
- 金融庁等からの指示を受けて未公開株の購入代金を取り返しているという団体から連絡があり、購入代金を取り返すためには、当該団体から別の未公開株や投資ファンドを購入する必要があると言われました。
- 金融庁等から認可を受けて未公開株の将来性を評価しているという団体から連絡があり、保有している銘柄は、上場の準備で金融庁へ届出が出されており上場確実であると言われ、買い増すよう勧誘を受けています。
□ 貸金等
○ 総量規制に関する相談等
- 10年以上、貸金業者で借入れと返済を繰り返していますが、最近新たに借入れをしようとしたら、収入を証明する書類として源泉徴収票等を提出するよう求められていますが、どういうことでしょうか。
* その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成21年1月1日~3月31日)」(平成21年4月30日)にアクセスしてください。
金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況表
(平成21年1月1日~3月31日)
1.類型別受付件数
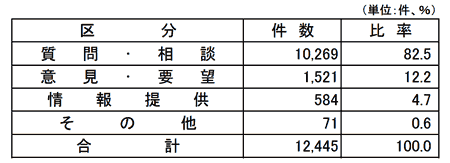
2.受付方法別件数
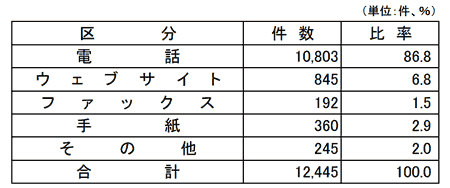
3.分野別受付件数
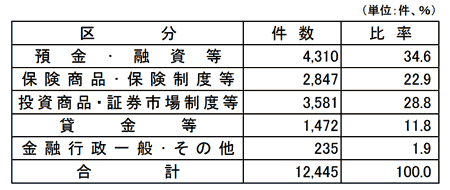
4.分野別・要因別の相談等受付件数
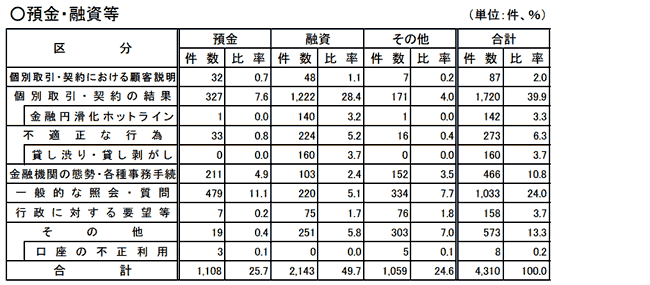
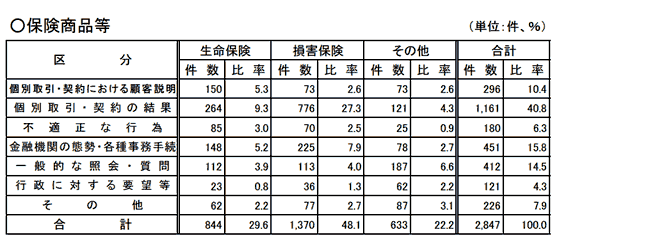
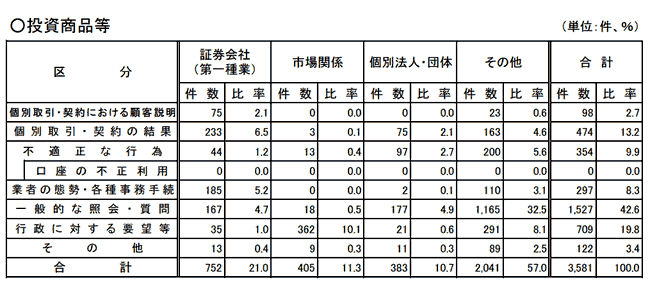
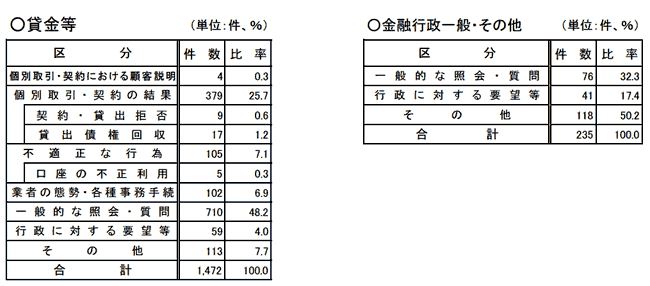
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
平成15年9月12日、金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務ガイドライン(現監督指針)を改正したところであり、その情報提供件数等について、四半期ごとに公表しています。
これによると、調査を開始した平成15年9月以降、本年3月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において、22,672件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。
また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、本年3月31日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、12,051件の利用停止、8,621件の強制解約等を行っています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」(平成21年4月30日)にアクセスしてください。
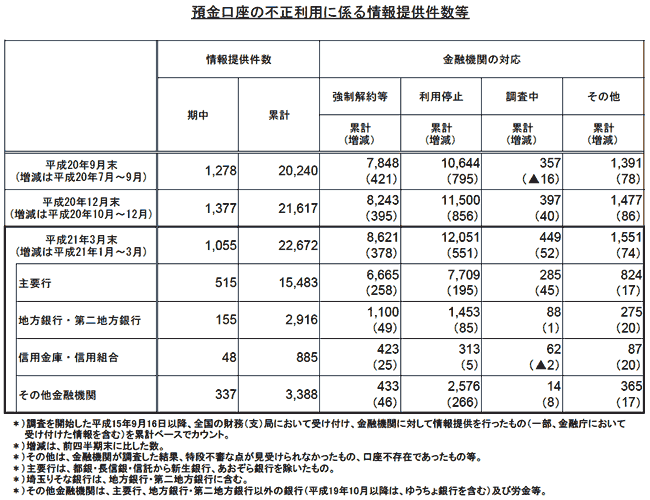
平成21年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)では、4月24日、「平成21年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」を公表し、平成21年度における証券検査の実施方針及び実施予定数を明らかにしました。今年度の証券検査基本方針及び証券検査基本計画の概要は以下のとおりです。なお、今回より対象となる期間を事務年度ベース(7月~翌年6月末)から年度ベース(4月~翌年3月末)に変更しています。
1.証券検査基本方針
(1) 基本的考え方
証券監視委は、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護を目指し市場監視を行っています。近年、証券検査の検査対象先の範囲の拡大や今般のグローバルな金融危機などを踏まえると、より、きめの細かい検査対応がこれまで以上に必要となってきており、業態や業者ごとの規模やリスク特性を勘案した、いわゆるリスク・ベースの柔軟なアプローチが重要となってきています。そして、証券検査の効率性と実効性の一層の向上を図る観点から、取引の公正確保を基本としつつ、公益確保や投資者保護をも念頭に、内部管理態勢に着目した検査も一層、充実させていく必要があります。
また、証券検査は、市場の動きに対してタイムリーかつ機敏に対応するとともに、顕在化しつつあるリスクに対しても将来に備えた機動的な対応を目指す必要があります。グローバルに活動する金融商品取引業者の破綻は、市場に大きな混乱をもたらし、場合によってはシステミック・リスクを引き起こす可能性があります。こうしたことから証券検査に対しては、金融商品取引業者における財務の健全性を含め、広くそのリスク管理態勢のあり方にも十分な目配りをする役割も期待されています。
証券監視委ではこのような大きな変化に対応するため、証券監視委の基本的使命を踏まえつつ、これまで以上に効率的かつ効果的な検査を追求していく必要があると考えています。
ここでいう「効率的な検査」とは、金融商品取引業者等自身の自己改善努力を最大限に活かし、これを補完するような検査を行うことであり、また「効果的な検査」とは、検査結果が金融商品取引業者等の内部管理態勢の持続的な改善等に確実に結びつくような検査を行うことです。
具体的には、以下の点に留意しつつ、効率的かつ効果的な検査を行います。
○法令や市場ルールに関する違反行為の検証を行うことを基本としつつ、公益確保や投資者保護を念頭に、金融商品取引業者の規模・特性を踏まえた上で、内部管理態勢等の適切性の検証に着目した検査
○検査対象先のリスクの所在を分析し、当該リスクに焦点を当てたメリハリのある検査
○実効性ある内部管理態勢整備に向けた金融商品取引業者の自主的な取組みに資するような双方向の対話等を重視した検査
○検査の透明性等を向上させるため、検査マニュアルの見直し、公表
(2) 重点検証事項
今年度においては、以下の検証項目について重点的に検証を行います。
○金融商品取引業者等の市場仲介機能にかかる検証
○金融商品取引業者等のリスク管理態勢にかかる検証
- グローバルに活動する金融商品取引業者等のシステムリスクや財務の健全性を含めたリスク管理態勢の検証
- 外国為替証拠金を取扱う金融商品取引業者等のシステム管理態勢の検証
○法人関係情報の管理態勢(不公正な内部者取引の未然防止)に係る検証
○投資運用業者等の業務の適切性に係る検証
○公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証
○自主規制機関の適切な機能発揮等のための検証
○新たな検査対象先・金融商品等に係る検証
○過去の検査における問題点の改善状況等に係る検証
2.証券検査基本計画
本年度の証券検査基本計画では、第1種金融商品取引業者等130社(うち財務局等が行うもの110社)、投資運用業者、投資助言・代理業者65社(うち財務局等が行うもの35社)に検査を実施する予定であり、さらに、自主規制機関、第2種金融商品取引業者等についても必要に応じて検査を実施する予定です。
※ 詳しくは、証券取引等監視委員会ウェブサイトから「平成21年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」(平成21年4月24日)にアクセスしてください。
平成21年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画の概要
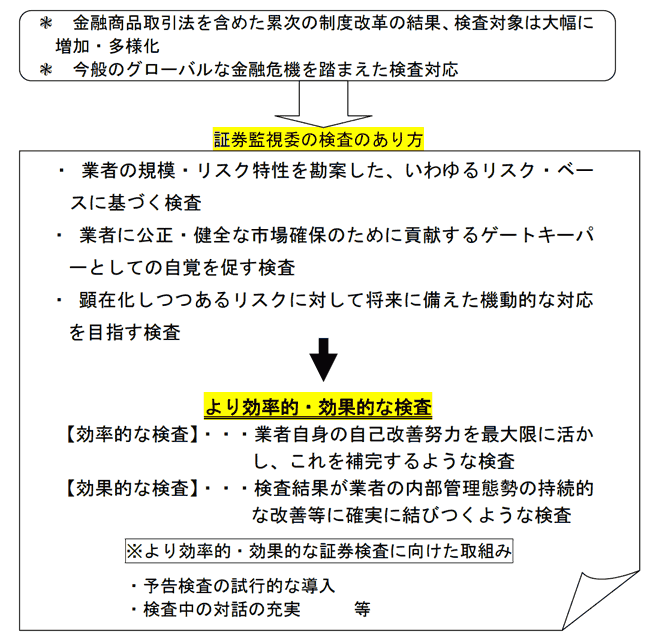
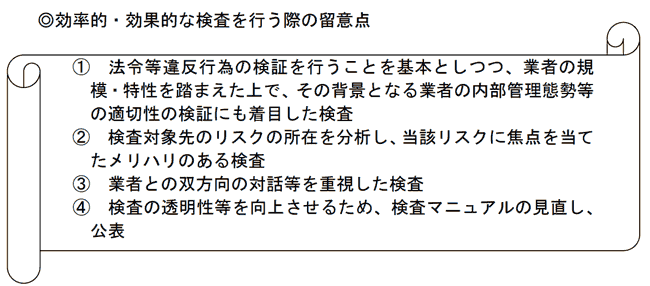
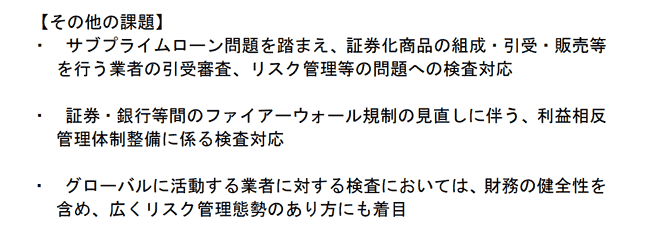
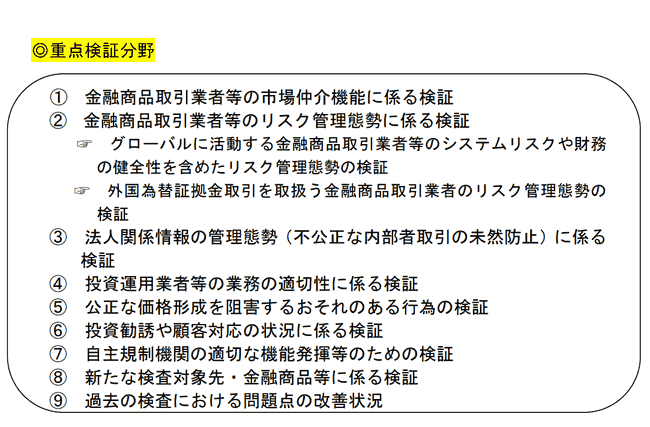
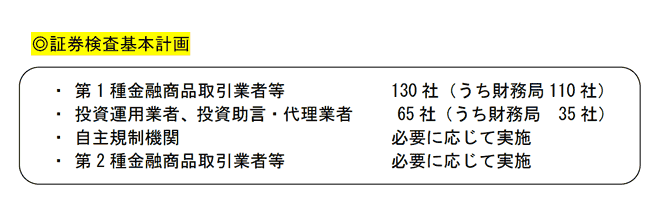

 検索
検索

