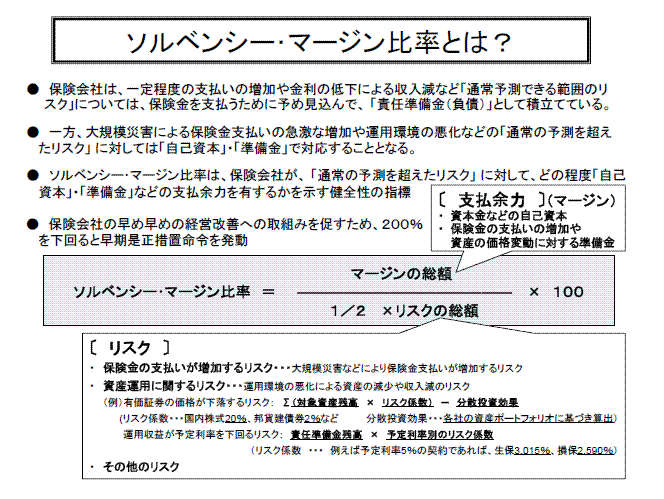アクセスFSA 第85号(2010年6月)
【法令解説等】
ソルベンシー・マージン比率の算出基準の見直しに関する保険業法施行
規則の一部を改正する内閣府令等について
1.ソルベンシー・マージン比率とは
保険会社は、一定程度の支払いの増加や金利の低下による収入減など「通常予測できる範囲のリスク」に対しては、保険金の支払いを予め見込んで、「責任準備金(負債)」として積み立てています。一方、大規模災害による保険金支払いの急激な増加や運用環境の悪化などの「通常の予測を超えたリスク」に対しては、「自己資本」・「準備金」などで対応することになります。つまり、保険会社の「ソルベンシー・マージン比率」とは、保険会社が、「通常の予測を超えたリスク」に対して、どの程度「自己資本」・「準備金」などの支払余力を有するかを示す健全性の指標です。また、ソルベンシー・マージン比率は、保険会社に対して、早めの経営改善を促すための指標となるものであり、同比率が200%を下回ると早期是正措置命令を発動することになります。
2.改正までの経緯
改正までの経緯としては、平成19年4月3日に公表された「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チームの報告書」に基づき、平成20年2月8日に、リスク計測の厳格化等を内容とする「ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子(案)」(以下、「骨子(案)」といいます。)を公表し、意見募集を実施しました。その後、同年10月の大和生命の破綻や、同年秋以降の金融危機の教訓、さらには骨子(案)に寄せられた意見等を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率の信頼性に係る一層の向上の観点から、更なる見直し作業を行い、平成21年8月28日に、「ソルベンシー・マージン比率の見直しの改定骨子(案)」(以下、「改定骨子(案)」といいます。)を公表し、改めて意見募集を実施しました。
改定骨子(案)に寄せられた意見等を踏まえ、平成21年12月28日に、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案等を公表し、意見募集を実施し、当該案に寄せられた意見等を踏まえ、平成22年4月9日に意見募集の結果を公表し、4月20に公布しました。
3.改正の概要
今回の改正の内容は、以下のとおりです。
○ ソルベンシー・マージン比率の分子であるマージン算入の厳格化
(1) 保険料積立金等余剰部分のマージン算入制限の導入
(2) 繰越欠損金等に係る繰延税金資産のマージン算入制限の導入(新設会社を除く)等
○ ソルベンシー・マージン比率の分母であるリスクについての計測の厳格化及び精緻化
(1) 各リスク係数の信頼水準の引上げ(90%→95%)
(2) 各リスク係数の基礎となる統計データのリニューアル
(3) 地震災害リスクを各社毎のリスクモデルのVaR99.5%によるリスク相当額として算出(現行では全社一律のリスクモデルでVaR99.5%により算出)
(4) 価格変動等リスクにおける分散投資効果を、各社の資産構成割合に基づき算出(現行では、生命保険会社30%、損害保険会社20%で一律)
(5) ヘッジ取引によるリスク削減効果についてはヘッジ効果が有効なものに限定
(6) 証券化商品及び再証券化商品のリスク係数の厳格化、CDS取引に係る信用スプレッドリスクの創設、金融保証保険のリスク係数の厳格化
その他の改正として、ソルベンシー・マージン比率の適正な算出について、保険計理人の確認事項に追加しています。
4.施行時期
今回の改正により、保険会社のソルベンシー・マージン比率は低下すると見込まれていますが、これは保険会社の財務状況が悪化したということではなく、算出基準が変わったことによるものです。このことについては、保険契約者や市場に広く周知徹底する必要があることから、施行時期は、平成24年3月期末から早期是正措置の指標として使用することとし、平成23年3月期末から開示できることを改正保険業法施行規則の附則に定め、保険会社向けの総合的な監督指針において開示が望ましいとすることを規定しました。
5.主な意見
上記3.の改正の内容のうち、リスク計測の厳格化及び精緻化に対する意見が最も多く(41件)、今回の改正の内容が保険契約者等に誤解を招かないように周知を行ってもらいたい(2件)という意見も寄せられました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成22年4月9日)にアクセスしてください。
「主要行等向けの総合的な監督指針」、
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成22年1月20日から平成22年2月22日にかけて広く意見の募集を行い、平成22年4月16日にパブリックコメントの結果を公表し、監督指針の一部改正を行いました。なお、改正された監督指針については、平成22年4月16日から適用しています。
以下、改正の概要について説明します。
1.「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
与信取引に関連したデリバティブ取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能について、利用者保護の充実を図る観点から以下の改正を行いました。
(1) 契約時点等における説明について
最悪のシナリオを想定した損失や解約清算金を説明していること
為替や金利等不確実な事項について、断定的判断に基づく説明をしないこと 等
(2) 実質的経営者への説明について
今後の経営に大きな影響を与える契約の場合において、取締役会等での意思決定の有無を確認していること 等
(3) 顧客のヘッジニーズに対する有効性の確認及び説明について
顧客ニーズに応じたデリバティブ取引の有効性を確認し、当該取引が顧客の今後の営業にどのような影響を与えるか顧客の理解を得ること 等
(4) 事後フォローについて
契約締結後、顧客の業況変化に応じたヘッジニーズに対する当該ヘッジの有効性等を確認するなど適切なフォローアップを行うこと 等
(5) その他
苦情が多い商品や取引の販売を継続するかどうかの検討を行うこと 等
2.「金融商品取引業者等向け総合的な監督指針」
通貨オプション取引・金利スワップ取引等の店頭デリバティブ取引及びこれと同様のリスク特性を有する仕組債の販売等について、上記1.に準じた改正を行いました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(平成22年4月16日)にアクセスしてください。

 検索
検索