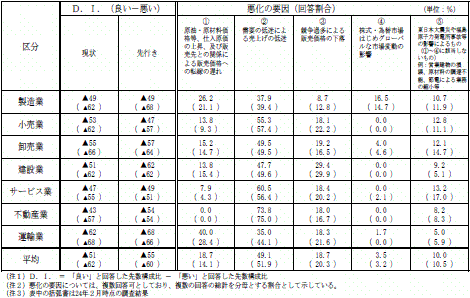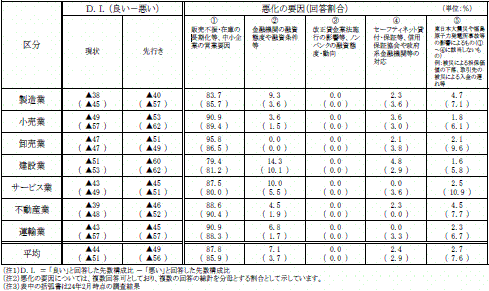アクセスFSA 第109号(2012年7月)

 |
 |
| 金融審議会総会(第28回)・金融分科会 (第16回)合同会合で挨拶をする 松下大臣 (7月4日) |
斉藤東証社長、米田大証社長と 面会をする松下大臣 (7月6日) |
【トピックス】
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、平成24年4月3日(火)から平成24年5月2日(水)にかけて、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、広く意見の募集を行い、その結果等を平成24年6月1日(金)に公表しました。
本件の命令は、平成24年6月1日(金)に公布され、同日より施行されています。
本件の命令の概要は以下のとおりです。
1.「銀行法施行規則」等の改正
動産担保融資(ABL)等の開発・普及等に資するため銀行等の子会社の業務に以下の業務を追加します。
(1)他の事業者が貸付等の債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
(2)親銀行等が貸付等の債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該貸付等の債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、及び購入した財産の所有・管理を行う業務
※なお、上記(2)の業務において「適正な価格で購入」することを求めていることから、平成24年6月1日に結果公表された主要行等向けの総合的な監督指針等において、監督上の留意点として「客観性・合理性のある評価方法による評価をしているか」という点を記載しています。
2.「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」等の改正
信託契約締結時の書面交付を要しない場合に、委託者との間で同一の内容の特定売掛債権(委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいいます。)の信託契約を締結したことがある場合を含めることとし、いわゆる一括信託の契約更新時に再度書面を交付しなくてもよいこととします。
また、あわせて、信託契約締結時に信託契約の内容の説明を要しない場合に、上記と同じ場合を含めることとし、一括信託の契約更新時に再度説明しなくてもよいこととします。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(6月1日)にアクセスして下さい。
障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について
金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、その取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成24年3月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を6月1日に公表しました。
主な調査結果は以下のとおりです。
1. 視覚障がい者対応ATMの設置率について
ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約69%です。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約88%(うち都市銀行等約89%)、信託銀行 約82%、地方銀行等 約52%、
第二地方銀行 約44%、信用金庫 約55%、信用組合 約55%、労働金庫 約61%2. 預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について
預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約81%【約92%】(うち都市銀行等100%【100%】)、信託銀行 100%【100%】、
地方銀行等 100%【100%】、第二地方銀行 100%【100%】、信用金庫 約100%【100%】、
信用組合 約98%【約99%】、労働金庫 100%【100%】注:【 】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率
3. 障がい者等に対するCSRを意識した取組み事例
各金融機関は、顧客のニーズやそれぞれの優先順位を踏まえつつ、障がいをお持ちの方々の利便性が更に高まるよう、それぞれ主体的に対応しています。取組みの一例は次のとおりです。
- 視覚障がい者の方に配慮した接客を目指し、全営業店に1名以上のサービス介助士の資格を保有する職員を配置。
- 点字カレンダーを視覚障がい者団体や盲学校に贈呈する活動を毎年継続して実施。月ごとに切取って使えるように工夫を凝らしている。
- 視覚特別支援学校の卒業予定者にATMの利用方法等について説明を行った。
- 視覚障がい者の方の自宅を訪問し、店舗の設備、接遇等について感想や希望を伺った。
- 利用者が多い営業店に振動式の呼出機を設置している。
- ホームページをリニューアルし、音声読み上げ、表示サイズ変更、画面色変更、ルビ(ふりがな、ローマ字)などアクセシビリティの向上を行った。
【参考】アンケート対象金融機関数
◎主要行等は16行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、シティバンク銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)
◎信託銀行は6行(住友信託銀行、中央三井信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)
◎地方銀行等は65行(地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)
◎第二地方銀行は42行(第二地方銀行協会加盟行)
◎信用金庫は271金庫
◎信用組合は158組合
◎労働金庫は13金庫
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(6月1日)」にアクセスしてください。なお、ウェブサイトに掲載した資料については、テキスト形式のものもございますので、読み上げソフトをお使いの方はそちらもご利用下さい。
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
中小企業金融の実態把握の一環として、平成24年5月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は以下のとおりとなりました。
1. 中小企業の業況感は、引き続き厳しい状況にありますが、そのような中、現状D.I.のマイナス幅が縮小傾向にあります。
悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「仕入原価の上昇等」及び「販売価格の下落」となっています。
2. 中小企業の資金繰りも、引き続き厳しい状況にありますが、そのような中、現状D.I.のマイナス幅が縮小傾向にあります。
悪化の要因としては、「中小企業の営業要因」の割合が最も大きくなっています。
(参考1)東日本大震災に関連した業況感に関する主なコメントについては以下のとおりとなっています。
≪製造業≫
○震災により被害を受けた製造設備等の復旧は進んでおり受注も戻っているが、販売単価の引下げや原材料高等によるコストの上昇で依然として厳しい状況にある(福島県)
○震災や円高の影響は和らぎ、機械器具関連や食品関連などを中心に業況は回復し安定しつつある(栃木県)
○金属製品製造業については、震災により需要が落ち込んだが、最近の受注状況は僅かであるが回復の兆しが出てきている(新潟県)
○震災やタイの洪水の影響により厳しい状況に陥っていたが、企業の自助努力により、良いとまでは言えないが受注を戻している事業者も見られる(千葉県)
○震災特需は収まったが、一方で震災やタイの洪水の影響を受けていた住宅部品などの調達が回復してきており、現状は安定している(三重県)
○一部には震災復興の需要はあるが、人口減などのため需要は伸びず、全体として悪い状況は変わらない(高知県)
≪小売業≫
○被災地復興支援として県産品を購入する動きに加え、旅客鉄道会社のキャンペーンによる観光客増加の影響などから、震災前と比べても好調である(岩手県)
○家電品関連は節電特需が終了し売上げが減少しているほか、青果物は原発事故の影響や天候不順による販売価格の上昇などにより厳しい状況であった(栃木県)
○昨年は復興支援のための被災地の物品販売により売上げ増加となったが、最近はその効果も薄れてきている。消費者の所得も増えておらず、消費マインドが盛り上がってこない(千葉県)
○売上げは昨年に比べ増加しているが、震災前に比べると厳しい。客単価は、依然として低価格傾向である(静岡県)
○東日本大震災から一年が経過し、買い控えは一息ついている。特に3月、4月は高額商品の売れ行きが良かった店舗もある(大分県)
≪卸売業≫
○企業の物流の滞りもなく、ほぼ震災前に戻っており、特に大きな懸念材料もない(山形県)
○復興需要に伴い建築資材等の卸売りは好調なものの、電気製品関係の卸売りは厳しい状況にあるなど、業種によって区々な状況である(宮城県)
○原発事故の風評被害で茶葉や海苔の売上げが落ちている。全体としては、需要の低迷や競争過多による販売価格の下落で厳しい状況にある(千葉県)
○国内需要については、震災の復興需要等により、建設資材など建設関連が堅調な動きを見せている(神奈川県)
○商品の仕入れや物流面等への震災の影響は回復しているが、仕入単価の上昇や小売業からの値下げ要求により業況は厳しい(愛媛県)
≪建設業≫
○復興関連工事の需要が旺盛なことから総じて堅調である一方、下請け企業では、原材料費や人件費が上昇していることから利幅が取れていない状況がみられる(岩手県)
○沿岸部の公共工事やマンション等の補修工事など、復旧・復興関連の需要が旺盛なことから、引き続き好調である(宮城県)
○震災の復興関連工事により受注は増加傾向にあるが、資材価格の高騰や受注単価の低下により収益の向上にはあまり繋がっていない(栃木県)
○震災の復興需要に伴い、一部の企業では受注が好調に推移している。また、建替需要は低迷しているものの、耐震・免震工事の受注が増加している企業も見られる(神奈川県)
○需要の低迷により現状は悪い。また、東北の復興需要で人手が不足しており、需要があっても十分に受注を受けられない状況にある(京都府)
○震災により建築資材の仕入れが困難な状況からは回復しているが、官民双方の需要の停滞、請負単価の低下は続いており、業況は厳しい状況にある(愛媛県)
≪サービス業≫
○県内主要観光地におけるゴールデンウィーク中の観光客数は、震災前とほぼ同水準だったものの、原発事故の風評などから関西以西や海外からの観光客は戻っておらず、全体としては厳しい状況が続いている(山形県)
○旅館業などでは、復興需要などにより一部に持ち直しの動きがみられるが、風評被害による影響は長期化している(福島県)
○復興関係者が集まる地域の飲食業は好調であるが、全体としては集客等に差がみられることから良くも悪くもない(宮城県)
○震災に伴う自粛等により中止となっていたイベントが復活したことなどから、宿泊・観光施設などの業況は好転している(群馬県)
○観光関連業は、震災の自粛ムードがあった昨年に比べ売上げは増加しているが、震災前に比べると良くはない(山口県)
○震災の影響で一時途絶えていた海外観光客が戻りつつあるなど、回復傾向にある(福岡県)
≪不動産業≫
○不動産賃貸については、県が民間アパートを借り上げ震災被災者に無償で提供していることもあって、物件の供給が不足しており、地元の人は希望するアパートに住めない状況が続いている(山形県)
○不動産賃貸については、古いビルから耐震性の高い中心部のビルにオフィス等を移転する動きがみられる。また、アパート等は震災被災者用の借上げを背景に、引き続き高い入居率となっている(宮城県)
○不動産賃貸については、震災被災者の避難に伴うアパート需要の動きは落ち着いた。土地の売買・仲介については、原発事故による放射線量の問題などから動きが鈍い(福島県)
○津波の浸水予想地域の見直しにより、当該地域の投資マインドが悪化している(高知県)
≪運輸業≫
○原発事故による農産物の風評被害などから物流が回復していない。また、燃料の高騰による大幅なコスト増を料金に反映できず、経営を圧迫し非常に厳しい状況にある(福島県)
○震災による工場の操業停止などにより、仕事量が多少減った時期もあるが、現在は回復傾向にある(茨城県)
○震災復興需要に伴い東北方面への貨物輸送は持ち直しているものの、関東や関西方面への長距離輸送は不振となっている。貨物輸送全体の取扱量は減少傾向が続いている(新潟県)
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要(平成24年6月29日)にアクセスして下さい。
「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改正(案)につきまして、平成24年5月31日(木)から平成24年6月20日(水)にかけて、広く意見の募集を行い、先般6月29日(金)にパブリックコメントの結果を公表し、各監督指針及び検査マニュアルの改正を行いました。
今般の改正は、本年1月20日に公表しましたシステムリスクの総点検の結果を踏まえ、金融機関に共通的な課題・問題点について、着眼点及び検証項目として、監督指針及び検査マニュアルに取り込むものです。
また、金融庁において、従来から金融機関の規模・特性に応じた検査・監督を行ってきたところ、こうしたこれまでの運用上の配慮事項について、改めて明確化を行っています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(6月29日)にアクセスして下さい。
証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組みの進捗状況について
「金融・資本市場に係る制度整備について」(平成22年1月21日、以下「制度整備」)では、先般の世界金融危機において認識された重要な課題の一つとして、「国債取引・貸株取引等の証券決済・清算態勢の強化」が盛り込まれました。これを受け、市場関係者において、証券決済リスク削減に向けた各取組の実施時期・実行期限等を定めた工程表の作成や、工程表に沿った検討・対応が進められてきたところです。
金融庁としては、市場関係者による、かかる工程表の作成や、工程表に沿った取組みは、我が国市場全体の決済リスク削減の進展につながるとともに、ひいては、我が国金融システムの安定に資すると考え、今後も、工程表に沿った取組みの実施を支援することとしています。
工程表については、半年毎(平成22年12月、平成23年6月、平成23年12月)にアップデートしており、本年6月末時点の進捗状況は以下のとおりです。
1. 国債取引
(1)経緯及び進捗状況
「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年6月29日、日本証券業協会、(株)日本国債清算機関(以下「JGBCC」)及び信託協会により、「国債取引の決済リスク削減に関する工程表」(以下「国債工程表」)が作成・公表されました。その後、上記3者をはじめとする市場関係者において検討が進められ、平成22年12月以降半年毎に検討結果が公表されているところです。
昨年12月以降、更に検討を重ねた結果、今般、(2)の通り各種の対応・合意がなされてきたところであり、これを反映して更新された「国債工程表」が、本年6月29日に公表されました。
(2)検討結果
○決済期間の短縮化
- 平成24年4月23日(約定分)からアウトライト取引の決済期間がT+2へ移行しました。
- 今後、アウトライトT+2化の実施状況のフォローアップを行うとともに、平成24年度下期に予定しているアウトライトT+1化の検討開始に向けた準備を行います。
○JGBCCの態勢強化
- 平成24年4月に「金融市場インフラのための原則」が公表されたことを受け、「最大総支払債務をもたらす可能性のある参加者とその関係法人の破綻」を想定した資金調達スキームの確立を目指して、「原則7 資金流動性リスク」への対応方法の検討を、運営委員会に諮問し、本年7月以降、特別委員会で検討することを決定しました。
○清算機関の利用拡大
- JGBCCは、信託協会との合意事項を踏まえ、信託銀行の特性に配慮した制度改正を行うため、業務方法書の一部を改定し、必要なシステム対応に着手しました。
- 信託銀行は、投資家等に対して、信託銀行の特性に配慮したJGBCCの制度改正概要等について説明を行っています。
- 信託銀行は、引き続き、投資家等の理解・承諾を得るよう努めるとともにJGBCCへの参加に伴う事務・システム等の変更についての具体的な検討を進め、投資家等の理解・承諾を得た上で、本件に係るJGBCC及び個別行におけるシステム対応に関する投資判断などの実情や他の市場インフラのシステムの整備の状況を踏まえ、平成26年前半を目途に運用有価証券信託でのJGBCCへの参加を実現します。
2. 貸株取引
「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年12月に(株)証券保管振替機構、(株)ほふりクリアリング及び市場関係者(証券会社、日本証券金融、信託銀行)により構成される貸株取引専門部会より、「貸株取引に係る決済リスク削減に関する工程表」(以下、「貸株工程表」)が作成・公表されました。
その後、平成26年1月の実施を目途にシステム対応を行うこととしている工程表の実現に向けて、検討が進められているところです。
※「国債工程表」及び「貸株工程表」の本体については、下記の各機関のウェブサイトをご覧ください。
信託協会(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news240629.html

 検索
検索