アクセスFSA 第192号

Contents
G20財務大臣・中央銀行総裁会議(G20福岡)について
6月8日(土)から9日(日)にかけて、日本議長の下、G20財務大臣・中央銀行総裁会議(G20福岡)が開催されました。G20福岡では、大臣・総裁間で活発な議論が行われ、採択された「共同声明(コミュニケ)」も中身の濃いものとして高い評価を得ました。金融セクターの優先課題としては、市場の分断回避、暗号資産を含む技術革新、高齢化と金融包摂、を取り上げましたので、これらの点を中心に成果をご紹介いたします。


○金融規制全体
金融規制全体に関しては、世界金融危機から10年が経ち、国際規制改革プログラムが概ね完了しています。今回、規制の実施とその影響評価作業や、新しいリスクと脆弱性への対応に軸足を移すとの姿勢を打ち出し、共同声明文から、合意された規制改革を「最終化する」という文言が初めてなくなりました。
○市場の分断回避
市場の分断(国際規制の実施時期のずれや各国独自規制等に起因)については、金融システムの安定性や金融仲介機能の効率性への負の影響に対する懸念が高まっています。
我が国は、G20でこの問題を初めて本格的に取り上げ、当方の要請に応じ、金融安定理事会(FSB)と証券監督者国際機構(IOSCO)が策定した報告書が歓迎されました。また、規制・監督上の協力を通じてこの問題に対処していくことが合意されました。今後は、デリバティブズ市場や資本と流動性の囲い込みの問題、国際連携等の分野を中心に、取組みを本格化していきます。
○技術革新
技術革新については、金融システムや経済全体に重要な便益をもたらし得るとの認識が共有されました。
一方で、暗号資産については、注意深く進展を監視し、リスクに警戒を続け、FSBその他の基準設定主体に、必要な対応の助言を求めることが合意されました。また、マネロン・テロ資金供与対策の面を強化し、金融活動作業部会(FATF)勧告適用への各国のコミットを前提に、FATFにおける具体的な適用基準の採択がG20おいて歓迎されました。
さらに、日本の要請に応じ、IOSCOが作成した当局者用の手引書(市中協議文書)が歓迎されました。この文書は、暗号資産に係る消費者・投資家保護等に関する初の国際的な成果であり、先日改正した資金決済法等の内容も盛り込まれています。
その他、日本の要請に応じ、FSBが作成した暗号資産当局者向けの台帳や、暗号資産に係る既存の取組みと規制ギャップに関する報告書が歓迎されました。この分野については、引き続き注視し、必要があれば多国間の対応を検討するという認識でG20各国は一致しています。
金融機関が仲介しない直接の金融取引が可能となる分散型金融技術については、その便益を十分享受できるよう、金融セクターへの影響分析や、当局・金融業界・学界・技術者等の対話の必要性等を内容とするFSBの報告書が歓迎されました。また、広く金融技術革新に関するマネロン・テロ資金供与対策に係る機会とリスクについて、FATFに作業・報告を要請することで合意されました。
また、6月8日に、G20技術革新セミナーを開催し、麻生大臣・IMFラガルド専務理事による基調講演の後、金融機関・IT企業の代表に、技術革新が金融セクターにもたらす機会とリスクについて、議論をして頂きました。また、当局・金融業界・学者・技術者等の専門家間で、分散型金融システムのガバナンスについても議論が行われました。金融庁としては、こうした形での議論は有益だと考えており、今後も取組みを進めていきます。金融庁からは、遠藤長官が講演を行いました。

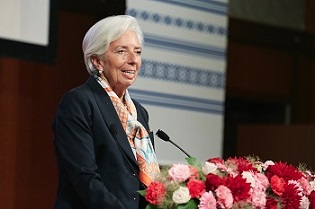

○高齢化と金融包摂
高齢化と金融包摂は、途上国を含め、世界各国の共通課題です。こうした認識の下、日本が議長を務める「金融包摂のためのグローバルパートナーシップ(GPFI)」により、金融リテラシーの向上等、金融包摂上の優先課題を網羅した「G20福岡ポリシー・プライオリティ」が取りまとめられ、これを承認しました。
また、6月7日に、G20高齢化と金融包摂ハイレベルシンポジウムを開催し、麻生大臣による開会挨拶、グリアOECD事務総長等による基調講演の後、国内外の有識者を招き、意見交換が行われました。金融庁からは遠藤長官がパネリストとして登壇しました。上記報告書や当シンポジウムを契機として、国際的な取組みや連携が加速することを期待しています。



この他、6月8日に、OECDと共催でG20/OECDコーポレートガバナンスセミナーを開催し、麻生大臣・OECDグリア事務総長による開会挨拶の後、当局・メディア・金融機関等から登壇者を招き、G20/OECDコーポレートガバナンス原則のグローバルな実施動向や各国の経験を共有するとともに、今後のあるべきコーポレートガバナンスの姿について議論をして頂きました。金融庁からは、遠藤長官が閉会挨拶を行いました。



今回のG20は、金融庁にとり、世界の金融の望ましい在り方を考える大変良い機会となりました。金融庁は引き続き、世界共通の課題の解決に向けて、このような機会を通じて各国と経験や知見を共有し、国際的な議論を深めてまいります。
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
金融庁では、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳及びインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況等を取りまとめ、定期的に公表しています。
今般、平成31年3月末までに発生した被害状況について、犯罪類型ごとに取りまとめ、6月14日に公表しました。
1.対象期間
- 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成31年3月
- 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成31年3月
- 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成31年3月
- インターネット・バンキング犯罪:平成17年2月から平成31年3月
2.被害発生件数
| 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 対象期間 の累計 |
|
| 偽造キャッシュカード | 383 | 306 | 396 | 260 | 7,210 |
| 盗難キャッシュカード | 2,930 | 3,915 | 10,520 | 12,987 | 82,981 |
| 盗難通帳 | 83 | 59 | 56 | 40 | 3,389 |
| インターネット ・バンキング |
1,561 | 763 | 367 | 343 | 7,370 |
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」(令和元年6月14日公表)にアクセスして下さい。
近年では、全国銀行協会や銀行員、警察官等を装ってキャッシュカードを被害者からだまし取る特殊詐欺(キャッシュカード手交型詐欺)の増加を主因に、盗難キャッシュカードによる不正出金の被害報告が急増しています。
特殊詐欺への対応について、関係省庁はこれまでにも各種の対策を講じてきました。しかしながら、認知件数・被害額共に高水準で推移しており、依然として深刻な情勢が続いています。
こうした状況を踏まえ、政府として、6月25日に第31回犯罪対策閣僚会議を開催し、特殊詐欺から高齢者を守るため、政府を挙げた総合対策について取りまとめた「オレオレ詐欺対策プラン」を決定しました。
会議では、麻生大臣から、「金融機関の窓口等で本人に声掛けや注意喚起を徹底していきたい」、「被害防止に向けた国民への広報啓発活動が重要」、「金融機関に対して、犯罪の未然防止に向けた取組みを促してまいりたい」と発言しています。
今後も政府一体となって、幅広い機関・団体・事業者の協力を得つつ、本プランの施策を推進してまいります。
 銀行協会職員や銀行員、役所職員、警察官が「キャッシュカードを預かる」「カードの暗証番号を尋ねる」ことは一切ありません。不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたりせず、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。
銀行協会職員や銀行員、役所職員、警察官が「キャッシュカードを預かる」「カードの暗証番号を尋ねる」ことは一切ありません。不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたりせず、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。
「金融分野のサイバーセキュリティレポート」の公表について
金融庁では、2015年7月、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」(以下、「取組方針」という)を策定・公表し、金融分野のサイバーセキュリティ強化に取り組んできました。
こうした中、デジタライゼーションの加速的な進展、国際的な議論の進展、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、近年、金融機関を取り巻く状況が大きく変化していること等を踏まえ、昨年10月、「取組方針」をアップデートしました。
昨事務年度は新たな「取組方針」に基づき、金融機関の大きな変化に対応するとともに、金融機関のサイバーセキュリティ管理態勢の強化、情報共有の枠組みの実効性向上などを通じて、金融分野のサイバーセキュリティ対策の向上に取り組んできました。
こうした昨事務年度の取組みにおいて把握した実態や共通する課題等について、当局、金融機関、関係機関等の間で認識を共有し、金融分野のサイバーセキュリティ対策の強化に繋げていくために、レポートとして取りまとめ、公表しました。
今後、当局として、デジタライゼーションの進展による金融分野を取り巻く環境の変化や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催によるサイバー攻撃のリスクの高まりを踏まえ、金融業界全体のもう一段のサイバーセキュリティ対策の強化を図って参ります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「「金融分野のサイバーセキュリティレポート」の公表について」(令和元年6月21日公表)にアクセスしてください。
第57回金融トラブル連絡調整協議会について
6月26日、第57回金融トラブル連絡調整協議会が開催されました。金融トラブル連絡調整協議会は、業態の枠を超えた情報・意見交換等を行い、金融分野における裁判外紛争解決制度の改善につなげるため、開催されているものです。
「各指定紛争解決機関の業務実施状況(平成30年度)」や「苦情・紛争解決に向けた取組み(特に顧客の適合性、商品理解等を踏まえた対応)」について説明があり、後者を中心とした意見交換が行われました。
※ 資料については、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融トラブル連絡調整協議会」から「第57回令和元年6月26日開催分」の「資料」にアクセスしてください。
※ 金融分野における裁判外紛争解決制度について詳しくお知りになりたい方は、「金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)」のページをご覧ください。金融トラブルでお困りの方は、「パンフレット「金融機関との間でトラブルをかかえている利用者の皆様へ(改訂版)」(PDF:215KB)」などをご覧ください。
「第13回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」の開催について
6月17日(月)に第13回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会を開催しました。
当懇談会は、改正貸金業法完全施行後の貸し手・借り手の状況をフォローしつつ、今後取り組むべき施策等について検討するため、平成24年9月に多重債務者対策本部の下に設置されたものです。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「お知らせ・広報」の中の「報道発表資料」から「「第13回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」の開催について」及び首相官邸ウェブサイトの「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」にアクセスしてください。

 検索
検索

