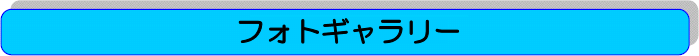アクセスFSA 第116号 (2013年2月)

財務局長会議にて挨拶する麻生大臣(1月30日)

財務局長会議にて挨拶する寺田副大臣(1月31日)
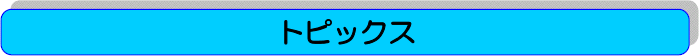
(1)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年10月1日~同年12月31日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成24年10月1日から同年12月31日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成24年10月1日から同年12月31日までの間(以下、「今期」という。)に、9,215件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均149件となっており、平成24年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績155件に比べてやや減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,617件(構成比28%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,508件(同27%)、投資商品等に関する相談等の受付件数2,914件(同32%)、貸金等に関する相談等の受付件数738件(同8%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数438件(同5%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、前期に比べて、ほぼ同水準となっています。
(2)保険商品等については、前期に比べて、ほぼ同水準となっています。
(3)投資商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、減少しています。
(4)貸金等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供等のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反等)に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)無登録営業に関するもの
(12)金融商品取引業者の不適正行為(ホームページを閉鎖し電話にでない、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(14)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ78口座の情報提供を行っています。
前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。
- 監督において行った165金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
- 金融庁が着手した17金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しています。
今回、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」の「融資に関する相談等」に以下の相談事例等を新たに追加しました。
「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」の期限が到来すると聞きましたが、平成25年4月以降は貸付条件の変更等ができなくなるのでしょうか。
今回、新たに追加したものを加えた以下の項目について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、こちらもご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
(0570-016811(ナビダイヤル)、IP電話・PHSからは03-5251-6811)
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
(03-3581-9909)
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年10月1日~同年12月31日)」(平成25年1月31日)にアクセスして下さい。
(2)平成24年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)の開催について
財務局及び沖縄総合事務局においては、平成17年度以降、地域密着型金融の取組みに関する知見・ノウハウの共有化等を目的に、地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)を開催しており、本年度の日程は以下のとおりです。
北海道財務局 (日程:平成25年3月8日 場所:札幌市)
東北財務局 (日程:平成25年3月15日 場所:仙台市)
関東財務局 (日程:平成25年2月28日 場所:東京都渋谷区)
北陸財務局 (日程:平成25年3月6日 場所:金沢市)
東海財務局 (日程:平成25年3月8日 場所:名古屋市)
近畿財務局 (日程:平成25年3月18日 場所:大阪市)
中国財務局 (日程:平成25年2月27日 場所:広島市)
四国財務局 (日程:平成25年3月5日 場所:高松市)
福岡財務支局 (日程:平成25年3月1日 場所:福岡市)
九州財務局 (日程:平成25年2月28日 場所:熊本市)
沖縄総合事務局(日程:平成25年3月6日 場所:那覇市)
なお、本年度のシンポジウムにおいては、昨年度と同様、広域での知見・ノウハウの共有化やシンポジウムの充実を図る観点から、一部の地域金融機関の経営者の方々に、「地域密着型金融の推進のサポ-ト役」として、主要営業地域外の財務局等が開催するシンポジウムにご参加いただき、自行(金庫)における取組み等についてご紹介いただくとともに、パネルディスカッションにもご参加いただく予定です。
また、シンポジウムの開催結果の概要につきましては、金融庁ウェブサイトに随時掲載する予定です。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成24年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)の開催について」(平成25年1月31日)にアクセスして下さい。
(3)「振り込め詐欺救済法」に基づく返金制度について
振り込め詐欺等の犯罪被害にあった方は、基本的には民事訴訟を提起して損害回復を行うことが可能ですが、「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んだ口座の残高や被害額に応じて、被害回復分配金(被害額の全部又は一部)の支払いを受けることができる場合があります。返金までの大まかな流れは以下のとおりです。
※ 振り込め詐欺のほか、社債、未公開株等の取引を装った詐欺やヤミ金融などの被害も、振込みにより被害が発生した場合は、振り込め詐欺救済法の対象となります。
いときは、この公告に係る預金等債権は、消滅することとなります。
(3)被害回復分配金の支払(返金)手続
被害回復分配金の支払い(返金)を受けるためには、振り込め詐欺等の犯罪被害にあった方は、振り込んだ先の金融機関へ申請する必要があります!
金融機関は、預金保険機構に対し支払い手続開始に係る公告(支払公告)を求め、預金保険機構が支払公告
 を行います。
を行います。金融機関は、消滅した預金等債権の額の金銭を原資として、上記支払公告の期間(30日以上※)内に支払申請があった被害者に対して、被害回復分配金を支払う(返金する)ことになります。
なお、各人に支払う被害回復分配金の額は、被害額により按分した額とされており、振り込んだ先の口座に十分な残高が残っていなかったり、他にも同様の被害にあった方がいる場合には、被害額に比べて被害回復分配金の支払額が少なくなったり、支払いが行われない場合もあります。また、消滅した預金債権の額が1,000円未満である場合は、支払い手続は行われません。
※これまで60日で運用していましたが、東北地方太平洋沖地震による被災者の方々への影響を考慮して、当面の間、支払手続申請期間を60日から90日に延長しております(地震発生後に実施する支払手続開始公告が対象)。
(4)その他
金融機関は、被害のお申し出がなかった等の理由により、被害者にお返しできなかった残余金を預金保険機構に納付します。このお金は犯罪被害者等支援事業(奨学金事業、民間団体に対する助成事業)に活用されます。詳しくはこちら「振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金の活用について」をご覧下さい。
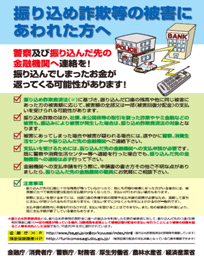
※詳しくは、金融庁のウェブサイトの「お知らせの一覧へ」中の「お知らせ」から「振り込め詐欺にご注意!」にアクセスしてください。
(4)「ABL」及び「資本性借入金」の積極的活用について
「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)において、中小企業等への経営改善、資金繰りの支援策として、「ABL(動産・売掛金担保融資)」の活用促進が盛り込まれました。
これを受けて、金融庁においては、平成25年2月5日に、「動産担保」や「売掛金担保」について、金融検査マニュアル上、「一般担保」(客観的な処分可能性がある担保)として認められるための要件の明確化などを行いました。
あわせて、同日、資本不足に直面している中小企業等への支援策である「資本性借入金」に関し、金融機関の税務上の取扱い(損金処理が認められる要件)についても明確化を行いました。
これらの取組みを通じ、金融機関における「ABL」及び「資本性借入金」の更なる活用を推進し、中小企業等への経営改善、資金繰りの支援を図っていきたいと考えています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用について」(平成25年2月5日)及び「資本性借入金の税務上の取扱いについて」(平成25年2月5日)にアクセスして下さい。
(5)「中小企業等金融円滑化相談窓口」の設置について
中小企業金融円滑化法が平成25年3月末で期限を迎えますが、様々な状況におかれた借り手の心配や質問にお答えするため、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)に基づき、全ての財務局・財務事務所に、平成25年2月22日付で「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置しました。
この窓口では、借り手からの相談・苦情・要望等を一元的に受け付けて、きめ細かく対応していきます。2月25日から業務を開始しており、借り手の皆様におかれてはぜひ遠慮なく、この相談窓口にご相談下さい。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業等金融円滑化相談窓口の設置について」(平成25年2月22日)にアクセスして下さい。
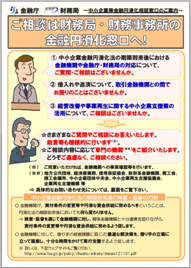

 検索
検索