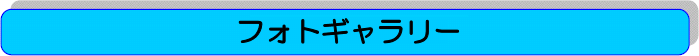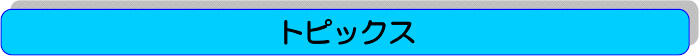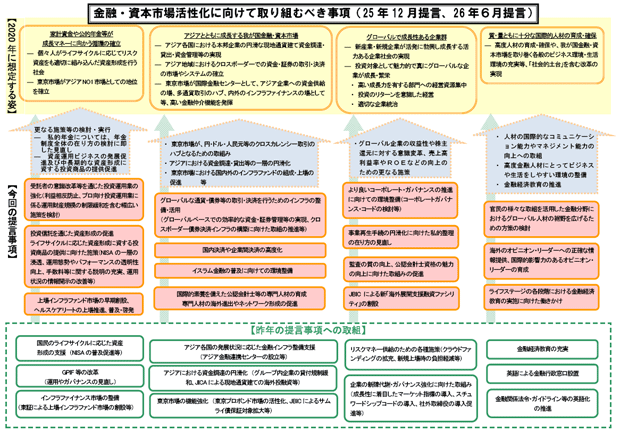アクセスFSA 第132号(2014年6月)

【トピックス】
 |
| 伊藤幹事から麻生大臣へ「金融・資本市場活性化に向けて 重点的に取り組むべき事項(提言)」を手交(6月12日) |
(1)平成26年金融商品取引法等を改正する法律(平成26年3月14日提出、5月23日成立)について
日本経済の再生のため、家計の金融資産を成長マネーに振り向けるための施策を始めとする日本の金融・資本市場の総合的な魅力の向上策を整備し、成長戦略を金融面から加速・強化していくことが重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、金融商品取引法等を改正する法律案を平成26年3月14日に国会へ提出しました。本法案は、5月23日に成立し、5月30日に公布されました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等
(1)投資型クラウドファンディングの利用促進
少額の投資型クラウドファンディングを取り扱う金商業者の参入要件を緩和しました。また、インターネットを通じた投資勧誘において詐欺的行為等が行われることを排除するための行為規制を導入しました。
(2)新たな非上場株式の取引制度
非上場株式の取引・換金ニーズに応える新たな取引制度を設けるに当たり、限定された投資家間での流通に留めることから、現行のグリーンシート銘柄制度とは異なり、通常の非上場株式と同様の規制を適用することとしました。
2.新規上場の促進や資金調達の円滑化等
(1)新規上場に伴う負担の軽減
新規上場後3年間に限り、「内部統制報告書」に対する公認会計士監査の免除を選択可能としました。
(2)上場企業の資金調達の円滑化等
上場企業が自社株を取得・処分する場合には、「大量保有報告書」の提出を不要としました。また、虚偽記載を行った上場企業が流通時に有価証券を取得した投資家に負う損害賠償責任について、無過失責任から過失責任(ただし、挙証責任は上場企業側)に変更しました。
3.市場の信頼性確保
(1)ファンド販売業者に対する規制の見直し
第二種金商業者が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱いを行うこと等を禁止しました。また、第二種金商業者について、国内拠点の設置等を義務付けました。
(2)金融指標に係る規制の導入
特定の金融指標の算出者に関する規制を導入しました。
その他、所要の改正を行いました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁の政策一覧」の中の「国会提出法案等」から、「国会提出法案(第186回国会)」における「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年3月14日提出、平成26年5月23日成立)」にアクセスしてください。
(2)保険業法等の一部を改正する法律(平成26年3月14日提出、5月23日成立)について
近年の保険会社を巡る経営環境の大きな変化を踏まえ、新たな環境に対応するために保険募集規制を整備することや、保険業の発展を通じて経済活性化への貢献を実現していくことが喫緊の課題となっていることから、保険の信頼性を確保するため、(1)保険募集の基本的ルールとして、顧客の意向把握義務及び顧客に対する情報提供義務を導入するとともに、(2)保険募集人に対して業務の規模・特性に応じた体制整備を義務付けることとしております。
また、保険会社等の海外への積極的な業務展開を推進するなど、保険業を活性化するため、(1)海外の金融機関等を買収した際の子会社の業務範囲の特例を拡大するほか、(2)保険仲立人に係る規制緩和、(3)実態に合った顧客対応を可能とするための規制緩和を行うこととしております。
今後、本法律の施行に向けて、関係政府令の整備を行って参ります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁の政策一覧」の中の「国会提出法案等」から、「国会提出法案(第186回国会)」における「保険業法等の一部を改正する法律(平成26年3月14日提出、平成26年5月23日成立)」にアクセスしてください。
(3)「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項(提言)」の公表について
金融・資本市場活性化有識者会合においては、「金融・資本市場活性化に向けての提言」(平成25年12月13日公表)の取りまとめ以降、数回にわたって、「提言」の実施状況のフォローアップ、「提言」の深掘りや新しい論点について議論が行われてきました。
平成26年5月14日、「金融・資本市場活性化有識者会合における年明け以降の主な意見」が公表されたところですが、今般(6月12日)、「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項(提言)」が取りまとめられ、幹事の伊藤隆敏政策研究大学院大学教授より、麻生財務大臣兼内閣府特命担当大臣に提出されました。
この提言の主な内容は、以下のとおりです。
1.第一に、企業の競争力強化や起業の促進により、本邦企業の収益力向上を図るべきであること、特に、より良いコーポレート・ガバナンスの強化や公的金融を呼び水とした民間資金の活用、企業の健全な新陳代謝や再編の促進などが重要であることが述べられています。
こうした点に関連した具体的な施策として、
- コーポレートガバナンス・コードの検討など、より良いコーポレート・ガバナンスに向けての環境整備
- JBICによる新たな海外展開支援融資ファシリティの創設
- 事業再生手続の円滑化に向けた私的整理の在り方の見直し(多数決の導入等)
などが挙げられています。
2.第二に、家計の金融資産を成長企業に振り向けるため、受託者の意識改革等を通じた投資運用業の強化を図るとともに、投資家のライフステージやリスク特性等を踏まえた投資商品の提供を促すことにより資産形成を促進することなどが述べられています。
こうした点に関連した具体的な施策として、
- 投資運用業について、投資運用業者と投資家との利益相反の防止等を通じた受託者の意識改革・プロ向け投資運用業に係る運用財産規模(200億円)の制限緩和等による投資運用業の発展・拡大
- 投資信託について、運用態勢やパフォーマンスの透明性向上、手数料等に関する説明の充実、投資家が自らの属性に適した商品を選びやすくするためのリスク・リターンの定量的な表示、運用状況に関する情報開示の充実等
- インフラファンド市場の早期の創設、インフラ投資への民間資金の供給促進
などが挙げられています。
3.第三に、我が国とアジア諸国との連携による、地域全体としての金融・資本機能の向上を図るべきであること、本邦企業の事業展開を更に後押しするため、決済機能の高度化等を図るべきであることが述べられています。
こうした点に関連した具体的な施策として、
- グローバルな通貨・債券等の取引・決済を行うためのシステムの整備・活用、
- 国内決済や企業間決済の高度化
などが挙げられています。
4.最後に、日本国内においても様々なレベルでの英語によるコミュニケーションが必要となるとともに、海外において日本人が現地でのマネジメントを求められるようになっていることを踏まえ、人材の国際的なコミュニケーション能力やマネジメント能力の向上に取り組むこと、高度金融人材にとってビジネスや生活をしやすい環境の整備を図ること、金融経済教育を推進していくべきであることが述べられています。
こうした点に関連した具体的な施策として、
- 官民の様々な取組を活用し、金融分野におけるグローバル人材の裾野を広げるための方策を検討すること
- ライフステージの各段階における金融経済教育の実施に向けた働きかけをしていくこと
などが挙げられています。
※ 詳しくは、和文は、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項(提言)」の公表について」(平成26年6月12日)、英文は、金融庁ウェブサイト(英語版)の「Topics」から「The Panel for Vitalizing Financial and Capital Markets Releases a Follow-up and Further Recommendations」![]() にアクセスしてください。
にアクセスしてください。
(4)「事前相談(予防的なガイド)」の開設について
金融サービス利用者相談室においては、従来、「金融機関との間の個別トラブルに関する相談等や金融行政に関する意見・要望等」への対応を主として行ってきましたが、金融サービス利用に伴うトラブルの発生の未然防止などに向けた事前相談の提供の充実を図るため、「事前相談(予防的なガイド)」を下記のとおり、開設することとしました。
| 1.名称 | : | 「事前相談(予防的なガイド)」 |
| 2.開設日 | : | 平成26年5月23日(金) |
| 3.受付時間 | : | 平日10時00分~17時00分(電話での受付) ※ファックス、ウェブサイトは24時間受付。 |
| 4.電話での受付 | : | 0570-016812 ※IP電話からは03-5251-6812におかけください。 |
| 5.ファックスでの受付 | : | 03-3506-6699 |
| 6.ウェブサイトでの受付 | : | こちらをクリックして下さい。 |
| 7.文書での受付 | : | 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 金融庁 金融サービス利用者相談室 |
(注)ファックス、ウェブサイト、文書で受け付けさせて頂いた場合には、相談室より、原則平日10時00分~17時00分の間に、お電話をお返し致します。 |
||
【受付内容】
事前相談においては、電話等による問合せに対し、一般的な
(1)金融商品の契約にあたっての留意点、
(2)金融機関破綻時の金融商品の保護、
(3)金融商品の特徴及び留意点等
について、金融庁ウェブサイトの掲載情報を中心に、以下の情報に基づきガイド(説明)します。
- 「知るぽると」掲載情報
- 業界団体等(全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会、生命保険文化センター、生命保険協会、日本損害保険協会及び日本FP協会)のウェブサイト掲載情報
【ご留意事項】
- 「金融機関との間の個別トラブルに関する相談等や金融行政に関する意見・要望等」については、0570-016811(IP電話からは、03-5251-6811)におかけください。
- 「事前相談(予防的なガイド)」については、主な金融商品の特徴や留意点などに関する一般的な内容をガイドするものです。個別の金融商品のご購入・ご利用にあたっては、必ず各金融機関に問合せ、内容を十分にご確認のうえ、ご自身の判断に基づきご対応下さい。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「事前相談(予防的なガイド)」の開設について」(平成26年5月23日)にアクセスしてください。
(5)「店頭デリバティブ取引情報」の公表について
金融機関における店頭デリバティブ取引に係るリスク評価や情報の保存・蓄積を促すことを目的として、平成25年4月より、金融商品取引業者等に対する店頭デリバティブ取引情報の保存・報告制度が開始されました。金融商品取引法第156条の66の規定に基づき、店頭デリバティブ取引市場の透明性と予測可能性を高める観点から、平成26年3月末における金融商品取引業者等から報告を受けた店頭デリバティブ取引情報の集計結果について、5月14日に公表しました。
今般、公表した結果では、平成26年3月末のわが国の金商業者等の店頭デリバティブ残高は、約3,800兆円となっています。このうち、金利関連デリバティブが約3,600兆円、信用関連デリバティブが約30兆円、為替関連デリバティブが約150兆円、株式関連デリバティブが約10兆円となっています。
今後も定期的に店頭デリバティブ取引情報の集計結果を公表していく予定です。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「店頭デリバティブ取引情報の公表について(平成26年3月末)」(平成26年5月14日)にアクセスしてください。
(6)「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた奨学金事業の通年募集について
振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた奨学金事業については、これまで申請期間を設けて実施してきましたが、平成26年6月2日より、年間を通じて随時募集することとなりました。
(奨学金制度の概要)
○担い手
公益財団法人 日本財団
○奨学金事業名
まごころ奨学金
○対象
犯罪被害者の子弟(高校生から大学院生まで)
※振り込め詐欺などの財産犯に限らず、生命犯、身体犯、交通事故等の犯罪全般を対象とします。
○形式
無利子での貸与
○返済期間
貸与期間の終了した月の翌月から起算して、半年を経過した月から30年以内
○募集期間
随時
○貸与金額
以下の金額を上限として、1万円単位で自由に設定可能
| 月額(上限) | 入学一時金(上限) | |
| 大学院 | 10万円 | 30万円 |
| 大学・短大 高等学校4年以上 専修学校専門課程 |
8万円 | 30万円 |
| 高等学校 高等専門学校3年以下 専修学校高等過程 特別支援学校高等部 |
国立・公立3万円 私立5万円 |
国立・公立6万円 私立25万円 |
当該事業の詳細につきましては、事業の担い手である「公益財団法人 日本財団」までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
- 公益財団法人 日本財団 まごころ奨学金係
- 電話:03-6229-5111
- FAX :03-6229-5160
詳細はこちら(http://nf-yoho.com/scholarship/index.html![]() )をご覧ください。
)をご覧ください。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた奨学金事業の通年募集について」(平成26年6月2日)にアクセスしてください。

 検索
検索