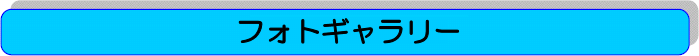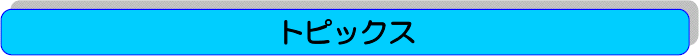アクセスFSA 第160号(2016年10月)
 |
 |
|
| 11月18日 金融仲介の改善に向けた検討会議(第6回)にて挨拶する 越智副大臣・武村大臣政務官 |
||
(1) 「平成28事務年度 金融行政方針」の公表について
金融庁は、金融行政が何を目指し、その実現に向け、平成28事務年度にいかなる方針で金融行政を行っていくかについて、本年10月に「平成28事務年度 金融行政方針」として公表しました。本方針は、PDCAサイクルを強く意識し、本年9月に公表した「平成27事務年度 金融レポート」における評価を踏まえ、とりまとめたものです。
本方針において、金融庁は、引き続き、 金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、
金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、 利用者保護/利用者利便、
利用者保護/利用者利便、 市場の公平性・透明性/市場の活力を確保することにより、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指すこととしています。
市場の公平性・透明性/市場の活力を確保することにより、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指すこととしています。
金融を取り巻く環境が急激に変化する中で、市場メカニズムを適切に発揮させつつ、上記を実現するため、
(1)金融当局・金融行政運営の変革
(2)国民の安定的な資産形成を実現する資金の流れへの転換
(3)「共通価値の創造」を目指したビジネスモデルの転換
といった変革に取り組んでいきます。
こうした基本方針の下、金融庁では、重点施策として、
 活力ある資本市場と安定的な資産形成の実現、市場の公正性・透明性の確保
活力ある資本市場と安定的な資産形成の実現、市場の公正性・透明性の確保 金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等
金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等 IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応
IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応 国際的な課題への対応
国際的な課題への対応 顧客の信頼・安心感の確保
顧客の信頼・安心感の確保 その他の重点施策
その他の重点施策
に取り組んでいきます。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」の中の「平成28事務年度金融行政方針について」にアクセスして下さい。
(2) 保険会社におけるリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書(ORSAレポート)及び統合的リスク管理(ERM)態勢ヒアリングに基づくERM評価の結果概要について
1.経緯等
保険会社においては、その取り巻くリスクの多様化・複雑化を踏まえ、規制の遵守に加え適切なリスクとリターンのバランスの下、全てのリスクを経営戦略と一体で統合的に管理する統合的リスク管理(ERM)態勢の整備・高度化を図ることが重要な課題となっています。
こうした中、2015年度より、保険会社がリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書(ORSAレポート)を作成した上で、金融庁へ提出する取組みを開始し、同レポート等をもとに、保険会社のERM評価を行いました。
(注)ERMとは、Enterprise Risk Managementの略。ORSAとは、Own Risk and Solvency Assessmentの略。
| 【概念図】 |
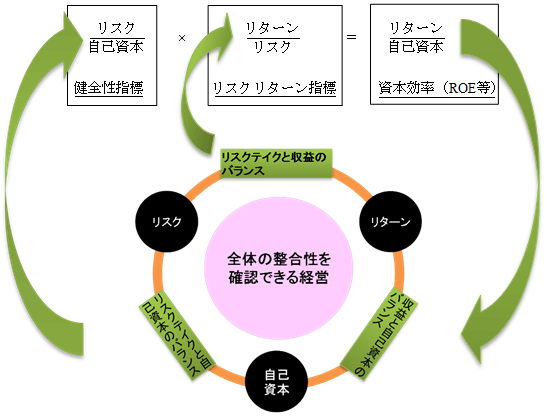 |
2.ERM評価の実施
平成27事務年度については、規模特性の観点から保険料等収入等に基づき保険持株会社8社、生命保険会社25社、損害保険会社23社を選定し評価を実施しました。
ERM評価にあたっては、評価目線を作成し、「リスク文化とリスクガバナンス」、「リスクコントロールと資本の十分性」、「リスクプロファイルとリスクの測定」及び「経営への活用」といった項目を検証し、ERMに関する態勢が整備されているか、ERMの考え方が保険会社内に浸透しているかといった観点から確認を行いました。
3.ERM評価の結果概要
各保険会社のERM評価結果については、レベル1~レベル5に区分し、それぞれの内容については下記のとおりです。
【ERM評価レベルの概要】
| 評価 レベル |
健全性面 | 収益性面 | ||
|---|---|---|---|---|
| レベル5 | 資本がリスクを十分上回っており、かつ健全性を確保する強固な態勢を保有している。 | + | 健全性を確保した上で、収益性を向上させる先進的な取組みが定着している。 | |
| レベル4 | 資本がリスクを十分上回り、健全性を確保する態勢を保有しているものの、強固な態勢とまではいえない。 又は 健全性を確保する強固な態勢を保有し、一定程度健全性を確保しているものの、十分な健全性を確保しているとはいえない。 |
健全性を確保した上で、収益性を向上させる先進的な取組みを導入している。 | ||
| レベル3 | 一定程度健全性を確保し、かつ健全性を確保する態勢を保有している。 | 健全性を確保した上で、収益性を向上させる先進的な取組みを検討中。 | ||
| レベル2 | 一定程度健全性を確保しているものの、健全性を確保する態勢が弱い。 又は 健全性に課題があるものの、健全性を確保する態勢を保有している。 |
健全性を確保した上で、収益性を向上させる取組みは、将来の課題として認識。 | ||
| レベル1 | 健全性に課題があり、また健全性を確保するシステムが弱い。 | 課題認識なし。 |
ERMを健全性確保に加え、リスク文化の醸成や収益性の向上にも活用し、経営全体に活かすガバナンスを備えた社は未だ一部であり、評価結果に以下のようなばらつきがみられました。
| 【ERM評価レベルの分布状況】 |
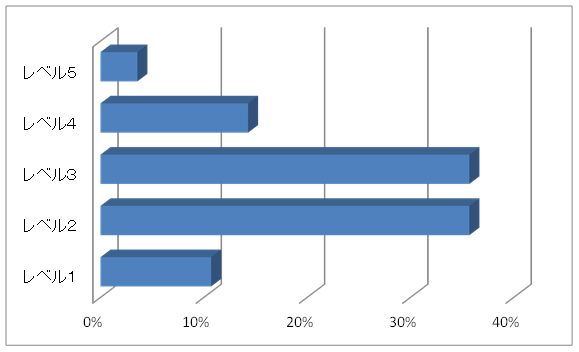 |
(注)今年度ERM評価の対象とした保険持株会社及び保険会社(計56社)の評価結果を単純にグラフ化
4.今後の課題
ERM評価は、定量的・画一的に健全性を評価するのみではなく、適切なリスク文化・ガバナンスと高度なリスク管理態勢を備えた保険会社における積極的なリスクテイクを合わせて評価する枠組みであり、金融庁としては、健全性を維持した上で保険会社の適切な成長を促す観点から、引き続きERMの高度化を促進していきます。
また、ERMヒアリング及びORSAレポートを通じ、現時点の静的な健全性評価にとどまらず、将来の動的な健全性を幅広く分析することで、より実態に即した監督を行っていきます。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「保険会社におけるリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書(ORSAレポート)及び統合的リスク管理(ERM)態勢ヒアリングに基づくERM評価の結果概要について」(平成28年9月15日)にアクセスしてください。
(3) 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall)」について
金融分野におけるサイバー攻撃の高度化が進む中、サイバーセキュリティの確保は、金融システム全体の安定のため喫緊の課題となっています。
このため、金融庁として、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」(平成27年7月公表)に沿って、金融機関のサイバーセキュリティ対策の向上に向けた取組みを推進しているところです。
先般、同方針に基づき、金融業界全体のサイバーセキュリティ対策の底上げを図るため、初めてとなる金融業界横断的な演習(通称:Delta Wall(※))を実施しました。
(※)Delta Wall:サイバーセキュリティ対策のカギとなる「自助」、「共助」、「公助」の3つの視点(Delta)と防御(Wall)
【演習概要】
○ 日程:平成28年10月24日(月)~27日(木)の4日間
○ 参加者:約80の金融機関が参加
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall)」について(平成28年10月20日)にアクセスしてください。
【演習の模様 】 】 |
【演習の模様 】 】 |
|
 |
 |
(4) 金融審議会 市場ワーキング・グループ 「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」(第1回)の開催について
企業が公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に、当該情報が他の投資者にも同時に提供されることを確保するフェア・ディスクロージャー・ルールについては、平成28年4月の金融審議会の報告において、「我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要がある」とされました。これを受け、金融審議会市場ワーキング・グループの下に「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」を設置し、実務的な議論を行うこととされました。
第1回会合は10月21日(金)に開催され、ルール導入の意義や導入に当たり留意すべき事項(対象となる情報の範囲、情報受領者の範囲等)について、幅広く議論がなされました。
なお、第1回会合にかかる議事録・資料につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「公表物」→「審議会・研究会等」→「金融審議会」→「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」にアクセスしてください。
(5) 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第7~9回)の開催について
10月19日(水)、11月2日(水)、9日(水)にそれぞれ第7~9回「金融審議会 市場ワーキング・グループ」が開催されました。
市場ワーキング・グループは平成28年4月開催の第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合における、麻生金融担当大臣による諮問を受けて設置されたもので、第7回会合では、5月の第1回に続いて「取引の高速化」をテーマとして議論がなされました。また、第8回会合は7月の第3回、8月の第4回、10月の第5回に続き「国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デューティー」を題材に開催されました。第9回会合では、「市場間競争と取引所外の取引、取引所の業務範囲」について話し合われました。
今後も市場ワーキング・グループ会合では、情報技術の進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について、幅広く検討を行う予定です。
なお、第1~6回会合にかかる議事録・資料、第7~9回資料につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から、「市場ワーキング・グループ」にアクセスしてください。
(6) 金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」(第2回、第3回)の開催について
FinTechは金融・市場の将来的な姿を大きく変えていく可能性が高いと考えられ、金融庁としては、FinTechの動きを利用者利便や生産性の向上、コスト削減などにつなげていくことができるよう、必要な対応を進めていく必要があります。
法制面での課題については、本年5月、銀行等による金融関連IT企業等への出資を容易にすることや、仮想通貨と法定通貨の交換業者の登録制導入等を図るための銀行法等の一部改正法案が成立したところですが、本年7月に金融制度ワーキング・グループを設置し、引き続き議論を行っております。
ワーキング・グループにおいては、決裁業務に係る法制面での課題について検討を行っていくこととされていますが、昨今のビジネス展開の状況等を踏まえ、まずは、銀行等と顧客との間に立って顧客のために決済関連サービスを提供するいわゆる中間的業者の法制面での取り扱いについて、検討を進めていくことが重要と考えており、10月18日(火)の第2回会合、28日(金)の第3回会合でこの問題についての検討を行いました。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融制度ワーキング・グループ」にアクセスしてください。
(7) 「金融モニタリング有識者会議」(第3回)の開催について
新しいモニタリングの基本的な考え方や手法等について、外部の有識者を交えて議論、整理し、新しいモニタリングの考え方をとりまとめ、金融機関等と共有を図るとともに国際的に発信していくため、「金融モニタリング有識者会議」(座長:吉野直行 アジア開発銀行研究所所長、慶應義塾大学名誉教授)を設置し、8月24日に第1回会合を、9月30日に第2回会合を、10月24日に第3回会合を開催しました。
第3回会合では、プルーデンス政策の基本的な考え方及び手法をテーマに幅広く議論がなされました。
なお、会議は非公開ですが、会議後、資料・議事要旨を金融庁ウェブサイトにて公表しています。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「金融モニタリング有識者会議」にアクセスしてください。
(8) 「金融行政モニター」におけるご意見等の受付状況及び金融庁の対応について
1.金融行政モニターについて
金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご意見等をお伺いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることにより、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあるところです。このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家が直接にご意見・ご提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓口」を設置し、寄せられたご意見等を金融行政に反映できる仕組みを構築しており、平成28年1月29日より運用を開始しています。
今般、本制度の実効性・透明性を図る観点から、平成28年3月から5月までの3か月間に寄せられたご意見等の受付状況及び金融庁の対応について、以下のとおり公表いたします。
(注)このほか、引き続き、金融庁に対して直接ご意見等を提出して頂くための「金融行政ご意見受付窓口」も設置しています。当該窓口に寄せられた意見等は、平成28年3月1日から5月31日までの間に205件となっています。
2.金融行政モニター受付窓口に寄せられたご意見等について
○平成28年3月1日から同年5月31日までに寄せられたご意見等
【受付件数】
9件
【主なご意見等】
(![]() 別紙)をご覧ください。
別紙)をご覧ください。
※公表にあたっては、金融行政モニター委員から金融庁幹部等にフィードバックのあったご意見等のうち、主なものについてご意見等の提出者の同意があるものに限り公表し、所属組織や個人等に係る情報は非公表としております。
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「ご意見・情報を受け付けます」の「金融行政モニター」にアクセスしてください。
(9) 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成28年7月1日~同年9月30日)について
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成28年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成28年7月1日から同年9月30日までの間に、8,491件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均137件となっており、平成28年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績150件に比べ、やや減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,812件(構成比33%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,329件(同27%)、投資商品等に関する相談等の受付件数2,170件(同26%)、貸金等に関する相談等の受付件数779件(同9%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数401件(同5%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、前期に比べて、やや減少しています。
(2)保険商品等については、前期に比べて、やや減少しています。
(3)投資商品等については、前期に比べて、減少しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが288件あり、そのうち147件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(199件)のうち、70代が48件(24%)、80代以上が40件(20%)、60代が28件(14%)、と高齢者についての相談が大部分を占めております。
(4)貸金等については、前期に比べて、やや減少しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関等に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)預金取扱金融機関における口座凍結等に関するもの
(7)預金取扱金融機関におけるホームページの画面表示に関するもの
(8)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(9)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応等)に関するもの
(10)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(11)貸金業者の不適切な業務運営に関するもの
(12)システム障害に関するもの
(13)外国為替証拠金取引業者の不適切な行為に関するもの
(14)外国為替証拠金取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの
(15)無登録営業に関するもの
(16)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの
(17)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、127の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
金融機関等の検査等に際して、22の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※詳しくは、「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成28年7月1日~同年9月30日)(平成28年10月31日)にアクセスしてください。

 検索
検索