【特集】
サブプライム問題などで世界の金融市場の動向が注目を集めるなか、2007年11月8日(木)、9日(金)の2日間に亘り、「IOSCO東京コンファレンス」が開催されました。世界46の国・地域から400人を越える証券監督当局と市場関係者が一堂に会し、証券行政のあり方についての議論や、直近の金融・資本市場の話題について意見交換を行いました。
IOSCO(証券監督者国際機構)とは、世界116の国・地域の証券監督当局や証券取引所等から構成される国際機関であり、証券監督に関する原則・指針等の国際的なルールの策定が行われています。金融庁および証券取引等監視委員会は、我が国における証券当局として、こうしたIOSCOの活動に積極的に貢献しています。
IOSCOでは、民間金融セクターとの対話の促進を目的に、平成16年から毎年、世界の主要な金融センターにて、コンファレンスを開催しており、第一回はニューヨーク、第二回はフランクフルト、第三回はロンドンで行われ、今回の東京での開催は四回目となりました。
コンファレンスの開会に当たり、渡辺金融担当大臣、IOSCO専門委員会の議長を務めるフランス金融市場庁のミッシェル・プラダ長官、及び米国証券取引委員会のコックス委員長からの基調講演がありました。渡辺金融担当大臣からは、直近のサブプライム問題について、危機を未然に防ぎ、また危機が起こった時に迅速にこれを認知し、対策を的確に講じていくために、各国の官民双方の叡智を結集することが求められているとの発言がありました。
オープニング・スピーチの後、「市場規制 -競争、収斂、そして協調」を基調テーマに、規制当局者と市場関係者の幹部による以下の六つのパネル・ディスカッションが行われました。
 |
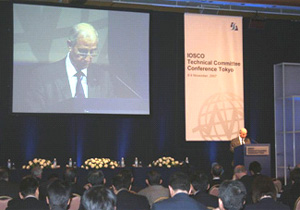 |
| オープニングスピーチを行う渡辺大臣 | IOSCO専門委員会の議長を務めるミッシェル・プラダ氏 |
|
|
| 400人を超える証券監督当局と市場関係者 | |
パネル1 「会計・監査における収斂」
会計・監査の分野では、近年のグローバルな資本市場の統合を背景に、基準の標準化や財務報告の質を高める取組みが行われています。
会計基準については、質の高いものへのコンバージェンスが図られるのと同時に、主要な資本市場の規制当局者において、同等性の評価又は相互承認に向けた作業を通じて外国の会計基準を認めることが検討されています。監査も、会計基準の適用を整合的なものとし、財務報告を高品質なものとする上で重要な役割を担っています。
本パネルでは、資本市場が国際化し統合しつつある状況において、質の高い財務報告を確かなものとするうえで必要な会計基準・監査がどのような役割を果たしていくかについて議論を行いました。長期的な問題として、会計基準の国際的なコンバージェンス及びIFRSに関する課題、監査基準のコンバージェンス、独立監査人監督機関からの影響について議論がなされました。また、最近の市場の混乱に関連して浮き彫りになった短期的な問題としては、金融商品の公正価値評価、特別目的事業体(SPEs)を利用したオフバランスシート取引について議論がなされました。
パネル2 「取引所間の競争と統合」
取引所のグローバルな再編は、特に2000年のユーロネクスト誕生以降加速し、規制当局者等においては、取引の公平性及び透明性を維持すると同時に、市場の効率性を向上することが課題となっています。過剰な規制コストを回避したうえで、投資者保護を図るための一つの方策としては、各国の金融商品の上場審査基準の標準化や規制の相互承認が挙げられます。同時に、代替的取引システム(ATS)/多角的取引施設(MTF)の出現により新たな競争も生まれています。
こうしたなか、本パネルでは、取引所のグローバルな競争や株式会社化・上場が、自主規制概念に与える影響、広がる代替的取引システム(ATS)/多角的取引システム(MTF)の影響によって加速する取引所間の競争の帰結、グローバルな調和と相互承認という考え方とIOSCOが担うことができる役割について議論しました。
パネル3 「金融コングロマリットに対するアプローチ」
1990年代後半以降、主要国の金融業界の再編が進み、いくつかの巨大な金融コングロマリット・グループが誕生しました。また、多くの国では、規制緩和を背景に、証券・銀行・保険の業態の垣根が低くなり、証券業の担い手は多様化し、クロスボーダーで活躍する金融機関が増加しています。
本パネルでは、グローバルなビジネスを展開する金融機関に対し、グループ内における統一されたリスク管理、コンプライアンス・利益相反の管理の際に直面する課題や、直近のサブプライム問題がこれらの管理体制に与えたインパクトなどが話し合われました。また、金融コングロマリットの形成が、世界的な傾向となりつつあるなかで、より有効となりえる規制制度は、欧州の一部及び日本のような銀行・証券・保険を一元的に監督する制度か、それとも米国やカナダのように業態・機能別の制度なのかについて、双方の制度に対する実務的な見解について議論が行われました。
パネル4 「規制当局間協力の新たな展開」
資本市場のグローバル化により、国境を越えた規制当局間の協力の強化が必要不可欠となっています。そのため、IOSCOは、そのメンバーに対し、法務執行分野における情報交換の枠組みである多国間MOU(情報交換取極め)への署名を促してきたところです。しかしながら、更なる規制当局間の協力が求められています。次なる協力分野は、監督上の情報を交換することや資産凍結・返還に関する協力等が考えられます。
本パネルでは、法務執行分野における情報交換及び情報交換を超える協力分野において、国境を越えた規制当局間の協力の必要性を議論し、その可能性を探りました。現行における情報交換の枠組みである二国間および多国間MOUにより、規制当局が必要とされる国際協力が可能となっているか、規制当局が国境を越えた法務執行事案に関し、相互に支援するための十分な手段を有しているか、また、規制当局がクロスボーダーで互いに規制を依存し合うために構築すべき重要要素について、議論が行われました。
パネル5 「オルタナティブ投資に対するアプローチ」
ヘッジファンドやプライベートエクイティなど、オルタナティブ投資市場は成長し続けており、規制上の課題としては、これらの多くが海外で設立・運営されるため、国内規制のみでは、非効率であり、効果的かつ公平な規制が行えない点などがあります。
本パネルでは、二つのセッションについて議論が行われました。第一セッションでは、ヘッジファンドに対する規制の是非や、複雑なグローバル資本市場のなかでの規制のあり方について話し合われ、第二セッションでは、主に流動性リスクや、ファンドのリテール化の是非について議論されました。前者については、米国サブプライム問題を発端とする市場の混乱から得た教訓や、ヘッジファンドの流動性リスクのあり方、投資家による解約リスクの管理のあり方、また、流動性の乏しいあるいは複雑な金融商品を評価する際の課題が話し合われました。後者については、ヘッジファンドへのアクセス手段を、主として高度な金融知識を有する投資家、あるいは適格投資家のみが持つことが、果たして公平か否かについて議論が行われました。
パネル6 クロージング・セッション「IOSCOの当面及び将来の課題」
コンファレンス最終日に行われた当パネルでは、IOSCOが今後直面する長期的・短期的な課題に関する議論が行われました。このうち長期的な事項については、市場規制間のコンバージェンスや競争が加速しつつある今日、規制当局関係者及び市場参加者が直面する課題について、前述の5つのパネルの総括を行われました。また、短期的な事項については、直近のサブプライム問題を踏まえ、市場の透明性や金融商品の評価手法について、また、投資銀行が果たした役割や格付機関の利益相反などについて議論されました。
最後は山本副大臣の閉会挨拶をもって二日間に亘る「IOSCO東京コンファレンス」の閉会となりました。

クロージングスピーチを行う山本副大臣
※詳しくは、金融庁ホームページの「大臣講話・講演等」から下記内容を、また、今号の【金融ここが聞きたい!】にアクセスしてください。
- IOSCO東京コンファレンス 山本副大臣閉会挨拶(平成19年11月9日)
- IOSCO東京コンファレンス 渡辺金融担当大臣基調講演(平成19年11月8日)
- IOSCO東京コンファレンス歓迎レセプション 佐藤金融庁長官挨拶(平成19年11月7日)英文
アクセスFSA第50号および第59号でもお知らせしましたが、金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会は平成20年1月4日(金)より、中央合同庁舎第7号館に移転いたします。
移転先の詳細は、次のとおりです。
| 区分 | 金融庁 | 証券取引等監視委員会 | 公認会計士・監査審査会 |
| 【郵便番号】 | 100-8967(変更なし) | 100-8922(新規) | 100-8905(新規) |
| 【電話番号】 | 03-3506-6000(代)(変更なし) | ||
| 【住所】 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 |
| 【移転日】 | 平成20年1月4日(金) |
| 【地図】 | 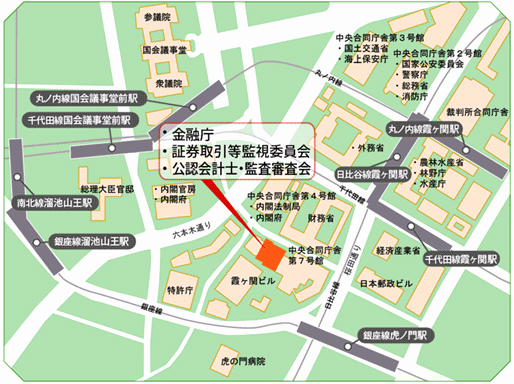 |
【お問い合わせ】総務企画局総務課管理室 TEL:03-3506-6000(代表)(内線3119、3414)
○ 全国一斉多重債務者相談ウィークについて(12月10日~16日開催)
内閣に設けられた「多重債務者対策本部」 |
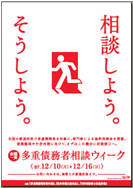 |

 検索
検索


