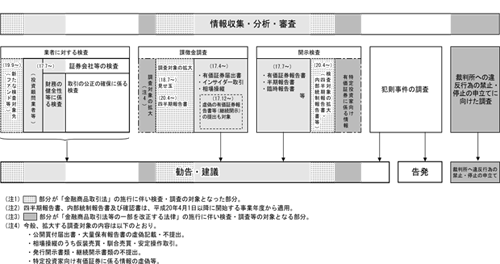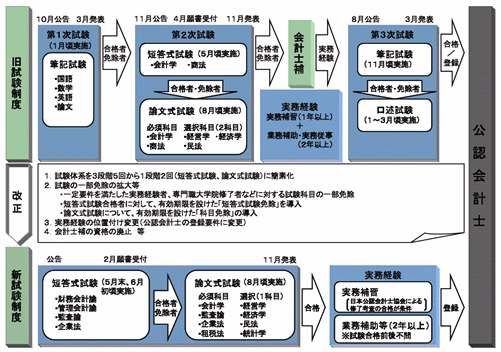アクセスFSA 第70号(2008年9月)
【トピックス】
中小企業金融の円滑化に向けた今後の対応について
1.はじめに
金融庁では、中小企業の業況が厳しい状況にあり、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が求められている状況の下、平成20年8月29日にとりまとめられた「安心実現のための緊急総合対策」
 に則り、9月2日、「中小企業金融の円滑化に向けた今後の対応について」を公表しました。
に則り、9月2日、「中小企業金融の円滑化に向けた今後の対応について」を公表しました。2.基本的考え方
我が国の景気は現状弱含んでおり、原油価格の動向等によってはさらに下振れするリスクが存在しています。中小企業の業況は厳しい状況にあり、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が求められています。
こうした状況の下、民間金融機関は、借り手企業の経営実態や特性に応じたリスクテイクとリスク管理をきめ細かく行い、中小企業に対する円滑な資金供給の確保と自らの財務の健全性の維持とが、好循環をもって実現していく状況を目指していくことが重要です。
地域金融機関は、特に地域密着型金融の一層の推進等を通じて、地域における適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮することが求められます。また主要行も、借り手企業の経営実態や特性を踏まえたきめ細かい融資判断を行い、それを顧客に対して十分に説明することが必要です。
3.具体的取組み
金融庁としては、以下の3項目に沿って、中小企業金融の円滑化に取り組んでいきます。
(1)きめ細かな実態把握と中小企業金融の円滑化に向けた監視の強化
- 商工会議所等へのアンケート調査を定期的に実施する。
- 地域の中小企業・金融機関等からの情報収集に努める。
- 中小企業金融の実態の監視を強化するため、「金融円滑化ホットライン」(電話番号:03‐5251‐7755)の一層の周知を図る。
- 関係省庁・機関との情報交換・連携を強化する。
(2)金融機関等への働きかけ
- 「安心実現のための緊急総合対策」を受け、主要行を含めた金融機関に対し、中小・零細企業に対する金融の円滑化を要請する文書を速やかに発出する。
- 地域密着型金融の取組みを一層積極的に推進する(取組み事例集の作成・公表、シンポジウムの開催、優秀事例の顕彰等)。
- 主要行に対しても、借り手企業の経営実態や特性を踏まえたきめ細かい融資判断を行い、それを顧客に対して十分に説明することを促す。
- 民間金融機関に対して、信用保証協会等と連携して中小企業に対する円滑な資金供給に努めるよう促す。
(3)実態を踏まえた適切な検査・監督行政の推進
- 今後の検査運営は、以下の方針に基づいて行うこととし、すべての検査官、金融機関、中小企業経営者等に徹底した周知・実践を図る。
»»中小企業の実態を踏まえた円滑かつ積極的な金融仲介機能が発揮できる態勢が構築されているかを重点的に検証する。
»»金融検査を質的に向上させ、重要な問題に焦点をあてた、金融機関の自主的な経営改善につながる「納得感」の高い検査を行う。
»»金融機関の規模・特性等に配慮し、検査負担の軽減を図る。
»»中小企業の特性を十分踏まえた評価を金融機関に促す金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の趣旨の周知・広報を徹底する。
- 中小企業への融資対応状況等について金融機関からのトップヒアリング等により確認する。その際、金融機関において、借り手企業の経営実態や特性を十分に踏まえ、実情に応じたきめ細かな融資判断を行い、それを顧客に対して十分に説明するよう、適切な対応を促していく。
- 中小企業の自己資本充実策や事業再生を支援するための制度的枠組みの整備を行う。
- 今後の検査運営は、以下の方針に基づいて行うこととし、すべての検査官、金融機関、中小企業経営者等に徹底した周知・実践を図る。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『中小企業金融の円滑化に向けた今後の対応について』(平成20年9月2日)にアクセスしてください。
| 平成20事務年度主要行等向け監督方針について 平成20事務年度中小・地域金融機関向け監督方針について 平成20事務年度保険会社等向け監督方針について 平成20事務年度金融商品取引業者等向け監督方針について |
金融庁では、主要行等、中小・地域金融機関、保険会社等、金融商品取引業者等の監督を行うにあたって、各事務年度の監督上の重点事項を明確化するため、年度当初に監督方針を策定・公表しています。
本事務年度は、9月5日に「平成20事務年度主要行等向け監督方針」「平成20事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」「平成20事務年度保険会社等向け監督方針」「平成20事務年度金融商品取引業者等向け監督方針」を策定・公表し、監督にあたって重点を置くべき分野等を示しました。
以下では、その概要を説明します。
1.はじめに
平成20事務年度監督方針の策定時点においては、サブプライム・ローン問題を契機とするグローバルな金融市場における緊張が続く中、景気は弱含んでおり、原油価格の動向等によってはさらに下振れするリスクが存在しています。
こうした環境において、
○主要行等は、金融の円滑化をはじめとした金融機能の十全な発揮に努め、預金者・借り手などの利用者の安心と利便の向上に寄与することが一層期待されます。金融機能の十全な発揮のためには、同時に主要行等が財務上の健全性を維持していることも重要であり、各行が質の高いリスク管理を定着させることが必要です。また、高度な金融機能の発揮に向けて、活力と競争を促すビジネス環境が整備され、それを主要行等が積極的に活用していくことも重要となります。
○中小・地域金融機関は、その金融機能を十全に発揮し、中小企業金融の円滑化や預金者などの利用者の安心と利便性の向上に寄与することが一層期待されています。金融機能の十全な発揮のためには、同時に自らの財務の健全性を維持していることも重要です。このため、地域金融機関においては、適切な経営管理の下、中小企業に対する円滑な資金供給の確保と財務の健全性の維持とが、好循環をもって実現していく状況を目指していくことが重要となっています。
○保険会社等は、契約者等の安心・利便の一層の向上の見地に立った業務運営を行い、国民生活の安定等に寄与していくことが期待されます。また、少子高齢化社会を迎えて、高齢者の医療や介護といった利用者ニーズに応えていくことも期待されます。保険会社等がその機能を十分に発揮し、契約者等に対する責任を的確に果たすためには、財務上の健全性を維持していることが重要であり、各社が質の高いリスク管理を行い、更にそれを向上させていくことが必要です。
○金融商品取引業者等は、金融商品取引法の下での対応を通じて、投資者の安心と利便を向上させるよう取り組むことが求められています。また、市場の担い手としての公共的な役割を自覚した業務運営を行い、信頼できる市場インフラの構築に貢献することも求められ、そのうえで、より質の高いサービスを提供するため、適切な内部管理態勢を構築しつつ、積極的な業務展開を行うことが期待されます。
こうした認識の下、本事務年度の監督方針においては、以下の分野に重点を置くとともに、これら諸課題について金融規制の質的向上の考え方を基本に取組みを進めていくこととしています。
2.重点分野
(1)主要行等
○金融機能の発揮と利用者の安心・利便
国民生活、そして経済活動を支える上で、金融の果たす役割は大きく、現下の経済情勢も踏まえると、主要行等が、創意工夫をこらした自主的な取組みにより、その金融機能を的確に発揮し、利用者の安心と利便の向上に寄与することが大切です。このことを踏まえ、以下の点に留意するものとしています。
- 金融の円滑化
- 資産運用ニーズへの対応
- 業務の継続性
- 金融機能の不正利用の防止
○リスク管理と金融システムの安定
内外の経済・市場環境が変化する中で、主要行等が、金融仲介機能を適切に発揮し続けるためには、適切な経営管理(ガバナンス)の下、質の高いリスク管理を定着させることが必要であり、それがひいては金融システムの安定にも寄与することとなります。このため、当局としても以下のような点に留意し、主要行等の自主的な取組みを促すこととしています。
- 証券化商品等に係るリスク管理の強化
- 収益基盤の充実
- リスク情報の開示の充実
- 国際的なフォーラムへの積極的な参加と情報収集・発信
○「市場強化プラン」に沿った取組み
当庁が昨年12月に公表した「市場強化プラン」は、我が国市場における金融サービス業の活力と競争を促し、内外の利用者にとっての我が国市場の魅力を高めるとともに、主要行等の海外展開にも資する内容となっています。本プランに沿った取組みの一環として、主要行等の監督に当たっても、以下の点に留意して、活力と競争を促すビジネス環境の整備に努めることとしています。
- 銀行グループの業務範囲拡大やファイアーウォール規制の見直し等
- 内外金融機関との対話の深化・充実
(2)中小・地域金融機関
○地域密着型金融の推進等を通じた中小企業金融の円滑化
中小企業の業況は厳しい状況にあり、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が求められている状況の下、借り手企業の経営実態や特性に応じたリスクテイクとリスク管理をきめ細かく行い、中小企業に対する円滑な資金供給の確保に努めていくことが重要となっています。地域金融機関においては、地域密着型金融の一層の推進等に努めていくことが重要であることを踏まえ、当局としても、以下の点に重点をおいて、中小企業金融の円滑化に向けた取組みを進めていくこととしています。
- 中小企業金融のきめ細かい実態把握と監視の強化
- 地域密着型金融の推進
○地域の利用者の安心と利便
地域の経済活動等を支える上で地域金融の果たす役割は大きく、その重要な担い手である地域金融機関においては、創意工夫をこらした自主的な取組みにより、地域の利用者の安心と利便性の向上に寄与することが大切です。こうした認識の下、以下の取組みに重点を置くこととしています。
- 資産運用ニーズへの対応
- 業務の継続性
- 金融機能の不正利用の防止
○リスク管理と地域における金融システムの安定
内外の経済・市場環境が変化する中で、地域金融機関が、金融仲介機能を適切に発揮し続けるためには、適切な経営管理(ガバナンス)の下、質の高いリスク管理を定着させることが必要であり、それがひいては地域における金融システムの安定にも寄与することとなります。このため、当局としても以下のような点に留意し、地域金融機関の自主的な取組みを促すこととしています。
- 適切なリスク管理
- 収益基盤の充実
(3)保険会社等
○契約者等の安心・利便の向上に向けた取組みの促進
平成17年以降、各保険会社において、保険金等の不適切な不払い等の問題が明らかとなっています。保険会社等が業務の適切性を自立的に確保し、契約者等の安心・利便の向上を図っていくためには、各保険会社等が適切な経営管理の下、自主的な業務改善に組織一体となって取り組んでいくことが重要であり、以下の点に留意した監督対応を行っていきます。
- 適切な保険金等支払管理態勢の構築
- 適切な保険募集態勢の確立
- 相談・苦情処理態勢の充実
○リスク管理の高度化の促進
金融サービス利用者のニーズが多様化し、金融市場が変動する中で、保険会社が様々なリスクを適切に把握し、契約者等に対する責任を的確に果たすためには、リスク管理の高度化による財務の健全性確保とその財務情報の適切な開示が必要です。このような点を踏まえ、具体的には、以下の点に留意した監督対応を行っていきます。
- サブプライム・ローン問題に関する教訓を生かしたリスク管理の高度化
- ソルベンシー評価の見直し
- 統合的リスク管理の推進
○保険会社等の属性に応じた監督対応
保険会社等の業務規模は、大規模のものから少額短期保険業者のような総じて小規模のものまで多様です。また、保険募集の形態も募集人・代理店を中心とするものや、通信販売を中心とするものなど多様化しています。このような状況を踏まえ、保険会社等の業務規模・態様等の属性に応じた監督対応を行っていきます。
- 保険会社グループ等への対応
- 少額短期保険業者への対応
- 特定保険業者への対応
- 保険募集形態の特色に応じた対応
(4)金融商品取引業者等
○投資者の安心・利便の向上
「貯蓄から投資」の流れを加速するためには、一般の投資者が安心して投資に参加できる環境を整備することが前提となります。金融商品取引法の適切な運用、各業者の財務の健全性の確認及び不適格業者への厳正な対応により、こうした環境の整備に取り組むため、以下の点に留意するものとしています。
- 金融商品取引法の定着
- 不適格業者の排除
- 投資者財産の適正管理
○信頼できる市場インフラの構築
我が国市場の競争力強化に向けて、市場の公正性・透明性を確保し、市場に対する信頼を強固なものとするよう取り組みます。そのうえで、多様な取引を円滑・確実に行うことができる、安全性・利便性の高い市場インフラの整備を図っていくために、以下の点に留意するものとしています。
- 株券電子化の円滑な実施
- 市場仲介者としての公共的役割の発揮
- 自主規制機能の一層の強化
○業務の多角化・高度化・国際化と適切な内部管理態勢の構築等
市場強化プランを踏まえ、活力のある市場の構築に向けて、各業者が自らの創意工夫により、より質の高いサービスを提供できるような環境を整備することが必要です。各業者の経営戦略を注視し、業務の多角化・高度化・国際化の状況を把握したうえで、適切な内部管理態勢が構築されているかを確認するため、以下の点に留意するものとしています。
- ファイアーウォール規制見直しへの対応
- 積極的な業務展開と適切な内部管理
- 積極的な業務展開に対応したリスク管理
- 証券化商品の適切なリスク評価・情報開示の強化
- 各種ファンドへの対応
3.金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション)の浸透と具体化
我が国市場の国際的な競争力を強化するためには、金融規制の質的向上が重要な課題となります。また、我が国の金融セクターは、金融システムの安定、利用者の保護、公正・透明な市場の確立と維持に向けたこれまでの取組みを定着させ、更に深化させるべき局面を迎えており、金融規制も、金融機関の自助努力や創意工夫を重視していく必要があります。
こうした状況を踏まえ、平成20事務年度の諸課題にも、ベター・レギュレーションの考え方を基本に取り組み、ベター・レギュレーションの考え方を監督部局全体に定着させ、4つの柱に以下のような形で取り組むことにより、その浸透と具体化を図っていくこととしています。
- ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な組合せ
- 優先課題の早期認識と効果的対応
- 自助努力の尊重とインセンティブの重視
- 行政対応の透明性・予測可能性の向上
なお、こうした取組みの実効性を高めるため、専門的人材の育成・確保や研修の充実などを通じ、職員の資質向上に努めるものとします。
金融庁では、以上のような監督方針に基づいて、本事務年度も引き続き、主要行等に対して、金融機関の自助努力や創意工夫を重視しつつ、実効性のある監督行政を効率的に遂行していきます。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から
「平成20事務年度主要行等向け監督方針について」(平成20年9月5日)
「平成20事務年度中小・地域金融機関向け監督方針について」(平成20年9月5日)
「平成20事務年度保険会社等向け監督方針について」(平成20年9月5日)
「平成20事務年度金融商品取引業者等向け監督方針について」(平成20年9月5日)
にアクセスしてください。
振り込め詐欺対策についての意見交換の実施について
9月16日に、警察庁、金融庁及び全国銀行協会との間で、振り込め詐欺の被害が急増している現状を踏まえ、意見交換を行いました。そこでは、警察庁刑事局長、当庁監督局長及び全国銀行協会会長から振り込め詐欺撲滅に向けた取組みについてそれぞれ説明を行い、今後の取組みも含めた意見交換を行いました。
その結果、10月を「振り込め詐欺対策強化月間」とし、警察庁、金融庁及び全国銀行協会が協力して振り込め詐欺対策を進めていくこととしました。
当庁においては以下のような取組みを行います。
○警察庁との合同による振り込め詐欺の未然防止等についての政府広報
○金融団体との意見交換の機会を活用し、ATM関連の対策等についての取組みの働きかけ
当庁としては、振り込め詐欺が金融機関を悪用する犯罪であることから、警察庁や全国銀行協会等と連携しつつ、振り込め詐欺防止のための取組みにさらに努めていきます。

握手する(左から)米田警察庁刑事局長、杉山全国銀行協会会長、三國谷監督局長
平成21年度税制改正要望について
去る9月1日、金融庁は「平成21年度 税制改正要望」を財務省及び総務省に提出しました。
本年は、 我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて、
1.「貯蓄から投資へ」の流れの促進
2.内外投資活動の推進のための環境整備
のために必要な税制上の措置を要望しています。
1.「貯蓄から投資へ」の流れの促進の観点からは、
○『日本版ISA』(小口の継続的長期投資非課税制度)の創設(小口で継続的に長期投資を通じた資産形成を行うことにより、小口投資家を育成していくために要望するもの)
○高齢者投資非課税制度の導入(60歳以上の高齢者が金融資産全体の6割を保有しており、株式や投信等でみると7割に及んでいること、そして近年は利子所得が低金利の下で減少しており、特に高齢者の家計にとっては配当所得が非常に増加して、これが「第2の年金」という重要性をもってきていることから、高齢者の老後の安心のために要望するもの)
○証券税制の特例措置における投資家利便への配慮
○確定拠出年金(401k)制度の充実
○金融商品間の損益通算の範囲拡大
等を要望しています。
2.内外投資活動の推進のための環境整備の観点からは、組合型投資ファンド課税(1号PE)の見直し等を要望しています。
本要望は、海外の投資家が日本の組合型ファンドに投資を行った場合に、当該海外投資家が日本で申告義務を負うこととならないよう見直しを要望するものです。
なお、日本の投資運用業者に投資を一任する場合にも同様の問題がありましたが、これについては20年度税制改正において措置されました。
その他、保険契約者の自助努力を支援する観点から、生命保険料控除制度等の見直しを要望しています。
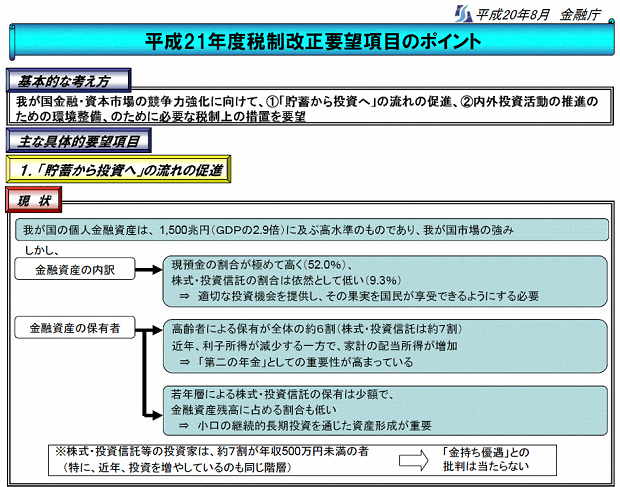 |
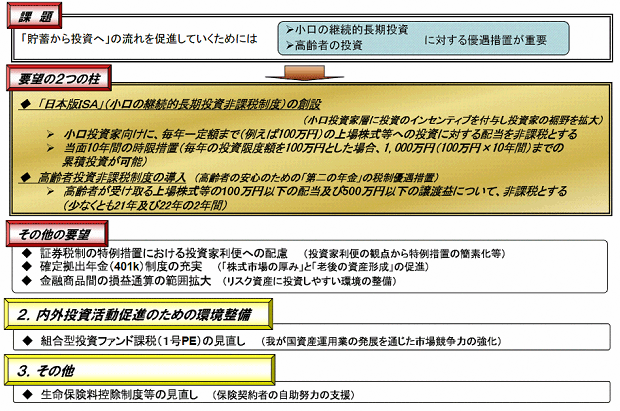 |
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「平成21年度 税制改正要望」について(平成20年8月28日)にアクセスしてください。
平成21年度機構・定員及び予算要求について
1.はじめに
サブプライム・ローン問題を契機として、海外監督当局とのより緊密な連携が不可欠になってきている状況等を踏まえ、その対応体制の強化等を図るとともに、金融システムに内在する市場リスク等各種のリスクを早期に認識・抽出し、的確に対応できるよう体制の充実・強化を図ることが必要です。
また、市場競争力の強化という観点も踏まえ、市場監視体制の強化や、多様な資金運用・調達機会の提供等を推進するための体制整備を図ることが重要です。
さらに、金融サービス利用者保護施策の推進等を図るとともに、利用者の利便性向上、業務効率化のための情報システムの整備を図ることが必要となっています。
金融庁では、これらの課題に対応するための諸施策等を実施するために必要な機構・定員及び予算要求を行っています。
2.機構・定員要求の内容
(1)海外監督当局等との連携強化のための体制整備
サブプライム・ローン問題を契機とした世界的な金融市場の混乱が続いている中、海外監督当局とのより緊密な連携が不可欠になってきている状況、国際会議における積極的な貢献がより重要となってきている状況等を踏まえ、国際的な対応体制を充実・強化することとしています。
(2)金融システムに内在するリスクを早期に認識し、的確に対応するための体制整備
サブプライム・ローン問題に見られるように、グローバルな経済や金融・資本市場の動向が金融システムの安定に大きな影響を与えうること等を踏まえ、金融システムに内在する市場リスク等各種のリスクを早期に認識・抽出し、的確に対応できるよう体制の充実・強化を図ることとしています。
(3)市場強化のための体制整備
「骨太の方針2008」に掲げられた「市場強化プラン」を着実に推進し、信頼と活力のある市場を構築するため、以下の体制整備を図ることとしています。
○市場監視体制強化のための体制整備
投資家が安心して市場に参加するために不可欠な市場の信頼性を確保するため、証券取引等監視委員会の体制整備等をはじめとする市場監視体制の強化を図ることとしています。
○多様な資金運用・調達機会の提供等を推進するための体制整備
取引所における取扱商品の多様化を図るとともに、これに対応した取引所監督体制を充実する等、多様な資金運用・調達機会の提供等を可能とするための体制を強化することとしています。
(4)金融サービス利用者保護施策推進等のための体制整備
改正貸金業法の円滑な実施のための体制整備等、金融サービス利用者保護の充実・強化を図るために必要な体制等を強化することとしています。
これらの体制整備のため、総務企画局65人、検査局18人、監督局42人、証券取引等監視委員会60人、公認会計士・監査審査会10人、総計195名の増員要求を行っています。
(参考 平成21年度定員要求)
(単位:人)
18年度末
定員19年度末
定員20年度末
定員21年度
増員要求20年度
増員要求
(増員数)総務企画局 304 296 314 65 48(15) 検 査 局 454 451 441 18 22(9) 監 督 局 221 238 253 42 34(18) 証券取引等
監視委員会318 341 358 60 80(22) 公認会計士・
監査審査会43 47 51 10 11(5) 総 計 1,340 1,373 1,417 195 195(69) 3.予算要求の内容
平成21年度予算要求については、
(1)海外監督当局等との連携強化や、金融システムに内在するリスクを早期に認識し、的確に対応するための体制整備等のための増員(195人)に必要な経費のほか、
(2)海外当局との連携強化(海外監督当局への職員派遣等)に必要な経費や、
(3)市場強化(市場監視体制の強化等)に必要な経費及び
(4)利用者の利便性向上、業務効率化のための情報システム整備等(有価証券取引等電子開示システムの運用・改善等)に必要な経費などを織り込み、
総額で約231億円の要求を行っています。
なお、預金保険機構に係る政府保証枠については、金融システムの安定を引き続き揺るぎないものとするとの考え方に基づき40.2兆円を要求しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「平成21年度機構・定員及び予算要求について」(平成20年8月28日)にアクセスしてください。
「平成19年度実績評価書」、「平成20年度事業評価書」及び「平成20年度総合評価書」の公表について
1. はじめに
金融庁においては、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、
(1)国民に対する金融行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること
(2)国民本位の効率的で質の高い金融行政を実現すること
(3)国民的視点に立った成果重視の金融行政を実現すること
を目指しています。
これまで金融庁においては、金融庁設置法で定めた法定任務(金融機能の安定、預金者・保険契約者・投資者等の保護、円滑な金融)について、政策評価に係る基本計画や実施計画などを策定の上、政策評価に鋭意取り組んでおり、実績評価に関しては、平成13年度(13年7月~14年6月)以降、毎年度を対象とする実績評価書を作成・公表しています。
また、政策評価をより一層予算に活用するとの観点から、平成15年度以降、毎年度、予算措置を伴う事業のうち新規あるいは拡充を予定している主なものを対象として事業評価(事前評価)を実施するとともに、過去に事業評価(事前評価)を実施し、効果が発現した事業のうち主なものを対象として事業評価(事後評価)を実施することとし、事業評価書を作成・公表しています。
加えて、今年度は、日本版ビッグバン以降の金融システムの改革に関する金融庁のこれまでの一連の施策を振り返りながら、その評価を行うことを目的として金融システム改革(日本版ビッグバン)についての総合評価書を作成・公表しています。
【参考】
政策評価とは、各府省が自らその政策の効果を把握・分析し、評価を行うことにより、次の企画立案や実施に役立てるものです。
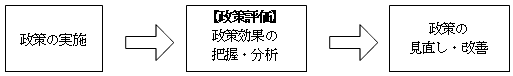
なお、政策評価には以下の3つの方式があります。
○実績評価方式
政策を決定する際に、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、目標期間が終了した時点で、目標の達成度合いについて評価する方式。
○事業評価方式
政策を決定する前に、あらかじめ期待される政策効果等を推計・測定し、政策目的が妥当か、行政が担う必要があるか、費用に見合った効果が得られるかなどの観点から評価する方式(必要に応じ事後の時点で、事前の時点に行った評価内容を踏まえ検証)。
○総合評価方式
政策の決定から一定期間を経過した後に、特定のテーマについて、政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式。
2.平成19年度実績評価書の内容
今回は、平成19年度(19年7月~20年6月)を対象とする政策評価実施計画に定めた25の政策について、実績評価を実施しました。
具体的には、金融庁が法定任務を遂行していくための25の政策について予め目標を定め、それぞれ目標の達成に向けて行った業務内容等を分析し、各政策の評価を行いました。なお、「端的な結論の基本類型」を参考にしつつ、各政策の状況を踏まえ必要に応じて補足説明を加えて端的な結論を記載しているほか、指標等に照らした当該年度の目標の達成度を3段階(A、B、C)で評価しています。
3.平成20年度事業評価書の内容
今回は、情報等の分野の事業で、平成21年度に予算措置を伴う事業のうち新規あるいは拡充を予定している主なものを対象に、事業評価(事前評価)を実施したほか、過去に事業評価(事前評価)を実施し、効果が発現した事業のうち主なものを対象に、事業評価(事後評価)を実施しました。
事業評価(事前評価)の実施に当たっては、事業の目標、目的及び内容を明らかにし、事業評価(事後評価)の実施に当たっては、具体的成果を踏まえ、いずれも、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を行っています。
4. 平成20年度総合評価書の内容
金融システム改革(日本版ビッグバン)の総合評価の実施に当たっては、フリー・フェア・グローバルの3原則及び金融システム複線化の観点から、それぞれの政策効果の発現状況等について分析するとともに、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を行っています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「平成19年度実績評価書」、「平成20年度事業評価書」、及び「平成20年度総合評価書」の公表について(平成20年8月29日)にアクセスしてください。
証券取引等監視委員会の事務処理状況の公表について
1. はじめに
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、金融庁設置法第22条の規定に基づき、毎年、事務処理状況を公表しており、本日、平成19年7月1日から同20年6月30日までの期間(以下「平成19事務年度」といいます。)における事務の処理状況を「証券取引等監視委員会の活動状況」として公表しました。なお、今回の公表は、証券監視委発足後16回目となります。
2. 概要
金融システム改革をはじめとする様々な改革の成果や情報技術(IT)の進展などを受けて、インターネット取引やクロスボーダー取引の増加、投資ファンド等を使った複雑な取引の増加など、金融・資本市場を取り巻く環境は大きく変化しています。
こうした中、市場監視機能の充実・強化も行われてきており、中でも、平成17年には、従来からの犯則事件の調査や証券会社等の取引の公正確保に係る検査に加え、新たに導入された課徴金調査のほか、開示検査、証券会社等の財務の健全性等に係る検査及び投資信託委託業者・投資顧問業者等に対する検査の権限も証券監視委に委任され、また、新たに外国為替証拠金取引を扱う業者が金融先物取引業者として検査の対象となるなど、証券監視委の検査範囲は大幅に拡大されました。
さらに、同19年7月には、新たに委員長及び両委員が就任し、中期的な活動方針である「公正な市場の確立に向けて」を公表し、近年の金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対して、機動性・戦略性の高い市場監視の実現と市場規律の強化に向けた働きかけの2本柱を掲げ、その使命達成に向けて取り組んでいるところです。
(市場分析審査)
平成19事務年度中に投資者など一般から受け付けた情報は5,841件となっています。
また、平成19事務年度の取引審査件数は、合計1,098件であり、前事務年度と比較すると59件増加しており、平成4年の発足以来最高の審査件数となっています。
さらに、直ちに法令違反とはいえないような取引についても幅広く注意を払っているほか、個別取引や市場動向の背景にある問題を重点的に分析する等、包括的かつ機動的な市場監視に努めています。
(証券検査)
証券検査については、発足以来最多となる219社の検査を終了し、問題点が認められた122社のうち、28社について行政処分等の勧告を行いました。特に、平成19事務年度は、検査対象先等に関する様々な資料・情報等を総合的に勘案して実施する一般検査に加え、市場をめぐる問題や関心事項について横断的なテーマを選定し、共通の課題がある検査対象先に対して行う特別検査を実施しました(OHT株式の信用リスクに係る証券会社のリスク管理態勢等の検証、外国為替証拠金取引業者の財務の健全性並びにリスク管理等に重点を置いた検証等)。
(不公正取引に対する勧告・告発)
不公正取引に対する勧告については、21件の課徴金納付命令(いずれも内部者取引に関するもの)の発出を求める勧告を行いました。この中には、公認会計士が監査の過程で知った監査先企業の内部情報を利用して取引を行ったもの(新日本監査法人職員による内部者取引)や、報道機関の職員が情報端末に入力された放送用原稿を閲覧したことにより重要事実を知り公表前に取引を行ったもの(NHK職員による内部者取引)など、上場会社の重要情報を知り得る立場にある者の職業倫理やその所属する法人等の情報管理体制にも問題があるような事例も見受けられました。
不公正取引に対する告発については、風説の流布及び偽計の嫌疑で2件、相場操縦の嫌疑で4件、インサイダー取引の嫌疑で2件の合計8件の告発を行いました。この中には、アイ・シー・エフ株取得に係る偽計事件において、大阪府警察本部と合同で強制調査を実施したものなど、事件の状況に応じて他の捜査機関と連携を図りつつ、効果的・効率的な調査の遂行に努めました。
(ディスクロージャーに関する勧告・告発)
ディスクロージャーに関する勧告については、平成20年6月19日に、課徴金額の過去最高額である15億9,457万9,999円の課徴金納付命令勧告(株式会社IHIに係る有価証券報告書等の虚偽記載)を行うなど、開示書類の虚偽記載に関して10件の課徴金納付命令の発出を求める勧告を行いました。
ディスクロージャーに関する告発については、虚偽の有価証券報告書等の提出につき2件・9名(アクセス事件、アイ・エックス・アイ事件)について、証券取引法に違反するとして告発を行いました。
(建議)
建議については、平成19事務年度の実績はないが、金融審議会において、課徴金制度の実施状況・運用実績を踏まえ、課徴金額の水準の引上げなどについて意見を述べました。これを踏まえ、これらの内容の盛り込まれた改正金融商品取引法が、平成20年6月6日に成立しており、建議を行うのと同様の効果を得ています。
◆証券監視委の活動状況
| 区分 | H4~14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犯則事件の告発 | 53 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 108 | |
| 勧告 | 244 | 26 | 17 | 39 | 43 | 59 | 428 | |
| 証券会社等に対する処分に係る勧告 | 244 | 26 | 17 | 29 | 28 | 28 | 372 | |
| 課徴金納付命令に関する勧告 | 9 | 14 | 31 | 54 | ||||
| 訂正報告書等の提出命令に関する勧告 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 問題点が認められた会社数* | 686 | 67 | 67 | 93 | 142 | 121 | 1,176 | |
| 建議 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
(事務年度:7月~翌年6月)
※ 「問題点が認められた会社数」とは、証券検査の検査結果通知書において問題点を指摘した会社の数をいいます。
※ 「問題点が認められた会社数」とは、証券検査の検査結果通知書において問題点を指摘した会社の数をいいます。
※ 詳しくは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「年次公表」から「平成19年度版年次公表」(平成20年8月28日)にアクセスしてください。
1-2 証券取引等の監視体制の概念図
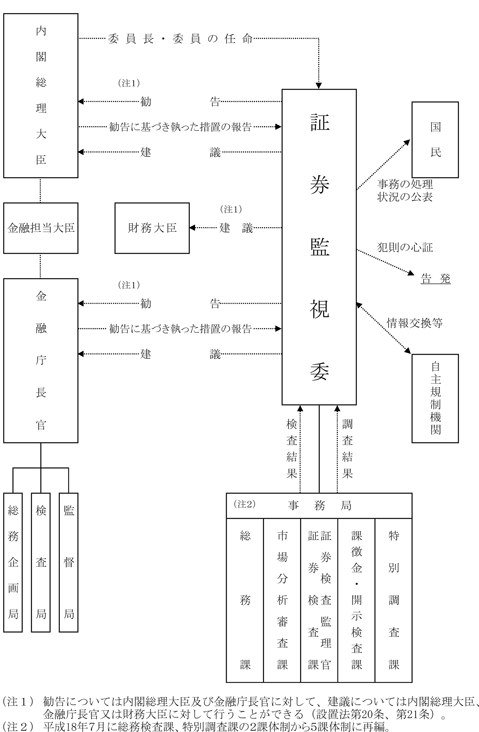
1-3 証券監視委の機能強化
1-4 証券監視委と内閣総理大臣、金融庁長官及び財務局長等の関係の概念図
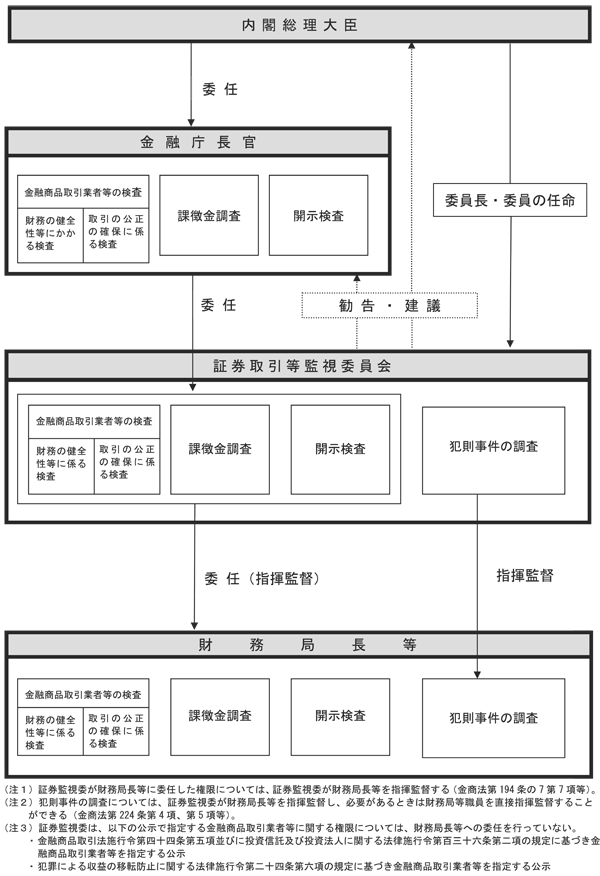
公認会計士・監査審査会の活動状況(平成19事務年度版)の公表について
公認会計士・監査審査会は、毎事務年度終了後、当該事務年度における活動状況を公表することとしていますが、今般平成19事務年度(平成19年7月~平成20年6月)における活動状況を取りまとめ、平成20年8月29日に公表しました。その概要は以下のとおりです。
● 品質管理レビューに対する審査及び検査
平成19事務年度は審査会の第2期(平成19~21事務年度)の初年度にあたりますが、第1期(平成16~18事務年度)における実績を踏まえ、これまでに指摘した監査事務所における品質管理上の問題に対する改善が各監査事務所において確実に定着するよう努めているところです。
具体的には、平成18年度及び平成19年度の日本公認会計士協会の品質管理レビューについて審査を行い、11監査事務所に対し検査を実施しました。その結果、5監査事務所について行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に対して勧告しました。
また、監査の質の維持・向上を図るための監査事務所による自主的な取組みを促すため、これまでに実施した検査における指摘事項の中から、品質管理の向上を図っていく上で有益であると考えられるものを「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」として取りまとめ、平成20年2月に公表しました。この内容については、全国各地の公認会計士協会地域会において説明会を開催しています。
● 公認会計士試験の実施
平成19年試験(短答式試験、論文式試験)及び平成20年試験(短答式試験)を実施しました。
また、審査会の下に公認会計士試験実施検討グループを設置し、公認会計士試験の実施面での改善に向けた検討を行い、その結果を踏まえ、審査会は「公認会計士試験実施の改善について」を平成19年10月に公表しました。
平成20年試験では、短答式試験においては従来の2週間の週末にわたる2日間を週末1日に短縮し、また、論文式試験においては法令基準等を配布する科目を2科目から5科目に増やすなど、改善策を順次実施しているところです。
※ 平成22年試験から短答式試験の実施を年2回に増やす予定です。
● 諸外国の関係機関との協力
諸外国の監査監督機関相互の情報交換等を目的として、監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)が平成19年3月に設立されていますが、第2回会合が平成19年9月にトロントで、第3回会合が平成20年4月にオスロで開催されています。審査会からは会長、常勤委員等が出席し、同フォーラムに積極的に貢献しているところです。
※ 詳しくは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「年次公表」から「平成19事務年度版[平成19年7月~平成20年6月](平成20年8月29日公表)」にアクセスしてください。
【公認会計士試験制度改正の概要】

 検索
検索