アクセスFSA 第89号(2010年11月)


JVC・ケンウッド・ホールディングス(株)に係る有価証券報告書等の
虚偽記載事件に係る第1回審判の模様(7号館15階金融庁大審判廷にて)
(10 月27 日)
【特集】
総合的な取引所検討チームの発足について
新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)においては、21の「国家戦略プロジェクト」の一つとして「総合的な取引所(証券・金融・商品)の創設の推進」が盛り込まれました。金融庁、農林水産省、経済産業省(以下「関係省庁」)は、その具体化に向け、第2回新成長戦略実現会議(10月8日開催)に提出された「21の『国家戦略プロジェクト』における年内の作業工程表」にて、10月中に検討の場を設け、本年中に中間整理を行い、中間整理に基づき必要が認められれば次期通常国会での法案提出を検討する旨、明らかにしたところです。
今般、この「検討の場」として、関係省庁の副大臣・大臣政務官で構成する「総合的な取引所検討チーム」を立ち上げ、下記の基本的な視点に基づき、関係者から公開で行うヒアリングのほか、意見交換を通じて検討を進めることとし、第1回会合を10月28日に開催し、以降順次開催しているところです。
総合的な取引所創設を促す制度・施策の検討に当たっての視点
1.総合的な取引所を創設するメリット、及びその実現を通じた新成長戦略の目標年である2020 年におけるアジアのメインマーケットとしての地位の確立とは、具体的にどのようなものか。
2.1.と対比して、現状の問題点は何か。例えば、本年、取引所間競争を促進するための証券・金融と商品との相互乗入れが可能となったが、その動きが具体化してこない理由は何か。
3.総合的な取引所の創設を促す制度・施策は何か。なお、その際、以下のような観点からの検討も行うこととする。
‐ 投資家・利用者の保護を図りつつ、市場参加者や一般投資家の参入を増加させるために何をすべきか。
‐ 商品の公正な価格形成とリスクヘッジの場として機能する産業インフラとしての取引所の国際競争力を維持強化するためには何をすべきか。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「総合的な取引所検討チームの発足について」(平成22年10月28日)にアクセスしてください。
また過去の検討チームにおける議事概要は「第2回総合的な取引所検討チーム(議事概要)」(平成22年11月9日開催)、「第3回総合的な取引所検討チーム(議事概要)」(平成22年11月19日開催)にアクセスしてください。
「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」の策定について
金融庁では、新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)工程表において「2010年度に実施する事項」とされている「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」の策定につき、検討を進めてきました。
その上でアクションプランの策定作業を本格化する段階に至ったため、その進め方を公表することとし、10月8日に「「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」の策定について」を公表しました。今後、公表された方針に沿って作業を本格化させることとしています。
我が国の成長戦略において金融は、(1)実体経済、企業のバックアップ役としてそのサポートを行うこと、(2)金融自身が成長産業として経済をリードすること、という2つの役割を果たしていくことが重要です。
金融庁としては、我が国金融が上記の2つの役割を適切に果たすための環境を整備するため、今後実施していく施策をまとめたアクションプランを、年内を目途に取りまとめる予定です。下記の検討項目を中心に、新成長戦略に掲げられた考え方を踏まえながら、各方面の関係者から適宜意見を聴取しつつ、工程表に掲載されている施策の具体化とともに、経済成長の実現に資する新たな施策の検討を進めることとしています。
アクションプランの検討項目
(1)企業の規模・成長段階に応じた適切な資金供給
- 中小企業等に対するきめ細かで円滑な資金供給
(地域密着型金融の促進(価値創造型の金融仲介機能の発揮等)等) - 新興企業等に対する適切な成長資金の供給
(新興市場等の信頼性回復・活性化、将来の成長可能性を重視した金融機関の取組促進等) - 大企業等に対する機動的な資金供給
(プロ向け社債発行・流通市場等)
(2)アジアと日本とをつなぐ金融
- アジアの主たる市場(メイン・マーケット)たる日本市場の実現
(総合取引所、英文開示の範囲拡大、四半期報告の大幅簡素化、プロ向け投資運用業、コーポレートガバナンスの強化、クロスボーダー取引に係る税制措置等) - 我が国金融機関のアジア域内での活動拡大
(アジア諸国の金融規制に係る政策協調推進、保険会社の海外不動産投資に係る規制の見直し等)
(3)国民の資産を有効に活用できる資産運用
- より質が高く、安心できる資産運用のための環境整備
(金融・証券税制(証券軽減税率の延長等)、プロ向け投資運用業(再掲)、金融ADR(裁判外紛争解決)制度の着実な実施等)
こうした作業を踏まえて、いずれかの段階で検討状況を公表し、必要に応じ、各方面の関係者からさらに意見を聴取したうえで、アクションプランとして取りまとめる予定です。
金融庁としては、このような金融分野の取組みを通じ、我が国の経済成長に積極的に貢献していきたいと考えています。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」の策定について(平成22年10月8日)にアクセスしてください。
【トピックス】
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について
中小企業金融の実態把握の一環として、平成22年8月に、全国の財務局等を通じて、商工会議所及び経営指導員等を対象に聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は以下のとおりとなりました。
1.中小企業の業況等に関するアンケート調査
○ 各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施しました。
(1)中小企業の業況感は、厳しい状況が続いています。
悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「販売価格の下落」が続いています。なお、前回調査に比べ、製造業において「為替市場等の変動の影響」の割合が上昇しています。
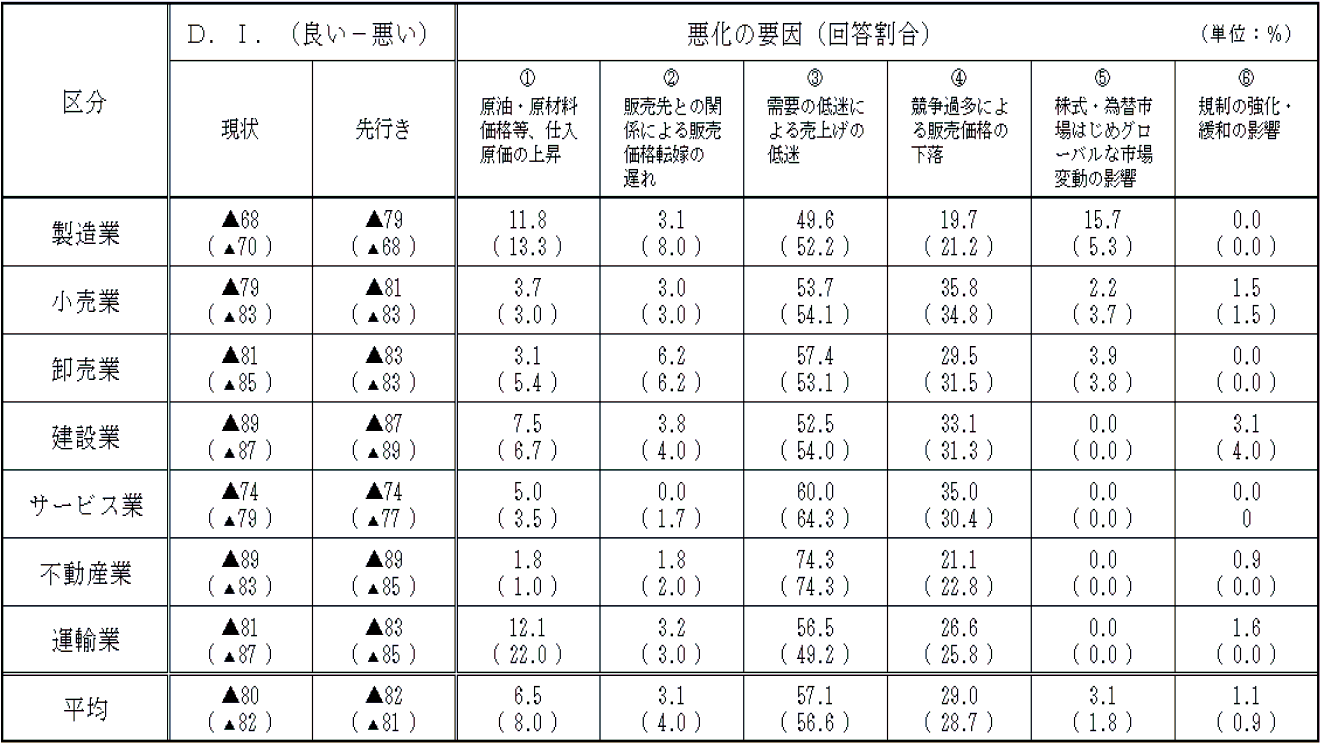
(注1)D.I. = 「良い」と回答した先数構成比 - 「悪い」と回答した先数構成比
(注2)悪化の要因については、複数回答可としている。
(注3)表中の括弧書は22年5月時点の調査結果
(2)中小企業の資金繰りについても、厳しい状況が続いています。
悪化の要因としては、「中小企業の営業要因」の割合が最も大きくなっています。
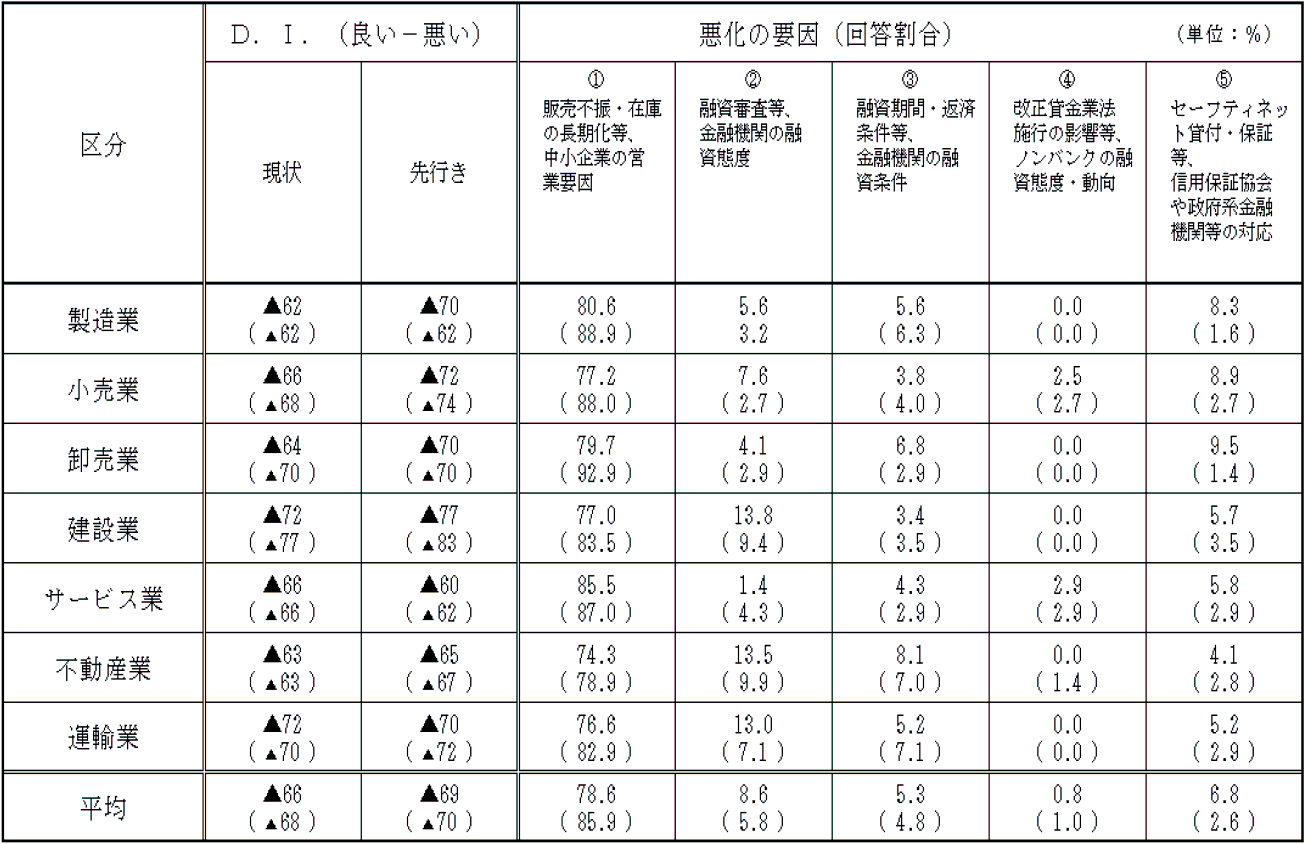
(注1)D.I. = 「良い」と回答した先数構成比 - 「悪い」と回答した先数構成比
(注2)悪化の要因については、複数回答可としている。
(注3)表中の括弧書は22年5月時点の調査結果
2.金融機関の融資動向等に関するアンケート調査
○ 各地域の商工会議所・商工会の経営相談員等596名を対象に、中小企業への融資姿勢に対する評価、金融庁施策の認知状況等について聴き取り調査を実施しました。
(1)中小企業への融資姿勢に対する評価について
- 積極的評価(「積極的である」及び「やや積極的である」の合計の割合)は、全業態合計で60.5%となっています。
- 消極的評価(「消極的である」及び「やや消極的である」の合計の割合)は、全業態合計で10.4%となっています。
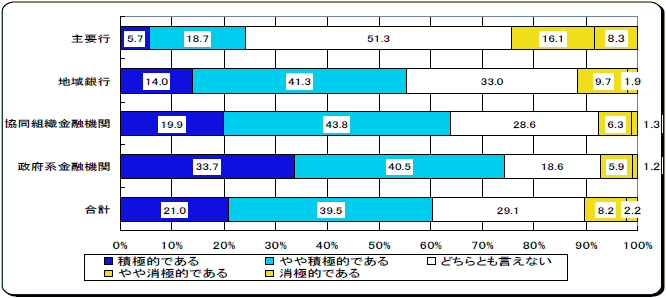
(2)中小企業に対する貸付条件の変更等への対応に関する評価について
- 積極的評価は全業態合計で65.3%となっています。
- 消極的評価は全業態合計で4.1%となっています。
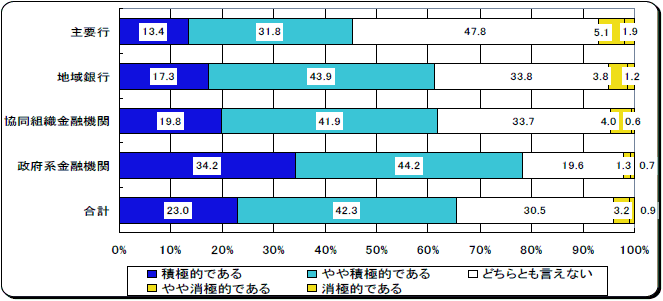
(3)金融機関における貸付条件の変更等に係る苦情相談への対応状況に関する評価について
- 積極的評価(「十分に対応している」及び「概ね十分である」の合計の割合)は、全業態合計で33.9%となっています。
- 消極的評価(「やや不十分である」及び「不十分である」の合計の割合)は、全業態合計で4.4%となっています。
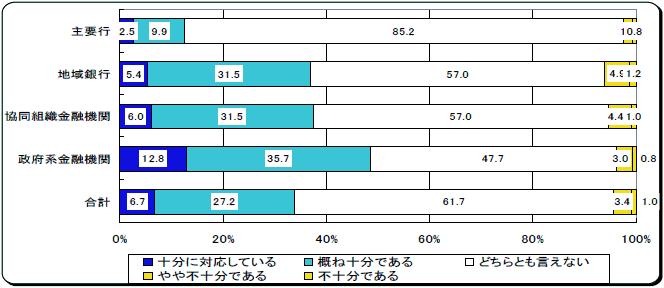
(4)中小企業に対するコンサルティング機能発揮に向けた取組み姿勢に対する評価について
- 積極的評価(「積極的である」及び「やや積極的である」の合計の割合)は、全業態合計で39.6%となっています。
- 消極的評価(「消極的である」及び「やや消極的である」の合計の割合)は、全業態合計で15.5%となっています。
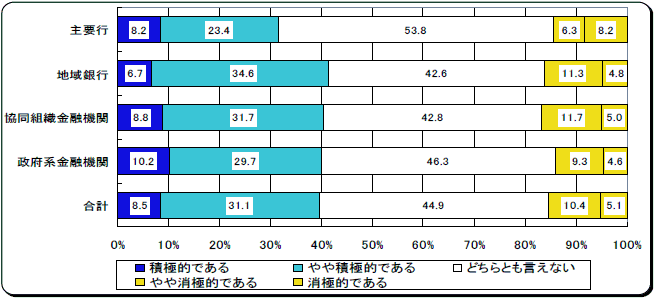
(5)金融庁施策の認知状況について
- 貸出条件緩和債権に該当しない場合の取扱いの拡充 94.8%
- 金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の内容 96.3%
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から中小企業金融に関するアンケート調査結果の概要(平成22年10月1日)にアクセスしてください。
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
金融庁では、預貯金者保護法の実施状況等を把握するため、偽造・盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪について、22年6月期までの被害の発生状況及び金融機関による被害者への補償状況を取りまとめ、10月20日(水)に公表を行いました。
<被害の発生状況及び補償状況の概要>
(1)偽造キャッシュカードによる被害発生件数は、22年度第1四半期(4~6月)では43件、対象期間累計(12年4月~)では3,617件となっています。対象期間における金融機関の補償率については、処理方針決定済みの件数ベースで98.7%となっています。
(2)盗難キャッシュカードによる被害発生件数は、22年度第1四半期(4~6月)では1,316件、対象期間累計(17年2月~)では30,997件となっています。対象期間における金融機関の補償率については、処理方針決定済みの件数ベースで83.9%となっています。
(3)盗難通帳による被害発生件数は、22年度第1四半期(4~6月)では37件、対象期間累計(15年4月~)では2,319件となっています。対象期間における金融機関の補償率については、処理方針決定済みの件数ベースで42.1%となっています。
(4)インターネットバンキングにおける被害発生件数は、22年度第1四半期(4~6月)では12件、対象期間累計(17年2月~)では590件となっています。対象期間における金融機関の補償率については、処理方針決定済みの件数ベースで85.2%となっています。
(注1)上記の補償率は、処理方針決定済みの件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合のものです。
(注2)被害発生件数等は、発生翌月15日までに各金融機関から報告された被害を取りまとめた速報値であることから、今後変動する可能性があります。
金融庁としては、引き続き、犯罪手口の多様化等を踏まえた情報セキュリティ対策の向上及び適切な顧客対応が図られるよう、金融機関の取組みを注視してまいります。
また、依然として、偽造・盗難キャッシュカード犯罪等が多数発生していることから、預貯金者の皆様におかれましては、自らも防犯対策に努めて頂きますようお願いいたします。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」(平成22年10月20日)にアクセスしてください。
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしており、その情報提供件数等について、四半期毎に公表しています。
これによると、調査を開始した平成15年9月以降、本年9月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において、29,749件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。
また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、本年9月30日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、16,048件の利用停止、11,042件の強制解約等を行っています。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」(平成22年10月29日)」にアクセスしてください。
| 情報提供件数 | 金融機関の対応 | ||||||
| 期中 | 累計 | 強制解約等 | 利用停止 | 調査中 | その他 | ||
| 累計 (増減) |
累計 (増減) |
累計 (増減) |
累計 (増減) |
||||
| 平成22年3月末 (増減は平成22年1月~3月) |
1,274 | 27,099 | 10,220 (461) |
14,534 (739) |
494 (▲29) |
1,851 (103) |
|
| 平成22年6月末 (増減は平成22年4月~6月) |
1,297 | 28,396 | 10,643 (423) |
15,264 (730) |
548 (54) |
1,941 (90) |
|
| 平成22年9月末 (増減は平成22年7月~9月) |
1,353 | 29,749 | 11,042 (399) |
16,048 (784) |
576 (28) |
2,083 (142) |
|
| 主要行 | 492 | 18,397 | 7,990 (205) |
9,079 (209) |
349 (38) |
979 (40) |
|
| 地方銀行・第二地方銀行 | 245 | 4,093 | 1,379 (36) |
2,245 (191) |
124 (0) |
345 (18) |
|
| 信用金庫・信用組合 | 72 | 1,180 | 548 (28) |
417 (30) |
84 (10) |
131 (4) |
|
| その他金融機関 | 544 | 6,079 | 1,125 (130) |
4,307 (354) |
19 (▲20) |
628 (80) |
|
*)調査を開始した平成15年9月16日以降、全国の財務(支)局において受け付け、金融機関に対して情報提供を行ったもの(一部、金融庁において受け付けた情報を含む)を累計ベースでカウント。
*)増減は、前四半期末に比した数。
*)その他は、金融機関が調査した結果、特段不審な点が見受けられなかったもの、口座不存在であったもの等。
*)主要行は、都銀・長信銀・信託から新生銀行、あおぞら銀行を除いたもの。
*)埼玉りそな銀行は、地方銀行・第二地方銀行に含む。
*)その他金融機関は、主要行、地方銀行・第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)及び労金等。
*)速報ベースであるため、精査により計数が修正されることがあり得る。
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等について
(期間:平成22 年7 月1日~9 月30 日)
金融サービス利用者相談室(以下「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成22年7月1日から9月30日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成22年7月1日から9月30日までの間に、13,480件の相談等(詳細については、「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(平成22年10月29日)をご参照ください。)が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均214件となっており、22年4月1日から6月30日までの間(以下「前期」)の実績(249件)と比べて減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが4,599件(34%)、保険商品等に関するものが2,712件(20%)、投資商品等に関するものが3,781件(28%)、貸金等に関するものが1,966件(15%)、金融行政一般・その他が422件(3%)となっています。
3.分野別の特徴等としては、
(1)預金・融資等については、預金保険制度に関する相談等が大幅に増加したものの、全体では前期に比べて減少しています。
(2)保険商品等については、前期に比べてやや減少しています。
(3)投資商品等については、未公開株に関する相談等が減少したものの、全体では前期とほぼ同水準となっています。
(4)貸金等については、総量規制に関する相談等が大幅に減少したことなどから、全体では前期に比べて大幅に減少しています。
4.なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報(注)も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(注)検査・監督上参考となる情報の例
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関による広告等の不適正な表示に関するもの
(3)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(4)預金取扱金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの
(5)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(6)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(7)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(8)保険会社の不払い等(付随的な保険金の支払漏れ、第三分野商品に係る保険金の不払い等)に関するもの
(9)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(10)損害保険会社の火災保険の保険料過徴収に関するもの
(11)貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反等)に関するもの
(12)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(13)システム障害に関するもの
(14)外国為替証拠金取引業者の不適正な行為に関するもの
(15)外国為替証拠金取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの
(16)無登録営業に関するもの
(17)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない、無断売買、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(18)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(19)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
(1)監督において行った217金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
(2)金融庁が着手した20金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ13口座の情報提供を行っています。
5.寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しています。
今回、新たに追加又は改訂する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」の項目・相談事例等は、以下のとおりです。
(1)保険商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
○保険内容の顧客説明に関する相談等
【相談事例等(保障内容等)】<追加修正>
- 保険金を請求したところ、約款の免責事由に該当するため支払われないと言われました。しかし、契約時には、そのような説明は受けておりません。
- 2社の医療保険に加入しており、手術をしたところ、A社からは保険金が支払われたのに、B社からは支払われませんでした。しかし、手術によって保険金が出ない場合があることは契約時にB社からは聞いていませんでした。
【アドバイス等】
- 個別の契約に係るトラブルについては、保険会社から十分に説明を受け、保険会社とよく話し合ってください。それでも解決が図られない場合には、生命保険協会生命保険相談所、又は日本損害保険協会(※)そんぽADRセンター等に相談してください。
(※)業界団体の連絡先等については、金融庁ウェブサイトの「指定紛争解決機関一覧」をご参照ください。
- 個別の契約に係るトラブルについては、保険会社から十分に説明を受け、保険会社とよく話し合ってください。それでも解決が図られない場合には、生命保険協会生命保険相談所、又は日本損害保険協会(※)そんぽADRセンター等に相談してください。
(2)投資商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
○未公開株式の取引に関する相談等
【相談事例等(金融庁や財務局等を騙る業者)】<追加修正>
- 金融庁の金融サービス利用者相談室の職員だと名乗る者から電話があり、無登録業者の注意喚起を行っていると言われ、過去の未公開株取引を教えてしまいました。
【アドバイス等】
- 金融庁等が、未公開株の取引等に関して、何らかの業務を外部へ委託することはありません。また、金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話で未公開株の上場時期について言及したり、未公開株の買取交渉を行ったりすることもありません。このような連絡があった場合には、詐欺的な商法であると考え、一切関わりにならないようにしてください。
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。
もし、そのような業者から連絡等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話・PHSからは03-5251-6811、ナビダイヤル 0570-016811)又は証券取引等監視委員会の情報受付窓口(03-3581-9909)
 に情報提供をお願いいたします。
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成22年7月1日~9月30日)(平成22年10月29日)にアクセスしてください。
ファンド販売業者に対する検査結果及び建議について
証券取引等監視委員会は、財務局等証券取引等監視官部門とともに、集団投資スキーム(ファンド)の持分の販売を行う業者の法令遵守状況について、平成21年度以降集中的に検査を実施してきたところですが、本年10月19日、改めて、これまでの検査において認められた問題事例について取りまとめ、公表を行いました。また、検査結果を踏まえ、金融庁長官に対して、いわゆる「事業型ファンド」(主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド)販売の契約締結前交付書面における分別管理に関する記載事項を拡充する必要があるとの建議を行いました。
本稿では、その概要を紹介することにより、ファンド販売業者に対し法令遵守態勢の整備・改善を求めるとともに、投資者の皆様に対し、ファンドへの投資を判断する際にはこれらの問題点に十分注意されるよう促すものです。
なお、詳細は、証券監視委ウェブサイト![]() http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101019.pdf(PDF:226K)
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101019.pdf(PDF:226K)![]() を御参照ください。
を御参照ください。
1.検査結果の概要
これまで検査を実施した35先のうち、約4割の15先において、重大な法令違反等が認められたことから、行政処分を求める勧告を行いました。更に、これら15先を含む25先(約7割)において法令違反等の事実が認められたため、検査結果通知書において当該問題点の指摘を行っており、検査を行ったほとんどのファンド販売業者について、何らかの問題点が認められる状況となっています。
(1)主な問題点
これまでの検査において認められた主な問題点は、以下のとおりです。
1.ファンドへの出資金の分別管理が不適切な状況(出資金の流用、使途不明等)
ファンド販売業者の販売したファンドについて出資金の分別管理が確保されておらず、同業者が出資金を自らの借入金の返済に充当した事例、ファンドの運用も行うファンド販売業者に関し、出資金を自社の運転資金等に流用した事例及び多額の出資金の使途が不明となっていた事例等、顧客の出資金がファンドの運用以外の使途に費消されている投資者保護上極めて問題の大きい事例が認められました。
こうした事例は、特に、事業型ファンドについて多数認められたことから、下記2.(2)1.のとおり、証券監視委は、10月19日、金融庁長官に対して建議を行ったところです。
2.顧客に対する虚偽の説明・告知や誤解を生ぜしめる表示等
ファンドの運用も行うファンド販売業者に関し、ファンド持分を保有していないにもかかわらず、これを保有しているように装って販売契約を締結して資金を集めた事例及び出資対象事業の運用実績の裏付けがないにもかかわらず自社のホームページに虚偽の利回りを表示した事例等、契約締結のため顧客に虚偽の情報等を提示している投資者保護上極めて問題の大きい事例が認められました。
3.無登録業者に対する名義貸し等
ファンド販売業者が、自社の名義で無登録の者に対してファンドの販売を行わせた事例等、登録制度を潜脱し、法令の規制下にない無登録の者に販売をさせている投資者保護上極めて問題の大きい事例が認められました。
4.ファンド販売業者自らが登録業務を逸脱している状況等
投資助言・代理業者が第二種金融商品取引業の登録を受ける前にファンドの販売を行った事例、業務範囲が限定されている適格機関投資家等特例業務届出者が、同特例業務の要件を満たさず、登録が必要となるファンドの販売や運用を行った事例等、法の業規制を逸脱し、登録制度により投資者の保護を図るとの法の趣旨に反する事例が認められました。
5.自己の利益を図るためファンド出資者の利益を害する運用を行う行為
投資運用業を行うファンド販売業者が、投資対象である未公開株式を既存株主から高値で取得してファンドに組み入れ、譲渡代金の一部を当該株主から自社に還流させる等、ファンドに不要な負担をさせることにより自社が利益を得ている投資者保護上極めて問題の大きい事例が認められました。
こうした問題点の発生原因をみると、ほとんどすべての事例において、ファンド販売業者の役職員の法令遵守意識の欠如や法令遵守態勢の未整備といった状況が認められました。
また、多くの事例において、ファンド販売業者とファンドの運用を行う者が同一の者であるか、形式上は別の者であっても実質的には一体的に運営されているといった実態が認められましたが、このような実態を背景に、分別管理の状況をはじめとするファンドの運用状況に対するファンド販売業者のチェックが形骸化している状況も認められました。
2.今後の対応等
(1)ファンド販売業者等
ファンド販売業者においては、登録業者等として法令遵守の責務があることを自覚し、上記の問題点及びその発生原因を踏まえ、投資者保護の観点から、法令遵守への取組みを行うことが強く求められます。
また、本年11月1日に設立された一般社団法人第二種金融商品取引業協会においては、今後、自主規制機関としての役割を十分に発揮し、ファンド販売業者をはじめとする会員業者の法令遵守の徹底に資することが強く期待されます。
(2)証券監視委等
1.建議
上記のとおり、特に事業型ファンドについて、ファンドの運用を行う者において分別管理を適切に行っていないにもかかわらず、ファンド販売業者がファンドの販売・勧誘を行っている状況が多く認められました。
また、このような状況においては、投資者に対して、重要な投資判断材料であるファンドの運用を行う者の具体的な分別管理の内容について、十分な情報提供がなされていません。
したがって、こうした状況に鑑み、10月19日、金融庁設置法第21条の規定に基づき、金融庁長官に対して、事業型ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図るため、出資金の分別管理の徹底及び投資者に対する重要な投資判断材料の提供の観点から、事業型ファンド販売の契約締結前交付書面における分別管理に関する記載事項を拡充する必要があるとの建議を行ったところです。
なお、当該建議を受け、金融庁は、10月22日に関係府令の改正案を公表しました。
2.検査等
引き続き、ファンド販売業者に対する検査に取り組み、分別管理の状況を含む法令遵守状況について問題が認められる場合には、行政処分を求める勧告を行う等厳正に対処し、その是正・改善を求めていくこととします。
なお、ファンド販売業者の検査において無登録業者の関与が認められた場合には、金融庁及び財務局等の監督部局、捜査当局等と連携の上対応することとしていますが、必要に応じ、法第192条に基づく裁判所に対する差止命令の申立て及び法第187条に基づく申立てのための調査に係る権限を行使する等、厳正に対処することとします。
悪質なファンド販売業者に関する注意
投資者の皆様におかれては、ファンド販売業者について問題点が多数認められていることを踏まえ、ファンドに対する投資を行うに当たっては、以下の点に十分注意してください。
(1)ファンド販売業者に関する情報の入手
投資者の皆様におかれては、ファンド販売業者に関して、金融商品取引業の登録又は適格機関投資家等特例業務の届出の有無を確認するなど、情報をできる限り収集し、信頼できる業者であるか否かを自ら判断することが重要です。特に、法違反である無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれが高いため、投資者の皆様は、一切応じないようにしてください。
また、登録や届出を行っているファンド販売業者であっても、金融庁・財務局等が、その業者の信用力等を保証するものではないため、その業者の信用力を慎重に見極めた上で、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
(2)取引内容の十分な理解
ファンド販売業者がファンドの販売・勧誘を行う際には、リスクに関する情報などについて、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならず、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないで契約を締結することが禁じられています(金融商品取引法第38条第7号及び第40条第1号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号)。また、ファンド販売業者は、契約締結前に、顧客に対して、金融商品取引業者である旨及び登録番号、契約や手数料の概要、損失が生ずることとなるおそれがあるときはその旨、ファンドの運用を行う者の分別管理の方法等を記載した書面を交付することが義務付けられています(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第87条第1項等)。
投資者の皆様におかれては、このようなファンド販売業者の説明や契約締結前交付書面の内容等をよく確認し、少しでも疑問がある場合には、ファンド販売業者に対して更なる説明を求めるようにし、取引内容が十分に理解できない状態での契約は行わないようにしてください。特に、事業型ファンドについては、投資対象である事業の実態や実現性、運用を行う者の分別管理の状況等について十分に確認してください。
(注)ファンド販売業者のうち、いわゆるプロ向けファンドの販売・勧誘を行う適格機関投資家等特例業務届出者については、登録業者と異なり、行為規制は虚偽告知及び損失補てんの禁止のみであり(金融商品取引法第63条第4項並びに第38条第1号及び第39条)、上記の説明や契約締結前交付書面の交付の義務は課されていません。したがって、投資の知識・経験が十分でない投資者の皆様におかれては、適格機関投資家等特例業務届出者が販売・勧誘するプロ向けファンドに対する投資を行うに当たっては、取引内容の確認・理解に一層の注意を払ってください。
※ 詳しくは、証券取引等監視委員会のウェブサイトの「報道発表資料」から悪質なファンド販売業者に関する注意にアクセスしてください。

 検索
検索

