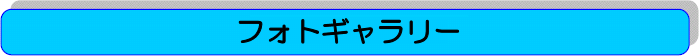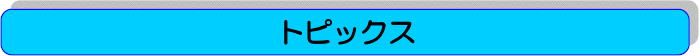アクセスFSA 第119号(2013年4月)
 |
| 財務局長会議にて挨拶する寺田副大臣(4月25日) |
 |
| 財務局長会議にて挨拶する島尻大臣政務官(4月25日) |
(1)「日本版ISA」の愛称決定について
日本版ISA(少額投資非課税制度)については、銀行・証券などの各業界団体等が参加する「日本版ISA推進・連絡協議会」が公募を行い、平成25年4月30日、女優の黒木瞳さんなどをメンバーとした選定委員会において、「NISA」(ニーサ)という愛称が決まりました。
NISAは、いずれか1つの金融機関でしか口座を開設できませんが、金融機関により異なる呼び名が使用されると、利用者が混乱するおそれがありました。そこで、こうしたことを防ぐため、「日本版ISA推進・連絡協議会」に対して当庁からも働きかけを行い、統一的に使用される「愛称」を検討してもらったものです。
銀行・証券など業態の垣根を越えて同一の愛称を使用することで、平成26年1月から導入される制度が、より多くの方々に親しみをもって利用され、制度の普及・促進につながることを期待しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「日本版ISA」の愛称決定について 」について(平成25年5月1日)にアクセスして下さい。
(2)上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について
先般、証券取引等監視委員会が市場監視活動を行う過程で、一部の上場会社において、インターネット上に公開している自社ウェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に資料を自社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずることなく保存したため、公表予定時刻より前に外部の者が容易に閲覧できるケースがあることが明らかとなりました。
法定開示書類や適時開示事項には、インサイダー取引規制上の「重要事実」に該当する情報が含まれていることから、このようなケースにおいては、外部の者が当該情報を利用した取引を行うことにより、金融商品市場の公正性が著しく損なわれるおそれがあります。
そうした取引を助長させかねない公表前の情報の杜撰な取扱いが放置されることは、我が国金融商品市場への信頼性の観点からも極めて重大な問題であり、直ちに改善される必要があることから、金融庁及び全国証券取引所は、平成25年4月5日、上場会社等に対し通知を発出し、法定開示書類や適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合には、下記の事項に留意し、直ちにシステム上の情報セキュリティ措置を講ずるなど、適切な改善を図っていくよう要請しました。
1. 公開ディレクトリに資料を保存した場合、情報セキュリティ措置を講じなければ、容易に外部者からのアクセスが可能であり、例えば、トップページ等にリンク付けを行っていなくても、アドレスを直接指定することでファイルを閲覧することは可能である。
2. このような事態を回避するためには、例えば、次のいずれかの措置を講ずる必要がある。
(1)公表予定時刻までは、公開ディレクトリに資料を保存しないこと
(2)公表予定時刻より前に公開ディレクトリに資料を保存する場合には、外部者が容易にアクセスできないよう、パスワードの設定等によるアクセス制限を実施すること
3. また、上記2.の措置を含む自社ウェブサイトへの会社情報の掲載手順については、社内でルール化した上で周知徹底される必要があり、併せてその遵守状況について定期的に点検を行うことが重要である。
また、本件に関連し、同日、全国証券取引所においても、今後の対応方針等を公表しています。全国証券取引所における対応方針等については、全国証券取引所のウェブサイトをご参照下さい。全国証券取引所の対応方針等(東京証券取引所リンク)
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」の「議事録・資料等」から「上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」(平成25年4月5日)にアクセスしてください。
(3)「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)において、中小企業等への経営改善、資金繰りの支援策として、「ABL(動産・売掛金担保融資)」の活用促進が盛り込まれました。
これを受けて、金融庁では、「ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用について」を平成25年2月5日に公表し、ABLの積極的な活用を推進しており、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定(案)につき、同日から3月6日にかけて、広く意見の募集を行い、4月10日にパブリックコメントの結果を公表し、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の改定を行いました。
改定後の「金融検査マニュアル」等については、平成25年3月期の決算処理から適用されます。
今後とも、金融機関におけるABLの積極的な活用を推進し、中小企業等への経営改善、資金繰りの支援を図っていきたいと考えています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年4月10日)にアクセスして下さい。
(4)「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の公表について
税理士たる公認会計士が自己脱税を行った場合、税理士法に規定された税理士の使命に照らし、法目的を逸脱するものになることから、税理士法上の信用失墜行為として厳格に処分されます。
また、公認会計士は、公認会計士法上、「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する」ことを使命とすることとされております。公認会計士による自己脱税は、こうした公認会計士の使命に照らし、求められている高い倫理を欠くものであることから、公認会計士法上の信用失墜行為として厳正に処分される必要があります。
このため、公認会計士による自己脱税についても、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準をできるだけ具体化・明確化すべく基本的な考え方を整理した「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成17年策定)において、公認会計士法上の懲戒処分の基本量定を定めています。
その後の自己脱税事案の積み重ねの中で、現行の基準では上記の趣旨に基づく対応が、必ずしも十分に行えない場合があり得ると考えられたことから、今般、過去の処分事例の状況や処分基準全体のバランス等を総合的に勘案しつつ、基本量定の見直し及び処分基準の一部改定を行い、パブコメ手続きの後、平成25年4月12日に公表しました。
なお、具体的な変更点は、以下のとおりです。
○公認会計士の自己脱税事案の基本量定についての見直し
現行の処分基準において、
不正所得高額(1億円以上)の場合、業務停止3月
不正所得少額(1億円未満)の場合、業務停止1月
とされているところ、
不正所得高額(2,000万円超)の場合、業務停止3月
不正所得少額(2,000万円以下)の場合、業務停止1月
と改定しました。
なお、今回改定した基本量定は、平成25年4月12日以後にした行為に対して懲戒処分等を実施する場合に適用します。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の公表について」(平成25年4月12日)にアクセスして下さい。
(5)平成24事務年度主要行等向け監督方針、平成24事務年度中小・地域金融機関向け監督方針、平成24検査事務年度検査基本方針の改正について
1.はじめに
金融庁においては、毎年事務年度(検査事務年度)当初に、
(1)金融機関の監督上の重点事項を明確化するため、業態別に監督方針を、
(2)検査運営の基本的な取組み姿勢や重点検証事項等を明確化するため、検査基本方針を、
それぞれ策定・公表しておりますが、主要行等向け監督方針、中小・地域金融機関 向け監督方針及び検査基本方針について、平成25年4月30日に改正をいたしましたので、内容を御紹介します。
2. 監督方針・検査基本方針の改正について(新規融資の積極的な取組みの促進)
日本経済がデフレから脱却し、力強い成長を実現していくため、金融機関は、顧客企業と向き合い、顧客企業の経営改善や事業再生に向けた支援のみならず、適切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、顧客企業の育成・成長を強力に後押しするという金融機関が本来果すべき役割を一層発揮していくことが求められています。
このため、金融機関における顧客企業の経営改善、事業再生、育成・成長につながる新規融資に関する取組みの状況について、例えば、以下のような着眼点に基づき重点的に検証することにより、金融機関による新規融資の積極的な取組みを促していくこととします。
(1)新規融資(特に中小企業・小規模事業者向け融資)について、どのような経営方針の下で積極的に取り組んでいるか。当該経営方針を営業の第一線に対してどのように周知徹底しているか。
(2)今後期待される景気回復局面における新たな資金需要の見通しについて分析を行い、当該分析結果に基づき融資の方針等を立てているか。
(3)資金需要の高まりが期待できる事業分野や地域について、定期的に分析を行い、当該分析結果に基づき新規融資の戦略・方針・具体的な目標等を立てているか。
(4)資金需要の掘り起しに当たって、具体的にどのような工夫・取組みを行っているか。
(5)貸付条件の変更等を行った債務者についても、債務者の実態を十分に把握した上で、新規融資に積極的に取り組んでいるか。仮に、謝絶する場合には、その理由を具体的に明示しているか。また、貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資の相談・申込みを謝絶していないか。
(6)顧客企業のライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮(販路開拓支援・海外進出支援等)を新規融資に結びつけるため、具体的にどのような工夫・取組みを行っているか。
(7)新規融資を行う際に、不動産担保や保証(信用保証協会保証、個人保証)を求めるのは、どのような場合か。
(8)ABL(電子記録債権の活用を含む)など、不動産担保や保証に依存しない融資の推進や資本性借入金の活用に当たって、具体的にどのような工夫・取組みを行っているか。
(9)新規融資についてどのような審査基準に基づき審査を行っているか。特に、中小企業・小規模事業者向け融資の審査に当たって、具体的にどのような工夫・取組みを行っているか。
(10)スコアリングによる定量面(P/L、B/S)の審査に偏重することのないようにするため、具体的にどのような工夫(定性面の評価等)・取組みを行っているか。
(11)新規融資に関する苦情・相談について、どのような態勢で対応しているか。
(12)業績評価や人事評価に当たって、新規融資の取組みを勘案しているか。
(13)新規融資の取組み、預貸率を含む金融機関のポートフォリオの状況等について、どのように分析し、情報開示を行っているか。
3. 最後に
以上が、主要行等向け監督方針、中小・地域金融機関向け監督方針及び検査基本方針の改正の主な内容です。当局としては、こうした取組みを通じ、金融機関による新規融資の積極的な取組みを促してまいります。
なお、監督方針及び検査基本方針本文(http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130430-7.html)の御一読もお薦めいたします。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成24事務年度監督方針及び検査基本方針の改正について」(平成25年4月30日)にアクセスして下さい。
(6)金融経済教育研究会報告書の公表について
先般の金融危機を踏まえ、利用者側の金融リテラシーを向上させ、利用者の金融行動を改善することが重要であるとの認識が、G20等における国際的な議論において共有される等、国民の金融リテラシーを向上させていくことがこれまで以上に重要となっており、金融経済教育の一層の推進が求められています。
このため、金融経済教育の現状をあらためて把握するとともに、我が国における金融経済教育の今後のあり方について検討を行うこととし、平成24年11月、金融庁金融研究センターに、有識者、関係省庁、関係団体をメンバーとする「金融経済教育研究会」を設置、議論を重ね、平成25年4月、報告書を公表しました。報告書の概要は、以下のとおりです。
- ローン、保険、資産運用商品等の金融商品を利用する上での留意点、必要な場合にどこにアドバイスを求めればよいかなど、個人の金融行動に役立つより実践的な内容とする。
- 国民にとって必要な金融リテラシーの内容を、教育の現場で利用しやすいものとなるよう具体化し、関係者で共有。
- 金融庁・金融広報中央委員会が中心となって、金融経済教育を効率的・効果的に推進する場(「金融経済教育推進会議」)を設置。報告書で指摘された課題について、役割分担と実施スケジュールを明確化。
今後、金融経済教育研究会報告書で指摘された課題に、金融広報中央委員会などの関係団体と連携しつつ、「金融経済教育推進会議」を開催する等、積極的に取組んでまいります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融経済教育研究会報告書の公表について」(平成25年4月30日)にアクセスして下さい。
(7)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年1月1日~同年3月31日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成25年1月1日から同年3月31日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成25年1月1日から同年3月31日までの間(以下、「今期」という。)に、9,249件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均159件となっており、平成24年10月1日から同年12月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績149件に比べてやや増加しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,750件(構成比30%)、投資商品等に関する相談等の受付件数2,708件(同29%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,380件(同26%)、貸金等に関する相談等の受付件数738件(同8%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数673件(同7%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、金融機関の態勢・各種事務手続に関する相談等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。
(2)保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(3)投資商品等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(4)貸金等については、前期に比べて、同水準となっています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供等のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)無登録営業に関するもの
(12)金融商品取引業者の不適正行為(ホームページを閉鎖し電話にでない、無断売買、口座開設拒否、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ84口座の情報提供を行っています。
前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。
- 監督において行った167金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
- 金融庁が着手した29金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
- 金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話・PHS からは03-5251-6811 - 証券取引等監視委員会の情報受付窓口
03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年1月1日~同年3月31日) 」(平成25年4月30日)にアクセスして下さい。

 検索
検索