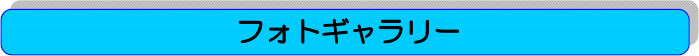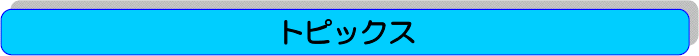アクセスFSA 第122号(2013年3月)
 |
 |
| 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの 供給のあり方等に関するワーキング・グループ」 (第3回)にて挨拶する寺田副大臣(7月30日) |
財務局長会議にて挨拶する寺田副大臣(7月31日) |
(1)「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、個人向け店頭バイナリーオプション取引の状況等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「内閣府令」という。)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」という。)の一部改正(案)について、平成25年5月14日から6月13日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年7月3日に公表しました。
改正後の内閣府令・監督指針は、平成25年7月3日に公布され、同年8月1日から施行されています。但し、バイナリーオプション取引等の既存取扱業者については、平成25年12月1日から適用されます。
本件の主な改正内容は、以下の通りです。
1.改正後の内閣府令において、バイナリーオプション取引等の個人向けの特定店頭オプション取引(注)の基本的な枠組みを以下のとおり規定。
(1)取引契約の締結前に、顧客に対し、権利行使価格(一定の方法により定められる ものにあっては、その算定方法)を提示すること。
(2)取引期間・期限を、顧客が、公正な価格で、投資判断に基づいて、取引を行うた めに必要かつ適切なものとすること。
(注)「特定店頭オプション取引」とは、金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引であって、取引に係るオプションが行使された場合に、あらかじめ金融指標として約定した数値と現実の数値の差に基づいて算出した額を授受することとなるもの。
2.また、改正後の監督指針においては、店頭デリバティブ取引業者が個人向けの特定店頭オプション取引を取り扱う場合の留意事項として、以下の点等に留意しつつ、自主規制機関が策定する自主規制規則の内容を遵守しているかを検証する旨を規定。
(1)金融商品取引としての適切性及び健全性を確保するため、以下の点等に留意しているか。
a.取引期間について、過度の投機的取引を助長するような短い期間に設定していないか。
b.顧客が取引に係るリスクを正確に把握して適切に投資判断を行えるよう、取引期間の開始前に、取引に係る権利行使価格等を決定・提示しているか。
c.同一の原資産、取引期間及び権利行使価格を有する商品について、店頭デリバティブ取引業者のみが有利となる取引条件を取り除いているか。
d.権利行使期間、権利行使価格及び原資産の価格等に照らし、公正な方法により取引価格(対価)を算出しているか。
(2)顧客の知識・経験・資力に応じた取引開始基準を設定しているか。また、顧客の属性に応じた取引限度額を設定し、モニタリングを行っているか。
(3)顧客が取引に係るリスクを正確に把握して適切に投資判断を行えるよう、リスク、商品内容及び損益実績等について、必要かつ十分な説明・情報提供を行っているか。また、投資者が過度な期待や誤った認識を持つことがないよう、広告・宣伝の適正化等を行っているか。
(4)顧客が合理的な投資判断を行うことができるよう、取引価格、権利行使価格及び判定価格の設定根拠について、十分に顧客に説明しているか。取引停止(いわゆる「売切れ」)については、事前に取引停止の判断基準を説明するとともに、取引停止の発生時においては、発生した旨及びその理由を公表しているか。また、取引価格や判定価格について、担当部署以外の第三者等によるモニタリングを行い、適切性を検証しているか。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年7月3日)にアクセスして下さい。
(2)「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)につきまして、平成25年5月24日から6月24日にかけて広く意見の募集を行い、7月5日にパブリックコメント結果を公表し、監督指針及び事務ガイドラインの改正を行いました。
改正の主な概要については、以下のとおりです。
1.金融会社に係るシステムリスク管理態勢の強化
貸金業者等の金融会社において、コンピューターシステムを用いて業務を大量処理している業者が見られる現状等を踏まえ、貸金業者、前払式支払手段発行者、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移動業者に対するシステムリスク管理態勢に関する監督上の着眼点を追加しました。
2.貸金業者の信用情報の目的外使用等の防止に係る態勢構築の強化及び指定信用情報機関と登録行政庁との連携
貸金業者に対する信用情報の目的外使用等の防止に向けた態勢構築の強化のための監督上の着眼点を追加するとともに、貸金業者の信用情報の目的外使用等に係る指定信用情報機関と登録行政庁の情報共有・連携について明確化を図りました。
3.電子債権記録機関に対する災害における金融に関する措置
電子記録債権が手形と同様に決済手段として利用されていること等を踏まえ、電子債権記録機関に対して災害における金融上の措置に関する要請を行うこととしました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年7月5日)にアクセスして下さい。
(3)障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について
金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、その取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成25年3月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を7月9日に公表しました。
主な調査結果は、以下のとおりです。
1.視覚障がい者対応ATMの設置率について
ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約72%です。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約89%(うち都市銀行等 約90%)、信託銀行 約83%、地方銀行等 約56%、第二地方銀行 約54% 、信用金庫 約62%、信用組合 約62%、労働金庫 約76%
2.預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について
預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約81%【約92%】(うち都市銀行等 100%【100%】)、信託銀行 100%【100%】、地方銀行等 100%【100%】、第二地方銀行 100%【100%】、信用金庫 100%【約100%】、信用組合 約99%【約99%】、労働金庫 100%【100%】
注:【 】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率3.本人確認及び認証システムの開発段階における視覚障がい者との協議等
各金融機関は、障がいをお持ちの方々の利便性が高まるよう、ATMの本人確認及び認証システムの開発の際に障がい者の方の意見を取り入れています。実績等の一例は、次のとおりです。
- ATMメーカーによる視覚障がい者団体へのアンケート結果を受領し、「ハンドセット方式」が最も利用しやすいとの意見を取り入れ、ハンドセット方式の視覚障がい者対応ATMを導入。
- ATMメーカーによる触覚記号方式の開発段階において、知覚心理学、実験心理学の専門家への委託研究という形で、視覚障がい者による操作性評価を実施。
【参考】アンケート対象金融機関数
◎主要行等 16行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、シティバンク銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)
◎信託銀行 5行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)
◎地方銀行等 65行(地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)
◎第二地方銀行 41行(第二地方銀行協会加盟行)
◎信用金庫 270金庫
◎信用組合 157組合
◎労働金庫 13金庫
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)」(平成25年7月9日)にアクセスしてください。なお、ウェブサイトに掲載した資料については、テキスト形式のものもございますので、読み上げソフトをお使いの方はそちらもご利用ください。
(4)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年4月1日~同年6月30日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成25年4月1日から同年6月30日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成25年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「今期」という。)に、11,220件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均180件となっており、平成25年1月1日から同年3月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績159件に比べてやや増加しています。
2.分野別の受付件数としては、投資商品等に関する相談等の受付件数3,780件(構成比34%)、預金・融資等に関する相談等の受付件数3,071件(同27%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,502件(同22%)、貸金等に関する相談等の受付件数751件(同7%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数1,116件(同10%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、金融機関の態勢・各種事務手続に関する相談が増加したことなどから、前期に比べて、やや増加しています。
(2)保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談が増加したことなどから、前期に比べて、やや増加しています。
(3)投資商品等については、行政に対する要望等に関する相談等が増加したことなどから、前期に比べて、大幅増加しています。
(4)貸金等については、前期に比べて、ほぼ同水準となっています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)外国為替証拠金取引業者の不適正な行為に関するもの
(12)無登録営業に関するもの
(13)金融商品取引業者の不適正行為(ホームページを閉鎖し電話にでない、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(14)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(15)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
(16)金融機関の信託業務における不適切な行為に関するもの
また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ46口座の情報提供を行っています。
前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。
- 監督において行った165金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
- 金融庁が着手した40金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」 「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
- 金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話・PHS からは03-5251-6811 - 証券取引等監視委員会の情報受付窓口
03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁ウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年4月1日~同年6月30日)」(平成25年7月31日)にアクセスしてください。

 検索
検索