アクセスFSA 第65号(2008年4月)
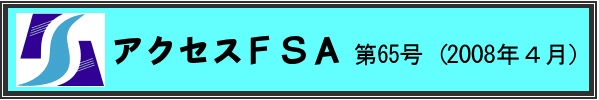
 |
 |
|
| ACCJ(在日米国商工会議所)において講演する 渡辺 大臣(4月7日) | 全国財務局長会議において挨拶する 渡辺 大臣(4月22日) |
【特集】
「金融サービス業におけるプリンシプル」等の公表について
我が国の金融・資本市場の魅力と競争力を高め、金融サービス提供者が利用者ニーズに応えた良質な金融サービスを提供できるようにしていくことは、我が国経済社会にとって重要な課題であり、そのためには、ビジネス環境や規制環境を、金融サービス利用者と提供者の双方にとってより良いものとしていくことが重要となります。こうした観点を踏まえ、金融庁では、昨年来金融規則の質的向上(ベター・レギュレーション)に向けた取組みを進めてきました。
このベター・レギュレーションの大きな柱の一つとして、「ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督の最適な組合せ」 という考え方を掲げてきました。そして、プリンシプルベースの監督の基軸となる主要なプリンシプル1について、関係する金融サービス提供者の代表の方と、昨年12月以降、議論を重ねてきました。
そして、14項目から成る「金融サービス提供者におけるプリンシプル」について、以下のとおり関係者2との間で共有することができ、平成20年4月18日(金)に公表しました。
| 金融サービス業におけるプリンシプル |
|
このプリンシプルについて、広く関係者の間で認識を共有できれば、以下のような効果が期待できると考えています。
|
今後、各金融機関が共有されたプリンシプルに沿って、自主的な経営改善に向けた努力を進めていくことを期待しています。金融庁としても、このプリンシプルを踏まえ、より良い規制環境を実現するために努めていきたいと考えています。まずはこのプリンシプルについて職員一人一人に浸透を図り、プリンシプルに即した実効的な行政対応に努めていくとともに、金融サービス提供者との間で継続的な対話を行い、更に議論を深めていきたいと考えています。
なお、金融庁では、平成19年3月1日に![]() 「金融上の行政処分について」を公表(資料「金融庁の監督手法について」4ページ目(表紙除く))し、その中で行政処分の基準について明らかにしてきました。今般、プリンシプルが共有されたことを踏まえ、運用にあたって留意されるべき事項を明確化するため、併せて「金融上の行政処分について」の一部改定を行いました。具体的には、金融機関が、行政当局と共有されたプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、軽減事由として考慮することを明確化しました。
「金融上の行政処分について」を公表(資料「金融庁の監督手法について」4ページ目(表紙除く))し、その中で行政処分の基準について明らかにしてきました。今般、プリンシプルが共有されたことを踏まえ、運用にあたって留意されるべき事項を明確化するため、併せて「金融上の行政処分について」の一部改定を行いました。具体的には、金融機関が、行政当局と共有されたプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、軽減事由として考慮することを明確化しました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『「金融サービス業におけるプリンシプル」等の公表について』(平成20年4月18日)にアクセスして下さい。
1. プリンシプルとは、法令等個別ルールの基礎にあり、各金融機関等が業務を行う際、また当局が行政を行うにあたって、尊重すべき主要な行動規範・行動原則という性格を有しています。また、プリンシプルベースの監督とは、上記のようなプリンシプルに沿って、各金融機関等がより良い経営に向け自主的な取組みを行っていくことに重点を置いていく監督の枠組みです。
2. 本プリンシプルをとりまとめるにあたっては、主な金融サービス提供者として全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、信託協会、国際銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、外国損害保険協会、日本証券業協会と意見交換会を開始し、議論を行いました。
また、全国労働金庫協会、投資信託協会、日本証券投資顧問業協会とは個別に意見交換を行いました。
【トピックス】
金融安定化フォーラムによる「市場と制度の強靭性の強化に関する金融安定化フォーラム(FSF)報告書」の公表について
金融安定化フォーラム(FSF) では、昨年10月のG7(七カ国財務大臣・中央銀行総裁会議)声明を受けて、今回の世界的な金融市場の混乱の背景にある要因を分析し、中期的な視点から様々な市場強化策を検討してきましたが、先般、その報告書がG7に提出され、4月11日(金)に米国ワシントンで開催されたG7会合において、本報告書に盛り込まれた提言を各国が実施することが合意されています。
FSF報告書の原文は、ページ数で71ページ、67の詳細な提言が盛り込まれた大部の報告書となっており、提言の概要(FSFのプレスリリースによるもの)の![]() 仮訳(金融庁作成)と併せて金融庁のウェブサイトから閲覧することができます。
仮訳(金融庁作成)と併せて金融庁のウェブサイトから閲覧することができます。
FSF報告書の提言は、
- 自己資本・流動性・リスク管理に関する健全性監督の強化
- 透明性・価格評価の強化
- 信用格付の役割・利用の変更
- 当局のリスク対応力の強化
- 金融システムにおけるストレスに対応するための堅固な体制
の5つの分野に大きく区分され、その対象はバーゼル銀行監督委員会(BCBS)や証券監督者国際機構(IOSCO)、国際会計基準審議会(IASB)等の国際基準設定機関(スタンダード・セッター)のみならず、各国の監督当局・中銀、更には金融機関をはじめとする民間セクターまで、多岐にわたっています。
今回のFSF報告書の大きな特徴は、こうした多岐にわたる関係者を横断した様々な対応策が1つのパッケージとして明確に提示されたというところにあり、サブプライム・ローン問題を契機とした混乱が続く金融市場に対し、当局、国際機関、民間セクター等といった関係当事者のための作業工程表を包括的に提示したことの意義は、極めて大きいと言えます。
また、FSF報告書は、主要な各国当局の高官や国際的な監督・規制機関の議長等から構成されるハイレベルな作業部会において準備されてきたものであり、G7会合において了承されたことも含め、各国トップレベルでの強いコミットメントの下に取りまとめられたパッケージであることも特徴の1つです。なお、我が国からは、当庁の佐藤長官が正式メンバーとして参加をしています。
金融庁としては、これまで、FSFをはじめとする国際的な議論や検討の場において、昨年11月に公表された「金融市場戦略チーム」の第一次報告書で指摘された論点(例えば、証券化の一連のプロセスにおける各当事者の情報伝達の確保やリスク管理の問題、バーゼルII実施の重要性等)について、我が国の考え方を積極的に主張してきました。
FSF報告書や今回のG7声明では、こうした「金融市場戦略チーム」報告書が指摘した論点について、基本的な方向性を同じくする問題意識や対応策等が示されており、こうした点について各国間で共通の理解が得られたものと考えています。
本件については、4月11日のG7声明において、6月のサミット財務大臣会合や秋のG7会合において報告書の提言の実施状況等について報告することが期待されていることから、金融庁としては、引き続き、FSFをはじめとする国際的な議論や検討に積極的かつ建設的に参画していきたいと考えています。
≪参 照≫
● 昨年10月G7声明ポイント(http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/frame.html)
● 本年4月G7声明ポイント(http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/frame.html)
● FSF報告書原文(
 http://www.fsforum.org/publications/FSF_Report_to_G7_11_April.pdf)
http://www.fsforum.org/publications/FSF_Report_to_G7_11_April.pdf)
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融安定化フォーラムによる「市場と制度の強靭性の強化に関するFSF報告書」の公表について」(平成20年4月12日)にアクセスしてください。
1. 金融安定化フォーラム(Financial Stability Forum :FSF)は、金融市場の監督及びサーベイランスに関する情報交換と国際協力の強化を通じて国際金融の安定を促進することを目的に、7カ国蔵相・中央銀行総裁会議(G7)によって1999年に創設されました。FSFには重要な国際金融センターを有する各国及び地域の関連当局、金融監督当局による国際機関(バーゼル銀行監督委員会、証券監督者国際機構(IOSCO)、保険監督者国際機構(IAIS))、国際金融機関(国際通貨基金(IMF)、世界銀行)等が参加しており、我が国からは金融庁、財務省及び日本銀行が参加しています。
財務局における多重債務者相談業務開始について
平成20年4月7日から各財務(支)局、沖縄総合事務局において、多重債務者に係る相談業務を開始しました。
多重債務者は、どこにも相談できないまま生活に行き詰まるおそれがあり、多重債務者向けの相談窓口の整備・強化を図っていくことは極めて重要な課題となっています。
昨年4月に策定された「多重債務問題改善プログラム」においても、自治体における相談窓口の整備に加え、財務局の相談体制の強化を図ることとされていたところです。
こうした中で、多重債務者からの相談を直接受け付けるとともに、自治体等関係者の取組みをバックアップするため、全国の財務局等に相談員を配置し、相談業務を開始することとしました。
各財務(支)局、沖縄総合事務局の相談窓口では、借金の問題でお悩みの方々からの相談に応じ、借金の状況等を聴取するとともに、債務整理に向けたアドバイスを行い、必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎを行います。
相談対応が可能な時間、連絡先等は、各財務(支)局、沖縄総合事務局のウェブサイトをご覧ください。(金融庁ウェブサイトはhttp://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20080407-1.html)
○「多重債務者相談マニュアル」の改訂について
昨年4月の「多重債務問題改善プログラム」の策定後、金融庁では、地方自治体の多重債務者向け相談の担当職員を対象に、相談時の心構えや相談手順等を分かりやすく解説した「多重債務者相談マニュアル」(冊子及びDVD)を作成し、昨年7月に全ての地方自治体等に配布しました。
本マニュアルに対しては、相談担当職員向けの各種研修やシンポジウム等の場において、「発展編として家計管理について論じたマニュアルを出して欲しい」とのご要望を多くいただきました。これを受けて、マニュアルの一層の充実を図るため、本年3月にマニュアルを改訂し、再度地方自治体等に配付しました。
今回の改訂版では、多重債務者相談担当者の更なる取組みのヒントとして、巻末に「補遺」を設け、多重債務者の真の生活再建のためには、適切に家計管理を行い、自らの収入に見合った生活を送ることが重要性となることを解説しています。
改訂版では、
○多重債務者に対し、きめ細かいヒアリングを通じた家計管理指導を行い、生活再建に必要な資金を融資する「グリーンコープ生協ふくおか」の取組み
○多重債務者の家計管理を支援する民間団体との連携を図る岩手県盛岡市の取組み
「多重債務者相談マニュアル」とその掲載資料は、金融庁ウェブサイトからご自由にダウンロードや資料の加工ができるようになっていますので、是非ご利用ください。

地域密着型金融に関する取組み事例集
‐平成19年度地域密着型金融シンポジウムにおける発表事例を中心に‐
地域密着型金融については、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、「特に先進的な取組みや、広く実践されることが望ましい取組みについては、年1回、全国に対する事例紹介や顕彰等を実施するものとする。」とされています。
また、平成20年2月20日、関係閣僚によって申し合わせがなされた、「年度末に向けた中小企業対策について」においても、各金融機関が行う地域密着型金融の取組みの中で、先進的な事例・普及が望ましい事例について取りまとめた事例集を作成することとされました。
金融庁では、これらを受け、平成19年度に全国各地の財務局等で開催された「地域密着型金融に関するシンポジウム」において発表された地域密着型金融の取組み事例を中心として「地域密着型金融に関する取組み事例集」を取りまとめ、3月31日に公表しました。
以下では、事例集に掲載した取組み事例の中から、一部を紹介します。なお、本事例集の項目については、平成19年4月5日に公表された金融審議会金融分科会第二部会報告書「地域密着型金融の取組みについての評価と今後の対応について-地域の情報集積を活用した持続可能なビジネスモデルの確立を-」において、地域金融機関に共通して取組みを求める内容として示された項目と対応しています。
(1) ライフサイクルに応じた取引先企業の支援
- 中小企業再生支援協議会を活用した事業再生
- 企業再生ファンド活用による事業再生
- 企業育成ファンド活用による企業支援
- ビジネスマッチングフェアの開催
- M&Aによる事業承継
(2) 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法
- 「業種別審査スペシャリスト」の養成
- 外部機関の与信審査能力を活用した融資
- 動産等を担保とした融資(ABL(Asset Based Lending))
(3) 地域の面的再生・地域活性化につながる多様なサービスの提供
- 地域における「面」的再生
- 観光事業と街づくり支援
- 地域貢献活動助成金
本事例集の公表を契機として、各金融機関において先進的な取組み事例に関するノウハウが共有され、地域密着型金融の一層の推進が図られることを期待しています。
※ 本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料等により作成したものであるため、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料等を作成した各金融機関における見解であり、当庁の見解を表したものではありません。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」又は「地域密着型金融」から、「地域密着型金融に関する取組み事例集 -平成19年度地域密着型金融シンポジウムにおける発表事例を中心に-の公表について」(20年3月31日)にアクセスしてください。
企業会計審議会総会について
企業会計審議会総会が平成20年3月27日に開催され、本審議会に置かれている3つの部会(企画調整部会、監査部会、内部統制部会)に関連する会計・監査・内部統制について、国際的な動向など最近の状況について報告と、本審議会の今後の運営方針について審議が行われました。
1.報告事項について
(1)会計基準をめぐる国際的動向について
EU(欧州連合)による会計基準の同等性評価1をめぐる最近の動向と今後の具体的なスケジュールなどについて、報告がありました。
(2)監査をめぐる国際的動向について
ISA(国際監査基準)を設定している(IAASB)国際監査・保証基準審議会において行われている「明瞭性プロジェクト2」、EUによる監査の同等性評価をめぐる最近の動向などについて、報告がありました。
(参考)EUによる監査の同等性評価
EU域内の規制市場に上場する企業を監査する第三国の監査事務所等についても、○EU加盟国当局に登録の上、当該当局の監督に服すること、または、○第三国において、法定監査指令で定められているものと「同等」な監督に服することが求められており、現在、ECは同等性評価の作業を進めています。
(3)内部統制報告制度の準備状況について
本年4月から導入している内部統制報告制度の準備状況について報告がありました。
2.企業会計審議会の今後の運営方針について
本審議会の今後の運営方針について、報告事項として報告された会計・監査・内部統制をめぐる国際的な動向など最近の状況を踏まえて審議が行われ、本審議会の審議事項として、以下のようにすることについて承認されました。
(1)企画調整部会
EUにおける同等性評価や会計基準の国際的なコンバージェンスの動向等を踏まえ、審議事項の企画調整を行うとともに、必要な審議・検討を行う。
(2)監査部会
監査基準をめぐる国際的な動向や会計基準の見直しに伴う改訂の必要性の検討等を踏まえ、継続的に監査基準の改訂作業を進める。
(3)内部統制部会
内部統制報告制度の円滑な実施に向けて、導入後に実施するレビュー結果を踏まえ、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の見直しや更なる明確化等について、必要な審議・検討を行う。
 |
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「企業会計審議会」にアクセスしてください。 |
1.EUでは、EU市場に上場する域内企業について、2005年からIFRS(国際会計基準)の使用が義務づけられています。EUに上場する日本を含む第三国の企業についても、2009年から国際会計基準又はこれと「同等」の基準の使用が義務づけられる予定であり、EC(欧州委員会)は、これまで日米加等の会計基準に対する同等性評価の作業を進めてきています。
2. 国際監査・保証基準審議会は、非常にわかりにくいと言われています、現在の国際監査基準の記載内容を整理して、すべての基準を○目的、○要求事項、○その他の説明の3段階に区分して記載し直すという取組みを行っています。
「協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ」について
協同組織金融機関のあり方をめぐっては、政府の規制改革・民間開放推進会議においても様々な議論があり、その結果、平成19年6月に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」において、「業務及び組織の在り方につき、総合的な視点から見直しを検討する」こととされ、19年度から検討を開始することとされました。
協同組織金融機関のあり方については、金融審議会の前身である金融制度調査会の平成2年の議論を最後に、本格的な検討が行われておらず、また、その検討に当たっては、幅広く、専門性の高い議論が必要と考えられます。
こうした点を踏まえ、1月31日の金融審議会金融分科会第二部会において、同部会の下に「協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ」を設置して検討を行うことが決定され、3月28日に第1回の会合を開催し、審議を開始しました。
今後、協同組織金融機関の今日的な役割や相応しい制度的枠組み等について、幅広い観点から議論が行われることとなります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「第二部会-協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ」にアクセスしてください。

 検索
検索

