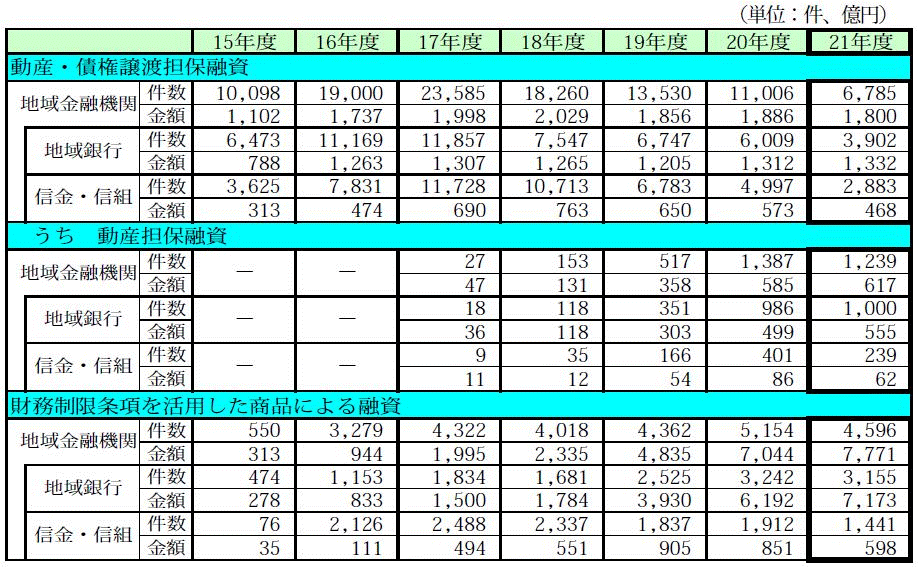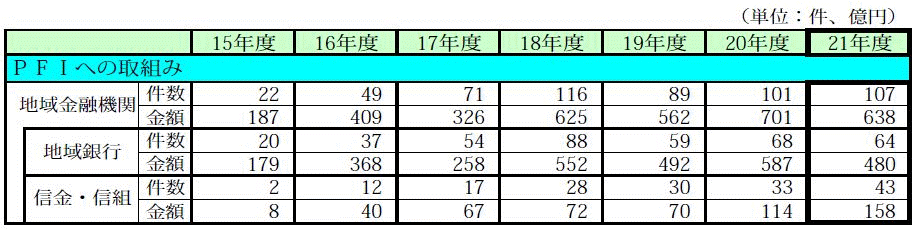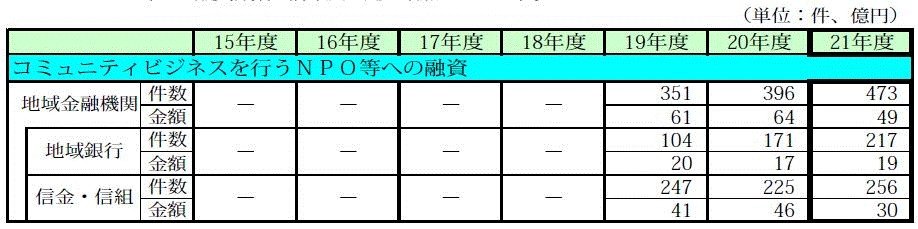アクセスFSA 第86号(2010年8月)

 自見大臣米国出張 |
 子ども見学デー「金融庁へGO!」 |
【フォトギャラリー】
※ 大臣、副大臣、大臣政務官が出席された会議等の写真を掲載し、皆さんに情報をお届けするものです。
 自見大臣(前列中央)、東京証券取引所を訪問 |
 税制調査会で挨拶をする大塚副大臣 |
【国際関係】
自見金融担当大臣の米国及び中国出張について
○米国出張
自見金融担当大臣は、8月16日から6日間の日程で、米国に出張しました。当地では、バーナンキ連邦準備制度理事会(FRB)議長、ブレイナード財務次官、ボルカー大統領経済顧問等と面談を行いました。一連の面談では、金融規制改革がマクロ経済や金融仲介機能に与える影響や金融・経済情勢等について、率直な意見交換を実施しました。
 ブレイナード財務次官(右側)との面談にて |
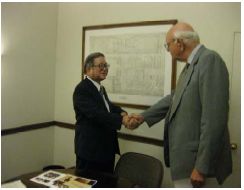 ボルカー大統領経済顧問(右側)との面談にて |
○中国出張
自見金融担当大臣は、8月27日から7日間の日程で、中国に出張をしました。当地では、第3回日中ハイレベル経済対話に出席し、温家宝首相と面談したほか、周小川中国人民銀行行長等、銀行・証券・保険各分野の監督当局責任者と面談を行いました。
特に、温家宝首相との面談では、日中の互恵協力を金融分野でも更に推進する観点から、中国企業の資金調達に対する我が国金融機関の更なる支援を円滑にするために、預金・貸出比率規制の我が国金融機関に対する柔軟な対応を要望し、温家宝首相からは、中国の日系企業が必要とする資金は必ず保障するとの回答を得ました。
 第3回日中ハイレベル経済対話の模様 |
 温家宝中華人民共和国首相(右側)との面談で |
【特集】
中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督長官グループがバーゼル銀行監督委員会による自己資本及び流動性に関する規制改革パッケージについて広範な合意に到達」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(総裁・長官グループ)は7月26日、バーゼル委において検討されている規制改革案に関して、プレス・リリースを公表しました。
1. 背景・経緯
バーゼル委は昨年12月17日、国際的に活動する銀行に関する一連の規制改革案を市中協議文書として発表しました。本規制改革案は、昨年4月のG20ロンドン・サミットにて合意され、その後9月のピッツバーグ・サミットにてあらためて確認された、銀行資本の質と量の双方を改善し、過度なレバレッジを抑制するとともに、流動性の基準を定める国際的なルールの原案です。
昨年12月の規制改革案の公表後、バーゼル委は、個別の銀行に与える影響度について、各国の銀行から収集したデータをもとに定量的影響度調査(QIS)を行ってきました。また、経済全体に与える影響を分析するため、マクロ経済モデルを用いた影響度評価も実施しました。バーゼル委では、こうした調査とともに、市中協議文書に対して本年4月16日までに各国から寄せられた多数のコメントを踏まえ、規制改革案の修正について検討が進められてきたところです。今回の総裁・長官グループによるプレス・リリースは、こうした検討の結果、広範な合意が得られた規制の設計要素(デザイン)について発表したものです。
2. 総裁・長官グループによる広範な合意(7月26日)のポイント
- 自己資本の質の改善(自己資本の定義)
自己資本のコア部分は、普通株及び内部留保(損失吸収力の最も高い資本)のみから構成すべきことが明確化(繰延税金資産、無形固定資産などを原則として控除)されていました。
→ 今般の合意により、各国の実情に応じ、以下のような控除項目の一部例外を容認することとなっています。
| 昨年12月の規制案 | 本年7月の見直し案 | |
| 繰延税金資産 | 全額を自己資本から控除 | 会計と税務の一時差異に基づくものはコアティア1部分の10%まで算入(注) |
| 無形固定資産 | 全額を自己資本から控除 | 会計基準の差異に基づく取扱いの不平等を是正 |
| 少数株主持分 | 自己資本へは不算入 | 銀行子会社の最低所要資本までは算入 |
- レバレッジ比率規制(資本/総資産)の導入
レバレッジ比率規制は、リスクベースの自己資本比率規制を補完することが目指されています。
→ 今般の合意では、移行期間を経て、第一の柱の下での取扱いに移行することを視野に入れつつ、2017年前半に指標や水準の最終的な調整を行うこととなりました。この移行期間の中では、資本(分子)をTier 1とし、総資産(分母)をオフバランス項目の一部に低い掛け目を適用することとした指標に基づき、3%の水準が補完的指標として機能するかテストされます。
- 流動性規制(流動性カバレッジ比率、安定調達比率)の導入
流動性カバレッジ比率は、30日間の厳しい流動性ストレスへの対応を可能とする流動資産の保有を求めるものです。
→ 今般の合意により、リテール預金流出率の引き下げ、適格流動性資産の定義の拡大等が行なわれることとなりました。
安定調達比率は、運用資産の流動性リスクの度合いに応じて調達側の安定度を求めるものです。
→ 今般の合意では、本比率について、観察期間が設けられ、2018年1月までに最終化することとなりました。
3. 今後の予定
バーゼル委や総裁・長官グループは引き続き規制改革案の詳細について議論を行うこととなっており、こうした検討結果が本年11月に予定されているG20ソウル・サミットに報告され、本年末までには最終的な規制改革パッケージが策定される予定です。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「国際関連情報」から平成22年7月27日 中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループがバーゼル銀行監督委員会による自己資本及び流動性に関する規制改革パッケージについて広範な合意に到達」の公表についてにアクセスしてください。
【トピックス】
貸金相談デスクの開設について
平成18年12月、多重債務問題の解決を図ることを目的として、「上限金利の引下げ」や「借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ総量規制の導入」などを内容とする改正貸金業法が全会一致で成立しました。
同法は、三年半の期間をかけて段階的に施行されてきましたが、本年6月18日に完全施行されました。
本年6月22日には、完全施行後、改正貸金業法を円滑に施行し、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討していくため、「改正貸金業法フォローアップチーム」が設置されました。
この「フォローアップチーム」では、「改正貸金業法に係る制度の周知徹底」 の施策を進める上での第1の柱としており、本年6月末までとしていた「あなたは大丈夫?キャンペーン」を本年8月末まで延長・拡大するなど、制度の周知に努めています。
金融庁では、これらの取組みの一環として、7月23日に、改正貸金業法に関する相談等の受付窓口として、『貸金相談デスク』を開設することとしました。『貸金相談デスク』においては、
- 貸金業法の改正により金利が下がったが、6月18日以前に契約した借入にも適用されるのか
- 年収証明書の提出を求められたが、提出しないと今後貸してもらえなくなるのか
といった、改正貸金業法に係る問い合わせや、貸金業者からの借入についての相談を受け付けています。
質問、相談等ございましたら、是非一度、貸金相談デスク(以下)へお問い合わせ下さい。
金融庁としては、今後とも、関係機関等とも連携しながら、相談の充実・強化を図るとともに、制度の周知徹底と実態把握に努めていきます。
| 名称 | :「貸金相談デスク」 |
| 開設日 | :平成22年7月26日 |
| 開設期間 | :平成22年12月28日まで |
| 受付時間 | :平日10時00分~18時00分 |
| 電話番号 | :0570-001127 ※IP電話・PHSからは03-3506-7229におかけください。 |
| 受付内容 | :改正貸金業法に関する相談等 |
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「貸金相談デスクの開設について」(平成22年7月23日)にアクセスしてください。
平成21年度における地域密着型金融の取組み状況について
金融庁においては、地域金融機関が行う地域密着型金融に関して、年1回、取組み実績や利用者等の評価について取りまとめを行っています。
本年7月23日に、平成21年度における地域密着型金融の取組み状況について取りまとめ、公表しました。概要は以下のとおりです。
対象金融機関は、地域銀行106(埼玉りそな銀行を含む)、信用金庫272、信用組合159の計537機関(公表日現在)です。
1.地域金融機関の取組み実績
各金融機関の取組み実績や成果について、各金融機関の公表や業界団体の取りまとめをもとに主な傾向をまとめれば、以下のとおりです。
(1)ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
○創業・新事業支援
創業・新事業支援に係る融資件数は前年度に比べ増加しています。企業育成ファンドの活用は前年度に比べ減少しています。
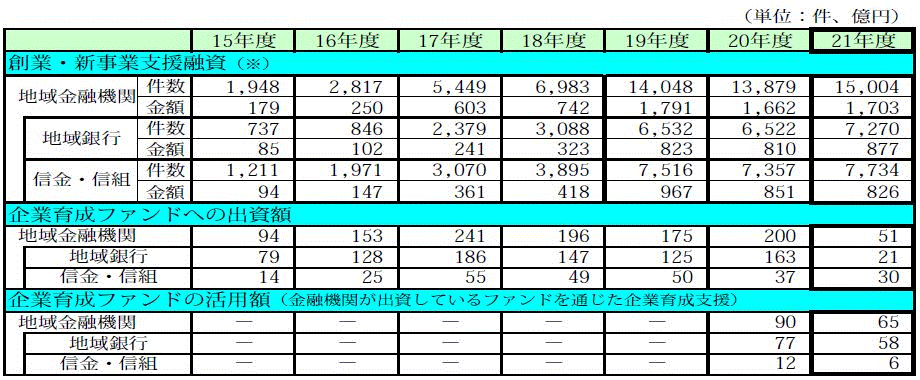
(※)18年度以前は「創業等支援融資商品による融資」。19年度以降は専用の融資商品の実績だけでなく、通常の融資による支援実績も含めて計上しているため、過年度の実績とは単純に比較できない。
○経営改善支援
経営改善支援取組み先のランクアップ率は前年度に比べ低下しています。ビジネスマッチングの成約件数は前年度に比べ増加しています。
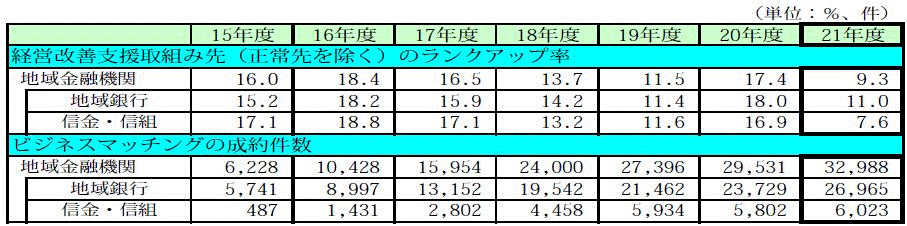
○事業再生支援
中小企業再生支援協議会と連携して支援し再生計画策定に至った件数、金融機関独自に支援し再生計画策定に至った件数は前年度に比べ増加しています。整理回収機構の支援決定の件数は前年度に比べ減少しています。
DDS(デット・デット・スワップ)やDES(デット・エクイティ・スワップ)の件数は前年度に比べ増加しています。一方、企業再生ファンドの活用は前年度に比べ減少しています。
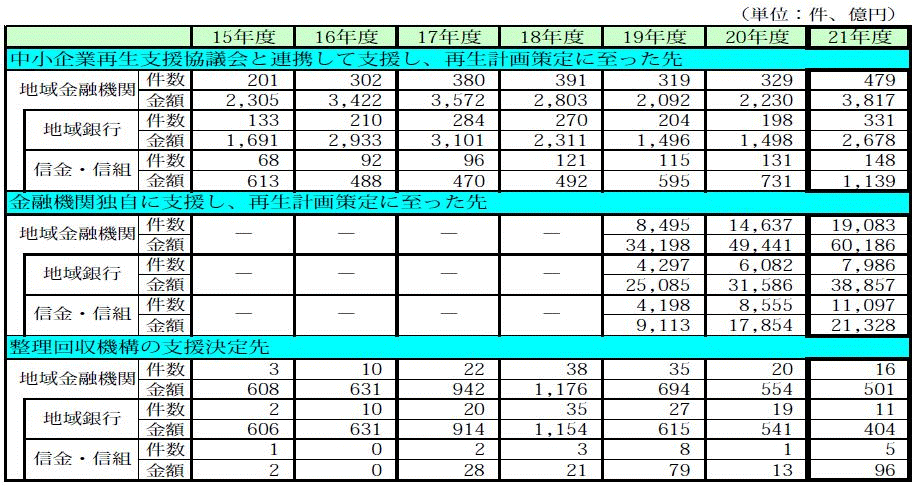
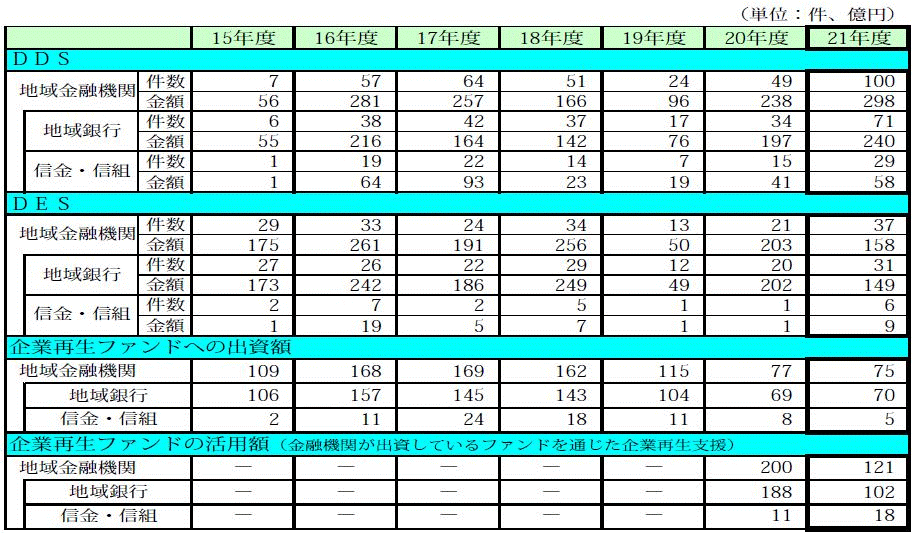
○事業承継支援
事業承継に係るM&A支援件数は前年度に比べ減少しています。

(2)事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
(3)地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
2.金融機関の実務者の評価
金融機関の実務者に対するアンケート調査の結果によると、各施策の取組みに対する評価は、事業承継支援を除き、「利用者の期待に応えるものとなっている」との評価が「期待に応えるものとなっていない」との評価を上回っています。
利用者の期待に応えるものとなっている主な理由として「利用者ニーズを的確に把握」が挙げられているが、他方、期待に応えるものとなっていない理由をみても、一部の項目では「利用者ニーズの把握が不十分」との回答が相応の割合を占めています。
また、期待に応えるものとなっている主な理由として「外部機関等の活用・連携が有効に機能」が挙げられていますが、他方で、期待に応えるものとなっていない理由として「内部に専門的なノウハウ・人材の蓄積がない」が最も多く挙げられているなど、内部の専門的なノウハウや人材の不足を外部機関の活用によって補っている状況も伺えます。
地域密着型金融が地域金融機関の経営にもたらす効果については、施策によって異なる面もありますが、債務者の財務状況等の継続的なモニタリングによる信用リスク管理の強化や取引先の経営改善等による債務者区分のランクアップ等の直接的な効果のほかに、職員の審査能力の向上や顧客・地域との信頼関係の向上等の間接的な効果も現れていると評価しています。
| 利用者の期待に応えるものとなっている | 応えるものとなっていない | |
|---|---|---|
| 創業・新事業支援 | 71.1 | 25.7 |
| 経営改善支援 | 87.3 | 10.5 |
| 事業再生支援 | 68.2 | 26.2 |
| 事業承継支援 | 44.1 | 47.1 |
| 担保・保証に過度に依存しない融資等 | 85.6 | 12.4 |
| 企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力の発揮 | 59.9 | 35.7 |
| 人材育成 | 68.6 | 27.6 |
| 地域全体の活性化等を視野に入れた面的再生 | 58.9 | 33.5 |
| 地域活性化につながる多様なサービスの提供 | 77.4 | 18.8 |
3.利用者等の評価
利用者等の評価に関するアンケート調査の結果によると、地域密着型金融の取組み全体については、積極的評価(「大変進んでいる」及び「進んでいる」の合計)が引き続き5割程度となっています。
また、個々の施策については、事業再生支援、事業承継支援、企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力の発揮など、積極的評価の割合が小さいものが多くなっています。
なお、個々の施策によっては、金融機関の取組みが進んでいるのかどうか「わからない」と回答する利用者が多いものもあります。
| 積極的評価 | 消極的評価 | わからない | |
|---|---|---|---|
| 地域密着型金融の取組み全体 | 51.1 | 29.6 | 19.3 |
| 創業・新事業支援 | 33.9 | 36.1 | 30.0 |
| 経営改善支援 | 41.9 | 33.2 | 24.9 |
| 事業再生支援 | 20.4 | 34.9 | 44.7 |
| 事業承継支援 | 22.9 | 32.5 | 44.7 |
| 担保・保証に過度に依存しない融資等 | 29.8 | 47.4 | 22.8 |
| 企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力の発揮 | 20.9 | 49.1 | 30.0 |
| 人材育成 | 26.2 | 34.6 | 39.2 |
| 地域全体の活性化等を視野に入れた面的再生 | 28.2 | 36.5 | 35.3 |
| 地域活性化につながる多様なサービスの提供 | 31.9 | 40.7 | 27.4 |
4.今後の課題
(1)平成21年度における地域金融機関の取組み状況をみると、経営改善支援、中小企業再生支援協議会の活用や金融機関独自の再生計画策定による事業再生支援、中小企業金融の円滑化に向けた担保・保証に過度に依存しない融資など様々な取組みが行われており、総じて実績が上がってきています。
(2)金融機関の実務者の評価をみると、多くの地域金融機関は、各施策の取組みが利用者の期待に応えるものとなっていると評価しています。そうした中で、利用者の期待に応えるものとなっていない理由として、内部の専門的なノウハウ・人材の不足が多く挙げられており、人材の育成や外部機関等の活用によるノウハウの蓄積が課題と考えられます。
(3)一方、利用者等の評価をみると、地域密着型金融の取組み全体については積極的評価が引き続き5割程度、個々の施策については取組みがなお不十分と評価されているものが多いなど、利用者の評価と金融機関の評価には開きが見られます。
なお、個々の施策によっては、地域金融機関の取組みが進んでいるのかどうか「わからない」と回答する利用者が多いものもあり、取組みの成果が利用者から見えにくい施策については評価が厳しくなりがちな面があることにも留意する必要があります。
(4)地域金融機関においては、今後も引き続き、人材の育成や外部機関の活用等を戦略的に行いつつ、目利き能力の向上やノウハウの蓄積に努め、利用者の期待やニーズに的確に対応するための取組みを組織全体として継続的に進めていくことが重要であると考えられます。
また、そうした取組みの成果について、利用者に分かりやすい形で積極的に情報発信していく努力も重要であると考えられます。
※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成21年度における地域密着型金融の取組み状況について」(平成22年7月23日)にアクセスしてください。
「金融検査指摘事例集」の公表について
金融庁は、平成22年7月21日に、「金融検査指摘事例集(平成21検査事務年度)」を公表しました。
1.金融検査指摘事例集
金融検査指摘事例集は、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるとともに、金融機関の自己責任原則に基づく内部管理態勢の強化等を促す観点などから17年から作成・公表しています。
本事例集は、21検査事務年度(平成21年7月~22年6月)に検査が終了(検査結果通知)した事例を基に作成しています。
今回の指摘事例集の特徴は、以下のとおりです
(1)「金融検査におけるベター・レギュレーションに向けた取組み(アクションプランII)」に掲げる「金融機関等との対話の充実・情報発信の強化」を推進するため、事例数の充実に努めています(注)。
なお、本事例集の構成は、昨年(21年12月)改定された「金融検査マニュアル」等の構成に従い、「経営管理(ガバナンス)」、「金融円滑化編」、「リスク管理等編」としています。
(2)金融機関の円滑な金融仲介機能の発揮が期待されている状況等を踏まえ、昨年末に「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」(43事例)を公表していますが、本年度版でも、本年6月までに通知された検査結果通知の中から事例を選定し、「金融円滑化編」で紹介しています。
(3)また、今回、指摘事例集の「別冊」として、新たに「金融グループ管理態勢」、「システムリスク管理態勢」、「外国銀行在日支店等」、「反社会的勢力に係る管理態勢」、それぞれについて事例集を作成しています。これらは、近時、金融機関にとって適切なリスク管理が求められている分野について、金融機関の自律的な態勢強化等を促すため、16年度以降に公表してきた指摘事例集の中から、参考となる事例を選定したものです。
(注)掲載事例数は、「金融検査指摘事例集」においては、評定事例47事例、指摘事例305事例となっています。また、「別冊」においては、金融グループ関係35事例、システムリスク関係87事例、外国銀行在日支店等関係59事例、反社会的勢力関係42事例となっています。全体で総計575事例(昨年度版は433事例)をとりあげています。
2.意見申出事例集
意見申出事例集は、意見申出制度導入(12年1月)以降の意見申出事案の中から、金融機関の業務運営上の参考となるものを選定し、その概要を紹介するため17年から作成・公表しており、毎事務年度、事例を追加して改訂を行っています。
しかしながら、21検査事務年度においては、金融機関にとって参考となる事例数が少ないことなどから、申出機関数・事案数の公表に留めています。
なお、21検査事務年度における意見申出実績は、2機関、15事案となっています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『「金融検査指摘事例集」等の公表について』(平成21年7月3日)にアクセスしてください。
また、過去の事例集については、平成16検査事務年度版(平成17年7月27日)、平成17検査事務年度版(平成18年7月5日)、平成18検査事務年度版(平成19年7月5日)、平成19検査事務年度版(平成20年7月4日)、平成20検査事務年度版(平成21年7月3日)、「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」(平成21年12月17日)の報道発表資料をご覧ください。

 検索
検索