【特集】
1.はじめに
本年10月1日(月)、郵政民営化が実施され、日本郵政株式会社を持株会社に、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険を子会社とする日本郵政グループが発足しました。今後、民間金融機関となったゆうちょ銀行・かんぽ生命保険については、金融庁で監督することになります。
そこで、郵政民営化の概要にも触れながら、ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険に対する監督体制等についてご紹介します。
2.郵政民営化の概要
(1)郵政民営化までの経緯
| 平成16年9月 | 「郵政民営化の基本方針」が閣議決定 |
| 平成17年10月 | 郵政民営化関連6法(郵政民営化法等)が成立 |
| 平成18年1月 | 日本郵政株式会社が発足 |
| 平成18年1月 | 「日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画」が決定 |
| 平成18年4月 | 郵政民営化委員会が郵政民営化推進本部の下に設置 |
| 平成18年12月 | 「郵便貯金銀行及び郵便保険会社の新規業務の調査審議に関する所見」を民営化委員会が公表 |
| 平成19年4月 | 「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」を日本郵政株式会社が提出 |
| 平成19年6月 | 実施計画に対する郵政民営化委員会の意見が公表 |
| 平成19年9月 | 総務省及び金融庁が実施計画を認可1 |
| 平成19年10月 | 郵政民営化の実施 |
(2)郵政民営化のスケジュール
○準備期(平成19年9月末まで)
準備会社として日本郵政株式会社が設立され、その下に、同様に準備会社として株式会社ゆうちょ・株式会社かんぽが設立されました。また、郵政民営化推進本部の下に、郵政民営化委員会が設置されましたが、その役割は、○主務大臣が新会社の業務拡大等の認可等を行う際に意見を述べること、○3年ごとに郵政民営化の進捗状況について総合的な見直しを行い、その結果に基づき郵政民営化推進本部長(内閣総理大臣)に意見を述べること等とされています。
○移行期(平成19年10月1日以降(最長で10年間))
日本郵政株式会社の下で、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、ゆうちょ銀行、及びかんぽ生命保険が営業を開始し、また、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を管理する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が設立されます。
この移行期間において、政府は、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分し(ただし、3分の1超は保有)、また、日本郵政株式会社は、その保有するゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の株式の全部を段階的に処分していきます。
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険は、この移行期間中、通常の銀行・生命保険会社と比べ、その業務範囲が制限されており、金融庁及び総務省による認可によって段階的に緩和されていくことになります。
○最終的な民営化の実現
遅くとも平成29年9月末までには、日本郵政株式会社は、その保有するゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の株式の全部を処分することとされています。完全民営化後は金融二社の業務範囲制限等は撤廃され、完全に他の民間金融機関と同様になります。
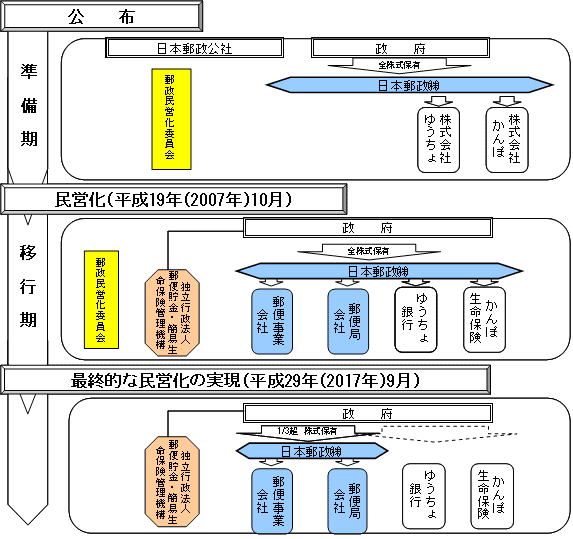
3.ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険に対する監督
(1)ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険について
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険は、本年10月1日、日本最大規模の銀行・生命保険会社として誕生しました。その規模は、以下のとおりとなっています。
-
資産 預金残高・保有保険金額 職員数 店舗数 ゆうちょ銀行 222.2兆円 187兆円 11,600名 234店舗 かんぽ生命保険 112.9兆円 153兆円 5,500名 81店舗 また、ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険は、郵便局ネットワークを利用し、銀行代理店の店舗は約2万4千局、保険募集人は約11万人となっています。
(2)監督体制
金融庁においては、今般、監督局に郵便貯金・保険監督参事官以下13名(平成19年10月1日現在)からなる郵便貯金・保険監督参事官室を設置しました。今後、当室において、銀行法上の銀行であるゆうちょ銀行、保険業法上の保険会社であるかんぽ生命保険、その金融持株会社としての日本郵政株式会社、及び銀行代理業者・保険募集人としての郵便局会社に対して、他の民間金融機関と同様の目線で適切な監督を行っていくこととなります。
具体的には、○適切な経営管理(ガバナンス)が行われているかどうか、○適切なリスク管理が行われ財務の健全性が確保されているかどうか、○コンプライアンス面を含め業務の適切性が確保されているかどうか、といった点をしっかりと見ていくことになります。
(3)業務範囲の拡大について
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の業務範囲については、郵政民営化法令において、○民営化当初は、日本郵政公社と同様になるようにし、○移行期間中においては、民営化委員会のご意見を聴取した上、他の金融機関等とのイコールフッティングの状況やゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の経営状況等を勘案しながら、段階的に緩和していく、○移行期間終了後は制限を撤廃する、という明確な枠組みが規定されています。
金融庁としては、ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険より新規業務の具体的な認可申請があった場合には、このような郵政民営化法令の枠組みに沿って、新規業務を行うに足る業務遂行能力・業務運営態勢の整備状況等を勘案しながら、適切に判断していくことになります。
4.おわりに
金融庁としては、郵政民営化について、郵貯・簡保事業が民間金融システムの中に混乱を起こすことなくうまく溶け込むことによって、日本の金融システム全体としての安定と活性化に寄与し、利用者利便の向上に資することが重要と認識しています。
今後もこうした観点を踏まえ、金融監督当局の立場から適切に対応していきたいと考えています。
(参考)
郵政民営化に伴い、改正されました政府令等に関する報道発表等のリンク先を表記しましたので、アクセスしてください。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令について(9月27日発出)
- 郵政民営化法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について(9月27日発出)
- 「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(案)」等にするパブリックコメントの結果について(9月20日発出)
- 「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果について(9月20日発出)
- 日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の認可(9月10日発出)
1「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の認可」(平成19年9月10日)を参照。
【金融便利帳】
※このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、分かりやすく解説するものです。
〇認定投資者保護団体制度とは
本年9月30日に施行された金融商品取引法(以下、「金商法」という。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、新たに金融商品取引業協会に関する章を設け、その中において、 「有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」として、「認可金融商品取引業協会」、「公益法人金融商品取引業協会」および「認定投資者保護団体」に関する規定を整備しています。
これは、新たに金融商品が次々と販売されるようになっていく中で、利用者保護および市場の公正確保と金融イノベーションの促進を図ろうとするには、法令に基づく規制のみによることは困難な面があるため、行政を補完する自主規制機関がその役割を発揮することが重要との認識によるものです。
このうち、「認定投資者保護団体」の制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられた制度であり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。
認定投資者保護団体については、金融商品取引業協会の章に規定されているものの、金融商品取引業者以外の者も設立が可能であり、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。
また、認定投資者保護団体が取り扱える業務範囲は、金融商品取引業者の行う金融商品取引業だけに限定されておらず、例えば、保険会社が行う特定保険契約の締結のように、金商法と同等の行為規制が適用される業務についても幅広く対象としています。
〇認定投資者保護団体の認定の基準は
認定投資者保護団体として認定されるための要件としては、金商法上の認可協会または公益協会ではない法人等で、認定を取り消されて2年を経過しない者等の一定の欠格条項に該当しないことのほか、以下の基準が定められています。
○認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること
○認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識、能力、経理的基礎を有すること
○認定業務のほかに業務を行っている場合、それにより認定業務が不公正になるおそれがないこと
以上のように、金商法において認定基準の基本的事項が定めていますが、実際に認定の審査を行う担当者の目線を統一するためには十分でないこと、また、認定申請予定者に行政当局の考え方をあらかじめ示すことにより、行政の透明性及び効率性の向上に資するため、さらに具体的な規定として、「認定投資者保護団体についての指針」を告示として定めています。指針で定められている主なポイントは次のとおりです。
指針の主なポイント
(1) 提出書類の様式を規定
(2) 法に定める認定基準「業務の実施の方法に関する書類」の内容について規定
(3) 法に定める認定基準「業務の適正かつ確実な実施のための知識及び能力を明らかにする書類」の内容について規定
(4) 法に定める認定基準「経理的基礎を証する書類」の内容について規定
(5) 法に定める「認定基準」の審査として、申請者が認定業務を適正かつ確実に行うに足りる人的構成を有しないと認められることがないかを審査することを規定
(6) 法に定める「認定基準」の審査として、他に行っている業務に関与する人員が、当該他の業務を行うことによって認定業務が不公正になるおそれがあると認められることがないかを審査することを規定
〇金商法施行後の認定の状況は
金融庁は、9月30日付で社団法人生命保険協会に対し認定投資者保護団体の認定を行いました(認定第1号)。苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要であり、認定を受けた団体が当業務を適切に進め、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。
※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「認定投資者保護団体についての指針(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成19年9月27日)、「認定投資者保護団体の認定について」(平成19年10月1日)にアクセスしてください。

 検索
検索

