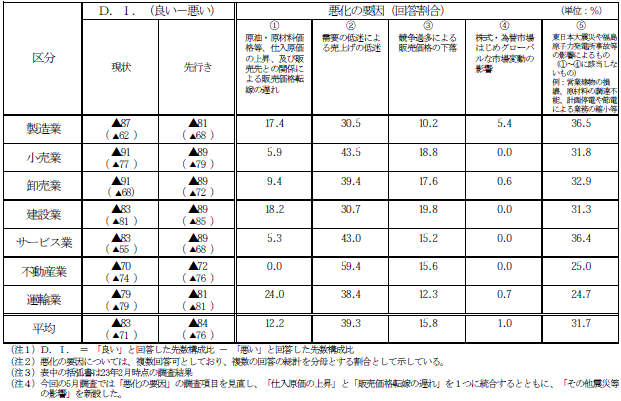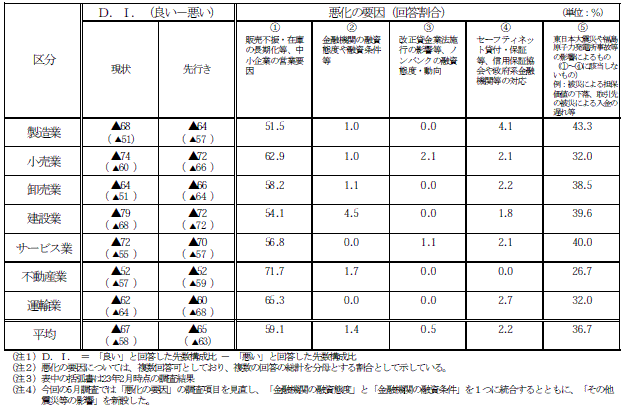アクセスFSA 第97号(2011年7月)

 |
 |
| 「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ 健全な消費者金融市場の形成に寄与した 金融機関」に対し顕彰する自見大臣(右) (6月20日) |
企業会計審議会総会・企画調整部会 合同会議で挨拶をする自見大臣 (6月30日) |
「東日本大震災関連情報」について
平成23年(2011年)東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。
金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。
1.東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています!
金融庁では、ウェブサイト上の「東日本大震災関連情報」ページにおいて、以下の項目別に情報提供をしています。
(1)預金者の皆さまへ
○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。
○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。
○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めています。
○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座があったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。
○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金融機関があります。
○なお、多くの方々の災害義援金により被災者の皆様方を支援することや、生活の建て直しを図ろうとする被災者の方々が銀行口座等を円滑に開設できるようにすることが極めて重要であることから、本人確認手続きについて必要な施策を講じています。
詳しくは、こちらをご参照ください。また、義援金等を装った詐欺にご注意ください。
当面の措置について
○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。
○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分(銀行等の取引停止処分等)は猶予されます。
○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
復興に向けて再スタートを切るにあたり、既往債務が負担となる方々へ
○金融庁は、いわゆる「二重債務問題」に関し、関係省庁と力を合わせて対応しています。政府が平成23年6月17日に策定・公表した「二重債務問題への対応方針」(内閣官房ウェブサイトへリンク)
 では、金融庁に関連する施策として、「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」、「金融検査マニュアルの運用明確化」といった施策が盛り込まれています。
では、金融庁に関連する施策として、「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」、「金融検査マニュアルの運用明確化」といった施策が盛り込まれています。○「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」については、金融庁がオブザーバーとして参加した「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」ウェブサイトへリンク)
 をとりまとめ、平成23年8月22日から適用を開始することとしています。震災の影響により、既往債務を弁済することができない、又は、近い将来に弁済できないことが確実と見込まれる個人の方々が、本ガイドラインに則して弁済計画案の作成等を行い、債権者との間で私的に合意(私的整理)することにより、法的倒産手続による不利益や信用情報機関への登録を回避しつつ、債務免除等を受けることができるようになります。
をとりまとめ、平成23年8月22日から適用を開始することとしています。震災の影響により、既往債務を弁済することができない、又は、近い将来に弁済できないことが確実と見込まれる個人の方々が、本ガイドラインに則して弁済計画案の作成等を行い、債権者との間で私的に合意(私的整理)することにより、法的倒産手続による不利益や信用情報機関への登録を回避しつつ、債務免除等を受けることができるようになります。○また、「金融検査マニュアルの運用明確化」については、「十分な資本的性質が認められる借入金」は、金融機関が債務者の財務状況等を判断(債務者区分)するにあたって、負債ではなく資本としてみなすことができる旨、「金融検査マニュアル」において記載されていますが、具体的にどのようなものが「十分な資本的性質が認められる借入金」に該当するのかについてより明確化してほしいとの要望がありますので、今後、その運用の明確化や周知の徹底を図る予定です。これにより、例えば震災の影響から債務超過に陥っている企業であっても、「十分な資本的性質が認められる借入金」を有する企業は、当該借入金を資本とみなすことにより、債務者区分が上昇し、新たな融資が受けやすくなるなどの効果が期待されます。
-
○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。
○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じた柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合については、保険協会や保険会社にご照会ください。
○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。
(4)上場企業等の皆さまへ
○東日本大震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置を延長するための政令を制定し、本年9月末までに提出すればよいこととしました。
○さらに、各取引所では、被災した会社の上場管理や、新規上場に係る審査等について、各種の取組みを行い、柔軟に対応することとしています。
(5)金融機関の皆さまへ
○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査定に係る特例措置及び運用の明確化を行っています。
○被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対応することとしています。
○また、被災地域等の金融機関が、中小企業金融円滑化法に基づく開示・報告を被災地域の実情に応じた形で行うことができるよう、開示・報告義務を弾力化することとし、内閣府令等を改正しました。
○更に、震災により、金融機関に様々な影響が生じうることを踏まえ、(1)地域における面的な金融機能を維持・強化するとともに、(2)預金者に安心していただける、万全の枠組みを設けるための、改正金融機能強化法が、平成23年6月22日に成立し、7月27日に施行されました。
○貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。
(6)金融機関等の相談窓口一覧
(7)プレスリリース一覧
(8)関連リンク
その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該情報は、日々更新しています。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重要な情報です」にアクセスして下さい。
2.東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて
金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及びQRコード(以下) からアクセスしてください。
3.金融庁ツイッターについて
金融庁では、ツイッターを活用して、東日本大震災関連の金融に関する情報を含め、金融に関する様々な取り組み等について、タイムリーな情報提供をしております。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁Twitter」![]() にアクセスしてください。
にアクセスしてください。
【震災関連トピックス】
「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について」の公表について
金融庁は、東日本大震災の影響により、上場企業が、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書など)について、同法に規定する提出期限までに提出できない可能性が生じているため、特例措置として、東日本大震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、今回新たに特例措置を延長するための政令を制定し、本年9月末までに提出すればよいこととしました。
この特例措置は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)」及び「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)」により、平成23年6月30日までに提出すればよいこととされていましたが、平成23年6月30日以後に本来の提出期限が到来する有価証券報告書等(例えば、3月決算の上場会社等の有価証券報告書)については、その提出期限までの提出が遅延する可能性があることから、当該有価証券報告書等に係る免責期限を延長するための政令を制定しました。
本政令の内容は以下のとおりです。
東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第4条第3項の規定に基づき、この特例措置の期限を延長するための政令を制定し、その期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長しました。なお、本政令は公布の日(平成23年6月22日)に施行されています。
本政令による延長の対象となる報告書は次のとおりです。
(1)有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)
(2)四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項)
(3)半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項)
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について」(平成23年6月22日)もしくは、「東日本大震災関連情報」の「上場企業等の皆様へ」から「有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について」(平成23年6月22日)にアクセスして下さい。
【その他のトピックス】
「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表」の公表について
「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日金融庁)においては、新興企業に対する適切な成長資金を供給する観点から、新興市場等の信頼性回復・活性化のために実施すべき事項が掲げられたところです。
また、その内容の具体化に向けては、金融庁に限らず、各取引所、日本証券業協会(以下「日証協」)、日本公認会計士協会(以下、「会計士協会」)等の市場関係者が主体となって検討を行い、具体的な取組みの実施期限を明確にした工程表を、平成23年前半を目途に作成・公表するよう求めていました。
これを受け、金融庁及び市場関係者による「新興市場等の信頼性回復・活性化策に係る協議会」において工程表が作成され、6月23日に公表されました(工程表のポイントは下記のとおりです)。
今後、市場関係者等が工程表に沿った取組みを進めていくこととなりますが、金融庁としては、市場関係者等による取組みに必要な協力を行うとともに、協議会の場を通して工程表の各取組みの進捗状況につき必要なフォローアップを実施することとしています。
(工程表のポイント)
1.上場前の企業の新興市場への上場促進
(1)グリーンシートの活用促進
日証協は、グリーンシートの役割・あり方について、非上場企業の資金調達機能を担ってきた経緯、本工程表に基づく新興市場に関する取組みの状況を踏まえ、抜本的な見直しを行う。〔平成24年3月までを目途〕
(2)一定の質が確保された上場前の企業のリスト化
経済産業省では、中小企業基盤整備機構との連携により、ベンチャーキャピタルが運営するファンドや投資先企業情報等のリストの作成、公表の準備が進められており、当該リストを活用する。今後の活用状況を踏まえ、市場関係者において、意見交換を行う。
2.上場審査等の信頼性回復・負担軽減等
(3)有価証券報告書等の虚偽記載の防止に向けた密度の高い情報共有
日証協は、会計士協会の協力を得て「連絡会」を設置し、今後、同連絡会において、主幹事証券会社、監査人及び取引所の間で有価証券報告書等の虚偽記載の防止に向けた密度の高い情報共有を図るための意見交換を進める。〔平成23年9月までを目途〕
(4)引受審査等における審査の適正化・明確化等
○日証協は、取引所及び証券会社等の協力を得て、反社会的勢力データベースの構築・照会に関する検討の終了後、速やかに、反社会的勢力以外の者で市場において市場の透明性・公正性の確保の観点から問題があるとされる者(いわゆる「反市場的勢力」)の取扱いを検討すべきではないかとの指摘等を踏まえ、市場関係者の認識の共有を図りつつ、必要な検討を進める。
○日証協は、上場に向けた必要な準備事項の概要(参考モデル)を策定する。合せて、日証協及び取引所において、同準備事項の概要(参考モデル)及び上場審査スケジュールの概要(参考モデル)について、それぞれのホームページ等により周知を行う。〔平成24年3月までを目途〕
○上場準備会社の初年度監査の「遡及的監査」に関して、次の環境整備に取組む。
i)「遡及的監査」では、監査範囲の制約により「無限定適正意見」以外の意見が付される可能性があることから、上場準備会社において、事前に社内管理体制の整備が進められるよう、会計士協会・監査法人において、上場に向けた必要な準備事項(監査スケジュールの概要を含めた参考モデル)等を整理する。合せて、会計士協会・監査法人、取引所及び証券会社等において、その周知を行う。〔平成24年3月までを目途〕
ii)現状、直前々期が「限定付適正意見」での上場が非常に少なく、「無限定適正意見」でないと上場承認が得にくいといった誤解が多いと考えられることから、取引所において、直前々期の「限定付適正意見」が許容可能であることの周知を図る。〔平成23年12月までを目途〕
iii)直前々期の意見不表明の可否については、遡及的監査の実施状況を踏まえつつ、いかにして投資者保護上の問題等を解決できるかについて、引き続き、金融庁及び市場関係者において意見交換を行う。
3.上場企業に対する負担の軽減及び適切な上場管理の実施
(5)内部統制報告制度の見直し
○監査法人及び取引所において、今回の内部統制報告制度の見直し内容及び「内部統制報告制度に関する事例集」について、引き続き、上場会社及び上場準備会社に周知を図る。
○今後、開示企業及び市場関係者から、具体的な事例についての意見があれば、それを集め、金融庁において、「内部統制報告制度に関する事例集」の充実を図る。
(6)成功例を積極的に生み出すための支援の重点化
各市場関係者のこれまでの取組状況等について紹介。
(7)リスク情報を含めた継続的な情報発信・開示の促進
取引所は、今後段階的に、新興市場の上場企業の大まかな業種や特性に応じたリスク情報の類型化に必要な基礎データの整理等を行い、公表する。
4.新興市場からの他の市場等への移行等
(8)新興市場の位置づけの明確化
各取引所において、新興市場の位置づけについて検討を行い、その明確化を図るため、各取引所・市場の実情を踏まえ、必要な措置を講じる。〔平成24年3月までを目途〕
(9)上場廃止銘柄の受皿の整備
日証協において、次の事項について検討を行う。〔平成24年3月までを目途〕
○フェニックス銘柄の指定基準、取扱期間
○仮に上場廃止となる銘柄が増加する場合に備えて、既存の取引所のシステムやPTSの利用、清算体制の整備、開示・売買管理体制等
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から『「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表」の公表について』(平成23年6月23日)にアクセスして下さい。
また、上記の工程表については、下記の各機関のウェブサイトに掲載されています。
「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」について
中小企業金融の実態把握の一環として、平成23年5月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は以下のとおりとなりました。
なお、平成23年3月に東日本大震災が発生したことに伴い、悪化の要因に係る調査項目を見直しています(注4参照)ので、前回調査(平成23年2月調査)結果と単純に比較できないことにご留意ください。
1.中小企業の業況感は、東日本大震災の影響もあり、厳しさを増しています。現状D.I.は、平成22年2月調査以来、5四半期ぶりにマイナス幅が拡大しています。
悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影響」となっています。
2.中小企業の資金繰りも、東日本大震災の影響もあり、厳しさを増しています。現状D.I.は、平成22年2月調査以来、5四半期ぶりにマイナス幅が拡大しています。
悪化の要因としては、「中小企業の営業要因」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影響」となっています。
(参考)東日本大震災に関連した主なコメントについては以下のとおりとなっています。
○店舗や工場等の建物等が損壊したことにより、営業が継続できない、または困難となっている(福島‐製造業、茨城‐小売業 ほか)
○機械が破損し、これに対する補填のための費用負担が増加している(福島‐製造業)
○部品、建築資材等の原材料や商品の調達が不能または困難となった結果、営業ができず売上げが減少している(長野‐製造業、鹿児島‐小売業、山口‐建設業 ほか)
○部品の供給停止や原材料の入荷に対する不安から、先行きが不透明である(長野‐製造業)
○夏場の電力不足や節電が生産活動に影響を及ぼす懸念があり、消費減退が予想される(山形‐製造業、福岡‐製造業、大分‐小売業、大阪‐中小企業全体 ほか)
○様々なものが自粛傾向にあるため、売上げ・収益が上がらない(北海道‐中小企業全体、埼玉‐中小企業全体 ほか多数)
○宿泊やイベント等のキャンセルにより販売不振・受注減少が見られる(茨城‐サービス業、奈良‐サービス業、岐阜‐卸売業 ほか多数)
○過度の自粛ムードは、消費の低迷を招き、復興の妨げになることを危惧している(香川‐小売業)
○被災地に取引先がある企業は、入金の遅れ等により収益状況が厳しい(岩手‐中小企業全体)
○被災企業の売掛金回収が困難となっている(山形‐製造業、岩手‐サービス業)
○原発に絡む出荷制限や風評被害によって、経済活動の縮小が懸念される(福島‐中小企業全体)
○風評被害による農・水産品の売上げの減少や観光客数の減少等を懸念している(新潟‐小売業、岐阜‐サービス業 ほか)
○特産の農産物等の運送需要期に、放射能汚染の風評が立つことにより影響が出ないか懸念している(山形‐運輸業)
○原発事故による風評や、放射線の影響による仕入れの先行きを不安視している(茨城‐卸売業、長野‐卸売業)
○自家発電設備など震災需要により受注が増えたものの、部品や資材の入手難などの問題を抱えている(愛知‐製造業、香川‐製造業、栃木‐建設業)
○小売店・コンビニでは生活必需品に震災需要がみられた。また、仙台圏からの買い物客も多く見られた(山形‐小売業)
○一部で震災需要が見込まれるが、一時的なものであることを懸念している(宮城‐不動産業、宮城‐中小企業全体)
○金融機関が新規融資や条件変更に前向きである(神奈川‐中小企業全体、愛媛‐中小企業全体 ほか)
○計画的に改善・革新に取り組む事業者には、金融機関も資金応需している(千葉‐卸売業)
○金融機関からの災害貸付等の資金調達により、資金繰りは緩和されている(宮城‐製造業 ほか)
○金融機関は、震災により影響を受けた事業者に対して、柔軟かつ迅速な対応をしている(千葉‐製造業 ほか)
○被災地の復興財源に充てるため、国の公共工事予算の削減が懸念される(山形‐建設業、島根‐建設業 ほか)
○公共工事予算が東北復興に重点配分されることが予想され、業者過多のなか、受注獲得競争が厳しく、資金繰り悪化の状況が続くものと思われる(静岡‐建設業、三重‐建設業、高知‐建設業)
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要(平成23年6月22日)にアクセスしてください。
「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ健全な消費者金融市場の形成に寄与した金融機関」に対する大臣顕彰について
改正貸金業法は、昨年6月18日に完全施行されましたが、金融庁においては、「改正貸金業法フォローアップチーム」を設置するなどして、制度の周知徹底、施行状況や影響等についての実態把握、制度のフォローアップ・点検などを行っています。
本フォローアップチームおいては、これまで4回にわたり関係者ヒアリングを実施しましたが、そのなかで、
○積極的に消費者向けローンを実施する取組み。
○多重債務相談と融資を組み合わせ、多重債務問題の解決に資する取組み。
などの地域金融機関における健全な消費者金融市場の形成に向けた優れた取組み事例が明らかになってきました。
このような取組みがさらに広がることを期待して、特に優れた取組みを行った8つの金融機関を、6月20日に自見大臣から顕彰いたしました。顕彰された金融機関とその取組みの概要は、次の通りです。
| 金融機関 | 取組みの概要 |
|---|---|
| 一関信用金庫 | 栗原市及び仙台弁護士会との提携による多重債務者対策や自殺防止対策等に資する「栗原市のぞみローン」の実施など。 |
| 多摩信用金庫 | 基本スタンス(困っているお客様の相談に応じていくこと)に基づく消費者ローン相談窓口の設置、「顔の見える関係」を重視した訪問活動の実施、融資後のモニタリングの実施など。 |
| 青和信用組合 | 多重債務相談室の設置、多重債務者対応マニュアルの整備、融資後の訪問活動による家計収支改善の進捗管理の実施など。 |
| 塩沢信用組合 | 多重債務相談態勢としての地元自治体と連携した相談窓口の設置、「個人の救済支援おまとめローン」の実施など。 |
| 尾西信用金庫 | 消費者ローン利用者のデータ分析等に基づく顧客のニーズに応じた対応の実施、高い頻度での訪問による顧客の問題解決に注力など。 |
| 但陽信用金庫 | 「よろず相談室」の設置、多重債務相談について弁護士・司法書士等と連携した対応、「生活再生ローン」の実施、融資後のモニタリングの実施など。 |
| 遠賀信用金庫 | 相談窓口である「暮らしの安心コーナー」の設置、多重債務相談について司法書士会と連携した対応、啓蒙用チラシ(年間約300万枚)の配布など。 |
| 南郷信用金庫 | 時間外の消費者ローン等相談窓口の設置、多重債務者相談マニュアルの整備、多重債務相談について弁護士・司法書士等と連携した対応など。 |
金融庁としては、引き続き、全国の都道府県、財務局における多重債務相談窓口の周知・広報を徹底していくとともに、各金融機関における、健全な消費者金融市場の形成に向けた取組みを強く促してまいります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ健全な消費者金融市場の形成に寄与した金融機関」に対する大臣顕彰について(平成23年6月20日)にアクセスして下さい。

 検索
検索