アクセスFSA 第64号(2008年3月)
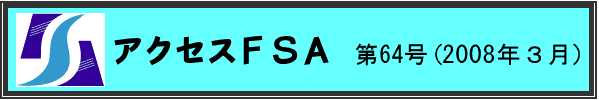
 |
 |
|
| 金融庁入庁式の模様(4月1日) | 企業会計審議会総会において挨拶する 山本 副大臣(3月27日) |
【トピックス】
新EDINETシステムの稼動開始について
金融庁では、平成20年3月17日より新EDINETシステムの稼動を開始しました。新システムは、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」に基づき開発されたもので、EDINETをより利便性高く、効率的で、かつ安全なシステムとし、ディスクロージャー制度をより有効かつ信頼性の高いものとすることを目的としたものです。
新システムの稼動に伴い、従来のシステムは停止しています。新EDINETに接続する際のURLは以下のとおりです。
- 書類提出用「http://www.edinet-fsa.go.jp/
 」
」
1. 新EDINETシステムの概要
(1) 新システムの主要なポイントは次のとおりです。
(a) XBRL導入による高度な情報利活用の実現
(b) 検索機能の強化等による利便性の向上
(c) セキュリティの強化
(d) システム運用効率の向上による行政コストの削減
(2) 旧EDINETシステムからの主な変更点
(a) EDINETコード体系の変更
(b) 端末の推奨環境の拡充
(c) 検索機能の変更
詳細については、「新旧EDINET移行ガイド」をはじめとする各種操作ガイドを参照してください。
各種操作ガイド:
なお、提出書類データ作成時における変更点については、下記図1を参照してください。
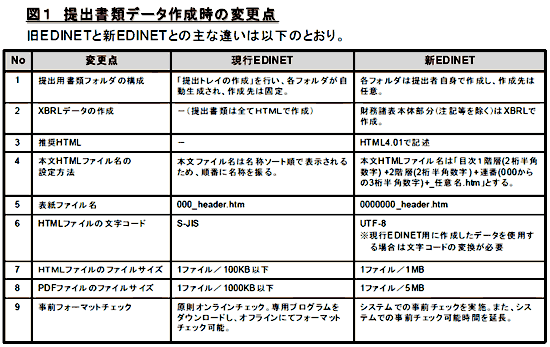
2. XBRL導入について
開示書類等提出者は、平成20年4月1日以後開始事業年度に係る有価証券報告書をEDINETへ提出する場合、財務諸表をXBRL形式により提出することとなります。
XBRL(eXtensible Business Reporting Language)とは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるように、国際的に標準化されたコンピュータ言語です。XBRLは、XMLというコンピュータ言語を基として開発されたものであり、コンピュータが理解可能な形で情報の構造化及び情報への意味付けを可能とします。新EDINETシステムにXBRLを導入することによって投資家等は、有価証券報告書等の情報をダウンロードし、直接コンピュータによる加工・分析等ができるなど、高度な情報利活用が可能となります。
XBRLの提出は、特定有価証券の発行者を含む全ての開示書類提出者が対象となります。XBRLの対象範囲、適用時期等については、下記図2~5を参照してください。
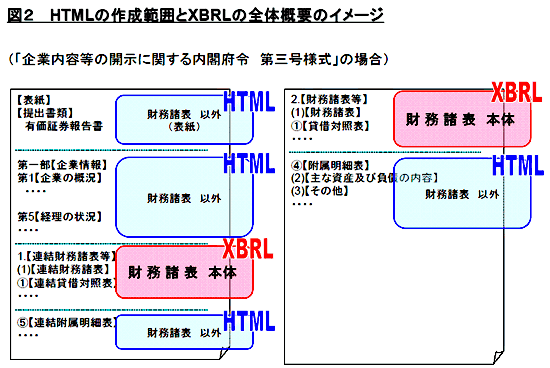
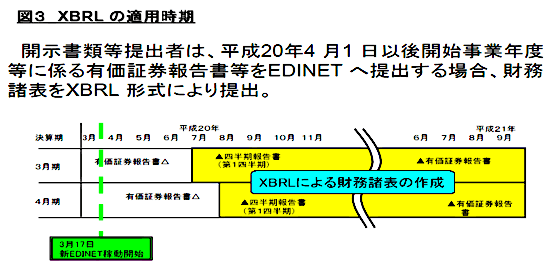
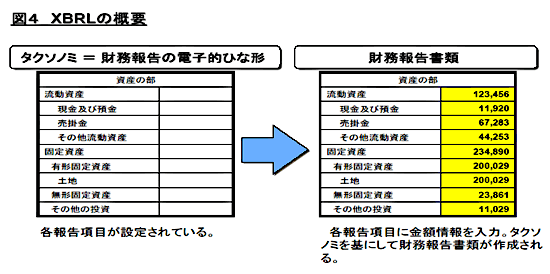
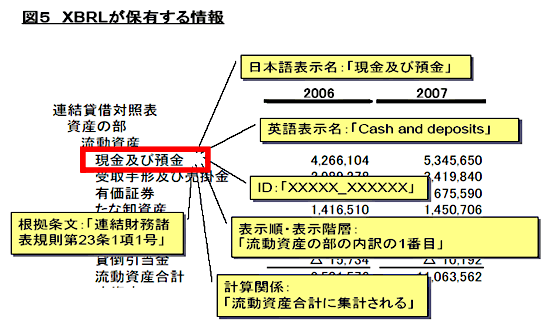
今般のEDINETへのXBRL導入は、財務情報を中心とした企業情報のディスクロージャーを高度化することで、証券市場の透明性を向上させるのみならず、社会経済活動の効率化にもつながるインフラ整備の一環であると考えます。提出会社や投資家等の関係者は、XBRL導入のメリットを理解し、積極的な対応を行って頂くことが重要となります。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「新EDINETシステムの稼動開始(3月17日)について」(平成20年3月17日)にアクセスしてください。
「金融商品取引法の疑問に答えます」の公表について
昨年9月30日に金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)が施行されて、6ヶ月が経過しました。金商法は、一般の投資者が安心して投資参加できるための制度インフラを整備し、「貯蓄から投資へ」の流れをより確実なものにしていこうとするものです。すなわち、投資者が安心して投資参加できるためには、金融商品販売の現場において、顧客それぞれの投資経験・ニーズ等に照らして、ふさわしい金融商品が、ふさわしい方法で提供されていくことが重要であり、金商法は、そのための法的な枠組みを整備しておくという、極めて常識的なねらいを持って制定されたものです。
しかしながら、その後、金融機関等の方から伺うところ、あるいは、金融庁の金融サービス利用者相談室などに一般投資者の方から寄せられるところによると、金融商品販売の現場においては、しばしば形式主義に偏した対応がとられ、時として、法令の趣旨から乖離した過剰ともいえる結果になっていることがあると聞きます。
そこで、金融庁ではこれまでの回答事例等をも踏まえて、今般2月21日、質疑応答集「金融商品取引法の疑問に答えます」をとりまとめ、公表しました。
この質疑応答集には、2つのねらいがあります。
1つのねらいは、法令の本来の趣旨と異なる、誤解とも言いうる顧客対応の事例について、その代表的なものを整理し、それらについての当局の考え方を示すことによって、金融商品販売の現場において、過不足のない対応がとられていくことを期するものです。
もう1つのねらいは、こうした考え方を当局において整理し、徹底することによって、当局サイドの各担当者においても、法令の本来の趣旨を踏まえたセンスのよい運用が行われていくことを期するものです。
質疑応答集は、全部で9つの質疑応答からなっており、その内容は、適合性原則、説明義務、広告規制、契約締結前交付書面、業規制の各分野をカバーしています。なお、質疑応答集原文の終わりに注記されているように、本質疑応答集は、「照会がなされた文脈を踏まえて、法令との関係について、その時点における見解を示したものである」ことに留意が必要です。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『金融商品取引法の疑問に答えます』の公表について」(平成20年2月21日)にアクセスしてください。
「内部統制報告制度に関する11の誤解」について
平成18年6月に成立した金融商品取引法により、上場会社を対象に、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の「評価」と監査人の「監査」を義務づける内部統制報告制度が、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されました。
この内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけることなく、効率性と有効性のバランスをとりながら整備することとを目指しており、昨年2月15日に企業会計審議会から公表されました、本制度における経営者の評価と監査人の監査を実施するための基準及び基準を実務に適用していくための実務上の指針(以下、「基準等」といいます。)などにおいてもそうした考え方が示されています。
すなわち、基準等においては、財務報告に虚偽記載の発生するリスクを的確に把握して、これに対応した内部統制を整備していただくことを強調しており、各企業においては、こうした基準等の趣旨を踏まえ、真にリスクのあるところには、適切な内部統制の整備を行い、重要性の乏しいところには、効率的にその整備を行うなど、それぞれの企業の状況等に応じて、創意工夫をこらして内部統制の整備を行っていただくことが期待されています。
しかしながら、内部統制報告制度に向けた準備作業において、実務の現場では、一部に誤解に基づいた過度に保守的な対応が行われているともいわれており、金融庁では、そうした指摘も踏まえ、「![]() 内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表し、改めて制度の意図を説明することとしました。
内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表し、改めて制度の意図を説明することとしました。
具体的には、
(a)米国SOX法のように、「どのような小さな業務でも内部統制を整備評価しなければならない。」、「膨大な文書化が必要」という誤解に対しては、重要な虚偽記載につながるリスクを抽出し、対象範囲を絞り込むことができること、「文書化」は必須ではないこと
(b)「内部統制の評価のために、期末に予定していたシステム変更や合併等の再編を延期しなければならない。」という誤解に対しては、予定通りシステム変更などを行っても内部統制は有効であり、監査人の監査意見も「無限定適正意見」を表明することができること
(c)「内部統制の評価結果に問題があると、上場廃止になったり、罰則の対象となる。」という誤解に対しては、内部統制に問題があっても、それだけでは、上場廃止や金融商品取引法違反にはならないこと
などを明らかにしています。
また、併せて公表しました「内部統制報告制度の円滑な実施に向けた行政の対応」においては、次のような対応を行うことによって、制度の実効性を確保しつつ、効率的・効果的な制度の実施を図ることとしています。
(1)内部統制報告制度の導入に向けた準備状況について、対象会社・監査人に対するヒアリング等を行い、準備段階における疑問点など把握します。
(2)その結果を踏まえ、基準等の内容の一層の明確化を図る観点から、(a)追加Q&Aの公表、(b)日本経団連、日本公認会計士協会、金融庁の間で共同の相談・照会窓口等の設置し、会社や監査人からの相談・照会に対応などを実施します。
(3)加えて、内部統制報告制度の導入にあたっては、過度に保守的な対応とならないよう、制度の円滑な実施の観点から指導中心の行政対応を行います。
※ ※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『内部統制報告制度に関する11の誤解』等の公表について」(平成20年3月11日)にアクセスしてください。
「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」の公表について
公認会計士・監査審査会![]() (以下、「審査会」といいます。)は、平成16年4月の発足以降実施した監査事務所に対する検査について、これまでも、結果の概要を公表してきました。
(以下、「審査会」といいます。)は、平成16年4月の発足以降実施した監査事務所に対する検査について、これまでも、結果の概要を公表してきました。
また、各監査事務所に対して原則として3年に1度実施されている日本公認会計士協会による品質管理レビューは、法定化されてから2巡目を迎えており、そうした中で、審査会としては、これまでの検査における具体的な指摘事例を提供することが、各監査事務所による監査の質の維持・向上を図るための自主的な取組みに資するものと考え、「監査の品質管理に関する検査指摘事例集![]() 」を取りまとめ、平成20年2月27日に公表しました。
」を取りまとめ、平成20年2月27日に公表しました。
1.事例集の対象とした検査
事例集において掲載対象とした検査は、平成16年4月から20年2月までに実施した合計30件です。今後は、事務年度ごとに見直しを行い、掲載事例の追加等を行う予定です。
2.事例集に掲載した指摘事例
事例集に掲載した指摘事例の中から、一部を次に紹介します。
なお、事例集において指摘していない事項はすべて適切であることを意味するものではないこと、また、事例集では、検査官が特定した改善を必要とする事項のうち、他の監査事務所においても参考になると思われる主なものを掲載しており、そのすべてを網羅的に掲載したものではないことに留意する必要があります。
<業務管理体制>
- 品質管理に関する方針及び手続において、監査事務所の最高経営責任者が、品質管理のシステムに関する最終的な責任を負っていることを明確にしなければならないにもかかわらず、内部規程において当該事項が定められていない。
<職業倫理及び独立性>
- 独立性の確認に関する責任者を定めておらず、独立性の確認が実施されていない。
<監査契約の新規の締結及び更新>
- 監査契約の新規の締結及び更新に係るリスク評価の検討過程や結果が文書化されていない。
<監査業務の実施>
- 監査実施者が監査計画段階において重要性の基準値を決定していない監査業務や監査計画段階において決定した重要性の基準値を意見形成時にのみ使用し、実施すべき監査手続の決定に利用していない監査業務がある。
- 廃棄品として評価減すべき棚卸資産について、被監査会社は評価減を行っていないにもかかわらず、監査実施者が棚卸資産の評価の妥当性について検討していない監査業務がある。
- 被監査会社から残高確認の選定対象を一部除外するよう要求され、正当な理由がないにもかかわらず、要求に従って除外している監査業務がある。
<監査調書>
- 監査調書の作成方法に関する具体的な内部規程がなく、また、教育研修や監査現場における指導監督が不十分であることから、監査調書に作成日付、作成者名及び調書番号等が記載されておらず、体系的に配列・整理されていない。
<監査業務に係る審査>
- 監査意見表明のための審査に関する方針と手続を整備しておらず、また、実際に監査意見の表明に先立って審査が実施されていない監査業務がある。
<品質管理のシステムの監視>
- 監査事務所としての品質管理及び個々の監査業務における品質管理のいずれの実施状況に関しても点検が実施されていない。
3.おわりに
審査会としましては、これまでに検査を実施した監査事務所のみならず、検査の対象とならなかった監査事務所においても、事例集の内容も踏まえて、監査の品質管理の一層の向上に努められることを期待しています。
※ 詳しくは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報一覧」から『「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」の公表について』(平成20年2月27日)![]() にアクセスしてください。
にアクセスしてください。
金融検査マニュアル・保険検査マニュアル等の一部改訂について
1.はじめに
金融庁は、昨年12月に銀行等による保険販売が全面解禁されたこと、本年2月の関係閣僚による「年度末に向けた中小企業対策」の申し合わせ等を踏まえ、本年3月17日、「金融検査マニュアル」、「保険検査マニュアル」、「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」、「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)」を一部改訂し、検査局長通達として発出しました(平成20年3月17日金検第109号)。
2.検査マニュアル改訂の経緯・概要
(a)銀行等による保険販売の全面解禁に伴う検査マニュアルの一部改訂
昨年12月22日に銀行等による保険販売が全面解禁されたことから、これに対応するため、銀行等による保険販売に関する検査マニュアルの一部改訂を行いました。(改訂対象:金融検査マニュアル、保険検査マニュアル)
改訂検査マニュアルでは、真に実効性のある保険契約者保護が確保されるためには、銀行等は自ら責任ある販売態勢、保険会社は銀行等の業務・組織等の特性を踏まえた代理店管理態勢を整備し、更には、保険契約者保護のために両者が必要な連携を行う態勢を整備することが必要との観点から、検証ポイントを記載しています。
具体的には、金融検査マニュアルにおいては、自ら責任ある販売態勢等の構築(販売後に発生する業務を含む)、保険募集における弊害防止措置等の確保、銀行等と保険会社との連携等に関する検証ポイントを記載し、保険検査マニュアルにおいては、銀行等の特性を踏まえた代理店管理を行うための態勢整備、銀行等と保険会社との連携等に関する検証ポイントを記載しています。
なお、これまでは銀行等による保険販売に関する保険会社・銀行等への検証ポイントは、いずれも「保険検査マニュアル」に記載していましたが、金融機関にとっての分かりやすさを向上させる観点から、検査の実態に合わせて記載することとし、銀行等に対する検証ポイントは「金融検査マニュアル」へ、保険会社に対する検証ポイントは「保険検査マニュアル」へ記載しています。
改訂検査マニュアルを活用した効果的な検査が行われることを通じて、保険契約者保護に資することが期待されます。
(b)十分な資本的性質が認められる借入金を資本とみなして査定する旨の改訂
本年2月20日に関係閣僚により申し合わされた「年度末に向けた中小企業対策について」において、「平成20年度に創設される中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本的劣後ローン)のような十分な資本性が認められる借入金は、これを資本とみなして融資先企業の債務者区分を査定出来る旨、金融検査マニュアルを改訂する。」とされたことを踏まえて、検査マニュアルの一部改訂を行いました。(改訂対象:金融検査マニュアル、保険検査マニュアル)
改訂検査マニュアルでは、資産査定における債務者区分の検討の際、債務者の実態的な財務内容の把握にあたり、十分な資本的性質が認められる借入金について資本とみなすことができ、例えば、償還条件について長期の期限一括返済となっていて、金利については赤字の場合利子負担が生じない等配当に準じた金利設定になっている劣後ローンは、十分な資本的性質が認められると考えられます。
なお、本取扱いはあくまでも借入金の実態的な性質に着目したものであり、債務者の属性や資金使途等によって制限されるものではありません。
今回の改訂検査マニュアルを通じて、中小企業の自己資本充実策拡大のための環境整備が進展し、中小企業の事業再生や新事業への取組みを促進する一助になることが期待されます。
(c)資産査定における金融検査マニュアルと保険検査マニュアルの整合性の確保
保険検査マニュアル付属資料「信用リスク検査用マニュアル」について、昨年2月の金融検査マニュアルにおいて改訂を行った『資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト「自己査定(別表1)」、「償却・引当(別表2)」』の内容に準じた見直しを行いました。
(d)その他
「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「事務ガイドライン」を「監督指針」に改める等の所要の見直しを行いました。(改訂対象:金融検査マニュアル、保険検査マニュアル、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕、信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕))
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」または「パブリックコメント」から、「金融検査マニュアル・保険検査マニュアル等の一部改訂について」(平成20年3月17日)にアクセスしてください。
特定保険業者に関する移行期間終了に伴う監督上の留意事項について
I.特定保険業者に関する移行期間終了について
1.平成18年4月の改正保険業法の施行により、施行前まで規制対象とされていなかった根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)は、「特定保険業者」として、当局の監督対象となりました。
2.あわせて、一定の事業規模の範囲内で、少額かつ短期の保険の引受けのみを行うことができる「少額短期保険業制度」が新たに導入されました。
3.特定保険業者は、平成18年4月から平成20年3月末までの間(移行期間)に、少額短期保険業者の登録等の対応を行うこととされました。
4.今般、当該移行期間の終了を迎えることとなったことから、金融庁は特定保険業者の少額短期保険業者等への円滑な移行、及び保険契約者等の保護をより確実なものとするため、以下の対応を行いました。
II.「特定保険業者に関する移行期間終了に伴う監督上の留意事項について」の概要
1.特定保険業者向けの対応
特定保険業者を監督している各財務局に対し、移行期間の終了時期を迎え、今後、各特定保険業者の状況に応じて、保険業法及び監督指針に基づきどのような手続きが必要であるかを実態に即して改めて説明するよう、指示を行いました。
2.保険契約者等向けの対応
移行期間終了後の特定保険業者の業務等について留意すべき点を周知するため、当庁ウェブサイト(一般のみなさんへ~保険を契約している方へ~「根拠法のない共済について」)の更新・拡充を行いました。
少額短期保険業者や特定保険業者等と保険契約を締結する場合や、現在締結している契約に関して、注意すべきポイント等を充実させています。
3.生命保険協会及び日本損害保険協会等への要請
社団法人生命保険協会及び社団法人日本損害保険協会等に対し、特定保険業者の円滑な移行に関する支援策の検討を要請しました。
III.おわりに
本年3月末をもって移行期間は終了しましたが、平成20年3月末までに少額短期保険業者の登録申請等を行った特定保険業者は、審査期間中は引き続き特定保険業を行うことができることとなっています。
一方、当該申請等を行わなかった特定保険業者は、平成20年4月以降、新規の保険の引受けはできなくなり、保険金の支払い等の管理業務を行いつつ、原則、平成21年3月末までに保有する保険契約を他の保険会社等に移転等の対応を行い、廃業することとなります。
金融庁としては、今後とも、特定保険業者の少額短期保険業制度等への円滑な移行及び保険契約者等の保護に万全を期すよう対応していきたいと考えています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「特定保険業者に関する監督上の留意事項について」(平成20年3月7日)にアクセスしてください。
金融行政アドバイザリーから寄せられた意見等について
平成20年2月29日、各財務(支)局に設置している金融行政アドバイザリーより、広く金融行政に関する意見等をいただいたことから、寄せられた意見等の概要及び金融庁としての対応方針を公表しました。
1.金融行政アドバイザリー制度について
金融行政アドバイザリー制度は、国民から、広く金融行政に関する意見や反響を的確に把握、収集することにより、金融行政の企画・立案及び事務運営の改善に役立て、金融行政サービスの一層の向上を図るとともに、国民への積極的な情報提供を行うことにより、金融行政に対する国民の理解の向上を図ることを目的とするものです。
金融行政アドバイザリーの任務としては次のとおりです。
(1)金融行政に関する意見等を報告すること。
(2)金融知識の普及、金融経済教育、利用者保護策、地域密着型金融の推進に係る取組み等の金融行政に関する広報に参画すること。
(参考)金融行政アドバイザリー委嘱状況
委嘱者数は各財務(支)局5名、合計55名。内訳は次のとおりです。
(a)金融機関の利用者(中小企業経営者等) 16名
(b)商工会議所の経営相談員、中小企業診断士、税理士、公認会計士等 15名
(c)消費者団体職員、地方公共団体(消費者相談窓口担当)の職員等 9名
(d)大学教授等の教育関係者、コンサルタント、ファイナンシャルプランナー等 15名
2.金融行政アドバイザリーから寄せられた意見等への対応方針
金融行政アドバイザリーから寄せられた意見等は、全体として、利用者保護への取組み強化や投資家に魅力ある市場となるような市場整備を求めるものが多く寄せられました。これらは金融庁としても注力すべき観点であると考えており、これまでも種々の取組みを行ってきたところですが、今後とも寄せられたご意見等をも踏まえより一層積極的に取り組んでいきます。主な意見等は下記のとおりです。
| 寄せられた意見等 | 対応方針 | |
|---|---|---|
| <バーゼルIIの実施(総論)> | ||
バーゼルIIでは、第1から第3の柱がワンセットとなって、銀行経営における健全性の向上、ひいては金融システムの安定に資することが期待される。(他11件) |
バーゼルIIは、自己資本比率の計算ルールである「第1の柱」に加え、金融機関の自己管理を促す「第2の柱」及び情報開示を通じた市場規律の活用に関する「第3の柱」といった枠組みが盛り込まれており、ご指摘のとおり、各金融機関の経営における健全性の確保、ひいては金融システムの安定に資するものであると考えております。こういった趣旨が活かされるよう、今後ともバーゼルIIの円滑な実施に取り組んでまいります。 |
|
| <金融商品取引法制> | ||
金融機関は借り手側の返済能力の審査・調査や、投資信託など金融商品のリスク説明を更に強化して欲しい。(他12件) |
金融機関における与信先の返済能力の適切な審査・調査や金融商品のリスク説明は重要と考えております。このため、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の中で、(a)与信先の財務状況、返済財源の的確な把握等、適切な審査管理体制、(b)リスク商品の販売・説明態勢の構築を求めています。金融庁としては、今後とも、このような監督指針等に基づき適切に対応してまいります。 |
|
徹底した利用者保護の実現が必要。金融商品取引業者へは徹底した法令遵守と広告、宣伝、勧誘規制を行う必要がある。(他10件) |
平成19年9月30日に施行された金融商品取引法においては、広告規制、契約前の顧客への書面交付義務やその説明義務など、金融商品取引業者等に対する利用者保護のための規制を整備してきたところです。今後は、これらの行為規制に関する法令遵守態勢が確保されているかについて、検査・監督を通じて的確に把握し、必要な対応を行ってまいります。 |
|
| <多重債務問題への対応> | ||
新しい法制は、利用者に対して「完全な」保護を保証するというよりは、「必要かつ最低限の」保護を定めたものであり、利用者の側にも、相応の金融リテラシーが要求される。(他7件) |
金融経済教育の充実を図ることは、重要な課題と認識しております。 昨年4月に策定された「多重債務問題改善プログラム」を踏まえ、
等に取り組んできたところであり、今後とも金融経済教育の一層の充実に努めてまいります。 |
|
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融行政アドバイザリーから寄せられた意見等について」(平成20年2月29日)にアクセスしてください。
平成19年度金融行政体験制度(インターンシップ)について
金融庁では、金融行政に関心を持つ学生の皆さんに対して、実践的な就業体験の機会を提供することで、学習意欲の喚起、職業意識の涵養及び金融行政についての理解の増進を図ることを目的として、平成18年度から「金融行政体験制度(インターンシップ)」を導入し、平成19年度においても、平成20年2月から3月の間で以下のとおり実施しました。
1.受入人数
本邦に所在する大学又は大学院の学生のうち、4名の実習生を受け入れました。
2.受入部署・日数等
総務企画局総務課、同局政策課広報室及び同局企画課において、2週間の受け入れを行ないました。
『お知らせ』
本制度については、今年度も、引き続き実施していくことを予定しています。
内容の詳細については、実習生より提言されたご意見等を踏まえ、現在検討中であり、応募方法等を含めて、別途当庁ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
向上心、探究心、チャレンジ精神の旺盛な学生の皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。
【参考】
平成19年度金融行政体験制度の概要
(1)実習時間は、月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後6時15分まで
(2)実習生を非常勤の国家公務員として採用
(3)実習生ごとに指導、監督、助言等を行う実習指導官を配置
今回、実習生として参加された皆さんに、以下のアンケート項目について回答していただきました(五十音順、実習時の学年を掲載)。
【アンケート項目】
(a)「金融庁」のインターン制度に応募した動機は何ですか。
(b)あなたが持っていた「金融庁」のイメージはどういうものでしたか。
(c)あなたが行った実務体験とその感想をお書きください。
(d)実務体験を終えて、あなたの「金融庁」のイメージはどうなりましたか。
(e)このようなインターン制度について、あなたのご意見・ご感想をお書きください。
坂本 明日香 さん
(明治学院大学大学院法務職研究科3年)
配属先:総務企画局総務課審判手続室

(a) 私は地方の経済活性化に興味を抱いており、そんな中で金融庁には取り組みの一つとして地域密着型金融の推進があり、中小・地域金融機関による地方の中小企業やベンチャー企業への支援を推進していることに興味を持っていました。
また、私は今まで法科大学院などで学んだ行政法に対し、あまり行政の現場を具体的にイメージすることができないこともあって、どちらかというと国民の側から行政処分などに対する救済を求める際に使われる法律といったイメージを抱いていました。行政の現場を体験することで自分の今までのイメージはどのようにかわるだろうかと思い、金融庁のインターンシップに応募しました。
(b) 金融庁が金融機関に対する処分を下したというニュースを聞く度、金融庁に対して厳しい検査・監督機関であり、「金融市場の番人」のようなイメージを抱いていました。
また、金融庁が不良債権問題に独立性を持った行政庁として取り組み解決に導いた実績を持つことや、地域密着型金融の推進などにより、中小・地域金融機関による地方の中小企業やベンチャー企業への支援を推進していることなどから、政府の金融行政を担う重要な役割を果たしているとのイメージもありました。
そして、従来に比べ金融商品も格段に増え、一般投資家の裾野も広がってきた今日においては金融市場の透明性・公平性は一層求められるようになってきているといえ、そのような状況に照らしてみると、インサイダー取引など金融市場を脅かす違法行為には厳しく対処すべきであり、金融庁の役割は重要だと思っていました。
(c) 私は、金融庁の総務企画局総務課審判手続室にインターンとして配属されました。同室は、金融庁課徴金制度の運用を行っており、イメージ的には金融庁の中の裁判所といった感じではないかと思います。審判官がいて、審判手続室の業務はいわば裁判所における書記官のような役割に近いと思います。そしてこの審判手続室の業務には、課徴金納付命令の事前手続きとしての審判手続きと、課徴金の納付・徴収に関する業務があります。
私は、主に課徴金納付命令の事前手続きとしての審判手続きを体験させて頂きました。実習内容としては審判官との打ち合わせや室員の方々との勉強会などに参加させて頂いたり、報道記者会見に同行させて頂いたり、また、金融庁の課徴金審判制度につき、他審判制度や訴訟制度とを比較して報告書にまとめたりといったことを行いました。
今回のインターンシップでは、金融庁の課徴金審判制度について他審判制度や訴訟制度との制度比較を行い、報告書にまとめました。また、報告書にまとめる過程で、職員の方に質問したり、またきめ細かくアドバイスして頂くことができたので、少しずつ理解を深めていくことができたように思います。
また、実習最終日には、審判手続室の室長はじめ全室員の方の前で報告会をする機会を持ってもらい、私は金融庁の課徴金審判が行政審判ということで被審人(裁判でいう被告人)に手続保障が充分なされているかという観点から、報告書にまとめる際に感じた審判手続きに関する疑問や感想などを自由に報告させて頂きました。その際、この金融庁の課徴金審判制度は、審判手続室の室員の方々が、法の不整備などを正しつつ、熟慮を重ねながら制度の運用を行っているのだと実感することができ、また、実際に業務に携わっている観点から率直な感想なども聞くことができたりしたことは、貴重な経験になったと思います。
また、法科大学院では法律の解釈を中心に学びますが、行政の現場では、もちろん法の解釈は厳格に行われますが、同時に法の不整備を正すため法律の改正案を国会に提出するということも行われます。このことから行政の現場には法適用のみならず、法の不整備を正すべく、その制度の問題点や改善点などを抽出することも求められると感じました。今回の実習での報告書にまとめる作業は、他の制度との比較から金融庁の課徴金審判手続きを理解し、その制度の不整備や問題点などをみつけることに役立ったと思いますし、そのような作業は法科大学院の学習などではあまり経験することがなかったので、とても新鮮でそのような視点を持つことが出来たことは私にとって大きな収穫でした。
(d) 今回の金融庁インターンシップに参加して、お世話になった審判手続室をはじめ、金融庁は金融市場の透明性・公平性確保のために厳しい検査・監督機関であり、「金融市場の番人」というイメージは変わることはありませんでしたが、そこには言うまでもなく、国民全体の利益・安全を守るという視点があるのだと改めて思いました。
金融庁が金融市場の透明性・公平性確保のため、金融機関や違法行為を行う人に対して、行政処分を課すことは、プロの投資家に限らず、このような金融機関に預金などをしている人に被害を出さないという、国民の保護という目的のためです。その目的のために、金融庁は精力的に様々な政策を打ち立て、金融商品取引法やその他関連法規についても不備があればその改正作業も厭わないのだと感じました。
このように今回のインターンシップにおける実務体験を通し、私の金融庁に対するイメージは「国民の経済的利益・安全を守るための金融市場の番人」に変わりました。
(e) 今回のインターンシップは2週間という短期間ではありましたが、学生にとってはなかなかイメージすることが出来ない行政の現場を話に聞くだけでなく、肌で感じられるよい機会となったと思いますし、今後もインターン制度のような機会が増え、多くの学生に利用されることを願います。
そして一つインターン制度に希望を挙げるとすると、2週間という実習期間では配属先であった課室の業務内容を体験するだけでも、中身が濃くとても充実していましたが、金融庁という組織全体を大きな視点で見てみる機会があってもよかったのではないかと思いました。(例えば、実習期間の2週目に入ったあたりで、他課室職員の方のお話を聞くなど)
内藤 寛子 さん
(慶応義塾大学総合政策学部3年)
配属先:総務企画局政策課広報室
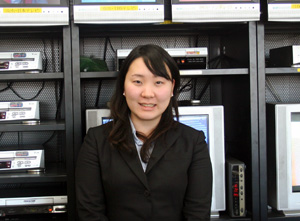
(a) 2007年夏、私は、上海と貴州省においてフィールドワークを行った。沿海地域の上海と、内陸地域の貴州省に赴いた事で、中国が外資企業を多く取り入れ沿海地域の成長を促している事実を目の当たりにしたのである。帰国後、興味程度で日本経済史や最近の日本経済の動向に目をやったところ、外資参入に対する法整備は中国の方が遅れているが、中国は政府を主体として外資企業を取り入れ、国有企業改革などを積極的に行っており、かたや日本は市場が開放された民主主義国家市場経済なのにもかかわらず、金融市場が閉鎖的である事実を知った。では、なぜ日本の金融市場は閉鎖的なのだろうか。これが私の問題の所在であった。金融庁のインターンシップに志望した理由は、国家公務員試験を受ける予定であるというよりも、政府が日本の金融状況にどのようにアプローチをしているのかを現場で見てみたい、というものであった。
(b) 近年、インサイダー取引や、外資企業の日本企業に対するM&Aなどが多くメディアで取り上げられていることから、「金融庁」という名をメディア媒体から耳にすることは頻繁にあったと思う。しかし、大学で勉強している範囲が金融とは全く異なっていたため、例えばニュースなどで、「金融庁」というトピックがあがっていても、特に気にかけることをしていなかった。よって、実際何をしている所なのか、は全くイメージもわかなかった。(すみません…)
官公庁である、というイメージから、民間企業と比較してお給料が安いのに仕事はきつそう、熱意を持った人が多そう等、短絡的なイメージはあった。
(c) 私が派遣された部署は、広報室であった。頼まれた仕事は主に四つある。
英字新聞やタブロイド紙の切り抜き、記者会見や記者レクチャーのセッティングのお手伝い、聴講、英語関連の諸々、事務的な作業(エクセルの表作りetc)である。
広報室長が、広報室は、『多くの情報を取り入れ、多くの情報を提供する』を掲げているとおっしゃっていた。そのため、英語のホームページの充実や、英字新聞からの情報獲得を積極的に行っているという。
初日に「少しなら英語ができます」と肯定してしまったため、英語関連の頼まれごとが多かったように感じる。毎回、「もっと英語をちゃんと勉強しておけばよかった…」と後悔しながらも、英字新聞と1日中格闘するという貴重な機会が与えられたことをとても光栄に思う。経済独特の単語を知ることが出来た。
また、記者会見や、記者レクチャー、そして取材などに同行させていただいたことはとても良い経験であった。普段なら見ることのできない貴重な場であり、ニュースで見る報道の「材料」がここから出来ているのだ、と感じた。
(d) お堅いイメージがあった金融庁であったが、実務体験を終え、働いている方々は明るい方ばかりで、親しみやすい雰囲気と思うようになった。
また、仕事に対してすごく熱意をもたれている方ばかりなのだな、と感じた。
(e) 他企業と異なり、省庁の実務を経験できる機会は非常に少ないように感じるため、このような機会は貴重だと思う。省庁に実際に働いている方々と直接お話できることも、また重要である。様々な情報から得られる省庁のイメージと、実際の現場はやはり違いがあるように思うし、公務員を目指している学生にとって現場を見ることができるという機会はやる気を増すきっかけとなる。
しかし、学生が期待しているほど、金融庁側の受け入れ態勢が整っているわけではないのも事実であろう。
山田 一貴 さん
(中央大学法学部2年)
配属先:総務企画局企画課

(a) ひとつは、多種多様なルールの立案を行い、さらに金融機関・市場と日常的なコミュニケーションをとっている金融庁で短期間でも過ごすことによって、職員の方々の視野の広さやその場に応じた対応力を間近で体感し、そこから自分の弱点や改善点を見出し、これからの大学生活でそれらを克服し自分の可能性を広げるためです。そしてもうひとつは、職場で実際にどのような能力が重要視されているのか今のうちに知ることは、公務員志望の私にとって大いにプラスになると考えたためです。
(b) 率直にいえば、公務員の中でも限られた人間しか携わることのできない「法律を作る」という仕事を行っているエリートな人たちの集まった場所というイメージを持っていました。
(c) ほとんどお役に立つことはできませんでしたが、少しだけ「法律を作る」という仕事の一部に関わることができました。すごく興味があって、インターン期間中にできたらいいなと思っていたことだったので、とても感動しました。
(d) エリートというイメージはまったく変わりませんでした。ただ、頭のよいだけではなく、本当に親切で人間としてすばらしい方々のいる場所でした。
(e) 公務員を目指す人たちにとってはもちろん、少し興味があるという学生にとっても非常に有益な制度だと思います。インターン期間中には、受け入れてくださった企画課の方々だけでなく、他の部署の方々もいろいろと声をかけてくださってインターンに行くのがとても楽しかったです。このインターンのおかげで自分の改善すべき点を見つけることができました。これをきっかけにして、さらに努力していきたいと思います。
横井 勇一 さん
(東京大学教養学部文科一類2年)
配属先:総務企画局政策課広報室

(a) 官庁という職場が、どのような職場なのか、インターンを通じて自分自身の目で見たかったからです。また、漠然とではありますが、金融関係の職場を自分の進路の一つと考えていたので、その中でも一般企業では見ることの出来ない、行政の裏側を見てみたいと思いました。
(b) 比較的新しい官庁ということもあり、スリムで風通しのよい組織というイメージです。
(c) 英字紙の指示された記事の切り抜きとコピー、庁内への配布では、職員の方が世界のどのようなニュースを注目しているのか考えることができました。自分でも記事のタイトルの和訳をさせていただいたこともありましたが、上手く訳せずとても苦労をしました。他の部署への印刷物の配布では、大臣室や参事官室など幹部職員の部屋から、現場の部屋まで見て回ることができ、それぞれの部屋の雰囲気を感じられました。また、大臣や長官の会見に同席させていただいたときには、間近でお話を聞くことができ、普段はテレビや新聞で一部しか見聞きできない模様を全て見ることができ、とても楽しかったです。
(d) やはり思ったよりも人数が少なく、比較的フラットな組織というイメージです。また、職員の方は、想像していたよりも穏やかで気さくな方が多く、あまり堅苦しさのようなものを感じることはありませんでした。また、職員の方とご飯を一緒に食べに行ったりするときに、実際に職員の方一人ひとりが、金融政策についてどのように考えているのかお聞きすることができ、非常に面白かったです。
(e) 普段は入ることもできない職場を自由に見ることができるインターンとして、とても面白いものでした。ぜひ今後とも継続して続けていってもらいたいと思いますし、一人でも多くの学生がインターンをできるよう、人数枠の拡大もしていただきたいと思います。また、学生の募集の仕方やインターンのプログラムにもより一層工夫を凝らしてほしいと思いました。ただ金融庁の内側を見るだけのインターンではなく、その中で学生が自分で考えて何かを得られるような機会にしていってほしいです。

 検索
検索

