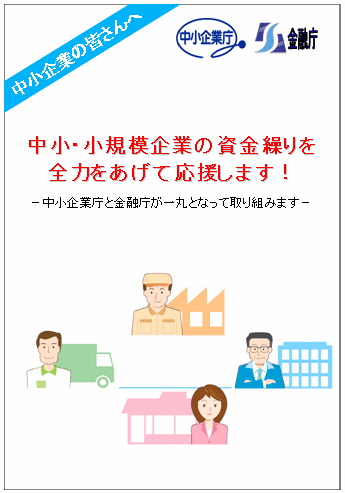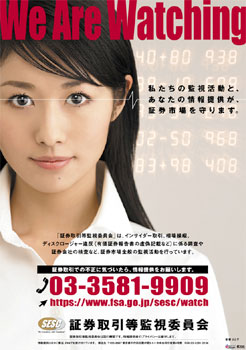アクセスFSA 第72号(2008年11月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。
Q: 今日東証の大発会で株価が9,000円に回復しまして幸先のいいスタートを切ったと思うんですが、これについての感想と、去年は最大の下落率を記録しましたけれども、今年はどういった年になってほしいというふうにお考えですか。
A:去年は私の記憶では、厳しい年初だったけれども後半には持ち直すんじゃないんですかなんていうことをおっしゃっている方もいらっしゃいましたけれども、今年は非常に厳しいというふうにおっしゃっている専門家あるいは関係者の方もいらっしゃいます。そういう中で各国ともそれぞれ、そしてまた協調して色々な対策をとっているわけですけれども、日本におきましても官民挙げてこの危機とも言われる状況を乗り切っていかなければならないという意味で、世界的に年末年始少し持ち直しておりますので、日本のスタートである本日、為替が安定しそして株価が上昇しているということは、みんなでこの難局を乗り切っていこうという、民間側といいましょうか経済界側の強い決意のあらわれであり、我々も同じような決意でやるべきことを全力を挙げてやっていかなければならないと。今のところは何かマーケットにしっかりやれよというふうに背中を押されているような感じすら、今のマーケットからはそんなような感じを受けています。
Q: まず北海道の札幌北洋ホールディングスが改正された金融機能強化法に基づく公的資金の注入(申請)の検討に入ったと昨日発表しました。まだこれから審査がありますが、実現するとなれば今般の改正法においては初めての事例となります。これについて大臣のご所見をお願いいたします。
A:私も北洋銀行が公的資本の受け入れの検討に入ったということは昨日発表されて知っております。もともと健全行と言われております金融機関がさらに体力を強化して北海道の中小企業等に資金を供給するということは地域経済にとっても非常にいいことだと思いますので、個別行の話としてというよりも一般論として、これを活用していただいて、その目的を達成していただければというふうに期待しております。
Q: これはほかの金融機関に与える影響などについてはどのようにお考えでしょうか。
A:過去似たような、しかし目的が全く違う例があって、下手にこういうことをするとマイナスになるんじゃないかというようなご意見もありましたけれども、これをきっかけに健全行がこういう形でこのスキームを利用していただくということは、金融の機能の使命を果たすという意味で、私はやっていただきたいし期待をしております。
Q: 金融機能強化法に基づく公的資金の申請についてですが、過日南日本銀行が検討の意向を明らかにされたということでこの件の評価と、それから株安ですとか地域経済の状況というのは、業界ある程度共通したものがあるということで、可能性としては今後も申請が続くこともあり得るのかなと思っておりますが、その辺りの状況のご認識は如何でしょうか。
A:金融機能強化法につきましては何回も申し上げておりますけれども、金融機関の体力が更に強化されることによって中小企業、地域経済への資金供給という職務を果たしていただきたいというのが法の趣旨であり、それは金融機関自身のご判断、そしてまた公的資金の参加を求める場合の申請ということになっているわけでございます。北洋銀行、それから南日本銀行がこれについて検討をし始めたということを発表されているということは、この趣旨にかなって、特に北海道あるいは鹿児島といった経済状況が非常に厳しいところでこれを活用して円滑な資金供給が出来るということは、私は申請をしていただいてそういうふうになれば非常にありがたいことでありますし、ほかの地域あるいはほかの金融機関でも是非こういうことをやっていただければありがたいというふうに思っております。
Q: 地方銀行の現況についてお伺いしたいのですが、これまで改正金融機能強化法による資本注入の申請を表明したところが2行出ていると思うのですが、それに加えて昨日、香川銀行と徳島銀行が経営統合を発表しました。現状地方銀行を取り巻く環境とか経営についての認識についてお伺いしたいのですけれども、よろしくお願いします。
A:合併の話の前に、今色々な金融機関、あるいは金融機関の上部団体というのでしょうか、信金・信組の上部団体等が公的資本注入の検討をされているやに聞いております。私は、前から申し上げているようにこういう世界的な金融機関の流動性の問題が実体経済に与えている影響が大きいわけでございますから、やれともやるなとも言いませんけれども、やっていただくのであれば非常にこれは、この法律の趣旨から見ていいことではないかと。歓迎したいと。繰り返しますけれども、やれとかやるなとか、あるいはまた実際に私のところに来ているということではございませんけれども、一般論としてはこういうことは中小企業に対する流動性供給という観点からもいいことだというふうに思っております。
今の四国の金融機関が合併をする、したいということについては、報道の中で私は承知しているだけでございますけれども、前回の時は金融機能強化法というのはある意味では合併というものも1つの大きな目的にあったと思っておりますけれども、今回は合併ということよりも中小企業、地域経済に対しての貸し出し余力、貸し出し体力をつけるという意味でやっていることでございますから、直接的な大きな目的ではないとは思いますけれども、やはり体力がそれによって強化されるという意味では、一般論としては、これはどうなるか分かりませんけれども、我々としてもこれについてもきちっと見守っていきたいというふうに思っております。
【お知らせ】
○ 金融円滑化「大臣目安箱」について
金融庁、財務省では、平成20年10月16日より、中小企業金融円滑化に向けた監視を一層強化するため、「貸し渋り、貸し剥がし」等の金融機関(民間金融機関及び政策金融機関)の融資に関する大臣直通の情報窓口(大臣目安箱)を開設しました。
大臣目安箱にいただいた情報は、そのまま大臣に届くこととなっており、また、民間金融機関に関するものは金融庁、政策金融機関に関するものは財務省の担当部局にも回付し、例えば、情報提供者が、「具体的な情報を金融機関に開示しても構わない」ということであれば、担当部局より当該金融機関に伝達し、内部チェックを要請するなど、行政を行う上での情報として活用していきます。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『金融円滑化「大臣目安箱」について』(平成20年10月17日)にアクセスしてください。
○ 金融円滑化ホットラインの開設について
金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を開設しています。
これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配慮が求められていることを踏まえ、平成20年4月4日に経済対策閣僚会議において決定された、「成長力強化への早期実施策」に盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢整備を行うこととしたものです。
本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただいているところです。また、寄せられた情報の中に、最近、融資の申込みに際し、融資申込先の金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資できない。」という対応をされた、といった内容のものがありました。
金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関与することもありません。
このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、下記の金融円滑化ホットラインに情報提供をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。
名称:金融円滑化ホットライン
受付時間:平日10時00分~16時00分
電話番号:03-5251-7755
受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等
※ ご留意事項
○ ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。
○ ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「特定業種に対する金融機関の貸出判断について」(平成20年6月17日)にアクセスしてください。
○ 中小企業の資金繰りを応援します!
~金融庁と中小企業庁は合同で中小企業の資金繰り支援の施策をまとめたパンフレットとポスターを作成しました~
日本経済は、世界経済の減速に伴い景気後退局面に入っており、中小企業の資金繰りも厳しさを増しています。 こうした中、政府では、中小企業の資金繰り支援のため各般の施策に取り組んでいます。 金融庁と中小企業庁では、今般、合同で中小企業に対する資金繰り支援の施策のうち、中小企業に特に知っていただきたい事項を分かりやすくとりまと めたパンフレットを作成しました。 従来、政策の広報は、所管省庁がそれぞれ行うことが多かったのですが、メッセージの受け手である中小企業の立場に立てば、どの省庁が所管している かにかかわらず、必要な情報を分かりやすく入手できることが重要と考えられることから、中小企業金融に関係する両庁の連携を行うこととしたものです。 |
|
まず、中小企業の金融円滑化に関するお問い合わせ先について、一覧にして掲載しました。
金融機関の融資等に関する大臣直通の情報受付窓口である、金融円滑化「大臣目安箱」や民間金融機関の融資等に関する電話による情報受付「金融円滑化ホットライン」、また、中小企業庁等に設置されている「中小企業金融貸し渋り110番」等のお問い合わせ先も、このパンフレットを御覧いただければ分かるようになっています。
また、施策に関しましても、新たな融資を受けたい方々に対する支援策、あるいは、既存の借入金の返済条件を変更したい方々に対する支援策、というように、ご希望される融資によってどういった支援策を利用できるのか、というようなことについてポイントを簡潔にまとめて記載しています。
「資金繰りが厳しく、返済条件を緩和してもらえれば助かるのだが、銀行に不良債権になるからと言われて、返済条件の変更に応じてもらえない。どうしたらよいのか」といったような声が中小企業の方々から聞かれます。そういった方々にこそ、このパンフレットを手にとっていただき、政府による資金繰り支援策を知っていただくことで、金融機関等とご相談していただく際の足がかりになればと思います。
今般の合同パンフレットに関しては、全国の最寄の財務局、経済産業局にも置いてありますので、是非お問い合わせください。
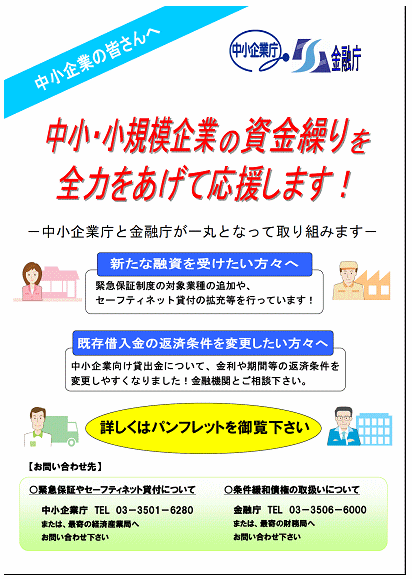
なお、上記のパンフレットに記載した、条件緩和の取扱いに関する施策について、簡潔にまとめたパンフレットもありますので、是非御覧いただきたいと思います。(下のパンフレットはウェブサイト上の![]() 「『中小企業の皆様へ(中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました)』」からも御覧いただけます。)
「『中小企業の皆様へ(中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました)』」からも御覧いただけます。)
○ 株券電子化が平成21年1月5日より実施されました!
株券電子化について、よくあるご質問をQ&A形式でお答えします。
Q1.株券電子化とは、どういうことですか?
株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(以下「ほふり」といいます。)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。
平成21年1月5日に株券電子化が実施され、上場会社の株主権の管理は新たな株式管理制度による電子的な管理に統一されました。
Q2.株券電子化のメリットは何ですか?
株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。
○株主にとっては、
i)株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。。
ii)株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。
iii)発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。
○発行会社(株主名簿管理人を含む。)にとっては、
i)株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなります。
ii)株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できます。
iii)株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。
○証券会社にとっては、
i)株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減されます。
ii)株主が株券をほふりに預託する場合やほふりに預託された株券を引き出す場合の手続を行う必要がなくなります。
Q3.株券電子化により、株主はどのような手続きが必要ですか?
(1)株券電子化の実施前に株券をほふりに預託した方は、特段の手続をとる必要はありません。
(2)株券電子化の実施までにほふりに預託せず、株券がお手元にある方は、株主名簿上の名義人の名前 で、発行会社により「特別口座」が開設され、権利は保全されています。
ただし、特別口座では株式の売却・担保設定等の取引はできません。取引をするためには、株主が証券会社に口座を開設し、特別口座から株式の振替手続を行うことが必要です。取引を希望する方は、特別口座を開設する信託銀行等や証券会社にご相談ください。
Q4.株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。
他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となります。
(1)特別口座の名義人との共同申請
(2)以下のいずれかの書類を提出して申請
○相続を証する書面
○裁判の判決、和解調書など
○株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)
これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。
Q5.株式担保取引はどのようにしたらよいのですか?
株券電子化実施後、株式を担保として差し入れる場合、銀行等の担保権者への口座に振り替えることにより行われます。取引を行おうとする方は、取引先の証券会社や銀行等にご相談ください。
なお、株式担保取引の匿名性については、株券電子化実施後についても確保が可能となっています。
Q6.未上場の株式は電子化の対象ですか。
株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。
(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。
Q7.株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。
株券電子化の実施後においては、株券を価値があるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って株券を回収する行為(注)などの詐欺的行為がないとは言い切れません。
金融庁や証券会社、関係団体などが株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはくれぐれもご注意ください。
(注)株券電子化後においても株券は、名義回復を行う際の重要な証拠書類となり得ますので、その管理・処分についてはご注意ください。
○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!
ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です
一昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。
具体的には、
1.他者からお金を集め(出資を募り)
2.何らかの事業や投資を行い
3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み
を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。
登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認ができます。
無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。
また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。
- 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、 利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。
- 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要等を記載した書面を交付しなければならない。
- 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
- 損失補てんをしてはならない。
たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。
なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるものではございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。
○ 電子記録債権法の施行について
平成19年6月20日に成立した「電子記録債権法(平成19年法律第102号)」が平成20年12月1日に施行されました。
電子記録債権は、当事者がインターネット等を通じて電子債権記録機関に電子記録を請求することにより債権の発生・譲渡ができる、手形・売掛債権等とは別の新たな類型の金銭債権です。
これまで、企業間の取引においては、手形が決済手段として利用されていました。手形には、支払期日前であっても割引によって現金化することができるなど、中小企業の資金繰りを支える機能がありました。一方、大企業においては、事務手続きの電子化を進める中で、紙媒体を利用することにより生じる事務コスト(発行・保管コスト等)はできるだけ削減したいという考えから、手形ではなく期日振込による決済や一括決済方式を行うようになってきており、手形の流通量は平成2年度をピークに年々減少しています。また、売掛債権は、債権の存在・発生原因の確認に係るコストや二重譲渡のリスクがあるため、流動性に乏しく早期の資金化が困難なものとなっています。
電子記録債権制度は、売掛債権等を電子データ化することで、前述のような様々なコストやリスクを解消するものであり、事業分野におけるIT化の進捗が著しい昨今、電子記録債権が事業者の資金調達における新しい手段として広く活用されることが期待されています。
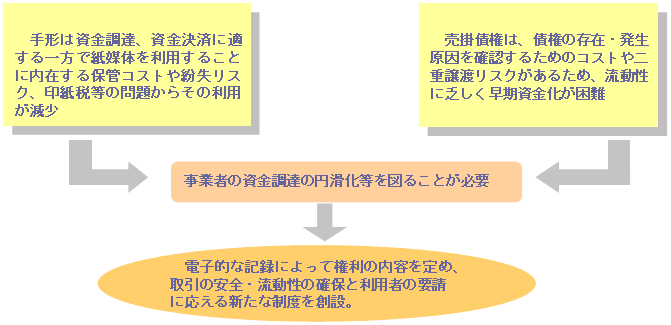
○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。
金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。
この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。
金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会及び平成20年10月1日に全国銀行協会![]() が認定を受けています。
が認定を受けています。
認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。
○ 皆様からの情報提供が市場を守ります!
証券取引等監視委員会 当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けており、平成19事務年度には、5,841件と多数の情報をお寄せいただきました。 個別銘柄に関する情報 相場操縦(見せ玉など)やインサイダー取引(会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど)、風説の流布(ネット掲示板の書込み等によるデマ情報など)、疑わしいディスクロージャー(有価証券報告書の虚偽記載など) やファイナンス(架空増資、疑わしい割当先など)、上場会社の内部統制の問題・・・ など 金融商品取引業者に関する情報 証券会社や外国為替証拠金取引業者、投資助言業者などによる不正行為(リスク説明の不足、システム上の問題など)や、財務内容の健全性等に関する問題・・・ など その他の情報 疑わしい金融商品・ファンド、無登録業者、市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)の情報・・・ など 以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。(なお、個別のトラブル処理・調査等の依頼には対応していませんので、ご了承ください) なお、インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口 |
一般からの情報提供を求めるポスター |
○ 金融庁認証局システムの廃止及び政府共用認証局への移行について
金融庁では、平成14年度から金融庁認証局の運用を開始し、認証業務を行ってきました。
認証業務とは、国民等と行政機関との間で処分通知等をオンラインでやり取りする際に、例えば処分権者のなりすまし、内容に改ざんが無いことを証明するもので、具体的には認証局システムを利用して官職証明書、サーバ証明書、コード署名証明書等の発行等を行うものです。
これまで、各府省単位で認証局を設置し認証業務を行ってきましたが、「霞が関WAN及び政府認証基盤(共通システム)の最適化計画」に基づき、認証業務の効率化を図るため、政府共用認証局へ集約・一元化することとし、金融庁においては、平成20年9月11日をもちまして金融庁認証局システムを廃止しました。
詳しくは、金融庁認証局の廃止に関する重要なお知らせ(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/ninsyo/ca/fsa_cpcps.html)をご覧ください。
今後、認証業務については政府共用認証局システムを利用して行います。
詳しくは、政府認証基盤(政府共用認証局)のサイト(http://www.gpki.go.jp/![]() )をご覧ください。
)をご覧ください。
○ 「e-Gov電子申請システム」ご利用について
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html![]() )の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。
)の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内・金融庁認証局について」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索![]() 」をご確認ください。
」をご確認ください。
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約![]() 」に同意していただく必要があります。
」に同意していただく必要があります。
「e-Gov電子申請システム」利用のメリット
いつでも
- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。
(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。
- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。
どこでも
- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。
(注) 添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。
- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。
※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくはe-Govトップページ![]() の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから
の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから![]() 」をご確認ください。
」をご確認ください。
○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内
金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。
また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。
日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。
○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。
※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。
【1月の主な報道発表】
※ ![]() マークのある項目につきましては、
マークのある項目につきましては、![]() から公表された内容にアクセスできます。
から公表された内容にアクセスできます。

 検索
検索